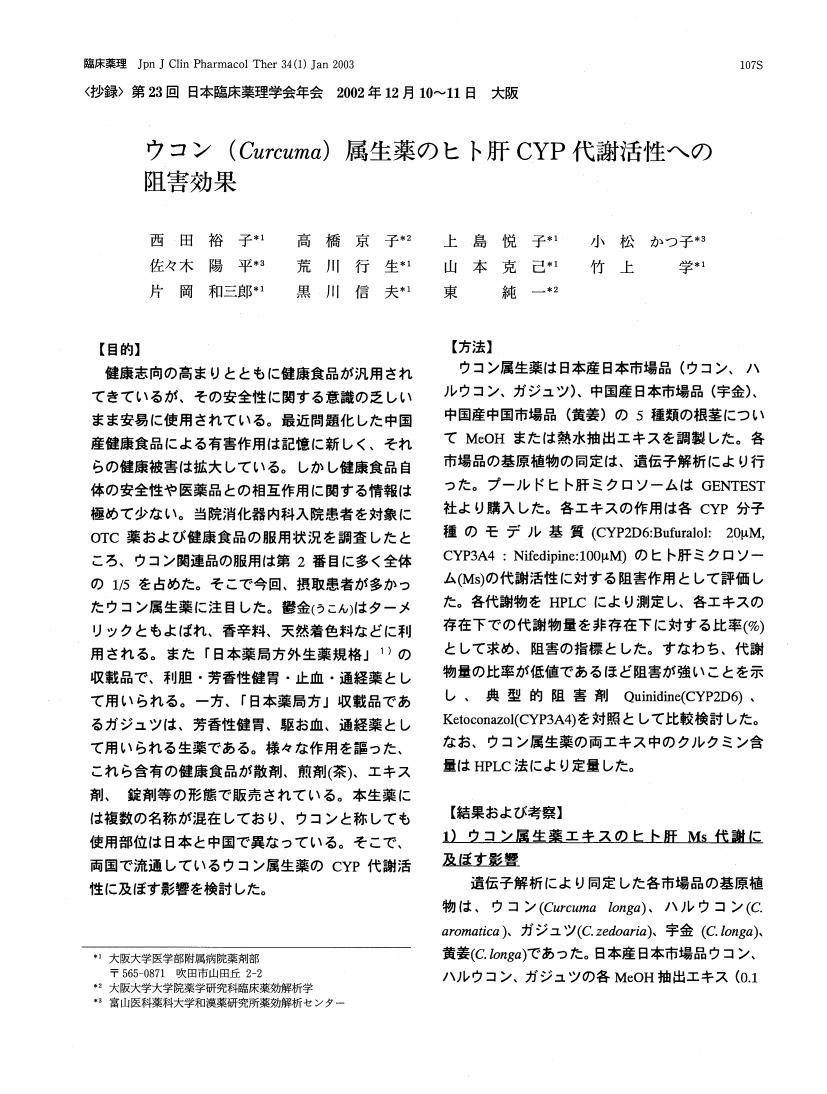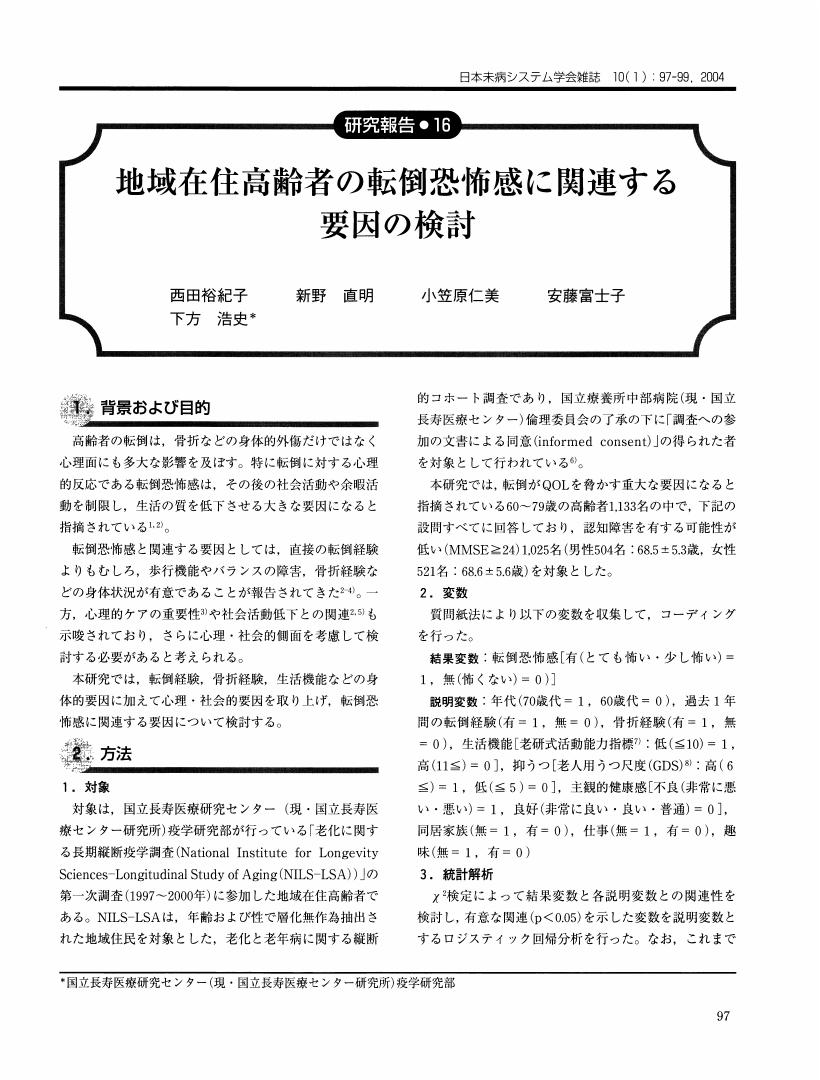- 著者
- 高橋 大生 井口 ゆかり 小川 元大 竹内 真太 西田 裕介 美津島 隆
- 出版者
- 東海北陸理学療法学術大会
- 雑誌
- 東海北陸理学療法学術大会誌 第28回東海北陸理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.143, 2012 (Released:2013-01-10)
【はじめに】 熱傷の急性期には早期の日常生活動作(以下、ADL)自立を目指す必要があるといわれている。また、自殺企図による熱傷の症例では身体的問題と精神的問題は並行して治療していかなければならないとされている。今回、焼身自殺を図ったことにより重症熱傷を呈したが、精神状態の変動に留意したリハビリの介入によってADLの向上、歩行の再獲得に至った症例を経験したため文献的考察をふまえて報告する。なお、症例には発表の主旨を十分に説明し同意を得ている。【患者情報】 対象は40歳代女性である。既往歴に大うつ病性障害、解離性障害があり、以前に3回の自殺企図があった。平成X年2月25日、灯油による焼身自殺を図り、当院へ救急搬送された。入院時所見としてTotal Burn Surface Area 50%のⅢ度熱傷、Burn Index(以下、BI)50、気道熱傷の合併を認め、Artzの基準で重症熱傷と診断された。当院ICUに入室し人工呼吸器管理となった。その後、同年2月25日、3月2日、8日に分層植皮術施行し、3月8日より拘縮予防のため理学療法の介入を開始した。5月23日に四肢関節可動域訓練、離床開始となった。【初期理学療法評価(6/3)】 身体機能の評価は安静臥位時HR144拍、呼吸数54回、ROM-T右足関節背屈-10°、左足関節背屈-5°、両股関節屈曲80°、MMT下肢2~3レベル、体幹・上肢3~4レベルであった。基本動作とADL評価は起居動作が中等度介助、起立は最大介助、歩行は実施困難な状態であり、FIMは40点であった。精神機能の評価は短縮版POMSの抑うつ項目が17点であった。問題点として#1. ROM制限、#2. 筋力低下、#3. 運動耐容能低下を挙げた。PT訓練はROM訓練、筋力訓練、起居動作訓練、呼吸指導とし、週5回、1回40分実施した。【治療経過】 初期は関節可動域訓練を中心とした拘縮予防を行った。5月18日、Head-up 40°可能となった。6月7日Tilt tableにて起立訓練を行った。6月13日に平行棒内歩行訓練開始し、6月23日にサイドストッパー型歩行器歩行訓練開始した。6月29日にT字杖歩行訓練開始となり7月4日に独歩開始した。【最終理学療法評価(7/4)】 身体機能の評価は安静臥位時HR121拍、呼吸数36回、ROM-T右足関節背屈-5°、左足関節背屈0°、右股関節屈曲95°、左股関節屈曲90°、MMT下肢4レベル、体幹・上肢4レベルであった。基本動作は全て自立となりFIMは79点であった。歩行能力は10m歩行試験(平地、T字杖)39.6秒、最大歩行距離は独歩で23mであった。【考察】 自殺企図の症例では精神的問題も治療していかなくてはならないとされていることから、本症例に介入する上で精神状態の変動を把握することはリハビリのフィードバックにつながる点で有用であると考えた。そこで精神状態と身体機能の変動を調べ、リハビリに反映していくために身体機能をFIM、精神機能をPOMSで経時的な評価を行った。その結果FIM得点の上昇に伴いPOMS(抑うつ項目)が減少する傾向がみられた。達成体験が自己効力感につながることから、可能な動作が増えたことで本症例の自己効力感が増大し、抑うつの軽減につながったと考えた。
1 0 0 0 OA 日本人男性にとっての育児休業
- 著者
- 西田 裕子 寺嶋 繁典
- 出版者
- 関西大学大学院心理学研究科心理臨床学専攻
- 雑誌
- Psychologist : 関西大学臨床心理専門職大学院紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.27-37, 2020-03-16
本邦における男性の育児休業取得率は2018年度の調査ではいまだ6.16%であり、厚生労働省が向上を目指しているものの、欧米諸国と比較すると極めて低い。本稿では、男性の育児休業取得率の低さの背景に存在する制度的な課題と共に、文化的・心理的課題を明確にし、男性の育児休業取得の促進に寄与する取り組みについて検討を行った。文化・心理的背景には、性役割分業意識や、集団意識、母性原理、自己主張の仕方などがあり、こうした現状の中で男性労働者が育児休業を取得したいと主張することは非常に困難である。男性の育児休業取得率向上は、企業や労働者への育児休業取得の利点を浸透させ、制度を拡充し、義務化を検討すること、さらには親になる教育を早期に始めることなど、多方面からの政策によってはじめて可能となるであろう。
1 0 0 0 航空自衛隊創設期の旧軍航空関係者の役割と米空軍の関与について
- 著者
- 中島 信吾 西田 裕史
- 出版者
- 防衛省防衛研究所
- 雑誌
- 防衛研究所紀要 = NIDS journal of defense and security (ISSN:13441116)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.105-130, 2020-01
1 0 0 0 IR 外来患者のホームエクササイズの実施状況と動機づけの関連性の検討
- 著者
- 秋山 陽子 西田 裕介 重森 健太 水池 千尋 金原 一宏 兵永 志乃 池谷 直美 福山 悟史 川久保 知美
- 雑誌
- リハビリテーション科学ジャーナル = Journal of Rehabilitation Sciences Seirei Christopher University
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.19-33, 2013-03-31
研究報告【はじめに】H-Ex.の実施状況と、動機づけの関連性を検討した。【対象】外来患者24名(平均年齢61±17歳、男性7名、女性17名)とした。【方法】質問紙調査法にて、H-Ex.の実施状況と動機づけの強さおよび個人属性を調査した。動機づけの強さの測定には『Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2』を一部修正して使用した。【結果】実施状況と動機づけの強さには、有意な相関はなかった。痛みが強いほど、H-Ex.を行わないという有意な相関があった。家族数が多いほど、内発的調整スタイルの得点が低いという負の相関があった。H-Ex.を行わない日が多い群と外的調整スタイルの得点の高い群との間に、有意な分布の差があった。就労形態と、同一視的・取り入れ的調整スタイルとの間にそれぞれ有意な分布の差があった。【考察】H-Ex.の実施状況と動機づけの強さの関係については、両者間に有意な相関がなかった。その要因として、介入そのものが動機づけを強くしたこと、実施状況調査の時期や期間が実施結果を良好にしたのではないかと考えた。
1 0 0 0 OA 肝円索腫瘤を呈したIgG4関連疾患の1例
- 著者
- 西田 裕紀 徳光 幸生 新藤 芳太郎 松井 洋人 松隈 聰 永野 浩昭
- 出版者
- 日本臨床外科学会
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.11, pp.2055-2060, 2019 (Released:2020-05-31)
- 参考文献数
- 11
症例は75歳,男性.膵管内乳頭粘液性腫瘍フォローのため施行された造影CTで,肝鎌状間膜内に20mm大の腫瘤を指摘された.超音波ガイド下生検を施行されたが,病理学的診断は困難であった.腫瘤は緩徐に増大傾向であり,FDG-PETで腫瘤にSUVmax=4.4の軽度集積を認めた.外科的診断目的で当科紹介となり,肝鎌状間膜由来の平滑筋肉腫や間葉系腫瘍を疑い,腹腔鏡下腫瘤切除術を施行した.腫瘤は肝円索の肝流入部に存在しており,腫瘤に近接していたG4を処理し,阻血域となった肝S4を部分切除した後に腫瘤を摘出した.切除標本の病理組織学的所見では,肝円索に多数のIgG4陽性形質細胞浸潤および線維化を認めた.血液検査で高IgG4血症を認めたため,IgG4関連疾患と診断した.肝円索病変を呈するIgG4関連疾患はこれまでに報告を認めない,稀な病態であると考えられた.
1 0 0 0 OA 高齢者の耳垢の頻度と認知機能,聴力との関連
- 著者
- 杉浦 彩子 内田 育恵 中島 務 西田 裕紀子 丹下 智香子 安藤 富士子 下方 浩史
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.325-329, 2012 (Released:2012-12-26)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 3 1
目的:耳垢は高齢者および知的障害者に頻度が高いことが知られており,湿性耳垢の頻度が高い欧米では高齢者の約3割に耳垢栓塞があるという報告もある.しかしながら乾性耳垢の多い日本においての報告はない.今回,本邦における一般地域住民における耳垢の頻度と認知機能,聴力との関連について検討した.方法:『国立長寿医療研究センター・老化に関する長期縦断疫学研究』第5次調査参加者中,60歳以上で,耳垢確認のための鼓膜ビデオ撮影検査を受け,かつ耳疾患の既往のない一般地域住民男女792人を対象とした.Mini-Mental State Examination(MMSE)と良聴耳の耳垢の有無,良聴耳の4周波数平均聴力との関連について一般線形モデルで検討した.結果:対象792人中良聴耳の耳垢を85人(10.7%)に認めた.MMSE 24点以上の群では良聴耳の耳垢が有るのは10.0%だけだったが,MMSE 23点以下の群では23.3%に耳垢を認めた.また良聴耳の平均聴力は年齢,性を調整しても耳垢有群では無群より有意に悪かった(p=0.0001).また,年齢,性,良聴耳平均聴力,教育歴を調整しても耳垢有の群では有意にMMSE得点が低かった(p=0.02).結論:本邦においても高齢者の1割に良聴耳の耳垢を認め,耳垢により聴力が低下している場合があることが示唆された.また耳垢を有する群では認知機能が悪いことが明らかとなった.
1 0 0 0 IR サッカー(フットボール)の誕生
- 著者
- 西田 裕之
- 出版者
- 奈良産業大学
- 雑誌
- 奈良産業大学紀要 (ISSN:09145575)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.193-198, 2012-12
1 0 0 0 中高年者に適用可能なワーク・ファミリー・バランス尺度の構成
1 0 0 0 OA 心理ストレス負荷による慢性炎症に関連する自律神経活動の検討
- 著者
- 臼井 晴信 西田 裕介
- 出版者
- 東海北陸理学療法学術大会
- 雑誌
- 東海北陸理学療法学術大会誌 第28回東海北陸理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.72, 2012 (Released:2013-01-10)
【目的】 慢性炎症は、生活習慣病を発症、進行させる一要因である。主に内臓脂肪中の免役細胞により慢性炎症が生じる。免疫細胞は自律神経の支配を受け、慢性炎症は一部自律神経活動により調節されると考えられる。心拍変動の周波数領域解析によるVLF(Very Low Frequency)の低下は、炎症反応や生命予後との関連が認められている。本研究ではVLFを慢性炎症に関与する自律神経活動の指標として用いる。 先行研究ではストレス負荷後30分以上遅延して炎症指標が増加し、その後持続することが認められている。本研究では心理ストレス課題により、VLFが課題後に遅延・持続して低下するという仮説を検証し、心理ストレスによる慢性炎症に関する自律神経活動の亢進を確認することを目的とする。【方法】 健常成人男性10名(26.3±4歳)を対象に測定した。座位による安静10分(課題前安静)の後、Stroop課題を20分間実施し、その後2時間座位による安静(課題後安静)をとった。課題前安静から課題後安静終了までの間、心拍数計(RX-800 Polar社)にて心拍を計測した。心拍のR-R間隔データに周波数領域解析を行い(Memcalc/Tarawa)、課題前安静、課題時、課題後安静10, 20, 30, 45, 60, 90, 120分の各時間のVLF値を算出した。また、BMI、腹囲を測定した。VLF値の変化を課題前安静値で除し、VLF変化率とした。各時間のVLF変化率と身体計測値についてSpeamanの順位相関係数にて関連を検討した。課題後にVLFが課題前安静よりも低下した群をVLF低下群、低下しなかった群をVLF非低下群とし、身体計測値について対応のないt検定により群間で比較した。なお、本研究は聖隷クリストファー大学倫理委員会の承認を得ており、対象者には口頭と文書にて説明し同意を得た。【結果】 対象10名中7名において30分程度遅延したVLFの低下を認め、内6名においてVLFの低下は60分以上持続した。45分、60分でのVLF変化率とBMIには中程度の有意な負の相関を認めた(それぞれr=-0.69, p<0.05, r=-0.64, p<0.05)。VLF低下群はVLF非低下群に比べ、体重と腹囲が有意に大きかった(それぞれp<0.05)。【考察】 7名で30分程度VLFが遅延して低下し、6名で60分程度低下が持続した。VLF低下の遅延・持続時間は、先行研究におけるストレス負荷後の炎症反応指標の遅延・持続した増加と類似している。ストレス負荷により慢性炎症を生じる自律神経活動が亢進したことを反映すると考えらえる。腹囲、BMIは内臓脂肪量と正の相関が認められている。課題後45分、60分のVLF変化率とBMIに負の相関を認めたこと、VLF低下群で体重と腹囲が大きいことより、内臓脂肪量とVLFの低下しやすさに関連があると考えられる。ストレス負荷による慢性炎症は、内臓脂肪の多い人で生じやすいという先行研究の結果と一致している。本研究の結果は、内臓脂肪の多い人は自律神経機能が低下していることを示唆している。【まとめ】 本研究よりストレス負荷により慢性炎症を生じる自律神経活動が亢進することが示唆された。また、内臓脂肪の多い人は自律神経機能が低下している可能性を示唆したことより、理学療法士は自律神経機能の改善を目的とした介入をする必要があると考える。
1 0 0 0 OA 回復期リハビリテーション病棟での理学療法士による心電図評価の必要性の検討
- 著者
- 臼井 晴信 秦野 吉徳 西田 裕介
- 出版者
- 東海北陸理学療法学術大会
- 雑誌
- 東海北陸理学療法学術大会誌 第27回東海北陸理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.163, 2011 (Released:2011-12-22)
【目的】現在、脳血管障害患者の多くが、急性期治療後、リハビリテーション目的で回復期リハビリテーション病棟(回復期病棟)へ入院している。厚生労働省によると、脳血管障害患者で発症から回復期病棟入院までの平均期間は36日、入院患者の平均年齢は71歳である。回復期病棟転院までの期間は短縮しており、入院患者の多くが、脳血管障害患者や高齢者であることを考えると、心血管系リスク管理が必要であると考えられる。当院回復期病棟入院中の脳血管障害患者の入院時標準12誘導心電図においても、57%の症例で何らかの所見を認めた。適切な心血管リスク管理と、運動処方・生活指導を行うために、理学療法士による運動時の心電図評価は必要不可欠であると考える。本症例報告の目的は、心原性脳梗塞により当院回復期病棟に入院し、理学療法実施中に頻脈を認め、心電図評価を行い、生活指導に至った症例の経験より、回復期病棟における心電図評価の必要性について、後方視的に考察することである。なお、本症例報告はヘルシンキ宣言に沿っており、データの使用に際しては、市立御前崎総合病院倫理委員会の承認を得た。 【患者情報・治療歴】症例は70歳代男性で、既往歴に心筋梗塞がある。2009年4月、上下肢脱力により近隣他病院へ搬送され、心原性脳梗塞の診断を受け入院した。第55病日、当院回復期病棟に転院した。入院時標準12誘導心電図において、安静時心拍数は76bpm、心房細動の所見を認めた。第74病日、理学療法での歩行練習直後、橈骨動脈触診により約160bpm、安静坐位時に約130bpmの頻脈を計測した。直後にモニター心電図(CM5)による評価を行い、安静時115bpm、歩行練習時145bpmの頻拍を認め、さらに基線の規則的な動揺を確認した。自覚症状はなく、呼吸数は安静時16回/分、歩行練習直後18回/分であった。理学療法中の評価結果を医師に報告し、医師は理学療法評価結果をもとに、翌日午後からの24時間のホルタ―心電図検査を処方した。第77病日時点での歩行形態は四点杖歩行軽介助で、1日に20m程度を数回練習していた。 【結果】ホルタ―心電図検査の結果、24時間平均心拍数は85bpm、最小心拍数は55bpm、最大心拍数は136bpmであった。18時、7~8時、10~11時台に最大心拍数120bpm以上を計測した。医師の所見は、心房細動に加え心房粗動を認め、リエントリー回路が2:1の頻度で興奮すると頻拍となるとのことであった。また、カテーテルアブレーションの適応となるが、年齢に対し侵襲的であると判断され見送られた。 【考察】退院後の安全な生活の獲得のため、頻拍を防止する必要があると考えた。150bpm以上の頻拍は、心拍出量の減少を来すと言われている。また、心血管系リスクを低減するためには、無酸素性作業閾値(AT)以下の運動強度で日常生活活動を行うことが良いと考える。高齢者でのATは最大酸素摂取量(V(dot)O2max)の約65%と言われている。ホルタ―心電図の検査結果より、頻拍を計測した時間帯は食事時と理学療法実施時(10~11時台)であると考えられた。本症例は、食事時に病室からデイルームまで約50mを車椅子自操により移動していた。以上より、運動時・運動後に頻拍になる傾向があると考えた。その後、理学療法実施中に脈拍の計測、心電図評価を継続して行った。退院前評価時(第175病日)には、屋内歩行は四点杖で自立した。退院前の安静時脈拍数は70~80bpm程度であった。自由な歩行速度で、短距離歩行後の脈拍数は約100bpm程度であり、Karvonenの式より算出した運動強度は約40%V(dot)O2maxであった。しかし、約40m以上連続で歩行すると、130bpm以上の頻脈になる傾向があり、運動強度は85%V(dot)O2max以上となった。以上のことより、本人・家族に対する退院後の生活指導として、自宅外での移動は車椅子による介助移動を推奨し、歩行する場合は40m程度で休憩することを指導した。自宅内移動は杖歩行自立と設定した。 【まとめ】モニター心電図は、非侵襲的で患者の負担も少なく、多くの心機能情報を得られる評価であると考える。今回、回復期病棟入院患者に対し、運動療法中に心電図評価を行い、退院後の生活指導につながった症例を経験した。回復期病棟では、1日9単位までのリハビリテーション実施が推奨されており、入棟後、身体活動量の急激な増加が考えられる。また、回復期病棟の診療保険点数は、検査・薬剤などの点数が入院料に含まる包括医療制度が採られ、検査、投薬は減らされている。そのような回復期病棟の現状・リハビリテーションの特徴を考えた時、回復期病棟入院患者に対し適切な心血管リスク管理を行い、安全な運動処方・生活指導を行うために、運動時の心電図評価は非常に有用かつ必要であると考えられる。
1 0 0 0 OA 中高年者に適用可能なワーク・ファミリー・バランス尺度の構成
- 著者
- 富田 真紀子 西田 裕紀子 丹下 智香子 大塚 礼 安藤 富士子 下方 浩史
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.89.17223, (Released:2018-11-15)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 4
A work-family balance scale was developed for middle-aged and elderly individuals. Employed people (N =1,351, 788 men and 563 women; age range, 40 to 85 years; mean age, M = 54.82, SD = 9.86 years) in the seventh study-wave of the National Institute for Longevity Sciences-Longitudinal Study of Aging participated in the study. We hypothesized a four-factor structure consisting of “work-to-family conflict,” “family-to-work conflict,” “work-to-family facilitation,” and “family-to-work facilitation.” An item pool based on previous studies was developed and administered to the participants, and confirmatory factor analysis was conducted on their responses. The results identified 16 items related to work-family balance with a four-factor structure, which supported the hypothesis (GFI = .924, RMSEA = .073). Multiple-group analysis of populations based on age group (middle-aged, elderly) and gender established the configural and measurement invariance of the scale. Moreover, reliability (α = .69―.85) and criterion-related validity were confirmed based on mental health. Furthermore, age (the 40s, 50s, 60s, over 70) and gender differences were partially identified in the four subscales that were developed.
1 0 0 0 OA ウコン (Curcuma) 属生薬のヒト肝CYP代謝活性への阻害効果
- 著者
- 西田 裕紀子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.40, 1998
- 著者
- 藤井 達也 西田 裕 阿比留 佳明 山本 雅司 黄瀬 正博
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.11, pp.1872-1877, 1995-11-15 (Released:2008-03-31)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 7 19
Diisopropylamine (DIPA), N, N-diisopropylethylamine (DIPEA), tributylamine (TNBA) and 7-(1-piperazinyl)-4-quinolone-3-carboxylic acid (2) were titrated in water-dimethylformamide (DMF) mixtures containing 45-98% DMF. Apparent pKa values in anhydrous DMF (pKDMF) were calculated by extrapolation from the variation in the half-neutralization pH values in aqueous DMF. The validity of the relative basicity derived from the pKDMFs was confirmed by examination of the kinetics of esterification of a derivative of 2 with 4-(bromomethyl)-5-methyl-1, 3-dioxol-2-one (DMDO-Br). Relative basicities in DMF were : the carboxylate anion of 2»DIPA>DIPEA>TNBA >the amino group in the piperazinyl part of 2. This order is clearly different from that observed in water.We concluded that DIPEA is a suitable agent to suppress the undesired esterification during the reaction to mask the amino group of 2 with a DMDO group, because it does not remove a proton from the carboxyl group, but only from the protonated amino group.
1 0 0 0 OA 地域在住高齢者の転倒恐怖感に関連する要因の検討
- 著者
- 西田 裕紀子 新野 直明 小笠原 仁美 安藤 富士子 下方 浩史
- 出版者
- 日本未病システム学会
- 雑誌
- 日本未病システム学会雑誌 (ISSN:13475541)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.97-99, 2004-08-30 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 42 Barthel Indexにより分類した重症群と軽症群における高齢入院患者の栄養状態の評価について(理学療法基礎系,一般演題(ポスター発表演題),第43回日本理学療法学術大会)
- 著者
- 内山 恵典 森上 亜城洋 西田 裕介
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, 2008-04-20
- 著者
- 森上 亜城洋 西田 裕介 三谷 美歩 中村 昌樹
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.6, pp.1027-1031, 2014
〔目的〕排泄行為と下腿最大周径,身体組成および栄養状態の間の関係性ならびに影響度から排泄行為能力に与える要因を把握することとした.〔対象〕後期高齢入院患者66名.〔方法〕排泄行為(バーサルインデックス)と,下腿長を100%とする腓骨頭下端から26%の部位での下腿最大周径,身体組成(予測身長,体重,BMI,筋肉量),および医科健診での栄養状態(血清アルブミン)との間の関係性を,相関および回帰分析により調べた.〔結果〕排泄行為は下腿最大周径と身体組成と栄養状態との間に有意な相関関係を示した.重回帰モデルにおいて排泄行為に影響する要因として下腿最大周径とAlbが選択された.〔結語〕下腿最大周径とAlbにより排泄行為能力を予測できる. <br>
- 著者
- 内山 恵典 森上 亜城洋 西田 裕介
- 出版者
- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION
- 雑誌
- 日本理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, pp.A0042-A0042, 2008
【はじめに】理学療法の対象となる高齢者の栄養問題の1つに蛋白質・エネルギー低栄養状態(PEM)が挙げられる。PEMは創傷治癒の遅延を招くだけでなく、入院期間の延長や死亡率にまで関係するとされている。これまでの研究で、日常生活動作(ADL)と血清データやBody Mass Index(BMI)との間に関係性は確認されている。一方、高齢者は脊柱の変形などの身体特性から身長を正確に測定することが困難であることが多い。また、ADL状況による栄養状態の変化は、対象者の生活の質にも大きく関わってくると考えられる。そこで本研究では、身長の予測式を用いてBMIと血清アルブミン値との関係性について、ADLの指標であるBarthel Index (BI)を用いて重症群と軽症群に分類し、比較検討した。<BR><BR>【対象と方法】対象は、65歳以上の磐田市立総合病院および公立森町病院における入院患者24名(男性10名・女性14名、平均年齢80.7±6.6歳)とした。対象者(家族含む)には本研究の同意を文書及び口頭で得た。また、本研究は、それぞれの病院に設けられた倫理委員会により承認を得て実施した。主な測定項目は、栄養状態の把握に血清アルブミン値(Alb)をカルテより調査した。また、栄養状態を反映する身体組成の評価として予測身長を用いたBMIを算出した。予測身長は、久保らによる回帰式「身長=2.1×(前腕長+下腿長)+37.0」を用いた。前腕長は、肘90度屈曲位で肘頭部近位部から尺骨茎状突起遠位部を計測し、下腿長は、腓骨頭近位部から外果遠位部までを測定した。データの比較には、対象者をADLの状態からBIが60点未満の者を重症群、60点以上の者を軽症群の2群に分類し、それぞれの群においてAlb、BMIの関係性をピアソンの積率相関を用いて分析した。また、各測定項目の群間の比較には、対応のないt検定を用いて比較した。有意水準はともに5%未満とした。<BR><BR>【結果とまとめ】BIの平均は、全体で60.6±33.4点、重症群で27.0±19.0点、軽症群で84.6±15.4点であった。Alb値の平均値と標準偏差は、全体で3.3±0.53g/dl、重症群で3.09±0.50g/dl、軽症群で3.57±0.47g/dlであった。BMIの平均値と標準偏差は、全体で20.8±3.4、重症群で20.1±3.0、軽症群で21.2±3.6であった。群間の比較では、BIが重症群で有意に低くなった以外は、全ての項目で有意差は認められなかった。一方、AlbとBMIとの関係性ついては、軽症群で、r=0.47と有意な関係性が認められ(p<0.05)、全体と重症群での関係性は、それぞれr=0.2、r=0.36と有意性は認められなかった。以上のことから、栄養状態を評価する際、予測身長を用いたBMIは軽症例に対して応用することが可能であると考えられる。
1 0 0 0 OA 854 高齢者における予測身長を用いた栄養状態の把握および下腿周径とBody Mass Indexとの関係(理学療法基礎系,一般演題(ポスター発表演題),第43回日本理学療法学術大会)
- 著者
- 森上 亜城洋 内山 恵典 西田 裕介
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, 2008-04-20
【はじめに】理学療法評価での栄養評価は、対象者の全身状態を把握すると共に、活動度の把握やプログラムの作成において重要となる。また、理学療法評価の中で広く応用されている栄養評価に Body Mass Index(BMI)がある。しかし、高齢者では脊柱の変形や活動度の低下により適切な身長を計測することは困難なことが多い。そこで本研究では、予測身長を用いてBMIを算出し、身体組成における栄養指標の1つである下腿周径との関係を検討した。さらに、下腿周径は活動度と関連することが知られていることから、Barthel Index(BI)との関係性についても検討した。<BR><BR>【対象と方法】対象は、65歳以上の入院患者24名(男性10名・女性14名、平均年齢80.7±6.6歳)である。対象者(家族含む)に研究内容と倫理的配慮について文書及び口頭にて説明し、研究参加の同意を得た。また、本研究は各施設の倫理委員会の承認を得て実施した。予測身長は、久保らによる回帰式「2.1×(前腕長+下腿長合計)+37.0」を用いた。前腕長は、肘90度屈曲位で肘頭から尺骨茎状突起遠位部までを計測し、下腿長は、膝90度屈曲位で腓骨頭近位部から外果遠位部までを測定した。体重は立位もしくは車椅子対応型体重計にて測定し、予測身長と合わせてBMIを算出した。下腿周径は、腓骨頭から外果中央部の腓骨頭から26%の膨隆部位を測定した。日常生活活動ならびに障害の程度を把握するためBIを用いた。統計的手法にはピアソンの相関係数の検定を行い、5%未満を有意と判定した。<BR><BR>【結果】各項目の平均値を示す。前腕長は22.5±1.8cm、下腿長は29.5±2.2cm、予測身長は146.5±8.1cmであった。BWは45.0±9.8kgであり、BMIは20.8±3.4(男性54±31.4、女性65±35.1)であった。26%下腿周径は28.4±3.8cmであった。相関係数ではBMIと26%下腿周径下腿最大周径はr=0.9であり、男性の26%下腿周径とBIはr=0.64と有意な関係を認めた(ともにp<0.05)。<BR><BR>【まとめ】本研究の結果より、栄養評価であるBMIと26%下腿周径との間には有意な関係性が認められた。このことは、脊柱の変形や活動度の低下等により身長の測定が困難な対象者においても、予測身長を用いることで栄養評価が可能になることがわかる。また、下腿周径は、体重やADLとの相関が高いことが報告されている。本研究においても、男性では26%下腿周径と身体活動状況を反映しているBIとの間に相関関係が認められた。以上のことより、予測身長を用いたBMIは栄養状態を反映し、男性においては26%下腿周径と身体活動状況との間に関係性があることから、26%下腿周径は栄養状態に加え、身体活動状況も反映する指標として、有効な理学療法評価指標になると考えられる。