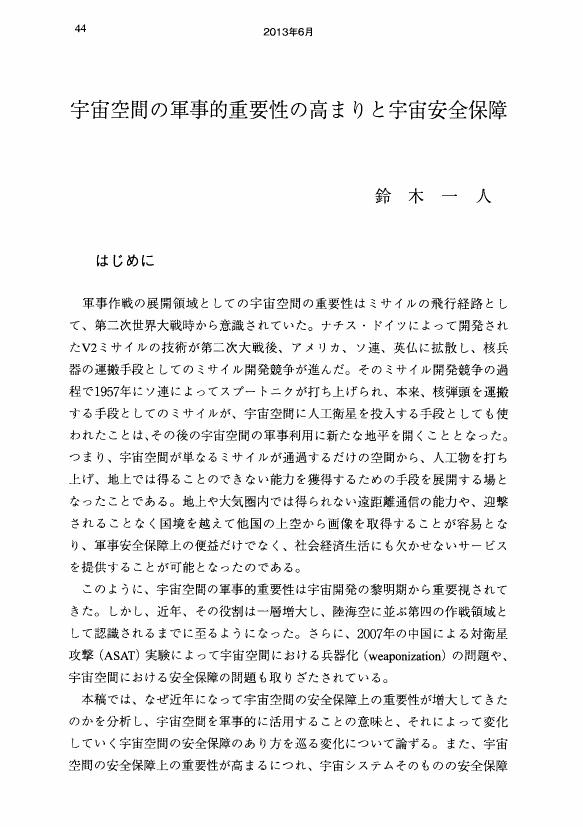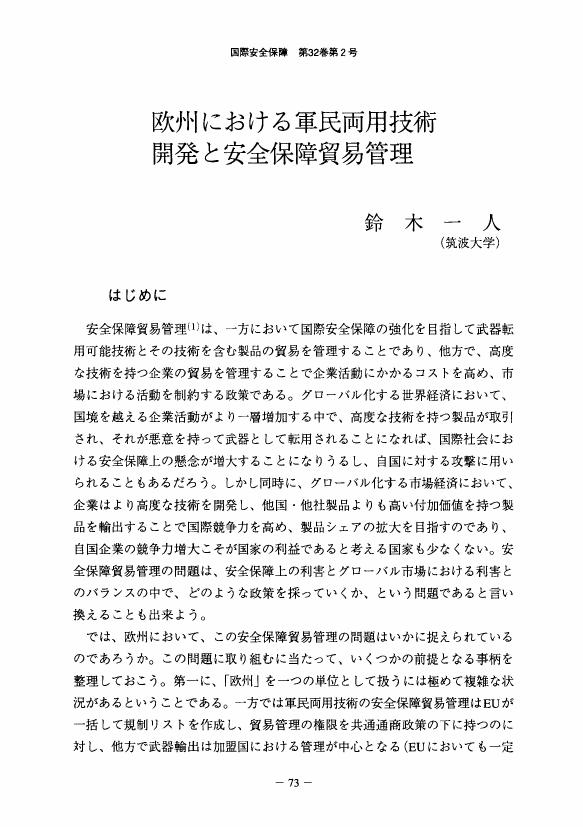1 0 0 0 OA カナダのヘイトプロパガンダ規制を巡る議論の展開
- 著者
- 鈴木 崇之
- 出版者
- 憲法学会
- 雑誌
- 憲法研究 (ISSN:03891089)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.29, 2022 (Released:2022-07-04)
1 0 0 0 OA 「ポスト・オバマ」の社会学 ジェフリー・アレクサンダーの「アメリカ大統領論」を中心として
- 著者
- 鈴木 健之
- 出版者
- 東北社会学研究会
- 雑誌
- 社会学研究 (ISSN:05597099)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, pp.95-114, 2019-10-16 (Released:2021-10-24)
- 参考文献数
- 29
本論は、ジェフリー・アレクサンダーの一連のアメリカ大統領論を手がかりとして、アメリカにおけるユニバーサリズムの理論的・実質的意義を探ろうとするものである。アレクサンダーは「アメリカン・ユニバーサリズム」の信奉者であり、師のタルコット・パーソンズと同様、ユニバーサリズムのさらなる普遍化(一般化)に志向するという点において、「機能主義的伝統」の正統な継承者である。ユニバーサリズムの対極にあるパティキュラリズムは、ユニバーサリスティック・パティキュラリズムである限りにおいて正当化されるものであり、一九六〇年代以降のアメリカにおける公民権運動に代表される「新しい社会運動」はユニバーサリスティック・パティキュラリズムの典型として論じられている。機能主義的伝統において、このアメリカン・ユニバーサリズムを最もよく体現している人こそ、アメリカの大統領であると論じられる。 まず、アレクサンダーの「大統領の社会学」の成立と展開をみていく。次に、パーソンズが取り出した「ユニバーサリズム」と「パティキュラリズム」という二つの社会的価値(パターン変数の一組)を用いながら、アレクサンダーの「オバマ主義」をトランプの視点から相対化する作業を行いたい。そして「オバマ主義」と「トランプ主義」を超克する途をパーソンズの「価値の一般化」の議論に確認し、アメリカ社会(学)の未来を展望することで結論としたい。
1 0 0 0 OA 集団の社会関係資本が主観的健康に及ぼす影響 大学生のクラブ・サークルを対象とした実証研究
- 著者
- 鈴木 伸生
- 出版者
- 東北社会学研究会
- 雑誌
- 社会学研究 (ISSN:05597099)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, pp.137-166, 2016-05-30 (Released:2021-12-29)
- 参考文献数
- 56
健康に対する集団の社会関係資本の効果は、当該集団の「文脈効果」によって生じるのか、それとも「メンバー個人の社会関係資本」によるのか。この問いにこたえるために、本稿では、結束型集団としての大学クラブ・サークルを対象に、集団の構造的・認知的社会関係資本が成員の主観的健康に及ぼす影響について、個人レベルと集団レベルの双方から検討した。 二〇一二年二月~三月にかけて総合大学の学生を対象に実施した調査データを用いて、ロジスティック回帰分析を行った結果、第一に、結束型集団では、集団レベルの構造的社会関係資本のみが主観的健康を促進していた。第二に、結束型集団では、従来健康に対して影響をもつと想定されてきた認知的社会関係資本の文脈効果は、構造的社会関係資本の文脈効果によるものであった。 以上の知見は、先行研究で未検討だった集団の構造的社会関係資本が、主観的健康に対して主要な役割を果たす点を示唆している。ただし、その効果は、一つの結束型集団に所属する個人においてのみ、有効である可能性がある。
1 0 0 0 OA 巻頭言 親子関係とソーシャル・サポート 三つの発達段階に着目して
- 著者
- 鈴木 伸生
- 出版者
- 東北社会学研究会
- 雑誌
- 社会学研究 (ISSN:05597099)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, pp.1-9, 2017-02-28 (Released:2021-12-18)
- 参考文献数
- 22
1 0 0 0 OA 個人化という問いの同時代的意義
- 著者
- 鈴木 宗徳
- 出版者
- 東北社会学研究会
- 雑誌
- 社会学研究 (ISSN:05597099)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, pp.43-60, 2016-05-30 (Released:2021-12-29)
- 参考文献数
- 22
『危険社会』が出版されて三〇年が経ったいまもなお、ベックが論じた個人化は、雇用と貧困における「自己責任」の問題を分析するツールとして利用する価値をもつ。たとえば、イギリス・ブレア政権がワークフェア政策を導入する際、ブレーンであったアンソニー・ギデンズは〝福祉依存〟の予防が必要であると主張していたが、こうした言説はいま、保守政権による過酷なサンクション政策を正当化し、多くの犠牲者を生み出している。ベックはむしろ、失業において個人的な責任が強調され、それが心理的な方法で解決されるようになることを批判していたのである。福祉受給者が福祉に依存し怠けているという非難については、ワークフェア政策がはじめに導入されたアメリカで、ナンシー・フレイザーが依存を心理学的問題に縮減するものであるとして批判している。これらの問題は、現在、ポストフォーディズム時代における自己啓発やフレキシビリティの必要性を説く言説が注目されるようになって、別のかたちで論じられるようになっている。なかでも、中産層の没落への不安と「同調」反応について論ずるコーネリア・コペチュは、ベックに依拠しながらも彼とは逆に「階級社会への回帰」を主張しているが、むしろベックの個人化論が労働者階級はいまだ個人化されつづけていると指摘したことにこそ、意義があると言える。
- 著者
- 鈴木 伸生
- 出版者
- 東北社会学研究会
- 雑誌
- 社会学研究 (ISSN:05597099)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, pp.193-220, 2015-07-10 (Released:2022-01-21)
- 参考文献数
- 43
本稿では、日本の新規大卒就職において、OBへのアクセスとその効果に格差が存在するのかどうかを検証した。一九八八-二〇〇六年に初職についた大卒者を対象に、代表性のあるJLPSデータを用いて分析を行った。 まず、OBへのアクセスについて検討した。その結果、高ランク大学の社会科学系への所属、サークル・部活動への熱心な参加によって、OBへのアクセスが促された。 次に、大企業・官公庁への入職に対するOB利用の効果を検討した。その結果、OB利用の主効果が見られる一方で、大学ランクとOB利用の交互作用効果は確認されなかった。 このように、OBへのアクセスには、高ランク大学の社会科学系か否かによって大きな格差が存在する一方で、OB利用の効果には、そのような格差は見られなかった。さらに、本稿の知見は、サークル・部活を経由するネットワーキングが、OBへのアクセス機会を増やす可能性を示唆している。
- 著者
- 鈴木 毅彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.1, pp.53-54, 2017 (Released:2022-03-02)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 OA スクロール文字の移動速度がユーザの理解に及ぼす影響
- 著者
- 鈴木 崇也 中村 量真 平田 卓 相原 佑次 北 恭成 野本 弘平 中村 芳知 沢田 久美子
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第28回ファジィシステムシンポジウム
- 巻号頁・発行日
- pp.655-658, 2012 (Released:2013-07-25)
情報量が多いのに対し表示スペースが限られているヒューマンインタフェースでは,スクロール文字がよく用いられる.スクロール文字では,その移動速度が速いほど表示される情報量は多くなるが,同時に読むことは困難となる.スクロール文字は読みやすくなければならない.しかも,実際のヒューマンインタフェースでは,その文字が明確に認識し易い事だけでは不十分である.スクロール文字の文が困難なくユーザに理解されなければならないのである. 本研究では,スクロール文字をユーザに示す実験が行われ,彼らの理解の度合いが客観的に計測された.そしてスクロール文字の移動速度がユーザの理解に及ぼす影響が定量的に評価された.
- 著者
- 鈴木 真吾
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.3, pp.61-85, 2021 (Released:2022-03-20)
本稿は、19世紀末から20世紀初頭のイズミルで発生した2つのコレラを事例に、細菌学という新たな科学知の受容、病気という現象の理解、そして現実の疫病対策への影響という理論と実践の両面から、近代オスマン都市の疫病対策を検討する。そしてコレラ対策の中心となった行政医たちに着目し、こうした疾病理解や新聞や雑誌の急速な発達の中で、近代オスマン帝国の衛生政策に地方社会がいかに組み込まれていったかを考察する。 1910年から11年のイズミルにおけるコレラ流行では、それに先立つイスタンブルでの細菌学研究所設立の影響もあり、上水道の断水や患者の隔離の徹底が対策の中心となるなど、1893年の流行の際とは異なる対策の新たな局面も見られた。しかし他方で、コレラの発症には人間側の条件、すなわち人間の身体にコレラ菌の生育に適切な環境が必要であるという理解の下、以前の流行の際に見られた行政・個人双方での諸対策も、「細菌の生育を防ぐ」対策として新たに位置づけられ、実行された。こうした事実から、時代の変遷によるコレラ理解と対策の変容のみならず、細菌学の到来により再編された疾病理解の枠組みの中に従来の対策が新たに意味づけられるという連続性も看取される。 イズミルのような地方都市で、こうした防疫実践を主導したのは、1867年にイスタンブルで開校した文民医学校出身の医師たちであった。帝国各地から集まった医学生は、卒業後、出身地の行政医に任ぜられ、帝国の衛生政策のエージェントの役割を果たした。彼らはコレラ対策の中心となるだけでなく、同時期に発達した新聞や雑誌などのメディアを通じて個人・家庭における日常的な健康維持を啓蒙した。このような活動を通じて、主体的に健康を維持する個人を作り出し、オスマン帝国の国家的な衛生政策に地方都市の個人を組み込む役割を果たしたのである。
1 0 0 0 OA 宇宙空間の軍事的重要性の高まりと宇宙安全保障
- 著者
- 鈴木 一人
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.44-59, 2013-06-30 (Released:2022-04-07)
1 0 0 0 OA 米国の国境管理体制をめぐる諸問題 ―南西国境の活動を中心に―
- 著者
- 鈴木 滋
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.48-66, 2012-12-31 (Released:2022-04-07)
- 著者
- 鈴木 健人
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.97-102, 2008-12-31 (Released:2022-04-20)
1 0 0 0 OA 軍事宇宙インフラにおける民間企業の役割
- 著者
- 鈴木 一人
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.51-74, 2008-09-30 (Released:2022-04-20)
1 0 0 0 OA フランスとESDP ―「ドゴール=ミッテラン主義」の制度化過程―
- 著者
- 鈴木 一人
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.25-48, 2006-12-31 (Released:2022-04-20)
1 0 0 0 OA 日本の安全保障貿易管理 ―その実践と課題―
1 0 0 0 OA 欧州における軍民両用技術開発と安全保障貿易管理
- 著者
- 鈴木 一人
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.73-98, 2004-09-30 (Released:2022-04-24)
1 0 0 0 OA 未成熟な日米の同盟関係
- 著者
- 鈴木 祐二
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1-2, pp.29-41, 2003-09-30 (Released:2022-04-24)
- 著者
- 鈴木 一人
- 出版者
- 一般財団法人 日本国際政治学会
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.207, pp.207_200-207_203, 2022-03-30 (Released:2022-03-31)
1 0 0 0 編集後記
- 著者
- 鈴木 一人
- 出版者
- 一般財団法人 日本国際政治学会
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.205, pp.205_188, 2022-02-04 (Released:2022-03-31)