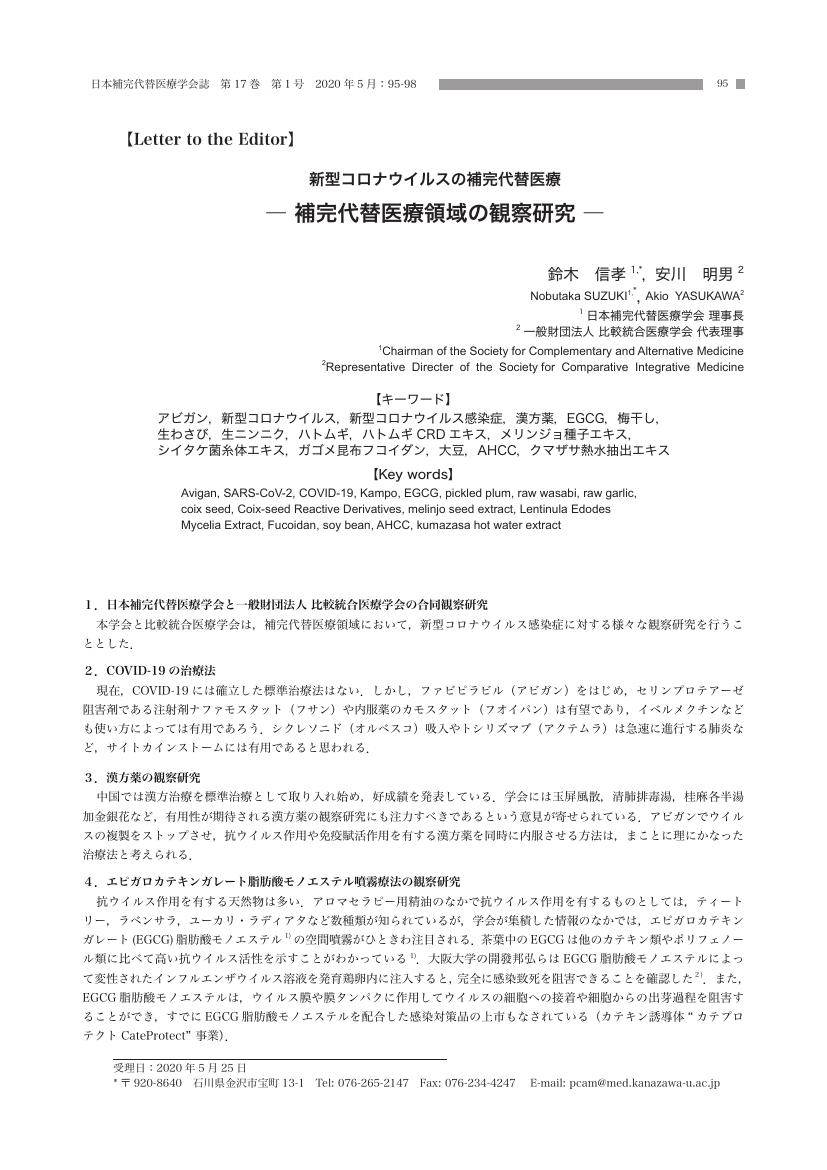2765 0 0 0 国家・政治と宗教的ナショナリズム:比較の視座におけるイランの西部国境地域
- 著者
- 松永 泰行 Colak Vakkas 貫井 万里 横田 貴之 鈴木 啓之
- 出版者
- 東京外国語大学
- 雑誌
- 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))
- 巻号頁・発行日
- 2021-10-07
本研究計画は、国家・政治と宗教的ナショナリズムの研究で未開拓な分野といえる、多民族多宗教国家下で競合するナショナリズム運動間の共存の様態と、その様態において文化ナショナリズムが果たしうる役割を、現地調査を通じた実証研究で明らかにする。本研究を通じ、主に政治的ナショナリズムの諸相に焦点を当てる既存研究の限界を克服し、そこで不問とされている前提を実証的に検証する。
1419 0 0 0 OA 顧客の名字がブランド選択に及ぼす影響 ― 視覚情報としての文字に注目して ―
- 著者
- 外川 拓 磯田 友里子 鈴木 凌 恩藏 直人
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.27-38, 2023-01-10 (Released:2023-01-10)
- 参考文献数
- 33
人は,自身の名前に含まれた文字を,含まれていない文字に比べて好ましく評価する。この傾向はネームレター効果と呼ばれ,ブランド選択をはじめとする様々な意思決定にも影響を及ぼす。例えば,先行研究によると,Lで始まる名前の消費者(例えば,Lundy)は,他の文字で始まる名前の消費者(例えば,Thomas)に比べ,名前の頭文字が一致するLexusを購入する傾向がある。本研究では,ブランド・ネームが漢字で表記されている場合,ネームレター効果がどのように生じるのかについて検討した。先行研究によると,漢字は聴覚情報ではなく,視覚情報として処理される。この言語的性質を踏まえ,漢字のネームレター効果は,ブランド・ネームと顧客の姓における表記(vs. 読み)の一致によって生じると予測した。総合胃腸薬の購買データを分析した結果,表記と読みが太田胃散と一致する太田姓の消費者は,読みのみが一致する姓(例えば,大田姓や多田姓)の消費者や,読みも表記も一致しない姓の消費者に比べて,太田胃散を購入する確率が高かった。本研究の結果は,ブランド・ネームに関する重要な理論的,および実務的示唆を提供している。
1148 0 0 0 OA ハトムギの抗腫瘍ならびに抗炎症作用に関する検討
- 著者
- 鈴木 里芳 徳田 春邦 鈴木 信孝 上馬塲 許 鳳浩 川端 豊慈樹 太田 富久 大竹 茂樹
- 出版者
- 日本補完代替医療学会
- 雑誌
- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.75-85, 2013 (Released:2013-10-30)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 8 2
ハトムギ [Coix lachryma-jobi L. var. ma-yuen Stapf] の子実は,これまで伝統薬として,中国や日本で古くから利用され,抗腫瘍,抗肥満,抗糖尿など様々な機能を持つことが報告されている.われわれは以前よりハトムギの渋皮,薄皮,外殻の生物作用に着目してきた.今回,従来より漢方などで使われてきたハトムギの子実の熱水抽出エキス(ヨクイニン)を比較対象として,子実,渋皮,薄皮,外殻のすべての部分を含む熱水抽出エキス (CRD),ハトムギの有用成分である Monoolein と Trilinolein の抗腫瘍,抗炎症作用を検討した.ヒト由来癌細胞に対する細胞増殖抑制作用については,乳癌細胞 (MCF-7),肺癌細胞 (A-549),喉頭癌細胞 (Hep-2) を用いて評価した.結果は両エキス,Monoolein, Trilinolein ともに各癌細胞に対して弱い増殖抑制効果を認め,その作用はヨクイニンよりも CRD, Monoolein, Trilinolein の方がより強かった.また,発癌予防作用については,ヒトリンパ腫由来の Raji 細胞と発癌プロモーターである TPA (12-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetete) を用いて,特異抗原発現能により評価した.結果は両エキス,Monoolein, Trilinolein ともに特異抗原発現を減少させた.また,ヨクイニンより CRD, Monoolein, Trilinolein がより強く発現を抑制した.一方,Monoolein は Trilinolein よりも強く抑制した.次に,ハトムギの抗炎症作用を検討するために,マウス皮膚上皮由来正常細胞に被検物質を作用させ,紫外線 (UVB) 照射前後ならびに加熱障害前後の細胞形態変化により評価した.結果は UVB 照射前後にかかわらずヨクイニンよりも CRD, Monoolein, Trilinolein が有意に細胞障害を抑制した.また,加熱障害前後については,ヨクイニンの方が CRD より細胞障害を抑制し,Monoolein は Trilinolein より有意に細胞障害を抑制した.以上のことから,子実以外にも渋皮,薄皮,外殻が有用であることが示唆された.さらに,Monoolein と Trilinolein は抗腫瘍,抗炎症を有することが示された.
- 著者
- 鈴木 信孝 滝埜 昌彦
- 出版者
- 日本補完代替医療学会
- 雑誌
- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.47-55, 2021-07-12 (Released:2021-07-15)
- 参考文献数
- 1
886 0 0 0 OA インテリジェントビジョンシステム(IVS)を用いた高速•高精度眼球運動計測装置の開発と評価
- 著者
- 鈴木 一隆 豊田 晴義
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.12, pp.1774-1778, 2007-12-01 (Released:2010-01-29)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 3
High-speed,minute eye movements such as ocular microtremors(OMTs),flicks and saccades contain important information about the health of the subject.Since OMTs have a frequency as high as 100 Hz and minute angular displacement as low as 0.01 degree,measuring the speed and position of OMTs with adequate accuracy under non-contact conditions in the long-term is difficult.To measure a living sample stably and reliably,we have developed a novel system for measuring eye movement by combining an intelligent vision system and the corneal reflex method.The intelligent vision system has both high-speed and real-time parallel image processing capabilities,which measure to a high level of precision at 1 KHz.We have carried out basic experiments usinga simulated eye in conjunction with experiments on OMTs and saccade measurements.The results of these experiments confirmed that such a system is sufficiently accurate.
619 0 0 0 OA 検診発見での甲状腺癌の取り扱い 手術の適応
- 著者
- 鈴木 眞一
- 出版者
- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会
- 雑誌
- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.70-76, 2018 (Released:2018-08-24)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
東日本大震災後の原発事故による放射線の健康影響を見るために,福島県では大規模な超音波検診が開始された。甲状腺検診を実施するとスクリーニング効果から一度に多くの症例が発見されるが,過剰診断にならないように,検診の基準を設定した。5mm以下の結節は二次検査にならず,二次検査後の精査基準も10ミリ以下の小さいものにはより厳格な基準を設けて,過剰診断を防ぐことを準備した上で検診を行った。その結果発見治療された甲状腺癌は,スクリーニング効果からハイリスクは少なく,かつ非手術的経過観察の対象となる様な被胞型乳頭がんは認められず,微小癌症例でも全例浸潤型でリンパ節転移や甲状腺被膜外浸潤を伴っていた。したがって,一次検査の判定基準,二次検査での精査基準さらに手術適応に関する基準などから,超音波検診による不利益は極めて少ないものと思われた。一方で発見甲状腺癌は過剰診断ではないのであれば,放射線の影響による甲状腺癌の増加ではと危惧されるが,現時点ではその影響を示唆する様な事象は得られていない。以上より,放射線被曝という特殊状況下で検診を余儀なくされたにも関わらず,厳格な基準を設定しこれを遵守しながら実施することによって,過剰診断という不利益を極力回避できていることがわかった。
- 著者
- 鈴木,翔
- 出版者
- 不明
- 雑誌
- 日本教育社会学会大会発表要旨集録
- 巻号頁・発行日
- no.62, 2010-09-13
406 0 0 0 OA 液体炭酸人工降雨法の普及に向けて ―2013年の液体炭酸散布による人工降雨実験事例―
- 著者
- 真木 太一 守田 治 鈴木 義則 脇水 健次 西山 浩司
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.2_88-2_93, 2015-02-01 (Released:2015-06-05)
- 参考文献数
- 7
356 0 0 0 OA 水子供養にみる胎児観の変遷
- 著者
- 鈴木 由利子
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.205, pp.157-209, 2017-03-31
水子供養が、中絶胎児に対する供養として成立し、受容される経緯と現状についての調査と考察を行った。水子供養が一般化する以前の一九五〇年代、中絶胎児の供養は、人工妊娠中絶急増を背景として中絶手術を担った医療関係者によって散発的に行われた。一九六五年代には、中絶に反対する「いのちを大切にする運動」の賛同者により、中絶胎児と不慮死者を供養する目的で「子育ていのちの地蔵尊」が建立され、一般の人びとを対象とした供養を開始した。一九七一年になると、同運動の賛同者により、水子供養専門寺院紫雲寺が創建された。同寺は中絶胎児を「水子」と呼び、その供養を「水子供養」と称し、供養されない水子は家族に不幸を及ぼすとして供養の必要を説いた。参詣者の個別供養に応じ、個人での石地蔵奉納も推奨した。この供養の在り方は、医療の進歩に伴い胎児が可視化される中、胎児を個の命、我が子と認識し始めた人びとの意識とも合致するものだった。また、中絶全盛期の中絶は、その世代の多くの人びとの共通体験でもあり、水子は不幸をもたらす共通項でもあった。胎児生命への視点の芽生えを背景に、中絶・胎児・水子・祟りが結びつき流行を生みだしたと考えられる。水子供養が成立し流行期を迎える時代は、一九七三年のオイルショックから一九八〇年代半ばのバブル期開始までの経済停滞期といわれたおよそ一〇年間であった。一方、水子供養の現状について、仏教寺院各宗派の大本山・総本山を対象に、水子供養専用の場が設置、案内掲示があるか否かを調査した。結果、約半数の寺院境内に供養の場が設置されているか掲示がみられ、明示されない寺も依頼に応じる例が多い。近年の特徴として、中絶胎児のみならず流産・死産・新生児死亡、あるいは不妊治療の中で誕生に至らなかった子どもの供養としても機能し始めている。仏教寺院を対象とした水子供養の指針書の出版もみられ、水子供養のあるべき姿やその意義が論じられている。
346 0 0 0 OA 北海道入江貝塚出土人骨にみられた異常四肢骨の古病理学的研究
- 著者
- 鈴木 隆雄 峰山 巌 三橋 公平
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.2, pp.87-104, 1984-04-15 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 3 4
北海道西南部の内浦湾に所在する入江貝塚から出土した,縄文時代後期に属する成人骨格の四肢骨に明らかな病理学的所見が認められたので報告する。この個体(入江9号人骨)は思春期後半に相当する年令段階にあると考えられるが,その四肢長骨は総て著しい横径成熟障害を示し,また長期の筋萎縮に続発したと考えられる骨の著明な廃用萎縮を呈していた。このような長骨の形態異常は長期に経過する筋麻痺を主体とした疾病の罹患によってもたらされるものと考えられるが,そのような疾患について,好発年令,発生頻度,麻痺分布,生命予后などの点から考察した。その結果,この入江9号人骨にみられた四肢骨病変の原疾患として急性灰白髄炎(急性脊髄前角炎,ポリオ,小児マヒ)が最も強く疑われた。
335 0 0 0 OA 運動と免疫
- 著者
- 鈴木 克彦
- 出版者
- 日本補完代替医療学会
- 雑誌
- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.31-40, 2004 (Released:2004-04-27)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 1
適度な運動は免疫能を高め,感染症や癌の予防に有効とされる一方,激しい運動やトレーニングは免疫能を弱め,炎症やアレルギーを助長するとされる.これらの機序については,激しい運動やトレーニングに伴い血中 NK 細胞・ T 細胞の数や機能,分泌型 IgA の唾液濃度などが一過性に低下し,免疫抑制作用のあるストレスホルモンや抗炎症性サイトカインが分泌され,易感染性につながると考えられている.一方,激運動に伴い好中球・単球が動員され活性酸素の産生が高まり,炎症反応や酸化ストレスを引き起こすが,適切な栄養・休養に加え,抗酸化物質等のサプリメントの使用によりこれらの反応を制御できる可能性が示されつつある.また,適度な運動習慣がストレスや感染に対する抵抗力(防衛体力)を強化するという科学的根拠が集積されつつある.本稿では予防医学・補完代替医療の適用の是非を念頭に置いて,運動免疫学分野の最新の研究成果を紹介する.
317 0 0 0 OA 恋人の有無が中学生の意識に与える影響 : 「恋人のできやすさ」に着目して
- 著者
- 鈴木 翔 須藤 康介 荒川 智美 寺田 悠希 澁谷 功太郎
- 出版者
- 東京大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 東京大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13421050)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.103-116, 2012-03-10
The purpose of our study is to make clear the significance of a boyfriend or girlfriend for junior high school students. For this purpose, we firstly investigated the determining factors of having a boyfriend/girlfriend, and then clarified the effects of the fact that one has a boyfriend/girlfriend on their self-consciousness. As a result of our analyses, we got following two findings. First, there are various factors which determine whether junior high school students have a boyfriend/girlfriend or not, and the factors differ according to each student's gender. Furthermore, the levels of academic accomplishment of the school also make a difference. Second, when we analyze the effects of that fact on their self-consciousness, it is necessary to consider not only the very thing that one has a boyfriend/girlfriend or not, but also if she or he is likely to have a boyfriend/girlfriend. Our analysis suggests that a success in love for girls in junior high has a more complex meaning compared with that for boys.
316 0 0 0 心霊スポットの空間分布パターンにみる超常現象観の時代変化
- 著者
- 鈴木 晃志郎 于 燕楠
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, 2019
<b>研究目的</b><br><br> 本発表は,地理学が得意とする空間的可視化の手法を用いて,富山県内の心霊スポットの分布が現代と100年前とでどう異なるかを空間解析し,その違いをもたらす要因について考察することを目的とする.本発表はエミックに扱われがちな事象をエティックに捉える試みであり,民俗学を中心に行われてきた妖怪変化の分類学を志向するものでもなければ,超常現象そのものの有無を論ずるオカルティズム的な関心も有しない.<br> 超常現象が何であるにせよ,それらが超常現象となり得るには,人目に触れ認知されなければならない.ゆえに超常現象は高度に文化的であり,その舞台として共有される心霊スポットは,組織化され商業化された一般的な娯楽からは逸脱した非日常体験を提供する「疎外された娯楽(Alienated leisure)」(McCannell 1976: 57)の1つとして社会の文化的機能のなかに組み込まれているとみなしうる.その機能に対して社会が与える価値づけや役割期待の反映として心霊スポットの布置を捉え,その時代変化を通じて霊的なものに対する社会の側の変容を観察することは,文化地理学的にも意義があると考えられる.<br><br><b>研究方法・分析対象</b><br><br> 2015年,桂書房から復刻された『越中怪談紀行』は,高岡新報社が1914(大正3)年に連載した「越中怪談」に,関係記事を加えたものである.県内の主要な怪談が新聞社によって連載記事として集められている上,復刻の際に桂書房の編集部によって当時の絵地図や旧版地形図を用いた位置情報の調査が加えられている.情報伝達手段の限られていた当時,恐らく最も網羅的な心霊スポットの情報源として,代表性があるものと判断した.この中から,位置情報の特定が困難なものを除いた49地点をジオリファレンスしてGISに取り込み,100年前グループとした.比較対象として,2018年12月にインターネット上で富山県の心霊スポットに関する記述を可能な限り収集し,個人的記述に過ぎないもの(社会で共有されているとは判断できないもの)を除いた57の心霊スポットを現代グループとした.次にGIS上でデュアル・カーネル密度推定(検索半径10km,出力セルサイズ300m)による解析を行い,二者の相対的な分布傾向の差異を可視化した.このほか,民俗学的な知見に基づきながら,それらの地点に出現する霊的事象(幽霊,妖怪など)をタイプ分けし,霊的事象と観察者の側とのコミュニケーションについても,相互作用の有無を分類した.<br><br><b>結 果</b><br><br> 心霊スポットの密度分布の差分を検討したところ,最も顕著な違いとして現れたのは,市街地からの心霊スポットの撤退であった.同様に,大正時代は多様であった霊的事象も,ほぼ幽霊(人間と同じ外形のもの)に画一化され,それら霊的事象との相互作用も減少していることが分かった.霊的なものの果たしていた機能が他に代替され,都市的生活の中から捨象されていった結果と考えられる.<br><br><b>文 献</b>:<br>MacCannell, D. 1976. <i>The Tourist: A new theory of the leisure class</i>. New York: Schocken Books.
289 0 0 0 日本列島とその周辺地域の深発地震の震源分布 : 和達・ベニオフ面の検討
- 著者
- 島弧深部構造研究グループ 赤松 陽 原田 郁夫 飯川 健勝 川北 敏章 小林 和宏 小林 雅弘 小泉 潔 久保田 喜裕 宮川 武史 村山 敬真 小田 孝二 小河 靖男 佐々木 拓郎 鈴木 尉元 鈴木 義浩 山崎 興輔
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地球科学 (ISSN:03666611)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.9-27, 2009
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2
島弧深部構造研究グループは,気象庁2006年刊行の地震年報によって,日本列島とその周辺地域で1983年から2005年までに発生した地震の震源分布を検討した.そのうち100km未満の地震はM4.5以上,100km以深の地震についてはM3以上のものを取り上げ,陸上は400mごとの等高線,海域は400mごとの等深線で示された地形図上にプロットして検討資料とした.震源の空間的な分布を明らかにするために,地震の分布する空間の下底の等深線を描いた.等深線は,北海道から千島列島に沿う地域では千島・カムチャツカ海溝付近から北西方に,本州に沿う地域では日本海溝付近から西方に,伊豆・小笠原諸島に沿う地域では伊豆・小笠原海溝付近から南西方に,九州ないし南西諸島とその周辺地域では,琉球海溝付近から北西方に次第に深くなるような傾向を示す.より細かく検討すると,等深線は単純ではない.等深線中に,直線状ないし弧状に走り,隣の単元に数10kmあるいはそれ以上に不連続的に変位する単元を識別できる.このような不連続部は,北海道・千島列島地域では北西-南東方向に走り,各深さのこのような不連続部は雁行状に並ぶ.これらの不連続変位部に境された一つの単元の拡がりは100ないし400kmである.より大きな不連続線として国後島の東縁付近と北海道中央を通るものが識別される.千島海盆付近で等深線は南東方に張り出しているが,これは千島海盆付近で震源分布域が下方に膨らんでいることを示す.本州東北部と,日本海の東北部および中央部では,直線状あるいは弧状に走る等深線を北西-南東と東西方向の不連続線が切る.これらによって境された単元の拡がりは100ないし200kmである.より大きな不連続線として,日本海南西部から本州の中央部を走る線が識別される.伊豆・小笠原諸島地域では,直線状あるいは弧状の等深線を切る不連続部は東北東-西南西方向をとる.これら不連続変位部に境された単元の拡がりは数10ないし200kmである.より大きな不連続線として伊豆・小笠原諸島北部と中央部を走るものが識別される.九州・南西諸島とその周辺地域では,直線状あるいは弧状の等深線を切る不連続部は東北東-西南西方向に走る.これら不連続部に境された単元の拡がりは80ないし250kmである.より大きな不連続線として大隈諸島と奄美大島間を走る線が識別される.このように,和達・ベニオフ面とよばれるものは地塊構造を暗示させる垂直に近い線によって境された,より小さな分節にわかれることが明らかになった.
258 0 0 0 OA 鰹節原料カツオの交番電流処理による脱脂について
- 著者
- 鈴木 康策
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.7-8, pp.435-437, 1957-11-25 (Released:2008-02-29)
- 参考文献数
- 2
In obtaining skipjack having so little body oil as to be suitable for making good “Katsuobushi” thereof, we cannot still to-day but rely on the natural coming of such material. If we had, therefore, any proper means of removing excessive oil from the fish, we would be able to remove also the limitation arising from the seasonal overgrowth of skipjack oil. Carrying out a few experiments on a small scale, the author has ascertained that very satisfactory results can be achieved by applying an alternating current to the material interposed intimately between the electrodes kept in running water. The results are summarized as follows. 1. The higher the voltage, the less oil remains in the meat after the treatment by an electric device shown schematically in Fig. 2. 2. Ampere of the electric current is not of consequence for the effective removal of the body oil. The best range of available voltage is 170-200 V., while too high voltages cause the meat to crack. 3. Continuous refreshment of water surrounding the meat as shown in Fig. 2 is essential to avoiding large and fruitless consumption of electric energy.
248 0 0 0 OA 診断までに1年半を要した膣内異物の5歳女児例
- 著者
- 岩川 眞由美 鈴木 利弘 大川 治夫 金子 道夫 堀 哲夫 池袋 賢一 雨海 照祥 中村 博史 平井 みさ子 野田 秀平
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本小児外科学会
- 雑誌
- 日本小児外科学会雑誌 (ISSN:0288609X)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.765-769, 1997-06-20 (Released:2017-01-01)
- 参考文献数
- 25
幼小児の帯下は,非特異性外陰膣炎が原因であることが多いが膣内異物も忘れてはならない疾患である. 今回,異物による帯下を主訴としながらも,多数の医療機関にて診断がつかず1年半の病悩期間を有した5歳児を経験した. 異物は全麻下にペアン,布鉗子の湾曲を利用しつつ容易に摘出できた. 摘出された異物は,ビー玉3個,人形の靴1足,プラスチックのビーズ7個,菓子包装紙1枚であった. 摘出後は経過良好で帯下も消失した.
219 0 0 0 OA 新型コロナウイルスの補完代替医療 ― 補完代替医療領域の観察研究 ―
- 著者
- 鈴木 信孝 安川 明男
- 出版者
- 日本補完代替医療学会
- 雑誌
- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.95-98, 2020-05-26 (Released:2020-06-09)
- 参考文献数
- 16
209 0 0 0 OA 東京とその周辺における火山災害の歴史と将来
- 著者
- 鈴木 毅彦
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.6, pp.1088-1098, 2013-12-25 (Released:2014-01-16)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1 6
This paper reviews historical volcanic disasters that have affected the Tokyo Metropolitan area and its surroundings, central Japan, and discusses the dangers of volcanic disasters occurring in future. The 1707 (Hoei) eruption of Fuji volcano, the 1783 (Tenmei) eruption of Asama volcano, and the so-called Kanto Loam, volcanic soil deposits containing large quantities of Holocene to Pleistocene fall-out tephras, suggest the potential hazards that originate from volcanic activities. Small to moderate eruptions (VEI 1 to 2) of Asama volcano have resulted in minor ash falls in and around Tokyo every one to two decades. It is most likely that Asama volcano will generate minor ash falls in the near future. Volcanic disasters caused by larger but rare eruptions of VEI 4 to 5 are considered, referring to the 1707 (Hoei) eruption of Fuji volcano, and measures and predictions for the next eruption of Fuji volcano. In this paper, volcanic disasters affecting Tokyo in the near future are not only those caused by ash falls but also those caused by lahar along the Tone, Edo, Sakawa, and Sagami rivers related to Asama, Haruna, and Fuji volcanoes, because the landform developments of these areas in Holocene and historical disasters suggest that these drainage basins have the potential for lahar disasters. In addition, more severe eruptions of VEI 6 to 7 are considered for their impacts and frequencies referring to geological records of air-fall tephras and/or pyroclastic flow deposits such as VEI 6 Hakone-Tokyo tephra (ca. 66 ka) and VEI 7 Aira-Tn tephra (ca. 29 ka).
203 0 0 0 IR 〔論 文〕 日本における「スパルタ教育」理解
- 著者
- 鈴木 円 Madoka SUZUKI 昭和女子大学初等教育学科
- 出版者
- 光葉会
- 雑誌
- 學苑 = GAKUEN (ISSN:13480103)
- 巻号頁・発行日
- vol.892, pp.83-95, 2015-02-01
The term Spartan education, translated into Japanese as "Suparuta kyoiku" is widely used nowadays to mean "severe education." This paper reviews 12 Japanese books or articles on Spartan education published from the 1870s to the 1970s and examines how the authors have understood Spartan education and in what context they have used the term. The above materials, published from the early Meiji to post-war period, suggest that Japanese learned about the education system of ancient Sparta from Western academic sources. However, after the influential bestseller, Shintaro Ishihara's Suparuta Kyoiku(Spartan Education; A book for raising tough kids), was published, leading Japanese educators seem to have begun using the term "Suparuta kyoiku" to mean Japanese militaristic education. Historically, Western classical scholars have acknowledged the value of Spartan public education in contrast to Athenian individualistic education. However, Japanese educators seem to have failed to understand the value of Spartan education because of the change in the understanding of the term "Suparuta kyoiku." The author concludes that educators ought to have used that term with that original sense in mind.
201 0 0 0 OA 日本における生活行為のリスク比較
- 著者
- 小川 順子 森 伸介 鈴木 正昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会 年会・大会予稿集 2004年秋の大会
- 巻号頁・発行日
- pp.5, 2004 (Released:2004-11-19)
一般人に原子力発電の理解を求めるために、しばしば原子力発電のリスクが様々な「生活行為のリスク」と比較される。「生活行為のリスク」は、1979年米国ピッツバーグ大学Cohenによって計算された「様々なリスクの比較表」に載っている値が一般によく使われており、原子力の広報にも役立ってきた。しかしながら、これらは25年前のしかも米国のデータで計算されたリスクである。そこで我々は、現代日本の状況に合った日本におけるリスク表に改訂することを目的に、「ガン」、「心臓病」、「自動車事故」、「火事」、「脳卒中」、「肺炎/インフルエンザ」、「エイズ」、「独身(男性)」、「独身(女性)」「喫煙」、「肥満」、「飲酒」、「自殺」、「殺人」、「航空機墜落事故」、「原子力産業」、「自然放射線」、「地層処分」、「大気汚染」、「屋内煙検知器」、「エアバッグ」の21項目のリスクについて損失寿命を算出した。