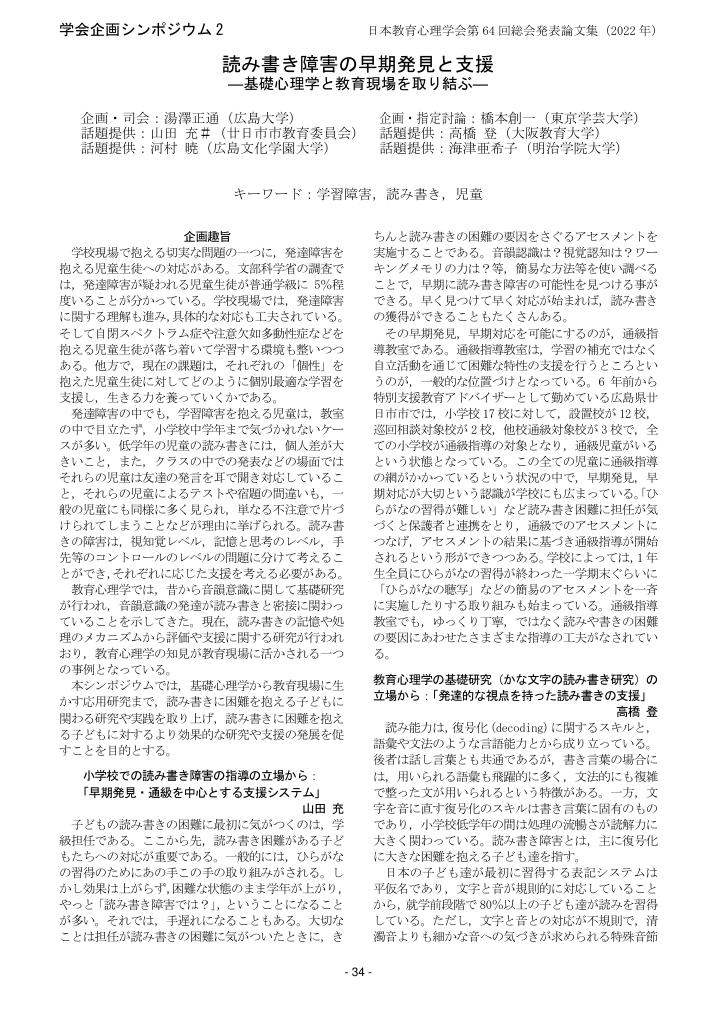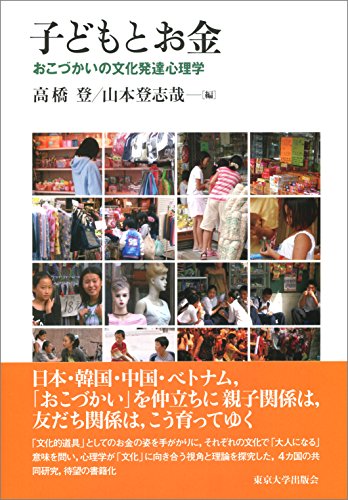6 0 0 0 OA 学童期における読解能力の発達過程 1-5年生の縦断的な分析
- 著者
- 高橋 登
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.1-10, 2001-03-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 10 15
本研究の目的は, 学童期の読解能力の発達過程を縦断的に分析することであった。被験児は大阪府内の公立小学校に通う, 高橋 (1996a) の就学前後の縦断研究に参加した子ども達であった。本報告では1・3・5年生の冬に行われた読解能力と, 関連する諸能力との間の関係が分析された。その結果, 以下の諸点が明らかになった。かな単語の命名速度は1年生の段階ではひらがなの読みの習得時期によって異なり, しかもこの時期の読解能力を規定していたが, 学年が上昇するに従い習得時期による違いはなくなり, しかも読解能力への影響力も少なくなっていった。一方漢字の符号化も5年生の読解能力を規定するものではなかった。従って符号化レベルでの処理の効率性は, 小学校高学年段階では読解能力を規定するものとはならないと考えられた。それに対して語彙は低学年から高学年まで読解を規定するものであり続けた。しかも学童期の語彙は, 前の調査時期の読解能力によっても説明されるものであった。このことはこの時期の子ども達が読むこと, すなわち読書を通じて語彙を増やし, それがまた読解の能力を高めるという相互的な関係にあるものであることを示すものと考えられた。
- 著者
- 呉 宣児 山本 登志哉 高橋 登 Takeo Kazuko Sato Tatsuya Pian Chengnan
- 出版者
- 共愛学園前橋国際大学
- 雑誌
- 共愛学園前橋国際大学論集 (ISSN:2187333X)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.125-135, 2009
研究ノート
2 0 0 0 OA 読み書き障害の早期発見と支援 基礎心理学と教育現場を取り結ぶ
- 著者
- 湯澤 正通 橋本 創一 山田 充 高橋 登 河村 暁 海津 亜希子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集 第64回総会発表論文集 (ISSN:21895538)
- 巻号頁・発行日
- pp.34-35, 2022 (Released:2022-10-20)
- 著者
- 柴山 真琴 ビアルケ(當山) 千咲 高橋 登 池上 摩希子
- 出版者
- 大妻女子大学人間生活文化研究所
- 雑誌
- 人間生活文化研究
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, no.29, pp.236-256, 2019
<p> 本研究では,小学校高学年児の国際児が,親の支援を受けながら現地校と補習校の宿題を遂行する過程で,どのような家族間調整がなされているのかを独日国際家族の事例に基づいて検討した.日本人母親が記録した約4 年間の日誌記録を「生態学的システム」の修正モデルを分析枠組みにして,家族間の調整過程を具体的に分析した結果,次の3 点が明らかになった.第一に,父母間では,対象児の学年に拘らず,自分が母語とする言語の宿題を支援する言語別役割分担を基本とする支援パターンが形成されていた.第二に,この言語別役割分担は,宿題をめぐる親子間調整の基本単位ともなっていた.現地校宿題をめぐる父子間調整は円滑に進んでいたが,補習校宿題をめぐる母子間調整では対立が頻発していた.第三に,対象児は,自分と活動(宿題遂行)との間に不具合が生じた時に,自らの環境認知に基づいて親に働きかけたり自らの行動を変化させたりする調整を行っていた.対象児の調整過程では,「役割期待」「時間展望」「目標構造」という3 つの軸が参照されていたと考えられる.</p>
- 著者
- 高橋 登 中村 知靖
- 出版者
- 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 = The Japanese journal of developmental psychology (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.37-49, 2020-03
- 著者
- 川端 皐月 高橋 登
- 出版者
- 大阪教育大学
- 雑誌
- 大阪教育大学紀要. 総合教育科学 = Memoirs of Osaka Kyoiku University (ISSN:24329630)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.163-178, 2020-02
2 0 0 0 OA 〈コミュニケーション障害と発達心理学の接点〉学童期の語彙能力
- 著者
- 高橋 登
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- コミュニケーション障害学 (ISSN:13478451)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.118-125, 2006-08-31 (Released:2010-04-21)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
本論文では,学童期の語彙獲得の過程について検討した.子ども達は,学童期も幼児期に劣らず多くの語彙を日々獲得している.ただし,そのプロセスは幼児期とは大きく異なる.第1に,子どもの語彙理解は時間をかけて深く,また広くなっていく.第2に,一定の語彙を獲得すると,その要素の知識に基づいて,それを組み合わせた新しい語の意味を推測によって知ることができるようになる.そして第3に,学校での授業だけでなく,たとえ1日あたりの読書時間はささやかなものであっても,それが積み重なることで子ども達は多くの言葉に接し,文脈から新たな言葉の意味を身に付けていく.
2 0 0 0 集団での絵本の読み聞かせ場面における子ども達の相互作用について
- 著者
- ビアルケ (當山) 千咲 柴山 真琴 高橋 登 池上 摩希子
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.172, pp.102-117, 2019 (Released:2021-04-26)
- 参考文献数
- 19
本研究は,ドイツの補習校に通い,ドイツ語を優勢言語,日本語を継承語とする独日国際児の事例において,二つの異なるジャンルの二言語の作文力が,小4から中3まででどのように形成されるのかを分析した。対象児は,日本居住の日本語母語児に比べ産出量や語彙,構文の多様性等の伸びが遅れながらも,談話レベルでは母語児に近い評価の作文を書いていた。その背景を二言語作文の縦断的分析により探ったところ,優勢なドイツ語に牽引されるように日本語も伸び,まず接続表現や構文の複雑化によって論理的つながりが改善され,次に全体構成や内容の高度化が生じることがわかった。またドイツ語作文のレベルに近い日本語作文を,限られた日本語の表現手段を工夫して書いているが,複雑な内容の説明における文法的誤用や漢字熟語の不足等に表現上の困難が見られた。以上の発達過程の特徴から,補習校での指導への示唆を抽出した。
1 0 0 0 OA テレビ漫画を材料とした物語理解の発達的研究
- 著者
- 高橋 登 杉岡 津岐子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.135-143, 1988-06-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this study was to investigate how children understood the plot of animated cartoons. Elementary school children from 1st grade through 6th grade and college students were to watch a T.V. cartoon. And then, they were asked about the story. The content of the interview consisted of two points: One was about the recall of the story, i.e., how much they would remember the content of the story, and the other was about the understanding of the characters, i.e., what attitudes they have toward them. The main results were as follows: 1) All groups of Ss remembered the story in structurally organized manner, but 2) the lower graders' recall was more episodic ; 3) Elementary school children were seen to have more extreme attitudes toward the characters than college students. It was concluded that story understanding was at first based on fragmentary information gradually becoming based on more integrated information.
1 0 0 0 OA ミネラルウォーターの成分組成について
- 著者
- 高橋 登枝子 徳村 治彦
- 出版者
- [愛知県食品工業試験所]
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.28-32, 1982 (Released:2011-03-05)
1 0 0 0 OA 第55回(2019年度)城戸奨励賞 選考経過および講評
- 著者
- 大塚 雄作 犬塚 美輪 高橋 登
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.228, 2021-03-30 (Released:2021-11-16)
修正 「Ⅰ.選考経過」の「2.選考委員」のリストに以下を追加。 金山元春
- 著者
- 柴山 真琴 ビアルケ(當山) 千咲 高橋 登 池上 摩希子
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.357-367, 2016 (Released:2018-12-20)
- 参考文献数
- 30
本稿では,国際結婚家族の子どもが二言語で同時に読み書き力を習得するという事態を,個人の国境を越えた移動に伴う国際結婚の増加というグローバル化時代の一側面として捉え,こうした時代性と子どもの言語習得とのインターフェースでどのような家族内実践が行われているのかを,ドイツ居住の独日国際家族の事例に基づいて紹介した。特に子どもの日本語の読み書き力形成にかかわる家族内実践にみられる特徴として,(1)現地の学校制度的・言語環境的要因に規定されつつも,利用可能な資源を活用しながら,親による環境構成と学習支援が継続的に行われていること,(2)家族が直面する危機的状態は,子どもの加齢とともに家庭の内側から生じているだけでなく,家庭と現地校・補習校との関係の軋みからも生じているが,家族間協働により危機が乗り越えられていること,が挙げられた。ここから,今後の言語発達研究に対する示唆として,(1)日本語学習児の広がりと多様性を視野に入れること,(2)子どもの日本語習得過程を読み書きスキルの獲得に限局せずに長期的・包括的に捉えること,(3)子どもが日本語の読み書きに習熟していく過程を日常実践に埋め込まれた協働的過程として捉え直すこと,の3点が引き出された。
1 0 0 0 自由なドラムス演奏の複数尤度を用いたHMMによる自動伴奏
- 著者
- 林 耕平 高橋 登紀夫 永田 晃弘 嵯峨山 茂樹
- 雑誌
- 研究報告音声言語情報処理(SLP) (ISSN:21888663)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018-SLP-122, no.45, pp.1-5, 2018-06-09
これまで,人間の演奏に自動伴奏付けを行う研究は広く行われてきたが,奏者は与えられた楽譜に従って演奏を行うという前提があった.そこで,本稿ではドラムスという楽器における,より即興的な演奏に対して自動伴奏付けを行う手法について議論する.まず,自由なドラムス演奏をリズムパターンの同期遷移や接続によって行われるものとして近似し,HMM (Hidden Markov Model) を用いてモデル化を行う.モデルの確率的な逆問題を解くことで,演奏のリズムパターンや演奏箇所の推定を行う.具体的には複数の尤度計算とテンポ推定を行い,Viterbi アルゴリズムによってモデルの最尤状態を推定する.また,ここまでの手法を評価するために実験を行い,高い精度で演奏箇所の推定が行われることを示す.更に,本稿では自動伴奏付けの構想についても述べる.
1 0 0 0 子どもとお金 : おこづかいの文化発達心理学
- 著者
- 高橋登 山本登志哉編
- 出版者
- 東京大学出版会
- 巻号頁・発行日
- 2016
1 0 0 0 OA 幼児の役割遊び・ふり遊びと「心の理論」の関連
- 著者
- 小川 真人 高橋 登
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.85-94, 2012-03-20 (Released:2017-07-27)
本研究では,「心の理論」とふり遊び,役割遊びの関係について実験的に検討した。モジュール説が想定するようにふりと「心の理論」が同一のメカニズムで説明可能であるとすれば,ふり遊びと心の理論との間に直接の関連が見られるであろうし,理論説やシミュレーション説が妥当であるとすれば,その間に直接の関連は見られないであろう。ただし,シミュレーション説による説明が妥当なものであるとすれば,ふり遊びは役割遊びを可能にすることを通じて「心の理論」の獲得を助けるであろう。本研究では,実験1において誤信念課題を実施し,あわせてふり遊びと役割遊びの課題を実施することで,「心の理論」とふり遊び,役割遊びの間の関係を実験的に検討し,実験2では,短期縦断的にふり遊びと役割遊びを子ども達に経験させ,それが子どもたちの「心の理論」獲得を助けることになるのか検討した。結果,実験1ではふり遊びと「心の理論」の関連は見られず,役割遊びにおいてのみ「心の理論」との関連が見られた。また,ふり遊びと役割遊びにおいても関連が見られた。さらに実験2ではふり遊び訓練の効果は見られず,役割遊びを訓練的に行うことで「心の理論」課題の得点が高くなった。本研究では,ふりにおける物の見立てや,現実とふりの区別と「心の理論」との関連は見られず,役割遊びにおいて他者の視点に立ち,そこで他者の感情や行動を考えることが「心の理論」と関連すると考えられた。
- 著者
- 柴山 真琴 ビアルケ(當山) 千咲 高橋 登 池上 摩希子
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.357-367, 2016
<p>本稿では,国際結婚家族の子どもが二言語で同時に読み書き力を習得するという事態を,個人の国境を越えた移動に伴う国際結婚の増加というグローバル化時代の一側面として捉え,こうした時代性と子どもの言語習得とのインターフェースでどのような家族内実践が行われているのかを,ドイツ居住の独日国際家族の事例に基づいて紹介した。特に子どもの日本語の読み書き力形成にかかわる家族内実践にみられる特徴として,(1)現地の学校制度的・言語環境的要因に規定されつつも,利用可能な資源を活用しながら,親による環境構成と学習支援が継続的に行われていること,(2)家族が直面する危機的状態は,子どもの加齢とともに家庭の内側から生じているだけでなく,家庭と現地校・補習校との関係の軋みからも生じているが,家族間協働により危機が乗り越えられていること,が挙げられた。ここから,今後の言語発達研究に対する示唆として,(1)日本語学習児の広がりと多様性を視野に入れること,(2)子どもの日本語習得過程を読み書きスキルの獲得に限局せずに長期的・包括的に捉えること,(3)子どもが日本語の読み書きに習熟していく過程を日常実践に埋め込まれた協働的過程として捉え直すこと,の3点が引き出された。</p>
1 0 0 0 OA 日本語母語話者における英語の音韻意識が英語学習に与える影響
- 著者
- 津田 知春 高橋 登
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.95-106, 2014 (Released:2016-03-20)
- 参考文献数
- 42
日本語を母語とする日本人中学生の英語の音韻意識と英語語彙,スペルの知識との関係が実験的に調べられた。スペルの知識は,オンセット・ライムが実在の単語と共通の偽単語を聴覚呈示し,それを書き取らせた。また,音韻意識はStahl & Murray(1994)を参考にして,英単語からの音素の抽出,音素から単語の混成,および日本語の音節構造を持つ単語・偽単語の音素削除課題が用いられた。全体で73名の中学校1年生,2年生が実験に参加した。その結果,語彙課題は学年によって成績に差が見られたが,その他の課題では学年差は見られなかった。また,音韻意識課題の誤りの多くは音素の代わりにモーラを単位として答えるものであった。語彙を基準変数とした階層的重回帰分析の結果,語彙は学年とスペル課題の成績で分散の50%以上が説明されることが確かめられた。また,スペル課題を基準変数とした階層的重回帰分析では,学年は有意な偏回帰係数が得られず,音韻意識の中では混成課題で有意な偏回帰係数が得られた。このことから語彙力を上げるためには,スペル課題で測定される英単語の語形成に関する知識が必要であり,語形成知識は,日本語の基本的な音韻の単位であるモーラではなく,音素を単位とする音韻意識を持つことによって身につくと考えられた。最後に,本研究の今後の英語教育への示唆について議論した。