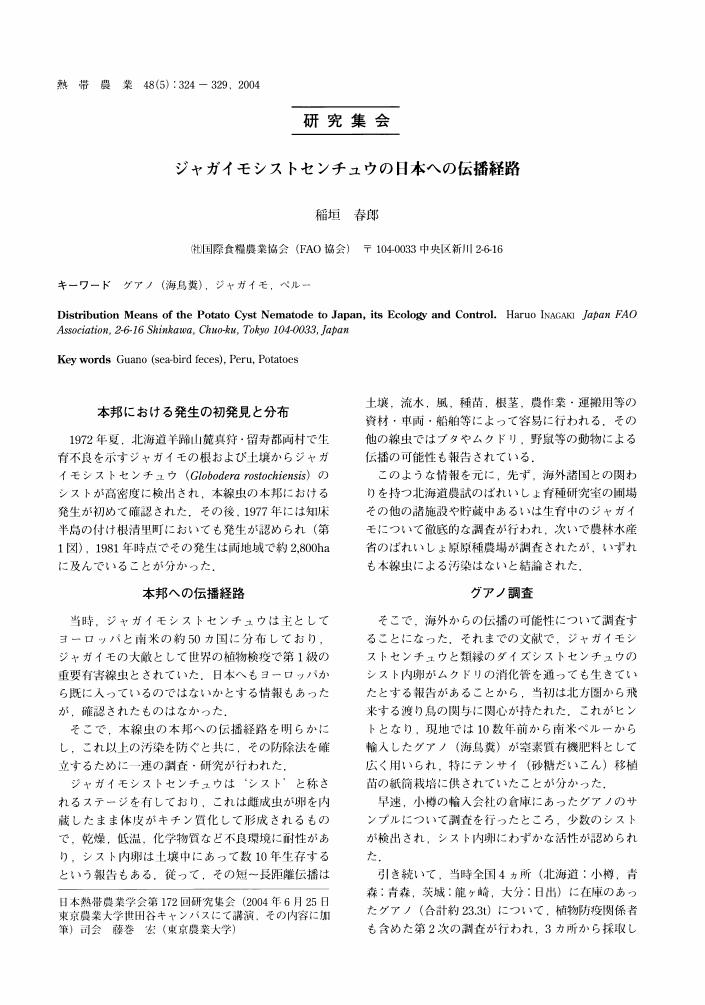1 0 0 0 OA 東北タイにおけるシロアリ活動の土壌に及ぼす影響
- 著者
- 三浦 憲蔵 スバサラム タドサク タウインタング ナクン ヌチャン ナリス 白石 勝恵
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.40-47, 1990-03-01
- 被引用文献数
- 2
東北タイ, コンケン県ポン地区においてシロアリ塚跡の地点で認められた高い生産力の要因を究明するため, 当地区においてキャッサバおよびゴマ畑でシロアリ塚跡の地点とその近傍の未攪乱の地点を対象に土壌の形態的および理化学的な検討を行なった.形態的には, シロアリ塚跡の地点では未攪乱の地点より, 層厚で, 暗色味の強い, 粘土に富むA層が形成されており, シロアリ活動による強度の土壌攪乱が認められた.特に塚跡の中心部では基岩の直上部に及ぶまで土壌攪乱による均質化が起こっていた.この土壌攪乱の程度は塚跡の中心部から外部に向かって次第に弱まった.理化学的には塚跡の地点では, それに隣接する未攪乱の地点と比較して, 粘土, 全炭素, 全窒素, 有効態リン, 交換性塩基(カルシウム, マグネシウム, カリウム)などの含量が高かった.シロアリ活動による土壌の形態的および理化学的な変化はシロアリが塚の主材料として用いたスメクタイト質の粘土を基岩直上部から運び上げ, さらに土壌粒子や団粒の膠着剤として用いた有機物(唾液や糞)を土壌中に取り込んだことに基づくものと考えられた.塚跡の地点における高い生産力はシロアリ活動による上記のような粘土と有機物の取り込みに起因する土壌肥沃度の向上によるものと考えられた.但し, 塚跡の中心部分では高pHによるリン, 鉄などの要素欠之が作物生育を制限したものと考えられた.以上より, シロアリ活動がもたらす土壌攪乱は元の土壌性質を一変させるほどに激しいものであり, 土壌の生成並びに肥沃度の面できわめて大きな意味を持つものと言えた
- 著者
- S. M. Lutfor RAHMAN Eiji NAWATA Tetsuo SAKURATANI
- 出版者
- Japanese Society for Tropical Agriculture
- 雑誌
- Japanese Journal of Tropical Agriculture (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.29-38, 1998-03-01 (Released:2010-03-19)
- 参考文献数
- 10
バングラデシュの高温期にトマトを栽培するためには耐乾性品種の育成が強く望まれている.このための基礎資料を得ることを目的として, 日本, アメリカ, バングラデシュなどのトマト16品種の耐乾性を評価した.評価した特性は, 収量・開花数・着果数・着果率・果実重・根及び地上部乾物重・開花までの日数・断水期間である.育苗中の断水処理により, 全ての品種で大きく収量が低下したが, その程度は品種により異なった.収量を含むいくつかの特性を総合的に評価した結果, 小型の果実をつける4品種の中ではチビッコが, 中型果実品種5品種の中ではTM 0126が, 大型果実品種7品種の中ではSevernianinが最も優れていた.また, 小型・中型の果実をつける品種群は, 大型の果実をつける品種群より耐乾性に優れる傾向があった.種々の要因を考慮すると, これらの比較的耐乾性に優れる品種の中でTM 0126が最も優れていると考えられ, 今後の育種及び研究材料として有望であると思われる.
- 著者
- イスラム カジ レザウル 井之上 準
- 出版者
- Japanese Society for Tropical Agriculture
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.1-5, 1988
バングラデシュ全土はLand levelによって5つに区分されるが, そのうち深水稲が栽培されているのは, Lowland (水深: 1.83m以上) , Medium Lowland (0.91-1.83m) およびMedium Highland (0.30-0.91m) の3地域である.本実験では, これら3地域から蒐集された335品種について節間伸長性を調査した.なお, 節間伸長性の大小は最低伸長節間の位置の高低によって判定した.得られた結果の概要は次ぎの通りである.<BR>1. 伸長最低節間の位置は第6節間から第16節間であったが, 最も多いのは第8節間の品種 (全体の約26%) , 次ぎは第9節間の品種 (約17%) で, 平均は10.1±2.7であった.なお, 東南アジアの浮稲にはほとんど見られないような, 第6節間が伸長する品種が約2%あった.<BR>2. 伸長最低節間の位置は当該品種が栽培されている地域の深水程度と密接な関係にあり, Lowlandの品種群で最も低く (8.1±1.8) , 次ぎはMedium Lowlandの品種群で (9.9±2.6) , Medium Highlandの品種群は最も高かった (11.6±2.3) .<BR>3. 浮稲では伸長最低節間の位置が低い品種ほど, 播種後節間伸長を開始するまでの期間は短い.従って, Land levelに関係なく伸長最低節間の位置が低い品種を栽培すれば, 播種から水位が上昇し始めるまでの日数が短いので, その期間に干害を受けることはほとんど無いはずであるが, 実際には干害は問題となっている.この原因は, 本調査で明らかにされたように, Land leve1が高い地域ほど伸長最低節間の位置が高い品種が栽培されているたあで, これは浮稲においては伸長最低節間の位置が低い品種ほど収量が低いという関係があるたあであろうと思われる.
1 0 0 0 OA 熱帯アジアの水田生態系における害虫管理技術
- 著者
- 寒川 一成 ケビン D.ギャラガー ピータ E.ケンモア
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.361-368, 1994-12-01
- 被引用文献数
- 1
The brown planthopper (BPH), Nilaparvata lugens has long been an outbreak-prone insect pest of rice since the introduction of paddy farming into Japan. BPH is also known as a monsoonic migrants originated in tropical Asia. The BPH was a rice-monophagous minor herbivore in the tropical paddy ecosystems of subsistent phase. However, it raised suddenly as a key-pest of high-yielding rice varieties (HYV) spread into tropical Asia during the "Green Revolution" in 1970s. The BPH outbreaks happened under the pest management with pesticides at International Rice Research Institute (IRRI) is an epitome of the BPH menace which is even now prevailing in tropical Asia. Pesticide use at IRRI farms started with γ-BHC against the rice stem borers in 1962. Since its first occurrence in 1964,BPH infestations magnified rapidly in spite of intensive control with diazinon and later with carbofuran. Eventually, IRRI farms were suffered by devastating outbreak of BPH in 1971-1976,until declining after sequential releases of BPH-resistant HYVs. Resurgence induced by pesticides, development of pesticide resistance, and biotype shifts in the BPH populations were attributed to the outbreak. Restraint of preventive use of pesticides was most effective to stop the BPH problems at IRRI. At present, the BPH density at IRRI farms is at far below the economic threshold level. The pesticide input is often mistakenly associated with increased productivity of the tropical rice, which is largely attributed to HYVs, fertilizers, and irrigation. In general, potential yield losses due to the insect pests are estimated about 10-20% by the on-farm assessments. Except for massive infestations, less than 10% can be caused by insect damages in a normal year. However, the on-farm economic assessment revealed unprofitability of pest control with high input of pesticides. Expected returns are generally low on high levels of pesticide use, and no control is often the economically acceptable option, and biological control in association with varietal resistance has consistently proven more profitable than pesticide use in long-term experiments. This is the reason why pesticides that were employed as a modern high-yielding technology needed official subsidy. In addition, the resurgence of BPH is the most expensive hidden cost of pesticide use. Population ecology of BPH and its natural enemies in the tropical paddy ecosystems demonstrated that pesticides readily led to explosive upsurge of BPH populations by destroying its natural enemy complex. High fecundity, short generation cycle, active dispersal, and tolerance to crowding are the biological properties of the BPH for its easy resurgence under the disruptive impact of pesticides to natural enemies. The BPH was initially uncurbed from natural enemies by pesticides used for controlling the other targeted insect pests such as stem borers. Escalated pesticide use against the upsurge of BPH infestations further promoted its resurgence. Eventually, such vicious cycle give rise to uncontrollable outbreaks of BPH, and disaster the rice production systems. Indonesia is a prime example of the country where the BPH crisis led to the establishment of ecologically sound pest management program in rice. Pesticides were initially adopted as an essential component of "Green Revolution" package for high-yielding technology, and 85% of their cost was subsidised. As increase of pesticide use, resurgence and outbreaks of the BPH prevailed throughout the rice granaries in the country in 1975-1979. Stagnation of rice production made the country the world-biggest rice importer in this period. Forcible planting of the BPH-resistant variety IR 36 suppressed the BPH outbreak, and led to the rice self-sufficiency in 1985. However, the BPH menace revived when IR 36 was replaced with new varieties having improved eating-qualities and high profitability. The BPH biotype adapted to the new varieties became epidemic over major rice areas in 1985-1986,in spite of as much as 10 times more pesticide supply. Collapse of the reliance to pesticides led to the switching of crop protection policy from pesticide-dependent to ecosystem-orientated IPM by the Presidential Instruction in 1986. Consequently, the 57 pesticides were immediately banned from use in paddy, and government subsidy for pesticides was completely abolished in 1989. At the same time, FAO Rice-IPM Program has launched. The principles of FAO Rice-IMP in the developing countries in tropical Asia is "Integration of biological control into crop production systems", where "Maximum conservation of natural enemies, minimum reliance on pesticides" is emphasized in implementation of the IPM. The concept arose largely in response to the crisis-driven outbreaks of BPH induced by prophylactic use of pesticides that had motivated by government policy and commercial promotion, as well as unprofitability of overdependence to pesticide technology for controlling the endemic insect pests in the tropical rice farming. Recognizing the central role of natural enemies of rice pests through on-farm paddy-ecosystem analysis by farmers themselves is the most strongest motive for farmers to change their pest control practices. The ecosystem analysis ensure that IPM is not distorted into a purely negative message "Don't spray pesticide this week". Instead, IPM is reinforced by positive reassurance "This field is in good condition this week". Pesticide use has effectively been reduced without spoiling productivity of rice by farmers trained IPM. Official support of FAO Rice-IPM have been promulgated in the Philippines, Indonesia, Malaysia, India, and Sri Lanka.
1 0 0 0 OA 黒ボク土にけおる土壌締固めがコムギ生育に与える影響
- 著者
- Muhammad Hasinur RAHMAN 河合 成直 Shah ALAM Sirajul HOQUE 田中 章浩 伊藤 實
- 出版者
- Japanese Society for Tropical Agriculture
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.129-135, 1999-09-01 (Released:2010-03-19)
- 参考文献数
- 27
農耕車輌などの踏圧による締固めが黒ボク土の特性とコムギ (Triticum aestivum L.cv.Nanbu-Komugi) の生長に及ぼす影響について, 温室環境下で検討した.測定は, 土壌の仮比重, 水分保持力, 全孔隙率, および, 草丈, 分げつ数, 茎および根の乾物重量, 根の体積・最大重・密度・バイオマス, 蒸発散量, 要水量および栄養消費量について行った.本研究から以下の結果が得られた.土壌締固めにより, 黒ボク土の仮比重は統計的に有意に増加し, 水分保持力と全空隙率は減少した.コムギの茎と根の生育量および蒸発散量は, 土壌の締固めにより, 著しく低下することが認められた.その反面, 要水量は締固め土壌で増加していた.また, 根: 茎葉の割合は高締固め土壌において高い数値を示した.しかし, 根の密度およびバイオマスは, 逆に高締固め土壌において低い値となった.さらに, 養分吸収量は土壌の締固めにより, 有意に減少した.
- 著者
- 渡辺 巌
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.146-149, 1993-06-01
- 被引用文献数
- 3
- 著者
- Ezenwa Ike Jacob Ayuba Francis
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.4, pp.300-305, 1999-12-01
Enterolobium-ギニアグラス草地の造成時における同伴作物栽培の実用性を調査するため, ナイジェリア南西部のイバダン(北緯7度20分, 東経3度50分, 標高200m)において試験を行った.作付け期間の初期(1997年5月)にEnterolobiumを植栽した後, 4m間隔の並木の間に, 次のような作付け方法で第1/第2シーズンに同伴作物を栽培した.処理1 : 作付無/ギニアグラス及びササゲ(カウピー, Vigna unguiculata(L.)Walp.), 処理2 : トウモロコシ/ギニアグラス及びササゲ, 処理3 : トウモロコシ及びギニアグラス/ギニアグラス, 処理4 : 作付無/作付無.総飼料用収量(トウモロコシ稈及びササゲ残渣, 子実は含まない)は, 処理1及び2でそれぞれ5.35及び5.68tDM/haで最も高く, 処理2では, さらに総穀物収量(トウモロコシ及びササゲ)が1.60t/haで最大であった.処理2及び3では, 同伴作物は, 第2シーズンにはEnterolobiumの成長を有意に抑制した.植栽後36週のEnterolobiumの樹高は, 処理1が最も高く, 次いで4,2,3の順で, それぞれ98.6,94.6,62.6,36.0cmであった.Enterolobium-ギニアグラス草地造成時には, 第1シーズンにはEnterolobiumの単作で, 第2シーズンにギニアグラスとササゲを導入する(処理1)か, 第1シーズンにEnterolobiumとトウモロコシの混作で, 第2シーズンにギニアグラスとササゲを導入する(処理2)作付方法が有利なことが明らかとなった.第1の作付方法ではEnterolobiumの成長が最大に, 一方, 第2の作付方法では総穀物収量が最大となった.
1 0 0 0 OA サトウキビ種子の発芽に対する温度の影響
- 著者
- 板倉 登 工藤 政明 仲宗根 盛徳
- 出版者
- Japanese Society for Tropical Agriculture
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.47-51, 1981-06-01 (Released:2010-03-19)
- 参考文献数
- 3
サトウキビ種子の発芽適温を知るために, 定温器内発芽試験ならびに温室内発芽試験を実施した.試験の結果, サトウキビ種子の発芽適温は35℃であり, 同最低温度は25℃, 最高温度は40℃以上と推定された.また, 明発芽性の傾向が認められた.温室内発芽試験では, 実生育苗における温室管理の実用的な指針が明瞭となり, 最高40℃を限度としてできるだけ高温条件とするように管理することで, 揃いの良い健全実生苗の得られることが明らかとなった.また, 播種時の覆土は有害であった.
- 著者
- 高橋 久光 セナン キャロル ハフフェイカ レイ C
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.22-27, 1993-03-01
培養液中の異なるZn濃度および遮光がトマトの生育, 窒素含有量および硝酸還元酵素の活性に及ぼす影響について検討した.Znの欠乏は, 草丈の伸長を抑制した.葉部の全窒素含有量はZn欠乏区, 微量区および標準区でほとんど差異が認められず, その傾向は茎部, 根部においても同様であった.しかし, 葉部の全窒素含有量に占める水溶性窒素含有量は, Zn欠乏区で高かった.葉部の硝酸還元酵素の活性は, 標準区で高く, Zn微量および欠乏区で低かった.その傾向は茎部および根部でも同様であった.なお, 根部の硝酸還元酵素の活性は, 葉部や茎部と比較して, 低かった.Zn欠乏作物の遮光実験下での植物体各部位の生体重および乾物重は, 各生育期間とも無遮光区で最も大きい値を示した.Zn欠乏作物の遮光実験下での葉部の硝酸還元酵素の活性は, 遮光によって低下し, 無遮光区で最も高く, 70%遮光区で最も低かった.根部の硝酸還元酵素の活性は, 4月12日と4月19日には無遮光区で高かったが, 他の部位と比較して, 全処理区ともその活性は低かった.
1 0 0 0 OA 輸入パパイアの損傷について
- 著者
- 矢口 行雄 中村 重正
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.141-144, 1992-06-01
1986年9月から1987年5月の9カ月間にわたりハワイ産パパイアの日本到着時における損傷について調査を行った.損傷の発生は, 生理的損傷0.9%, 機械的損傷1.8%, 腐敗0.9%で, これらの季節的変動をみると12月が最も高く, 4月, 5月が最も低い傾向を示した.
1 0 0 0 OA パラグアイ・イグアス地域の不耕起畑におけるダイズ根系分布の実態
- 著者
- 関 節朗 干場 健 Jorge BORDON
- 出版者
- Japanese Society for Tropical Agriculture
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.33-37, 2001-03-01 (Released:2010-03-19)
- 参考文献数
- 11
パラグアイ南東部穀倉地帯における不耕起栽培ダイズ (Glycine max (L.) Merr.) の収量は近年減少傾向にある.この原因が不耕起栽培を継続した圃場での根の発育不良にあるか, どうかを明らかにするため, 年数, 耕起法, 前作物, 土壌の異なる11圃場についてダイズの根の形態, 分布を調査した.その結果, 不耕起畑では地表下5~10cmのところで, 主根が彎曲したり, 主根の伸長が止まり, 代わりに側根が水平に伸長したり, 主根の伸長・肥大が貧弱で側根がタコ足状に発達したりしているダイズが多数観察され, このようなダイズでは根系が地表近くに分布する傾向が認められた.一方, 耕起畑および開墾初年目の畑では主根伸長異常のダイズは少なかった.土壌調査結果によると主根の土壌下層への伸長不良は, 播種床下の土壌硬度が高いほど, また土壌表層と下層のリン酸濃度の差が大きいほど多くなる傾向にあった.このことから長年不耕起栽培を継続した畑では, 土壌に圧密層が形成され, また施肥リン酸が表層に集積するなどして, ダイズ根の土壌下層への伸長を妨げて根系分布の表層化を招き, 軽度の気象変動 (干ばつ) にも生育が左右され, 近年の収量低下の原因になっているのではないかと考えられた.
1 0 0 0 OA マンゴー炭疽病の生物の防除法に関する研究 (I) マンゴー葉面の微生物相と拮抗菌の探索
- 著者
- 諸見里 善一 澤岻 哲也 田場 聡 安谷屋 信一 本村 恵二
- 出版者
- Japanese Society for Tropical Agriculture
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.34-41, 2003-03-01 (Released:2010-03-19)
- 参考文献数
- 32
各葉齢のマンゴー葉から希釈平板法により微生物を分離し, 生育過程における葉面微生物相の変遷を調べた.また, マンゴーハウス内気中の微生物相も調査し, 葉圏と気中の微生物相の比較・検討を行った.その結果, 気中および各齢葉面の細菌相では, 色素生成細菌が多く, 特に黄色陰性球菌 (Y, N, C) と白色陰性球菌 (W, N, C) の優占が認められた.グラム陰性菌と陽性菌の割合に着目すると, 気中では両菌の割合がほぼ同じであったが, 生葉上では全体的にグラム陰性菌がまた落葉上では陽性菌が優占した.一方糸状菌相では, 気中から多種の糸状菌が分離され, 複雑な菌相を示したのに対し葉面では菌相が単純化した.気中と各齢葉面のすべてで認められた菌はCladospoyium属とPenicillium属の菌のみであった.これらの葉面から分離した細菌および糸状菌であるマンゴー炭疽病菌をPDA培地上で対峙させ拮抗性を検討した.その結果, 細菌には強い拮抗性を示すものは少なかった.それに対し, 糸状菌ではPenicillium属菌は高い拮抗性を示すものが多く, とくに, P.citrinumとP.expansumの2種は最も強い拮抗性を有した.これらの菌の培養ろ液も炭疽病菌に対した高い抗菌性を有することから, 拮抗機作は抗菌物質によるものと考えられる.
1 0 0 0 ナイジェリア東部州の水稲作に対する勧告
- 著者
- 山本 信一
- 出版者
- Japanese Society for Tropical Agriculture
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.4, pp.193-201, 1965
筆者は, 1962年7月から1カ年, 単身軽装備で西アフリカのナイジェリア連邦東部州にあつて, 同国の稲作を指導した.その結果, 土壌改良と用水管理が最も重要であるとし, 上記英文の稲作改善勧告書を作成提出した。
1 0 0 0 OA ジャガイモシストセンチュウの日本への伝播経路
- 著者
- 稲垣 春郎
- 出版者
- Japanese Society for Tropical Agriculture
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.5, pp.324-329, 2004-12-01 (Released:2010-03-19)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- 志和地 弘信 遠城 道雄 林 満
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.107-114, 2000-06-01
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 7 3
ダイジョ(D.alata)およびナガイモ(D.opposita)のそれぞれの数系統とジネンジョ(D.japonica)について, 塊茎の肥大生長に対する種および系統の光周反応を比較検討した.夏至前後の6月1日と7月1日に, 植え付け後60日目の株に対して, 10時間日長の短日処理を20回行った.6月の処理では, 塊茎の肥大生長は全ての種および系統において促進された.一方, 7月の処理において, 塊茎の肥大生長は, ダイジョの早生および晩生系統において促進されたが, ダイジョの極早生系統, ツクネイモ群およびジネンジョにおいては促進されず, ナガイモ群およびイチョウイモ群では逆に抑制された.この結果から, 塊茎の肥大生長は第一義的には短日によって促進されるが, 短日に対する反応の程度は, 塊茎の生育段階によって異なり, 塊茎の生長の緩慢期における処理は肥大生長を旺盛期へと転換させて促進的に作用するが, 生長の転換期の処理では促進効果が無く, 転換期以降の処理は逆に抑制的に作用することが明らかになった.ダイジョの極早生系統の塊茎は14時間日長の条件下では温度条件を変えても, 肥大生長の転換は誘起されなかったが, 12時間日長の条件下では転換された.温度は肥大生長の転換には影響を及ぼさなかった.このことから, 短日はダイジョの塊茎の肥大生長を旺盛な生長へ転換させる主要因であることが確認された.しかし, ナガイモおよびジネンジョの塊茎は, 14時間日長の条件下では肥大生長の転換が認められなかったが, 緩慢な生長を続け, ダイジョの反応とは異なることが明らかになった.熱帯原産のダイジョにおいて, 感光性が弱く, 極早生の形質を有する系統は温帯での栽培が可能であると推察された.
1 0 0 0 OA チュニジアオオムギにおける自然相互転座系統の検出
- 著者
- 倉内 伸幸
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.4, pp.264-267, 1997-12-01
- 被引用文献数
- 1
チュニジアから収集したオオムギ300系統のうち, 10系統を栽培種と交配した.そのうち2系統は, 雑種第1代の種子稔性が半不稔性であった.同様に, 花粉稔性も半不稔性であり, 花粉母細胞減数分裂第一分裂中期で1つの4価染色体と5つの2価染色体が観察された.雑種第2代では可稔性と半不稔性が1 : lに分離した.この結果は, これら2系統が1個の相互転座をもつことを示している.転座染色体を同定するため, 既知の転座テスター系統と交配を行った.雑種第1代の花粉母細胞減数分裂第一分裂中期の染色体対合を観察した.第5染色体と第7染色体をもつ転座テスター系統とのF_1個体でのみ6価染色体が出現したことから, 転座染色体は第5染色体と第7染色体で起こっていることが明らかとなった.また, これら2系統のF_1個体の染色体対合は7つの2価染色体が観察されたことから, 同じ染色体上で相互転座が起こったと考えられる.
- 著者
- 安渓 貴子
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.5, pp.333-337, 2005-12-01
1 0 0 0 OA ヤムイモ生産の現状と将来性(課題: 熱帯・亜熱帯におけるイモ資源の現状と課題)
- 著者
- 志和地 弘信 豊原 秀和
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.5, pp.323-328, 2005-12-01
- 著者
- 中野 寛 小林 真 寺内 方克
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.78-84, 1998-06-01
- 被引用文献数
- 5
インゲンマメは一般に耐暑性が低く, 高温下では落花・落莢現象が激しくなり結莢率が著しく低下する.そこで, 耐暑性品種ハイブシと石垣2号, および非耐暑性品種のケンタッキーワンダーの若莢用インゲンマメ3品種を用い, 高温に感受性の高い時期を解明することにした.植物体を日平均気温約33℃で1日間もしくは5日間処理することにより, 花芽には高温ストレスに弱い時期が4期あることが明らかになった.一方, すでに開花している花や未熟莢は, 同じ温度で連続処理しても全く落花・落莢しなかった.4期のうちの1期は開花前々日から開花前日の時期であった.他の2期は開花9日前頃と12日前頃であった.耐暑性品種のハイブシと石垣2号では, その2期の間, すなわち11日頃に高温ストレスにやや強い時期が認められた.しかし, 耐暑性の低いケンタッキーワンダーでは, その時期も高温に感受性が高かった.残る1期は開花前15日から25日前の時期であった.この時期の花芽は高夜温に弱く, 5日間の処理で日平均気温が約33℃でも夜温が低い場合(昼温/夜温 : 36.8℃/28.1℃)には高温障害を受けなかったが, 夜温が高い場合(昼温/夜温 : 34.2℃/32.3℃)には花が小型で奇形の不完全花となり結莢率も低下した.開花前日の花芽に一日間だけ日平均気温約33℃(昼温/夜温 : 36.9℃/28.2℃もしくは34.2℃/33.0℃)の処理をすると, 翌日開いた花の結莢率は著しく低下した.そこで, 高温感受期をより詳しく決定するために, 午後4時から午前0時迄もしくは午前0時から午前8時迄の8時間だけ, 植物体に高温処理(32.5℃)を行った.これは葯壁の裂開, 花柱の伸長, 受粉, 花粉の発芽, 花粉管の伸長, 受精が行われる期間である.しかし, いずれの8時間高温処理でも結莢率は全く低下しなかった.このことから32.5℃の高温では生殖過程に直接的に作用し障害を与えるものではなく, 高温による障害が徐々に蓄積され, 8時間以上の長い時間の高温処理があってはじめて上述した生殖生長のいずれかの過程が不全となると考えられた.
- 著者
- 中野 寛 小林 真 寺内 方克
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.123-129, 2000-06-01
- 被引用文献数
- 4
常温で栽培しているインゲンマメ(日平均気温、約23.6℃)の個体を高温条件下に移した時, 着莢率は7日目頃から低下し始めた.約29.6℃では15日目頃には0〜15%まで低下し, その後も着莢率は回復しなかった.しかし, 約28℃の条件下では, 15日頃から着莢率は高まり始め, 30日頃には常温で栽培されている個体と同様の着莢率(80%以上)まで回復した.この着莢率の回復は, 栽培する時期が変わることによる日長や日射量の季節変化のような要因で生じたものでなく, 約28℃の高温にインゲンマメが馴化し, 高温下で莢を着生する能力を獲得したものであることが確認された.この約28℃下の高温馴化は, 耐暑性品種のハイブシと石垣2号では顕著であったが, 感受性のケンタッキーワンダーでは生じなかった.また, 耐暑性品種も約29.6℃では高温馴化は認められなかった.昼温と夜温の組み合わせに関しては, 昼温/夜温が32.3℃/23.9℃でも, 30.4℃/25.7℃でも着莢率の低下と高温馴化による回復の経時的変化は同様であった.高温馴化した個体を約一ヶ月の間, 常温である約23.6℃に戻した後, 再び約28℃の高温条件に移した場合には, 高温馴化機能はすでに失われていた.これらの個体では, 初めて高温処理を受けた個体と同様に, 着莢率は徐々に低下しまた回復した.