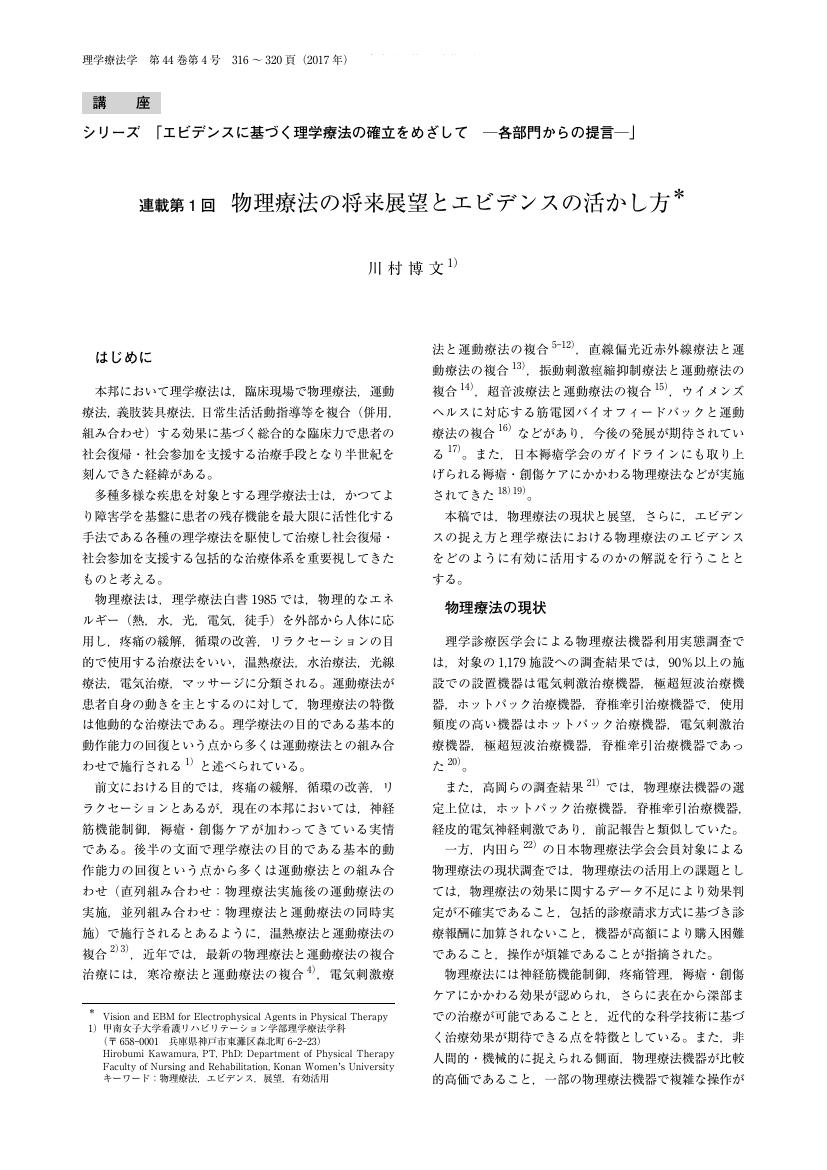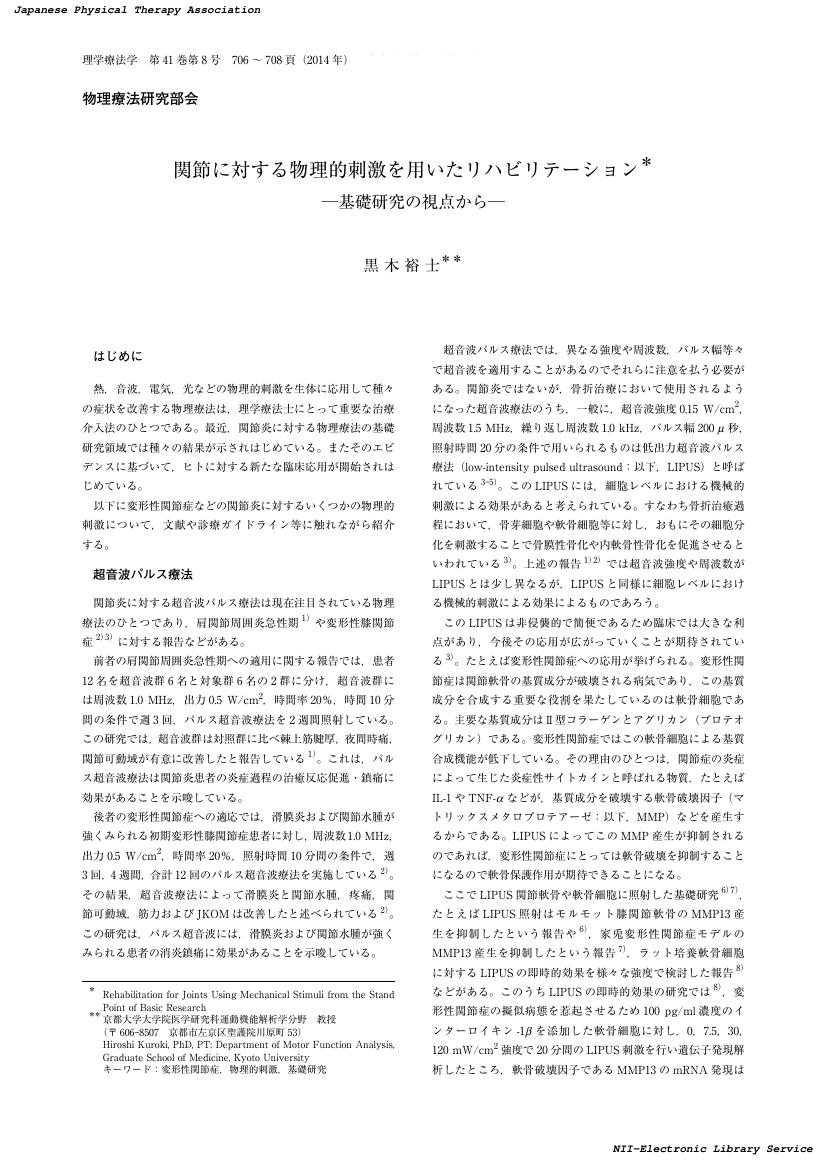1 0 0 0 OA 理学療法診断に基づく臨床推論の可能性
- 著者
- 天野 徹哉 内田 茂博 伊藤 秀幸 田中 繁治 森川 真也 玉利 光太郎
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.8, pp.579-583, 2014-12-20 (Released:2017-06-10)
1 0 0 0 OA 腰痛症の評価と治療
- 著者
- 伊藤 俊一
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.8, pp.511-514, 1998-11-30 (Released:2018-09-25)
- 参考文献数
- 26
1 0 0 0 OA 物理療法の将来展望とエビデンスの活かし方
- 著者
- 川村 博文
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.316-320, 2017 (Released:2017-08-20)
- 参考文献数
- 37
1 0 0 0 OA 関節に対する物理的刺激を用いたリハビリテーション -基礎研究の視点から-
- 著者
- 黒木 裕士
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.8, pp.706-708, 2014-12-20 (Released:2017-06-10)
1 0 0 0 OA 外来理学療法に対する脳卒中後遺症者の期待と理学療法士の意識との相違
- 著者
- 吉野 貴子 飯島 節
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.5, pp.296-303, 2003-08-20 (Released:2018-09-25)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 3
本研究では,脳卒中外来理学療法のあり方に示唆を得ることを目的として,1)外来理学療法の長期化の現状,2)外来理学療法に対する脳卒中後遺症者の期待と理学療法士の役割意識,3)外来理学療法と通所リハサービスを併用している者と通所リハサービスのみの利用者との比較の3点について検討した。調査は在宅脳卒中後遺症者284名と理学療法士200名を対象に郵送アンケート法にて実施した。その結果,外来理学療法が長期化する傾向があること,脳卒中後遺症者の多くが外来理学療法に対して麻痺や身の回りの動作が回復することを期待していること,一方,理学療法士は,機能回復よりも身体機能やADLの維持や確認を主な役割として意識していることが明らかとなった。以上から,患者と理学療法士が外来理学療法における目的を共有することがまず重要である。そうすることによって,地域リハビリテーションにおける外来理学療法の役割が明確化し,外来理学療法が患者の生活の再構築に貢献できることが示唆された。
- 著者
- 藤原 求美 山口 実果 手塚 康貴 太田 忠信
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.6, pp.330-333, 2006-10-20 (Released:2018-08-25)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2
本研究の目的は,脳卒中患者・骨関節疾患患者・健常高齢者におけるFour Square Step Test (以下,FSST)の検者内信頼性と妥当性について検討することである。対象は脳卒中患者30名,骨関節疾患患者20名,健常高齢者20名とし,FSST,Berg Balance Scale(以下,BBS),Timed Up and Go test(以下,TUG)を測定した。脳卒中患者30名のうちFSSTを完全に実施できた患者は24名であった。FSSTは2回の測定を2日間行い,その測定値より級内相関係数を求めた結果,全対象者で高い再現性(ICC=0.807〜0.985)を示した。またFSSTとBBS,BBSとTUGの間には危険率1%未満の有意な相関関係(ρ=0.677〜0.860)が認められ,FSSTとTUGの間には危険率5%未満の有意な相関関係(r=0.559〜0.948)が認められた。結果より,FSSTは上記の対象者において有用な評価方法であると示唆された。
1 0 0 0 OA 脂質異常症に対する理学療法
- 著者
- 平木 幸治
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.5, pp.386-391, 2013-08-20 (Released:2017-07-13)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 大迫 絢佳 山内 真哉 梅田 幸嗣 笹沼 直樹 児玉 典彦 内山 侑紀 道免 和久
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- pp.11849, (Released:2021-01-13)
- 参考文献数
- 15
【目的】クリーゼを呈した重症筋無力症患者に対し,日々の病態を評価する指標を用いて理学療法を実施し,自宅退院の転帰に至った症例を経験したので報告する。【症例】75 歳女性。胸腺腫摘出術後,誤嚥性肺炎を機にクリーゼを呈した。薬剤療法を行い第27 病日より離床を開始した。【方法】日々の病態評価にQMG スコアの頸部屈曲保持時間と下肢挙上保持時間,修正Borg Scale を用いて,離床や運動療法を実施した。【結果】FIM は,57 点から112 点まで回復し自宅退院となった。【結論】QMG スコアと修正Borg scale を指標として病態評価を行いながら運動療法を実施したことで,overwork weakness を生じることなく自宅退院に導くことができた。
1 0 0 0 OA 物理療法のEBM:臨床的推論・医療判断学
- 著者
- GOH Ah-Cheng
- 出版者
- Japanese Society of Physical Therapy
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.253-256, 2012-06-20 (Released:2018-08-25)
Van der Vleutenらによると,臨床的推論技術は,治療技術と同様に重要なものだと述べている。臨床的推論プロセスは,起きている問題の原因を特定し,正しい治療目的を設定し,さらに最適な治療技術を施すために重要なものであり,患者に治療を施す前に行われるものである。たとえ優れた技術をもった治療者であっても,適切な臨床的推論技術なしには効果的な治療を患者に行うことはできない。適切な治療技術に関係する事項について述べることは,今回の目的ではない。しかし,よい臨床的推論技術が,治療結果を成功に導く前提条件であるということを認識することは重要である。理学療法士は,専門分野や臨床経験年数の違い,バイオメディカルサイエンスについての知識量により,様々な臨床的推論プロセスが用いられている。これらの要素については,物理療法を例に用いながら述べていく。物理療法の臨床的推論プロセスは,図1に示した。ステップ1では,標的組織にどのような生物物理学的変化をもたらしたいかを決定する。たとえば急性損傷の場合,炎症過程において,熱感,発赤,疼痛,腫脹の4つの兆候がみられる。そのため,急性炎症の治療では,組織を冷やすことが必要となる。ステップ1で他に必要となるのは,生物物理学的変化をもたらすために,最適な物理療法介入がなんであるかを判断することである。今回の例では,寒冷療法(アイスパックやアイスマッサージ)が,損傷組織の温度を下げるためにもっともよく用いられる方法である。ステップ2では,標的組織に対し期待する生理学的効果を決定する。たとえば,組織温度が15℃まで減少した時には,血管収縮が起こり,血流が減少する。一方,組織温度が10℃まで減少するか,寒冷療法を15分以上行うと,血管拡張が起こり,結果として血流が増加する。このようなことから,求める生理学的効果が損傷組織周囲の血流を減少することであれば,寒冷療法は15分以下とし,組織温度の減少は15℃程度とする。ステップ1と2で行われた決定により,ステップ3の臨床効果へと続いて行く。今回の例では,臨床効果は腫脹の減少により得ることができる。今まで述べた臨床的推論と医療判断プロセスは,物理療法を用いたすべての治療法に用いることができる。効果的な治療効果を得るために,理学療法士は臨床場面での臨床的推論と医療判断学の重要性を理解することが必要である。
1 0 0 0 OA 地域在住高齢者における骨量および筋量の低下と身体活動との関連性
- 著者
- 谷口 善昭 牧迫 飛雄馬 中井 雄貴 富岡 一俊 窪薗 琢郎 竹中 俊宏 大石 充
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- pp.12150, (Released:2022-02-22)
- 参考文献数
- 47
【目的】地域在住高齢者における骨量・筋量低下と身体活動との関連性を明らかにすることを目的とした。【方法】地域コホート研究(垂水研究2018)に参加した地域在住高齢者173 名を分析対象とした。骨量低下は%YAM が70% 以下とし,筋量低下は四肢骨格筋指数がサルコペニアの基準より低いものとした。身体活動量は3 軸加速度計を用いて,座位行動時間延長,中高強度身体活動時間低下,歩数低下の有無に分類した。骨量・筋量をもとに正常群,骨量低下群,筋量低下群,骨量・筋量低下群の4 群に分類し,基本情報および身体活動を比較した。【結果】骨量・筋量低下群は正常群と比べて中高強度身体活動時間が有意に減少していた(オッズ比3.29,p < 0.05,共変量:年齢(5 歳階級),性別,歩行速度低下,うつ傾向)。【結論】骨量・筋量低下を併存している高齢者は,中高強度身体活動時間が減少していることが示唆された。
1 0 0 0 OA 歩行中の機能的電気刺激療法により痙縮減弱を認めた多発性硬化症の一例
- 著者
- 西角 暢修 若杉 樹史 水野 貴文 山内 真哉 笹沼 直樹 内山 侑紀 道免 和久
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- pp.12117, (Released:2022-01-25)
- 参考文献数
- 15
【目的】二次進行型MS 患者の下腿三頭筋の痙縮に対して,FES を前脛骨筋に実施し,痙縮の減弱に伴い歩行能力向上を認めたため報告する。【症例】40 歳台男性。再発と寛解を繰り返しているMS 患者で,今回4 度目の再発にて歩行困難となり入院。ステロイドパルス療法が施行されたが,右下腿三頭筋の痙縮や前脛骨筋の筋力低下が残存し,歩行が不安定であった。【方法】FES は,歩行練習中に右前脛骨筋に対して5 日間実施した。評価は,介入前後でMAS や足クローヌス,6 分間歩行距離などを測定した。【結果】FES 介入前後でMASは2→1+,クローヌススコアは4 →1,6 分間歩行距離は80 m →150 m であった。【結論】前脛骨筋へのFES は,即時的に下腿三頭筋の痙縮を減弱させ,立脚期の反張膝や遊脚期での躓きが減少することで,歩行能力を向上させる可能性があることが示唆された。
- 著者
- 渡邊 慎吾 大瀧 亮二 小野 修 齋藤 佑規 竹村 直
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.43-48, 2022 (Released:2022-02-20)
- 参考文献数
- 18
【目的】亜急性期脳卒中者に対するBody Weight Supported Overground Training(以下,BWSOT)の効果を検討した。【方法】脳梗塞により右片麻痺を呈した73 歳男性を対象とした。ABA シングルケースデザインを用い,A 期は通常の理学療法を実施し,B 期はA 期の介入に加えてBWSOT を実施した。評価項目は歩行速度,6 分間歩行距離,麻痺側Trailing Limb Angle(以下,TLA)および麻痺側足関節底屈モーメントとした。【結果】歩行速度,6 分間歩行距離はA 期と比べ,B 期でより大きな改善を認めた。さらに歩行速度,6 分間歩行距離の改善に伴い,TLA,足関節底屈モーメントの改善がみられた。【結論】BWSOT は亜急性期脳卒中者の歩行能力,運動学・動力学的指標を改善し得る理学療法戦略であると考えられた。
1 0 0 0 中国台北理学療法士協会の紹介
- 著者
- Tang Tommy
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.84-85, 1994
- 著者
- 大平 高正 池内 秀隆 伊藤 恵 木藤 伸宏
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.7, pp.420-425, 2004-12-20 (Released:2018-09-25)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2
本研究の目的は,高齢者を対象に歩行開始時の足圧中心点(以下,COP)の後方移動(以下,逆応答現象)を調べ,1)足指筋力,足関節背屈筋力,歩行開始前後の静的バランス能力との関連性を調べること,2)各パラメータの若年者との相違を調べ,高齢者における逆応答現象の移動距離が減少する要因を調べることである。中枢神経疾患の既往の無い,在宅生活を送っている自立歩行可能な高齢者15名を対象とした。計測パラメータは,①逆応答現象の前後方向最大距離 : As,②逆応答現象の左右方向最大距離 : Al,③歩行前静止立位バランス : Bd,④歩行後静止立位バランス : Ad,⑤逆応答出現までの潜時 : Cd,⑥足指最大圧縮力体重比 : Fg,⑦足指圧縮力の増加の傾き : Gs,⑧足指圧縮力発生までの潜時 : Gd,⑨足指圧縮力発生から最大圧縮力までの時間 : Tp,⑩足関節背屈トルク体重比 : Dtとした。AsとAlに強い正の相関が認められた。AlとBdに負の相関が認められた。CdとGdに正の相関が認められた。若年者群との比較では,高齢者群はGsが有意に低かった。転倒群に対し運動療法を施行するとAl,Gsの増大,Bd,Gdの短縮が認められた。今回の調査では,高齢者の逆応答現象に関与する因子の明確化には至らなかった。
1 0 0 0 OA 腰部疾患手術後の遺残下肢症状に対する電気療法の継続効果
- 著者
- 宮城島 一史 対馬 栄輝 石田 和宏 佐藤 栄修 百町 貴彦 柳橋 寧 安倍 雄一郎
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.5, pp.291-296, 2018 (Released:2018-10-20)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
【目的】本研究の目的は,腰部疾患手術後の遺残下肢症状に対する入院中の電気療法の継続効果を検討することである。【方法】対象は,腰椎後方手術後に下肢症状が遺残した50 例とし,症状部位に10 分間電気療法を実施した。入院中に電気療法を継続した例(電気継続群),電気療法の継続を中止した例(電気中止群)の2 群に分類し,下肢症状のVAS を調査した。【結果】電気継続群は39 例,電気中止群は11 例であった。電気継続群のVAS(術前→初回電気療法前→退院時)は70 →40 →14 mm であり,各時期で有意差を認めた。電気中止群のVAS は63 →45 →41 mm であり,初回電気療法前から退院時で有意差を認めなかった。多重ロジスティック回帰分析の結果,退院時のVAS(オッズ比:1.04)が選択された。【結論】腰部疾患手術後の遺残下肢症状に対し,入院中に電気療法を継続した群は,退院時の症状の回復が良好であった。
1 0 0 0 OA 内側型変形性膝関節症における歩行時大腿・下腿回旋運動の解析
- 著者
- 菅川 祥枝 木藤 伸宏 島澤 真一 弓削 千文 奥村 晃司 吉用 聖加 岡田 恵也
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.7, pp.412-419, 2004-12-20 (Released:2018-09-25)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 4
本研究では,角速度センサを用いて歩行時の骨盤,大腿,下腿の回旋運動の計測を行い,変形性膝関節症患者で得られた角速度波形より健常例とは異なる特徴を同定し,その特徴を明らかにすることを目的とする。対象は健常若年群5名,健常高齢者群8名,変形性膝関節症群21名である。結果は変形性膝関節症群では健常群と異なる角速度波形が確認できた。骨盤の回旋運動には大きな相違は見られなかった。大腿は,荷重反応期での内旋,立脚中期の外旋運動の減少が見られた。下腿では,健常者は歩行時,立脚初期には下肢回旋運動は複雑な運動が行われており,変形性膝関節症群では下腿回旋運動の減少がみられた。また周波数解析では変形性膝関節症群は健常者群と比較し,第1ピーク周波数が低周波域に移動しており,さらに,スペクトルの広がりの不均一性が認められ,下腿回旋運動の調和性が失われていると推測した。本研究で用いた角速度センサによる下肢肢節回旋測定は,臨床においての理学療法効果判定に有用である可能性が示された。
1 0 0 0 OA 加齢に伴う消化・吸収・排泄機能の変化
- 著者
- 万行 里佳
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.6, pp.636-642, 2021 (Released:2021-12-20)
- 参考文献数
- 43
1 0 0 0 OA 理学療法診断学構築の方法と意義
- 著者
- 玉利 光太郎 内田 茂博 天野 徹哉 伊藤 秀幸 田中 繁治 森川 真也
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.8, pp.609-614, 2013-12-20 (Released:2017-07-04)
1 0 0 0 OA 幼児期における運動の協調性と感覚異常の関連性の検討
- 著者
- 松田 雅弘 新田 收 古谷 槇子 楠本 泰士 小山 貴之
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.248-255, 2018 (Released:2018-08-20)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
【目的】発達障害児はコミュニケーションと学習の障害以外にも,運動協調性や筋緊張の低下が指摘され,幼少期の感覚入力問題は運動協調性の低下の原因のひとつだと考えられる。本研究は幼児の運動の協調性と感覚との関連性の一端を明らかにすることを目的とした。【方法】対象は定型発達の幼児39 名(平均年齢5.0 歳)とした。対象の保護者に対して,過去から現在の感覚と運動に関するアンケートを実施した。運動の協調性はボールの投球,捕球,蹴る動作の25 項目,80 点満点の評価を行った。5,6 歳児へのアンケート結果で,特に感覚の問題が多かった項目で「はい」と「いいえ」と回答した群に分けて比較した。【結果】「砂場で遊ぶことを嫌がることがあった。手足に砂がつくことを嫌がった」の項目で,「はい」と回答した群で有意に運動の協調性の総合点が低かった。【結論】過去から現在で表在感覚の一部に問題を示す児童は,児童期に運動の協調性が低い傾向がみられた。