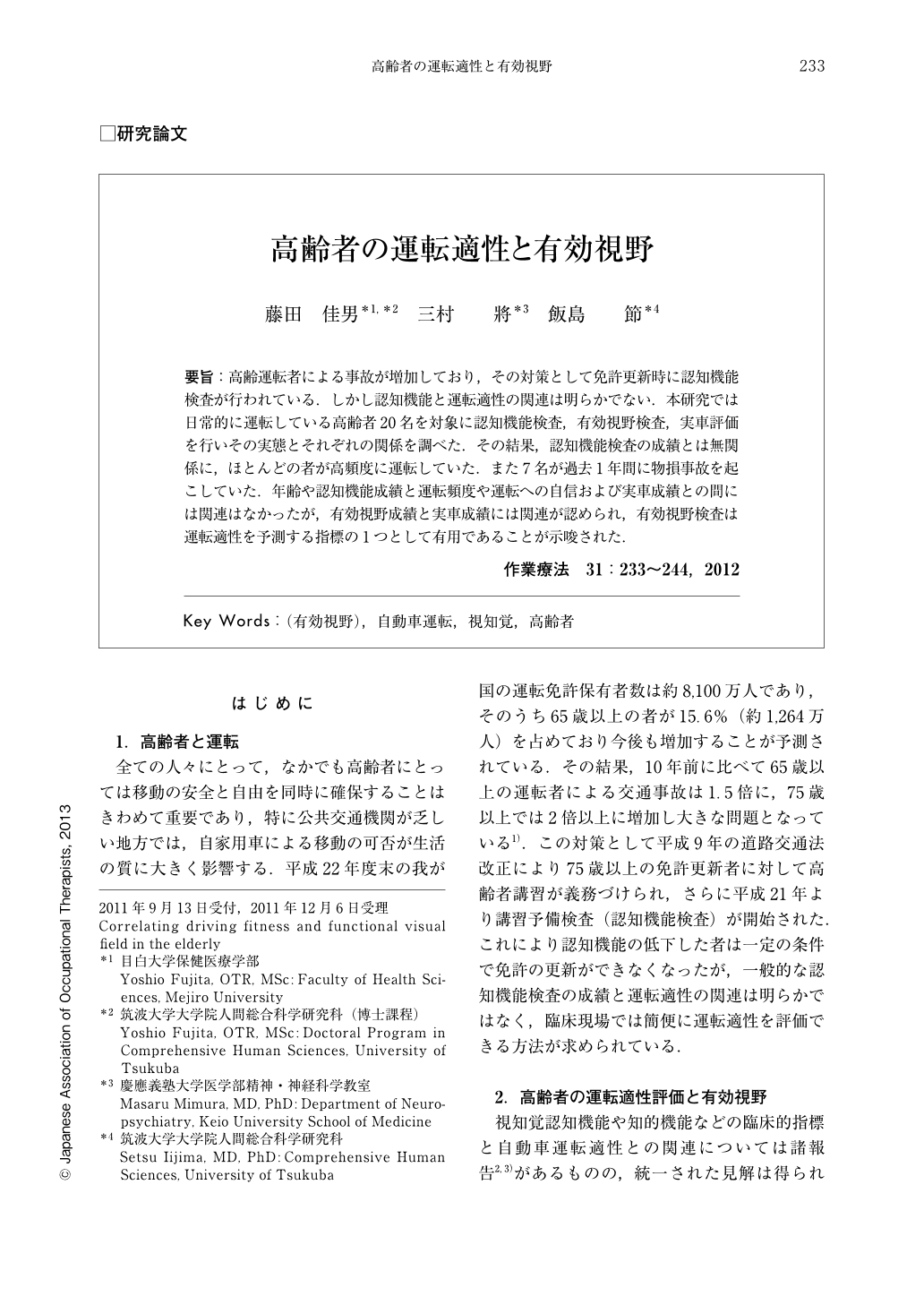- 著者
- 礒 玲子 飯島 節
- 出版者
- 国際医療福祉大学
- 雑誌
- 国際医療福祉大学学会誌 (ISSN:21863652)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.10-20, 2016-03-31
目的:高齢者介護分野における医療機関より在宅への移行時を中心とした多職種・諸機関間連携へのクライアントの参加や意思決定の現状と課題を,連携の展開過程に沿って明らかにする. 対象:医療機関または介護保険事業所に勤務する様々な専門職者と利用者本人・家族の合計23名を対象とした. 方法:クライアントの連携への参加の現状と課題について半構造化面接を行い,グラウンデッド・セオリーアプローチに基づき分析した. 結果:クライアントの連携への参加や意思決定を困難にしている連携の阻害要因として,『連携目的の不一致』,『連携対象についての認識不足』,『情報共有困難』および『レベル・態度・姿勢』の4要因が示され,専門職者とクライアントとの間の情報の非対称が認められた. 結論:クライアントの連携への参加と主体的な意思決定を促すためには,専門職者との間の情報の非対称を克服する取り組みを行うことが最も重要であり,連携におけるクライアントの位置づけや参加について専門職者側の意識を高めてゆくことが必要である.
4 0 0 0 両側松葉杖一側下肢完全免荷歩行獲得の可否と上肢筋力の関連
- 著者
- 大森 圭貢 熊切 博美 小野 順也 立石 真純 笠原 酉介 武市 梨絵 横山 有里 岩崎 さやか 多田 実加 最上谷 拓磨 笹 益雄 飯島 節
- 出版者
- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION
- 雑誌
- 日本理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.Ab1089-Ab1089, 2012
【はじめに、目的】 両側松葉杖での一側下肢完全免荷歩行(以下,松葉杖免荷歩行)は,下肢の免荷を必要とする際の有効な移動手段であるが、その獲得に難渋することは少なくない.松葉杖免荷歩行には,肩甲帯下制筋,肘伸展筋,肩内転筋,手指屈筋などの筋が関与し,それぞれ徒手筋力検査法でgood以上の筋力が必要とされている.しかし,徒手筋力検査法による筋力評価は客観性が低いことが指摘されており,臨床での指標としては不十分な面がある.松葉杖免荷歩行の獲得に必要な上肢筋力を客観的な尺度で明らかにすることができれば,トレーニング内容や期間などを考える際の有用な情報になると考えられる.本研究の目的は,松葉杖免荷歩行獲得の可否と等尺性上肢筋力の関連を検討し,松葉杖免荷歩行獲得に必要な上肢筋力を明らかにすることである.【方法】 対象者は松葉杖免荷歩行練習の指示があった者のうち,20歳以上,上肢に骨関節疾患の既往がない,評価に必要な指示に従える,研究に同意が得られる,の全ての条件を満たす者とした.前向きコホートデザインを用い,年齢,身長,Body Mass Index,性別,松葉杖歩行の経験,松葉杖免荷歩行獲得の可否,上下肢筋力を評価,測定した.松葉杖免荷歩行が可能か否かは,200m以上の安全な歩行の可否で判断した.理学療法開始日から毎回の実施日に3名の理学療法士が確認し,2名以上が一致した評価を採用した.そして理学療法開始日に歩行可能な者を歩行自立群,理学療法開始から1週間以内に歩行可能になった者を獲得群,歩行可能にならなかった者を不獲得群に分類した.理学療法開始日に,握力,肘伸展筋力,肩伸展筋力,肩内転筋力,肩甲帯下制筋力,膝伸展筋力を測定した.測定には,油圧式握力計と徒手筋力計を用い,上肢筋力は左右それぞれの最大値の平均,膝伸展筋力は非免荷側の最大値を求め,それぞれ体重比を算出した.松葉杖免荷歩行と上下肢筋力の評価は,それぞれ異なる理学療法士が行い,さらにお互いに得られた結果を伏せるようにし,測定者バイアスを排除した.分析は,松葉杖免荷歩行獲得に関連する変数を検討するために,獲得群と不獲得群間の各変数をχ2乗検定とMann-WhitneyのU検定で比較した.次に有意差のあった筋力の変数が,獲得群と不獲得群を判別できるかをReceiver Operating Characteristic(ROC)曲線の曲線下面積から検討した.統計的有意水準は危険率5%未満とした.【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院臨床試験委員会の承認を受け(受付番号第244号),対象者には十分な説明を行い,書面による同意を得て実施した.【結果】 対象者32名のうち,歩行自立群13名を除いた19名を分析対象とした.単変量解析の結果,獲得群(6名)/不獲得群(13名)の中央値は,身長168.5/161.0(cm),握力0.64/0.46(kgf/kg),肘伸展筋力0.24/0.19(kgf/kg),肩伸展筋力0.14/0.11(kgf/kg),肩内転筋力0.21/0.13(kgf/kg)であり,いずれも獲得群の方が有意に高値であった.その他の変数は,いずれも有意差がなかった.ROC曲線の曲線下面積は握力が0.95であり,獲得群を判別できる有意な指標であった.さらに握力0.57kgf/kgでは,感度83%,偽陽性度8%の精度で獲得群を判別できた.同様に肘伸展,肩伸展,肩内転のそれぞれの筋力の曲線下面積は,順に0.87,0.85,0.89であり,それぞれの筋力(kgf/kg)が,0.23,0.13,0.17では,感度80%以上,偽陽性度25%以下で獲得群を判別できた.【考察】 理学療法開始日に松葉杖免荷歩行が可能な者は半数以下であり,1週間の訓練後にも松葉杖免荷歩行獲得が困難な者が少なくなかった.獲得群と不獲得群間では身長,握力,肘伸展筋力,肩伸展筋力,肩内転筋力で有意差があったことから,理学療法開始1週程度の間に松葉杖免荷歩行を獲得できるか否かには,これらの因子が関連すると考えられた.さらに握力0.57 kgf/kg,肘伸展筋力0.23 kgf/kg,肩伸展筋力0.13 kgf/kg,肩内転筋力0.17 kgf/kgでは,それぞれ高い精度で獲得群を判別できたことから,これらの上肢筋力を上回った者では,1週間程度の理学療法によって松葉杖免荷歩行獲得が見込まれると考えられた.【理学療法学研究としての意義】 松葉杖免荷歩行の獲得が容易ではないこと,そして歩行ができない者が1週間内に獲得できるか否かを理学療法開始時の評価によって予測できる可能性を示した研究であり,理学療法評価及び予後予測において有用である.
- 著者
- 飯島 節
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.12, pp.2386-2391, 2016-12-10 (Released:2017-12-10)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 介護サービスの導入を困難にする問題とその関係性の検討
- 著者
- 鈴木 浩子 山中 克夫 藤田 佳男 平野 康之 飯島 節
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.139-150, 2012 (Released:2014-04-24)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
目的 何らかの在宅サービスが必要であるにもかかわらず,介護サービスの利用に至らない高齢者に関して,介護サービスの導入を困難にしている問題を明らかにし,問題の関係性を示すモデルを共分散構造分析にもとづいて作成することにより,有効な対策について検討する。方法 高齢者相談業務に従事する本州地域657か所の行政保健師に対し,自記式質問紙による郵送調査にて事例調査を実施した。調査対象事例は,本研究に該当する介護サービスの導入が困難な高齢者で,回答する保健師が,2000年 4 月以降家庭訪問による介入援助を行った,とくに印象に残る 1 事例とした。調査内容は,回答者および所属する自治体の属性,対象事例の基本的属性,対象事例への介入援助の結果,事例調査および文献検討により作成した介護サービスの導入を困難にする問題43項目である。有効回答を得た311通(有効回答率47.3%)を解析対象とした。介護サービスの導入を困難にする問題について,因子分析を行った後,共分散構造分析により関係性の検討を行い,最も適合度の高いモデルを選定した。結果 1) 介護サービスの導入を困難にする問題は,項目分析,因子分析の結果,第 1 因子『生活の変化に対する抵抗』,第 2 因子『親族の理解•協力の不足』,第 3 因子『手続き•契約における能力不足』,第 4 因子『インフォーマルサポートの不足』,第 5 因子『受診に対する抵抗』が抽出•命名された。2) 因子分析で得られた 5 因子を潜在変数として共分散構造分析を行った結果,GFI=0.929,AGFI=0.901,CFI=0.950と高い適合度のモデルが得られた。このモデルから,『生活の変化に対する抵抗』,『親族の理解•協力の不足』の問題に,『手続き•契約における能力不足』,『インフォーマルサポートの不足』,『受診に対する抵抗』の問題が重なり,介護サービスの導入が困難となっていることが示された。結論 行政保健師を対象とした事例調査により,介護サービスの導入を困難にする問題の関係性が示された。このような高齢者への支援には,個々の問題に応じた介入援助方法の他,手続き能力やサポートが不足し,支援が必要な高齢者を早期に把握,対応する体制を地域レベルで検討することが必要である。
1 0 0 0 OA 外来理学療法に対する脳卒中後遺症者の期待と理学療法士の意識との相違
- 著者
- 吉野 貴子 飯島 節
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.5, pp.296-303, 2003-08-20 (Released:2018-09-25)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 3
本研究では,脳卒中外来理学療法のあり方に示唆を得ることを目的として,1)外来理学療法の長期化の現状,2)外来理学療法に対する脳卒中後遺症者の期待と理学療法士の役割意識,3)外来理学療法と通所リハサービスを併用している者と通所リハサービスのみの利用者との比較の3点について検討した。調査は在宅脳卒中後遺症者284名と理学療法士200名を対象に郵送アンケート法にて実施した。その結果,外来理学療法が長期化する傾向があること,脳卒中後遺症者の多くが外来理学療法に対して麻痺や身の回りの動作が回復することを期待していること,一方,理学療法士は,機能回復よりも身体機能やADLの維持や確認を主な役割として意識していることが明らかとなった。以上から,患者と理学療法士が外来理学療法における目的を共有することがまず重要である。そうすることによって,地域リハビリテーションにおける外来理学療法の役割が明確化し,外来理学療法が患者の生活の再構築に貢献できることが示唆された。
- 著者
- 上岡 裕美子 吉野 貴子 菅谷 公美子 大橋 ゆかり 飯島 節
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.239-247, 2006 (Released:2006-09-22)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2 1
29組の脳卒中後遺症者(患者)と担当理学療法士(PT)を対象に,それぞれが認識している理学療法目標の相違を,発症からの時期別に検討した。その結果,患者は回復期後期群では運動機能改善を目標と認識していた。維持期群は歩行・運動機能の改善と認識する者と,現状維持と認識する者の両方が認められた。一方,PTは回復期後期の患者に対して社会的役割取得および歩行改善を,維持期の患者に対しては運動機能・活動の維持および社会参加の促進を目標と認識していることが示された。いずれの時期においてもそれぞれ患者とPTが認識している目標には相違が認められ,今後,両者が確実に目標を共有するための目標設定方法について検討することが必要であると考えられた。
1 0 0 0 OA 半側空間無視の長期経過 机上検査で所見が消失した患者の経過を中心に
- 著者
- 森田 秋子 小林 修二 濱中 康治 三吉 佐和子 飯島 節
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.6, pp.708-711, 2005-11-25 (Released:2011-03-02)
- 参考文献数
- 6
脳血管障害発症後早期に半側空間無視 (unilateral spatial neglect 以下USN) を呈し, その後机上検査および行動観察において所見が認められなくなった患者の長期経過を追った. 症例1は61歳男性, 3年前の右被殻出血後に左USNが出現したが, その後机上検査および行動観察にてUSNは出現しなくなり自宅へ退院した. しかし, 百人一首遊びあるいは電動車椅子操作などのストレスのかかる場面で, 左USNが再び出現した. 症例2は62歳男性, 初回の右被殻出血後に左USNが出現したが, 退院時には机上検査, 行動所見ともに所見は認められなかった. 6年後あらたに右片麻痺をきたし, 大脳左半球の脳梗塞が疑われた. 再発作直後は両方向への注意低下を認めたが, 徐々に左USNが明らかに認められるようになった. 症例3は70歳男性, 64歳時に右被殻梗塞発症後早期に左USNが出現したが, その後机上検査でも行動所見でも認められなくなり自宅退院した. 6年後ADLと知的レベルの全般的な低下を来たし, 検査の結果左USNが再び検出された.3例では, 発症早期に机上検査と行動所見において明らかな左USNが認められたが, その後所見は出現しなくなった. しかし, 新規課題あるいは難易度の高い課題, 疲労時, 反対側に出現した脳梗塞などによりUSNが再び出現した.USNは, USNそのものの重症度, 患者の課題遂行能力および環境要因, の3つの要素の相対的な関係において出現様式が規定されるものと考えられた. 一度は検出できなくなったUSNが, 全般的注意機能の低下や環境変化などにともなって再び出現する場合があることは, 高齢者においてとくに注意すべきである.
1 0 0 0 OA 最大一歩幅や歩行動作における下肢筋群の加齢に伴う役割の変化
- 著者
- 櫻井 陽子 武市 尚也 杉村 誠一郎 飯島 節
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.171-175, 2017 (Released:2017-05-02)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
〔目的〕下肢筋力は最大一歩幅や歩行に大きく関与する.股関節屈曲筋群,膝関節伸展筋群,足関節底屈筋群に着目し,最大一歩幅と歩行におけるそれぞれの役割の変化を加齢的側面から調査することとした.〔対象と方法〕女性77名を対象とし,若年者群,前期高齢者群,後期高齢者群,超高齢者群の4群に分類し,身体機能や動作能力において検討した.〔結果〕最大一歩幅と最大歩行で,若年者群は股関節屈曲筋群,前期高齢者群は膝関節伸展筋群,後期高齢者群は膝関節伸展筋群および足関節底屈筋群と有意な相関がみられたが,超高齢者群では有意な相関はみられなかった.〔結語〕歩行や最大一歩幅において相対的に大きな役割を担う筋群は,加齢に伴い変化していくことが示唆された.
1 0 0 0 OA 大腿骨頸部・転子部骨折患者の術後1週目における退院時歩行自立度の予測因子に関する検討
- 著者
- 武市 尚也 西山 昌秀 海鋒 有希子 堀田 千晴 石山 大介 若宮 亜希子 松永 優子 平木 幸治 井澤 和大 渡辺 敏 松下 和彦 飯島 節
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.48100763, 2013 (Released:2013-06-20)
【はじめに、目的】 大腿骨頸部・転子部骨折 (大腿骨骨折) 患者における退院時の歩行自立度は退院先や生命予後に影響を与える. 先行研究では, 退院時歩行能力に関連する因子として年齢, 性, 認知機能, 受傷前歩行能力などが報告されている (市村, 2001). しかし, 術後1週目の筋力, バランス能力が退院時の歩行自立度に及ぼす影響について検討された報告は極めて少ない. そこで本研究では, 大腿骨骨折患者の術後1週目の筋力, バランス能力が退院時の歩行自立度に関連するとの仮説をたて, それを検証すべく以下の検討を行った. 本研究の目的は, 大腿骨骨折患者の術後1週目の筋力, バランス能力を独立変数とし, 退院時歩行自立度の予測因子を明らかにすることである.【方法】 対象は, 2010年4月から2012年9月の間に, 当院に大腿骨骨折のため手術目的で入院後, 理学療法の依頼を受けた連続305例のうち, 除外基準に該当する症例を除いた97例である. 除外基準は, 認知機能低下例 (改訂長谷川式簡易認知機能検査: HDS-R; 20点以下), 入院前ADL低下例, 術後合併症例である. 調査・測定項目として, 入院時に基本属性と認知機能を, 術後1週目に疼痛と下肢筋力と下肢荷重率を調査および測定した. 基本属性は, 年齢, 性別, 術式である. 認知機能評価にはHDS-Rを, 疼痛評価にはVAS (Visual Analog Scale) をそれぞれ用いた. 疼痛は, 安静および荷重時について調査した. 下肢筋力の指標には, 膝関節伸展筋を用い, 検者は筋力計 (アニマ株式会社, μ-tasF1) にて被検者の術側・非術側の等尺性筋力値 (kg) を測定し, 体重比 (%) を算出した. バランス能力の指標には下肢荷重率を用いた. 測定には, 体重計を用いた. 検者は被検者に対し, 上肢支持なしで体重計上5秒間, 最大荷重するよう求め, その際の荷重量 (kg) を左右測定し, 体重比 (%) を算出した. 歩行自立度は退院1日前に評価された. 歩行自立度はFIMの移動自立度 (L-FIM) に従い, 歩行自立群 (L-FIM; 6以上) と非自立群 (L-FIM; 6未満) に分類した. 統計解析には, 退院時歩行自立群および非自立群の2群間における基本属性および術後1週目の各因子の比較についてはt検定, χ²検定を用いた. また, 退院時の歩行自立度を従属変数, 2群間比較で差を認めた因子を独立変数として, ロジスティック回帰分析を実施した. さらに, 退院時歩行自立度の予測因子とロジスティクス回帰分析で得られた予測式から求めた数値 (Model) のカットオフ値の抽出のために, 受信者動作特性 (ROC) 曲線を用い, その感度, 特異度, 曲線下面積より判定した.【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は当院生命倫理委員会の承認を得て実施された (承認番号: 第91号).【結果】 退院時における歩行自立群は48例, 非自立群は49例であった. 基本属性, 認知機能は, 年齢 (自立群73.9歳 / 非自立群81.8歳), 性別 (男性; 35% / 10%), 術式 (人工骨頭置換術; 56% / 29%), HDS-R (27.2 / 25.9) であり2群間に差を認めた (p<0.05). 術後1週目におけるVASは安静時 (1.0 / 1.8), 荷重時 (3.7 / 5.0) ともに非自立群は自立群に比し高値を示した (p<0.05). 膝伸展筋力は術側 (22.0% / 13.8%), 非術側 (41.8% / 27.6%) ともに自立群は非自立群に比し高値を示した (p<0.05). 下肢荷重率も術側(75.3% / 55.8%), 非術側 (98.2% / 92.3%) ともに自立群は非自立群に比し, 高値を示した (p<0.05). 2群間比較で差を認めた因子を独立変数としたロジスティクス回帰分析の結果, 退院時歩行自立度の予測因子として, 術側膝伸展筋力 (p<0.05, オッズ比; 1.14, 95%信頼区間; 1.04-1.28)と術側下肢荷重率 (p<0.05, オッズ比; 1.04, 95%信頼区間; 1.01-1.08) が抽出された. その予測式は, Model=術側膝伸展筋力*0.131+術側下肢荷重率*0.04-4.47であった. ROC曲線から得られたカットオフ値は, 術側膝伸展筋力は18% (感度; 0.72, 特異度; 0.77, 曲線下面積; 0.78), 術側下肢荷重率は61% (感度; 0.76, 特異度; 0.68, 曲線下面積; 0.76), そしてModelは0.77 (感度; 0.76, 特異度; 0.87, 曲線下面積; 0.82) であった.【考察】 大腿骨骨折患者の術後1週目における術側膝伸展筋力と術側下肢荷重率は, 退院時の歩行自立度を予測する因子であると考えられた. また, ロジスティクス回帰分析で得られた予測式から算出したModelはROC曲線の曲線下面積において上記2因子よりも良好な判別精度を示した. 以上のことから, 術側膝伸展筋力および術側下肢荷重率の両指標を併用したModelを使用することは, 単一指標よりも歩行自立度を予測する因子となる可能性があるものと考えられた.【理学療法学研究としての意義】 本研究の意義は, 術後早期における退院時歩行自立度の予測因子およびその水準を示した点である. 本研究の成果は, 急性期病院において転帰先を決定する際の一助になるものと考えられる.
1 0 0 0 高齢者の運転適性と有効視野
- 著者
- 藤田 佳男 三村 將 飯島 節
- 出版者
- 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.233-244, 2012-06-15
要旨:高齢運転者による事故が増加しており,その対策として免許更新時に認知機能検査が行われている.しかし認知機能と運転適性の関連は明らかでない.本研究では日常的に運転している高齢者20名を対象に認知機能検査,有効視野検査,実車評価を行いその実態とそれぞれの関係を調べた.その結果,認知機能検査の成績とは無関係に,ほとんどの者が高頻度に運転していた.また7名が過去1年間に物損事故を起こしていた.年齢や認知機能成績と運転頻度や運転への自信および実車成績との間には関連はなかったが,有効視野成績と実車成績には関連が認められ,有効視野検査は運転適性を予測する指標の1つとして有用であることが示唆された.
1 0 0 0 OA デイサービス利用高齢者の運動能力に関する自己認識と転倒の関連について
- 著者
- 平野 康之 藤田 佳男 鈴木 浩子 飯島 節
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.705-710, 2010 (Released:2010-11-25)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
〔目的〕5つの運動機能検査を用いて運動能力に関する自己認識が適切に行えているかどうかの評価(以下適切度)を実施し,転倒との関連について検討した。〔対象〕デイサービス利用高齢者76名とした。〔方法〕日常動作に関連が深い5つの運動機能検査(Functional reach test,立ち上がりテスト,またぎテスト,台昇降テスト,最大歩幅テスト)について対象者自身による予測値と実測値を測定した。得られた予測値と実測値の一致の程度をもとに適切度を評価し,適切評価群と不適切評価群の2群に分類して転倒との関連について検討した。〔結果〕「立ち上がりテスト」と「またぎテスト」に基づく評価では,不適切評価群の転倒経験者の割合が適切評価群のそれに比して有意に多い結果を示した。また,5つの運動機能検査の適切度を総合して判断した評価(以下5P適切度)においても同様の結果を示した。さらに転倒予測指標としての感度と特異度の検討では,単一検査の適切度に比して複合検査による5P適切度の方が感度ならびに特異度ともに比較的良好な値を示した。〔結語〕本研究で用いた運動能力に関する自己認識評価は転倒予測として臨床応用できる可能性があり,単一検査の適切度よりも複合的な適切度を用いる方がより転倒予測精度を向上できる可能性が示唆された。
- 著者
- 上岡 裕美子 斉藤 秀之 大橋 ゆかり 飯島 節
- 出版者
- 茨城県立医療大学
- 雑誌
- 茨城県立医療大学紀要 (ISSN:13420038)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.97-108, 2010-03
脳卒中者(以下患者)への理学療法の目標設定方法としてチェックリスト式患者参加型目標設定法(Patient Participation Goal-setting Method using Checklist: PPGMC)を用い、また目標達成度の測定にGoal Attainment Scaling (GAS) を用いて、その臨床有用性を検討した。3組の患者と担当理学療法士(以下PT)を対象に事例検討を行った。PPGMCは生活機能目標チェックリストと目標共有シートからなり、患者とPTが一緒に利用する。手順は、1)生活機能目標チェックリストに希望する目標をチェックする、2)目標を話し合う、3)決定した目標を目標共有シート記入する、4)理学療法を実施しGASで定期的に評価する、とした。最後にPTへ質問紙調査を行った。その結果、どの事例もPPGMCを用いることで各患者独自の生活機能目標を設定できた。質問紙から、PPGMCは活動・参加に関する患者の希望を把握しやすい、GASを用いて目標を段階的に達成し共通の認識を持つことで患者の意欲向上につながった、との意見が得られた。これらより脳卒中者への理学療法においてPPGMCとGASの使用が臨床的に有用であることが示唆された。
- 著者
- 武市 尚也 渡辺 敏 松下 和彦 飯島 節 西山 昌秀 海鋒 有希子 堀田 千晴 石山 大介 若宮 亜希子 松永 優子 平木 幸治 井澤 和大
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.48100763, 2013
【はじめに、目的】 大腿骨頸部・転子部骨折 (大腿骨骨折) 患者における退院時の歩行自立度は退院先や生命予後に影響を与える. 先行研究では, 退院時歩行能力に関連する因子として年齢, 性, 認知機能, 受傷前歩行能力などが報告されている (市村, 2001). しかし, 術後1週目の筋力, バランス能力が退院時の歩行自立度に及ぼす影響について検討された報告は極めて少ない. そこで本研究では, 大腿骨骨折患者の術後1週目の筋力, バランス能力が退院時の歩行自立度に関連するとの仮説をたて, それを検証すべく以下の検討を行った. 本研究の目的は, 大腿骨骨折患者の術後1週目の筋力, バランス能力を独立変数とし, 退院時歩行自立度の予測因子を明らかにすることである.【方法】 対象は, 2010年4月から2012年9月の間に, 当院に大腿骨骨折のため手術目的で入院後, 理学療法の依頼を受けた連続305例のうち, 除外基準に該当する症例を除いた97例である. 除外基準は, 認知機能低下例 (改訂長谷川式簡易認知機能検査: HDS-R; 20点以下), 入院前ADL低下例, 術後合併症例である. 調査・測定項目として, 入院時に基本属性と認知機能を, 術後1週目に疼痛と下肢筋力と下肢荷重率を調査および測定した. 基本属性は, 年齢, 性別, 術式である. 認知機能評価にはHDS-Rを, 疼痛評価にはVAS (Visual Analog Scale) をそれぞれ用いた. 疼痛は, 安静および荷重時について調査した. 下肢筋力の指標には, 膝関節伸展筋を用い, 検者は筋力計 (アニマ株式会社, μ-tasF1) にて被検者の術側・非術側の等尺性筋力値 (kg) を測定し, 体重比 (%) を算出した. バランス能力の指標には下肢荷重率を用いた. 測定には, 体重計を用いた. 検者は被検者に対し, 上肢支持なしで体重計上5秒間, 最大荷重するよう求め, その際の荷重量 (kg) を左右測定し, 体重比 (%) を算出した. 歩行自立度は退院1日前に評価された. 歩行自立度はFIMの移動自立度 (L-FIM) に従い, 歩行自立群 (L-FIM; 6以上) と非自立群 (L-FIM; 6未満) に分類した. 統計解析には, 退院時歩行自立群および非自立群の2群間における基本属性および術後1週目の各因子の比較についてはt検定, χ²検定を用いた. また, 退院時の歩行自立度を従属変数, 2群間比較で差を認めた因子を独立変数として, ロジスティック回帰分析を実施した. さらに, 退院時歩行自立度の予測因子とロジスティクス回帰分析で得られた予測式から求めた数値 (Model) のカットオフ値の抽出のために, 受信者動作特性 (ROC) 曲線を用い, その感度, 特異度, 曲線下面積より判定した.【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は当院生命倫理委員会の承認を得て実施された (承認番号: 第91号).【結果】 退院時における歩行自立群は48例, 非自立群は49例であった. 基本属性, 認知機能は, 年齢 (自立群73.9歳 / 非自立群81.8歳), 性別 (男性; 35% / 10%), 術式 (人工骨頭置換術; 56% / 29%), HDS-R (27.2 / 25.9) であり2群間に差を認めた (p<0.05). 術後1週目におけるVASは安静時 (1.0 / 1.8), 荷重時 (3.7 / 5.0) ともに非自立群は自立群に比し高値を示した (p<0.05). 膝伸展筋力は術側 (22.0% / 13.8%), 非術側 (41.8% / 27.6%) ともに自立群は非自立群に比し高値を示した (p<0.05). 下肢荷重率も術側(75.3% / 55.8%), 非術側 (98.2% / 92.3%) ともに自立群は非自立群に比し, 高値を示した (p<0.05). 2群間比較で差を認めた因子を独立変数としたロジスティクス回帰分析の結果, 退院時歩行自立度の予測因子として, 術側膝伸展筋力 (p<0.05, オッズ比; 1.14, 95%信頼区間; 1.04-1.28)と術側下肢荷重率 (p<0.05, オッズ比; 1.04, 95%信頼区間; 1.01-1.08) が抽出された. その予測式は, Model=術側膝伸展筋力*0.131+術側下肢荷重率*0.04-4.47であった. ROC曲線から得られたカットオフ値は, 術側膝伸展筋力は18% (感度; 0.72, 特異度; 0.77, 曲線下面積; 0.78), 術側下肢荷重率は61% (感度; 0.76, 特異度; 0.68, 曲線下面積; 0.76), そしてModelは0.77 (感度; 0.76, 特異度; 0.87, 曲線下面積; 0.82) であった.【考察】 大腿骨骨折患者の術後1週目における術側膝伸展筋力と術側下肢荷重率は, 退院時の歩行自立度を予測する因子であると考えられた. また, ロジスティクス回帰分析で得られた予測式から算出したModelはROC曲線の曲線下面積において上記2因子よりも良好な判別精度を示した. 以上のことから, 術側膝伸展筋力および術側下肢荷重率の両指標を併用したModelを使用することは, 単一指標よりも歩行自立度を予測する因子となる可能性があるものと考えられた.【理学療法学研究としての意義】 本研究の意義は, 術後早期における退院時歩行自立度の予測因子およびその水準を示した点である. 本研究の成果は, 急性期病院において転帰先を決定する際の一助になるものと考えられる.
1 0 0 0 高度痴呆の残存機能評価
- 著者
- 飯島 節
- 出版者
- 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.170-173, 2005-03-25
1 0 0 0 三つ編みの研究(第2報) : 痴呆性老人の評価尺度としての検討
- 著者
- 守口 恭子 飯田 房枝 飯島 節
- 雑誌
- 作業療法 = The Journal of Japanese Occupational Therapy Association (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, 2001-05-15
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 飯島 節
- 出版者
- The Japan Geriatrics Society
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.170-173, 2005
The elderly with dementia show distinct characteristics and different remaining abilities even in advanced disease. For improvement of the quality of care for the elderly, it is essential to evaluate their remaining abilities. Mini-communication Test, Braiding Test and Vitality Index have been developed to evaluate the abilities remaining in the elderly with severe dementia. The reliability, validity and usefulness of these new methods were discussed.
- 著者
- 溝口 環 飯島 節 江藤 文夫 石塚 彰映 折茂 肇
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.10, pp.835-840, 1993-10-25 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 17 31 17
痴呆に伴う各種の行動異常は介護者にとって大きな負担となるが, 行動異常を定量的に評価する方法はまだ確立されていない. そこで, Baumgarten らの Dementia Behavior Disturbance Scale (DBDスケール) を用いて, 痴呆患者の行動異常の評価を試み, 評価法の信頼性と妥当性ならびに介護者の有する負担感との関連について検討した.痴呆群27例 (アルツハイマー型21例, 脳血管性6例, 男性9例, 女性18例, 平均年齢77.7歳) および神経疾患を有するが痴呆のない非痴呆群17例 (男性2例, 女性15例, 平均年齢76.8歳) の外来通院患者と施設入所痴呆患者10例 (アルツハイマー型9例, 脳血管性1例, 男性2例, 女性8例, 平均年齢82.3歳) を対象とした. DBDスケールは, 28項目の質問からなり, 異常行動の出現頻度を5段階に分けて介護者が評価した.DBDスケールの信頼性については, 再テスト法の相関係数0.96, Cronbach のα係数0.95, 評価者間信頼性は Intraclass Correlation Coefficient (ICC) 平均0.71と何れも高い値を示した. 妥当性については, DBDスケール得点と簡易知能質問紙法 (SPMSQ) 誤答数との相関係数0.54と知的機能との相関は良好であった. DBD得点とアンケートで評価した介護者の負担感との間に有意の相関を認め (r=0.53), 介護の負担度を反映し得る指標としての有用性も示唆された.DBDスケールは, 痴呆に伴う行動異常の客観的評価や経過観察の方法として信頼性が高く, 介護負担も反映しうる有用な評価法である.
1 0 0 0 OA 簡便な高齢者用運転能力評価法の開発
- 著者
- 飯島 節
- 巻号頁・発行日
- 2013
科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書:基盤研究(C)2010-2012