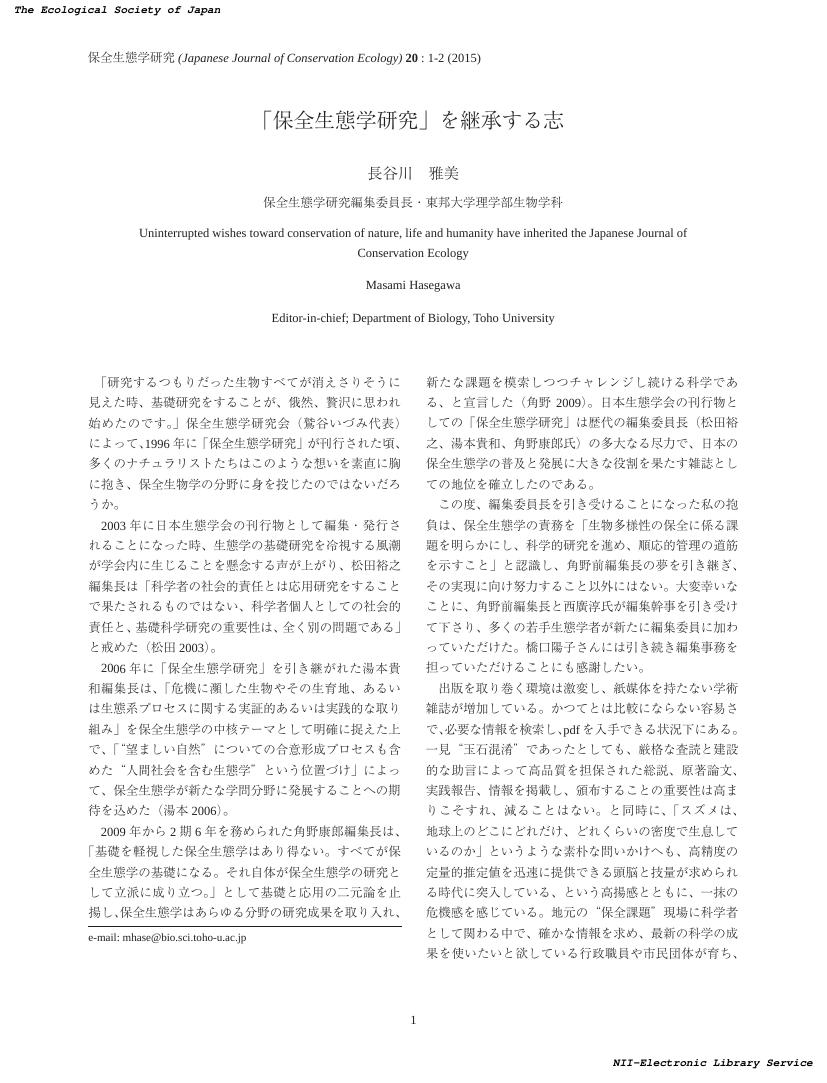1 0 0 0 OA 「保全生態学研究」を継承する志
- 著者
- 長谷川 雅美
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.1-2, 2015-05-30 (Released:2017-11-01)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA 釧路湿原大島川周辺におけるエゾシカ生息痕跡の分布特性と時系列変化および植生への影響
- 著者
- 冨士田 裕子 高田 雅之 村松 弘規 橋田 金重
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.143-153, 2012-07-30 (Released:2017-04-27)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 9
近年、ニホンジカの個体数の急激な増加により、各地で自然植生に対する様々な影響が現れている。森林に対する影響の報告が多いのに対し、踏査等が困難な湿原へのシカの影響については報告が少ないのが現状である。そこで北海道東部の釧路湿原中央部の大島川周辺をモデルサイトとし、2時期に撮影された空中写真からGISを使用してエゾシカの生息痕跡であるシカ道を抽出し、その変化と分布特性を調べた。さらに、現地で植生調査を行い、調査時よりエゾシカの密度が低かったと考えられる5年前の植生調査結果との比較を行った。また、植生調査区域でエゾシカのヌタ場の位置情報と大きさの計測を行った。その結果、調査範囲62.2ha内のシカ道の総延長は、1977年に53.6kmだったものが2004 年には127.4kmとなり、約2.4倍の増加が認められた。ヌタ場は、2時期の空中写真の解析範囲内では確認されなかったが、2009年の現地調査では大島川の河辺に11ヶ所(合計面積759m2)形成されていた。以上から、大島川周辺では30年間でエゾシカの利用頻度が上昇し、中でも2004年以降の5年間でシカ密度が急増したと考えられた。両時期とも川に近いほどシカ道の分布密度が高く、ヌタ場は湿原内の河川蛇行部の特に内側に好んで作られていた。蛇行の内側は比高が低く、川の氾濫の影響を受けやすいヌタ場形成に都合のよい立地であることに加え、エゾシカの嗜好性の高いヤラメスゲが優占する場所で、えさ場としても利用されていた。大島川周辺には既存のヨシ-イワノガリヤス群落、ヨシ-ヤラメスゲ群落が分布していた。ただし、河辺のヌタ場付近にはヤナギタデ群落が特異的に出現し、DCA解析からこの群落はエゾシカの採食、踏圧、泥浴びなどの影響で、ヨシ-ヤラメスゲ群落が退行して形成された代償植生であることが示唆された。
1 0 0 0 OA 社会性狩りバチにおける血縁認識 (<特集>社会性昆虫における認識機構とカースト分化機構)
- 著者
- 熊野 了州 粕谷 英一
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.183-191, 1999-08-25 (Released:2017-05-25)
- 参考文献数
- 56
- 著者
- 黒田 有寿茂 中濵 直之 早坂 大亮 玉置 雅紀 花井 隆晃
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- pp.2214, (Released:2023-04-30)
- 参考文献数
- 60
スパルティナ・アルテルニフロラ(Spartina alterniflora Loisel.)は北アメリカの大西洋岸およびメキシコ湾岸原産の干潟や河口の塩性湿地に生育するイネ科多年生草本である。本種は干潟の陸地化や沿岸域の保護を目的とした意図的な導入、また非意図的な移入・逸出によって世界各地に分布を広げており、定着地に大規模な密生群落を形成することで在来の生態系や産業に大きな影響を及ぼしている。日本国内において、本種は 2008 年に愛知県豊橋市の梅田川河口で初めて確認され、その後 2010 年に熊本県で確認された。スパルティナ・アルテルニフロラのもつ干潟生態系への脅威から、2014 年には本種を含むスパルティナ属全種が特定外来生物に指定された。本稿ではスパルティナ・アルテルニフロラの形態的・生態的な特徴と、2020 年に山口県下関市で新たに確認された本種の侵入状況ならびに駆除の現状についてとりまとめた。
1 0 0 0 OA 琵琶湖東岸における絶滅危惧植物タチスズシロソウ大群落の出現とその保全
- 著者
- 山口 正樹 杉阪 次郎 工藤 洋
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.111-119, 2010-05-30 (Released:2018-02-01)
- 参考文献数
- 21
アブラナ科の越年生草本タチスズシロソウArabidopsis kamchatica subsp.kawasakianaは環境省のレッドリストに絶滅危惧IB類として記載されている。生育地が減少しており、その多くが数百株以下の小さな個体群である。著者らは、2006年春に、琵琶湖東岸において3万株以上からなるタチスズシロソウの大群落が成立していることを発見した。この場所では2004年から毎年夏期にビーチバレーボール大会が行われており、砂浜が耕起されるようになった。この場所の群落は埋土種子から出現したものと考えられ、耕起により種子が地表に移動したことと、競合する多年草が排除されたごとが群落の出現を促した可能性があった。2006年には、この群落を保全するため、ビーチバレーボール大会関係者の協力のもと、位置と時期を調整して耕起を行った。その結果、3年連続で耕起した場所、2年連続で耕起後に1年間耕起しなかった場所、全く耕起しなかった場所、初めて耕起し左場所を設けることができた。この耕起履歴の差を利用し、翌2007年に個体密度と面積あたりの果実生産数を調査することで、タチスズシロソウ群落の成立と維持に重要な要因を推定した。2006年に初めて耕起した場所では、耕起しなかった場所に比べて、翌年の個体密度、面積当たりの果実生産ともに高くなった。2年連続耕起後に1年間耕起を休んだ場所では、3年連続で耕起した場所に比べて、翌年の個体数は増えたが果実生産数は増加しなかった。また、結実期間中(6月)に耕起した場所では、結実終了後に耕起した場所に比べて、翌年の個体密度と果実生産数が低下した。これらのことから、秋から春にかけてのタチスズシロソウの生育期間中には耕起を行わないことと、結実後に耕起を行うことがタチスズシロソウ個体群の保全に有効であると結論した。このことは、ビーチバレーボール大会のための耕起を適切な時期に行うことにより、砂浜の利用と絶滅危惧植物の保全とが両立可能であることを示している。
1 0 0 0 OA 多様度指数間の相関関係 : 各種の指数値は何を表すか
- 著者
- 伊藤 秀三
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.187-194, 1990-12-31 (Released:2017-05-24)
- 被引用文献数
- 2
Correlations among nine indices of species diversity, HURLBERT's S(100), ITOW's b, FISHER's α, three varieties of SIMPSON's d, MCINTOSH's index, SHANNON's H', and PIELOU's J', were studied using measurements taken in 57 forests, from the humid tropical to the humid warm-temperate regions of East Asia, Pacific islands and Amazonian upstream. The indices were categorized into two groups according to their correlations. In first group, consisting of S(100), b, α and 1/d, values are sensitive to changes in species richness. (1-d), (1-d)/(1-d)max, MCINTOSH's index, H' and J' belong to the second group. The indices studied showed intra-but not inter-group correlation. The number of species occurring once in the community is significantly correlated with FISHER's α.
1 0 0 0 OA 季節適応としての昆虫の表現型可塑性
- 著者
- 石原 道博 世古 智一
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.27-32, 2007-03-31 (Released:2016-09-10)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
表現型可塑性は、昆虫では翅多型や季節型および光周期による休眠誘導などの現象として一般的に知られ、季節適応にきわめて重要な役割を果たしている。これらの可塑性は異なる季節に出現する世代の間で見られ、季節的に変動する環境条件に多化性の昆虫が適応した結果、進化したと考えられている。しかしながら、これまでの研究は、可塑性が生じる生理的メカニズムについて調べたものばかりが目立ち、適応的意義まで厳密に調べた研究は少ない。表現型可塑性に適応的意義があるかどうかを明らかにすることは、表現型可塑性の進化を考えるうえでも重要なことである。この総説では、イチモンジセセリとシャープマメゾウムシの2種の多化性昆虫を対象に、世代間で見られる表現型可塑性が寄主植物のフェノロジーに適応したものであることを紹介する。シャープマメゾウムシでは、春に出現する越冬世代成虫は繁殖よりも寿命を長くする方向に、夏や秋に出現する世代の成虫は寿命よりも繁殖に多くのエネルギーを配分している。イチモンジセセリでは、秋に出現する世代のメス成虫は春および夏に出現する世代のメス成虫に比べてかなり大きな卵を産む。また、この世代が野外で遭遇する日長・温度条件下で幼虫を飼育すると、他の世代のものよりも大卵少産の繁殖配分パターンを示す。これらの表現型可塑性は、世代間で生活史形質問のエネルギー配分量の割合が変化するものであり、寄生植物のフェノロジーおよび寄主植物の質の季節変化に対する適応と考えられる。
1 0 0 0 OA 水辺生態系の物質輸送に果たす遡河回遊魚の役割
- 著者
- 帰山 雅秀
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.51-59, 2005-04-25 (Released:2017-05-27)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 7
The consequences of nutrient loss (oligotrophication) and attendant low productivity on biodiversity and productivity in the ecosystem has recently invoked the interest of researchers, as result of loss of wild anadromous fish by acceleration of urbanization and deterioration of natural riparian ecosystem such as dam construction, habitat destruction, and artificial hatchery program. In Japan, chum salmon (Oncorhynchus keta) have been mass-produced by hatchery program, while numerous wild Pacific salmon have been almost extinguished by a combination of the urbanization and the deterioration of riparian ecosystem. This review focuses on effects of anadromous fish on biodiversity and productivity in the riparian ecosystem with relation to dynamics of nutrient, biofilm, aquatic insects, salmonids, terrestrial animals, and human activity, and isotopic evidence for enrichment of salmon-derived nutrients. Anadromous fish are key species for sustaining production and biodiversity in the riparian ecosystem. For sustainable conservation management of riparian ecosystem, the rehabilitations of wild salmon population, system of material cycle, and natural rivers are critical important issues in Japan.
- 著者
- 深澤 圭太 石濱 史子 小熊 宏之 武田 知己 田中 信行 竹中 明夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.171-186, 2009-07-31 (Released:2017-04-20)
- 参考文献数
- 51
- 被引用文献数
- 10
野外の生物の分布パターンは生育に適した環境の分布や限られた移動分散能力などの影響をうけるため、空間的に集中した分布を持つことが多い。データ解析においてはこのような近隣地点間の類似性「空間自己相関」を既知の環境要因だけでは説明できないことが多く、近い地点同士ほど残差が類似する傾向がしばしば発生する。この近隣同士での残差の非独立性を考慮しないと、第一種の過誤や変数の効果の大きさを誤って推定する原因になることが知られているが、これまでの空間自己相関への対処法は不十分なものが多く見られた。近年、ベイズ推定に基づく空間統計学的手法とコンピュータの能力の向上によって、より現実的な仮定に基づいて空間自己相関を扱うモデルが比較的簡単に利用できるようになっている。中でも、条件付き自己回帰モデルの一種であるIntrinsic CARモデルはフリーソフトWinBUGSで計算可能であり、生物の空間分布データの解析に適した特性を備えている。Intrinsic CARモデルは「空間的ランダム効果」を導入することで隣接した地点間の空間的な非独立性を表現することが可能であると共に、推定された空間的ランダム効果のパターンからは対象種の分布パターンに影響を与える未知の要因について推察することができる。空間ランダム効果は隣接した地点間で類似するよう、事前分布によって定義され、類似の度合いは超パラメータによって制御されている。本稿では空間自己相関が生じるメカニズムとその問題点を明らかにした上で、Intrinsic CARモデルがどのように空間自己相関を表現しているのかを解説する。さらに、実例として小笠原諸島における外来木本種アカギと渡良瀬遊水地における絶滅危惧種トネハナヤスリの分布データへの適用例を紹介し、空間構造を考慮しない従来のモデルとの比較からIntrinsic CARモデルの活用の可能性について議論する。
- 著者
- 今村 彰生
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.115-125, 2018 (Released:2018-07-23)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2
琵琶湖淀川水系および三方五湖の固有種であり絶滅危惧種であるハスについて、2011年3月~ 2016年11月にかけて生息調査を行った。2014 年に発表した175 地点に、190 地点を新たに調査した。本研究では北西岸の調査地を重点的に増やし、これによって、ハスの生息が確認できた地点を前報の58 から135 地点に増やすことができた。また、北西部(北湖)にはハスの生息地点が多数存在することが判明した。前報と同様に、説明変数を底質、水路形状、水路の護岸の有無、水路の樹木の有無、ヨシ帯の有無、季節(春、夏、秋)とした一般化線形混合モデル解析を実施した。その結果、ハスの在/ 不在に正の影響を与える要因として、砂質の湖底の重要性が示され、礫質についても重要であることが新たに示された。これら365 地点のうち、332 地点についてハスの成魚と未成魚を区別して記録した。成魚と未成魚がいずれも在の地点が17、成魚のみの地点が41、未成魚のみの地点が65、いずれも不在の地点が209であった。成魚と未成魚の在/ 不在を応答変数行列として、上記の水路形状、水路の護岸の有無、水路の樹木の有無、ヨシ帯の有無を説明変数にPERMANOVA 解析を実施したところ、底質と護岸が有意な影響を与えていることが示された。琵琶湖西岸でのハスの在/ 不在を示した地図に、一般化線形混合モデル解析から得られたハスの生息確率予測値を、色分けして図示したところ、北湖と南湖における生息地の現状の差が明瞭に示され、本研究で新たに調査した北西部にハスの生息地が多数あり、未検出の調査地点にも生息確率が高い地点が複数あった。一方南湖では生息確率の高い地点が極めて少なく、本研究での検出地点以外でのハスの生息の見込みは少ないことが示された。本研究で得られた砂底、礫底の重要性を踏まえ、北湖に砂浜が相対的に多く残存していることも合わせて考えると、今後の砂浜の維持や河川からの砂の供給の重要性についても注目する必要がある。
1 0 0 0 OA 深泥池湿原に夜間出没するニホンジカCervus nippon
- 著者
- 辻野 亮 鄭 呂尚 松井 淳
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.159-166, 2015-11-30 (Released:2017-10-01)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
市街地に隣接した深泥池湿原(京都市)にニホンジカCervus nipponが出没して問題になっていることから、深泥池湿原と周辺林のニホンジカの関係を明らかにすることを目的として、深泥池湿原とその周辺林に自動撮影カメラを2014年6月16日から12月17日まで34台設置し(深泥池湿原に4台、深泥池湿原の東に位置する宝ヶ池公園東部に17台、宝ヶ池公園西部に5台、西に位置する本山国有林に3台、京都大学上賀茂試験地に5台)、動物の行動を調査した。のべ2700.2日の調査によって、哺乳類が1485枚11種(55.0頭/100カメラ日)撮影されたことから、都市域に残存しているこれらの森林は、哺乳類の生息地として重要な役割を果たしていると推測された。その一方で、撮影回数の93.2%がニホンジカで占められており、単調な哺乳類相となっていることが示唆された。深泥池湿原での撮影頻度は、日中は0に近く、夜間に高い値を示した。一方、宝ヶ池公園西部と東部では逆の傾向を示した。本山国有林と上賀茂試験地では、昼夜間で撮影頻度はそれほど変わらなかった。以上から、宝ヶ池公園に生息するニホンジカが日没頃の時間帯に深泥池湿原に侵入し、夜間は湿原に滞在して、日の出頃の時間帯に再び宝ヶ池公園の森林に帰ってゆくことが推測された。
1 0 0 0 OA 特定外来生物オオクチバスの違法放流 : 岩手県奥州市のため池の事例(保全情報)
- 著者
- 角田 裕志 満尾 世志人 千賀 裕太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.243-248, 2011-11-30 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 4
We investigated the fish fauna in 50 irrigation ponds in Iwate prefecture, northeastern Japan. Four cases of new invasions of alien largemouth bass, Micropterus salmoides, into previously non-invaded ponds were observed during surveys from 2008 to 2009. Given the limitations of natural migration by largemouth bass, all of these cases were likely the result of illegal stocking. In three of the ponds, establishment of new populations of bass was successfully prevented by the removal of collected individuals during our survey. However, the population eradication in the remaining pond failed, and the recruitment of juveniles was observed in 2010 surveys. Our results suggest that the Invasive Alien Species Act was insufficient to prevent illegal stocking of largemouth bass and that further countermeasures such as monitoring surveys and patrolling are needed.
1 0 0 0 OA 適応的な表現型可塑性による複数ハビタット利用とハビタット選択
- 著者
- 工藤 洋
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.66-70, 2007-03-31 (Released:2016-09-10)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
ハビタットの環境が大きく変わると、適応度が大幅に低下する可能性がある。適応的な表現型可塑性は、環境変動に際して適応度の低下を防ぐ働きがある。本稿では、適応的な表現型可塑性の機能として、複数ハビタット利用とハビタット選択とがあることを指摘した。複数ハビタット利用では、それぞれのハビタットでの適応度を高めるような表現型を可塑性によって実現する。ハビタット選択では、不適な環境を回避し好適な環境を利用するような形質変化が可塑性によってもたらされる。複数ハビタット利用の例としては、両生類の対捕食者誘導防御・昆虫の季節多型・水生植物の陸生型形成などがある。また、ハビタット選択の例としては、昆虫の相変異に伴う飛翔多型・休眠による季節適応・植物の被陰回避反応・開花調節などがある。
- 著者
- 松村 健太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.179, 2022 (Released:2022-10-22)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
移動は雄の繁殖に多大な影響を与える。移動活性の高い雄は多くの雌と遭遇することが可能であるため、交尾成功度が増加すると予想される。その一方で、移動活性の低い雄は雌との遭遇頻度が低い分、交尾後の受精成功度の増加のための投資量が多いと予想される。昆虫において、脚は移動のみならず、交尾の際にも使用される重要な付属肢としての役割も持ち、様々な種で脚の形態に性的二型が見られる。雄の脚において、移動に有利な形態は、交尾時の雌の把握では不利になる可能性もあり、雄の脚は様々な選択圧のバランスによって形作られていることが推測される。受精成功度への投資量が多い移動活性が低い雄は、移動活性の高い雄とは異なる形態の脚を持つことが予想される。本研究では、コクヌストモドキTribolium castaneum Herbstを対象として、歩行活性に対する人為選抜への繁殖形質や脚の形態の反応について調査を行った。その結果、移動活性の低い方向へ選抜された系統の雄は、移動活性の高い系統の雄よりも脚が有意に長いことが明らかとなった。長い脚を持つ雄は、交尾時の雌からの抵抗に耐えることを可能とし、交尾時間の延長による受精成功度の増加において有利であることが示唆された。筆者らによる研究の結果から、脚の性的サイズ二型の進化やその度合いに種間変異が見られる現象についても議論したい。
1 0 0 0 OA 西太平洋湿潤地域の植生帯と針葉樹優占の生物地理学
- 著者
- 相場 慎一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.313-321, 2017 (Released:2017-12-05)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 4
日本から台湾・東南アジア島嶼部・ニューギニア・オーストラリア東岸を経てタスマニアとニュージーランドに至る西太平洋湿潤地域では、巨視的に見ると、寒冷な気候で針葉樹と落葉広葉樹が優占し、温暖な気候では常緑広葉樹が優占する。ただし、針葉樹が優占する植生帯は、北半球だけに存在する「落葉広葉樹林」(暖かさの指数、WI=45〜85℃、寒さの指数、CI<−15℃)を挟んで、「北方針葉樹林」と南北両半球にまたがる「温帯・熱帯針広混交林」という2つの森林帯に別れている。北方針葉樹林は夏が短く冬が厳しい大陸性気候(WI=15〜45℃、CI<−15℃)に成立するのに対し、両半球にまたがる温帯・熱帯針広混交林は寒い冬を欠く海洋性気候(WI<144℃、CI>−15℃)に成立する。さらに、熱帯低地を中心とするWI>144℃の地域には「熱帯・亜熱帯常緑広葉樹林」が分布し、西太平洋湿潤地域の森林帯は以上4つに大別される。北方針葉樹林は日本の高緯度または高標高に分布し、亜高山帯林や亜寒帯林とも呼ばれる。温帯・熱帯針広混交林は、日本では太平洋側の狭い標高帯に限って分布する(いわゆるモミ・ツガ林など)が、台湾やニュージーランドではより広い標高帯に渡って(より暖かい気候にまで)分布する。これら両半球の温帯針広混交林は、東南アジアやニューギニアの熱帯山地の針広混交林へと連続的に変化していく。以上のことから、針葉樹が優占する温帯・熱帯林を総称して、北方針葉樹林とは独立した、温帯・熱帯針広混交林と名付けたのである。温帯・熱帯針広混交林では、比較的涼しい夏(熱帯山地では年を通じた低温)が常緑広葉樹の生育を制限する一方、温暖な冬(熱帯山地では冬がないこと)が落葉広葉樹の生育を制限することで、針葉樹が優占しているのであろう。巨視的に見た時に針葉樹が寒冷な気候で優占することは、土壌の貧栄養条件と関連している可能性があり、広葉樹が優占する気候帯であっても貧栄養土壌上では局所的に針葉樹が優占しうることは、その可能性を支持する。西太平洋地域と世界各地を比較すると、東太平洋地域で2つの針葉樹林帯が連続するのと対照的であることを指摘した。
1 0 0 0 OA 小型風力発電施設がコウモリ類の活動量に与える影響:北海道東部の事例
- 著者
- 脇 翔吾 赤坂 卓美 安藤 駿汰
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.197, 2022-10-25 (Released:2023-01-01)
- 参考文献数
- 95
今日急速に普及している風力発電は、温室効果ガスの削減に大きく貢献する一方で、コウモリ類の事故問題が顕在化してきている。しかし、近年大型風車と同様に普及が進んでいる小型風車による影響は軽視されてきた。そこで本研究では、小型風車によるコウモリ類への影響を把握することを目的に、北海道根室振興局内に存在する小型風車を対象に、小型風車の存在がコウモリ類の活動量に与える影響を明らかにした。キタクビワコウモリとヤマコウモリ属 /ヒナコウモリ属の活動量は風車直近の方が対照区(風車から 100 m以上離れた場所)よりも高かった。また、ホオヒゲコウモリ属の活動量は区間で違いはなかった。本研究の結果は、小型風車では、これまで大型風車で死亡リスクが高いといわれてきた属(キタクビワコウモリとヤマコウモリ属 /ヒナコウモリ属)だけでなく、死亡リスクが低いとされてきた属(ホオヒゲコウモリ属)も少なからず影響が受ける可能性を示唆する。このことから、今まで軽視されてきた小型風車におけるコウモリ類の保全対策は急務であると言える。
1 0 0 0 OA クマは本当にアンブレラ種か? : 2.「細かいフィルター、粗いフィルター」アプローチ
- 著者
- 高槻 成紀
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.131-133, 2011-05-30 (Released:2018-01-01)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
I previously (Takatsuki, 2009) proposed the following question: Although bears are often regarded as umbrella species, is this actually true? So far, I have not been able to find scientific evidence in support of this, and I feel that conservation activities should be based on scientific approaches. Indeed, this opinion is in accordance with that of S. Boutin (2005) in his review of the ecological effects of carnivores in boreal forests of Nordic countries, in which he discussed several effects of bears on ungulates, hares, rodents, and vegetation through cascade effects. Boutin emphasized that a "fine-filter" conservation approach that focuses on particularly charismatic carnivores often overlooks ecological processes and that carnivore-oriented conservation requires large refuges. However, actual refuges are often too small for such large carnivore species, particularly in Europe. Such approaches that focus only on carnivores as umbrella species risk the loss of endangered species or organisms requiring particular ecological processes. For biodiversity conservation, a "coarse-filter" approach that focuses on ecological processes such as wild fires, logging, and succession is more important and effective. Given that the social conditions of Japan in terms of biological conservation are often more similar to those of Europe than of North America, a "coarse-filter" approach may be more appropriate for bear conservation in Japan.
1 0 0 0 OA 知床国立公園の森林再生地における林冠構造の評価:適応的管理の視点から
- 著者
- 鈴木 紅葉 小林 勇太 高木 健太郎 早柏 慎太郎 草野 雄二 松林 良太 森 章
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- pp.2118, (Released:2022-10-25)
- 参考文献数
- 48
森林の再生は、気候変動や生物多様性の損失などの社会課題に対する有効な手段の一つである。北海道知床国立公園内の森林再生地では、本来の潜在植生である針広混交林の再生を目指した森林再生活動が実施されている。ここでは、科学的知見をもとに合意形成し、管理手法を実践しながら改善する適応的管理のアプローチが取り入れられている。本稿では、この森林再生活動の成果を航空機レーザ測量およびドローン写真測量を用いた林冠構造解析によって評価した。具体的には、植栽地における樹冠高と構造的多様性、代表的な森林タイプにおける 2004年から 2020年までの 16年間の森林成長量を算出した。その結果、在来種の植栽地では他の森林タイプよりも顕著な森林成長が見られたものの、構造的多様性の回復は遅いことがわかった。このことから、活動開始から約 40年が経過しても未だ構造的多様性の回復には至っていないことが示唆された。当地での適応的管理に基づく森林再生活動の内容を紹介し、森林再生のあり方を議論することで、他地域における参考情報を提供したい。
- 著者
- 名取 俊樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.183-189, 2008-11-30 (Released:2016-09-17)
- 参考文献数
- 18
氷河期からの遺存種であるキタダケソウ(Callianthemum hondoense Nakai et Hara)は、北岳(南アルプス北部、山梨県)の南東斜面のみに生育する固有種であり、将来、地球温暖化の影響などにより、その存続が危惧されている。そこで、公表されている気象資料やキタダケソウに関する資料の整理、キタダケソウの満開日や生育場所の土壌pH、消雪時期の野外調査を行った.そして、富士山頂での年平均気温が20世紀後半から上昇していること、また、キタダケソウの満開日の経年変化や、キタダケソウの生育場所の土壌pHと消雪時期の特性を明らかにした。それらの結果をもとに、キタダケソウに及ぼす地球温暖化の影響について考えた。
1 0 0 0 OA トビムシと微生物のリンク(<特集2>土壌生態学の新展開)
- 著者
- 金田 哲
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.217-225, 2004-12-25 (Released:2017-05-26)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 4