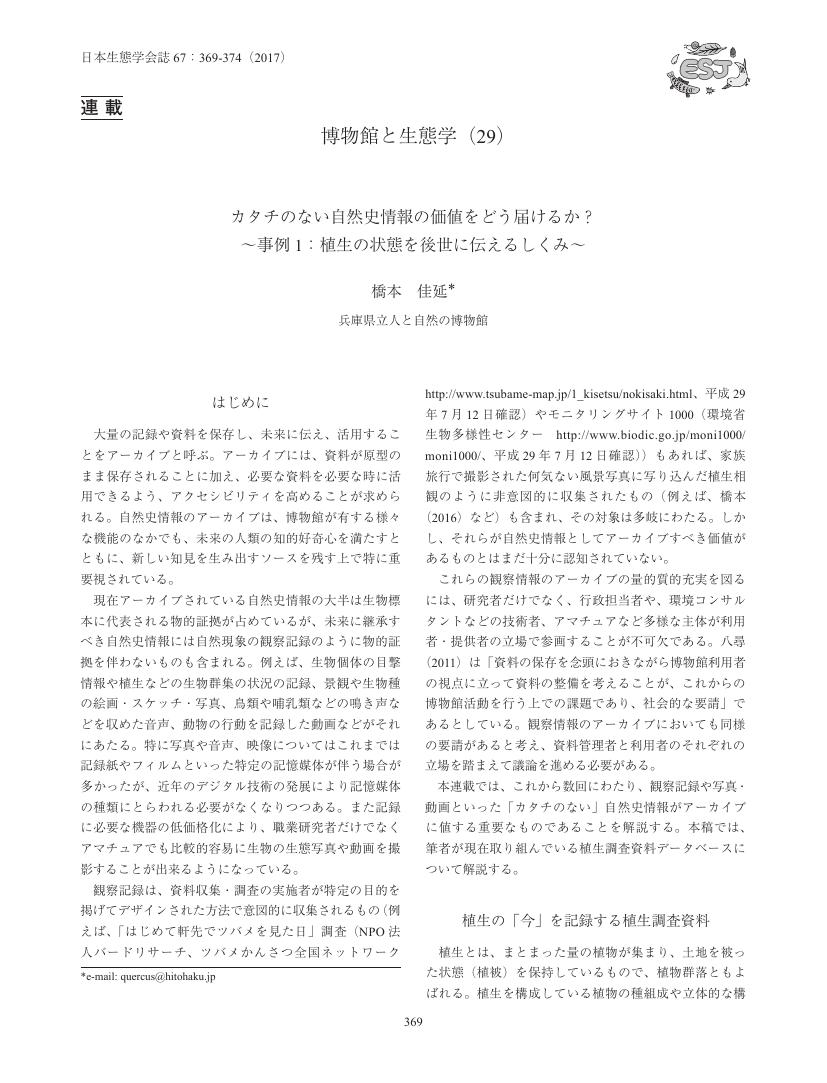2 0 0 0 OA カタチのない自然史情報の価値をどう届けるか?
- 著者
- 橋本 佳延
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.369-374, 2017 (Released:2017-12-05)
- 参考文献数
- 10
2 0 0 0 OA 「研究データ公開」における人材と体制の問題 : 研究図書館の可能性(学術情報)
- 著者
- 真板 英一
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.81-86, 2014-03-30 (Released:2017-05-19)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 OA 日本におけるスキー場開発の進展と農山村地域の変容 (<特集>スキー場開発と自然保護)
- 著者
- 呉羽 正昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.269-275, 1999-12-25 (Released:2017-05-25)
- 参考文献数
- 25
2 0 0 0 OA 日本における生物多様性情報概況 ―生物多様性情報概況GBIO の和訳公開と国内動向―
- 著者
- 大澤 剛士 細矢 剛 伊藤 元己 神保 宇嗣 山野 博哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.215-220, 2016 (Released:2016-06-01)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
要旨: 2013 年、生物多様性情報学の世界的な現状と課題をまとめた地球規模生物多様性情報概況(Global Biodiversity Informatics Outlook: GBIO)が公開された。これは地球規模生物多様性概況(Global Biodiversity Outlook: GBO)の生物多様性情報分野版に相当するもので、生物多様性情報学という分野の趨勢を確認し、今後を見据える重要文書である。筆者らGBIF 日本ノードJBIF では、本文書を意訳し、オープンデータライセンス(CC-BY)で公開した。さらに文書の公開に併せて公開ワークショップを実施し、国際的な状況と日本の現況について議論を行った。その結果、生物多様性情報の分野において、国際的な課題と日本の課題の間にはギャップがあることが見えてきた。本稿は、GBIO 翻訳版の公開に併せ、2014 年12 月15 日に開催された第9 回GBIF ワークショップ「21 世紀の生物多様性研究ワークショップ(2014年)「日本と世界の生物多様性情報学の現状と展望」」における議論をもとに、日本における生物多様性情報の現状と課題について論じる。
- 著者
- 名取 俊樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.183-189, 2008
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
氷河期からの遺存種であるキタダケソウ(Callianthemum hondoense Nakai et Hara)は、北岳(南アルプス北部、山梨県)の南東斜面のみに生育する固有種であり、将来、地球温暖化の影響などにより、その存続が危惧されている。そこで、公表されている気象資料やキタダケソウに関する資料の整理、キタダケソウの満開日や生育場所の土壌pH、消雪時期の野外調査を行った.そして、富士山頂での年平均気温が20世紀後半から上昇していること、また、キタダケソウの満開日の経年変化や、キタダケソウの生育場所の土壌pHと消雪時期の特性を明らかにした。それらの結果をもとに、キタダケソウに及ぼす地球温暖化の影響について考えた。
- 著者
- 馬場 幸大 西尾 正輝 山崎 裕治
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.61-66, 2016 (Released:2016-10-03)
- 参考文献数
- 34
要旨 国指定天然記念物であるイタセンパラについて小規模水槽飼育を実施し、飼育条件の違いが成長や生残に与える影響を調査した。実験条件として、1日あたりの給餌の頻度(1回、3回)、個体の密度(5匹、20匹)そして日当たり(日なた、日陰)の3つの項目に注目した。これらの条件を組み合わせた8通りの実験群を3組ずつ用意し、1か月ごとに生残率を算出し、標準体長および体重を計測した。さらに、本種の繁殖期とされる9月および10月における計測については、性成熟の判定を行った。飼育実験の結果、豊富な餌量の供給および低密度における飼育によって、良好な成長が期待できることが示唆された。一方で、残餌や高水温に起因する水質悪化が、摂餌活性および生残率の低下をもたらす可能性が示された。また、すべての実験群において性成熟する個体が出現した。これらのことから、保護池のような広大な土地が確保できない場所においても、効果的な条件を整えた小規模水槽において本種の飼育は可能であり、有効な保全方策の1つとなることが明らかとなった。
- 著者
- 冨士田 裕子 加川 敬祐 東 隆行
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.77-92, 2016 (Released:2016-10-03)
- 参考文献数
- 38
要旨 環境省により準絶滅危惧(NT)に指定されているチョウジソウの保全のために、日本におけるチョウジソウの産地記録を標本調査と文献調査等によって整理し、現地調査を行い、現存個体群についてはシュート数と生育環境の調査を行った。チョウジソウは北海道から宮崎県に至る38都道府県の180産地で記録があり、そのうち61産地での生育が確認されたが、7都府県で絶滅、7府県で現状不明で生育が確認できなかった。残存生育地は、各県で1?数か所であることが多く、広い分布域をもちながら、産地は散在し不連続であった。生育が確認された立地は、林床、湖岸林縁、湖岸草地、草原と多様であった。多くの場所が湖岸や河川敷、谷斜面脚部など、元々氾濫や水位変動の影響を受ける場所であった。これらの立地のうち、現在は堤内地となっている場所では、攪乱が起こりにくいと考えられた。
- 著者
- 武田 博清
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.211-222, 1994
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 26
2 0 0 0 日本におけるハシブトガラスとハシボソガラスの棲み分け
- 著者
- 樋口 広芳
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.353-358, 1979
- 被引用文献数
- 4
HIGUCHI, Hiroyoshi (Lab. For. Zool., Fac. Agr., Univ. Tokyo). 1979. Habitat segregation between the Jungle and Carrion Crows, Corvus macrorhynchos and C. corone, in Japan. Jap. J. Ecol., 29 : 353-358. Corvus macrorhynchos and C. corone use a wide variety of natural resources for food and habitat, and are typical ecological generalists. Because their food is already well known, the habitats of these generalists were investigated. A clear habitat segregation was recognized in this study, which was rather different from the general habitat description appearing in many bird books in Japan. The differences of habitats shown in this study were supported by the results of the examination of stomach contents. By comparison with the situations on the Asian continent, it was suggested that in Japan the habitat of C. macrorhynchos is constricted by sympatry with C. corone.
- 著者
- 川北 篤
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.321-327, 2012
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 1
イチジクとイチジクコバチの間に見られ絶対送粉共生や、アリとアリ植物の共生のように、植物と昆虫の間には、互いの存在なしには存続し得ないほど強く依存し合った共生系が多く存在する。これらの生物の地理的分布は、共生相手の存在に強く依存すると考えられ、実際、共生相手の移動分散能力が限られるために共生系自体の分布が制限されていると考えられる例がいくつも存在する。しかし、イチジクとイチジクコバチ、ならびにコミカンソウ科とハナホソガ属の絶対送粉共生は、島嶼域を含む世界各地の熱帯域に幅広い分布をもつ。さまざまな共生系の間で分布に大きな違いが生まれた背景には、共生系の成立年代や、それぞれの共生者の移動分散能力が関わっていると考えられるが、これらの要因がどのように共生系ごとの分布の違いを生み出したのかについてはほとんど研究されていない。コミカンソウ科植物(以下、コミカンソウ)は世界中に約1200種が存在し、そのうち約600種がそれぞれに特異的なホソガ科ハナホソガ属のガ(以下、ハナホソガ)によって送粉されている。ハナホソガは受粉済みの雌花に産卵し、孵化した幼虫が種子を食べて成熟するため、両者にとって互いの存在は不可欠である。分岐年代推定の結果から、絶対送粉共生は約2500万年前に起源したと考えられるが、この年代は白亜紀後期のゴンドワナ大陸の分裂や、熱帯林が極地方まで存在した暁新世〜始新世の温暖期から大幅に遅れており、陸伝いの分散で現在の世界的分布を説明することは困難である。また、マダガスカル、ニューカレドニア、太平洋諸島など、世界各地の島嶼域にもコミカンソウとハナホソガの共生が見られることから、両者が繰り返し海を渡ったことは確実である。分子系統解析の結果、コミカンソウとハナホソガは、それぞれ独立に海を渡り、到達した先で新たに共生関係を結んだ場合がほとんどであることが分かった。コミカンソウ、ハナホソガそれぞれが単独で海を渡ることができることは、共生を獲得していないコミカンソウ科植物やホソガ科ガ類が、世界各地の海洋島に到達していることからも分かる。コミカンソウとハナホソガの共生が現在のような分布を成し遂げた背景には、両者が1000kmを超える長距離を分散でき、かつ本来の共生相手ではない種とも新たに共生関係を築くことができたことが重要であったと考えられる。生物地理学に「共生系」という視点を取り入れることで、島の生物の由来を新しい視点で捉えられるかもしれない。
2 0 0 0 日本生態学会60周年記念座談会
- 著者
- 奥富 清 黒岩 澄雄 小野 勇一 川那部 浩哉 只木 良也 松本 忠夫 松田 裕之
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.157-177, 2013
- 著者
- 小泉 逸郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.265-269, 2007
本稿は私がポスドク中に滞在した北欧フィンランドで感じた日本とフィンランドの研究スタイルの違いについて、文化的側面から考察します。海外の研究において役立つ実践的な話は、えころじすと@世界のバックナンバーでしっかりと紹介されているので、本稿では趣を変えてみました。これまでの寄稿では日本と海外の研究体制の違いが紹介されてきましたが、重要なのはこういった違いが生み出される文化的・歴史的背景を理解し、今後の日本の方向性を考えることだと思います。
- 著者
- 橋口 大介 山岸 哲
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.161-170, 1981
In winter, brown dippers are mainly solitary and exclusive in relationship with adjacent conspecific individuals. They drive other individuals out of their surrounding spaces along stream by threat (warning call, confronting) or aggressive behavior (chasing flight). The area along the stream, where a dipper can find others approaching is limited, and this area is defended as a territory. Some individuals are observed within narrow ranges (Sedentary type), and they held stable territorial ranges. On the other hand, others (Nomadic type) live within more extensive ranges, and change their territorial ranges day by day. Roosting individuals in upstream areas must be nomadic ones and they come downstream for feeding during the daytime.
- 著者
- 和田 直也
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.205-212, 2008
- 参考文献数
- 51
北緯35°から北緯80°までの広い範囲に分布しているチョウノスケソウ(Dryas octopetala sensu lato)について、中緯度高山の立山個体群と極地ツンドラのニーオルスン個体群を比較しながら、生育環境、葉形質と花特性の変異や環境の変化に対する応答、集団内の遺伝的多様性について紹介し、諸変異の要因について論じた。夏季の積算温度は、立山の方がニーオルスンに比べ3.1倍高かったが、日射量はほぼ同じであった。但し、ニーオルスンにおける日射量は初夏に高く、夏至以降急激に減少していた。このような生育環境の違いに対応して葉形質に違いがみられ、立山を含む中緯度高山帯におけるチョウノスケソウの葉は、ニーオルスンを含む寒帯や亜寒帯の集団に比べてLMA (leaf mass per area)が小さく窒素濃度が高かった.また、雌蕊への投資比(雌蕊重量/雄蕊と雌蕊の重量)は花重量との間に正の相関を示したが、その変化率は立山個体群の方が低く、ニーオルスン個体群に比べて集団内における性表現の変異幅が小さい傾向にあった。さらに、立山個体群における遺伝的多様性は、これまで報告されている北極圏の個体群と比較して低かった。最後に、気候変動に対する本種の応答反応を予測する上で、いくつかの課題を指摘した。
- 著者
- 金尾 滋史
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.143-146, 2008
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 4
- 著者
- 清水 健太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.432-437, 2007
- 著者
- 片山 昇
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.324-333, 2007
相利共生とは、相互に関係する生物種が互いに相手から利益を受ける関係であり、あらゆる生態系にみられる。しかし、相利共生は状況に応じて変化し、時として解消される。相利共生は多様な生物種を生み出してきた大きな要因であるため、相利共生の動態を解明することは生態学や進化学の重要な課題となってきた。アリとアブラムシの関係は、アブラムシが甘露を提供するかわりに、アリがアブラムシの天敵を排除するという、良く知られた相利共生の一つである。しかし、アリ-アブラムシの関係は生態的あるいは進化的に変化しやすく、相利から片利、さらには敵対にいたるまで多様な形態が存在する。このようなアリ-アブラムシ系における関係の変異の創出や相利共生の維持機構について、これまでの研究ではアブラムシがアリに随伴されることに対するコストと利益を考慮した最適化理論が用いられてきたが、その範疇に収まらない例が多い。一方で、(1)アブラムシの内部共生細菌は宿主の形質を変化させる、(2)アリは局所的な昆虫の群集構造を決める、ということが明らかにされてきた。そこで本稿では、アリ-アブラムシ系を複数の生物が関わる相互作用として捉え直し、相利共生の動態について議論する。特に、(1)アリ-アブラムシ-内部共生細菌による複合共生系の存在と、(2)アリ-アブラムシの相利共生とアブラムシ天敵の群集動態とのフィードバックについて仮説を提唱する。
- 著者
- 佐々木 顕 東樹 宏和 井磧 直行
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.174-182, 2007
- 被引用文献数
- 1
日本のヤブツバキCamellia japonicaの種特異的な種子食害者であるツバキシギゾウムシCurculio camelliaeの雌成虫は、頭部の先に伸びた極端に長い口吻を用いてツバキの果実を穿孔し、果実内部の種子に産卵を行う。このゾウムシ雌成虫の攻撃に対し、ツバキ側も極端に厚い果皮という防衛機構を発達させている。日本の高緯度地方ではヤブツバキの果皮は比較的薄く、ツバキシギゾウムシの口吻も比較的短いが、低緯度地方では果皮厚と口吻長の両者が増大するという地理的なクラインが見られ、気候条件に応じて両者の軍拡共進化が異なる平衡状態に達したと考えられる。日本15集団の調査により口吻長と果皮厚には直線関係が見られ、また、両形質が増大した集団ほどゾウムシの穿孔確率が低いツバキ優位の状態にあることが東樹と曽田の研究により知られている。ここではツバキとゾウムシの個体群動態に、口吻長と果皮厚という量的形質の共進化動態を結合したモデルにより、共進化的に安定な平衡状態における口吻長と果皮厚との関係、穿孔成功確率、それらのツバキ生産力パラメータや果皮厚と口吻長にかかるコストのパラメータとの関係を探った。理論の解析により、(1)ツバキ果皮厚と、ゾウムシの進化的な安定な口吻長との間には、口吻長にかかるコストが線形であるときには直線関係があること、(2)コストが非線形であるときにも両者には近似的な直線関係があること、(3)南方の集団ほどツバキの生産力が高いとすると、緯度が低下するほど果皮厚と口吻長がより増大した状態で進化的な安定平衡に達すること、(4)ゾウムシの口吻長にかかるコストが非線形である場合、ゾウムシの平均口吻長が長い集団ほどゾウムシによる穿孔成功率が低くなることを見いだした。これは東樹と曽田が日本のヤブツバキとツバキシギゾウムシとの間に見いだした逆説的関係であり、ツバキシギゾウムシ口吻長には非線形コストがかかると示唆された。平均穿孔失敗率と口吻長との間に期待されるベキ乗則の指数から、ゾウムシの死亡率はその口吻長の2.6乗に比例して増加すると推定された。
1 0 0 0 OA 白山におけるクロユリ集団の動態 (<特集>中部山岳地域の高山植生と地球温暖化)
- 著者
- 畑中 康郎 野上 達也 木下 栄一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.213-218, 2008-11-30 (Released:2016-09-17)
- 参考文献数
- 19
白山の標高2,450mのMizuyajiri調査地に永久方形区が設置され、クロユリの調査が1992年より実施された。その結果、次の事が明らかになった。1、クロユリは多くの種子をつける。2、実生はまれに出現するが、通常、実生の数は非常に少ない。3、多くの鱗茎葉により栄養繁殖が行われる。よって、白山のクロユリ集団では、集団の維持は主に栄養繁殖によって行われている。しかし、この結果は集団維持に対する実生の貢献の可能性を完全に否定するものではない。調査期間中、比較的まとまった数の実生の出現が1回起きたということは、条件が整えばクロユリ種子が発芽して集団の維持に貢献すること、の可能性を示唆する。いずれにしても、10年、20年という時間間隔のなかで一度起こる事象を検証するためには、10年程度の調査期間はあまりに短すぎる。また、12年間にわたる調査期間中に有茎個体の個体数、集団構造は大きく変動したことは、白山のクロユリ集団が現在も刻々変化していることを示している。温暖化などによる地球環境の変化が高山帯の植物や植生にどのような影響を与えるかは今のところ定かではないし、その変化を予想することは難しい。したがって、白山のクロユリ集団の変化と気温等の変化の関係を明らかにすることは極めて重要であり、定点での継続観察が必要である。
1 0 0 0 OA 奈良県立里, 川股両鉱山及び和歌山県飯盛鉱山の廃水の河川生物に及ぼす影響
- 著者
- 御勢 久右衛門
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.38-45, 1960-02-01 (Released:2017-04-08)
- 被引用文献数
- 2
I studied the effluents of three copper sulphide mines, Tateri Mine and Kawamata Mine in Nara Prefecture and of the Imori Mine in Wakayama Prefecture, with regard to their effect on stream organisms. The water insects were collected quantitatively at several stations of the rivers which receive the mine-water(Figs. 6,7,8,9). The effect of the effuents is very distinct. The water insects decrease in species number as well as in individual number with the distance from the source.