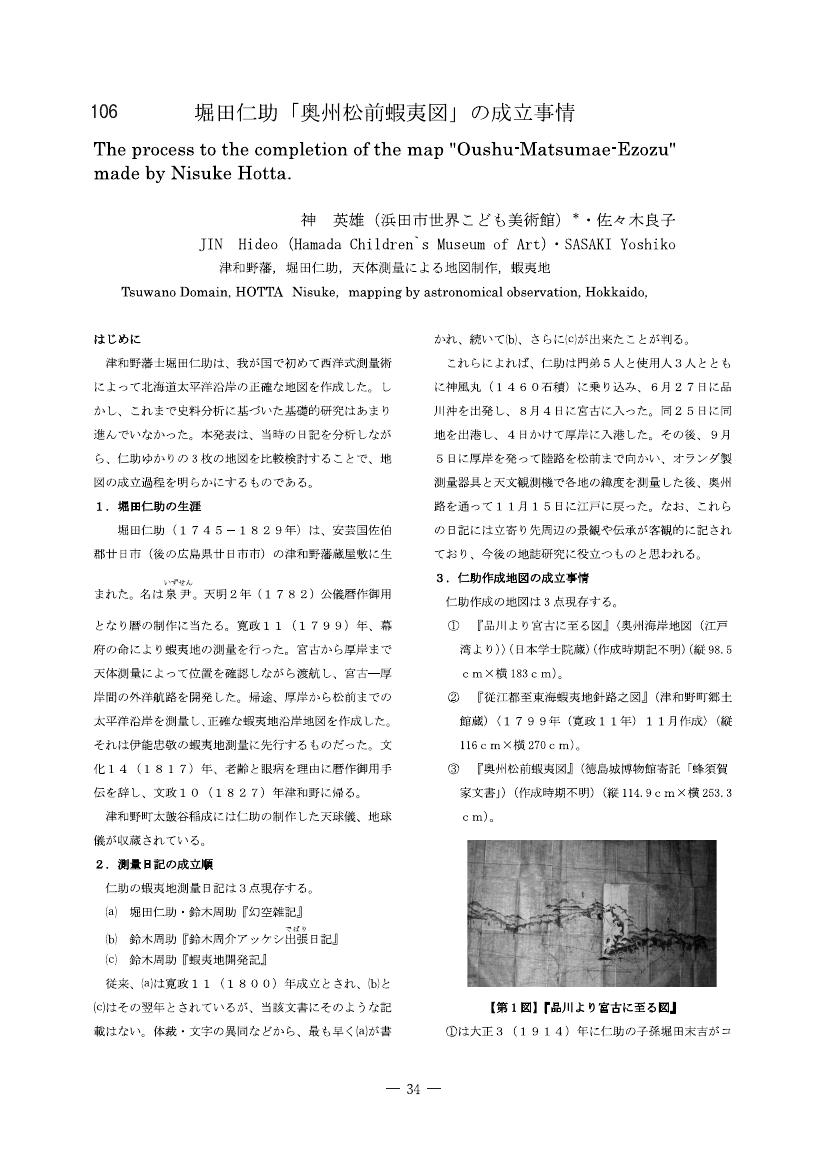3 0 0 0 OA Twitter 投稿データにみられる地域方言の分析
- 著者
- 峪口 有香子 桐村 喬
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2014年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.112-113, 2014 (Released:2020-06-13)
3 0 0 0 OA 記念碑の建立と比喩
- 著者
- 大平 晃久
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2011年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.20, 2011 (Released:2012-03-23)
文化地理 岐阜県内の文学碑の事例を中心に、記念碑と場所の関係を比喩として読み解き、記憶-場所論に新たな視点を提示する。
3 0 0 0 OA 「見せ物の場所」から「生きられる空間」へ
- 著者
- 李 小妹
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2008年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.501, 2008 (Released:2008-12-25)
本研究は,中国・シンセンにある「錦繍中華」,「中国民俗文化村」と「世界之窓」という三つのテーマパークにおいて,新しい都市空間がいかなる過程で作りあげられているのかについて考察する。これらのテーマパークは,中国国内で初めて作られた同類の観光施設として,中国の文化観光開発事業をリードし,経済開発の産物と見本であると同時に政治文化の発信地でもある。テーマパークがもつこのような経済的,政治文化的特性は,シンセンの都市空間のそれを反映している。そのうえ,市場経済化とグローバル化の中で成長したシンセンは,グローバル時代における中国都市の都市空間の変容と,都市空間を生きる人々とのかかわりのダイナミックな変容実態を,他のどの都市よりも先見的に,よりよく反映している。本研究において,これらのテーマパークの建設経緯,展示内容および展示手法について検討し,「見せ物の場所」と「生きられる空間」といった二つの視座から,開発側である中国政府と華僑資本家および「ユーザー」である観光客や少数民族の若い労働者による「空間の生産」がいかなるものかを明らかにした。 まず,「見せ物の場所」としてこれらのテーマパークは,中国および世界の歴史文化といった大きなテーマの下で,「社会主義的国民国家」と「市場経済の発展ぶりおよび生活の向上」を見せ,経済発展を正当化する手段であると同時に,愛国主義教育といったような政治宣伝の場でもある。 また,アンリ・ルフェーブルの「表象の空間」とエドワード・ソジャの「第三空間」の概念を用いて,これらのテーマパークが「見せ物の場所」であると同時に「生きられる空間」でもあると確認した。具体的に三つの場面を挙げながら論じる。場面_丸1_:「錦繍中華」において,観光客であるシンセン住民がテーマパークを自らの所有物でもあるように他の町から来た観光客に紹介する時の,彼らの表情や振る舞い型や使った言葉と話す口調から,彼らがこの空間に付与された意味を自分たちの住民としてのシンセン・アイデンティティとも言うべき主体性の発揮が見られる;場面_丸2_:「中国民俗文化村」に百人以上の少数民族の若者が働いている。彼らはテーマパークのすぐ近くにある社員寮に住み,テーマパークを中心に生活している。テーマパークの中での活動と言えば,観客にパフォーマンスしたり民族文化を紹介したりするような労働だけでなく,売店やレストランで自ら消費者になって見せる身から見る身に変身するのである。こうした「生産」と「消費」の間に移行する身体は,見せ物の場所を生きられる空間へと変えている。場面_丸3_:「世界之窓」で80歳の闇ガイドに出会った。彼は「75歳以上の老人が入場無料」という規則で毎日テーマパークに来ている。目的は観光ではなく,観光客にテーマパークを案内することで案内費を稼いでいるのだ。彼のようなテーマパークに雇われていないガイドをここにおいて「闇ガイド」と名付け,彼らによって「世界之窓」という空間が一種の抵抗空間として生産されている。つまり,シンセンのテーマパークは,観光客や少数民族の若者や闇ガイドのおじいさんのような住民や「ユーザー」の空間であって,彼らの諸活動によって抵抗の空間,または「生きられる空間」に練り上げられている。 国民国家のアイデンティティと民族文化は,常に変化しており,確立される必要性に迫られている。従って,それらが空間と時間の枠組みのなかで再生産され,再確認されるプロセスは,わたしたちの周りに絶えず展開されている。万里の長城が5000年の中国歴史文化を象徴するように,シンセンは経済発展がもたらした現代性を象徴する。シンセンの都市空間は,いわばひとつのテーマパークのような存在であって,そのテーマというのが,「グローバル化」であり,中国の改革開放の成功(「社会主義体制」と「市場経済様式」との接合)である。中国が社会主義の政治体制と資本の自由化との間に,その矛盾と戦いながら自らの発展の道を探りつつあると同様に,中国の人びとは,矛盾に満ちた都市に放り出された身をもって,都市を自分たちの需要に合わせながら作り変えている。こうした表象され,実践され生きられる空間には経済発展に巻き込まれている社会的諸主体間の関係性が生き生きと作られ,また現されてもいる。わたしたちが今日及び近未来の中国の都市空間と中国社会を理解するのに,こうした関係性としての空間を第三空間的想像力で考察することはきわめて有意義であろう。
3 0 0 0 大都市圏郊外におけるアパート居住者の特性
- 著者
- 西山 弘泰 小泉 諒 川口 太郎
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.35-35, 2009
本発表では,1970年以降東京都心から25~30km圏に立地するアパートに着目し,その居住者の実態を明らかにすることを目的としている.本研究の対象地域は東京都心から25km,埼玉県南西部に位置する東武東上線鶴瀬駅半径1kmを範囲とした住宅地である(図2).当地域は埼玉県富士見市,三芳町の一部で,小規模な戸建住宅や共同住宅,商店などが混在している.都市計画法による用途地域は,第1種中高層住居専用地域(建蔽率60%,容積率200%)が主ある.東武東上線鶴瀬駅から池袋駅までの所要時間は約30分と比較的都心へのアクセスは良い.鶴瀬駅周辺の住宅地開発は,1957年の公団鶴瀬第一団地,1962年の公団鶴瀬第二団地の開発に端を発し,その後地元や東武東上線沿線の中小ディベロッパーを中心とした小規模な戸建住宅地開発,農家や地主のアパート建設が中心である.アパートの建設は1970年以降増加し,1980年代から1990年代前半にかけて増加が著しい.これは鶴瀬駅の南隣にあるみずほ台駅の土地区画整理事業が完了し,そこに地権者がアパートを建設したことや,農家や地主が地価の上昇によって不動産収入が必要になったこと,共同住宅建設に住宅金融公庫の融資を受けられるようになったことなどが要因と考えられる.2005年の国勢調査によると対象地域においてアパートに居住する世帯は3,266世帯である.本研究では2009年3月,対象地域に立地するアパート3,000戸にポスティングによるアンケート調査を実施し,135票(回収率4.5%)の郵送回答を得た.対象者の世帯の種類は,単身世帯が72世帯,夫婦のみの世帯17世帯,夫婦と子からなる世帯が26世帯,片親と子からなる世帯が13世帯,その他の世帯が7世であった.単身世帯が半数以上を占めているものの,世帯構成以外に,年齢,職業,学歴,出身地などは多様で一括りにすることは困難である.単身者は40歳未満が40世帯,40歳以上が32世帯で平均年齢41.8歳であった.住居の間取りは1Kや1DKで,一戸当たりの平均延べ床面積は27.0_m2_であった.また築年数は10~19年,駅から徒歩10分のアパートを4万円以上6万円未満で居住するというのが平均的である.単身者の仕事は,37人が正規の職に就いており,17人がアルバイト・パート,派遣・嘱託といった非正規労働に従事している.その他,学生が6人,無職・家事が12人であった.40歳未満の若年単身者の居住期間が約3年と短いのに対して,40歳以上の単身者は7年と永い.夫婦のみの世帯は,40歳未満の比較的若い層が17世帯中11世帯と多かった.住居の間取りは,2DKや2LDKで,一戸当たりの平均延べ床面積は46.5_m2_,家賃は6万円以上8万円未満が最も多かった.転居の意向をみてみると,40歳未満の世帯で転居予定の世帯が多かったのに対して,40歳以上の世帯で不明確な回答が多かった.夫婦と子からなる世帯も夫婦のみの世帯同様40歳未満の比較的若い世帯が大半を占めていて,第一子も小学校就学前が多くなっている.間取りや延べ床面積,家賃については,夫婦のみの世帯と類似している.40歳以下の世帯では転居志向が強く,転居先は近隣の戸建住宅を購入することを希望している.一方,夫が40歳以上の世帯では居住年数が平均12年と長くなっていて,転居意思が低いのが特徴である.最後に,片親と子からなる世帯では,1世帯を除いた12世帯が母子世帯であった.家賃は6万円以上8万円未満と6万円未満が同数であった.築年数をみてみると他のグループと比べ築年数が経過しているアパートに居住する世帯が多いのも特徴である.明確な転居意思を持った世帯は皆無であり,滞留傾向が強くなっている.以上のように,若年の単身者やファミリー世帯においては,転居意思や居住年などから従来のようにアパートが仮の住まいとして認識されていることがわかる.一方で,比較的年齢の高い層や片親世帯などはアパートに滞留する傾向がみられることが指摘できる.
3 0 0 0 OA 記念碑と場所の関係
- 著者
- 大平 晃久
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2009年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.59, 2009 (Released:2009-12-16)
人文地理学において記念碑を対象とした研究は隆盛をみているが、個別の記念碑研究ではなく、記念碑と場所の関係の一般化を指向する研究は少ない。本発表では,まず,既存のモニュメントを否定するアンチ・モニュメントの事例,とりわけベルリン・バイエルン地区の「追憶の場」を紹介し,そこにみられる記念碑と場所との関係を考える。その上で,バイエルン地区「追憶の場」の事例から,場所間の見立てという記念碑の働きに注目する。 アンチ・モニュメントとは,ドイツにおいてナチスの記憶と向き合う中で生まれた,従来の記念碑の概念を打ち崩そうとする作品群に与えられた名称である。ザールブリュッケンやカッセルの不可視の「記念碑」,ベルリン・ゾンネンアレのセンサーが感知したときのみ説明文が浮かび上がる「記念碑」、ホロコースト記念碑の計コンペで落選した、ブランデンブルク門を破壊してその破片をばらまくというプラン,ブランデンブルク門南の敷地にヨーロッパ各地の強制収容所跡地行きのバスが発着するバスターミナルを建設し,アウシュヴィッツなどの行き先を表示した真っ赤なバスが市内を毎日行き来すること自体を「記念碑」とするプラン,アウトバーンの一部区間を走行速度を落とさざるを得ない石畳にすることで「記念碑」とするプランなどが事例としてあげられる。 ベルリンの「バイエルン地区における追憶の場」はそうしたアンチ・モニュメントの系譜に位置づけられるプロジェクトである。戦前にアインシュタイン,アーレントなど中流以上のユダヤ系住民が数多く暮らしていたこの地区では,地域の歴史を掘り起こす住民運動が起こった。その結果,1993年に記念碑の設計コンペが実施され,シュティ, R.とシュノック, F.によるプランが1位となった。閑静な住宅地区であるここバイエルン地区では,あちこちの街灯に妙な標識が取り付けられている。全部で80枚のそれらの標識は,例えば片面がカラフルなパンのイラスト,もう片面には「ベルリンのユダヤ人の食料品購入は午後4時から5時のみに許可される。1940. 4. 7」というナチス時代のユダヤ人を迫害する法令の文章が記され、,標識の下に簡潔な記念碑としての説明が取り付けられている。商店の看板とみまがうようなポップなイラストと恐ろしい文言からなる標識群は,その形態からも,またそれらが日常の生活の場にあり生々しい過去と日々向かい合うように設けられている点からも,まさに既存の記念碑を否定するアンチ・モニュメントといえよう。 これらのアンチ・モニュメントにおける,場所と記念碑の関係を検討すると,まず,脱中心的であったり不可視であったりすることから,そもそも場所との位置的な対応を問うこと自体が無効である可能性がある。一方で,アンチ・モニュメントが決まったメッセージを伝えるのではなく,記念碑をめぐる実践が意味を作り出す点は場所的な特性として指摘できる。このようにアンチ・モニュメントは場所と記念碑の関係に新たな視点をもたらすものなのである。 バイエルン地区「追憶の場」については、個々の標識については第三帝国当時ではなく現在の景観とおおむね対応している点も特徴的である。過去におけるパン屋や病院など小スケールの事物を記念するというオンサイトの記念碑の文法に則りながら,通常の意味でオンサイトの記念碑ではない点は訪れる者を戸惑わせるものである。しかし,歴史地理的な探索ではなく,現代における実践を誘うものとしてこの記念碑(標識群)は捉えられるべきであろう。現代のスーパーマーケットの前の標識をみてナチス期の商店を想起するという実践は,場所間の見立てであり、バイエルン地区の標識は,そうした見立てを誘うものとして捉えられることを指摘したい。そして,管見の限り,アンチ・モニュメントはいずれも場所間の見立てである一方,大半の記念碑はそうではない。例外は記念碑としては周辺的である文学碑の一部と,聖地など宗教関係の記念碑に限定されると考えられる。 ここで垣間みた場所間の見立ては記念碑の対場所作用の一例に過ぎない。そうしたレトリカルな分析の可能性,また広義の記念碑=「記憶の場」まで含めた考察の必要性を試論的に指摘しておきたい。
3 0 0 0 アメリカにおけるエアリア・スタデイによる日本研究と日本の近代化
- 著者
- Bedford Yukiko N.
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.6, pp.504-517, 1980
3 0 0 0 場所の再概念化
- 著者
- 成瀬 厚
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.19-19, 2011
1970年代の人文主義地理学によってキーワードとされた「場所place」は概念そのものの検討も含んでいたが,その没歴史的で,本質主義的な立場などが1980年代に各方面から批判された。1990年代にはplaceを書名に冠した著書や論文集が多数出版されたが,そこでは場所概念そのものの検討はさほどなされなかったといえる。本報告では議論を拡散させないためにも,検討するテクストをプラトンの『ティマイオス』および,そのなかのコーラ=場概念を検討したデリダの『コーラ』を,そしてアリストテレスの『自然学』および,そのなかのトポス=場所概念を検討したイリガライの「場,間隔」に限定する。プラトン『ティマイオス』におけるコーラとは,基本的な二元論に対するオルタナティヴな第三項だといえる。コーラは岩波書店全集では「場」と翻訳されるものの,地理的なものとして登場するわけではない。『ティマイオス』は対話篇であり,「ティマイオス」とは宇宙論を展開する登場人物の名前である。ティマイオスの話は宇宙創世から始まるが,基本的な種別として「存在」と「生成」とを挙げる。「存在」とは常に同一であるもので,理性(知性)や言論によって把握される。これは後に「形相」とも呼び変えられる。「生成」とは常に変化し,あるという状態のないものであり,思わくや感覚によって捉えられる。創世によって生成した万物は物体性を具えたもので,後者に属する。そのどちらでもない「第三の種族」として登場するのが「場=コーラ」である。コーラとは「およそ生成する限りのすべてのものにその座を提供し,しかし自分自身は,一種のまがいの推理とでもいうようなものによって,感覚には頼らずに捉えられるもの」とされる。その後の真実の把握を巡る議論は難解だが,ここにコーラ概念の含意が隠れているのかもしれない。いや,そう考えてしまう私たちの真理感覚を問い直してくれるのかもしれない。デリダはコーラ概念を,その捉えがたさが故に検討するのだ。「解釈学的諸類型がコーラに情報=形をもたらすことができるのは,つまり,形を与えることができるのは,ただ,接近不可能で,平然としており,「不定形」で,つねに手つかず=処女的,それも擬人論的に根源的に反抗するような諸女性をそなえているそれ[彼女=コーラ]が,それらの類型を受け取り,それらに場を与えるようにみえるかぎりにおいてのみである」。『ティマイオス』では,51項にも3つの種族に関する記述があり,それらは母と父と子になぞらえられる。そして,コーラにあたるものが母であり,受容者であり,それは次のイリガライのアリストテレス解釈にもつながる論点である。このコーラの女性的存在はデリダの論点でもあり,またこの捉えがたきものを「コーラ」と名付けたこの語自体の固有名詞性を論じていくことになる。アリストテレスのトポス概念は,『自然学』の第四巻の冒頭〔三 場所について〕で5章にわたって論じられる。トポスは,物体の運動についての重要概念として比較的理解しやすいものとして,岩波書店全集では「場所」と翻訳されて登場する。アリストテレスにおける運動とは物質の性質の変化も含むため,運動の一種としての移動は場所の変化ということになる。ティマイオスはコーラ概念を宙づりにしたまま,宇宙論をその後も続けたが,アリストテレスは「トポス=場所」を物体の主要な性質である形相でも質料でもないものとして,その捉えがたさを認めながらも論理的に確定しようとする。トポスには多くの場合「容器」という代替語で説明されるが,そこに包含される事物と不可分でありながらその事物の一部でも性質でもない。イリガライはこの容器としてのトポスの性質を,プラトンとも関連付けながら,女性としての容器,女性器と子宮になぞらえる。内に含まれる事物の伸縮に従って拡張する容器として,男性器の伸縮と往復運動,そして胎児の成長に伴う子宮の拡張,出産に伴う収縮。まさに,男性と女性の性関係と母と子の関係を論じる。この要旨では,デリダとイリガライの議論のさわりしか説明できていないし,これらの議論をいかに地理学的場所概念へと展開していくかについては,当日報告することとしたい。
3 0 0 0 東京の都市空間と地域社会の変容:カステルとハーヴェイの理論から
- 著者
- 西山 志保
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.64-75, 1997
- 被引用文献数
- 1
This paper attempts to review the theoretical framework of the urban restructuring process proposed by M. Castells and D. Harvey, and to examine the effectiveness of their western theories through field survey of restructuring urban space and local communities in Tokyo.M. Castells and D. Harvey have explained the restructuring process of urban spaces focusing on the mechanism of capital accumulation, but their analytical concepts are different. Castells uses the concept of the Dual City. This concept means that residential segregation and segmentation of spaces do exist among classes according to whether they heve access to a high level of education and culture or not. Harvey uses the concept of Flexible Accumulation, which means almost all new societal systems have the aim of capital accumulation. Castells puts stress on a change of the social structure in the global cities, while on the other hand Harvey examines the urban space, focusing on the relationship between global cities and local communities.For research purposes, I picked two case study areas in downtown Tokyo. One is Misaki-cho where many residents own their own land and buildings, and the other is Kanda-Tsukasa-cho where almost all residents live on leased land. These two local communities are located near the heart of Tokyo, and they contain many small scale businesses. But the pattern of landownership and community history are completely different.The conclusions are as follows:1) The residential space in Tokyo has became more segregated and segmented by the occupation and income of the residents. So the concept of the Dual City is applicable to Tokyo to some extent. Also rapid increase of offices and big changes of land use in Tokyo have been a part of the urban process of Flexible Accumulation at the global level.During the 1980's, Tokyo was affected by the global changes in more or less the same way as New York and London.2) At the local community level, landowners in Misaki-cho rebuilt their own buildings before the bubble economy, so they could cope with the structural economic changes during the 1980's individually. On the contrary, in Kanda-Tsukasa-cho, rapid increase of land prices did force changes in the residential land use to offices. So, we may conclude that the global changes did not directly affect local changes, but the history, socio-economic characteristics and social relationship of the local communities was an influence upon the restructuring and transformation process of urban space.In the next stage of my research, I will try to make it clear how the local community responds to the huge global economic pressure and resists capital accumulation. This is none other than building a new theoretical framework to bridge the macro-global changes and micro-local changes of urban spaces.
- 著者
- 豊田 哲也
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, pp.312-312, 2007
<B>1.問題の所在</B><BR> 「都市と地方の格差問題」は今日わが国における最も重要な政策テーマとなったが、その事実認識について論争はつきない。現象としての所得格差には2つの意味がある。一つは「都市-地方」という空間的な関係であり、もう一つは「富裕層-貧困層」という階層的な関係である。ところが多くの場合、前者の分析は1人あたり県民所得など平均値の差のみに注目し、格差の階層的構造についての視点を欠く。一方、後者の分析は所得再分配調査など全国一律のデータをもとにおこなわれ、地域間の比較については関心がない。しかし、地域と地域の間に格差があるのと同様、どの地域もその内部に階層的な格差を抱えていることは自明の事実である。例えば、高級マンションとホームレスが併存する大都市と、過疎化・高齢化が進む中山間地域を含む地方とでは、いずれの地域で格差がより大きいであろうか。また、地域間・地域内の格差はどの程度拡大しているのか。本研究では、世帯所得の地域格差を空間的・階層的かつ時系列的に分析し、こうした格差を生み出す要因として人口や雇用など地域の社会経済条件との関連を検討することを目的とする。<BR><B>2.所得の地域格差</B><BR> 使用するデータは「住宅・土地統計調査(都道府県編)」である。「世帯の年間収入」の階級別世帯分布から、線形補完法でメジアン(中位値)、第1五分位値(下位値)、第4五分位値(上位値)を推定するとともに、ジニ係数を求める。なお、実質所得は世帯人員の規模の影響を受けるため、SQRT等価尺度を用いて調整を加えた。1998年から2003年にかけて、等価年間収入の中位値は全国平均で286万円から267万円に約9%低下している。都道県別に見ると、神奈川、東京、千葉など首都圏と愛知で高く、沖縄、鹿児島、宮崎、高知など九州・四国と青森など東北で低い(図1)。<BR> 次に、年間収入の中位値を横軸に、ジニ係数を縦軸にとって各都道府県の散布図を描く(図2)。おおむね年間収入が高いほどジニ係数は低いという逆相関を示す。東京は両者とも高いのに対し、大阪や京都では所得水準が中程度でありながらジニ係数は高い。地方でジニ係数が目立って低いのは富山、新潟、長野、山形など北陸・信越地方で、高いのは徳島・高知など南四国と和歌山である。5年間の変化を見ると、縦軸方向で示される地域内格差はやや拡大しているが(ジニ係数の平均値:0.294→0.299)、横軸方向のばらつきで示される地域間格差は、予想に反してむしろ縮小していることがわかる(中位値の変動係数:0.126→0.109)。平均対数偏差(MLD)を用いた要因分解によっても、この結果は支持される。<BR><B>3.地域格差の要因</B><BR> 空間的な地域間格差と階層的な地域内格差をもたらす要因を探るため、人口や雇用などの地域の変数と所得およびジニ係数との間で相関係数を算出した(表1)。人口構成に関しては、生産年齢人口が多く老年人口が少ない地域ほど所得水準は高い。一方、女性就業率の高さは地域内格差の縮小に貢献している。また、労働力需要が弱い高失業率地域では、所得の下位値が低下しジニ係数が高まる傾向にある。職業別就業構造との関係を見ると、農林漁業が多いほど所得水準は全般的に低く、事務職が多いほど所得水準は高いが、両者ともジニ係数への影響は中立的である。これに対し、専門技術職は上位値を引き上げ、サービス業は下位値を引き下げるよう作用し、両者が相まって格差を拡大する要因となっている。対照的に、ブルーカラー就業者の多い地域では格差が抑制されている。さらに、このような地域間の所得格差は人口移動と強い正の相関を示すことから、地方から都市への人口集中をより促進するよう作用していると考えられる。<BR><B>4.今後の課題</B><BR> 世帯所得の格差に関する今回の分析から、問題は地域間格差の拡大ではなく、むしろ地域内格差の拡大にあると言える。結果についてさらに解釈を深めるには、推計方法や地域区分を再検討する余地がある。これ以外に都道府県別の世帯所得データが得られる「全国消費実態調査」や「就業構造基本調査」を用いた場合と、結果を比較検証する必要もあろう。今後、地域格差の要因を究明していくには、論理的な因果関係を組み込んだ説明モデルの構築が求めらる。<BR>
3 0 0 0 OA 世帯所得の地域格差とその変動
- 著者
- 豊田 哲也
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2007年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.312, 2007 (Released:2007-12-12)
1.問題の所在 「都市と地方の格差問題」は今日わが国における最も重要な政策テーマとなったが、その事実認識について論争はつきない。現象としての所得格差には2つの意味がある。一つは「都市-地方」という空間的な関係であり、もう一つは「富裕層-貧困層」という階層的な関係である。ところが多くの場合、前者の分析は1人あたり県民所得など平均値の差のみに注目し、格差の階層的構造についての視点を欠く。一方、後者の分析は所得再分配調査など全国一律のデータをもとにおこなわれ、地域間の比較については関心がない。しかし、地域と地域の間に格差があるのと同様、どの地域もその内部に階層的な格差を抱えていることは自明の事実である。例えば、高級マンションとホームレスが併存する大都市と、過疎化・高齢化が進む中山間地域を含む地方とでは、いずれの地域で格差がより大きいであろうか。また、地域間・地域内の格差はどの程度拡大しているのか。本研究では、世帯所得の地域格差を空間的・階層的かつ時系列的に分析し、こうした格差を生み出す要因として人口や雇用など地域の社会経済条件との関連を検討することを目的とする。 2.所得の地域格差 使用するデータは「住宅・土地統計調査(都道府県編)」である。「世帯の年間収入」の階級別世帯分布から、線形補完法でメジアン(中位値)、第1五分位値(下位値)、第4五分位値(上位値)を推定するとともに、ジニ係数を求める。なお、実質所得は世帯人員の規模の影響を受けるため、SQRT等価尺度を用いて調整を加えた。1998年から2003年にかけて、等価年間収入の中位値は全国平均で286万円から267万円に約9%低下している。都道県別に見ると、神奈川、東京、千葉など首都圏と愛知で高く、沖縄、鹿児島、宮崎、高知など九州・四国と青森など東北で低い(図1)。 次に、年間収入の中位値を横軸に、ジニ係数を縦軸にとって各都道府県の散布図を描く(図2)。おおむね年間収入が高いほどジニ係数は低いという逆相関を示す。東京は両者とも高いのに対し、大阪や京都では所得水準が中程度でありながらジニ係数は高い。地方でジニ係数が目立って低いのは富山、新潟、長野、山形など北陸・信越地方で、高いのは徳島・高知など南四国と和歌山である。5年間の変化を見ると、縦軸方向で示される地域内格差はやや拡大しているが(ジニ係数の平均値:0.294→0.299)、横軸方向のばらつきで示される地域間格差は、予想に反してむしろ縮小していることがわかる(中位値の変動係数:0.126→0.109)。平均対数偏差(MLD)を用いた要因分解によっても、この結果は支持される。 3.地域格差の要因 空間的な地域間格差と階層的な地域内格差をもたらす要因を探るため、人口や雇用などの地域の変数と所得およびジニ係数との間で相関係数を算出した(表1)。人口構成に関しては、生産年齢人口が多く老年人口が少ない地域ほど所得水準は高い。一方、女性就業率の高さは地域内格差の縮小に貢献している。また、労働力需要が弱い高失業率地域では、所得の下位値が低下しジニ係数が高まる傾向にある。職業別就業構造との関係を見ると、農林漁業が多いほど所得水準は全般的に低く、事務職が多いほど所得水準は高いが、両者ともジニ係数への影響は中立的である。これに対し、専門技術職は上位値を引き上げ、サービス業は下位値を引き下げるよう作用し、両者が相まって格差を拡大する要因となっている。対照的に、ブルーカラー就業者の多い地域では格差が抑制されている。さらに、このような地域間の所得格差は人口移動と強い正の相関を示すことから、地方から都市への人口集中をより促進するよう作用していると考えられる。 4.今後の課題 世帯所得の格差に関する今回の分析から、問題は地域間格差の拡大ではなく、むしろ地域内格差の拡大にあると言える。結果についてさらに解釈を深めるには、推計方法や地域区分を再検討する余地がある。これ以外に都道府県別の世帯所得データが得られる「全国消費実態調査」や「就業構造基本調査」を用いた場合と、結果を比較検証する必要もあろう。今後、地域格差の要因を究明していくには、論理的な因果関係を組み込んだ説明モデルの構築が求めらる。
The aim of this paper is to examine transport service as one of the transport conditions which are factors in the choice of means of transport and of traffic flows, from a geographical point of view.By dealing with a coefficent of the transport service of air lines and an accessibility of airports, the author clarifies regional differences in transport service and their changes from 1970 to 1982 in Japan's domestic air transport.Flight time, fare, and the number of flights are used as indices of transport service.The conclusions derived from this study are as follows:As for transport service of lines, the gap between main lines and local lines is as great as before with a few exceptions such as the Osaka-Kochi line and the Osaka-Tokushima line. Expressed regionally, it is clear that the level of transport service is high in western Japan, and low in eastern Japan.As for changes of transport service from 1970 to 1982, the lines with a high growth rate of transport service are also concentrated in western Japan.Tokyo and Osaka are the most important airports in domestic air transport. But a striking contrast can be found between the lines from Osaka and those from Tokyo. That is to say, the growth rate of"Beam lines"from Tokyo is mostly high, while that from Osaka is low or negative.Of these three indices of transport service, an increase and decrease in the number of flights is the most important factor affecting the growth rate of the transport-service coefficient. The shortening of flight time by jet planes is as secondary factor. Although great utility of the shortening of flight time can be seen in the lines where jet planes started flying between 1970 and 1982, flight time has not shortened on other lines. It can be said that shortening of flight time by jet planes has reached its limit.As for accessibility of airports, in spite of progress in expanding infrastructure at local airports, there is an evident gap between local airports and main airports such as Tokyo, Osaka, Sapporo, and Fukuoka. Expressed regionally, accessibility of airports in western Japan is mainly higher than accessibility of airports in eastern Japan.But a different regionality appears in the change of accessibility. Although the growth rate of the main airports remains low, the airports in eastern Japan and in the districts facing the Japan Sea, such as Asahikawa, Memanbetsu, Kushiro, Komatsu, Toyama, and Aomori, show a high growth rate.By opening new lines and by increasing the number of flights, many of these airports with a high growth rate of accessibility are strengthening linkages with the principal airports on both the main and local lines.Shortening of flight time by jet planes is not necessarily an important factor in terms of the growth rate of accessibility.
3 0 0 0 情報化社会とサイバースペースの地理学:研究動向と可能性
Since the middle of the 1990s, the rapid diffusion of the Internet into society has driven various social transformations. A number of geographical studies with diverse approaches on the impacts of information technologies (IT), including the Internet, have been carried out in Western countries, although Japanese geographers have produced few studies. This paper provides an overview of research trends in this field among Western geographers in the latter part of the 1990s and early 2000s. A framework proposed by Dodge and Kitchin is employed. In this framework, geographical aspects of IT are broadly divided into two categories: the impacts of IT on real economies and societies (called 'geographies of information society') and the geographical characteristics of virtual space emerging in computers and information networks (called 'geographies of cyberspace'). Using this framework, studies analyzing the geographies of information society are reviewed first, and then studies discussing geographies of cyberspace are considered. Finally, a research strategy for Japanese geographers in this field is proposed.While almost all studies on the impacts of IT on real economies and societies discuss the technical possibilities or the economic benefits of IT usage up to the first half of the 1990s, geographers increasingly have paid attention to the social and political consequences of the penetration of IT. A clear trend from a techno-economic view to a socio-political view is observed. Within this trend, eight issues are discussed: 1) industrial location in the IT age, 2) new urban IT-industrial clusters, 3) growth strategies of peripheral areas using IT, 4) emergence of e-commerce, 5) IT and the city, 6) the digital divide, 7) electronic surveillance, 8) political impacts of the Internet.The first studies by geographers on the characteristics of virtual space emerged around 1997. Several new analytical concepts, e. g. Adams' 'virtual place' and Batty's 'virtual geography', were proposed. Many cultural geographers became interested in the socio-cultural aspects of the virtual world as argued by Kitchin, who first proposed the concept of 'geographies of cyberspace'. A research approach of 'spatial analysis of cyberspace', by which the virtual locations and spatial structure of cyberspace are analyzed applying traditional methods of spatial analysis, was also proposed. The spatial characteristics of various media of cyberspace, e. g. e-mail, chat rooms and multiple user domains (MUDs), were analyzed and methods for mapping cyberspace were developed under this approach.From the review of studies in this field, two major trends are identified. One is the growing attention to the social, political and cultural aspects of IT's impacts in either the real or virtual worlds. Another trend is the wide acceptance of the concepts of 'cyberspace' or 'virtual space' by geographers. This acceptance may reflect the rapid penetration of these concepts into both general and academic society.Two current research areas are identified to activate Japanese geographers' work in this field. First, close examination of new, advanced IT usage in Japan, e. g., e-commerce and mobile phones, is required. These studies will open the possibility for a new model of information society suitable to Japan as well as other Asian countries. Second, the introduction of the socio-cultural approach accepted among Western geographers is effective. The positive participation of social geographers and cultural geographers is expected.
2 0 0 0 OA 旧版地形図の履歴からたどる戦前地図作成史 ―神戸大学文学部所蔵地図資料に基づく―
- 著者
- 井口 琢人 菊地 真
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2022年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.42-43, 2022 (Released:2022-11-30)
- 著者
- 河角 龍典 加藤 政洋
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.144-145, 2012
嘉手納基地ゲート前に建設された「ビジネスセンター」の地形景観をGISを用いて復原し、都市計画との関連性について検討する。
2 0 0 0 OA 伝承された古代の呪術的防衛と渡辺党ネットワーク ー茨木童子伝承を中心にー
- 著者
- 中山 雄斗
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2018年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.112-113, 2018 (Released:2020-06-13)
2 0 0 0 OA 韓国におけるプロ野球・サッカーチームの立地条件
- 著者
- 松田 隆典
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2022年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.92-93, 2022 (Released:2022-11-30)
2 0 0 0 OA 堀田仁助「奥州松前蝦夷図」の成立事情
- 著者
- 神 英雄 佐々木 良子
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2014年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.34-35, 2014 (Released:2020-06-13)
2 0 0 0 OA 九州北部地域における方言の共通語化
- 著者
- 塩川 奈々美 峪口 有香子
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2015年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.176-177, 2015 (Released:2020-06-13)
2 0 0 0 野麦の集落と農牧地:日本アルプス地誌 第1報
- 著者
- 鏡味 完二 松原 義継
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.5, pp.375-386,418, 1955
The settlement of "Nomugi" lies on a compound talus at the hight of 1320m above sea level. (Fig. II) This talus was constructed on the northern side of "River Mashita", at the western foot of "Nomugi Pass" 1672 meters high). "Nomugi" was the most important pass in the "Northern Japanese Alps" in the days about 50 years ago, through which a highway was constructed in the feudal times from Takayama to Matsumoto (Fig. I). Every day about 70-80 "da" (one "da" is the cargo of one cattle) was conveyed through this pass.In the settlement of "Nomugi" there are 29 houses now, but about 50 years ago were neary 50 houses. Among these houses, there were three inns, four doss houses and other shops such as bar, grocers, etc. But all these shops transformed their occupations to agricultural, pastral, or forestry. As the result of this change of trade, the prosperity of this village was declined. The reason of this decline was the construction of Chuo Line Railway from Nagoya to Tokyo, and then the opening of Hokuriku L.R.W. along the coast of Japan Sea and finally Takayama L.R.W. from Gifu to Toyama. All the communication through "Nomugi pass" was pillaged by these rail road traffic, and the number of "Nomugi" decreased gradually from about 50 to 30 since 50 years ago. Thus this settlement has turnd into a lonely mountain village and "Nomugi Pass" was almost closed to passengers. This village is a rare example in Japan which has no medical man and no electric lamp.But this place would revive if a plan of construction of tourist bus road on the ridge line from "Nomugi Pass" to the top of Norikura Volcano only be realized in these years.The meaning of the place name of "Nomugi" may be explained an old Japanese words, namely "no"=field, "mugi"=apparent place from every direction. This means the topographical feature of the talus on which this settlement stands.The annual mean temperature of this place is 6.7°C.. This value coincides with that of the inner land type climate in the central part of Hokkaido. With the summer maximum temperature 28°C, and comparatively stronger sunshine with longer shining hour, these owe to the nature landform of talus on which this village stands, farmers can plant summer crops suitable to the low temperature such as buckwheat, barnyardgrass, soyabean, millet, corn etc.. Thus the production of crops. amounts to 90% of the whole agricultural products. But rice culture finds no place on account of the low temperature. As the result of the shorter period free from the frost (199 days), these crops frequently experienced the frost damage and diminished the yield.Thus the length of self sustaining of food in this village is only 4…5 months in a year. (Average number of cultivated field per one house is one ha..) We can find a definite relationship between the distance from farm house and the species of crop; namely vegetable field near the house, fields of buckwheat, millet etc. apart from it. Because the former requires much more labour than the latter. Mulberry trees are planted on foot-path or on the escarpments of river terraces and their tall trees need a ladder to pick the leaves.This village has 47 head of plough cattle by 27 farm houses. They breed them in the way of transhumance; grazing in summer, pen feeding in winter. Summer grazing is taken in the sloping pasture on the mountain side of Norikura Volcano (Its area is abont 800ha..). Mowing fields are found near the farm houses and so they lie on the place lower than the pasture. Its area is about 300ha.. From this mowing field farmers collect their hay, and by the labour efficiency of this colection the number of cattle can be bred in one farm house is defined. In this village the highest number is only 3.
- 著者
- 山下 清海
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, pp.42-42, 2004
今日、世界の華人社会は、ダイナミックに膨張と拡散を続けている。中国では、1970年代末以降の改革開放政策の進展に伴い、新たに海外へ移住する者、すなわち「新移民」が急増した。香港では、1997年の香港の中国返還を前に、海外移住ブームとなり、多数の香港人が移住した。台湾でもアメリカを中心に海外移住の流れが続いている。 東南アジアでは、1970年代半ばからベトナム戦争やインドシナの社会主義化で、ボートピープルなどの難民(華人が多く含まれる)が流出した。いったん東南アジアや南アメリカなどへ移住した華人が、さらに北アメリカやヨーロッパなど他の地域へ移住して行く現象を、中国では「再移民」と呼んでいる。 従来の伝統的な華人社会は、「新移民」や「再移民」の増加によって、大きな変容を迫られている。 本研究は、このような最近におけるアメリカ華人社会の変容を、ロサンゼルス大都市圏を対象に考察するものである。考察に際しては、ダウンタウンのオールドチャイナタウンと、新しく郊外に形成されたニューチャイナタウン(モントレーパーク、ローランドハイツ)を比較しながら進めていく。なお、現地調査は、2003年8月と2004年7月に実施した。