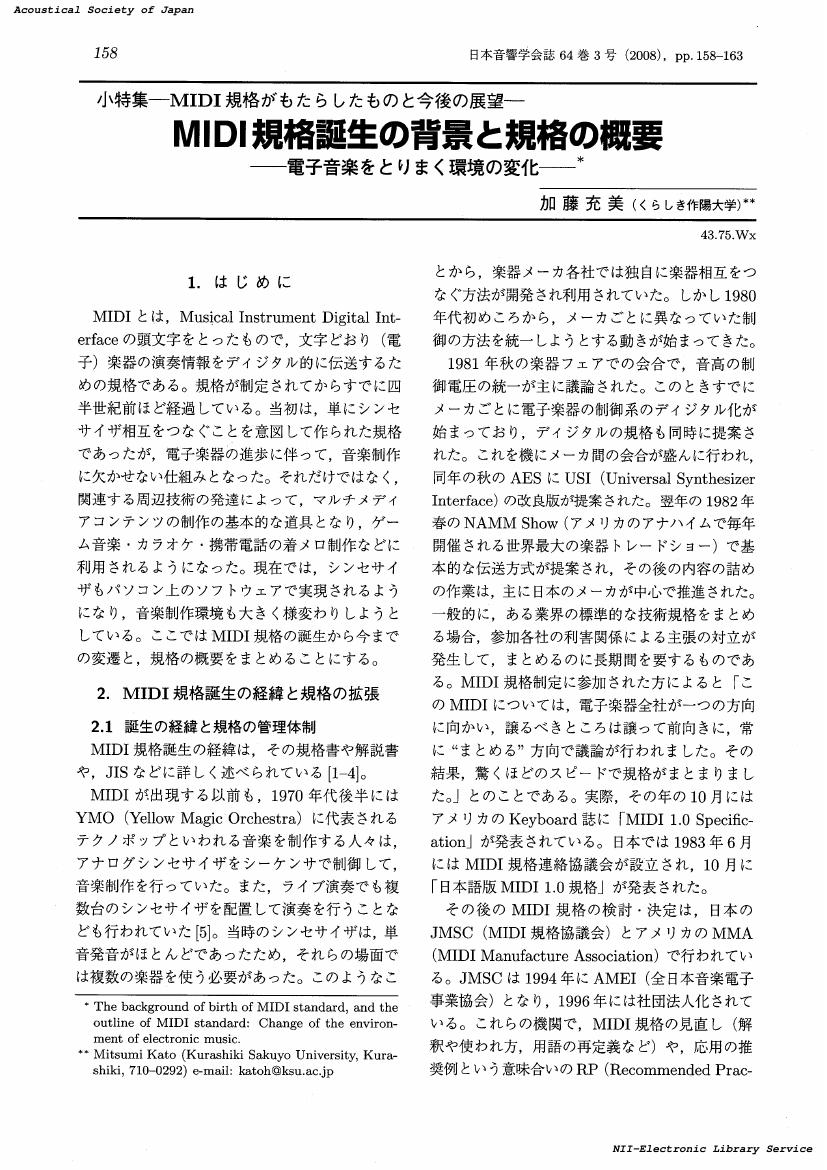1 0 0 0 銀担持アクリル繊維を含む抗菌紙の殺菌作用機構
銀担持アクリル繊維とポリエステル繊維の混抄紙(iZi)の抗菌特性とその殺菌機構を明らかにした。iZiは、Legionella pneumophilaを含む細菌に対して強い殺菌力を有していた。iZiの殺菌力は、食塩、ペプトン共存下で低下することを認めた。iZiの殺菌化学種は・OHであることを証明し、さらに菌体内でリビングラジカルとして継続的な殺菌効果を示すと考えられた。また、iZiから菌体へ銀が移行することを示した。iZiの殺菌力は、銀含量に強く依存した。
1 0 0 0 OA 訓読・諏訪大明神絵詞(一)(<共同研究>関東周辺の歴史と文学の研究)
- 著者
- 山下 正治
- 出版者
- 立正大学人文科学研究所
- 雑誌
- 立正大学人文科学研究所年報. 別冊 (ISSN:02887681)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.A9-A18, 2006
1 0 0 0 OA 山岡荘八における作品の変容と連続―『徳川家康』・「御盾」を中心に―
- 著者
- 上 昭子
- 出版者
- 東洋大学日本文学文化学会
- 雑誌
- 日本文学文化 = Japanese Literature and Culture (ISSN:13468723)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.91-99, 2010
1 0 0 0 体験型地理学習ソフト : チリチリらんど
- 出版者
- NECインターチャネル(発売元)
- 巻号頁・発行日
- 1994
- 著者
- 雨宮剛 エルダル・ドーガン編著
- 出版者
- 雨宮剛
- 巻号頁・発行日
- 2006
1 0 0 0 OA 「エンパワメント」:その使用を思いとどまらせるものについての考察
- 著者
- 山口 理恵子
- 出版者
- 日本スポーツとジェンダー学会
- 雑誌
- スポーツとジェンダー研究 (ISSN:13482157)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.138-146, 2014 (Released:2017-04-28)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 IR カントの空間論
- 著者
- 上田 徹 UEDA Toru
- 出版者
- 筑波大学哲学研究会
- 雑誌
- 筑波哲学 (ISSN:09162046)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.p41-56, 1994-03
1 0 0 0 OA 電気生理学の基礎的テクニック
- 著者
- 井之口 昭
- 出版者
- 日本耳科学会
- 雑誌
- Ear Research Japan (ISSN:02889781)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.380, 1989 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 IR 日本の保育観の歴史的変遷からとらえる保育 : 保育の質の向上を目指して
- 著者
- 井上 明美
- 出版者
- 花園大学社会福祉学部
- 雑誌
- 花園大学社会福祉学部研究紀要 = Bulletin of the Faculty of Social Welfare Hanazono University (ISSN:09192042)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.35-44, 2020-03-12
1 0 0 0 OA 今、なぜ民俗学の歴史離れか―1970年・80年代の歴史学者から民俗を読む―
- 著者
- 西海 賢二 NISHIGAI Kenji
- 出版者
- 現代民俗学会
- 雑誌
- 現代民俗学研究 = Journal of Living Folklore (ISSN:18839134)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.41-52, 2009-03
It has been some time since people began to argue that folklore studies is in decline. The author might not be alone in thinking that a huge gap is opening between folklore studies and history as an adjacent academic field. In this paper, by looking back at works of and exchange among Tatsuo Hagiwara (Medieval history), Yoshihiko Amino (Medieval history), and Yoshio Yasumaru (Modern history), all historians who were active in the 1970s and 1980s and who positively evaluated folklore studies in Japan, the author provides, in the form of a memoir, insights into the possibility of integrating folklore studies and history, before questioning the integration of folklore studies with sociology, cultural anthropology, and ecology as currently proposed by scholars of folklore studies.
- 著者
- 三沢 英一
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳動物学雑誌: The Journal of the Mammalogical Society of Japan (ISSN:05460670)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.5-6, pp.311-320, 1979-03-30 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
環境の異なった, 北海道大学農学部付属苫小牧地方演習林, 札幌市羊ケ丘, 札幌市盤渓の3地域においてキタキツネのフン分析による食性の比較を行った。1) 各地域ともエゾヤチネズミがキツネの主要な餌であった。2) 苫小牧演習林, 羊ケ丘では春, 秋にエゾヤチネズミの採食率は増加し, 冬に減少した。それらの地域で昆虫類, 野生果実の採食率は夏と秋に増加した。3) 冬にエゾヤチネズミの採食率の低下を補うキツネの餌は苫小牧演習林ではノウサギ, 羊ケ丘ではニワトリとトウモロコシがそうであった。4) 盤渓では冬にエゾヤチネズミの採食率の低下は見られなかった。また年間を通じて人為的食物への依存が見られた。5) 各地域とも冬に野鳥の採食率は増加した。6) 人為的影響の強い環境ほどキツネの人為的食物への依存は強かった。
1 0 0 0 OA 医療機関における患者の個人情報に関する事故の現状 —電子媒体が関係したケースの分析—
- 著者
- 品川 佳満 橋本 勇人
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療情報学会
- 雑誌
- 医療情報学 (ISSN:02898055)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.6, pp.311-319, 2013 (Released:2014-12-19)
- 参考文献数
- 13
本研究は,電子媒体(インターネットを含む)が関係した医療機関における患者の個人情報に関する事故の現状を明らかにすることを目的とした.そのため,2008年から2012年に報道・公表された事故について,情報セキュリティサイトや新聞記事データベースから記事を収集し分析した.結果として,186件の報道記事等が収集され,その内容から以下の現状が明らかになった. 1) 事故の起きた媒体は,USBメモリが47.0%ともっとも多かった. 2) 原因は,紛失と盗難で84.4%と大半を占めていた. 3) 事故は,院外・院内のあらゆる場所で発生し,媒体の院外への持ち出し理由は主に「研究・学習」,「業務継続」であった. 4) 医師を中心に,退職者を含むすべての職種が事故を起こしていた. 5) 漏えい(流出)につながっていた事故は10.8%と少ないが,媒体の19.0%にしかセキュリティが施されていなかった. 6) 病名が含まれていたケース,100人以上の個人情報が含まれていたケースが半数以上あった. 7) 47.3%の事故で病院のルールに対する違反が確認された.
1 0 0 0 OA 回復期の脳卒中患者における上肢用ロボット型運動訓練装置ReoGoⓇ-Jの有用性の検討
- 著者
- 石垣 賢和 竹林 崇 前田 尚賜 久保木 康人 高橋 佑弥
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.575-584, 2019-10-15 (Released:2019-10-15)
- 参考文献数
- 18
回復期の脳卒中後上肢片麻痺者に対し,15日間のロボット療法の効果検証を行った.対象は,2015年6月から2018年8月の期間に当院に入院した,初発の脳卒中後上肢片麻痺者のうち,15日間のロボット療法を実施した群(介入群)と,1ヵ月間の通常訓練を実施した群(対照群)とした.方法は,介入群と対照群で傾向スコアマッチングを実施し,Fugl-Meyer Assessment(以下,FMA)肩・肘・前腕の変化量を比較した.結果は,介入群36名,対照群62名で,22ペアがマッチングされた.FMA肩・肘・前腕の変化量は,介入群が対照群に比べ有意に改善を示した.ロボット療法を用いた介入は,効率的に回復期の脳卒中患者の上肢機能を改善させる可能性がある.
1 0 0 0 OA 耳の保護のための防音具(防音用耳保護具)について
- 著者
- 切替 一郎 河村 正三
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.125-128, 1955-06-30 (Released:2017-06-02)
1 0 0 0 OA 足関節捻挫受傷患者の歩行時の足圧中心について
- 著者
- 笠井 将也 葛山 元基 佐藤 謙次 岡田 亨
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.48101956, 2013 (Released:2013-06-20)
【はじめに、目的】 足関節捻挫は整形外科領域において多い疾患であり、それに対する理学療法評価の1つに足圧中心(COP)が用いられることがある。足関節捻挫受傷患者は歩行時にCOPが外側偏位しやすいとの報告が散見されるが、歩行の立脚期を相分けし、COPの偏位を詳細に検討した報告は少ない。そこで本研究の目的は足関節捻挫受傷患者における歩行時のCOPの偏位を詳細に検討することとした。【方法】 対象は、当院リハビリ通院患者で過去1年以内に足関節捻挫を受傷した11名、11肢(捻挫群:男性6名、女性5名、平均年齢24.4±10.2歳、平均身長168.5±12.8cm、平均体重64.4±17.2kg、受傷後平均60.1±70.3日)、および下肢疾患の既往のない健常者19名、19肢(対照群:男性9名、女性10名、平均年齢27.2±5.1歳、平均身長165.6±8.1cm、平均体重58.1±9.3kg)とした。捻挫群では両側受傷例および炎症所見、歩行時痛のある者は除外し、対照群は全例右足の測定および解析を行った。全対象者に対し、足圧分布測定装置winpod (Medicapteures社製)を用いて歩行時の足底圧分布、COPをサンプリング周期150Hzにて計測した。歩行路上にセンサープレートを設置し、被験者には5歩目がセンサープレートを踏むように指示し、数回の練習の後に計測を行った。計測時の歩行速度は自由速度とし、裸足にて3回計測を行い、平均値を解析の対象とした。解析方法はSelby-Silversteinらの方法に準じ、パソコン上でwinpod描画ツールを用い、得られた足底圧分布図の外周に枠を作図した。その後足底圧分布図を前後方向に3等分し、枠内に3等分線を作図した。COPの始点をFoot contact(FC)、3等分線とCOPの交点をそれぞれEarly-midsupport(EM)、Late-midsupport(LM)、COPの終点をToe off(TO)と設定した。次に、外枠の内側線から各点(FC、EM、LM、TO)までの最短の距離と、外枠の内側線から外側線までの距離を計測した。得られた内側線から各点の距離を、内側線から外側線の距離で除した値をpronation-spination index(PSI)とした。検討項目は各点のPSIとし、これを捻挫群と対照群で比較した。統計処理はSPSS ver.12を用い、Mann-WhitneyのU検定を使用し、有意水準は5%未満とした。【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は船橋整形外科病院倫理委員会の承認を受け、被験者には研究の主旨と方法について十分な説明をし、承諾を得て実施した。【結果】 各測定点のPSI平均値は、FCにおいて捻挫群62.9±6.8%、対照群51.7±3.7%であり捻挫群で有意に高値を示した(p=0.000)。EMにおいて捻挫群60.3±10.1%、対照群49.4±5.6%であり捻挫群で有意に高値を示した(p=0.002)。LMにおいて捻挫群53.0±9.3%、対照群47.5±5.5%であり捻挫群で有意に高値を示した(p=0.020)。TOにおいて捻挫群30.2±8.2%、対照群26.7±8.0%であり両群間に有意差はなかった(p=0.279)。【考察】 PSIが高値を示すほどCOPの外側偏位を表している。本研究において、捻挫群では対照群と比較し、有意にPSIが高く、COPが外側に偏位していた。このことから足関節捻挫受傷患者は歩行時のCOPが外側へ偏位するとした過去の報告を支持する結果となった。また本研究では歩行の立脚期をFC、EM、LM、TOの4期に分けてより詳細に検討した。その結果、FC、EM、LMにおいて有意差を認めたが、TOでは有意差は認められなかった。したがって、足関節捻挫受傷患者は歩行時において、踵接地から外側に荷重し、足指離地では正常に戻ることが示された。足関節捻挫により前距腓靭帯や踵腓靭帯の機能が低下し、後足部が回外位になりやすく、後足部の回内制限を前足部で代償するためこのような結果につながったと考える。【理学療法学研究としての意義】 足関節捻挫により立脚前期から中期にCOPが外側へ偏位しやすいことが明らかとなった。特に後足部が回外位をとりやすいと考えられ、捻挫の再受傷の危険性が増加する可能性がある。今後理学療法を展開する上で、COPを評価の一助とするとともに、立脚前期からの過度な外側荷重を内側へ誘導するアプローチを検討していく必要があると考える。
1 0 0 0 OA 看護大学生におけるキャリア成熟度と職業選択志望動機との関連
- 著者
- 堀井 瀬奈 能見 清子
- 出版者
- ヒューマンケア研究学会
- 雑誌
- ヒューマンケア研究学会誌 = Japanese Society of Human Caring Research (ISSN:21872813)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.27-33, 2020-03-31
目的:A 大学看護学部生の学年ごとのキャリア成熟度を明らかにし,志望動機との関連について検討する.方法:A 大学看護学部生1 ~ 4 年生300 名を対象とし無記名自己式質問紙調査を行った.質問項目はキャリア成熟度,職業選択志望動機,研究者が作成した学習意欲の原動力とした.結果: 回収された質問紙は241 部( 回収率80%) で,有効回答235 部を分析対象とした.一元配置分散分析を行った結果,キャリア成熟度の値は学年間で有意差はみられなかった.重回帰分析の結果,キャリア成熟度の〔関心性〕〔自律性〕〔計画性〕全ての因子と内発的動機に有意な正の関連がみられた.考察: キャリア成熟度を高めるには内発的動機を高く維持することが重要であるという知見が得られた.
1 0 0 0 OA 死を書く方法としての虚構 : アシア・ジェバール『オラン、死んだ言葉』
- 著者
- 武内 旬子
- 出版者
- 神戸市外国語大学研究会
- 雑誌
- 神戸外大論叢 = Journal of foreign studies (ISSN:02897954)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.6, pp.47-70, 2005-11-30
- 著者
- 加藤 充美
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, pp.158-163, 2008-03-01 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 14