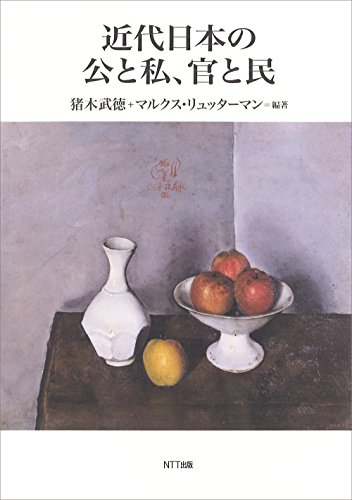1 0 0 0 OA 八戸⼯業大学におけるラーニングマネージメントシステム(HIT-LMS)の構築と活⽤
- 著者
- 小玉 成人 小久保 温 笹原 徹 大室 康平
- 出版者
- 八戸工業大学
- 雑誌
- 八戸工業大学紀要 = The Bulletin of Hachinohe Institute of Technology (ISSN:24346659)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.211-218, 2020-03-03
- 著者
- 坂本 光太
- 出版者
- 国立音楽大学大学院
- 雑誌
- 音楽研究 : 大学院研究年報 = Ongaku Kenkyu : Journal of Graduate School, Kunitachi College of Music (ISSN:02894807)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.177-193, 2019-03-29
ヴィンコ・グロボカール Vinko Globokar(b.1934)はフランス生まれのスロベニア人作曲家、トロンボーン奏者、即興演奏家である。彼の代表作と目される事も多い金管楽器ソロ作品、《レス・アス・エクス・アンス・ピレ Res/As/Ex/Ins-pirer》(1973)は、「身体性」というイメージで漠然と語られこそすれ、今まで詳細に分析・検討されることはほとんどなかった。本稿は、グロボカールの作曲の師であり、《セクエンツァ第5番 Sequenza V》(1966)を共同で作ったルチアーノ・ベリオ Luciano Berio(1925-2003)の影響を指摘しながらこの楽曲の作品を詳細に分析し、その数的な構造性と美学を明らかにすることを目的とする。まずグロボカールと、ベリオの《セクエンツァ第5番》の関係について触れた後に、その影響を踏まえながら、6つの観点(1.特殊奏法の使用法と2.楽曲を構成する10のセクションの「小節」数の枠組み、3.奏法のモード的な配置方法、4.音列、5.ダイナミクス、6.音声学的な要素)から、それぞれの数的な構造性を分析した。その結果、《レス・アス・エクス・アンス・ピレ》においてグロボカールは、ベリオの《セクエンツァ第5番》から、音声学的要素、音色の拡大(種々の特殊奏法の使用)、身体性の導入などの点において大いに影響を受けながらも、それらを徹底的に拡大し、さらに体系化・組織化したこと、そしてその体系化・組織化には、意図的とも言える欠落を伴っているということが明らかになった。ベリオの楽曲では数回用いられるに過ぎなかった吸気による奏法を、楽曲の根幹に関わるコンセプトとして用い、演奏者に限界までの身体的負担を強いる事によって、楽曲を、演奏そのものが崩壊していくというプロセスに変えてしまったことは、Beck(2014)やグリフィス(1981)も指摘しているように、この楽曲に独自の意味を持たせている。すなわち、「演奏者の身体と楽器は、正確に音を出すための装置である」という規範を反転させ、生身の人間の身体が関わる時の、システムの否応なしの崩壊を現出しているのである。そして、楽曲中の各パラメーターに現れる数的な構造の中の意図された欠落は、自壊に至る身体のプロセスと共に、「完全な数的構造」=「体系化・組織化」という規範から、音楽そして身体の逸脱(解放)を重要な美的契機として呈示している。
1 0 0 0 OA 日本の高等学校における韓国語教育に望むこと
- 著者
- 浜之上 幸
- 出版者
- 神田外語大学言語メディア教育研究センター
- 雑誌
- 言語メディア教育研究センター年報 = The language and Media Learning Research Center Annual Report (ISSN:24337056)
- 巻号頁・発行日
- no.2017, pp.7-28, 2018-03-20
1 0 0 0 OA スペインにおける「新しい」中国系コミュニティの形成と特徴
- 著者
- 山本 須美子
- 出版者
- 東洋大学社会学部
- 雑誌
- 東洋大学社会学部紀要 = The Bulletin of Faculty of Sociology,Toyo University (ISSN:04959892)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.17-31, 2018-03
The purpose of this paper is to reveal the historical development, diversity, and economic activities of the Chinese community in Spain. It also clarifies the haracteristics of the Chinese community in Spain, comparing it to those in other European countries. In conclusion, compared with the diversity of Chinese people in the U.K., rance, and the Netherlands--where since the 1980s people from mainland China have joined people from Hong Kong or Indochina (from where immigration peaked in the 1960s and 1970s), the Chinese community in Spain--where less educated people (mainly from Zhejiang)immigrated since the 2000s--is homogeneous. It has been found that the characteristics of the economic activities of the Chinese community in Spain include the rapid transition of small businesses from catering to sewing, resale and wholesale, and running wholesales or import-export goods shops produced in China or other European countries. It should also be noted that there is great similarity between the Chinese community in Spain and that in Italy.The Chinese population in Italy is larger than that in Spain, and there is a span of economic activities in the cities due to this larger population that is not seen in Spain.
1 0 0 0 OA 「内省的近代化」を文脈とするCSR解釈の試み . CSRの可能性を展望する .
- 著者
- 谷口 照三
- 出版者
- 桃山学院大学
- 雑誌
- 桃山学院大学総合研究所紀要 = ST.ANDREW,S UNIVERSITY BULLETIN OF THE RESEARCH INSTITUTE (ISSN:1346048X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.47-63, 2012-03-30
1 0 0 0 OA 生存権に関する一考察 : プログラム規定の意味をさぐって
- 著者
- 齋藤 康輝 SAITO Koki 朝日大学法学部助教授
- 出版者
- 朝日大学法学会
- 雑誌
- 朝日法学論集 = The Asahi law review, Asahi University School of Law (ISSN:09150072)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.1-37, 2007-01
- 著者
- 菊池 徹 Toru KIKUCHI
- 雑誌
- 南極資料 (ISSN:00857289)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.1017, 1961-01
- 著者
- 平山 善吉 Zenkichi HIRAYAMA
- 雑誌
- 南極資料 (ISSN:00857289)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.980-990, 1961-01
1956年以来昭和基地の建築は毎年,改造,増築等を行いつつ現在(1960年)に至っている.その間1957年から58年迄の基地放棄の1年間があったにせよ,建物は充分にのそ機能を発揮しつつ,健全な成長をとげている.ここでは,初期の平面計画の問題からおし広げられた,現在迄の様子を,新めて基地の立地条件,輸送の問題にふれながら,年ごとにその成長の過程を述べてある.この中では1956年当時の建築面積が,250.6m^2から413.0m^2(1960年)と飛躍的な発展をしたものの,これらのうちの多くは,現地で建設された,簡易建築物であることも見のがすことはできない.またその是非については色々と問題もあろうが当然なされるべき処置であると同時に,その結果は今後の参考になろうと考えられる.最後に1959年,すなわち基地再開時の建物の考察の結果を述べてある.最後にこの建物について検討を加えるならば,そこには若干の不備があったにせよ,南極大陸に立ち自然の猛威に抗しつつ,充分にその目的を達し得たと思う.
- 著者
- 井上 努 イノウエ ツトム Tsutomu Inoue
- 雑誌
- 立教大学観光学部紀要 = Rikkyo University bulletin of studies in tourism
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.132-136, 2018-03
1 0 0 0 OA 特許文書からのブートストラップ手法を用いた課題・効果表現対の抽出
- 著者
- 坂地 泰紀 野中 尋史 酒井 浩之 増山 繁
- 雑誌
- 研究報告自然言語処理(NL)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009-NL-192, no.14, pp.1-8, 2009-07-15
特許文書から直接的なユーザの便益に相当する表現と,技術上の解決課題を示す表現を自動的に抽出するアルゴリズム 「Cross-Bootstrapping」 を提案する.抽出した直接的なユーザの便益に相当する表現と,技術上の解決課題を示す表現はパテントマップを生成するために役立つ.本手法は,二つの手がかりと統計情報を用いて,ブートストラップ的に表現対を抽出する.また,辞書や人手により作成したパターンを用いず,自動的に表現を抽出することができる.最後に本手法の評価実験を行い,パテントマップを自動生成するために,十分な性能を達成したことを確認した.
1 0 0 0 OA 脈絡膜破裂のある外傷性黄斑円孔への硝子体手術の1例
- 著者
- 山崎 健一朗 和田 浩卓 桜田 伊知郎 門之園 一明 佐伯 宏三 Kenichiro YAMAZAKI Hirotaka WADA Ichiro SAKURADA Kazuaki KADONOSONO Kozo SAEKI 佐伯眼科クリニック 佐伯眼科クリニック 佐伯眼科クリニック 横浜市立大学附属市民総合医療センター眼科 佐伯眼科クリニック Saeki Eye Clinic Saeki Eye Clinic Saeki Eye Clinic Yokohama City University Medical Center Department Of Ophthalmology Saeki Eye Clinic
- 雑誌
- 横濱醫學 = The Yokohama medical journal (ISSN:03727726)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.197-200, 2005-05-31
背景:脈絡膜破裂を伴った外傷性黄斑円孔に対し硝子体手術を行った一例を経験したので報告する.症例と所見:26歳女性,うちあげ花火が直接右眼にあたり鈍的外傷となった.初診時の矯正視力は0.01であり,白内障,前房出血,黄斑円孔,脈絡膜破裂に伴う黄斑下出血と網膜浮腫がみられた.3週間後黄斑円孔は拡大した.6週後の蛍光眼底造影にて黄斑部に及ぶ網膜循環障害を認めた.受傷6週間後にインドシアニングリーンを用いた内境界膜剥離術を行った.黄斑下手術は行わなかった.結果:術後黄斑円孔は閉鎖し,視力は0.5に改善した.重篤な術後合併症は見られなかった.結論:脈絡膜破裂のある外傷性黄斑円孔に対しても硝子体手術は有効であると考えられた.
1 0 0 0 OA 伝統芸能と子ども(第1報) : 新野の雪祭りの記録
- 著者
- 松崎 行代
- 出版者
- 飯田女子短期大学
- 雑誌
- 飯田女子短期大学紀要 (ISSN:09128573)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.45-65, 2004-05-27
長野県下伊那郡阿南町新野に室町時代より伝わる雪祭りは,国の重要無形文化財に選定され,民俗学的にも高い研究価値を認められている.長い歴史の中でムラの人々の生活に根付き伝承されてきたこの祭りは,ムラビトの心の拠り所と言える.本稿では,雪祭りに参加する子どもたちの現状を平成15・16年の2年間にわたる調査から報告するとともに,その中に見られる子どもたちの育ちについて考察した.子どもたちは祭りの仕事・役割を通して自己の存在を確立させ,ムラに対する愛着感を一層深め,また自然(神)に対する畏敬の念を知った.伝統芸能などの地域文化は多様で縦走的であり,そこに潜む教育力は大変大きい.本稿を礎に,伝統芸能と子どもについて児童文化的見解を深めていきたい.
1 0 0 0 OA GPS受信状態を用いた屋内外判定法
- 著者
- 勝田 悦子 内山 彰 山口 弘純 東野 輝夫
- 雑誌
- 研究報告高度交通システム(ITS)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011-ITS-47, no.18, pp.1-8, 2011-11-03
携帯電話の普及とともに携帯電話にGPSを搭載することが求められるようになり,ナビゲーションなどの目的でGPSを利用する機会が増えている.本研究ではGPSの新しい利用方法として,Signal to Noise Ratio(SNR)などGPSの受信状態を用いて端末が屋内・屋外のどちらに存在するかを判定する方法を提案する.このため,様々な屋内外環境においてGPSの受信状態を収集し,各環境での特性から事前に判別モデルを構築しておくことで,屋内外判定をリアルタイムに実行する.屋内外判定により,屋内外で位置推定法をシームレスに切り替えたり,地図情報と組み合わせた位置推定の精度向上などの実現が期待される.提案手法の精度を確認するため,郊外や都市部など様々な屋内外環境でGPSの信号強度を収集し環境に応じて評価した結果,屋内外が切り替わってから7秒で90%の判定成功率を達成できることを確認した.
1 0 0 0 OA 深海産共生二枚貝類のシンカイヒバリガイにおける貪食機構
1 0 0 0 OA 配偶者選択の点から見た身体に対する接触回避の適応的意義
- 著者
- 羽成 隆司 河野 和明 伊藤 君男
- 雑誌
- 椙山女学園大学 文化情報学部紀要 (ISSN:13470477)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.91-98, 2012
- 著者
- 南川 幸 塩谷 つね子 平野 年秋 ミナミカワ エンヤ ヒラノ M. MINAMIKAWA T. ENYA T. HIRANO
- 雑誌
- 名古屋女子大学紀要 = Journal of the Nagoya Women's College
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.21-34, 1973-03-15
"日本産ヒダナジタケ目Aphyllophorales中の肉質キノコ類に関し,その菌類分類学的位置および種の特徴をまとめ,肉質キノコ類を含む科の菌類分類学的特徴について言及し,ヒダナシタケ目中最も美味で広く世界的に利用されているアンズタケ科Cantharellusの成分,特にPro-Bitamine D_2 エルゴステリンに関して定量測定を進め次の結果を得た.1.アンズタケ科のエルゴステリンの含有量はほぼ0.08%から0.2%ぐらいまである.2.アンズタケ科のうちオオムラサキアンズタケが0.19%,ヒナアンズタケの0.17%,アンズタケの0.16%が比較的多く,つづいてベニウスタケ,ミキイロウスタケ,クロラッパタケ,シロアンズタケモドキの0,10%で,アクイロウスタケ,アカラッパタケは比較的少ない.3.エルゴステリンは成熟が進むにつれて増加する傾向が明らかになった.4.エルゴステリンは子実体の各部位により含有量に大きな差がある.すなわち菌傘部に多く菌柄部が少ない."
1 0 0 0 近代日本の公と私、官と民
- 出版者
- NTT出版
まえがき / 猪木 武徳 ; マルクス・リュッターマン序章 公と私の境界、転換点、収束点 : 利益と智・徳 / 猪木 武徳1 幸田露伴の見立て2 「個人」は「社会」のあとで発見された3 個人と組織の関係で発生する「公」と「私」第Ⅰ部 歴史にあらわれた「ヒダ」として第1章 書簡の私的記号について / マルクス・リュッターマン1 はじめに2 書札礼の原点3 書札礼の政治・行政との絡まり : 御教書や御内書までの経過4 時宜と斟酌 : 言葉の高下をめぐる規定・相談・不和5 書札礼の伝承法 : 流派・家伝・秘伝・出版6 おわりに第2章 イエズス会文献における公と私 / デトレフ・シャウベッカー1 「公・私」のいろいろ2 私的書簡 : 垣間見る3 公開年報の特徴 : タペストリー裏の糸あわせ4 日本年報の編纂・再現 : 日本人キリシタンが優等生5 三つの例6 最後に第3章 アメリカ憲法史から見た公と私、官と民 / 阿川 尚之1 アメリカ憲法史のテーマ2 「公」と「私」3 「官」と「民」4 アメリカ憲法の考え方5 「官」の肥大防止6 「民」による「公」への参画7 「私」の領域保護8 「民」の横暴防止9 まとめ第Ⅱ部 近代日本の人物像を通して第4章 公共性を支える非政治的倫理 / 田島 正樹1 福澤諭吉の「気品」と「瘠我慢」2 丸山眞男『忠誠と反逆』における「誅争」3 武士道的エートスの空洞化4 ギリシア的公共性論の限界5 インテグリティ(内的一貫性)6 インテグリティの母胎7 映画『ジャスティス』におけるインテグリティの競争8 アナロジーとしての相互理解第5章 「極悪非道地主」真島桂次郎の公と私 / 井出 文紀1 はじめに2 「極悪非道の悪地主」としての真島桂次郎3 真島像の異なる見方4 真島の苦悩?5 おわりに第6章 小泉信三の天皇像 : 君主をめぐる公と私 / 武藤 秀太郎1 はじめに2 大逆事件をめぐる思索3 「不合理的なもの」としての愛国心4 福澤諭吉の「発見」5 天皇像をめぐる相克6 おわりに第7章 公智と友情 : 福澤と西郷の場合 / 猪木 武徳1 はじめに2 福澤諭吉と西郷隆盛にとっての明治維新3 『明治十年丁丑公論』と「公智・公徳」論4 福澤の「公」と「私」の視点5 キケロ「友情論」の示すこと6 貴族階級の「公的義務」への献身という要素7 シーザーとブルータスの友情と決別8 結びにかえて第Ⅲ部 社会科学の学説から第8章 江戸の商人道における「正直」 / 桂木 隆夫1 はじめに2 公共哲学的問題関心3 世俗倫理としての正直=庶民の自由の観念4 海保青陵における正直の方法論第9章 納税をめぐる公と私 / 中岡 俊介1 はじめに2 所得税法の変遷 : 制度確立と課税強化のプロセスについて3 大正九年の所得税法改正 : 改正の背景と目的4 所得税法改正のプロセス : 議会審議と政府の対応から5 財界側の抵抗 : 「資本の論理」の限界6 おわりにかえて : 「官」の論理と「資本」の論理第10章 被用者年金の分立・統合過程にみる官と民、公と私(戦前) / 木村 真1 はじめに2 戦前の公務員の年金制度3 社会保障の整備と共済組合の関係4 戦前の年金制度における官と民、公と私第11章 高田保馬の勢力説 / 橋本 努1 はじめに2 駆動因としての民族 : 『社会学概論』と『勢力論』3 普遍主義としての帝国形成4 おわりに第12章 上田貞次郎と自由主義の凋落 / 望月 和彦1 はじめに2 上田貞次郎の「新自由主義」3 大正デモクラシーからマルクス主義へ4 河合栄治郎の自由主義5 満州事変以後の状況変化6 自由主義への抑圧7 河合栄治郎の抵抗とその結果8 おわりに第Ⅳ部 教育と研究において第13章 教育機関における公と私の分担 / 紙谷 雅子1 平成の日本2 連邦による公有地付与と高等教育機関 : アメリカ合衆国の「公立大学」3 カレッジからユニヴァーシティへ4 カレッジ・ライフとカレッジ・スポーツ5 ユニヴァーシティとリサーチ6 カーネギー財団のカテゴリー7 学生集団の構成と選抜8 アメリカ合衆国の高等教育から見た日本の高等教育第14章 帝国大学の初志 : 初代総長、渡辺洪基の考えたこと / 瀧井 一博1 官学アカデミズムとしての帝国大学2 初代総長、渡辺洪基3 帝国大学の創設4 創立期帝国大学と国家学会 : 伊藤博文入会問題に即して5 渡辺における知 : 官民を還流するもの第15章 知的生産の二つの秩序 : 私益と公益のはざま / 上山 隆大1 はじめに2 知識の公的空間と私的空間3 株式保有を通した「公的」アカデミアの変容4 スタンフォード大学の実験5 1980年代~90年代のスタンフォードの投資戦略6 まとめにかえて第Ⅴ部 空間論として見る第16章 屋外空間の公と私 : 近代日本の公園史から / 白幡 洋三郎1 公園と地域文化2 西洋が見た日本の「公園」3 日本が見た西洋の「公園」4 日本における「公園」の誕生5 西洋の公共空間体験の場としての居留地公園6 土着の「公」園、外来の「公」園7 日比谷公園の誕生と公共空間の観念第17章 都市と建築 / 井上 章一1 都市の裏面に政治を読む2 領主と国王の居館を見くらべる3 家作制限からときはなたれて4 カタログ化のはてに終章 問題と展望 : 公と私、の概念によせて / マルクス・リュッターマン共同研究会記録「近代日本の公と私、官と民――比較の視点から」
1 0 0 0 OA キー・コンピテンシーを育む幼児教育のあり方
- 著者
- 高山 静子
- 出版者
- 東洋大学ライフデザイン学部
- 雑誌
- ライフデザイン学研究 = Journal of Human Life Design (ISSN:18810276)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.89-104, 2017-03
1 0 0 0 OA リアルタイム遠隔テキストコミュニケーションにおける対人許容応答時間の評価
- 著者
- 宮部 真衣 吉野 孝
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.1214-1223, 2009-03-15
テキストベースのリアルタイムコミュニケーションにおいて,メッセージ作成の長時間化は円滑なコミュニケーションを妨げる.コミュニケーションを円滑に行うためには,相手が許容できる時間内にメッセージ作成を終える必要がある.これまでに,システムの応答時間に関する人間の許容応答時間については明らかにされている.しかし,システムを介したテキストベースの対人リアルタイムコミュニケーションにおいて,相手の応答をどれだけ待つことができるのかについては明らかにされていない.本研究では,テキストベースのリアルタイム遠隔コミュニケーションにおける対人許容応答時間の評価を行う.評価実験では,対話状況を1対1での特に目的のない自由な対話とし,「相手の入力状況の提示」および「対話段階の進行」による対人許容応答時間への影響についての検証を行った.評価実験より,以下の知見を得た.(1) 対人許容応答時間は,平均で1分51秒であった.(2) 相手の入力状況を提示し,対話の序盤に測定するという条件下において,対人許容応答時間は平均2分35秒であり,相手の入力状況の提示により,対人許容応答時間が長くなる可能性が高い.(3) 対話の経過時間は,対人許容応答時間に対して大きな影響を及ぼさない可能性が高い.
- 著者
- 鈴木 寛
- 出版者
- 八戸工業大学
- 雑誌
- 八戸工業大学紀要 = The Bulletin of Hachinohe Institute of Technology (ISSN:24346659)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.184-194, 2020-03-03