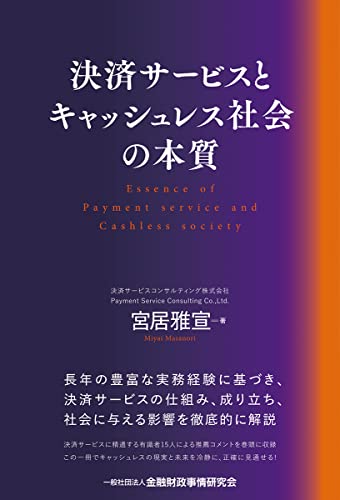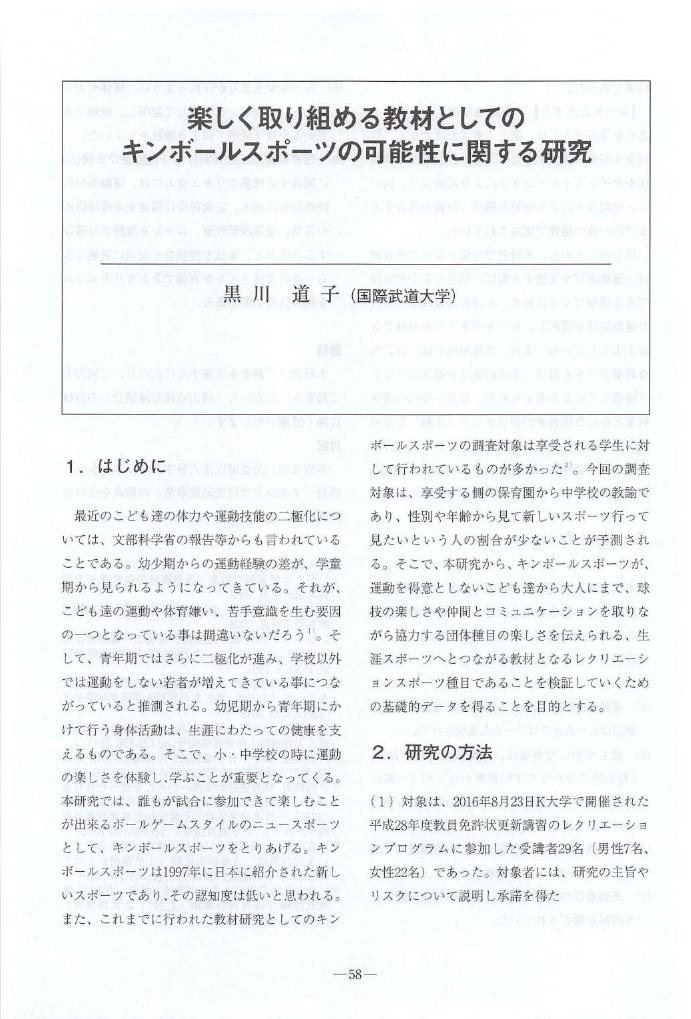1 0 0 0 OA カキ'平核無'のエタノール処理による脱渋機作
- 著者
- 福嶋 忠昭 北村 利夫 村山 秀樹 吉田 敏幸
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE
- 雑誌
- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.685-694, 1991 (Released:2008-05-15)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 10 12
渋ガキ'平核無'を用い, エタノールによる脱渋機作を種々の観点から検討した. 結果は以下のとおりである.1. デシケータ内に果実を入れ, ふたをずらして開口部を設けて35%エタノールまたは5%アセトアルデヒド処理を施したところ, 両処理区とも果実内のアセトアルデヒド含量は4日目まで同じような値を示したにもかかわらず, エタノール処理の方がアセトアルデヒド処理より早く脱渋した。2. 乾熱果または煮沸果を種々の濃度のアセトアルデヒド溶液に2日間さらし, 果肉内のアセトアルデヒド含量と脱渋量の関係式を求めた. これをエタノール処理中の果実に適用すると, アセトアルデヒドの非酵素的作用だけで脱渋するには, 果実内に存在するアセトアルデヒドの量が著しく少なかった.3. エタノール処理の果肉組織の浸透圧と水不溶性物質の保水能は増加する傾向があった. その程度は脱渋速度が大きい処理2~4日で著しかった.4. 煮沸果を90°C下で乾燥すると, 目減りが増加するとともに浸透圧が増加し, 可溶性タンニン含量が減少し, 12時間後にはアセトアルデヒドの発生が認められなくても完全に脱渋した.5. エセホンやIAAを組織切片に与えても脱渋が認められ, IAAをへたに浸潰し放置して置くと果実は完全に脱渋した.以上の実験を踏まえて考察した結果, エタノールによる脱渋は, 処理によって生ずるアセトアルデヒドの非酵素的作用による水溶性タンニンの不溶化によるのみならず, エタノールによって誘導される細胞壁多糖類の分解がタンニン細胞周辺組織の浸透圧の上昇を招き, その結果タンニン細胞中の水が脱水され, 接近したタンニン分子が水素結合や疎水結合により巨大分子となって脱渋するものも相当あると推察された.
- 著者
- 脇田 幸延 山永 隆史 片山 豊 永野 琢朗 小倉 直人 東山 滋明 河邉 讓治 市田 隆雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- pp.2022-1298, (Released:2022-08-10)
- 参考文献数
- 19
【目的】本研究の目的は,核医学領域における,診断参考レベル(Japan Diagnostic Reference Levels 2020: DRLs 2020)に基づいた円滑な線量管理を可能とするソフトウェアを開発することである.【方法】プログラミング言語Visual Basic for Applications(VBA)を用い,実投与量計算機能,自施設とDRLs 2020の比較機能,小児核医学検査の適正投与量計算機能等を実装した.更にソフトウェア導入前,後における実投与量を評価した.【結果】本ソフトウェアにより簡便な実投与量計算や,DRLs 2020との比較が可能となり,円滑な線量管理を実現し得た.また,線量評価の結果より,ソフトウェアを導入することで自施設の投与量を把握し,最適化の参考とすることができた.【結語】核医学領域では自作のソフトウェアを臨床に導入することで,DRLs 2020に則した線量管理が可能である.
1 0 0 0 OA 複雑化する社会の問題と伝統、自然、情報テクノロジー
- 著者
- 石井 晴雄
- 出版者
- 愛知県立芸術大学
- 雑誌
- 愛知県立芸術大学紀要 = The Bulletin of the Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music (ISSN:03898369)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.29-42, 2006
- 著者
- 矢守 克也 高 玉潔
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.13-25, 2007 (Released:2008-01-10)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2 2
本研究は,高等学校と地域社会において,ゲーミング手法を活用して実施した防災学習実践(アクション・リサーチ)について報告したものである。まず第1に,学習という営為について,Lave & Wenger(1991)らが提唱した学習論(実践共同体学習論)に依拠して整理した。第2に,今日の防災学習をとりまく課題を指摘し,Laveらの学習論はそれらの課題にとり組むとき,有力な指針を与えることを指摘した。第3に,以上を踏まえて,防災学習にゲーミングの手法が有効だと考えうる根拠を,Duke(1974)のゲーミング論をもとにして明らかにした。次に,以上の議論にもとづいて,1年あまりにわたって実施した防災学習のアクション・リサーチについて,その内容と経過を報告した。具体的には,高校生と関係者の協働によって,非常持ち出し品をテーマとした防災ゲームが成果物として完成し,その後,それが地域社会における防災教育のためのツールとして活用されている実態について述べた。最後に,以上の成果を総括し,当初受動的な学習者でしかなかった高校生が,本プロジェクトによって防災に関する実践共同体の有力メンバーとして参加するなど,実践共同体の構造に大きな変化が生じたこと,さらに,こうした共同体の柔軟な構造変容を伴った学習こそが,海溝型地震など周期の長い自然災害を対象とした防災実践には要請されていることを指摘した。
1 0 0 0 Le poète assassiné
- 著者
- Guillaume Apollinaire
- 出版者
- Édition
- 巻号頁・発行日
- 1916
1 0 0 0 マリー・ローランサンとその時代展 : 巴里に魅せられた画家たち
- 著者
- 富安玲子 渡辺浩美 堤祐子 [ほか] 編
- 出版者
- マリー・ローランサン美術館
- 巻号頁・発行日
- 2011
1 0 0 0 L'éventail de Marie Laurencin
- 著者
- 辛酸なめ子 横山由紀子執筆
- 出版者
- 川村記念美術館
- 巻号頁・発行日
- 2010
- 著者
- 米倉 茂
- 出版者
- 佐賀大学経済学会
- 雑誌
- 佐賀大学経済論集 / 佐賀大学経済学会 (ISSN:02867230)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.71-122, 2008-05
- 著者
- 米倉 茂
- 出版者
- 佐賀大学経済学会
- 雑誌
- 佐賀大学経済論集 / 佐賀大学経済学会 (ISSN:02867230)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.6, pp.95-154, 2008-03
- 著者
- 米倉 茂
- 雑誌
- 佐賀大学経済論集 / 佐賀大学経済学会 (ISSN:02867230)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.153-196, 2008-09
1 0 0 0 決済サービスとキャッシュレス社会の本質
1 0 0 0 リチウム導電体探索におけるデータ科学活用の実際
- 著者
- 鈴木 耕太 菅野 了次
- 出版者
- 一般社団法人 粉体工学会
- 雑誌
- 粉体工学会誌 (ISSN:03866157)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.5, pp.220-225, 2022-05-10 (Released:2022-06-08)
- 参考文献数
- 26
In materials chemistry, technology related to data science methods is attracting attention because of their high potential. In this review, we introduce the examples of material search for lithium-ion conductors from classical methods to the use of materials informatics, including our practical examples. Appling informatics technology such as the recommender system, the novel approaches in the composition-based material search were examined. Although some novel materials were discovered, high ionic conducting properties (e.g., σ > 10−4 S cm−1) were not confirmed. As a result, in the case of lithium-ion conducting crystalline materials, dramatic improvements in material search efficiency have not been achieved even if the most advanced methods have been applied so far. Therefore, it is necessary to establish a novel approach for material search by combining the various techniques from classical to advanced methods, including the experimental, theoretical calculation, and informatics approaches.
1 0 0 0 OA 楽しく取り組める教材としてのキンボールスポーツの可能性に関する研究
- 著者
- 黒川 道子
- 出版者
- 公益財団法人 日本レクリエーション協会
- 雑誌
- Leisure & Recreation(自由時間研究) (ISSN:09151729)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.58-64, 2017 (Released:2019-10-31)
1 0 0 0 IR オープン・イノベーション戦略と組織能力 : 研究開発組織の分化と統合
- 著者
- 中園 宏幸 Hiroyuki Nakazono
- 出版者
- 同志社大学
- 巻号頁・発行日
- 2015
https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB12905353/?lang=0
日本、米国シリコンバレー、英国ロンドン近辺の幾つかの企業について、共同開発、技術提携、技術情報会社の役割などを聞取り調査した結果、オープンイノベーションの問題を、取引コストの視点から分析することが有効であることがわかった。取引コストはさらに「取引相手を探索するコスト」と、「企業内部での調整コスト」の2つに分けられる。この視点の有効性を大規模サンプルで検証するために、日本の上場製造企業を対象に質問票を実施した。本社研究開発部門については「技術提供」と「技術獲得」、事業部については「技術獲得」を調査した。その結果、以下のことが判明した。(1)まず、取引相手を探索する部門の存在は、これらすべての取引を促し、この意味で探索コストを共通に減らすのに有効である。これに対し、調整コストのあり方は、取引や企業組織のタイプによって異なる。(2)本社研究開発部門の、外部への技術提供の決定には、事業部門との調整が必要であり、事業部の数が多くなるほど、外部への提供は抑制される。これと整合的に、事業部の権限が強い分権型マネジメント・コントロールであるほど、外部への提供は減少する。ただし、部門間で技術情報を共有する仕組みがあれば、この調整コストは減少し、外部提供が促される。逆に、中央の研究開発部門の権限が強い場合は、テクノロジー・プッシュ型の外部提供が行われる。(3)次に、本社研究開発部門の技術獲得は、事業部が多くなるほど促進される。そしてマネジメント・コントロール・システムが、事業部の権限が強い分権型であるほど、こうした本社部門による技術獲得は増大し、事業部からの要請に基づくニーズ・プル型の技術獲得が行われる。(4)これは事業部における技術獲得に影響し、分権型システムであるほど、事業部自らが技術獲得を行う必要性を減少させる。こうした調査の実施は他には皆無といってよい。また、分析結果についても、技術取引を取引コストの視点から捉え、さらに取引コストを構成する内部調整コストを、マネジメント・コントロールと関連させて分析した点で重要である。
1 0 0 0 OA 2001年度の日本産業動向
- 著者
- 日本興業銀行産業調査部
- 出版者
- みずほコーポレート銀行
- 雑誌
- 興銀調査
- 巻号頁・発行日
- vol.2001(7), no.305, 2001-10
1 0 0 0 OA 膜の誘電特性
- 著者
- 浅見 耕司
- 出版者
- 日本膜学会
- 雑誌
- 膜 (ISSN:03851036)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.6, pp.350-352, 2004-11-01 (Released:2011-03-04)
- 参考文献数
- 8
In this article I describe the application of dielectric spectroscopy to charged membranes in aqueous media. Possible mechanisms, such as interfacial polarization and counterion polarization, are discussed for dielectric relaxation in the membrane systems.
1 0 0 0 OA 雲仙火山1991年噴火,地質観察記録(その1)
- 著者
- 大学合同観測班地質班
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.47-53, 1992-04-01 (Released:2017-03-20)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 4