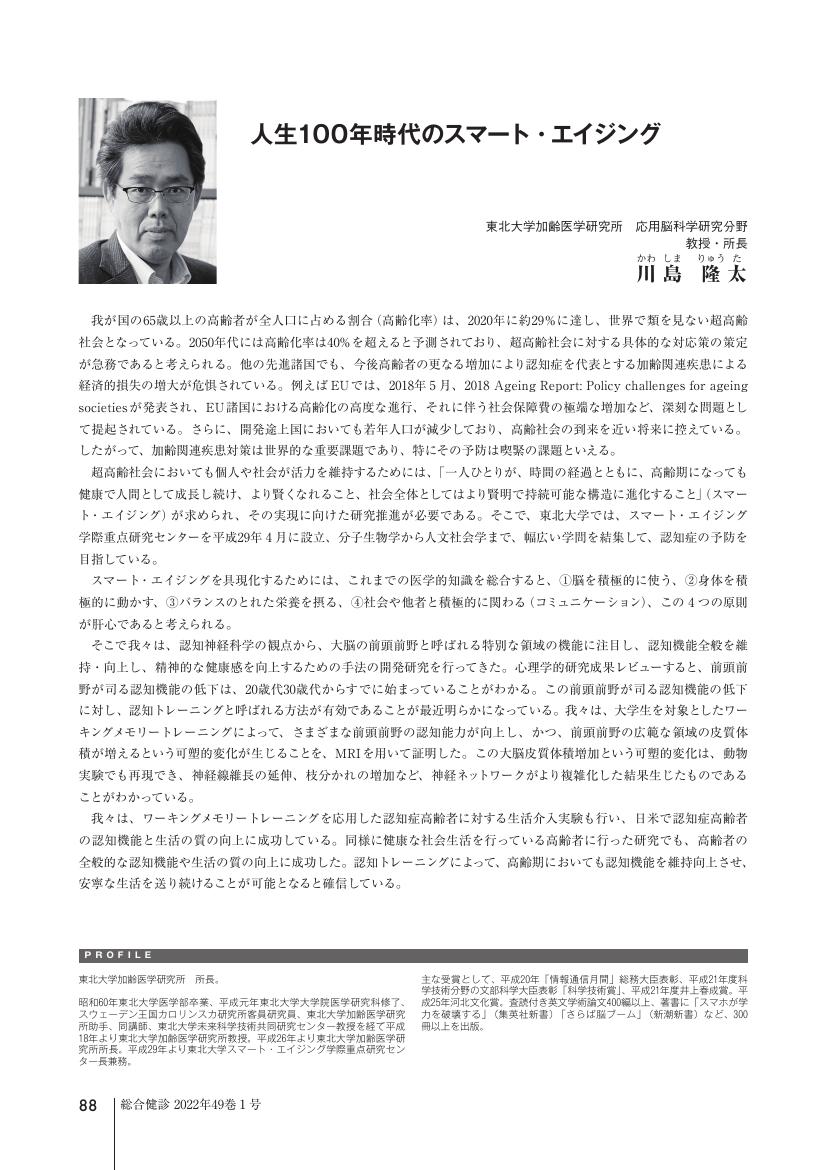1 0 0 0 OA 瀬戸内海はどのような海か
- 著者
- 柳 哲雄
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.6, pp.10-14, 2008-06-01 (Released:2012-02-15)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 OA 量子統計力学における密度行列の展開
- 著者
- 久保 亮五
- 出版者
- 物性研究・電子版 編集委員会
- 雑誌
- 物性論研究 (ISSN:18837808)
- 巻号頁・発行日
- vol.1951, no.38, pp.24-41, 1951 (Released:2009-11-26)
A general theorem is proved on the density matrix of quantum statistics. Let the de sity matrix be ρ {M} =exp [-βΣMl=1Hl], in which the operators Hl's are not always commutable. ρ {M} can be expanded in series of the formρ {M} =ΣMΣmi=0 n≥0 Σ {ml} M--- {mn} Mρ* {mM1} ---ρ* {mn} ρ {M-m1----mn} where. the sets {m1}, --- {mn} are groups of operators chosen from the set {M} and operators belonging to different groups are commutable. The summation is to be taken over all the possible choice of the sets {m1} --- {mn}.ρ {k} is defined byρ {k} = [Π {k} exp (-βHj)] s where suffix s means the symmetrization by changing the order of the products. And ρ* {m} is defined byρ* {m} =Σ {k}l (-) m-k ρ {k} ρ {m-k} which is proved to be 0 (βm+1). the series expansion here proved is very useful in quantum statistics.
1 0 0 0 OA 動態測定による日本語アクセントの解明
- 著者
- 杉藤 美代子
- 出版者
- The Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1969, no.55, pp.14-39, 1969-03-31 (Released:2010-11-26)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 山岳修行僧行尊の伝記と詠歌についての総合的研究
まず行尊の伝記研究では、史実研究と偶像研究との双方を視野に入れて研究を進め、その成果として川崎が「行尊年譜(稿)」を作成した(『研究成果報告書』)。この年譜に基づいて考察すると、史実研究の面では、(1)行尊の宗教活動の中核には護持僧としての活動があり、熊野御幸先達の事績などもその枠組みの中で捉える必要があること、(2)行尊の験功の事例は天台宗寺門派の伝記よりもむしろ『真言伝』に多く記録されており、史実の解明にも有効であることが判明した。他方、偶像研究の面では、(3)天台宗寺門派においては長承三年(1134)園城寺金堂再興供養を最高潮とするかたちで行尊伝が構成されていることが判明し、以後の再興事業において行尊による再興が常に規範とされたことが推測される。上記については研究論文を準備している。次に行尊の詠歌研究では、佐藤がその表現を和歌史上に位置づけるべく試みた(『研究成果報告書』)。行尊の和歌表現は同時代のそれと共通するところが多く、特異な体験によって裏打ちされた特徴的な表現が微温的に現われている、というのが結論である。これらと並行して、行尊が活躍したのと同時期、院政期における他宗の山岳信仰にも目を配り、川崎が南都(興福寺及び真言律宗寺院)における葛木峯=金剛山信仰の展開を跡付けた。なお研究を進めるなかで、行尊の詠歌が、行尊の宗教活動、ひいては後代の天台宗寺門派による偶像化を支える重要な道具として機能したことも一層鮮明となったが、その論証は今後の課題とせざるをえなかった。
1 0 0 0 OA 日本甲殻類学会若手の会第3回自由集会オンライン開催の報告
1 0 0 0 OA 特別講演1「人生100年時代のスマート・エイジング」
- 著者
- 川島 隆太
- 出版者
- 一般社団法人 日本総合健診医学会
- 雑誌
- 総合健診 (ISSN:13470086)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.88, 2022 (Released:2022-04-10)
1 0 0 0 OA ツイート削除最高裁判決の意味するもの -ネット上の権利侵害情報は削除してもらえるのか-
1 0 0 0 OA 芸術作品に見る対数螺旋の効果
- 著者
- 吉田 美穗子
- 出版者
- 梅花女子大学文化表現学部
- 雑誌
- 梅花女子大学文化表現学部紀要 = Baika Women's University Faculty of Cultural and Expression Studies Bulletin (ISSN:24320420)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.112-122, 2021-03-20
図形を回転するとその軌跡は円となるが、等しい倍率で拡大もしくは縮小しながら回転するとその軌跡は螺旋となる。正方形の黄金比を用いた回転を基本として様々な分数の正多角形の外心を中心としてその外角の角度分を、黄金比率の割合で拡大しながら回転させてその軌跡の円弧を繋げていった結果、黄金角である約137.5°に近い外角を持ち、分母・分子が1つ飛びのフィボナッチ数で現わされる正8/3角形、正13/5角形が最もバランスの良い効果的な現れ方をすることをこれまでに確かめた。また、その時の対数螺旋はr = e0.20051θ の式で表され、螺旋の接線と中心からの線とがなす角度は約78.7°であった。本稿ではr = e0.20051θ の式で表される対数螺旋を例に、部分的に、あるいは全体の構図として設計されたであろう作品を挙げ、制作者が絵画を見る者に自分の意図を確実に伝えるために仕組んだ表現手法の一つであることを実証しようとするものである。対数螺旋の効果を予測した、建築・インテリアでのデザインへの応用・転用が望まれる。
1 0 0 0 OA 言語研究の底を流れる思想を考える ―推論様式を手掛かりとして―
- 著者
- 山本 英一
- 出版者
- 関西大学外国語教育研究機構
- 雑誌
- 関西大学外国語教育研究 (ISSN:13467689)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.47-61, 2008-10
Prevailing linguistic theories, whether they are of syntax or of pragmatics, are loadedwith ideas that often leave Japanese linguists perplexed and alienated. At the root of theseideas is a Western metaphysical tradition that dates back to Plato and Aristotle, according towhich divine reality is considered to exist beyond the reach of our sensory perception. Thus,physical objects and physical events are just “shadows”, both temporary and inconsequential,of their ideal or perfect forms, which are inaccessible to those that use only their senses.Since Japanese linguists, however, tend indeed to believe in things that they can perceivewith their five senses, to them such trust in divine reality is incomprehensible.Awareness of this ideal or perfect existence is claimed to be universal, and achievedthrough rationality. This belief often leads major Western linguists to assume that humanbeings are entirely rational and reliably efficient creatures, and blithely to ignore allirrational and inefficient aspects to their communicative behavior. Focusing on several modesof inference that seem relevant to pragmatics, this paper suggests that attention should begiven to non-monotonic reasoning (i.e., a method of inference that allows the production ofmore than one interpretation of an utterance), the idea of which is both non-rational andaslo perfectly palatable to Japanese linguists, whose thinking is quite independent of theWestern metaphysical tradition referred to above.
- 著者
- 藤内 栄太
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- こころの科学 (ISSN:09120734)
- 巻号頁・発行日
- no.154, pp.63-67, 2010-11
- 著者
- 林 直樹
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- こころの科学 (ISSN:09120734)
- 巻号頁・発行日
- no.154, pp.102-104, 2010-11
- 著者
- 岡野 憲一郎
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- こころの科学 (ISSN:09120734)
- 巻号頁・発行日
- no.154, pp.30-35, 2010-11
- 著者
- 中村 由美子
- 出版者
- アークメディア
- 雑誌
- 臨床精神医学 (ISSN:0300032X)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.9, pp.1231-1236, 2010-09
1 0 0 0 OA 教科「情報」の入学試験問題って?:情報システム分野の問題(2)
「第4回中高生情報学研究コンテスト」で上位入賞をした高校生による研究が,どのような環境やプロセスを経て生まれてきたかについて,勤務校の物理部とSSHでの取り組みを例として述べる.STEAM教育の枠組みの中で実践的・創造的に行う情報学研究では,生徒自身の「ワクワク」を原動力にAARサイクルを短期間に何度も回す姿が見られ,生徒の学びに向かう力や情報活用能力の向上には驚くべきものがある.また,質の高い探究が自発的,継続的に行われるためには,外部機関や専門家メンターによる十分な支援環境の中で生徒たちが切磋琢磨しながら学びあい,先輩から後輩へ精神や技術が引き継がれる「学びの生態系」を作っていくことが重要である.
1 0 0 0 OA 携帯情報端末で利用できるバス時刻表示システムの考察
- 著者
- 棚橋 二朗 中岡 快二郎
- 雑誌
- 第60回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.1, pp.235-236, 2000-03-14
1 0 0 0 OA 新しいラドン線量換算係数を考える
- 著者
- 床次 眞司
- 出版者
- 日本保健物理学会
- 雑誌
- 保健物理 (ISSN:03676110)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.282-293, 2018 (Released:2019-03-03)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 3 6
New dose conversion factors (DCF) for radon progeny inhalation have been presented in the latest ICRP publication 137. There used to be a large difference in the DCF between those derived from epidemiological (ICRP 65) and from dosimetric approaches (ICRP 66). In parallel, UNSCEAR has presented their own DCF. The UNSCEAR DCF fell in the two results given by ICRP. This revision results in a higher DCF than before. This is based on the recently new scientific findings obtained by pooled analyses of epidemiological data from European studies on residential radon and lung cancer. Although the publication 137 is used only for occupational exposures, it will be able to be applied because of the consistency. For occupational exposures the new DCF is two times higher than the previous value and is estimated to be 17 nSv per Bq h m-3. It may be different from the previous one by a factor of more than 3 for public exposures (approximately 21 nSv per Bq h m-3). Using the mean indoor radon concentration in Japan, an annual effective dose due to radon progeny inhalation indoors is estimated to be 0.9 mSv a-1. As the DCF is calculated according to aerosol characteristics, site-specific DCFs can be provided.
1 0 0 0 OA ステープルラインに発生した肺MAC症の1例
- 著者
- 小松 弘明 泉 信博 月岡 卓馬 岡田 諭志 戸田 道仁 原 幹太朗 伊藤 龍一 西山 典利
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会
- 雑誌
- 気管支学 (ISSN:02872137)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.130-133, 2018-03-25 (Released:2018-03-29)
- 参考文献数
- 13
背景.肺切除後のステープルラインに発生した腫瘤の鑑別としては,局所再発以外に異物肉芽腫や感染による腫瘤形成が挙げられる.症例.74歳女性.68歳時に,S状結腸癌に対しS状結腸切除術を施行.72歳時に,左肺転移に対し左肺舌区部分切除術を施行.74歳時に,右肺転移に対し右肺上葉部分切除術を施行.右肺切除術後3か月目に,胸部CTで左肺舌区部分切除部のステープルラインに右肺手術時には認められなかった24 mm大の腫瘤が急速に増大し,同部位にFDG-PET検査で異常集積を認めた(SUV max:5.11).診断と治療を兼ねて左肺舌区域切除術を施行した.病理診断は乾酪壊死を伴う類上皮肉芽腫で,切除標本の培養およびPCRでMycobacterium aviumが同定された.右肺術後3か月の間に左肺ステープルラインで急速に腫瘤が増大しており,右肺手術時の人工呼吸器管理/分離肺換気による気道クリアランスの低下が左肺の非結核性抗酸菌感染の顕在化につながったと考えた.結語.ステープルラインに発生した腫瘤の診断は難しく,悪性が否定できない場合は診断と治療を兼ねて切除を検討すべきと考える.