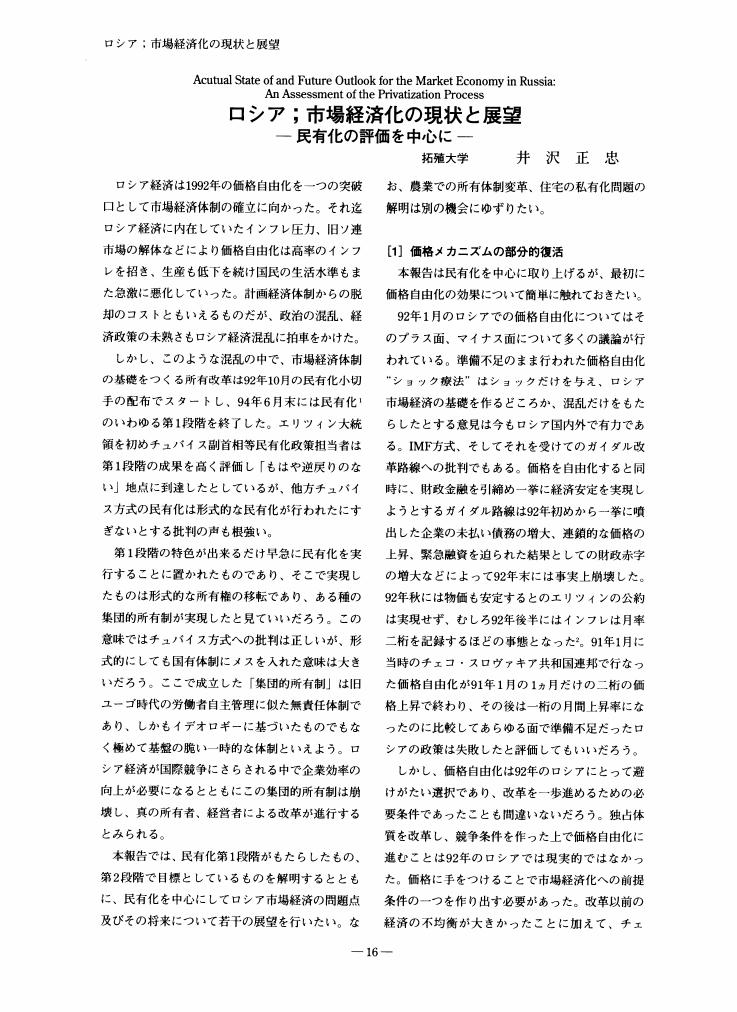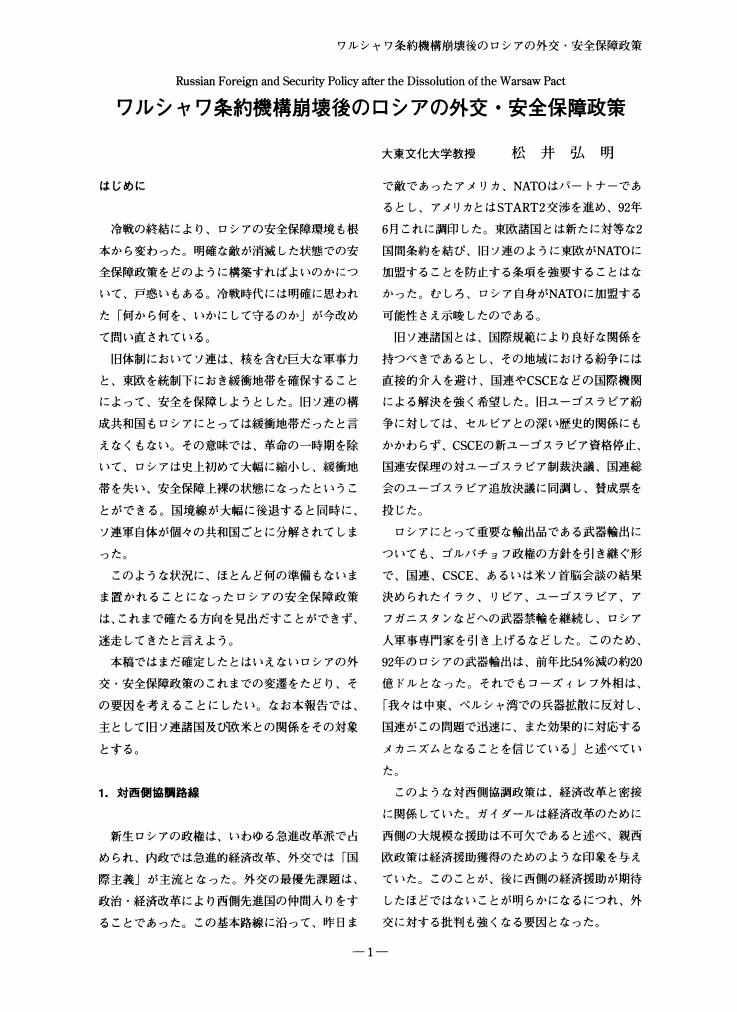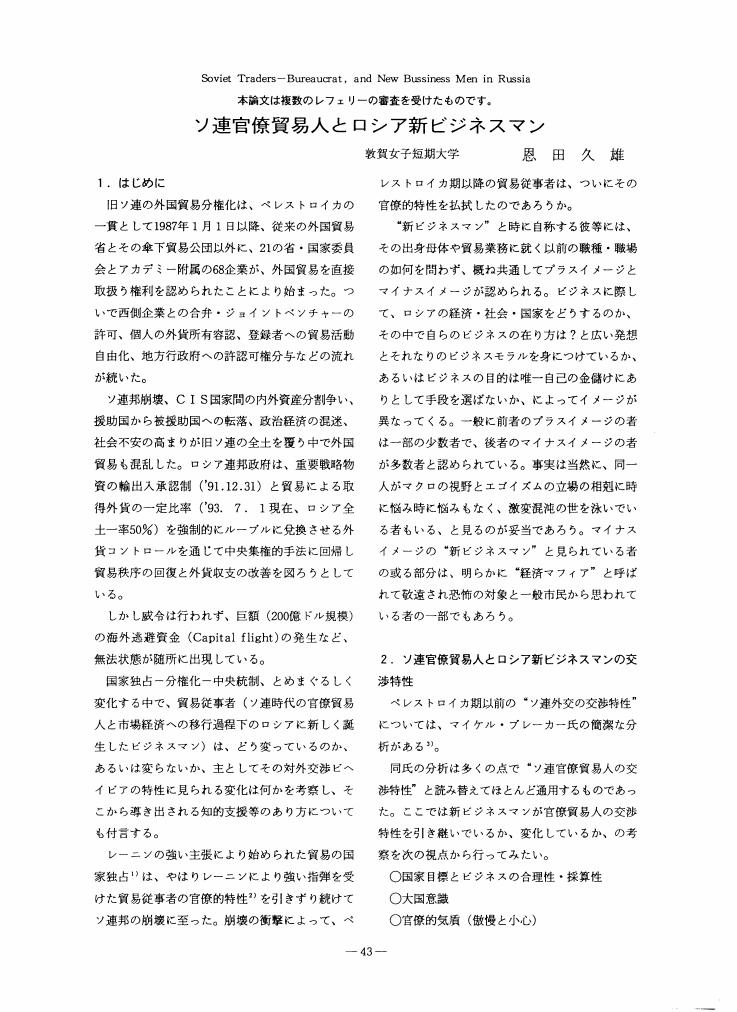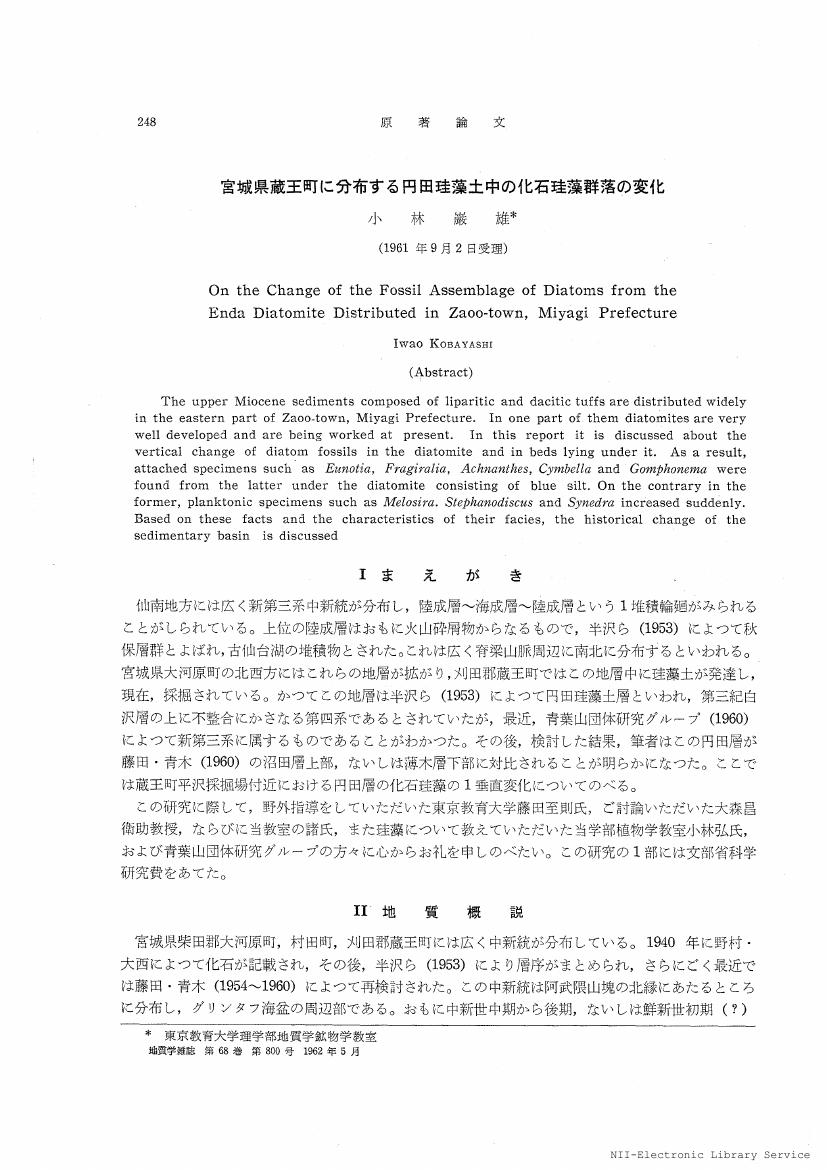1 0 0 0 OA チェコの私有化
- 著者
- 小森 吾一
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧学会年報 (ISSN:21854645)
- 巻号頁・発行日
- vol.1993, no.22, pp.84-88, 1993 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA ロシア; 市場経済化の現状と展望 ―民有化の評価を中心に―
- 著者
- 井沢 正忠
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧学会年報 (ISSN:21854645)
- 巻号頁・発行日
- vol.1994, no.23, pp.16-26, 1994 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 38
1 0 0 0 OA エリツィン政権下のロシア・マスコミ
- 著者
- 鈴木 康雄
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧学会年報 (ISSN:21854645)
- 巻号頁・発行日
- vol.1994, no.23, pp.27-32, 1994 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 OA ポスト共産主義の政治思想の動向
- 著者
- 中村 裕
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧学会年報 (ISSN:21854645)
- 巻号頁・発行日
- vol.1994, no.23, pp.6-15, 1994 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 29
1 0 0 0 OA ワルシャワ条約機構崩壊後のロシアの外交・安全保障政策
- 著者
- 松井 弘明
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧学会年報 (ISSN:21854645)
- 巻号頁・発行日
- vol.1994, no.23, pp.1-5, 1994 (Released:2010-05-31)
1 0 0 0 OA 「移行期 (ソ連からロシアへ) における新たな品質改善策」 ―工作機械工業を中心にして―
- 著者
- 五十嵐 則夫
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧学会年報 (ISSN:21854645)
- 巻号頁・発行日
- vol.1993, no.22, pp.51-59, 1993 (Released:2010-05-31)
1 0 0 0 OA 「混沌の中の宗教界」
- 著者
- 川端 香男里
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧学会年報 (ISSN:21854645)
- 巻号頁・発行日
- vol.1993, no.22, pp.39-41, 1993 (Released:2010-05-31)
1 0 0 0 OA ロシアにおける市場経済化と経営者形成の現段階
- 著者
- 溝端 佐登史
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧学会年報 (ISSN:21854645)
- 巻号頁・発行日
- vol.1993, no.22, pp.1-14, 1993 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 22
1 0 0 0 OA ソ連官僚貿易人とロシア新ビジネスマン
- 著者
- 恩田 久雄
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧学会年報 (ISSN:21854645)
- 巻号頁・発行日
- vol.1993, no.22, pp.43-50, 1993 (Released:2010-05-31)
1 0 0 0 OA ロシアの憲法問題
- 著者
- 松下 輝雄
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧学会年報 (ISSN:21854645)
- 巻号頁・発行日
- vol.1993, no.22, pp.15-26, 1993 (Released:2010-05-31)
- 著者
- 清水平 ちひろ 江川 裕美 近藤 摂子
- 出版者
- 日本皮膚科学会大阪地方会・日本皮膚科学会京滋地方会
- 雑誌
- 皮膚の科学 (ISSN:13471813)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.5, pp.527-533, 2009 (Released:2010-08-22)
- 参考文献数
- 18
2008年4月から同10月までの当院入院症例のうち,疥癬40例に対してイベルメクチン投与と安息香酸ベンジルオイラックス外用を行った。全例が65歳以上であった。イベルメクチン投与中および投与後に有害事象を認めた症例は臨床検査値異常が5例,基礎疾患によると考えられる死亡例が2例あった。このうち臨床検査値異常の5例はいずれも無治療で正常化した。軽度の肝障害を認めた2例に対してもイベルメクチンの内服治療を行ったが,投与後に臨床検査値の悪化は認めなかった。投与回数については疥癬のライフサイクルからは少なくとも2回の投与が望ましいと考えられた。しかし,2回で治癒した例は71%に過ぎず,12例で3回以上の投与を必要とした。疥癬の集団発生では,当院のような高齢者症例の多い場合でも積極的な内服加療が有効であり,比較的安全に使用できることが確認された。
1 0 0 0 OA プログラミング上達を加速させるマスコットキャラクター付き統合開発環境の開発
- 著者
- 浦山 優樹 齋藤 雄人 塩野 駿 竹林 晃 谷口 翔一 門地 翔太 江見 圭司
- 雑誌
- 研究報告コンピュータと教育(CE) (ISSN:21888930)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019-CE-149, no.4, pp.1-6, 2019-02-23
IT エンジニアがプログラミングを始めて間もない頃,一人で統合開発環境のエラーメッセージと向き合ったつらい経験をすることが多い.ここでは初級レベルから中級レベルになるために,統合開発環境へのプラグインでプログラマーにアドバイスを行うことで上達を加速できるようにした
1 0 0 0 機械学習への位相幾何学的アプローチ
学習とは、学習データの入力から出力までのプロセスを多数の学習パラメータで表現し、学習パラメータを変分によって最適化することである。学習のクォリティは大別すると2つの要素で決まっている。すなわち、過学習を避けつつより一般性のある関数空間を扱える表現と、ベクトル空間内で複雑な構造を持った学習データに対する適切な最適化である。本研究では、表現に対するアプローチとしてゲージ場の理論の様々なテクニックを用い、最適化のための入出力データが内在するトポロジカルな特徴に着目することによって、両者に変革的な進歩をもたらすことを目指す。
1 0 0 0 OA 可解カオスの数理と応用(2)―双対性―
- 著者
- 梅野 健
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 応用数理 (ISSN:24321982)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.99-108, 2022-06-24 (Released:2022-09-30)
- 参考文献数
- 12
1 0 0 0 OA 2つの異なる立体表現手法を混ぜたキャラクターアニメーション
- 著者
- 中原 ひかり 松永 康佑
- 雑誌
- エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2020論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, pp.204-205, 2020-08-22
二次元で描かれたイラストを立体的に動かす技術が発展しており、近年多くのコンテンツで利用されている。本研究では、Live2Dを用いたキャラクターの疑似的な立体表現と、従来の3DCGによる立体表現を重ね、それぞれ異なるカメラワークと立体表現の組み合わせによる映像を制作する。異なる立体表現を同時に提示することで得られる空間認識刺激を利用した映像表現手法について報告を行う
1 0 0 0 OA H. リーマンの「ゲネラルバス」理論 通奏低音演奏、機能和声、そして指感覚を整合する試み
- 著者
- 三島 郁
- 出版者
- 日本音楽表現学会
- 雑誌
- 音楽表現学 (ISSN:13489038)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.1-12, 2019-11-30 (Released:2020-11-30)
- 参考文献数
- 28
19世紀におけるドイツ語圏での「ゲネラルバス」という用語は、バロック期の「通奏低音」としてではなく、和声理論にも使われていた。その延長上にフーゴ・リーマン Hugo Riemann (1849–1919) は理論・実践書『ゲネラルバス奏法の手引き(ピアノの和声練習)Anleitung zum Generalbass=Spielen (Harmonie=Übungen am Klavier)』(1889–1917)を出版した。彼はそこでバロック作品の通奏低音についての説明や実践課題も多く載せながら、さまざまな記号を駆使して和声の機能面を強調する。 本稿では、この『手引き』の内容を、リーマンのゲネラルバスの使用法や和声理論教育の方法の観点から分析し、彼のゲネラルバスの捉えかたを考察し、明らかにした。リーマンのゲネラルバス理論は、和音の縦の構成音を示すバロックの通奏低音の理論と、和音の横の流れを示す19世紀の和声理論という、一見逆のシステムをもつようにみえる二つの理論に対して、それらを鍵盤上で実践する指の動きで結びつけることによって整合性をもたせようとしたものである。そのゲネラルバス実践には、機能和声という条件の下でも、指感覚を重んじながら「正しい」進行をすることが求められている。
1 0 0 0 OA 宮城県蔵王町に分布する円田珪藻土中の化石珪藻群落の変化
- 著者
- 小林 巌雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.800, pp.248-254, 1962-05-25 (Released:2008-04-11)
- 参考文献数
- 12
1 0 0 0 OA 急性呼吸不全の患者に対する体位管理の効果の検討―体位管理が酸素化に及ぼす影響―
- 著者
- 江口 玲子
- 出版者
- 福岡赤十字病院 看護部
- 雑誌
- 福岡赤十字看護研究集録
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.26-29, 2012-12-25
1 0 0 0 OA AI エージェントの社会実装における論点の整理 —「AI さくらさん」の事例から—
- 著者
- 藤堂 健世 佐久間 洋司 大澤 博隆 清田 陽司
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.5, pp.638-642, 2020-09-01 (Released:2020-11-02)
1 0 0 0 OA 孫子の兵法と新陰柳生流兵法 ―比較思想的考察―
- 著者
- 笠井 哲
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.40-47, 1988-07-30 (Released:2012-11-27)
- 参考文献数
- 35
The purpose of this article is to compare strategy in the Sonshi School with that in the Shinkage-Yagyu School. In particular, kido or the “tricky way” is compared with hyori or “tactics”, because these two words are key words in both strategies. Kido implies a movement of troops, whereas hyori means action in tachiai or man to man combat. However, hyori was also thought to be applicable to a movement of troops as well. Therefore, it is possible to compare these two concepts.The results of this article are summarized as follows:1) Kido or tricky way in Sonshi means unusuality in the battlefield. Hyori or tactics in the Shinkage-Yagyu School deceives an opponent in tachiai. In this point kido can be considered to be similar to hyori.2) A difference between kido, tricky way, and hyori, tactics, is that kido in Sonshi is just strategy, and has nothing to do with ethics. However, hyori or tactics in the Shinkage-Yagyu School obtains truth through falsehood, has truth in itself, and devises a stratagem. Since hyori in the Shinkage-Yagyu School is suitable for tendo or Natural Reason, hyori is not incompatible with ethics when considering aspects of the Shinkage-Yagyu School.