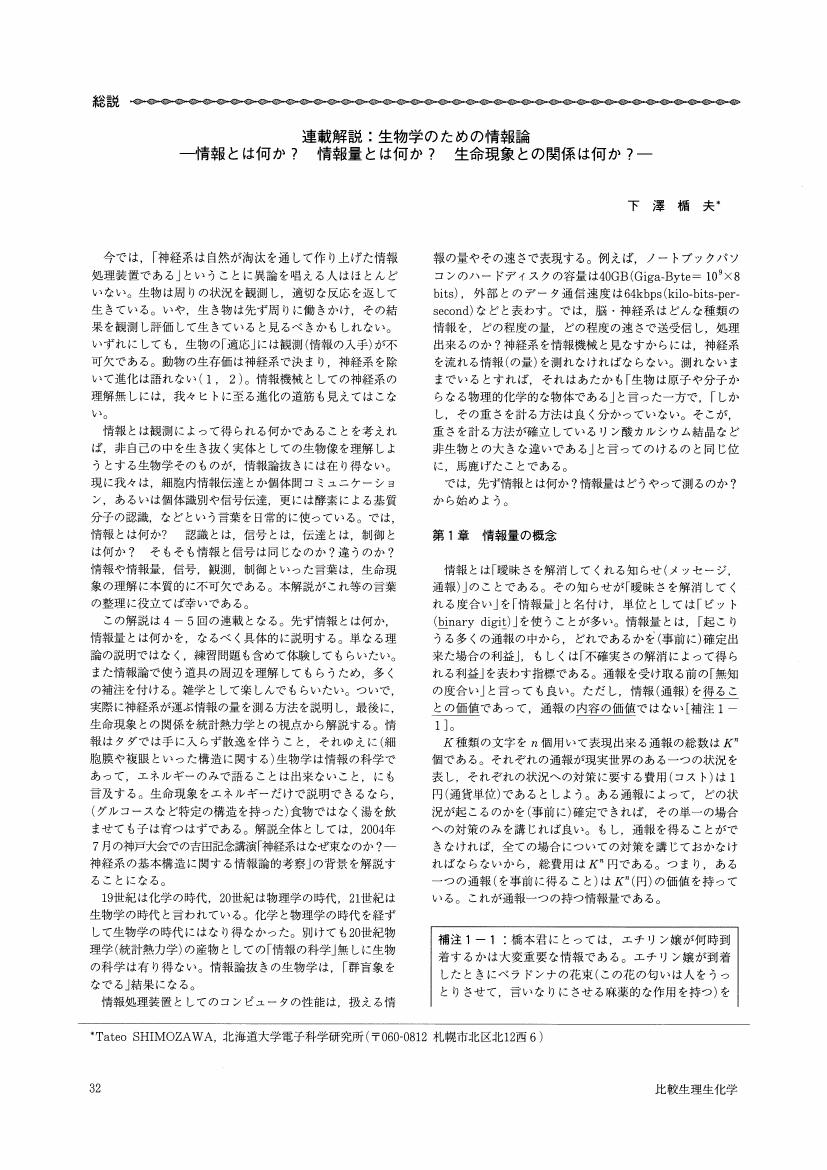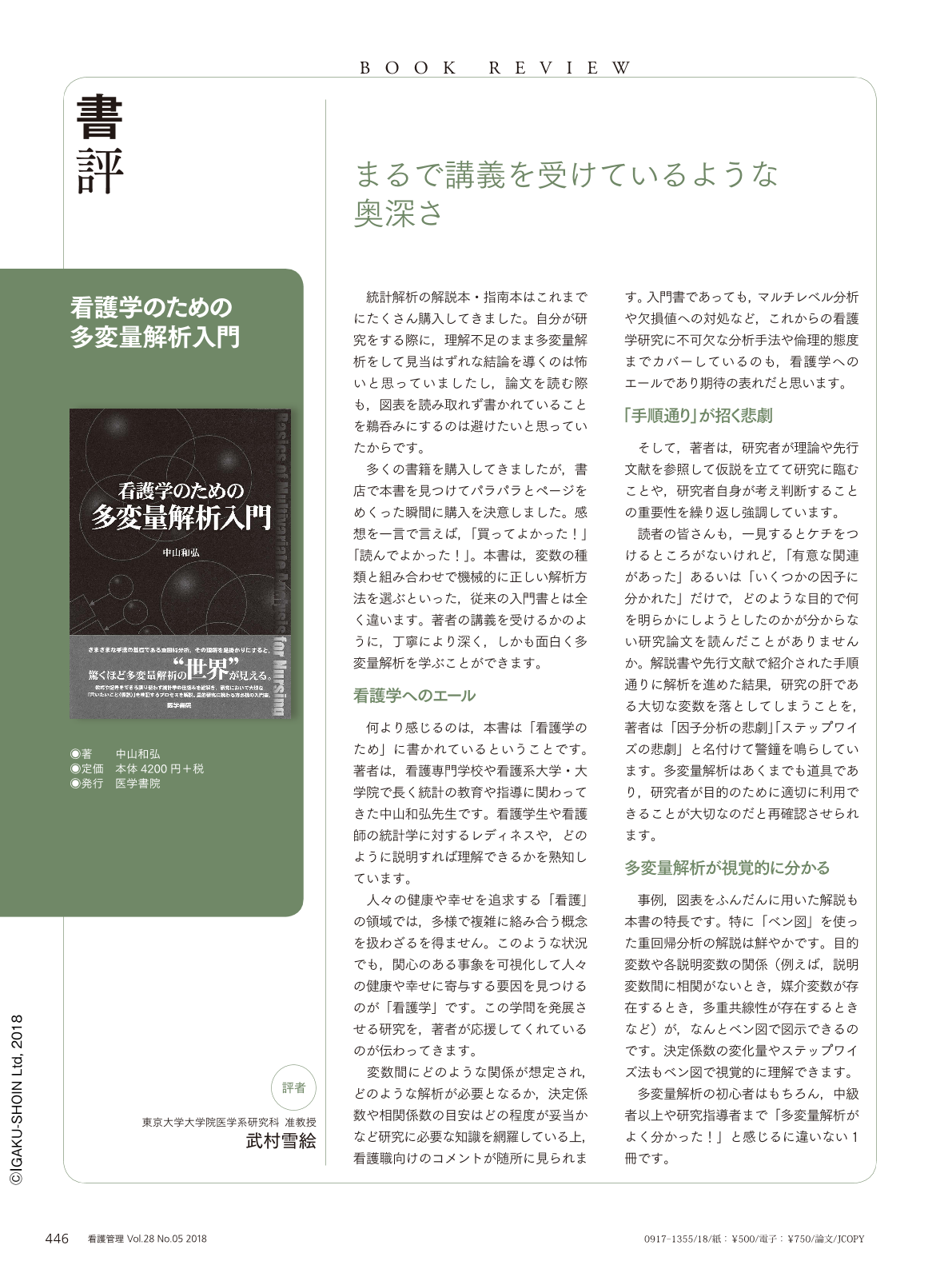8 0 0 0 OA 著作物と作品概念との異同について
- 著者
- 駒田 泰土
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」事務局
- 雑誌
- 知的財産法政策学研究 (ISSN:18802982)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.145-161, 2006-04
8 0 0 0 OA 連載解説: 生物学のための情報論
- 著者
- 下澤 楯夫
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.32-37, 2005-03-31 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 8
8 0 0 0 OA NO作動性神経と勃起障害
- 著者
- 安屋敷 和秀 戸田 昇 岡村 富夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.1, pp.21-28, 2002 (Released:2002-12-10)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 1 1
多くの臓器機能がノルアドレナリン作動性神経とコリン作動性神経による拮抗的二重支配によって生理的調節を受けている.しかし,陰茎海綿体を含む血管系においては,収縮神経であるノルアドレナリン作動性神経に拮抗的支配を行っているのはコリン作動性神経ではなく,非アドレナリン性,非コリン性(NANC)神経と考えられてきた.陰茎海綿体を支配するNANC神経が一酸化窒素(NO)作動性神経であり,同神経の興奮により活性化した神経型NO合成酵素が,NOを合成する.同神経から遊離されたNOが海綿体平滑筋細胞内の可溶性グアニル酸シクラーゼを活性化し,上昇したサイクリック(c)GMPにより海綿体平滑筋は拡張し,流入した血液の充満により勃起が生じる.海綿体内の血液量を調節する海綿体動静脈にもNO作動性神経が分布し,その機能の強さが海綿体>動脈>>静脈であることも勃起の発生に役立つかもしれない.したがって,海綿体洞への血液流入を妨げる動脈閉塞や海綿体や支配動脈を拡張するNO作動性神経機能の低下は,勃起障害(Erectile Dysfunction: ED)の原因となりうる.ただし,海綿体および血管内皮に存在する内皮型NO合成酵素によって合成されるNOも,勃起機能に一部関与する可能性がある.選択的ホスホジエステラーゼ5型(PDE-V)阻害薬であるバイアグラ(Sildenafil)は,主として神経由来のNOにより産生されたcGMPの分解を抑制し,EDを改善する効果があると考えられる.勃起機能の体系的な研究を通して,より選択的で安全なED治療薬の開発が望まれる.
- 著者
- 河崎 陽一 松永 尚 千堂 年昭
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.4, pp.286-290, 2009 (Released:2010-07-30)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 3 3
The hazardous effects of insoluble microparticles generated in injections has been a matter of concern for some time and recently,plastic ampoules have been developed for injection containers as a means of decreasing particle contamination on opening ampoules.To our knowledge,as no studies have been done on insoluble microparticle contamination arising when plastic ampoules are opened,we performed the present study to compare particle contamination from glass ampoules on opening with that from plastic ones and assessed the contribution of the ampoule material to particle generation.We observed that insoluble microparticle contamination from plastic ampoules was significantly lower than that from glass ampoules and therefore conclude that the amount of insoluble particles appears to be relatedtothematerialoftheampouleand recommend using plastic ampoules to prevent microparticle contamination.
8 0 0 0 OA 大学生の卒業研究における研究内容の変容の契機
- 著者
- 正司 豪 尾澤 重知
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会研究報告集 (ISSN:24363286)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, no.3, pp.40-47, 2021-10-29 (Released:2021-10-29)
本研究の目的は,コロナ禍において修士課程に進学予定の大学生を対象に1年間にわたる研究内容の変容の契機を明らかにすることである.本研究では,大学4年生9名に対し半構造化インタビューを行なった.質的な分析の結果,研究内容の変容の契機は,(1)指導教員からの助言 (2)ゼミの先輩からの助言 (3)同じ関心を持つ学外の他者との対話,の3つに類型化することができ,「ゼミの仲間同士の学び」が不十分な事例が見られた.そこで,ゼミにおいて孤立化を防ぐ支援の必要性が示唆された.
8 0 0 0 OA ILO169号条約と国内立法の動向
- 著者
- 中野 育男
- 出版者
- 専修大学学会
- 雑誌
- 専修商学論集 (ISSN:03865819)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, pp.109-118, 2020-01-20
8 0 0 0 OA レファレンス事例・ツール紹介 27 「民国報紙」の探し方
- 著者
- 木下雅弘
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- アジア情報室通報 (ISSN:18840256)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, 2022-09
8 0 0 0 OA 「不正義の景観」デジタルアーカイブにおける日系カナダ人家族の記憶
- 著者
- 稲葉 あや香
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.e11-e15, 2022 (Released:2022-04-04)
- 参考文献数
- 20
本稿は日系カナダ人財産没収を主題とする「不正義の景観(LoI)」アーカイブを事例に、デジタルアーカイブが日系カナダ人の想起に与える影響を考察する。LoIアーカイブは学術資料、日系カナダ人の集合的記憶、家族の記憶という3つの側面を持つ。日系カナダ人ユーザーが書いた記事の分析から、ユーザーにとってLoIの資料が家族史として重要である事が示された。ユーザーは感情に着目することで、財産没収が持つ行政の不正義と家族の過去という側面を、共に個別的な家族の記憶として理解する。このような理解は、より大きな集団の物語と個別的な記憶を競合なく並存させることができるデジタルアーカイブの表現の可能性を示唆している。
8 0 0 0 OA まじなひの研究 : 施術自在
8 0 0 0 OA C・R・ホイッタカー『ロ-マ帝国のフロンティア』
- 著者
- 柴野 浩樹 シバノ ヒロキ Hiroki Shibano
- 雑誌
- 史苑
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.87-100, 1996-03
8 0 0 0 —看護学のための—多変量解析入門
- 著者
- 武村 雪絵
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 看護管理 (ISSN:09171355)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.5, pp.446, 2018-05-10
まるで講義を受けているような奥深さ 統計解析の解説本・指南本はこれまでにたくさん購入してきました。自分が研究をする際に,理解不足のまま多変量解析をして見当はずれな結論を導くのは怖いと思っていましたし,論文を読む際も,図表を読み取れず書かれていることを鵜呑みにするのは避けたいと思っていたからです。 多くの書籍を購入してきましたが,書店で本書を見つけてパラパラとページをめくった瞬間に購入を決意しました。感想を一言で言えば,「買ってよかった!」「読んでよかった!」。本書は,変数の種類と組み合わせで機械的に正しい解析方法を選ぶといった,従来の入門書とは全く違います。著者の講義を受けるかのように,丁寧により深く,しかも面白く多変量解析を学ぶことができます。
- 著者
- 千田和明
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.863, 2022-11
8 0 0 0 OA 温度受容の分子機構
- 著者
- 富永 真琴
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.4, pp.219-227, 2004 (Released:2004-10-01)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 11 8 10
日本に暮らす私たちは1年を通して四季折々様々な温度を感じて過ごしており,さらに,約43度以上と約15度以下は温度感覚に加えて痛みをもたらすと考えられている.私たちはそれらの温度を感じ,意識的・無意識的にそれに対応して熱の喪失や産生等を行っている.外界の温度受容の場合,末梢感覚神経が温度刺激を電気信号(活動電位)に変換してその情報が中枢へと伝達されると考えられているが,温度受容に関わる分子として,哺乳類では6つのTRPチャネル;TRPV1(VR1),TRPV2(VRL-1),TRPV3,TRPV4,TRPM8(CMR1),TRPA1(ANKTM1)が知られており,それぞれに活性化温度閾値が存在する(TRPV1>43度,TRPV2>52度,TRPV3>32-39度,TRPV4>27-35度,TRPM8<25-28度,TRPA1<17度).TRPV1,TRPV4とTRPM8は,その活性化温度閾値が一定でなく変化しうる.TRPV1の活性化温度閾値は代謝型受容体との機能連関によって30度近くまで低下し,体温が活性化刺激となって痛みを惹起しうる.これらの温度感受性TRPチャネルは感覚神経に多く発現しているが,皮膚表皮細胞等ほかの部位に発現しているものもある.この6つの温度感受性TRPチャネルのうち,TRPV1,TRPV2,TRPA1は温度刺激による痛み受容にも関与していると思われる.身近でありながらほとんど明らかでなかった温度受容のメカニズムが受容体分子の発見ととも明らかになりつつある.
8 0 0 0 OA 吾妻鏡 : 吉川本 第1-3
8 0 0 0 合衆国憲法修正一条の表現の自由とヘイトスピーチ
- 著者
- 小谷 順子
- 出版者
- 日本法政学会
- 雑誌
- 法政論叢 (ISSN:03865266)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.160-169, 1999
When racial/sexual harassment became rampant in the U.S. in 1980s, many colleges and universities along with local governments adopted regulations which proscribed hate speech and other fotms of hatred. In 1992, however, the Supreme Court struck down an ordinance banning "fighting words" that insulted or provoked violence "on the basis of race, color, creed, religion or gender." In R.A.V.v.City of St. Paul, the Court stated that the ordinance impermissibly discriminated against unpopular topics. Critics of R.A.V. showed deep concern for the logic of the Court and others provided their reasoning for upholding strictly framed regulations. In this Article, I intend to present outline of the debate on hate speech regulations in the United States. In Chapter II, I overview the anti-regulation argument by presenting R.A.V. and then point out the flaw in its logic. In Chapter III, I turn to the pro-regulation argument and discuss how the proponents of the regulations solves the problem of content/viewpoint discrimination. I then present the harm caused by hate speech, and finally analyze hate speech regulations under the values of the Freedom of Speech.
8 0 0 0 OA 2011 年東北地方太平洋沖地震の震源のモデル化
- 著者
- 川辺 秀憲 釜江 克宏
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震工学会
- 雑誌
- 日本地震工学会論文集 (ISSN:18846246)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.2_75-2_87, 2013 (Released:2013-03-08)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 3 7
2011年東北地方太平洋沖地震(Mw9.0)に対し、経験的グリーン関数法を用いたフォワードモデリングにより工学的に重要な0.1~10秒の周期帯を対象とした震源のモデル化を行った。結果として、宮城県沖から茨城県沖にかけて、5つの強震動生成域からなる震源モデルを提案した。得られた震源モデルにおける5つの強震動生成域は、これらの地域における地震調査研究推進本部による想定震源域内にほぼ含まれていること、強震動生成域のみの地震モーメントは総地震モーメントの5%程度であり、より周期の長い地震動、巨大津波及び地殻変動を説明する震源モデル(海溝軸側に大すべり領域)とは相補的であるとの結果が得られた。
8 0 0 0 OA 親の離婚が子どもの家族形成に与える影響
- 著者
- 永井 暁子
- 出版者
- 日本女子大学社会福祉学科
- 雑誌
- 社会福祉 = Social Welfare (ISSN:02883058)
- 巻号頁・発行日
- no.62, pp.87-100, 2022-03-31
- 著者
- 長尾 徹
- 出版者
- 一般社団法人 日本口腔腫瘍学会
- 雑誌
- 日本口腔腫瘍学会誌 (ISSN:09155988)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.94-102, 2017-09-15 (Released:2017-09-27)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 2 2
口腔咽頭がんの罹患率は,世界全体では全がんの6番目に位置している。いまだに進行がんが多く,その生存率は全がんの平均より低い。口腔がんの早期診断,予防策としての口腔がん検診の科学的根拠はいまだ明らかになっていない。2016年ニューヨークでWHOの共催の下に,Global Oral Cancer Forumと題する口腔がんの早期発見,予防に関する世界会議が開催された。その中で口腔がん検診が重要課題として取り上げられた。口腔がん検診の有効性は,口腔潜在性悪性病変のがん化を予測するsurrogate marker,視覚的検査の補助診断の開発が鍵となる。歯科診療所におけるハイリスク(喫煙)グループの個別型口腔がん検診は増分費用効果比の算出から費用対効果は高いと評価されている。一方で,喫煙習慣を有する集団をいかに定期的に歯科診療所の検診の場に勧奨するか,個別検診をどこでどのように実施するか今後の研究を検討する必要がある。
8 0 0 0 OA サハリンの言語世界 : 単語借用から見る
- 著者
- 津曲 敏郎
- 出版者
- 北海道大学大学院文学研究科
- 雑誌
- サハリンの言語世界 : 北大文学研究科公開シンポジウム報告書
- 巻号頁・発行日
- pp.1-10, 2009-03-08
本稿ではまずサハリンの言語状況を概観し、特に近年のウイルタ語をめぐる動きを紹介する。次にサハリンの先住民言語の間に見られる単語の相互借用について、先行研究からいくつかの例を紹介するとともに、あらたな事例を提供する。最後に、単語借用以外の文法面や口頭文芸においても影響関係が見られることにふれ、「言語地域」としてのサハリンの重要性を指摘する。