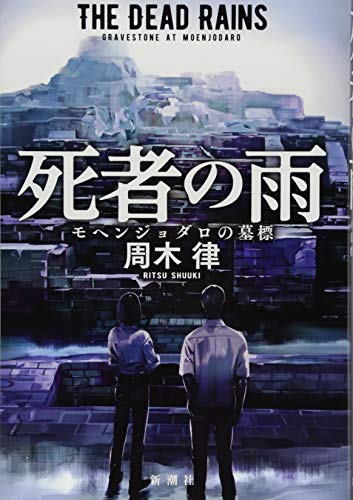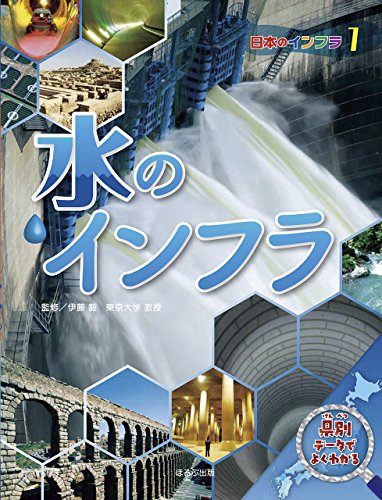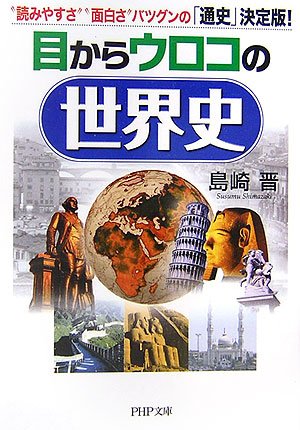1 0 0 0 死者の雨 : モヘンジョダロの墓標
1 0 0 0 ガンダーラとモヘンジョダロ : 平山郁夫のスケッチブック
1 0 0 0 インダス文明の社会構造と都市の原理
1 0 0 0 インダス文明とモヘンジョダロ展
- 著者
- サンケイ新聞大阪本社編
- 出版者
- サンケイ新聞大阪本社
- 巻号頁・発行日
- 1986
1 0 0 0 IR 文学と政治の間で--戦時中のオ-ウェル
- 著者
- 照屋 佳男
- 出版者
- 早稲田大学社会科学部学会
- 雑誌
- 早稲田人文自然科学研究 (ISSN:02861275)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.p83-107, 1986-03
論文
1 0 0 0 OA 水戸藩における定府進展に伴う城下町および江戸藩邸の変容
- 著者
- 岩本 馨
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.560, pp.305-310, 2002-10-30 (Released:2017-02-04)
The purpose of this paper is to analyze the "Jofu" system of Mito-han, which means settlement in Edo. The main contents of this paper are as follows. a) From the beginning of the Tokugawa shogunate, lord usually lived in the Edo estate, and then, in the eighteenth century, vassals of Mito-han began to immigrate to Edo. At first, immigration was encouraged by lord. b) However, the advance of immigration was too rapid to be controlled, and the system of the castle city and the Edo estate had to be transformed critically.
1 0 0 0 IR ジョージ・オーウェルのイデオロギー : BBC時代のプロパガンダ
- 著者
- 田辺 翔平
- 出版者
- 龍谷大学大学院英語英米文学会
- 雑誌
- 英語英米文学研究 (ISSN:02862352)
- 巻号頁・発行日
- no.41, 2013-03-31
1 0 0 0 OA 水戸藩の香統
- 著者
- 堀口 悟 鈴木 健夫 村田 真知子 Satoru Horiguchi Takeo Suzuki Machiko Murata
- 出版者
- 茨城キリスト教大学
- 雑誌
- 茨城キリスト教大学紀要 I.人文科学 = Journal of Ibaraki Christian University I. Humanities (ISSN:13426362)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.197-217, 2019
When the four volumes of the Book of the Way of Incense (Kōdōsho) in the collection of the Mito City Museum were shown to the public for the first time in 1992, Akiyama Takashi contributed the introductory essay for the occasion. In this essay, Akiyama expressed doubts on the theory endorsed so far by Nishiyama Matsunosuke in his Iemoto seido no kenkyū(Research on the iemoto system)published in 1982 by Yoshikawa Kōbunkan, although he fell short of producing evidence against it. Nishiyama had stated that inside the domain of Mito, approximately the same territory as today’s Ibaraki prefecture, in regard to new disciples for the Shino School of incense “not even one was to be found for the entire period [of the Mito feudal domain]. It is thus conceivable that the way of incense was not accepted by the milieu in the Mito domain that developed Mitogaku”.In our research, drafted by three authors, we thoroughly examined the four volumes of the Book of the Way of Incense, consisting of Mito-shi hakuzō Kōnoki-jo (Introduction to Ko-awase, an incense matching game- Mito City Museum), Mito-shi hakuzō Kotokumikō (The earlier ten kinds of kumikō - Mito City Museum), Mito-shi hakuzō Hachikumikō (The eight kinds of kumikō- Mito City Museum) and Kōdō meikan (Compendium of the Way of Incense). While taking into account the previous studies by Midorikawa Fumiko and others, we also considered the historical documents of the Mito domain, with the purpose of investigate the relations between the domain of Mito and the way of incense in the early modern era (1603-1867).On one hand, we proceeded to reprint and revise the four original volumes of the Mito City Museum, adding explanatory notes, a translation into modern Japanese and related essays. The book we are currently writing with these contents will be entitled Kinseishoki no Kō-bunka (The culture of the incense in the early modern period) and its publication is planned for March 2020. It intends to clarify the culture of the incense in Kyoto (cultural capital) and in Mito (province) in the early modern period, from the year 1603 to the year 1700.On the other hand, in the present paper titled The incense tradition in the Mito domain we have broadened the outlook to the whole early modern period and considered the above-mentioned theory by Nishiyama.Consequently, it came to light that the first daimyō (feudal lord) of the Mito domain Tokugawa Yorifusa was enthusiastic about the way of incense, wrote a book himself on the subject and presented it to the Emperor Go-Mizunoo. Furthermore, Tokugawa Mitsukuni, the second daimyō of the Mito domain, presented the Emperor Go-sai with the book Fusō-shūyōshū, while both the fourth daimyō Munetaka and the eight daimyō Narinobu showed interest in the art of incense. The analysis of the documents also revealed that two vassals of Yorifusa, Okajima Matayuki and Iio Biku were practicing and researching the way of incense, proving that the tradition of incense continued until the latter part of the Edo period.However, regarding the way of incense in the Mito domain there are still aspects needing further investigation, which prevent us to reach a full clarification of the matter. Therefore, we are hereby releasing our findings in the form of research notes.
1 0 0 0 尿道脱の手術
尿道脱とは女子尿道粘膜が外尿道口より反転脱出した状態で,粘膜が全周にわたり脱出した完全(輪状)尿道脱と部分的尿道脱に区別される。いずれも外尿道口にイチゴ状の軟らかい赤色の腫瘤として認められる。時間の経過とともにうつ血,浮腫を来し腫瘤は増大するが,いずれの場合でも膀胱内にカテーテルの挿入可能なことにより診断は容易である。治療として,a)保存的整復術,b) Fritsch氏結紮法,c)切除術,の3方法がある。整復術についてはBalloon catheterを用いて還納整復させる方法が好結果を得ている報告1)があるが,一般には再発しやすく,またFritsch氏結紮法を推奨する報告2)も見られるが,最も普通に行なわれているのは切除術である。
1 0 0 0 OA 国際会議報告:The 34th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (IEEE MEMS 2021)
- 著者
- 菅 哲朗
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌E(センサ・マイクロマシン部門誌) (ISSN:13418939)
- 巻号頁・発行日
- vol.141, no.4, pp.NL4_1, 2021-04-01 (Released:2021-04-01)
1 0 0 0 OA 図書館だよりNo.184
- 著者
- 近畿大学中央図書館
- 雑誌
- 図書館だより = Tosyokan Dayori
- 巻号頁・発行日
- no.184, pp.1-4, 0000
1 0 0 0 OA 図書館だより号外
- 著者
- 近畿大学中央図書館
- 雑誌
- 図書館だより = Tosyokan Dayori
- 巻号頁・発行日
- no.号外, pp.1-2, 2021-04-02
- 著者
- 尾上 栄浩 神崎 雄一郎 門田 暁人
- 出版者
- FIT(電子情報通信学会・情報処理学会)運営委員会
- 雑誌
- 情報科学技術フォーラム講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.261-266, 2012-09-04
1 0 0 0 IR 近世の白話小説訓訳本に関する日本語史的研究
- 著者
- 葭内 ありさ
- 出版者
- 日本家庭科教育学会
- 雑誌
- 日本家庭科教育学会大会・例会・セミナー研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.60, 2017
<strong>目的 </strong><br /> 本研究は、高校家庭科において、知的障がい者通所福祉施設と外部連携し、知的障がい者の織ったさおり織を用い、ITを活用した交流を通じて、高校生の障がい者への理解を深め、多様性、ダイバーシティを尊重する視点の育成を試みたものである。 <br /><strong>背景</strong><br /> 2016年4月に「障害者差別解消法」が施行され、障がい者への合理的配慮を求める事が法的にも定められた。障がいの有無、ジェンダー、宗教、民族、人種、性的志向など個人の違いの幅による多様性を生かした共生社会を目指すダイバーシティ教育が一層求められるようになったと言える。一方で、中学迄の義務教育段階と異なり、高校段階では特別学級は設置されていない。義務教育段階でも、必ずしも特別学級との交流が図られている訳ではない中、高校段階に於いては教育の中で意識的に障がい者との交流を図らなければ、障がい者理解の機会を得る事は一層容易くない。<br /> そこで本研究では、対象を必修2年「家庭総合」3クラス120名とし、通常施設との交流に於いて人数や距離に制約のある点を、ITを活用することで克服を試み、必修科目に於いて全員で障がい者施設との交流を図った。特に、魅力的な個性を生かすさおり織を用いることを通じて、障がい者への視点を育むことに着目した。<br /> なお、さをり織は、城みさを氏が考案した、糸の緩さや糸の選び方、編み方において各自の個性を生かし自己を表現する、「差」を織り込む織物である。リサイクルの余糸を繋ぎ合わせたものが織用の糸として用いられているため環境にも優しい。障がい者施設の作業所でも多く取り入られている。<br /><strong>方法</strong><br /> 埼玉県の知的障がい者通所福祉施設と連携した。作業所で織ったさをり織を用いた服を高校生が作り、さらにその服を紹介する動画を班で製作し、福祉施設で上映会を行い、その際インターネットビデオ通話を用いて東京の高校と埼玉の施設を繋ぎ、施設見学や通所の障がい者、施設職員の方々と高校生との双方向の交流を行い、事前事後のアンケート調査と感想の分析を行った。<br /> なお、本研究は、2011年度より実践を重ねる、消費の背景に着目するエシカル・ファッションを用いた、消費者教育の一貫であり、家庭科教育学会において発表済みである(葭内、2014、岡山大学/葭内、2015、鳴門教育大学/葭内、2016、新潟朱鷺メッセ)。2016年度の本研究は、科学研究費奨励研究の助成により行った。<br /> 世界的に厳しい基準のGOTS認証を取得した有機綿花を、日本が誇る高い技術を持つ日本綿布社が織ったオーガニックコットンの布を用いた服をまず製作し、さをり織をアレンジした。動画は製作した服を紹介するのに留まらず、エシカル・ファッションのプロモーションイメージビデオとして製作した。動画は、ユニバーサルデザインを目指し、文字による説明を入れ、グローバル対応として可能な限り英語訳も加えた。10人グループで製作した動画は、クラスで中間発表会を行い、アドバイスを互いにすることで、内容の充実を図った。最終完成作品はクラス発表会を行い、生徒による相互評価やアドバイスを行い、各クラスで優れた動画2本が選ばれ、福祉施設で上映された。また、福祉施設併設のパン工房とカフェで販売されるクッキーをインターネットによる施設見学時に高校生が試食した。<br /><strong>結果</strong><br /> 高校生は、服の製作段階に於いて、さをり織を魅力的に感じ、個性豊かなアレンジの服が完成した。事前調査では、障がい者福祉施設への事前知識がある生徒の方が施設への関心がある割合が高く、知識と施設への関心は相関関係にあることがわかった。高校生の感想からは、通所の障がい者の作業の様子や生徒へのメッセージや感想、自分たちの作った動画への好意的な反応への喜び、その他の双方向の交流により、障がい者への理解を深め、多様性を認め合う共生社会への視点が育まれたことがわかった。
1 0 0 0 高齢者結核の問題 : 高齢者施設の集団感染を経験して
- 著者
- 倉渕 隆 鳥海 吉弘 平野 剛 遠藤 智行 栗林 知広 小峯 裕己
- 出版者
- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 空気調和・衛生工学会 論文集 (ISSN:0385275X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.117, pp.1-10, 2006-12-05 (Released:2017-09-05)
- 参考文献数
- 19
建築基準法の改正に伴い,居室には原則として機械換気設備の設置が義務付けられることとなったが,現状では地域性や建物性能に対応した換気システムの適切な選択方法が整備されていない状況にある。本研究では,住宅に設置される各種常時換気設備について,外界気象条件や建物気密性能による問題点と改善対策を解明することを目的とし,戸建住宅を対象とした年間に渡る換気シミュレーションによる検討を実施した。その結果,第1種換気設備-本体給排気では建物気密性能によらず良好な換気充足度の評価を得ることができるが,第1種換気設備-居室給排気および第2種換気設備-居室給気では2階居室の空気汚染が問題になること,第3種換気設備-水周り排気では2階の新鮮外気の給気量不足が問題になることなどを明らかにし,考えられる改善対策の効果について検討した。
1 0 0 0 OA 「轉禍爲福」 ─ポストコロナ時代と栄養学─
- 著者
- 村山 伸子
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.1, pp.1-2, 2021-02-01 (Released:2021-04-05)
- 参考文献数
- 3