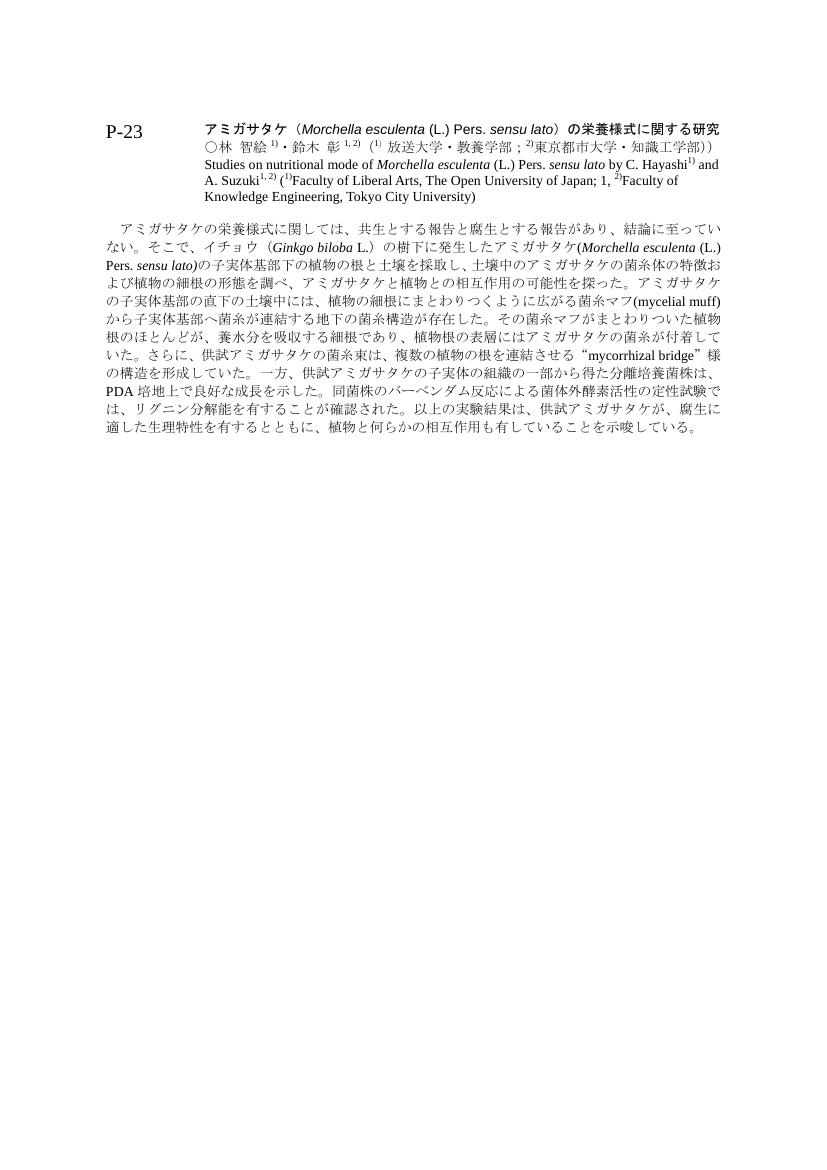1 0 0 0 OA 親から幼児へと向けられる食塩摂取意識に関するアンケート研究
- 著者
- 吉田 心 佐藤 慎太郎 川俣 恵利華 川俣 幸一
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.1, pp.27-36, 2021-02-01 (Released:2021-04-05)
- 参考文献数
- 26
【目的】本研究の目的は,保護者自身への食塩摂取意識と子どもへ向けられる意識との関係を明らかとし,効果的な食育活動に繋がる保護者側の因子を探ることであった。【方法】対象は宮城県の子育て広場に通う103人の幼児とその保護者であった(親の平均年齢34.6歳,子どもの平均年齢2.7歳)。親自身の食塩量に関する意識を問う14項目,それと対になる子どもへの食塩量に関する意識を問う14項目のアンケート調査を実施した。結果は単純集計後,二項ロジスティック回帰分析を実施するために因子分析にて総合数値を求めた。【結果】子どもへの食塩量の意識と,親自身の食塩量の意識を比較したところ,14項目中12項目で意識の違いが見られた。因子分析後に実施した保護者と子どもの年齢,保護者の性別,アンケート13項目とで調整した二項ロジスティック回帰分析の結果では,味の付いたご飯,ルーのかかったご飯,スナック菓子の食塩量について有意な回帰式が得られた(それぞれp=0.024,p=0.044,p=0.011)。【結論】子どもへ向けられる食塩摂取量の意識と親自身の食塩摂取量の意識については全ての項目で有意な正の相関を示し,殆どの項目で子どもに向けられた意識の方が親自身の意識よりも有意に高かった。また多変量解析の結果,子育てのための食塩指導を親向けに開催する場合,味の付いたご飯,ルーのかかったご飯,スナック菓子の食塩量について指導することが,効果的な食育活動の一つとなることが示唆された。
- 著者
- 林 智絵 鈴木 彰
- 出版者
- 日本菌学会
- 雑誌
- 日本菌学会大会講演要旨集 日本菌学会第62回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.90, 2018 (Released:2019-04-17)
1 0 0 0 OA ラドンによる断層推定の可能性
- 著者
- 下 道國
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.7, pp.477-478, 1996-07-15 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 滑稽演説会 : 吃驚仰天
- 著者
- 斎藤勇雄 (漫言居士) 著
- 出版者
- 後凋閣
- 巻号頁・発行日
- 1888
1 0 0 0 OA ピエゾ方式インクジェットプリンタの技術動向
- 著者
- 酒井 真理
- 出版者
- 一般社団法人 日本画像学会
- 雑誌
- 日本画像学会誌 (ISSN:13444425)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.167-173, 2002 (Released:2006-07-01)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 6
- 著者
- 吉留 大樹 石井 靖彦 小野田 弘士
- 出版者
- 一般社団法人 環境情報科学センター
- 雑誌
- 環境情報科学論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.252-257, 2020
<p><tt>国内の戸建住宅における省エネ基準は,設計時の外皮性能および一次エネルギー消費量のみで評価されるため,施工技術や断熱施工精度による影響の実態が明らかになっていない。そこで,本研究ではあるモデルハウスにおける温湿度・HEMS データの実測評価および標準住宅モデルにおける熱収支シミュレーションの分析により,施工技術や断熱施工精度の影響を定量的に評価した。その結果,現行基準やトップランナーの住宅では施工技術や断熱施工精度の影響が大きく,除霜期においてはその熱損失が6 割以上を占めることが示された。</tt></p>
1 0 0 0 OA 清酒用麹菌の遺伝子操作技術
- 著者
- 五味 勝也
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.7, pp.494-502, 2000-07-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2 2
- 著者
- 清水 哲郎
- 出版者
- 東北哲学会
- 雑誌
- 東北哲学会年報 (ISSN:09139354)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.65-72, 1994
- 著者
- Keiichiro Kagawa
- 出版者
- The Institute of Image Information and Television Engineers
- 雑誌
- ITE Transactions on Media Technology and Applications (ISSN:21867364)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.114-121, 2021 (Released:2021-04-01)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 4
Multi-tap CMOS pixels that are composed of a single photodiode, multiple sets of a charge transfer gate and storage diode, and a draining gate can implement functional imaging. In this paper, imaging systems based on the multi-tap CMOS pixel are categorized into those with synchronized active illuminations and those using coded exposure. Applications for quantitative wide-field imaging based on spatial frequency domain imaging (SFDI) using structured light projection and multi-exposure laser speckle contrast blood flow imaging (MELSCI) utilizing multiple exposure times are shown. The multi-tap CMOS pixel provides additional benefits like suppression of ambient light and motion artifact with SFDI and efficient sampling at a video rate with MELSCI.
1 0 0 0 家庭生活の歓び
- 著者
- Th.ボヴェー[著] 三浦安子訳
- 出版者
- ヨルダン社
- 巻号頁・発行日
- 1979
1 0 0 0 IR On the Wheel Falling : Fortune in Wyatt's Poems(Chugoku-Shikoku Studies in English Literatrue)
- 著者
- 楠木 佳子
- 出版者
- 日本英文学会中国四国支部
- 雑誌
- 英文学研究 支部統合号 (ISSN:18837115)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.301-311, 2009
- 著者
- Taku Harada Yukinori Harada Taro Shimizu
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.6736-20, (Released:2021-03-22)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 3
Exposure to quinolones is known to be an independent risk factor for aortic dissection; however, the association with vertebral artery dissection remains unclear. We report two cases of vertebral artery dissection that occurred 4 and 8 days after exposure to levofloxacin, respectively. Both patients had risk factors for vertebral artery dissection, and quinolone use could have been avoided. These two cases indicate that quinolone exposure can be a risk factor for vertebral artery dissection. Considering the possible mechanism, it is better to avoid the prescription of quinolones to patients who have insufficient connective tissues to avoid vertebral artery dissection.
1 0 0 0 しょう油業界に思う
- 著者
- 小手川 力一郎
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.11, pp.897-898, 1972
1 0 0 0 OA 対数正規分布の応用
- 著者
- 清水 邦夫
- 出版者
- Japanese Society of Applied Statistics
- 雑誌
- 応用統計学 (ISSN:02850370)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.55-59, 1988-09-30 (Released:2009-06-12)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 麦麹のフェノール性物質について
- 著者
- 栗林 義宏
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.12, pp.549-552, 1967
- 被引用文献数
- 1
(1) 麦麹抽出液のフェノール性物質の検出に1次元ペーパークロマトグラフィーを行なった。展開溶剤としてベンゼン:エタノール:2-ブタノール:N-アンモニア(30:30:30:10v/v)系がバニリン酸,フェルラ酸,バニリンの分離にすぐれていることを見出した。<BR>(2) 麦麹のフェノール性物質として従来未知のバニリン酸,フェルラ酸およびバニリンの存在を証明した。<BR>(3) 麦麹のくり香ようのにおいは,これらフェノール性物質が一因子と考えた。
1 0 0 0 IR 堕胎罪についての若干の考察
- 著者
- 谷脇 真渡
- 出版者
- 桐蔭法学会
- 雑誌
- 桐蔭法学 (ISSN:13413791)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.1-21, 2014-05
1 0 0 0 介助犬使用が肢体障害者に及ぼす効果の検討
- 著者
- 石川 智昭 神沢 信行 高柳 友子 三浦 靖史
- 出版者
- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION
- 雑誌
- 日本理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.48101833-48101833, 2013
【背景】 国内での介助犬は90年代初めに誕生した。当時は介助犬に関する法律はなく、一般家庭のペットと同じ扱いであったため、介助犬使用者(以下、使用者)が外出時に入店拒否や公共交通機関の乗車拒否を多く経験し、介助犬の存在が反って使用者の外出時の障害になっていた。そのような状況を改善するために、2002年に身体障害者補助犬の育成や利用円滑化の促進を目的とした身体障害者補助犬法が制定され、盲導犬に加えて介助犬と聴導犬が法律で認められた。また2007年に改訂され、相談窓口の設置と従業員56人以上の民間企業の補助犬受け入れが義務化された。さらに育成に関しては、2009年に国内初の介助犬総合訓練センターが愛知県に開設され、ハード面における環境整備は進んでいる。 しかし、介助犬実働数は2012年11月時点で61頭に留まっている。この理由として、リハ専門職における介助犬の認知度が低く、リハ専門職から肢体障害者への介助犬に関する情報提供が圧倒的に少ないことも普及を妨げている一因と考えられる。【目的】 我々は第44・45回学術大会において、介助犬使用者の心理的QOLが高いことを報告し、介助犬使用が高い心理的QOLに関連している可能性を示唆した。さらに、第46回学術大会において、介助犬使用が肢体障害者に及ぼす効果について、前向き調査を5名の使用者を対象として実施し、介助犬使用が肢体障害者の心理的QOLと身体的QOLの一部を高めることを報告しているが、今回、調査人数を10名まで拡大したので報告する。【方法】 2009年1月~2012年11月に、本研究に同意の得られた介助犬使用予定の肢体障害者を対象に実施した。調査方法は使用前の1例のみ郵送で実施し、その他は直接対面してADL評価、QOL評価、不安・抑うつ評価を調査した。調査項目は、functional independence measure (FIM)、Barthel Index (BI)、instrumental activities of daily living (IADL)、MOS 36 Item Short Form Health Survey version2 (SF-36v2)、sickness impact profile (SIP)、state trait anxiety index (STAI)、self-ratingpdepression (SDS)を実施した。統計解析はウィルコクソン符号順位和検定を用い、有意水準は5%未満とした。【倫理的配慮、説明と同意】 本研究はヘルシンキ宣言に則り、必要な倫理的配慮を十分に行った上で同意の得られた介助犬使用予定者を対象とした。【結果】 調査対象は肢体障害者10名(性別:男性4名、女性6名)、年齢は44.9±15歳(23-68歳)、疾患は、頸髄損傷2、胸髄損傷1、脳出血1、ミエロパチー1、アミロイドポリニューロパシー1、脊髄係留症候群1、筋ジストロフィー1、脳性麻痺1、線維筋痛症1に、介助犬使用者認定前の5.0±5.7ヶ月と認定後の9.0±5.5ヶ月の時点に実施した。ADL評価は、BI、FIM、IADL共に変化を認めなかった。QOL評価の変化は、SF-36v2では、身体機能Δ7.74点(p<0.05)、日常役割機能Δ4.77点(p=0.31)、体の痛みΔ4.11点(p=0.20)、全体的健康感Δ4.56点(p=0.13)、活力Δ3.99点(p=0.15)、社会生活機能Δ7.89点(p=0.09)、日常役割機能(精神)Δ10.20点(p=0.059)、心の健康Δ9.30点(p<0.05)であった。 SIP(低値ほどQOLが高い)では、全体得点はΔ-8.27点(p<0.05)、身体領域得点はΔ-11.96点(p<0.05)、心理社会領域得点はΔ-6.59点(p=0.18)、独立領域得点はΔ-5.78点(p=0.16)であった。有意な改善を示したのは、SIP各項目では、身体領域のうち、可動性Δ-18.31点(p<0.05)、移動Δ-24.71点(p<0.05)、心理社会領域のうち、社会との関わりΔ-10.73点(p<0.05)であった。統計学上、有意でなかったが改善傾向を示したのは、心理社会領域の情緒Δ-14.39点(p=0.08)であった。 介助犬使用前におけるSTAI状態不安は39.05±8.96、STAI特性不安は41.75±9.70、SDSは42.10±9.10で、使用前から不安や抑うつはから認めず、認定後も同様であった。【考察】 介助犬使用介入前後の比較結果から、介助犬使用は、心理的QOLと肢体障害者の移動や可動性などの身体的QOLを向上させること、さらには社会的QOLである社会相互性も向上させることが明らかになった。肢体障害者の身体的QOLが改善することで、行動範囲が拡大し外出の機会が増え、人との関わりが増えることが社会的QOLの改善の理由として考えられた。これらの結果より、介助犬使用は、肢体障害者の社会参加に寄与することが示唆された。【まとめ】 介助犬の使用は、肢体障害者の身体的QOLと心理的QOL、更には社会的QOLの改善に寄与する。【理学療法学研究としての意義】 肢体障害者のQOL向上の一手段として、介助犬の有用性に関するエビデンスを確立することにより、リハ専門職の介助犬に対する認知度を向上させ、さらに介助犬の普及を促進するために、極めて重要な研究である。
- 著者
- 赤松 利恵 串田 修 高橋 希 黒谷 佳代 武見 ゆかり
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.1, pp.37-45, 2021-02-01 (Released:2021-04-05)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
【目的】「健康な食事・食環境」認証制度における外食・中食部門の応募促進と継続支援に向けて,スマートミールの提供状況と事業者が抱える課題を整理すること。【方法】2018年度に認証され,2020年更新対象となった外食55,中食24計79事業者を対象とした。2020年1~2月,Webフォームを用いて,更新意向の他に,スマートミールの提供状況と課題をたずねた。他に,認証時の情報から,応募部門,認証回,店舗の場所,星の数の情報を用いた。量的データの結果は,度数分布で示し,自由記述の回答は,コード化の後,類似する内容をまとめ,カテゴリ化した。【結果】79事業者を解析対象とした(解析対象率100%)。70.9%(n=56)の事業者が,更新すると回答した。項目に回答した49の更新事業者の63.3%(n=31)が【メニューに対する肯定的な評価】など,顧客からの反応が「あった」と回答した。また,71.4%(n=35)の事業者が認証前後の売上げに「変化なし」と回答したが,81.6%(n=40)の事業者が認証のメリットがあったと回答した。40.8%(n=20)の事業者が【メニューに関する課題】などを感じていた。【結論】外食・中食事業者の認証制度への応募促進と認証継続の支援には,メニュー開発やコスト削減に関する課題と,スマートミールの認知度向上など普及啓発に関する課題の解決が必要だと示唆された。
1 0 0 0 OA 外食事業者の食べ残し記録の取組状況および提供量と食べ残しに対する態度
- 著者
- 頓所 希望 赤松 利恵 齋木 美果 小松 美穂乃 井邉 有未 渡邉 紗矢
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.1, pp.46-52, 2021-02-01 (Released:2021-04-05)
- 参考文献数
- 26
【目的】外食産業の食品ロスは食品産業で最も多く,およそ半分が食べ残しである。本研究は,健康的な食環境整備と食べ残し削減の取組を促進するため,外食事業者の食べ残し記録の取組状況と提供量や食べ残しに対する態度を検討した。【方法】2019年5月に実施した外食事業者を対象としたインターネット調査で得た398人のデータを利用した。「食べ残し記録」の取組は「計測・記録」群,「目測・記録」群,「目測のみ」群,「把握なし」群の4群とした。属性,食べ残しの有無,食品ロス削減の取組状況,提供量と食べ残しに対する態度を「食べ残し記録」の取組4群で比較した。態度は,「提供量は食べる量に影響する」などの7項目を質問し,「肯定」「否定」の2群とした。各質問項目の群別比較は,χ2 検定を用いた(有意水準5%未満)。【結果】「計測・記録」群11人(2.8%),「目測・記録」群52人(13.1%),「目測のみ」群232人(58.3%),「把握なし」群103人(25.9%)であった。4群間で属性などを比較した結果,「計測・記録」群は,従事年数が長く(p=0.009),食品ロス削減の取組を行い(p<0.001),量より味を重視する態度をもっていた。【結論】食べ残しを計測し記録している外食事業者は5%未満であり,その事業者は従事年数が長く,食品ロス削減の取組を行っており,適量提供に対して望ましい態度をもつことが示唆された。
1 0 0 0 OA 中山間地域在住高齢者の近隣食環境とたんぱく質摂取量の関連 ─横断研究─
- 著者
- 五味 達之祐 上岡 洋晴
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.1, pp.3-13, 2021-02-01 (Released:2021-04-05)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1
【目的】地域レベルの介護予防の推進のために,中山間地域における近隣食環境とたんぱく質摂取量との関連を明らかにすることを目的とした。【方法】本研究は中山間地域在住高齢者942名を対象とした横断研究である。地理情報システムによって自宅からスーパーとコンビニまでの最短距離を算出し,簡易型自記式食事歴法質問票にて調査したたんぱく質摂取量が低いこととの関連性を多変量回帰分析にて調べた。生活内の移動に関する環境要因として鉄道駅とバス停のアクセスについても検討した。副次アウトカムとして主なたんぱく質供給源である食品群別摂取量とスーパーとコンビニまでの距離との関連を調べた。【結果】スーパーまでの距離とたんぱく質摂取量との有意な関連はなかったが,コンビニが遠いほどたんぱく質摂取量が少なくなる有意な傾向性がみられた。バス停が 400 m圏内にないことが,少ないたんぱく質摂取量と有意に関連した。スーパーとコンビニそれぞれまでの距離と主なたんぱく質供給源の摂取量との有意な関連はみられなかった。【結論】スーパーまでの最短距離とたんぱく質摂取量には有意な関連はなかったが,コンビニが遠いこと,バス停までのアクセスが悪いことが少ないたんぱく質摂取量と有意に関連した。中山間地域におけるたんぱく質摂取の促進のための食生活改善アプローチには,コンビニやバス停へのアクセシビリティに配慮した支援策が必要であることが示唆された。