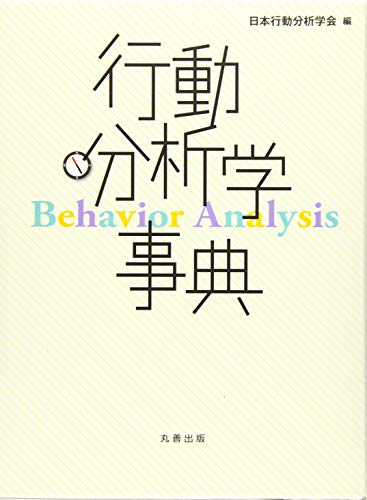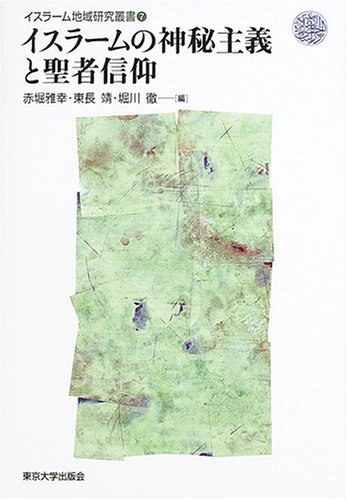7 0 0 0 OA 世界史未履修問題を考える
- 著者
- 鳥越 泰彦
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.10, pp.8-12, 2008-10-01 (Released:2012-02-15)
- 著者
- 田中 卓也
- 出版者
- 共栄大学
- 雑誌
- 共栄大学研究論集 = The Journal of Kyoei University (ISSN:13480596)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.29-37, 2019-03-31
「スポーツする少女」は,1960 年代より少女マンガという形で誌面に登場した。『アタックNo.1』や『サインはV!』では,バレーボールを題材に少女たちに厳しい練習を行わせるとともに,恋や友情など思春期の悩みなどを展開させることになった。オイルショック以降になると,日本は高度成長期を終え,安定成長期へと移行し,多くの国民の関心は個人の多様な価値観を求めるようになった。1970 年代以降になると,少女マンガはなりをひそめ,ギャグマンガやお笑いブームなどにより衰退化していくことになった。
7 0 0 0 OA なぜ我々はAAASに注目するのか
- 著者
- 榎木 英介
- 出版者
- 北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニット
- 雑誌
- 科学技術コミュニケーション (ISSN:18818390)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.49-55, 2007-09
- 著者
- 大島 希巳江
- 出版者
- 日本笑い学会
- 雑誌
- 笑い学研究 (ISSN:21894132)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.14-24, 2011
欧米などの低コンテキストな多民族社会と、日本のような高コンテキスト社会では人々の間で語られるジョークや笑い話の種類およびスタイルが異なる。コミュニケーションにおいて必要とされる要素がそこにはあらわれると思われる。そこで2010年4月から2011年3月の1年間で「日本一おもしろい話」プロジェクトを運営し、サイト上で日本各地からおもしろい話を募集した。毎週、投稿された話をサイトに掲載し、おもしろいと思う話に投票してもらうというシステムをとり、日本人がおもしろいと感じる話を分析することを試みた。その結果、560の有効な投稿があり、1949票の投票がされた。投票により、毎月のトップ10までを決定し、それらの話の分類と分析を行ったところ、多くが投稿者の体験談であることがわかった。全体としては言い間違いや同音異義語を使った、言葉に関する話が最も多かった。また、年代でみるとおもしろい話の多くは40代、50代、30代からの投稿であった。性別でみると、女性は突発的な偶然から起きる言い間違い・聞き間違いなどに関する話が最も多く、男性からの投稿は作り込まれた言葉遊び、文化・社会を反映した笑い話などが多いことがわかった。今回のプロジェクトで日本人のユーモアの傾向が一部明確になり、また今後の研究の貴重な資料になると考えている。
7 0 0 0 蜂須賀斉裕
- 著者
- 小出植男 著
- 出版者
- 大政翼賛会徳島県支部
- 巻号頁・発行日
- 1943
7 0 0 0 正三位蜂須賀斉裕公事蹟 : 御贈位記念
- 著者
- 長森 美信
- 出版者
- 天理大学
- 雑誌
- 天理大学学報 = Tenri University journal (ISSN:03874311)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.1-32, 2020-02
壬辰丁酉(文禄慶長)の戦乱(1592~98年)によって多くの朝鮮人が日本軍に連れ去られた。朝鮮政府は,彼らを被擄人(被虜人)と呼び,その「刷還(送還)」につとめたが,17世紀前半までに帰国したことが確認できる被擄人の総数は6000人余りという。数万人とされる被擄人の大部分は異域・異国で暮らすことを余儀なくされたのである。被擄人のうち,有田・萩・薩摩などで陶磁器生産に従事した陶工や一部知識人等についての研究が蓄積されているものの,一般的な被擄人たちの定住過程については不明な点が多い。被擄人の大部分は自ら記録を残すことがなかったからである。本稿では,日本で洗礼を受けてキリシタンとなった被擄人の記録,すなわち,16世紀末~17世紀に日本で活動した宣教師の記録と17世紀前半の長崎平戸町の人別帳史料を通して,朝鮮被擄人が日本に連行され,定住していく過程を考察した。
7 0 0 0 IR 中絶の自由は選択的中絶を含むのか?--優生主義とジェンダー
- 著者
- 柿本 佳美 KAKIMOTO Yoshimi
- 出版者
- 京都女子大学現代社会学部
- 雑誌
- 現代社会研究 (ISSN:18842623)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.79-91, 2006-12
本稿では、日本社会における中絶の意味と役割の変化をたどり、胎児の性による中絶を手がかりに、優生主義について検討することを目的とする。江戸時代末期まで、中絶は家族計画の手段の一つとして、女性たちの間で処理されてきた事柄であった。しかし、明治政府成立後、中絶は、1880年の堕胎罪の創設を経て、1940年、国民優生法によって非合法化された。この法では、「国民素質ノ向上ヲ期スル」という言葉に当時の優生思想の影響を見ることができる。そして、この流れを受け継ぐ形で制定された優生保護法では、中絶は人口政策および優生主義の実践の一環として機能することとなった。優生主義が問題となるのは、これが既存の社会構造にある差別的な状況を反映し、これを強化する傾向にあるからである。胎児の性を理由とする中絶が示すように、中絶は、女性の身体への自由を超えて、優生主義的な個人の「欲望」を実現する医学的手段ともなりうるのである。This article aims to make clear the change of the sense of abortion, from one of the means of birth control to a way of a practice of selection of fetus. The group of disability people in 1970's Japan opposed to the activists of "Women's Lib (Women's Liberation)", insisting that the selective abortion makes a society which tolerates to eliminate many handicapped people, and that women's right of abortion permits it. Accepting their accusation, women activists have arrived to the position that "want to have a child is egoistic, want not to a child is also egoistic". But the progress of medical technology makes possible to select a fetus, either avoiding the physical state undesirable, or choosing the sex desirable. And the new eugenics, especially called "laissez-faire eugenics", describes the prenatal diagnostic as the hopeful and useful technology, because it realizes a society in which people do not have any painful future having a child undesirable. We can see a moral difficulty of new eugenics by reason of admitting the condition of elimination of the fetus, which reflects the disability in this society and the inequality of female.
- 著者
- 高際 澄雄
- 出版者
- 宇都宮大学国際学部
- 雑誌
- 宇都宮大学国際学部研究論集 (ISSN:13420364)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.13-22, 2010-02
7 0 0 0 暑熱(熱中症)による国内死者数と夏季気温の長期変動
- 著者
- 藤部 文昭
- 出版者
- 日本気象学会
- 雑誌
- 天気 (ISSN:05460921)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.5, pp.371-381, 2013-05-31
- 参考文献数
- 25
1909~2011年の人口動態統計資料を使って,暑熱による国内の年間死者数と夏季気温の変動を調べた.暑熱による死者数は,戦前から戦争直後まで年間200~300人程度で推移した後,1980年代にかけて減少したが,記録的猛暑になった1994年を契機にして急増し,戦前を上回る数になった.しかし,暑熱による死亡率は1994年以降も戦争前後も同程度であり,年齢層ごとに見ると戦前から現在まで一貫して高齢者の暑熱死亡率が高いことから,近年の暑熱死者数の増加の一因は人口の高齢化にあることが分かる.また,診断運用上の変化による見かけの増加も死者数の増加に寄与している可能性がある.一方,暑熱による年間の死者数・死亡率と夏季気温(7,8月平均気温)との間には,戦後の減少期と1990年代後半以降を除いて0.7~0.8の相関があり,夏季気温の変動1℃当たり暑熱死亡率は40~60%変化する.
7 0 0 0 OA 関東山地秩父累帯両神山チャートユニットのパイルナップ構造
- 著者
- 吉田 和弘 松岡 篤
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.6, pp.324-335, 2003-06-15 (Released:2008-04-11)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 2 3
関東山地両神山地域に分布する両神山チャートユニットは,地質図に表現しうる3つのサブユニットに区分される.両神山チャートユニットは全体として,チャート砕屑岩シーケンスが構造的に積み重なったパイルナップ構造を呈している.サブユニット1とサブユニット2のチャートからジュラ紀中世Aalenianを,両サブユニットの珪質泥岩からはジュラ紀中世Bajocian~Bathonian前期を示す放散虫化石がそれぞれ得られた.復元した海洋プレート層序の比較からは,両神山チャートユニットが秩父累帯北帯の柏木層あるいは橋立層群に起源をもつナップであるとするとらえ方は成立しがたい.両神山チャートユニットに比較可能な秩父累帯の地質体としては,南帯の海沢層と北帯の上吉田層がその候補として挙げられる.
7 0 0 0 行動分析学事典 = Behavior analysis
- 著者
- Kakui Keiichi
- 出版者
- Zoological Society of Japan
- 雑誌
- Zoological Science (ISSN:02890003)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.6, pp.468-470, 2019-12
- 被引用文献数
- 2
This study describes shell-exchange behavior in the hermit-crab-like tanaidacean Macrolabrum sp. (Pagurapseudidae: Pagurapseudinae) under captive conditions. I observed one shell exchange by Macrolabrum sp., the behavioral sequence of which was as follows: a shell-carrying tanaidacean 1) grasped the edge of the aperture of an empty gastropod shell with its right cheliped; 2) inspected the condition inside the shell four times by inserting the anterior portion of its body into the shell; and 3) moved into the shell, posterior end (pleotelson) first. The elapsed time from the initial grasping of the empty shell to completing the move into it was 2 min 20 sec. In contrast to a Pagurapseudes tanaidacean and hermit crabs, the individual of Macrolabrum sp. did not examine the external surface of the shell during the single shell exchange observed.
7 0 0 0 OA 科学映像を守る 記録映画の保存と活用
- 著者
- 久米川 正好
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.6, pp.400-407, 2012-09-01 (Released:2012-09-01)
- 被引用文献数
- 1
アナログ時代のフィルムは,劣化,散逸し,死蔵されている。われわれはアナログ時代の貴重な科学映画作品を収集し,高度な技術でデジタル復元し,保管している。この映像をWebで国内外に広く提供することにより,記録映画界の発展に寄与するとともに,日本の文化,科学,産業の継承と発展に貢献しようと,2007年4月1日「NPO法人科学映像館を支える会」を設立した。その活動の意義,5年間の収集,保管と提供に関する実績を紹介する。またその間に生起されたさまざまな課題,特に作品の劣化と資料の散逸および著作権処理問題などを明らかにした。今後,映像遺産を守り,どう生かすべきかについても触れた。
7 0 0 0 イスラームの神秘主義と聖者信仰
- 著者
- 赤堀雅幸 東長靖 堀川徹編
- 出版者
- 東京大学出版会
- 巻号頁・発行日
- 2005
- 著者
- 宇野 友美 佐藤 愼二
- 出版者
- 学校法人 植草学園短期大学
- 雑誌
- 植草学園短期大学紀要 (ISSN:18847811)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.69-77, 2013 (Released:2018-04-13)
7 0 0 0 OA 気分障害の治療と概日リズム
- 著者
- 池田 正明
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.6, pp.469-476, 2007 (Released:2007-12-14)
- 参考文献数
- 60
大うつ病,躁うつ病,季節性うつ病などの気分(感情)障害には,気分の日内変動,体温やコルチゾール位相の変異,REM潜時の短縮など概日リズムに関連した症状がある.気分障害の治療,特に躁病相の予防と治療には気分安定薬としてリチウム,バルプロ酸およびカルバマゼピンが広く用いられ,効果をあげているが,その作用は活動性の亢進や生気感情の亢進を抑制するいわゆる抗躁作用ばかりでなく,躁病相への移行の抑制や各相の持続期間にも影響を与えている.また最近では抗うつ薬による治療に抵抗性のうつ病症例にリチウム治療が有効であることがわかり,気分安定薬は躁病相ばかりでなく,うつ病相にも効果のあることが明らかになっている.気分安定薬の気分障害に対する作用の分子機構についてはまだ確定的なものはないが,リチウムの標的因子としてGSK3βが,リチウムとバルプロ酸の共通の標的因子としてIMPase(イノシトールモノホスファターゼ)が同定され,それぞれの機能と治療効果発現機構が注目されている.概日リズムの発振を行っている時計遺伝子が発見され,その発現機構が明らかになってきたが,気分安定薬であるリチウムやバルプロ酸に概日リズム位相を変化させる作用のあることが報告された.これはリチウムがGSK3βの抑制作用を介して時計遺伝子産物の分解を促進すること,あるいは核移行を抑制することを通じて,概日リズムの周期や位相の形成に直接関与していることによると考えられている.
7 0 0 0 OA 国立国会図書館所蔵『発禁図書函号目録』(安寧ノ部・風俗ノ部)
- 著者
- 大塚奈奈絵
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 参考書誌研究 (ISSN:03853306)
- 巻号頁・発行日
- no.77, 2016-03-25
7 0 0 0 OA 新聞におけるカラー印刷の進展と現状
- 著者
- 深田 一弘
- 出版者
- JAPAN TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY
- 雑誌
- 紙パ技協誌 (ISSN:0022815X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.7, pp.834-844, 1999-07-01 (Released:2009-11-19)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1 1
20 years ago, few newspapers printed copies with four-color printing because of the technical limitations of the pre-press and printing press. Since the introduction of computerized pre-press systems and automated plate-making and printing equipment, you probably see four-color items on most newspaper everyday.Once the color reproduction process required experts. Now computerized color processing technology makes it editors' jobs. They choose a favorite picture on a display screen and then hit a command button to transmit it to a designated page. When the development of a new advertisement system is completed, which gets originals with digital form via web from advertisement agencies, process time required for putting an advertisement on a page will be shortened and the quality of printings would be better.Japanese newspapers utilize offset presses for four-color printing in general. Satellite type machines were dominant in the past. A tower type machine appeared in the Japanese market 4 to 5 years ago and it thrives at present for the space efficiency and more color pages.