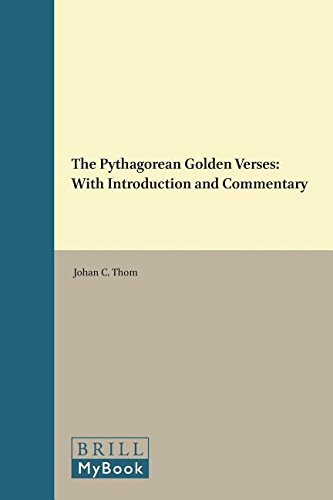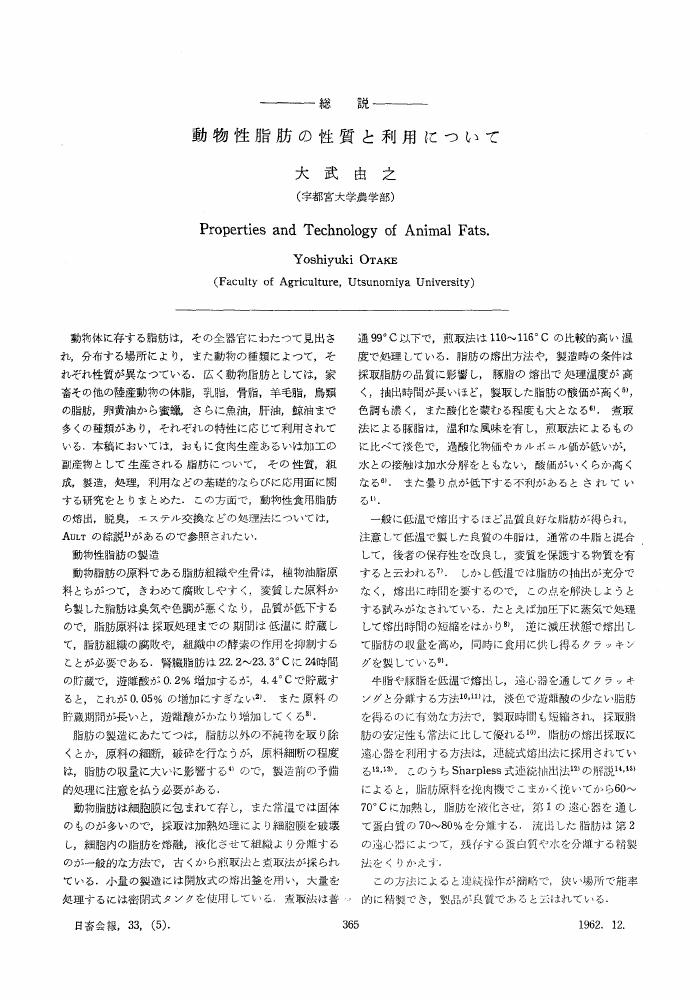- 著者
- by Johan C. Thom
- 出版者
- E.J. Brill
- 巻号頁・発行日
- 1995
1 0 0 0 IR 奈良、平安時代における中国音楽の受容と変容--踏歌の場合
- 著者
- 趙 維平
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.11-41, 2011-03
中国は古代から文化制度、宮廷行事などの広い領域にわたって日本に影響を及ぼした。当然音楽もその中に含まれている。しかし当時両国の間における文化的土壌や民族性が異なり、社会の発展程度にも相違があるため、文化接触した際に、受け入れる程度やその内容に差異があり、中国文化のすべてをそのまま輸入したわけではない。「踏歌」という述語は七世紀の末に日本の史籍に初出し、つまり唐人、漢人が直接日本の宮廷で演奏したものである。その最初の演奏実態は中国人によるものであったが、日本に伝わってから、平安前期において宮廷儀式の音楽として重要な役割を果たしてきたことが六国史からうかがえる。小論は「踏歌」というジャンルはいったいどういうものであったのか、そもそも中国における踏歌、とくに中国の唐およびそれ以前の文献に見られる踏歌の実体はどうであったのか、また当時日本の文化受容層がどのように中国文化を受け入れ、消化し、自文化の中に組み込み、また変容させたのかを明らかにしようとしたものである。
1 0 0 0 OA 〈クィア〉に読むこと、〈クィア〉を読むこと : 村田沙耶香『トリプル』
- 著者
- 黒岩 裕市 KUROIWA Yuichi
- 出版者
- 名古屋大学大学院人文学研究科附属超域文化社会センター
- 雑誌
- JunCture : 超域的日本文化研究 (ISSN:18844766)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.168-174, 2020-03-26
本稿は2019年7月26日に名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリで行なわれた、超域文化社会センター(TCS)セミナー第7回「〈クィア〉に読む、〈クィア〉を読む--村田沙耶香『トリプル』を中心に」の報告である。
1 0 0 0 OA 『数学の現象学』精読(1)
- 著者
- 竹山 理
- 出版者
- 奈良学園大学
- 雑誌
- 奈良学園大学紀要 = Bulletin of Nara Gakuen University (ISSN:2188918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.205-221, 2015-03-10
- 著者
- 小林 直弥
- 出版者
- 日本大学
- 雑誌
- 日本大学芸術学部紀要 (ISSN:03855910)
- 巻号頁・発行日
- no.43, pp.27-38, 2006
日本における「舞(まい)」の始源的要素の中には、常に為政者(皇帝・天皇)への「服従」とシャーマニズムを伴う「舞」行為が存在する。その中でもとりわけ特異な存在が「八〓舞」である。この「舞」は、古代中国をその源とし、韓国における「雅楽」においては、中心的な役割を果たしている。が、8列8人、総勢64名による「八〓舞」は、日本では『日本書紀』に記載されるものの、宮中に現存する「雅(舞)楽」には何故か、その存在がない。そこには、日本が中国や朝鮮半島からの外来芸能や文化から、いよいよ独自の文化を形成する方向へ進む、歴史の流れが隠されており、また、儒教思想と仏教思想のどちらを国家が選択したかなど、さまざまな歴史的背景も読み取れるのである。本研究では、わずかな記述のみに残る「八〓舞」を中心に、日本の宮廷楽舞の始源的要素について考察したものである。
- 著者
- 坂本 正樹 花里 孝幸
- 出版者
- 日本陸水学会
- 雑誌
- 日本陸水学会 講演要旨集 日本陸水学会第72回大会 水戸大会
- 巻号頁・発行日
- pp.166, 2007 (Released:2008-03-31)
1 0 0 0 遷御後の御神楽について
- 著者
- 鎌田 純一
- 出版者
- 皇学館大学史学会
- 雑誌
- 皇学館史学 (ISSN:09122435)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.53-71, 2008-01
1 0 0 0 OA 考古学の中の毒と薬
- 著者
- 杉山 二郎 山崎 幹夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.6, pp.463-468, 1979-06-01 (Released:2018-08-26)
世界の文化史の中で, 毒や薬が果して来た役割は大変に大きく, 興味深い, お招きした杉山二郎氏には「鑑真」「大仏建立」「正倉院」「西アジア南北記」などの著書があり, その博学と見識の深さについてはつとに知られるところである。時間が足りなかったため, 今日はその一端をうかがうに止まったが, いわばイントロダクションとも言うべき今日のお話の中だけにも, 我々にとって興味ある問題のヒントがいくつもあったように思われる。
- 著者
- Mochizuki, Kotarō, 1865-1927
- 出版者
- "The Liberal news agency"
- 巻号頁・発行日
- 1910
1 0 0 0 IR 「舞踏会」を読む
- 著者
- 野村 圭介
- 出版者
- 早稲田商学同攻会
- 雑誌
- 早稲田商学 (ISSN:03873404)
- 巻号頁・発行日
- no.313, pp.p732-706, 1986-02
1 0 0 0 IR ある文明開化のまなざし--芥川竜之介「舞踏会」とピエ-ル・ロティ
- 著者
- 吉田 城
- 出版者
- 京都大学フランス語学フランス文学研究会
- 雑誌
- 仏文研究 (ISSN:03851869)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.119-128, 1998
1 0 0 0 OA 長期記憶情報の利用における中央実行系の役割
- 著者
- 金田 みずき 苧阪 直行
- 出版者
- 日本基礎心理学会
- 雑誌
- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.20-29, 2004-09-30 (Released:2016-11-22)
This study investigated the role of the central executive in the use of long-term memory, and in particular examined semantically encoding verbal stimuli using long-term information. A dual-task method was adopted. The primary task was an immediate serial recall which used two types of verbal stimuli, nonwords and words. It has been reported that the recall of words is better than the recall of nonwords because nonwords contain a phonological code without any semantic information, whereas words involve both types of information. The main analysis compared the performance of the recall of nonwords and words when secondary tasks were performed simultaneously. The secondary tasks were articulatory suppression and verification of simple arithmetic that imposed a burden on the phonological loop and central executive, respectively. The recall performance of the nonwords was disrupted by the same amount by each of the secondary tasks. However, the recall performance of the words was effected more when an arithmetic task was performed. These results confirmed the assumption that the central executive plays an important role in semantically encoding verbal information.
1 0 0 0 OA 蛋白質の変性と再生
- 著者
- 濱口 浩三
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.11, pp.1052-1060, 1988-11-01 (Released:2009-11-13)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1 1
In this review I first described the stability of proteins obtained from unfolding experiments and how the replacement of a specified amino acid residue with other residues in a protein affects the protein stability. Second, I described the kinetics of unfolding and refolding of proteins. The transition from folded state to unfolded state or from unfolded state to folded state is highly cooperative, and no structural intermediate is detected. Therefore, it is difficult to understand how the regular structure of the native protein is formed from the unfolded molecule. Finally I described the pathway of the disulfide bond formation from reduced proteins.
1 0 0 0 IR 『ラクシュミー・タントラ』における創造説とグナ(性質)
- 著者
- 三澤 祐嗣
- 出版者
- 東洋大学国際哲学研究センター
- 雑誌
- 国際哲学研究 = Journal of international philosophy (ISSN:21868581)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.189-200, 2018-03
Lakṣmītantra is one of the major texts of the Pāñcarātra sect and is estimated to have been compiled and edited between the ninth and twelfth centuries. The major t hemes o f t he t ext i s t he p hilosophy and cosmogony that are unique to the Pāñcarātra sect, and the text has widely taken in various thoughts to produce eclectic thoughts.According to the creation theory of Lakṣmītantra, as i n the c ase o f o ther texts b y t he Pāñcarātra sect, divine creation is seen as the "pure creation" (śuddhasṛṣṭi) and the creation of the material world is the "non-pure creation" (śuddhetarasṛṣṭi). The metaphysical development of various principles, and mythic creation is explained in a complex and intertwined manner. In this theory, something called guṇa appears from time to time. The term, which means attributes or nature, particularly when i t i s r eferred to a s t hree kinds of guṇa as seen in the Samkhya school, is explained as something like constitutive elements which diversify the world as well as an attribute which governs the mind. On the other hand, in Lakṣmītantra, it appears in various places in the creation theory and has different meanings according to the phase in which it appears.The present article identifies and classifies guṇa-s that appear in the creation theory in Lakṣmītantra. Guṇa-s can be roughly divided into "mythic six guṇa-s" and "what is made up with three guṇa-s." The former is related to the "pure creation" and the latter the "non-pure creation." Although it appears irregular at first glance, the article has shown that each guṇa is relayed and merged in a complex manner.
1 0 0 0 IR 『ラクシュミー・タントラ』における創造説とグナ(性質)について
- 著者
- 三澤 祐嗣
- 出版者
- 東洋大学国際哲学研究センター
- 雑誌
- 国際哲学研究 = Journal of international philosophy (ISSN:21868581)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.229-238, 2017-03
1 0 0 0 OA 動物性脂肪の性質と利用について
- 著者
- 大武 由之
- 出版者
- 公益社団法人 日本畜産学会
- 雑誌
- 日本畜産学会報 (ISSN:1346907X)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.5, pp.365-373, 1962 (Released:2008-03-10)
- 参考文献数
- 188
1 0 0 0 OA インスタントコーヒー中の鉄結合性物質の検索
- 著者
- 関口 伸子 藤村 理佳 村田 容常 本間 清一
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.689-698, 1992-04-01 (Released:2008-11-21)
- 参考文献数
- 11
インスタントコーヒー中のFe(II)と結合する成分を検索する目的で,0.1mMのFeSO4を含む0.01M酢酸緩衝液(pH4)を溶出液とするゲル濾過HPLC(カラム平衡法)を用いて実験を行った. (1) EDTAをHPLCにかけると,溶離液中のFeの濃度の平衡がくずれ,EDTAの濃度に比例したFe濃度の山と谷ができた. (2) コーヒー,モデルメラノイジン,フィチン酸,カフェイン,クロロゲン酸の鉄結合性をカラム平衡法で検討したところ,コ一ヒー,モデルメラノイジン,フィチン酸にはFe(II)との相互作用があることがわかった.カフェイン,クロロゲン酸のFe(II)との相互作用は本法ではなかった. (3) イソプロピルアルコールを用いてコーヒー成分の分画をこころみた.70%イソプロピルアルコールが可溶性成分と不溶性成分の分離に一番有効であることがわかった. (4) コーヒーの70%イソプロピルアルコール不溶性成分を水抽出し,トヨパールHW-40 (coarse)で分画したところ,中間に溶離する可視部の吸光度の低い画分と,最後に溶離する赤褐色のクロロゲン酸残基を含む画分はFe(II)との相互作用があった. (5) コーヒーの70%イソプロピルアルコール可溶性成分をトヨパールHW-40 (coarse)で分画したところ,最初に溶離する褐変色素の画分はFe(II)との相互作用があった. (6) コーヒーの70%イソプロピルアルコール不溶性成分を水抽出したあとの繊維状の不溶性物質にもFe(II)との相互作用があった. 終わりにインスタントコーヒーを提供していただいたネッスル株式会社に感謝いたします.