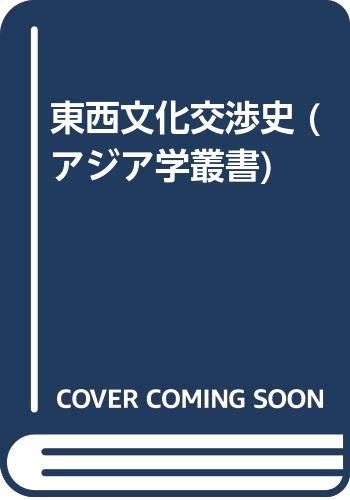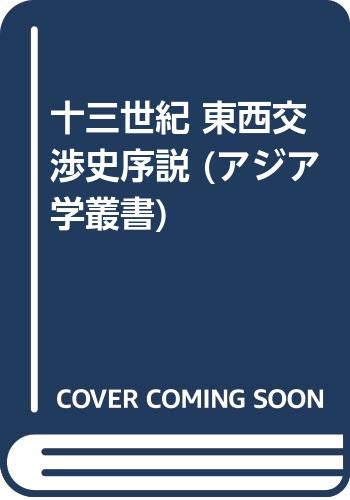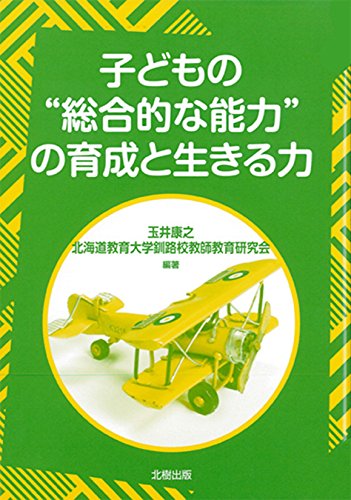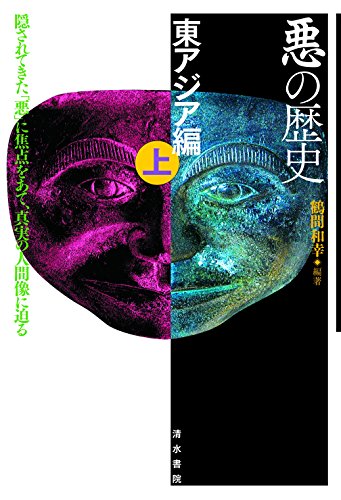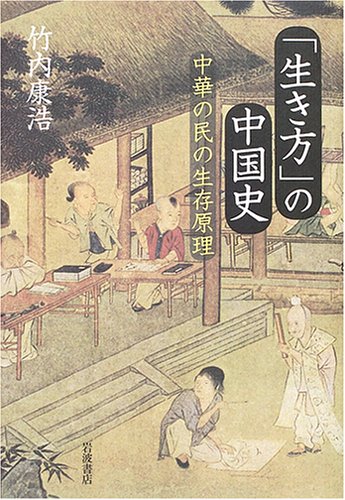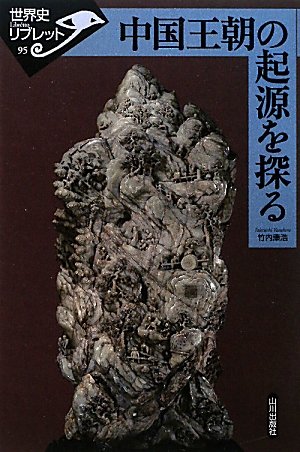1 0 0 0 OA 日本と中国の小学校理科授業の比較
- 著者
- 張 娜 香西 武
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.5-8, 2011 (Released:2018-04-07)
- 参考文献数
- 5
科学技術先進国として日本では小学校理科における多いところに参考する価値があると思われる。両国の小学校理科に関する指導要領,授業時数,理科授業の比較を通じて,現在中国と日本で小学校理科授業の様子が明らかにする。
1 0 0 0 スイスの住居・集落・街
1 0 0 0 OA 語認知速度を高める訓練が聴解力に及ぼす効果 : 日本人EFL学習者に翻訳課題を与えた場合
- 著者
- 山口 智子
- 出版者
- The Japan Society of English Language Education
- 雑誌
- 全国英語教育学会紀要 (ISSN:13448560)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.83-91, 1999 (Released:2017-05-01)
- 被引用文献数
- 1
It is generally thought that it is difficult for Japanese EFL learners to comprehend language information only by auditory input because their priority in learning is written English, and so they depend more on visual language than auditory language. By examining the word translation latency of an English word presented by a computer as auditory stimulus, it was evident that good listeners can answer more rapidly and exactly than poor listeners in conditions of both high frequency words and low frequency words (Yamaguchi 1997). Therefore, the effects of training given to poor listeners for two months were measured in order to examine whether listening comprehension would be improved or not if the speed of word recognition becomes rapid. The results were that their speed became more rapid, and furthermore their listening comprehension also increased. The importance of increasing the speed of word recognition in listening instruction for poor learners was therefore supported.
1 0 0 0 十三世紀東西交渉史序説
1 0 0 0 日本の防共・枢軸外交の再検討
今年度は特別研究員採用期間の3年目に当たり、昨年度に続いて資料収を継続し、2009年9月から2010年2月までの期間に日独共同大学院プログラムを利用してドイツ、ハレ=ヴィッテンベルク・マルティン=ルター大学での在外研究を行った。まず資料収集作業としては、モスクワと北京に滞在してロシア国立図書館(2009年8月)、中国国家図書館(同9月)に関連文献を調査したことが挙げられる。さらにドイツ渡航後にはドイツ外務省政策文書館(同10~11月)、イギリス国立公文書館(同11~12月)、ミュンヘン歴史学研究所(2010年1月)、ベルリン=リヒターフェルデ連邦文書館(同)、国際連盟公文書館(同)で作業を実施した。すでにベルリンでは何度も渡航して資料を収集していたが、今回はとりわけ中央や在外公館の間の公信だけでなく、1930年代に駐華大使を務め、日中戦争初期に和平工作を行ったオスカル・トラウトマンの日記を撮影できたことが成果として特筆される。また、ロンドンでの作業は今回が初めてであり、華北分離工作から日中戦争、日米開戦に至る東アジア情勢や、世界政治における枢軸形成に関するイギリス側の基本資料を収集できた。また年明けにはジュネーヴ国際連盟文書館を訪れ、デジタルカメラで約3,000枚分の資料を集めることができた。ハレでの在外研究では、まずこの都市で9月末から10月初頭にかけて開催されたドイツ語圏日本研究学会に出席し、ドイツ、オーストリア、スイスなどから訪れた日本学研究者と知遇を得た。それに続いて10月初頭に1週間開催された東大・ハレ大秋季共同アカデミーでは、「市民社会とその対抗構想」というテーマでの討論に参加した。その後、面談を通じてパトリック・ワーグナー教授からの博士論文指導を受けた。
1 0 0 0 OA 社会的笑いに関する心理学研究の動向
1 0 0 0 OA 日本社会の多元的階層構造
- 著者
- 林 雄亮
- 出版者
- 立教大学
- 雑誌
- 応用社会学研究 (ISSN:03876756)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.43-55, 2012-03-25
1 0 0 0 OA ごっこにおける言語行為の発達的分析 : 方言と共通語の使い分けに着眼して
- 著者
- 加用 文男 新名 加苗 河田 有世 村尾 静香 牧 ルミ子
- 出版者
- 心理科学研究会
- 雑誌
- 心理科学 (ISSN:03883299)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.38-59, 1996-09-30 (Released:2017-09-10)
In this we obtained 1815 speech act samples of children in make-believe play, coded and counted along with the speech act theory, at day-care-centers in 4 prefectures of Japan. We sorted these samples into 4 categories, 2 of which were "in "and"out" of the make-believe frame (lines and stage directions) introduced by Garvey (1984) and Giffin (1984). The other 2 categories were "out of make-believe play" (more realistic speech acts) and "confusion" of these, introduced by us (IOPC). On the other hand, from the view point of speech style we sorted these same samples into the two categories of either dialect or standard language (DS). Results of the cross-analysis of IOPC and DS in each age group (3-5years) were as follows. (1) Even 3 year-old children who use dialect language in their daily life used standard language in their lines (speech utterances in a make-believe frame). (2) 3 year-old children uttered more "lines" and "confusions", while 4 year-old uttered more "out of frame" and "out of play", and 5 year-old uttered much more "lines". Based on these results, we made critical discussions of the differentiation-integration hypothesis of fantasy and reality (ex., Scarlett & Wolf, 1979 ; Dilalla & Watson, 1988) and the signifiant-signifie paradigm of make-believe play. We supported the idea of multiple levels of role taking (Giffin, 1984) and proposed the mood hypothesis of make-believe play.
1 0 0 0 OA 舌痛症・咽喉頭異常感症に対して滋陰至宝湯が有効であった3例
- 著者
- 白井 明子 小川 真生 広田 京子 吉崎 智一 小川 恵子
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.22-27, 2015 (Released:2015-06-29)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2
滋陰至宝湯は『万病回春』巻之六・婦人虚労門収載の中国・明時代(1368~1644)の方剤で,気鬱を伴う慢性咳嗽に有効であるとされている。滋陰至宝湯は,その構成生薬から,滋養し,虚熱を冷まし,気を巡らせ,消化機能を高めるという滋陰清熱,理気健脾の方剤と言える。今回われわれは,本方剤が奏効した舌痛症,咽喉頭異常感症の3症例を経験した。口渇,口乾,粘稠痰といった陰虚症状を伴い,腹部右側の鼓音をはじめとする気鬱の症候を認める舌痛症,咽喉頭異常感症には,滋陰至宝湯は有効な処方となり得ると考えた。
1 0 0 0 OA 低酸素による自律神経・循環反応の解析:反跳現象と種差について
- 著者
- 平川 晴久 林田 嘉朗
- 出版者
- The University of Occupational and Environmental Health, Japan
- 雑誌
- Journal of UOEH (ISSN:0387821X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.117-129, 2002-06-01 (Released:2017-04-11)
- 被引用文献数
- 3 2
低酸素によって引き起こされる自律神経系と循環系の反応、および暴露直後にみられる心拍の反跳現象について解析を行った. 血圧測定用カテーテル, 心電図そして腎交感神経活動記録用電極を慢性に植え込んだWistar ratを用い, hypocapnic (Hypo), isocapnic (Iso), hypercapnic (Hyper) hypoxiaの暴露を行った. Isoでは, 血圧及び心拍数は変化しなかったが, Hypoでは, 血圧は低下し心拍数は増加, Hyperでは, 血圧は上昇し心拍数は低下した. 腎交感神経活動はいずれにおいても増加した. IsoとHyperの終了直後, 心拍数は一過性に増加した. この心拍反応は, 腎交感神経活動の反応とは相関しなかった. このことより, この心拍の反跳現象は, 交感神経よりもむしろ副交感神経系のメカニズムによるものと考えられた. 低酸素時の循環反応は動物により異なると考えられているが, 類似した条件において行われた実験においては種差に関わらず, その結果は, ほぼ一致するものであった.
- 著者
- Ryota AKABANE Touko SATO Atsushi SAKATANI Mizuki OGAWA Masayoshi NAGAKAWA Hirosumi MIYAKAWA Yuichi MIYAGAWA Hiroyuki TAZAKI Naoyuki TAKEMURA
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.19-0595, (Released:2020-02-26)
- 被引用文献数
- 3
Information regarding the pharmacokinetics of oral sildenafil in dogs with pulmonary hypertension is limited. In this study, we examined the pharmacokinetics of oral sildenafil in a canine model of chronic embolic pulmonary hypertension (CEPH). The CEPH model was developed by repeatedly injecting microspheres into the pulmonary arteries. The pharmacokinetics of oral sildenafil at 1, 2 and 4 mg/kg was evaluated using four dogs with pulmonary hypertension in the fasted state. The plasma concentrations of sildenafil were determined using high-performance liquid chromatography, and pharmacokinetic parameters were calculated using a noncompartmental analysis. Sildenafil was well tolerated in this study. Proportional increments in the maximum plasma concentration and area under the curve extrapolated to infinity at drug doses of 1, 2 and 4 mg/kg were detected using a power model analysis. No significant differences were observed among the three doses in the time to maximum plasma concentration. The mean residence time and elimination half-life were slightly but significantly higher at a dose of 4 mg/kg than at a dose of 1 mg/kg.
1 0 0 0 子どもの"総合的な能力"の育成と生きる力
- 著者
- 玉井康之 北海道教育大学釧路校教師教育研究会編著
- 出版者
- 北樹出版
- 巻号頁・発行日
- 2017