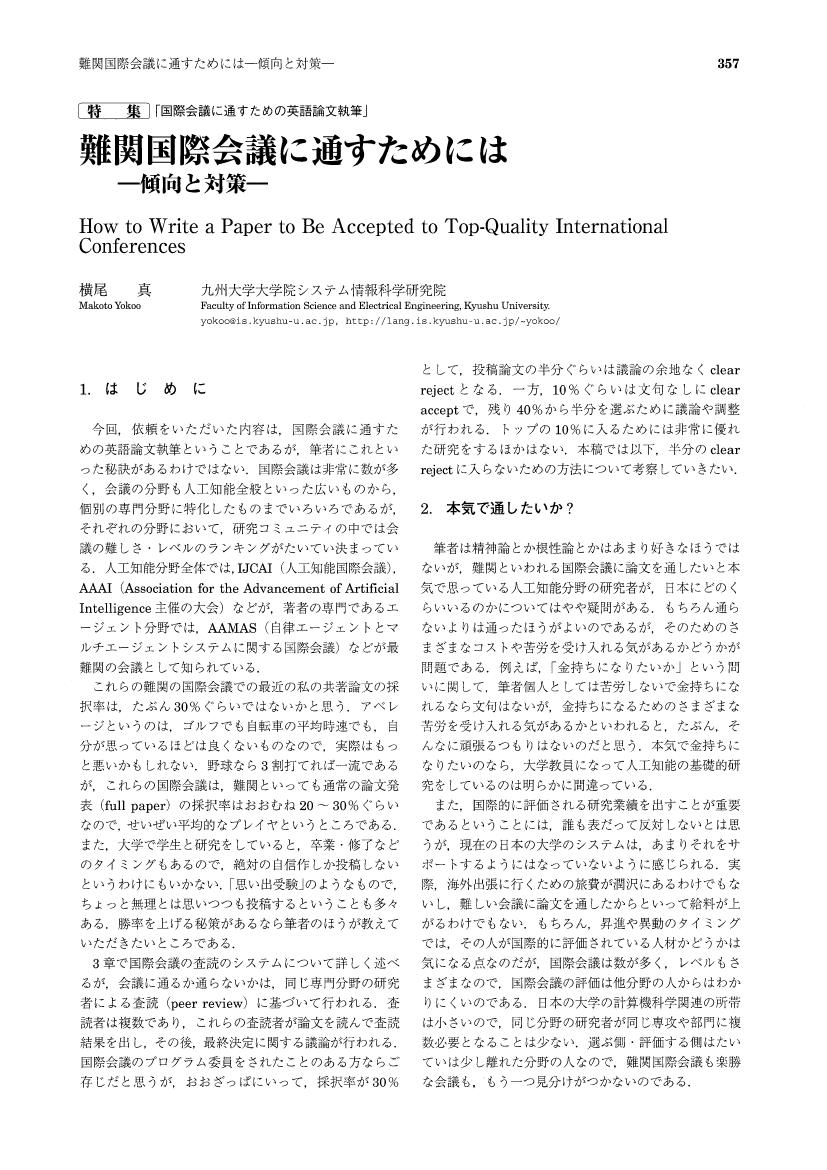- 著者
- Yusuke Morita Daisuke Matsubara Mitsuru Seki Daisuke Tamura Toshihiro Tajima
- 出版者
- Tohoku University Medical Press
- 雑誌
- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)
- 巻号頁・発行日
- vol.258, no.3, pp.177-182, 2022 (Released:2022-10-25)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 3
Perimyocarditis is a rare and serious cardiac complication following COVID-19 vaccination. Young males are most at risk after the second dose. With the introduction of the booster (third) dose, some reports have focused on the risk of perimyocarditis after a booster dose. However, no currently available report in Japan has comprehensively described this phenomenon. A healthy 14-year-old Japanese male, who had completed a two-dose primary series of the BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) vaccine six months prior, developed fever and chest pain within 24 hours after a homologous booster dose. He was transferred to our institute because of worsening chest pain. A multiplex PCR test showed no evidence of active viral infections, including SARS-CoV-2. Electrocardiography revealed ST-segment elevation in almost all leads, suggesting pericarditis. Echocardiography showed normal systolic function. Laboratory data demonstrated C-reactive protein levels of 8.8 mg/dL and elevated cardiac damage markers (troponin T, 1.9 ng/mL; creatine phosphokinase, 1527 U/L; MB isoenzyme, 120 U/L), suggesting myocarditis. He was diagnosed with perimyocarditis associated with the booster dose, which was confirmed by cardiac magnetic resonance imaging four days after initial symptoms. Chest pain improved spontaneously along with a resolution of electrocardiographic findings and laboratory data within several days. He was discharged eight days after admission. Perimyocarditis is less frequent after a booster dose than after primary doses. In this case, the patient with booster-dose-associated perimyocarditis showed favorable clinical course without severe sequelae. The patient’s clinical course was consistent with findings on previous large-scale reports on primary-dose-associated perimyocarditis and case series on booster-dose-associated perimyocarditis.
6 0 0 0 OA カストラートの光と陰
- 著者
- 金谷 めぐみ 植田 浩司
- 出版者
- 西南女学院大学
- 雑誌
- 西南女学院大学紀要 = Bulletin of Seinan Jo Gakuin University (ISSN:13426354)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.85-91, 2014-03-01
6 0 0 0 OA 学校管理下における柔道の死亡・重篤障害の特徴 ~中学1年生・高校1年生を対象に~
- 著者
- 中谷 祐実 近藤 良享
- 雑誌
- 中京大学体育研究所紀要 = BULLETIN OF RESEARCH INSTITUTE OF HEALTH AND SPORT SCIENCES CHUKYO UNIVERSITY
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.1-8, 2017-03-31
6 0 0 0 OA 持続的腎機能代替療法(CRRT)施行中の全身管理 抗凝固能管理および栄養管理
- 著者
- 中永 士師明
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本急性血液浄化学会
- 雑誌
- 日本急性血液浄化学会雑誌 (ISSN:21851085)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.9-16, 2013-06-01 (Released:2022-09-16)
- 参考文献数
- 40
持続的腎機能代替療法(CRRT)施行症例の多くは敗血症や多臓器不全を合併しており,救命のためには栄養管理を含めた集学的治療が必要となる。また,CRRT施行中は抗凝固薬を使用することになるため,出血傾向を助長させることなく,また,過凝固にもならないような抗凝固能管理も必要となる。CRRT施行患者に対する栄養管理におけるエビデンスはほとんどなく,急性腎傷害(AKI)や敗血症に準じた栄養管理が推奨される。AKI患者では早期からの栄養管理が腎機能や予後の改善に繋がる。CRRTの利点は除水による輸液スペースの確保により,十分量の薬剤,栄養,血液製剤の投与が可能になる。欠点は薬剤やビタミンなどの栄養素が一部除去されてしまうため,投与量を調整する必要が生じることである。CRRT施行中の栄養管理としては,①underfeedingの許容,②早期から栄養管理を考慮し,カロリー摂取,蛋白摂取を正しく行う,③少量でも可能な限り経腸栄養を行う,の3点が重要となる。
6 0 0 0 OA 科学技術のリスク評価における非専門家の役割 : 森永ヒ素粉乳中毒事件を中心に
- 著者
- 白木 駿佑 木越 清信
- 出版者
- 日本コーチング学会
- 雑誌
- コーチング学研究 (ISSN:21851646)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.253-264, 2019-03-20 (Released:2019-09-02)
- 参考文献数
- 15
This is the case study that the race pattern of a 400-m sprint was improved by “Affirmation”. The affirmation is a method of accomplishing goal and used in the world for business, education and so on. The purpose of this study was to obtain practical wisdom when using the affirmation to sports. A male sprinter had been having the problem of the 400-m race pattern and tried to solve it by the affirmation. Then, while correcting the affirmation sheet each time the race was done, the problem was solved four months from beginning to use the affirmation. He could not realize the image of the race pattern in the first half of the practical process. But in the second half of the practical process, he changed the contents of affirmation sheet greatly, realized the target model of race pattern which is the moderate deceleration type one month later. Besides, he had read the short affirmation sheet every day during this practice process. From this process, it was suggested that it is difficult to make the high-quality affirmation sheet in a short period from using it for the first time, and that it is necessary to use the short sentence involved realistic and clear image for continuous implementation of affirmation.
6 0 0 0 IR 精神医療福祉と支援 : 管理から脱することは可能か
6 0 0 0 IR 信頼の倫理学的考察
- 著者
- 奥田 秀巳
- 出版者
- 広島大学(Hiroshima University)
- 巻号頁・発行日
- 2015
内容の要約
6 0 0 0 OA 難関国際会議に通すためには : 傾向と対策(<特集>国際会議に通すための英語論文執筆)
- 著者
- 横尾 真
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.357-361, 2008-05-01 (Released:2020-09-29)
- 著者
- 入山 茂
- 出版者
- 日本応用心理学会
- 雑誌
- 応用心理学研究 (ISSN:03874605)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.149-157, 2020-11-30 (Released:2021-02-28)
- 参考文献数
- 39
This study examined the relationship between judgements of suicide by laypersons in suspicious death investigations, and the presence or absence of a suicide note and deceased's information that did not support suicide. We asked university students to judge the possibility of suicide in a fictitious investigation of suspicious death; 72 subjects received a case with "a suicide note" and deceased's information, 71 subjects received a case with "a suicide note" and without deceased's information, 71 subjects received a case with "no suicide note" and deceased's information, and 72 subjects received a case with "no suicide note" and without deceased's information. Analysis of variance results showed that subjects who received a case with "a suicide note" judged the possibility of suicide as slightly higher than subjects receiving cases without "a suicide note". Subjects who received the deceased's information judged the possibility of suicide as slightly higher than subjects without it.
6 0 0 0 OA LINEのデータセンターを構成するネットワーク技術
- 著者
- 小林 正幸 金丸 洋平 土屋 俊貴 市原 裕史
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.4, pp.257-263, 2020 (Released:2020-03-01)
- 参考文献数
- 11
6 0 0 0 OA 山田耕筰の日本歌曲とアクセント理論 : ――演奏の視点からみた分析――
- 著者
- 鈴木 亜矢子 Ayako Suzuki
- 出版者
- 東京音楽大学
- 雑誌
- 東京音楽大学大学院論文集 = Bulletin of the doctoral programs, Tokyo College of Music (ISSN:21895767)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.90-106, 2016-03-01
6 0 0 0 OA 誤振込における金銭返還請求権の法的性格
- 著者
- 向瀬 育恵
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.41-66, 1999-12
6 0 0 0 OA 諸外国の国民投票法制及び実施例【第3版】
- 著者
- 山岡規雄
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 調査と情報 (ISSN:13492098)
- 巻号頁・発行日
- no.939, 2017-02-07
6 0 0 0 ペリグリーノスの昇天
6 0 0 0 IR 「入門」の再検討 (1)
- 著者
- 岩元 修一
- 出版者
- 宇部工業高等専門学校
- 雑誌
- 宇部工業高等専門学校研究報告 (ISSN:03864359)
- 巻号頁・発行日
- no.67, pp.13-22, 2021-03
本稿は日本中世の訴訟手続きの一つである「入門」(いりかど)について、関係史料を順次取り上げ再検討を加え、訴訟手続きの総体的な理解に資そうとするものである。ここでは関係史料のうち「沙汰未練書」と「国分氏古文書」の記述を対象にして再検討を行うものである。
6 0 0 0 OA 交通博物館の至宝「岩崎・渡辺コレクション」
- 著者
- 菅 建彦
- 出版者
- 社団法人 日本写真学会
- 雑誌
- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.108-112, 2004-04-25 (Released:2011-08-11)
「岩崎・渡辺コレクション」は, 明治30年代の日本の鉄道の蒸気機関車, 駅舎, 橋梁等の構造物など記録した写真資料で, 国有化以前の日本の鉄道の姿を伝える貴重な記録である.コレクションの主体は3,347枚の乾板で, 若き企業家渡辺四郎と岩崎輝彌が高名の写真師小川一真に撮影させたものである.現在使用している複製用陰画フィルムは, 40年前に乾板を引き伸ばして得た印画を撮影したもので, 早晩劣化を免れない.貴重な資料を末永く活用するためにディジタル画像化などの対策を講じることが重要な課題である.
6 0 0 0 OA 都市と周縁文化 : エリザベス時代におけるロンドンの劇場
- 著者
- 石塚 倫子
- 出版者
- 人間環境大学
- 雑誌
- 人間と環境 : 人間環境学研究所研究報告 : journal of Institute for Human and Environmental Studies = Journal of Institute for Human and Environmental Studies (ISSN:13434780)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.65-75, 1998-03-31
AD43年、ローマ人のブリタニア征服以来、都市として着実に発展してきたロンドンは、16世紀末には世界に誇るメトロポリスとなっていた。シティと呼ばれる市壁の内部はイギリス経済の中枢として機能し、一方、市壁の外側の隣接区域には、大都市の必要悪とも言える施設(酒場、売春宿、劇場、精神病院、らい病院、処刑場、牢獄など)が寄り集まっていた。特にテムズ川南岸のサザックは「リバティ」と呼ばれ、複雑な権力関係が錯綜していたため逆に無法地帯と化していた。サザックにはシティからはじき出された浮浪者、犯罪人、失業者、得体のしれない外国人等が集まり、歓楽と危険、解放と無秩序が入り乱れた特殊な世界となっていた。しかし、都市ロンドンはこの周縁の地に、穢れたもの、忌まわしいものを引き受けてもらうことで、内部の秩序を保っていたのである。シティとサザック-この二種類の地域は文化における中心と周縁の関係に相当し、互いに緊張関係を保ちながら都市ロンドンを支えていた。特に大衆劇場は周縁に位置し、当時の都市文化を裏側から照射する場でもあった。ここでは、シェイクスピア劇を中心に大衆劇場の周縁性と意義について論じてみた。
6 0 0 0 OA 馬車と宮殿 : 17世紀のピッティ宮諸計画案における馬車の影響
- 著者
- 金山 弘昌
- 出版者
- 学校法人 開智学園 開智国際大学
- 雑誌
- 日本橋学館大学紀要 (ISSN:13480154)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.39-52, 2003-03-30 (Released:2018-02-07)
16世紀後半のヨーロッパ諸宮廷において,ある新しい流行が広まった。馬車の使用である。同世紀末までに馬車は貴族階級の主要な移動手段となり,さらには宮廷儀礼において重要な役割を果たすようになった。馬車の急速な普及は建築や都市計画にも影響を与えた。それまでは騎馬のみを前提としていたパラッツォ(都市型邸館)において,馬車庫や馬車の動線の確保が必要となったのである。この点について,本論考では,17世紀イタリアのパラッツォの建築計画における馬車の使用の影響を,フィレンツェのピッティ宮の事例の検討を通して考察する。トスカーナ大公の宮殿である同宮は,当初ルネサンスのパラッツォとして建設された後,16世紀後半,いまだ馬車が決定的に普及する以前に増築改修された。それ故,翌17世紀においては,馬車のための諸設備の増築の必要が明白かつ緊急の課題となった。まず1610年までにボーボリ庭園に至る馬車の「通路」が設けられた。さらに同宿改修のための多くの未実施の計画案の中にも,馬車関連の施設の提案が見出される。 1641年には,大公の建築家アルフォンソ・パリージが,大公の弟ジョヴァンニ・カルロ公の意見に基づき,ロッジア(開廊)形式の馬車庫を新設の側翼に設けることを提案した。また宮廷のグァルダローバ職で技師のディアンチント・マリア・マルミが1660年代と70年代に提案した各種計画の中にも,馬車庫や多数の馬車の使用に適した広場の整備,中庭からボーボリ庭園に至る新しい馬車道などが見出される。さらに大公の「首席侍従」のパオロ・ファルコニエーりも,1681年にピッティ宮の全面改修を提案した際,馬車関連施設の不備を同宮のもっとも重大な欠点の一つと考えた。ファルコニエーりは特に馬車の動線システムの再構築に配慮し,デコールム(適正さ)の原理を遵守しつつ,大公やその一族の馬車動線を「雑役」用のそれと明確に区別した。このように,たとえ大半の提案が構想段階に留まったとはいえ,17世紀の大公の宮廷の建築家や廷臣たちが,馬車の問題に対して常に関心を払っていたことは明らかなのである。