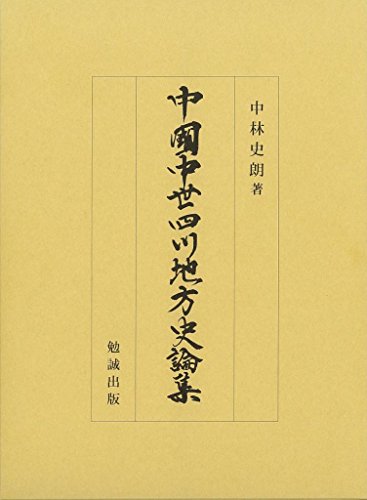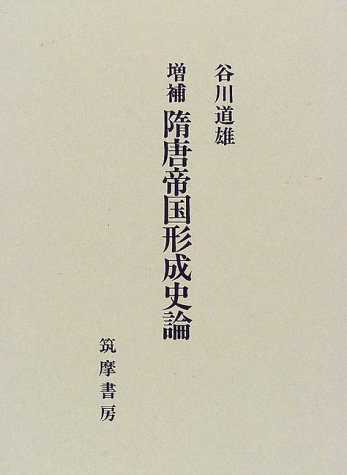^<11>C-glucose を経口投与した8例のパーキンソン病患者と5例の正常者の脳内 glucose 代謝を検討するため,positron emission computed tomography (PET)により,大脳皮質(前頭葉,側頭葉,後頭葉)及び線条体における^<11>Cの集積量を比較検討した。^<11>C-glucose は光合成法により^<11>CO_2より精製した。(1)パーキンソン病患者8例の内4例につき線条体及び大脳皮質各部の^<11>C集積量には有意差は認められなかった。(2)8例のパーキンソン病患者の線条体及び大脳皮質各部の^<11>C集積量と正常例5例のそれとを比較検討したが有意差はなかった。
1 0 0 0 札幌市近郊に生息するエゾジカの季節移動と土地利用
北海道西部でも個体数が増加しているエゾシカ(<i>Cervus nippon yesoensis</i>)は,近年札幌都市部にも出没し,自動車事故や列車との衝突事故などその被害は年々拡大している.しかし,都市部に出没したエゾシカは銃器を用いた対策などが難しく,未だ管理の有効な手立ては見つかっていない.更に,都市部に生息するエゾシカの生態に関する先行研究も極めて少なく,対策を講じるための基礎情報が不足しているのが現状である.<br> 本研究では,都市部に出没するエゾシカの季節移動パターンと生息地利用を把握する為,札幌市に隣接する北広島市及び江別市においてテレメトリー調査とライトセンサス調査を行った.テレメトリー調査は,2012年 1月~ 2013年 3月にかけて北広島市の国有林内で生体捕獲を実施し 4頭(雄 2頭,雌 2頭)を捕獲した.捕獲した雄には VHF発信機を,雌 1頭には VHF発信機及び GPS首輪を,もう 1頭の雌には VHF発信機及び GPS首輪と膣挿入型電波発信機を装着した.放獣後,VHF発信機は三角法を用いて週 2回の頻度で位置を特定した.GPS首輪は 3~ 6時間毎に測位するよう設定し,月1回の頻度で位置データの遠隔回収を行った.ライトセンサス調査は,2008年 5月~ 2012年 12月の期間で北広島市(23.4km)と江別市(26.5km)において実施した.<br> 結果,テレメトリー調査では 4頭全てに季節移動がみられ,そのうちの 3頭が JR千歳線と国道 274号線を横断した.また 1頭の雌は昨年利用した越冬地には戻らず,夏に利用した道立野幌自然公園内で越冬し,その後約 7km離れた札幌市厚別区に一時的に移動した.また,ライトセンサス調査では,目撃個体数は両市で増加傾向が見られ特に農地での観察割合が最も高くなった.<br> 以上から,捕獲個体が江別市や札幌市に移動している事と,両市でエゾシカの増加傾向が示唆された事から,今後も都市部でのエゾシカによる様々な軋轢の多発が懸念される為,市の垣根を越えた「広域管理」が必要とされる.
1 0 0 0 OA 生物コーナー
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.6, pp.368-370, 1992-06-25 (Released:2009-05-25)
1 0 0 0 字彙12卷首1卷末1卷
1 0 0 0 OA MHCはどのように進化してきたのか?
- 著者
- 笠原 正典
- 出版者
- 日本組織適合性学会
- 雑誌
- 日本組織適合性学会誌 (ISSN:21869995)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.135-138, 1994 (Released:2017-03-31)
- 参考文献数
- 19
Bourletらによって最初の非哺乳類MHC遺伝子(ニワトリのクラスIIβ鎖遺伝子)がクローニングされた後,爬虫類,両生類,硬骨魚類,軟骨魚類から続々とMHC遺伝子が分離され,現在では最も原始的な脊椎動物である無顎類(ヤツメウナギ,メクラウナギ)を除くすべての脊椎動物綱からMHC遺伝子が分離されている. 本稿では,ヒトから軟骨魚類に及ぶ多様な生物種のMHC遺伝子を解析することにより明らかとなったMHC遺伝子(分子)の進化の特徴について述べてみたい.
1 0 0 0 OA MHC領域の比較ゲノム解析
- 著者
- 椎名 隆
- 出版者
- 日本組織適合性学会
- 雑誌
- 日本組織適合性学会誌 (ISSN:21869995)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.139-155, 2006 (Released:2017-03-30)
- 参考文献数
- 26
MHC抗原はどのくらい前に誕生し, 悠久の時を経てどのように現型を獲得してきたのだろうか, また, 完成度の高いMHCシステムを有する動物は何であろうか. これらの疑問に答えるために, 筆者らは様々な動物におけるMHC領域のゲノム配列を決定し, それらの配列の間の詳細な比較解析を進めている. 本稿では, MHC領域の比較ゲノム解析の構想とこれまでに得られた知見について概説した.
1 0 0 0 日本美術年鑑
- 著者
- 美術研究所 [編集]
- 出版者
- 美術研究所
- 巻号頁・発行日
- 1936
- 著者
- Michimasa Matsumoto
- 出版者
- Fuji Technology Press Ltd.
- 雑誌
- Journal of Disaster Research (ISSN:18812473)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.6, pp.1125-1141, 2018-11-01 (Released:2018-11-01)
- 参考文献数
- 27
As of spring 2018, evacuation orders have been lifted from the entire area of Naraha Town and most of Tomioka, except for certain areas. While many evacuees have chosen their evacuation destinations as their permanent residences, some have returned to their former towns. This paper examines the factors involved in the “differentiation” and “integration” of Naraha and Tomioka residents before and after the disaster and the various forms they assume, based on the results of questionnaire surveys conducted in 2012 and 2015 as well as interviews conducted on a continuing basis since the disaster. In this process, it has become apparent that a split exists between Naraha, whose residents are moving toward “integration” with the lifting of the evacuation order, and Tomioka, whose residents are progressing toward “differentiation.”
- 著者
- 藤本 一男
- 雑誌
- 津田塾大学紀要 = Journal of Tsuda College (ISSN:02877805)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.141-153, 2017-03-16
- 著者
- Akira Toyomura Tetsunoshin Fujii Shinya Kuriki
- 出版者
- ACOUSTICAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- Acoustical Science and Technology (ISSN:13463969)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.6, pp.432-435, 2018-11-01 (Released:2018-11-01)
- 参考文献数
- 16
- 著者
- 任海 龍朗 菅野 智也 谷口 修也 田邊 亨 林正岳
- 出版者
- 福井県理学療法士会
- 雑誌
- 理学療法福井 = Journal of Fukui physical therapy (ISSN:13433040)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.23-25, 2015
1 0 0 0 IR J.デューイの芸術論にみる芸術の分類についての考え方
- 著者
- 西園 芳信
- 出版者
- 鳴門教育大学
- 雑誌
- 鳴門教育大学研究紀要 (ISSN:18807194)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.311-318, 2012
The aim of this paper is to suggest a curriculum or guidance method for art education materials in schools through making the way of thinking in Dewey's Art Experience classification clear. Dewey takes a classification way of thinking through the medium of art. From this standpoint, there are two main groups : the automatic arts which use the medium of the body(e.g. dancing, singing, etc.)and the shaping art(e.g. sculpture, architecture, etc.)which mainly exist outside of the body. Then, Dewey says that quality shown through the differences in the artistic medium will be unique, however, the quality shown is not classed in black and white, but has continuity. Following this, taking a continuous way of thinking as an artistic experience is important in the music and art materials of schools.
1 0 0 0 IR 明治神宮大会における学生参加をめぐる諸問題 : 小橋一太の果たした役割
- 著者
- 尾川 翔大
- 出版者
- 日本体育大学総合スポーツ科学研究センター
- 雑誌
- 日本体育大学スポーツ科学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.31-41, 2018-01-23
本研究は、平成29年度YMFSスポーツチャレンジ助成奨励研究「戦間期の日本におけるスポーツ政策に関する歴史学的研究」(代表:尾川翔大)の成果の一部である
1 0 0 0 OA 足底からの心血管系生理情報計測によるヘルスケア機器実現に向けた基礎的検討
- 著者
- 加藤 雄樹 井村 誠孝 黒田 嘉宏 大城 理 南部 雅幸
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.23-30, 2012-02-10 (Released:2012-07-13)
- 参考文献数
- 15
Recently, in order to achieve the prevention or early detection of diseases, many studies have been carried out to measure physiological information in everyday life. The purpose of this study is to develop the mat-type device to measure physiological information fro6m the sole. ECG (Electrocardiogram) and PPG (Photoplethysmogram) that are the indices of the cardiovascular system were adopted as physiological information. ECG is measured by conductive coupling without using the paste and capacitive coupling that is able to obtain ECG and PPG with socks. PPG is obtained by measuring the reflected light to incident infrared light at periphery. PWV (Pulse wave velocity) which is the index of the arteriosclerosis is able to be calculated from ECG and PPG. The subjective experiment reveals that the developed system can measure ECG and PPG. In addition, the system can measure ECG and PPG in case of wearing socks. Moreover, by simultaneous measurement of blood pressure, PWV was calculated by the developed system and the good correlation was found between PWV and blood pressure. In addition, the experiment showed that the PWV were changed with the blood pressure changes due to exercise. Therefore, result of this experiment showed this system has the potential to monitor the condition of cardiovascular system, and suggested the possibility to estimate the blood pressure without compression by the cuff.
1 0 0 0 中國中世四川地方史論集
1 0 0 0 中國史上の民族移動期 : 五胡・北魏時代の政治と社會
1 0 0 0 営農技術体系評価・計画システムFAPSの開発
多様な営農リスクや経営目標を明示的に考慮できる営農計画手法を簡易に利用できるように,目標分析やリスク分析が行えるシステムを開発した.このシステムでは,試算分析と数理計画法の統合的利用が可能である.システムは,表計算ソフトをベースにVBAを用いて開発されており,手法面では多様な経営目標,収益リスクおよび作業リスク,労働や土地の制約に加えて機械作業時間や施設処理能力の制約が考慮できる点が特徴である.また,システム面では,機械作業可能時間等の算出機能,演算に用いるモデル構造の選択機能が特徴である.1996年7月の試作システムの配布開始から2001年12月末までの累積利用申込者数は575件であり,このうち66%を都道府県の農業改良普及センターや試験研究機関が占めている.システムの適用事例は少なくとも80以上があり,技術評価と営農計画に大別できる.本研究により,システムが持つべき機能および基本構造は明らかになった。今後の課題としては,システムが取り扱うデータを3種類に区分し,農業技術体系データベースを構築することが求められている。
1 0 0 0 OA コミュニティビジネスとソーシャルビジネス,何が違う? 大きなビジネスマーケットで行政から民間へシフトチェンジ NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター代表理事永沢映氏に伺う
- 著者
- 森田 歌子
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.5, pp.302-303, 2009 (Released:2009-08-01)