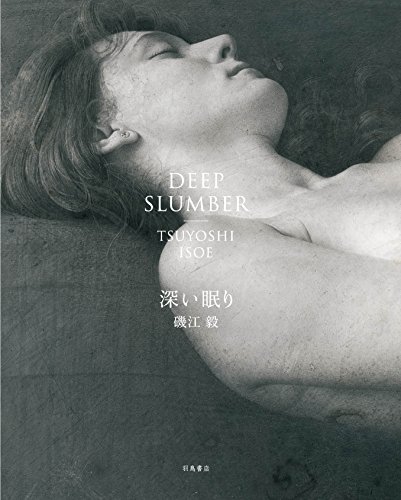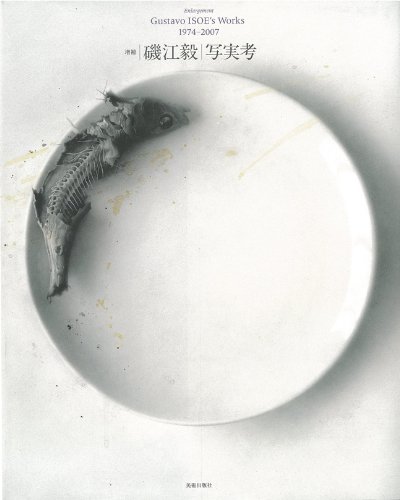1 0 0 0 消えゆく美音に酔いしれる:みみは万能への入り口
- 著者
- 東田 道久
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.7_1-7_1, 2017
街ではみみにふたをして歩いている人をよく見かける。あれはよろしくない。みみは危険察知アンテナとして最も感度の良い器官であり、それにふたをすると危険に反応できない。著者は最近とんでもないスピーカーを買い、静寂を目指して引いていく音の響きの美しさにめざめた。そこには「精度と純度」がある。人生の引き際にもその美学を反映させたいが、そのためには種々の意見に純粋な気持ちでみみを傾け、脳を刺激し続けることが大切な気がする。
1 0 0 0 医学生における喫煙状況と学業成績の関係
- 著者
- 川根 博司 松島 敏春
- 出版者
- Japan Society for Medical Education
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.6, pp.379-383, 1998
1996年度および1997年度に, 当大学の第5学年医学生における喫煙状況と学業成績の関係を調査した.喫煙状況の調査方法としては, 呼吸器内科に臨床実習のため回ってきた際に, 各班ごとに1人ひとりの喫煙習慣について聞き取りを行った.学業成績は第5学年までストレートに進級してきたか, 1回でも留年したことがあるかで評価した.1996年度, 1997年度の男子学生の喫煙率は, ストレート組でそれぞれ48.9%, 39.1%であるのに対して, 留年組では80.6%, 65.4%と有意に高かった.女子学生においても, 1996年度, 1997年度の喫煙率はストレート組がそれぞれ8.7%, 9.1%なのに, 留年組は25.0%, 37.5%と高率を示した.喫煙状況が学業成績に関係することが示唆される.わが国において, 医学生に対するアンチスモーキング教育をもっと積極的に進めていく必要がある.
1 0 0 0 OA 玉海卷1-151,156-204附刻13種
- 著者
- 宋王應麟撰
- 出版者
- 慶元路儒學刊萬暦遞修刊
- 巻号頁・発行日
- vol.[14], 1000
1 0 0 0 医学生の喫煙問題とアンチスモーキング教育
- 著者
- 増澤 徹 妙中 義之 巽 英介 宮崎 幸治 戸田 宏一 大野 孝 安 在穆 中谷 武嗣 馬場 雄造 宇山 親雄 高野 久輝 越地 耕二 福井 康裕 高橋 克己 笹川 広志 塚原 金二 土本 勝也 大海 武晴
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY FOR ARTIFICIAL ORGANS
- 雑誌
- 人工臓器 (ISSN:03000818)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.260-265, 1996-04-15
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 7
長期体内埋込実験可能な全人工心臓システムの実現のために、1) 油圧駆動用血液ポンプの改良、2) モータ駆動方式改良による効率向上、3) 経皮的エネルギー伝送部と体内埋込用電池との結合、4) 急性実験によるシステム埋め込みの検討および埋込時の発熱観察を行った。最大流量8L/min、効率12%の全人工心臓を実現し、経皮的エネルギー伝送および体内埋込用電池にて1時間以上の駆動が可能であることを確認した。また、急性動物実験にて、システム全体が体内に完全に埋込可能であること、体内に埋め込んだ状態で人工心臓の発熱が4℃以下であることを確認した。本結果より十分に長期体内埋込実験に耐えうる全人工心臓システムを実現できたと考える。今後は長期体内埋込評価実験に移行し、システムの更なる評価および改良を行っていく。
1 0 0 0 在京民放による見逃し番組無料配信の構想に驚き
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ニューメディア (ISSN:02885026)
- 巻号頁・発行日
- no.1439, pp.10-11, 2014-10-27
民放連会長が2014年9月18日の定例会見で、在京キー5局の取り組みとして、CM付き無料見逃し配信サービスを共同で検討することに合意したと発表した。「来年度中くらいには実験レベルのことができればと」と述べた。筆者の第一印象としては、自分の耳を疑うとい…
- 著者
- 増成 和敏
- 出版者
- 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.99-108, 2011
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
本論は,インターナショナル工業デザイン株式会社(IID)の設立経緯について,主として文献史料とヒアリング調査より,以下の内容を明らかにした。1)IIDは,松下幸之助の主導により氏のデザインに対する考えを実現するために設立された社外デザイン事務所である。2)竹岡リョウ一は,松下幸之助の指示によりIIDの設立準備をし,初代社長として経営を任された。3)初代副社長Y・アラン島崎を見出したのは中川電機社長中川懐春であり,アラン島崎の日本進出の意志を松下幸之助へ伝えたことが,IID設立に繋がった。4)IIDのデザイン活動は,松下電器の経営幹部からも期待されていた。IIDは家電製品の典型を創出し,製品評価を高め、販売に貢献した。
- 著者
- 森 尚也
- 出版者
- 神戸女子大学
- 雑誌
- 神戸女子大学文学部紀要 = Bulletin of The Faculty of Literature, Kobe Women's University (ISSN:13415913)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.1-14, 2016-03
1 0 0 0 レ・フレ展 = Les peintres frais
- 出版者
- 彩鳳堂画廊
- 巻号頁・発行日
- 1987
1 0 0 0 OA 和漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻
- 著者
- 寺島良安尚順 編
- 巻号頁・発行日
- vol.[74], 1600
1 0 0 0 OA 麻痺性イレウスを呈し瘻孔形成を認めた全身性エリテマトーデスの高齢男性の1例
- 著者
- 大下 恭弘 原田 亘 刈屋 憲次
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.4, pp.413-417, 1999-04-05 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
症例は60歳,男性.平成8年1月抗核抗体陽性,DNA抗体陽性,LEテスト陽性,持続性蛋白尿,貧血,リンパ球減少を認め,ARAの診断基準でSLEと診断.平成8年3月腹痛出現.腸雑音の低下および腹部X線写真にて小腸ガスと鏡面像を認め,麻痺性イレウスと診断.経口小腸造影検査では上部空腸間に瘻孔を認めた.イレウスの原因がSLEの血管炎と考えられ,プレドニン60mgより開始し,イレウスは改善したが,瘻孔は開存したままであった.
1 0 0 0 IR アダム・スミスの平等論と分配的正義論 (服部正治教授記念号)
- 著者
- 新村 聡 ニイムラ サトシ Satoshi Niimura
- 出版者
- 立教大学経済学研究会
- 雑誌
- 立教経済学研究 (ISSN:00355356)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.4, pp.49-67, 2016-02
1 0 0 0 OA 研究発表 西洋人の歌舞伎史
- 著者
- 中村 哲郎
- 出版者
- 国文学研究資料館
- 雑誌
- 国際日本文学研究集会会議録 = PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON JAPANESE LITERATURE (ISSN:ISSN0387)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.55-64, 1980-02-01
The contact of kabuki and Westerners started long ago at the end of the sixteenth century. And then after the opening of Japan to the West towards the end of the nineteenth century, the art form that the average Westerner first knew as “the theater of Japan“ was kabuki―not noh, a formalized art form with a limited audience, one for the ruling classes.However, the Western intellectuals who visited Japan in the mid-Meiji period and saw both kabuki and noh and then evaluated their quality as art forms leaned overwhelmingly towards noh, and in the twentieth century this tendency became ever more pronounced. Even within Japan, in the late Meiji periud opinions such as N atsume Soseki’s famous pro-noh and anti-kabuki stand were heard. He wrote,“I don’t hesitate to declare a performance vulgar. In contrast to this, noh can be thought of as creating a pure world separate from this everyday mundane one; it is played honestly and straightforwardly.”Thus East and West displayed a united front in this matter.In this paper the author has examined why this should have been so. In their first encounter with modern Westerners neither kabuki ―emblematic of the Edo popular arts― nor the bunraku puppet theater nor Japanes traditional music and dance gave rise to such fervent and devoted admirers as those for noh like Fenollosa or Perry. It is safe to say that, in comparison with the case of noh, there was not even one single Western intellectual in the modern age who truly loved kabuki wholeheartedly. We can probably attribute this to modern Western man, with his yardstick of individualism for judging art , finding it difficult to grasp the essence of many aspects of a riotous popular theater form like Kabuki and thereby being unable to have a genuine spiritual response to it. In this way, a substantial enconter between kabuki and modern Westerners has had to wait until recent times. It is only very recently that some Western recearchers in the dramatic arts have come to realize the fundamental character of noh and kabuki: if noh is Grecian and Apollonian , then kabuki is Roman and Dionysian.Even today a fixed attitude of disdain towards kabuki remains among a minority of intellectuals in the West, and this can be considered as one cause of the disparity that can be seen in both quality and quantity between noh research and that into kabuki in the West today and of the scanty numbers of speciali sts in Edo literature as well.
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンピュ-タ (ISSN:02854619)
- 巻号頁・発行日
- no.455, pp.132-133, 1998-10-26
「ソフトウェア自体については(中略)製造物責任の対象としていない」(経済企画庁編の「逐条解説 製造物責任法」=商事法務研究会発行=から引用)。このため,情報システムとPL(製造物責任)法は一般には関係が薄いものと考えられてきた。しかし,ついに情報システムのPLを問う国内初の訴訟が起こされた。 原告は青森県の食品メーカー,ヤマモト食品(青森県青森市)。
1 0 0 0 OA 第137回 関東部会(2017年10月28日開催:文京区)
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.151, no.Supplement, pp.S60-S120, 2016 (Released:2018-01-10)