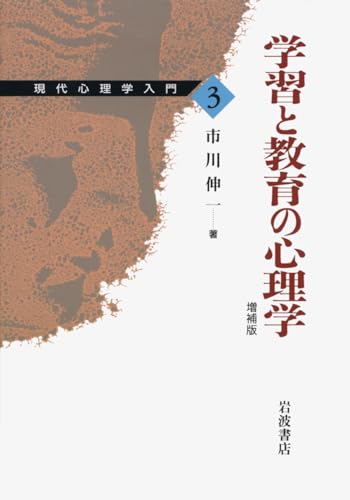1 0 0 0 OA リハビリテーション医学における症例報告の重要性
- 著者
- 出江 紳一
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会宮城県理学療法士会
- 雑誌
- 理学療法の歩み (ISSN:09172688)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.2-4, 2005 (Released:2005-04-27)
- 参考文献数
- 9
診療技術は臨床意志決定とスキルとに分けられる。症例報告は高度の診療スキルの上に成り立つものであり,その積み重ねによって臨床意志決定の能力が向上する。本稿ではリハビリテーション医学研究における症例報告の意義を,希少症例の治験,介入「無効」例から学ぶこと,介入の多様性の側面から述べ,さらに質的研究の重要性を強調した。
1 0 0 0 IR 大学における官僚制度形骸化の歴史
- 著者
- 中山 茂
- 出版者
- 神奈川大学経営学部
- 雑誌
- 神奈川大学国際経営論集 (ISSN:09157611)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.1-5, 1999-03
1 0 0 0 重要文化財安養院宝篋印塔保存修理工事報告書
- 著者
- 文化財建造物保存技術協会編
- 出版者
- 安養院
- 巻号頁・発行日
- 1980
- 著者
- 角山 剛 松井 賚夫 都築 幸恵
- 出版者
- 産業・組織心理学会
- 雑誌
- 産業・組織心理学研究 (ISSN:09170391)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.25-34, 2001-03
- 著者
- 近藤 康裕
- 出版者
- 日本ヴァージニア・ウルフ協会
- 雑誌
- ヴァージニア・ウルフ研究 (ISSN:02898314)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.66-78, 2015-10-10
1 0 0 0 OA 「存在」と「非存在」のはざま
- 著者
- 中戸 一子
- 出版者
- サイコアナリティカル英文学会
- 雑誌
- サイコアナリティカル英文学論叢 (ISSN:03866009)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, no.28, pp.41-51,88, 2008 (Released:2011-05-24)
- 参考文献数
- 8
Virginia Woolf tried to realize her ideal of human existence in her novel Orlando. It is in fantasy that a man can turn into a woman or live for nearly four centuries. Woolf had a strong wish to grasp the ‘moment of existence, ’ and this novel was to be a successful attempt to give it form, for Orlando is a fantasy.Woolf inherited a mental illness that incessantly troubled her. To her the only way to prevent the incidence of illness was to write novels, and writing was effective therapy for her.In Orlando she made her hero turn into a woman, and many a man of unpolished beauty. Both husband and wife were androgynous. Orlando and Shelmerdine spent ten days of blissful marriage which they began just after they met. They did not need many words to communicate with each other. To be together was all that they needed.At the very moment of happiness the idea of death occurred to Orlando. However, it no longer threatened her but allured her. Just like Orlando the author Virginia Woolf must have felt the same way, for the novel is in one sense the author herself, and in every work she wrote of the search of the moment of existence.In reference to “being” and “non-being, ” they are analyzed herein along the theory of C. G. Jung. For Woolf “being” was far more important for her life and for her writings than “non-being.” What are implied in these words are to be metaphysically ascertained.
1 0 0 0 OA 「第4回降水に関する国際会議」報告
- 著者
- 中北 英一 宝 馨
- 出版者
- 水文・水資源学会
- 雑誌
- 水文・水資源学会誌 (ISSN:09151389)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.286-290, 1993-09-10 (Released:2009-10-22)
1 0 0 0 OA ヴァルター・シュピースとヴァイマル文化
- 著者
- 副島 美由紀
- 出版者
- 小樽商科大学
- 雑誌
- 小樽商科大学人文研究 (ISSN:0482458X)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, pp.127-150, 1997-03-31
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1897年10月16日, 1897-10-16
1 0 0 0 OA スーパーコンピュータ利用環境の現状と展望
- 著者
- 構造工学委員会 非線形解析小委員会
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:02897806)
- 巻号頁・発行日
- vol.1990, no.421, pp.43-52, 1990-09-20 (Released:2010-08-24)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 明石 欽司
- 出版者
- 慶應義塾大学法学研究会
- 雑誌
- 法学研究 (ISSN:03890538)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.11, pp.1-40, 2015-11
論説序論第一章 予備的考察 : 国際法(史)研究におけるライプニッツの位置付け はじめに 第一節 「国際法」関連文献及び国際法概説書におけるライプニッツ (一) 一八世紀の「国際法」関連文献におけるライプニッツ (二) 一九世紀国際法概説書におけるライプニッツ (三) 二○世紀以降の国際法概説書におけるライプニッツ 第二節 国際法史研究者の視点からのライプニッツ (一) 国際法史概説書におけるライプニッツ (1) 一九世紀末までの国際法史概説書におけるライプニッツ (2) 二○世紀以降の国際法史概説書におけるライプニッツ (二) 国際法史の個別研究におけるライプニッツ まとめ(以上, 本号)第二章 ライプニッツの「法」観念 はじめに 第一節 ライプニッツの法認識を巡る若干の特色 第二節 ライプニッツの法観念の基本的構成 まとめと若干の考察(以上, 八十九巻四号)第三章 ライプニッツの「国家」観念 はじめに 第一節 「社会」 第二節 国家観念を巡る諸問題 第三節 国家の抽象的人格性 まとめと若干の考察(以上, 八十九巻五号)第四章 ライプニッツの「主権」理論 : "Suprematus"観念の分析を中心として はじめに 第一節 「統治権」観念の錯綜 第二節 "Suprematus"・"summa potestas"・"superioritas territorialis"・"Souveraineté" 第三節 "Suprematus"理論における帝国等族 第四節 "Suprematus"の特質 まとめと若干の考察(以上, 八十九巻六号)第五章 ライプニッツの「国際法」観念 はじめに : ライプニッツの欧州社会観とユース・ゲンティウムを巡る諸観念 第一節 ライプニッツのユース・ゲンティウム理論 第二節 ライプニッツのユース・ゲンティウム理論の内実 まとめと若干の考察結論(以上, 八十九巻七号)
1 0 0 0 OA 蔵持重裕先生の略歴と主要業績 (日本中世史特集号)
- 雑誌
- 史苑
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.1, pp.254-260, 2015-01
1 0 0 0 IR 文機能とアスペクトの相関をめぐる一考察 : テイル形の人称制限解除機能を中心に
- 著者
- 山岡 政紀
- 出版者
- 創価大学日本語日本文学会
- 雑誌
- 日本語日本文学 (ISSN:09171762)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.27-39, 2014-03-20
日本語の動詞テイル形の解釈はアスペクトの視点から行われることが多いが,「ああ,腹が立つ」のように人称制限のある主観的感情表現をテイル形に換えると,「彼は腹が立っている」のように人称制限が解消される。このような現象を根拠として,テイル形のより本質的な意味をアスペクトではなくエビデンシャルであるとする主張がなされている。本稿では動詞ル形が持つ発話時への局在性とテイル形が持つ時間幅との意味対立が結果として <感情表出> と <状態描写> という文機能の対立を表していることを論証した。また,「私は腹が立っている」のような第一人称主語で感情表現のテイル文は <状態描写> ではあるがエビデンシャルとは言えないので,それを根拠の一つとしてテイル形の意味はエビデンシャルよりもアスペクトの方がより本質的であることを考察した。
1 0 0 0 原菊太郎文庫
- 著者
- 徳島県立近代美術館編集
- 出版者
- [徳島県立近代美術館]
- 巻号頁・発行日
- 1996
1 0 0 0 IR 広島県三次市の地域活性化政策によるワイナリーの役割と観光振興 (近藤和明教授退職記念号)
- 著者
- 富川 久美子 トミカワ クミコ Kumiko Tomikawa
- 出版者
- 広島修道大学ひろしま未来協創センター
- 雑誌
- 修道商学 = Papers of the Research Society of Commerce and Economics (ISSN:03875083)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.73-93, 2015-09