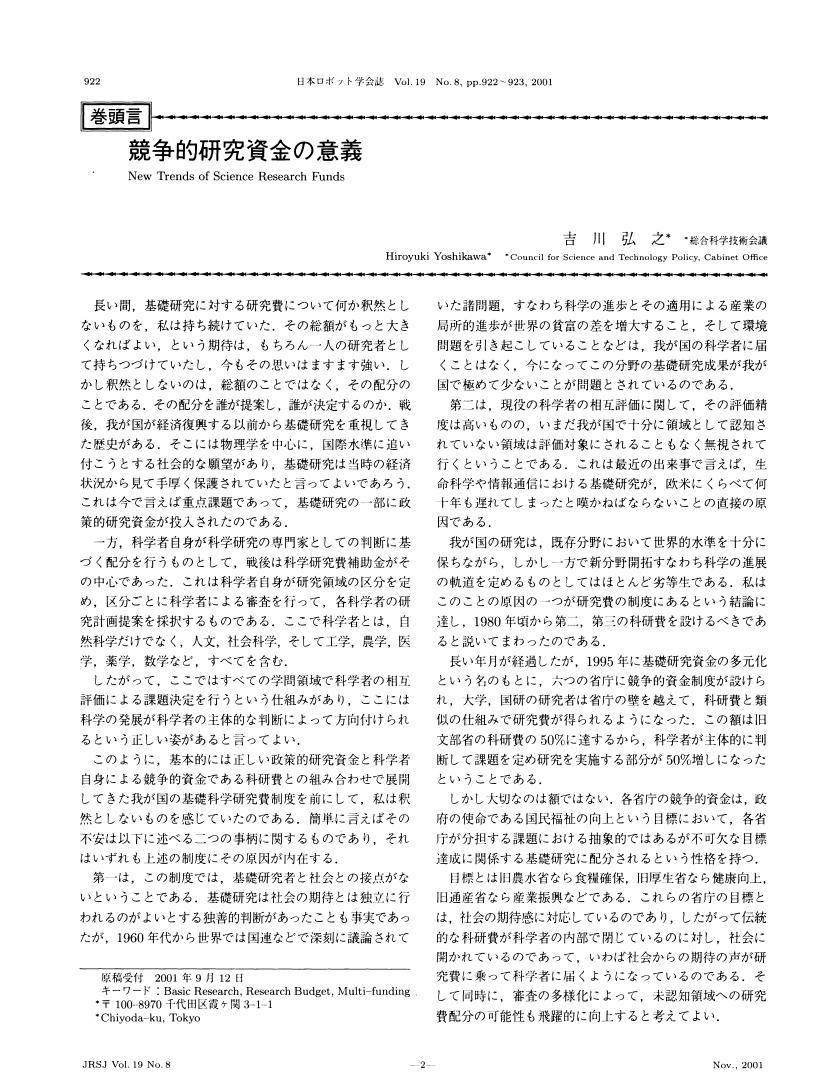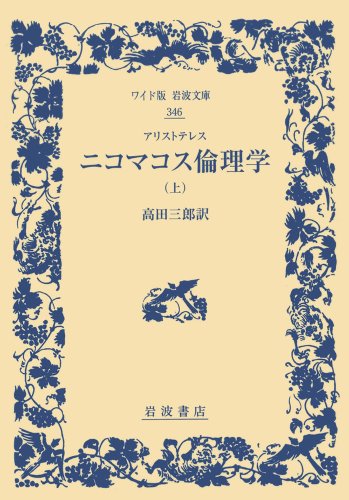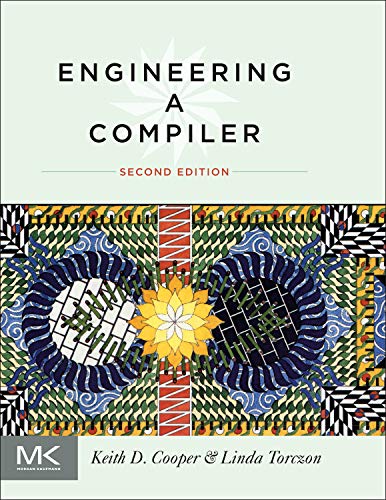- 著者
- So Kanako Tei Yuna Zhao Meng Miyake Takahito Hiyama Haruka Shirakawa Hisashi Imai Satoshi Mori Yasuo Nakagawa Takayuki Matsubara Kazuo Kaneko Shuji
- 出版者
- Nature Publishing Group
- 雑誌
- Scientific Reports (ISSN:20452322)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, 2016-03-17
- 被引用文献数
- 35
「しびれ」による痛みのメカニズムを解明 -糖尿病や血流障害によるしびれ治療薬の開発に期待-. 京都大学プレスリリース. 2016-03-18.
1 0 0 0 教育月報
- 出版者
- 栃木県教育委員会事務局
- 巻号頁・発行日
- 1950
1 0 0 0 OA 競争的研究資金の意義
- 著者
- 吉川 弘之
- 出版者
- 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.8, pp.922-923, 2001-11-15 (Released:2010-08-25)
1 0 0 0 OA 環境サイドから見た腐食防食技術の課題と展望:原子力エネルギーの利用
- 著者
- 山本 正弘 佐藤 智徳
- 出版者
- 公益社団法人 腐食防食学会
- 雑誌
- Zairyo-to-Kankyo (ISSN:09170480)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.193-198, 2014-04-15 (Released:2014-11-14)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 酸化金屬磁石に就て
- 著者
- 加藤 與五郎 武井 武
- 出版者
- 社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 工業化学雑誌 (ISSN:00232734)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.506-509, 1933
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1886年10月08日, 1886-10-08
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1903年12月29日, 1903-12-29
- 著者
- 加藤 與五郎 武井 武
- 出版者
- The Mining and Materials Processing Institute of Japan
- 雑誌
- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.539, pp.167-176, 1930
1 0 0 0 電子工作キットを利用した音声認識ロボットの製作
- 著者
- 福庭 隆弘 北村 達也
- 出版者
- 甲南大学
- 雑誌
- 甲南大学紀要. 知能情報学編 (ISSN:18830161)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.131-144, 2010
1 0 0 0 ニコマコス倫理学
- 著者
- アリストテレス [著] 高田三郎訳
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 2012
- 著者
- 林 隆伯 中泉 文孝 矢野 博明 岩田 洋夫
- 出版者
- 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.163-171, 2005
- 被引用文献数
- 6 2
We developed a spherical immersive projection display, a new model of EV(EnspheredVision). This display consists of spherical screen, plane mirror, convex mirror, six projectors and mechanical shutter. Multiple projector enables to improve the image resolution and brightness as compared with the former EV. Observer can watch the 360 degree panoramic stereo image using liquid crystal shutter glasses.
1 0 0 0 江戸時代方言資料の調査とその収集
すでに収集した、崎門派の新発田藩儒臣渡辺予斎の資料を分析するとともに、本年度も予斎関係の資料の収集に努めた。新発田市立図書館には、新発田藩校の資料が纒めて収められているため、館長に依頼して予斎関係資料の他の情報を得られるようにした。その結果、予斎についての情報を持っている当地の郷土史家を知ることができ、『国書総目録』掲載以外の資料が他にあることを確かめることができた。氏所蔵のコピー(以下、コピー本と略称)とこれまで収集した同じ資料を比較すると、筆跡が同一であることが判明した。東北大学本には「速水義行録」と記されているため、いずれも速水義行の書写と考えられる。重複本として『予斎先生鞭策録会読箚記』の例を見ると、コピー本は、丁寧な書体で書写されている点から、清書本と考えられ、東北大学本は、草稿本に当たる。一方、『予斎先生訓門人会読箚記』もコピー本は、丁寧な書体で書写されて、清書体の体裁をとっているが、それは、途中までで、後は下書きの形態になって完成を見ていない。この点でコピー本だけでは不安が残るので、原本によって調査しなければならないが、原本所蔵者との連絡が取れていないので、この比較は今後に回すしかない。同一本が二本ある場合、正本と副本との関係で後に遺されたのではなかろうかと考えられる。『予斎先生鞭策録会読箚記』をコピー本と東北大学本とで比較すると、いずれにも脱文、脱字、清濁の有無等があって方言資料としての優劣は、いまだ決めかねている。資料調査の過程で、講義録は講義者の出身地の言葉で纒められているため、当時の講義録の調査が大々的に行なわれるべきことを痛感した。
1 0 0 0 Engineering a compiler
- 著者
- Keith D. Cooper Linda Torczon
- 出版者
- Elsevier/Morgan Kaufmann
- 巻号頁・発行日
- 2012
桜島は活発な火山活動を続け、火山灰は周辺地域の生活環境や生産活動に大きな影響を与えている。この火山灰の処理については、各自治体は苦慮しているのが現状である。本研究は、この無用の廃物として処理に因っている火山灰を材料面に有効的に利用することを目的とするものであり、その研究成果の概要は次のとおりである。1、火山灰中の水に可溶性フッ素イオン、塩化物イオンおよび硫酸イオンなどの陰イオンを浮選法により分離除去した。除去率はF^ー:89%,Cl^ー:87%,SO^<2ー>_4:60%を示した。2.コンクリ-ト中の鉄筋の電位差を測定し、腐食状況と電位差との相関を検索した。その結果、腐食の経時変化とともに電位の変動が認められた。3.火山灰は海砂に比べ、比重が大きく、摩耗抵抗性もよい性質を有している。したがって、コンクリ-ト用細骨材として用いた場合、高強度コンクリ-トおよび摩耗特性を求める構造物への利用が十分可能である。4.火山灰の陶磁器素地への利用は、火山灰60〜70%、粘土30〜40%を配合することにより、従来の黒薩摩焼の焼成温度より160℃も低い温度で焼成することができ、省エネルギ-化が画られた。また、陶磁器釉薬への利用は、火山灰325メッシュ通過粒分を単独で用い、良好な釉薬が得られた。5.火山灰80%、粘土20%の配合割合の50mm×50mm×5mmのテストピ-スを作り、焼成温度1160℃で、1〜2時間焼成することにより、陶磁器質タイルを試作することができた。これは日本工業規格の試験法に適合し実用化できることがわかった。
- 著者
- 和田 幸司
- 出版者
- 日本法政学会
- 雑誌
- 法政論叢 (ISSN:03865266)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.162-186, 2012
1 0 0 0 近世西本願寺門跡の地位獲得と葛藤
- 著者
- 和田 幸司
- 出版者
- 吉川弘文館
- 雑誌
- 日本歴史 (ISSN:03869164)
- 巻号頁・発行日
- no.771, pp.17-31, 2012-08
- 著者
- 和田 幸司
- 出版者
- 近大姫路大学教育学部紀要編集委員会
- 雑誌
- 近大姫路大学教育学部紀要 (ISSN:18834515)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.89-101, 2013
1 0 0 0 近世大坂渡辺村真宗寺院の特質と身分上昇志向
- 著者
- 和田 幸司
- 出版者
- 日本政治経済史学研究所
- 雑誌
- 政治経済史学 (ISSN:02864266)
- 巻号頁・発行日
- no.561, pp.17-45, 2013-09
1 0 0 0 宗旨人別帳の別記載化と身分 : 摂津国川辺郡火打村を事例として
- 著者
- 和田 幸司
- 出版者
- 近大姫路大学教育学部紀要編集委員会
- 雑誌
- 近大姫路大学教育学部紀要 (ISSN:18834515)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.264-251, 2014