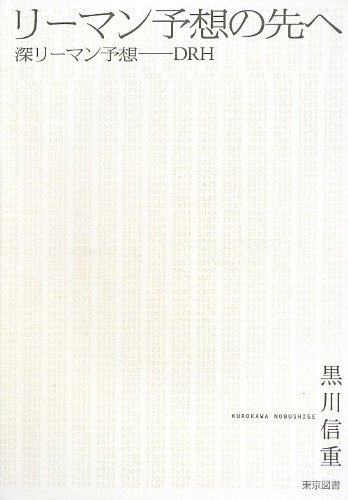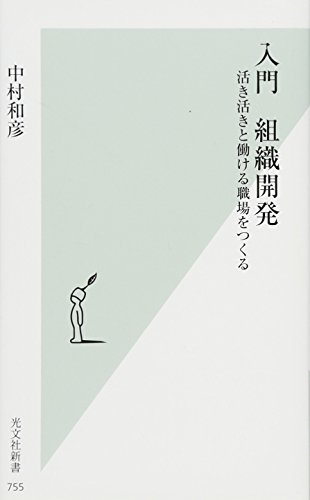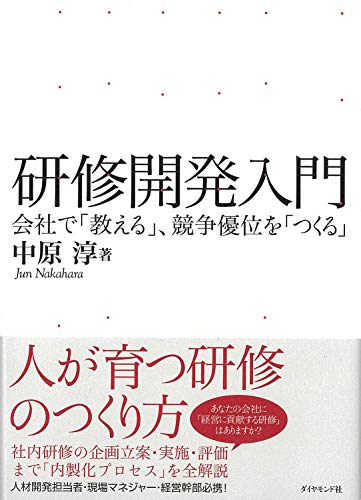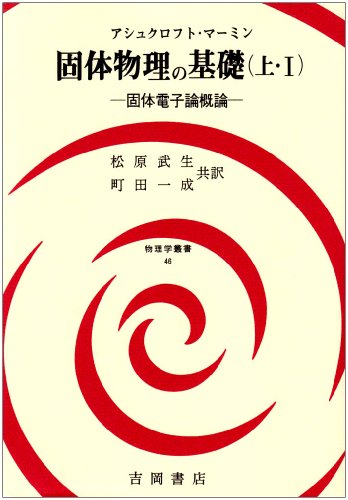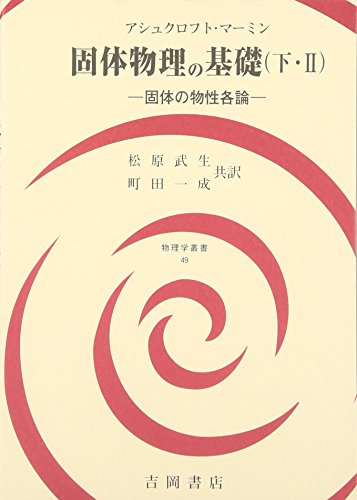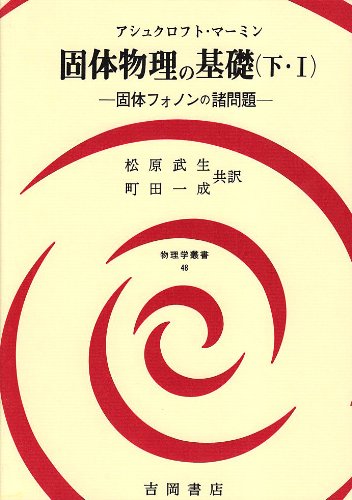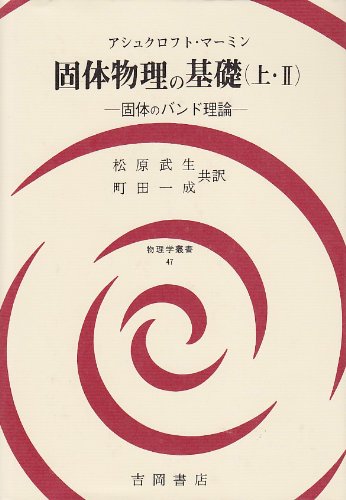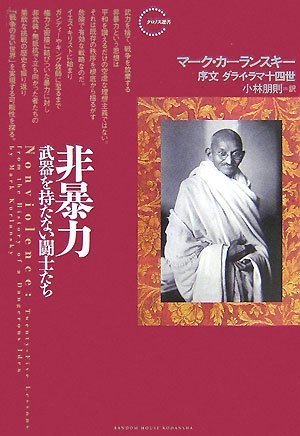1 0 0 0 IR 剣道における心理的競技能力調査について
- 著者
- 植田 史生 福本 修二 吉田 泰将 石手 靖 望月 康司 大嶽 真人
- 出版者
- 慶應義塾大学体育研究所
- 雑誌
- 体育研究所紀要 (ISSN:02866951)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.25-33, 2005-01
For best performance in competitive sports, technique, stamina, spirit, and good conditioning are generally considered to be necessary. In Kendo a concert of "Shin-Gi-Tai (Mind-Technique-Body)" or "Shin-Ki-Ryoku (Mind-Spirit-Power)" is also an important element of a scoring hit. And as one becomes a more experienced player, he will notice the mind is the most crucial of all. When players do well in practice or matches, they most often say their "spirits" or "energies" are running high. These words sometimes mean concentration, perseverance, willpower, or fighting spirit. In this study a "Diagnostic Inventory of Psychological-Competitive Ability for Athletics 2 (DIPCA.2)" is conducted and analysis is made on the participants of the All Japan Kendo Federation Special Training Program and the members of the varsity Kendo teams of a "K" University and its affiliate high school. The results are as follows.1. In the comparison of the "five factors," national representatives returned high marks on "will to win," "mental concentration and stability," "confidence," and "strategic planning," while the ordinary participants of the training program scored high in "teamwork." However, no statistical significant difference was observed between these two groups.2. There was a significant difference in "confidence" in the "twelve degrees" between national representatives and ordinary participants.3. No significant difference was observed in "will to win" among all groups.4. Significant differences existed in "fighting spirit" and "perseverance" between college and high school students.
1 0 0 0 OA 『平家物語』の建礼門院造形 : 延慶本を中心に
- 著者
- 趙 文珠
- 出版者
- 梅光学院大学
- 雑誌
- 日本文学研究 (ISSN:02862948)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.12-21, 2001-02-20
1 0 0 0 リーマン予想の先へ : 深リーマン予想--DRH
1 0 0 0 入門組織開発 : 活き活きと働ける職場をつくる
1 0 0 0 研修開発入門 : 会社で「教える」、競争優位を「つくる」
1 0 0 0 IR 近世初期の小豆島・豊島(手島)における石場に関する史料について
- 著者
- 白峰 旬
- 出版者
- 別府大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 別府大学大学院紀要 (ISSN:13450530)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.41-64, 2010-03
1 0 0 0 OA 連載シリーズ:科学英語を考える「the ってどういう意味?」
- 著者
- ガリー トム
- 出版者
- 東京大学大学院理学系研究科・理学部
- 雑誌
- 東京大学理学系研究科・理学部ニュース
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.13-13, 2005-05
第6回 : 「 相手が知っているかどうか」ということと情報の流れ
1 0 0 0 イスも通路も BIG ! ! アラブ人の集まるシネコン
1 0 0 0 OA 連載シリーズ : 科学英語を考える
- 著者
- ガリー トム
- 出版者
- 東京大学大学院理学系研究科・理学部
- 雑誌
- 東京大学理学系研究科・理学部ニュース
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.5, pp.16-17, 2006-01
第10回 : 英語らしい英語を書くコツ
- 著者
- Jeong Hoon Yang Bum Sung Kim Woo Jin Jang Joonghyun Ahn Taek Kyu Park Young Bin Song Joo-Yong Hahn Jin-Ho Choi Sang Hoon Lee Hyeon-Cheol Gwon Seung-Hyuk Choi
- 出版者
- 日本循環器学会
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-15-0673, (Released:2015-11-19)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 32
Background:Limited data are available on the long-term clinical outcomes of coronary chronic total occlusion (CTO) patients who receive optimal medical therapy (OMT) compared with percutaneous coronary intervention (PCI).Methods and Results:Between March 2003 and February 2012, 2,024 patients with CTO were enrolled in a single-center registry. Among this patient group, we excluded CTO patients who underwent coronary artery bypass grafting and classified patients into the OMT group (n=664) or PCI group (n=883) according to initial treatment strategy. Propensity-score matching was also performed. The primary outcome was cardiac death. The median follow-up duration was 45.8 (interquartile range: 22.8–71.1) months. In the PCI group, 699 patients (79.2%) underwent successful revascularization. In the propensity-score matched population (533 pairs), there was no significant difference in the rate of cardiac death between the OMT and PCI groups (hazard ratio, 1.57; 95% confidence interval, 0.91–2.72, P=0.11). In the subgroup analysis, there were no significant interactions between the PCI strategy and cardiac death among several subgroups except that regarding collateral flow grades 0–2 vs. those with grade 3 (P=0.01).Conclusions:As an initial treatment strategy, PCI did not reduce cardiac death compared with OMT for the treatment of CTO in the drug-eluting stent era.
1 0 0 0 電磁気
- 著者
- Edward M.Purcell [著]
- 出版者
- 丸善
- 巻号頁・発行日
- 1989
1 0 0 0 固体電子論概論
- 著者
- アシュクロフト マーミン著 松原武生 町田一成訳
- 出版者
- 吉岡書店
- 巻号頁・発行日
- 1981
1 0 0 0 固体の物性各論
- 著者
- アシュクロフト マーミン著 松原武生 町田一成訳
- 出版者
- 吉岡書店
- 巻号頁・発行日
- 1982
1 0 0 0 固体フォノンの諸問題
- 著者
- アシュクロフト マーミン著 松原武生 町田一成訳
- 出版者
- 吉岡書店
- 巻号頁・発行日
- 1982
1 0 0 0 固体のバンド理論
- 著者
- アシュクロフト マーミン著 松原武生 町田一成訳
- 出版者
- 吉岡書店
- 巻号頁・発行日
- 1981
1 0 0 0 電磁気
- 著者
- Edward M. Purcell [著] 飯田修一監訳
- 出版者
- 丸善
- 巻号頁・発行日
- 1970
1 0 0 0 非暴力 : 武器を持たない闘士たち
- 著者
- マーク・カーランスキー著 小林朋則訳
- 出版者
- ランダムハウス講談社
- 巻号頁・発行日
- 2007
1 0 0 0 OA 4階層プラン認識モデルを使った対話の理解
- 著者
- 飯田 仁 有田 英一
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.6, pp.810-821, 1990-06-15
日本語の話し言葉による対話では 述語の代用的表現 格要素の省略 縮小表現等を使った断片的な発話が多く現れる.このような特徴を持つ対話の理解および翻訳を行うには 各発話を対話の進展の流れに沿って解釈することが必要である.本論文では対話を理解するための一つの機構として 4階層のプラン認識モデルを使った目標指向型対話の理解の手法を提案する.4階層のプランとは(1)ある情報の交換が話し手と聞き手の間の順序付けられた発話で表現できるという知識であるインタラクションプラン (2)対話を介した情報伝達のための行為が一連の情報伝達行為で実現できるという知識であるコミュニケーションプラン (3)ある行為が順序付けられた行為の達成で実現できるという知識であるドメインプラン (4)対話が対話展開のための言語運用行為で実現できるという知識であるタイアログプランである.これらのプランを利用すると対話の進展に伴う各発話と話題領域の知識との関係付けを漸次進めていくことが可能となり 対話全体に渡る構造をつくることができる.対話の構造の中で断片的な発話の解釈をすることにより代用的表現 格要素の省略を復元できる.
- 著者
- 青木 俊明 星 光平 佐藤 崇
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集D (ISSN:18806058)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.43-53, 2006
本研究では集団状況における協力意向の形成機構を検討した.私的利益,手続き的公正,同調圧力を操作した心理実験の結果,以下の知見および示唆を得た.1)集団状況では,私的利益感,同調圧力感が重要な態度形成要因であること.2)同調圧力を作用させた実験参加者の約1割が公的受容を伴う同調で態度を形成していた.3)私的受容による同調と合わせると,4割強の実験参加者が同調圧力の影響を受けて態度を形成していた.4)私的受容と公的受容の分岐要因は,同調圧力感,私的利益感,手続き的公正感と推察される.5)同調を示す場合,私的利益感と手続き的公正感が低く,同調圧力感が高い場合には公的受容が促され,私的利益感と手続き的公正感が高く,同調圧力感がさほど高くない場合には私的受容が促されることが示唆された.