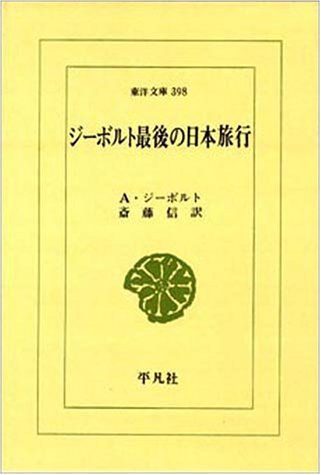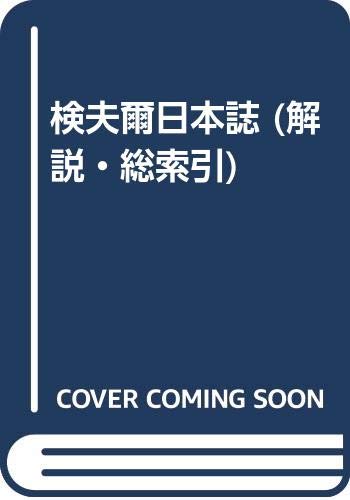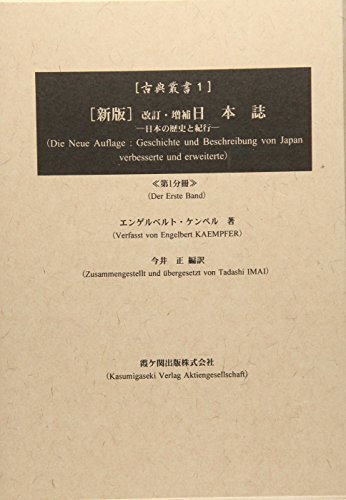1 0 0 0 OA 太陽熱利用デシカント空調システムに対する室内空調負荷および換気回数の影響評価
- 著者
- 児玉 昭雄 大蔵 将史
- 出版者
- 社団法人空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 空気調和・衛生工学会論文集 (ISSN:0385275X)
- 巻号頁・発行日
- no.127, pp.11-18, 2007-10-05
太陽熱温水器を駆動熱源とするデシカント空調機と顕熱処理用の冷却コイルを組み合せた太陽熱利用デシカント空調システムについて,全冷房出力に対するデシカント空調部の寄与割合に着目し,室内全熱負荷,顕熱比,換気回数の影響を調べた.処理風量と太陽熱温水器の循環水流量が室内顕熱負荷と連動する本システムでは,顕熱負荷の増加に伴って除湿機再生温度が低下することに加えて,顕熱交換器の低温側空気中の外気割合が増加することで給気温度が土昇し,デシカント空調プロセス部の寄与割合は低下する.換気回数が増加しても再生空気入口温度が低下して顕熱交換器で給気温度が低下するため,冷却コイルに求められる顕熱処理能力は増大しない.
1 0 0 0 OA 太陽熱利用開放形吸収式除湿乾燥システムの模型再生器に関する実験研究
- 著者
- 崔 光煥 木村 建一
- 出版者
- 社団法人空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 空気調和・衛生工学会論文集 (ISSN:0385275X)
- 巻号頁・発行日
- no.51, pp.43-51, 1993-02-25
- 被引用文献数
- 1
再生器,熱交換器,蓄乾槽,および除湿器からなる太陽熱利用開放形吸収式除湿乾燥システムのうち,再生器について屋内で行った実験の結果を報告する.従来の屋外の実験では,外気条件の変動,特に風速の変動が激しいため,再生器の特性を把握することが困難である.そこで,開放式模型再生器を製作し,定常状態で再生表面の温度を一定にし,水溶液の流量を制御しながら再生器の空気層の高さと風速を変え屋内実験を行い,風速と風量の再生量に及ぼす影響を調べた.その結果,空気層の高さが異なる場合,風量の水分蒸発量への影響はほとんどなく同じ空気層の場合には風速が大きいほうの再生量が多かった.また,吸収剤として使用した塩化リチウム水溶液の電導率と温度を測定しあらかじめ作っておいた塩化リチウム水溶液用標準濃度曲線を用いて運転中に水溶液の抽出をせずに濃度を容易に連続して求める新しい方法を提案した.実際にこの方法で濃度を求め連続記録することができた.実験結果から計算して求めた無次元数間の関係は文献所載の層流に対する物質移動の式に比べ0.5m/s以上の風速域ではやや離れるが,より低風速域ではかなり異なる結果となった.
1 0 0 0 自己増殖オートマトンの設計と試作-生命の数学モデル-
- 著者
- 高橋 磐郎 早迫亮一
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.238-248, 1990-02-15
- 被引用文献数
- 1
オートマトンによる自己増殖器官の実現には多くの試みが行われている.基本的アイディアはNeumannによって そしてそれを引き継いだBurks らによって理論的には一応完成したと考えられる.またその改良なども多く報告されている.しかし実際に動作可能な実体として設計されたものは報告されていない.本論文では 2次元格子によるNeumannのモデルを3次元格子に拡張することにより オートマトンによる自己増殖器官の設計に成功したので その概要について報告する.Neumannのモデルは 2次元格子上における29種の状態のオートマトンによるものであるが 2次元格子上では混線なしに情報を交差させることが難しい.NeumannはCrossing Organ等を導入することによりそれを解決しようとしたが 膨大な容量が必要であり またきわめて複雑な同期操作を行わなければならなかった.われわれは 領域を3次元格子空間に拡張することにより その情報の交差の問題を解決した.そのため オートマトンの状態の種類は41種に増えたが 情報の交差は著しく簡単になった.その他いくつかの改良を加え 各機能における構造を極度に簡潔化したため オートマトンによる自己増殖器官が実現できた.われわれの作成した自己増殖器官は1O0x20Oの2層からなり おそらく最も簡単なものであろうと確信している.
1 0 0 0 IR 十九世紀後半イギリスにおける労働者状態
- 著者
- 菊池 光造
- 出版者
- 京都大學經濟學會
- 雑誌
- 経済論叢 (ISSN:00130273)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.1, pp.p1-32, 1977-07
1 0 0 0 IR イギリス鉄鋼合理化と全国レベルの労使関係
- 著者
- 菊池 光造
- 出版者
- 学術雑誌目次速報データベース由来
- 雑誌
- 經濟論叢 (ISSN:00130273)
- 巻号頁・発行日
- vol.140, no.5, pp.15-39, 1987
- 著者
- 菊池 光造
- 出版者
- 大阪商業大学
- 雑誌
- 地域と社会 (ISSN:13446002)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.5-8, 2007-09
1 0 0 0 OA カイラル磁性体におけるスピン位相制御の理論
1 0 0 0 捜神後記訳注(1)
- 著者
- 捜神後記研究會
- 出版者
- 中國文學研究会
- 雑誌
- 中國學論集 (ISSN:09183299)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.54-67, 2004-02
1 0 0 0 OA 国民に問ふ : 金輸出再禁止是非
- 著者
- 高橋是清, 井上準之助 [著]
- 出版者
- 明治図書出版協会
- 巻号頁・発行日
- 1932
- 著者
- von Philipp Franz von Siebold
- 出版者
- auf Kosten des Verfassers
- 巻号頁・発行日
- 1854
1 0 0 0 シーボルトの最終日本紀行
1 0 0 0 ジーボルト最後の日本旅行
1 0 0 0 ジーボルト最後の日本旅行
- 著者
- 増田 彩乃 田中 智之
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. E-1, 建築計画I, 各種建物・地域施設, 設計方法, 構法計画, 人間工学, 計画基礎 (ISSN:13414518)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.789-790, 2008-07-20
- 著者
- 駒崎 久明 楠見 孝 繁桝 算男
- 雑誌
- 認知科学 = Cognitive studies : bulletin of the Japanese Cognitive Science Society (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.4, pp.97-107, 1998-12-01
- 被引用文献数
- 8
1 0 0 0 OA アルゼンチン経済の危機と「大来レポート」(秋元英一先生退職記念号)
- 著者
- 阿部 清司
- 出版者
- 千葉大学
- 雑誌
- 千葉大学経済研究 (ISSN:09127216)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.399-418, 2008-12
Argentina suffered from severe economic crisis in 2001, which was triggered by the dollar peg, excessive issues of national bonds and the IMF policy package. More fundamentally, the crisis was caused by the bad governance, the widespread corruption, the lack of industrialization, the lack of modern market mechanism, the lack of democracy, the lack of response to the globalization, etc. Argentina has attained independence since 1816, but there still exist political rivalry between local and central governments. The disunity has inhibited any modern social reform, with the old social system still dominating the country. Argentina now lives on the century-old heritages with any social modernization neglected from generation to generation. The lacks that caused the crisis were also pointed out by the socalled Okita Report which was produced by the joint Argentina-Japanese research team headed by Dr. Saburo Okita. The Okita Report 1 of 1986 makes an in-depth analysis of macro economy, agriculture, industry, transportation and foreign trade of Argentina with valuable policy recommendations. The Okita Report 2 of 1996 focused on foreign trade, especially trade with Asian countries, and foreign direct investment from Asia, pointing out strongly the lack of willingness to export, develop and modernize. The Okita Reports mean a culmination of good relations between Argentina and Japan. A revaluation of the Okita Report was done at a conference in Buenos Aires in 2006, twenty years after the Okita Report 1. Many participants admitted that the value of the Okita Report for Argentina Economy remains intact. Its practical proposal the essence of which contains the need of industrialization will retain its precious value for the future for Argentina. It will be referred to by farsighted policy makers of Argentina in coping with the tide of globalization. Otherwise, Argentina would remain underdeveloped while other Latin American countries make further progress.
1 0 0 0 検夫爾日本誌
- 著者
- エンゲルベルト・ケンペル著 坪井信良訳
- 出版者
- 霞ケ関出版
- 巻号頁・発行日
- 1997
1 0 0 0 日本誌 : 日本の歴史と紀行
- 著者
- エンゲルベルト・ケンペル著 今井正編訳
- 出版者
- 霞ヶ関出版
- 巻号頁・発行日
- 2001