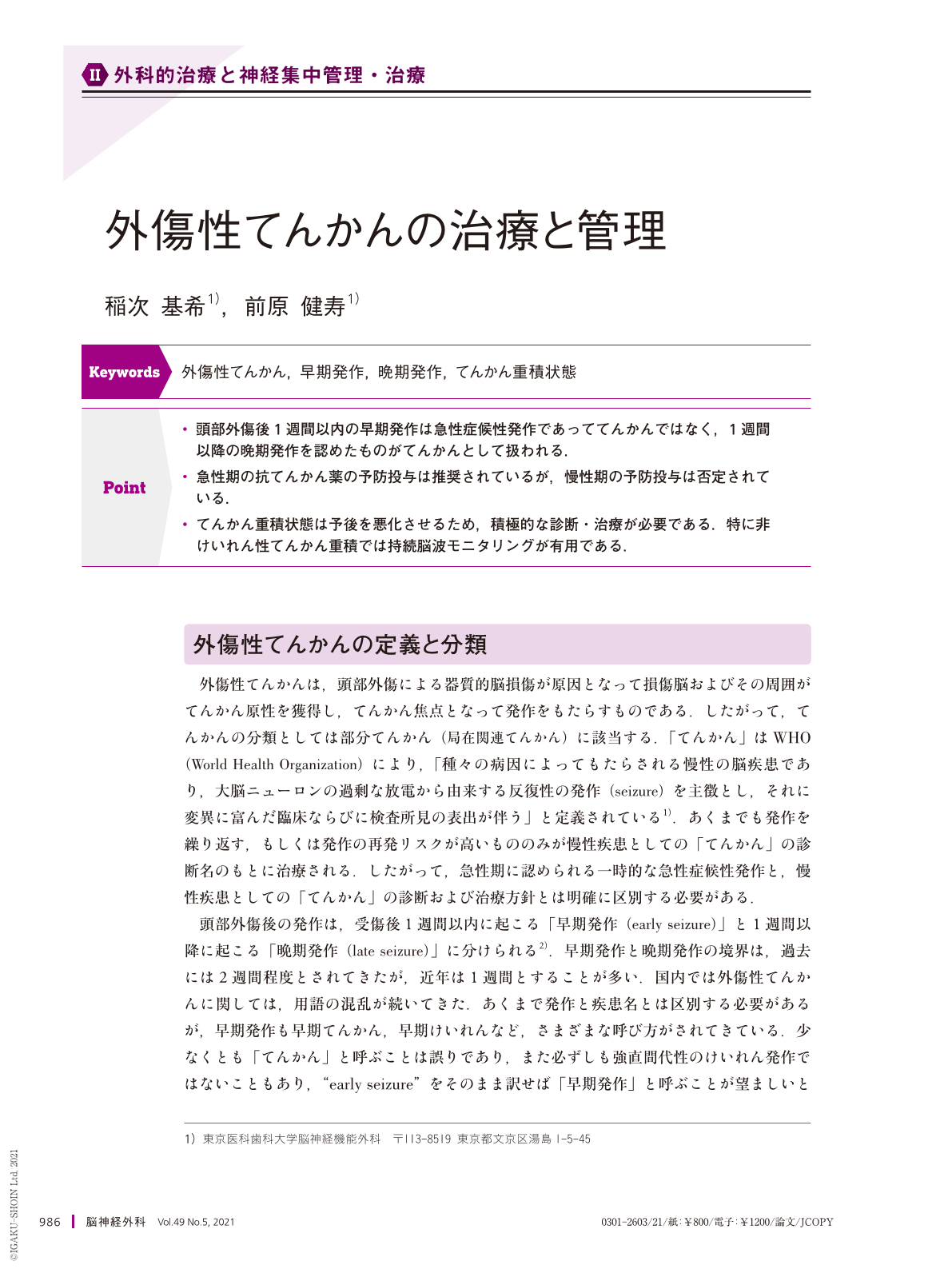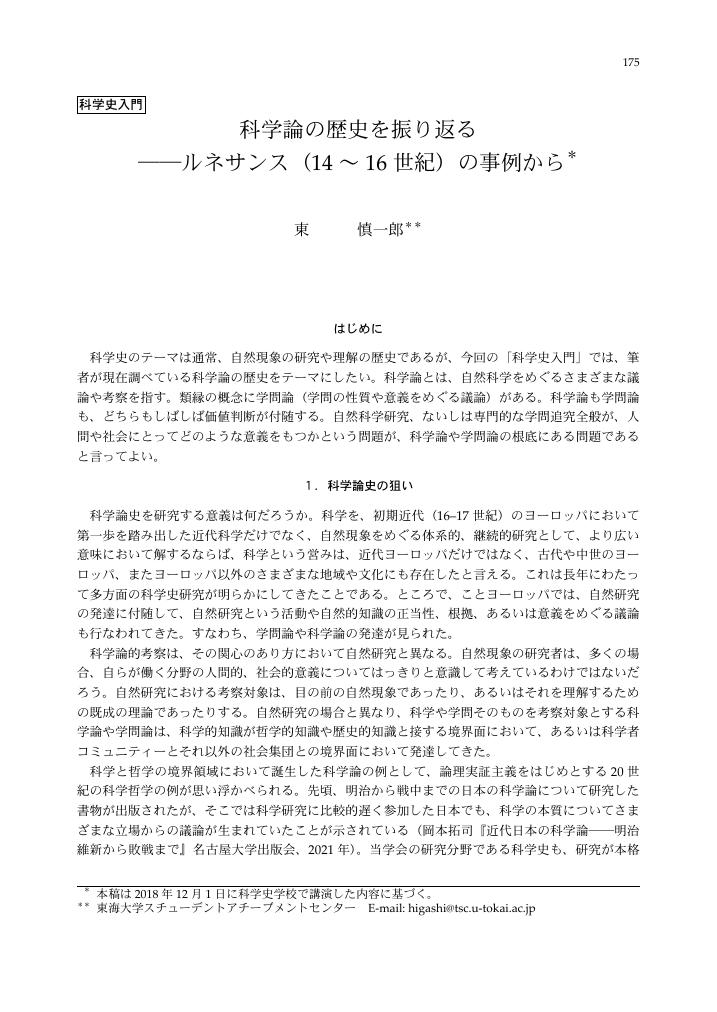3 0 0 0 鏡像としての村落--横溝正史『八つ墓村』
- 著者
- 倉田 容子
- 出版者
- 昭和文学会
- 雑誌
- 昭和文学研究 (ISSN:03883884)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, pp.13-25, 2011-09
3 0 0 0 OA 醸造物の熟成と調熟
- 著者
- 大塚 謙一
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.83-86, 1974-02-15 (Released:2011-11-04)
熟成の問題は醸造物にとって, その付加価値を高める常に最も重大な手法であり, 多様化の時代に入り, 益々その重要性が高まりつつある。本年はこの問題について一連の解説を予定しているが, まずこの方面の権威である大塚博士に御執筆をお願いした。熟成と調熟を明確に区別すべきだなど, ユニークな提案が盛リ込まれている。
3 0 0 0 OA 日本の恐竜研究はどこまできたのか?:東・東南アジアの前期白亜紀フォーナの比較
- 著者
- 柴田 正輝 尤 海魯 東 洋一
- 出版者
- 日本古生物学会
- 雑誌
- 化石 (ISSN:00229202)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, pp.23-41, 2017-03-31 (Released:2019-04-03)
- 被引用文献数
- 1
Researches on Japanese dinosaurs make progress dramatically in these decades, since the first dinosaur discovery in the present territory of Japan was made in 1978. Currently, Japanese dinosaur fossils have been unearthed in 16 prefectures of Japan, from Hokkaido to Kagoshima. However, all named Japanese dinosaurs, seven original genus and species, are known only from three localities of the Lower Cretaceous of the Inner Zone of Southwest Japan; Kuwajima and Kitadani formations of the Tetori Group in Ishikawa and Fukui respectively, and “lower formation” of the Sasayama Group in Hyogo. Abundant dinosaur body fossil records from these sites make it possible to compare and discuss as a dinosaur assemblage, namely “Dinosaur Fauna (hereafter DF)”, to other Early Cretaceous DFs in East and Southeast Asia. Comparisons of Shiramine (Kuwajima Fm.), Katsuyama (Kitadani Fm.) and Tamba-Sasayama (“lower formation”) DFs to Hekou, Jehol and Mazongshan DFs from China (North China Craton) and Khorat DF from Thailand (Indosina Terrane) shows interesting results on relationships among faunal changes, paleogeography and paleoenvironment; Shiramine and Jehol DFs, in the early Early Cretaceous, shares faunal similarities under a relatively cool climate, Katsuyama DF, in the middle Early Cretaceous, became to include “southern”-type dinosaurs, such as an allosauroid and a hadrosauroid under somewhat dry and temperate climate, and Tamba-Sasayama DF, in the late Early Cretaceous, includes a neoceratposian shared with Mazongshan DF and sauropod with “peg” like teeth shared with Khorat DF under seasonal dry and temperate climate. Although more sophisticated chronological, paleogeographical, and paleoenvironmental data are needed to understand their relationships, our result implies that there were possibly several routes for dinosaur divergences in the eastern margin of Asia continent, and some taxa might have been originated in the Early Cretaceous of Asia.
3 0 0 0 外傷性てんかんの治療と管理
3 0 0 0 IR ナフマニデスの聖書解釈研究 : 知の源泉とその彼方
- 著者
- 志田 雅宏
- 出版者
- University of Tokyo(東京大学)
- 巻号頁・発行日
- 2018
審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 市川 裕, 東京大学教授 鶴岡 賀雄, 早稲田大学教授 矢内 義顕, 京都大学准教授 勝又 直也, 明治学院大学准教授 高木 久夫
3 0 0 0 実録「仁義なき戦い」・戦場の主役たち・これは映画ではない!
- 著者
- 創雄社・実話時代編集部編集
- 出版者
- 洋泉社
- 巻号頁・発行日
- 1998
3 0 0 0 OA 中世における仏身論の展開
- 著者
- 蓑輪 顕量
- 出版者
- 一般財団法人 東京大学仏教青年会
- 雑誌
- 仏教文化研究論集 (ISSN:13428918)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.40-61, 2020-03-20 (Released:2021-10-13)
3 0 0 0 OA 効果量と検定力分析入門 : 統計的検定を正しく使うために
- 著者
- Mizumoto Atsushi Takeuchi Osamu
- 出版者
- 外国語教育メディア学会 関西支部メソドロジー研究部会
- 雑誌
- 2010年度部会報告論集「より良い外国語教育のための方法」
- 巻号頁・発行日
- pp.47-73, 2011-06-06
統計的検定は,標本から得たデータ分析結果を母集団にまで一般化させる目的で行われる。統計的検定では,サンプル・サイズ,有意水準,効果量,検定力の4つが検定結果の良し悪しを決定する重要な要素であるため,その基礎的概念の理解が検定を正しく使うためには重要である。そこで,本稿では,効果量と検定力分析の2つの概説を行い,統計的検定を用いている研究において,効果量報告と検定力分析の使用を推奨することを目的とする。
3 0 0 0 OA JAK キナーゼ
- 著者
- 朝比奈 昭彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.157-158, 2018 (Released:2018-03-16)
- 参考文献数
- 8
3 0 0 0 OA 科学論の歴史を振り返る : ルネサンス(14~16世紀)の事例から
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.298, pp.175-181, 2021 (Released:2022-08-01)
- 著者
- 綛谷 智雄
- 出版者
- 福岡医療福祉大学
- 雑誌
- 福岡医療福祉大学紀要 (ISSN:18834434)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.71-77, 2010
3 0 0 0 中央ユーラシア草原地帯における初期青銅器生産体制と流通
3 0 0 0 OA 空間ガンマ線量率への黄砂の影響
3 0 0 0 OA 朱鞠内湖における希少魚の持続的利用と地域振興 : ステークホルダー間の協働に着目して
- 著者
- 川野輪 真衣
- 巻号頁・発行日
- pp.1-63, 2020-03-25
北海道大学. 学士
3 0 0 0 OA 説明可能AI技術のこれまでとこれから
- 著者
- 亀谷 由隆
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.83-92, 2022-10-01 (Released:2022-10-01)
- 参考文献数
- 81
現在注目される人工知能技術は高い予測性能をもつ機械学習モデルが主体となっており,これらのモデルを健康や財産に関わる分野へ応用する試みも始まっている.しかし,その際の問題の一つがモデルの不透明性であり,このような不透明性を軽減するための一連の技術が近年「説明可能AI (explainable artificial intelligence, XAI)」という研究分野を形成している.本稿ではXAI研究の流れを振り返り,現在行われているXAI研究における概念と手法の分類や整理を行うとともに,XAI研究における将来の課題について述べる.
3 0 0 0 OA 日本人の古層のスピリチュアリティを求めて : 『竹取物語』を資料にして
- 著者
- 窪寺 俊之
- 出版者
- 関西学院大学
- 雑誌
- 神學研究 (ISSN:05598478)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.81-96, 2007-03
3 0 0 0 OA 室内ジョギングにおける遠隔音声による声援効果に関する研究
- 著者
- 島崎 貴志 金井 秀明
- 雑誌
- 研究報告グループウェアとネットワークサービス(GN) (ISSN:21888744)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015-GN-95, no.11, pp.1-8, 2015-05-07
世界各国,様々なスポーツがあり,競技大会が開かれるものが多い.競技大会では,選手たちが腕を競う一方,声援を送り,選手をサポートするファンも会場には存在する.声援は試合会場など近接にいるものからもらうが,その場にいないファン,つまり,遠隔地からの声援は効果がないのか疑問に思う.本研究では,その可能性を明らかにするために,室内ジョギングを対象とした遠隔音声および機械音声による声援の効果を明らかにする.検証は 「近接と遠隔」,「遠隔音声のみと録音」,「人と機械音声」 をそれぞれ比較することにより行った.
3 0 0 0 OA 地域主義・地域(主義)政党・地域ポピュリスト : 概念に対する一考察
- 著者
- 宮内 悠輔 ミヤウチ ユウスケ Yuusuke Miyauchi
- 雑誌
- 立教大学大学院法学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.39-79, 2017
3 0 0 0 OA 近代日本の哲学と仏教
- 著者
- 湯浅 泰雄
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.1969, no.19, pp.108-146, 1969-03-31 (Released:2010-01-20)
- 参考文献数
- 37
It seems that the modern philosophers in Japan, Nishida, Tanabe, Watsuji and Miki, are not so interested in Confusiasm in proportion to Buddhism. They have been bred in Confusiastic education in their boyhood, and in their youth they were strongly influenced by modern European philosophy which made them critical to the feudal Confu-siastic moral in their beyhood. I think, however, the framework of their philosophical thought are based upon the Confusiastic tradition unconsciously. Unfamiliarity with the Western thought, which grew by degrees, led them back to the Eastern tradition and Buddhism. Confusiastic education in their boyhood had survived here uncon-scionsly. For, the orthodox Confusiastic school in Tokugawa Era (Sogaku) had been established from the first under the strong influ-ence of the medieval Cninese Buddhism, Zen and Kegon sect, so buddhistic and confusiastic ways of thinking are inseparable in their philosophies.They seek the unified or undivided horizont of theoretical and practical philosophies. In the tradition of western philosophy, the unity between “theoria” and “praxis” may be a metaphysical ideal that can be never possible in our dayly experiences in this world. They insist, on the contrary, that this unity is the most immediate experience in human life. For instance, Nishida's “Pure Experience” means the fundamental unity of Good and Reality. This way of thinking, I think, has its origin in “Kakubutsu-Chichi” (Intuition through things) in modern Confusiasm (Sogaku).Then, they divided two kinds or directions in practice: introverted and extroverted. Extroverted practice means social and ethical activities, and the introverted practice means the religious and metaphysical “inner way”, through which man can ascend to the height of “hierophany”. This “inner way” to the great religious awakening, which has its origin in the fundamental spirit of Mahayana Buddhism, Sunya, bring the true human personality to its perfect realization and also make possible the unity of theoretical and extroverted practical human activities in this world.By the way, their ways of thinking have been influenced not only by Buddhism but also by the traditional culture in Japan. For, the Chinese culture does not like the mystical “inner way”, so the Zen and Kegon sects in medieval China attach more importance to the moral custom in the dayly-life in this world, compared with the same sects in Japan. In the tradition of Japanese culture, I think it is possible to find the powerful tendencies to seek the dialectical unity between the “inner way” and the daily ethics, for instance as in Kukai's Mystical-esoteric Buddhism.
3 0 0 0 OA 講演 芸術と技術
- 著者
- 山内 得立
- 出版者
- 日本美術教育学会
- 雑誌
- 美術教育 (ISSN:13434918)
- 巻号頁・発行日
- vol.1958, no.41, pp.4-11, 1958-03-15 (Released:2011-08-10)