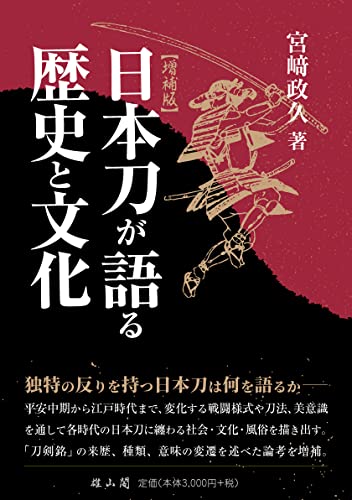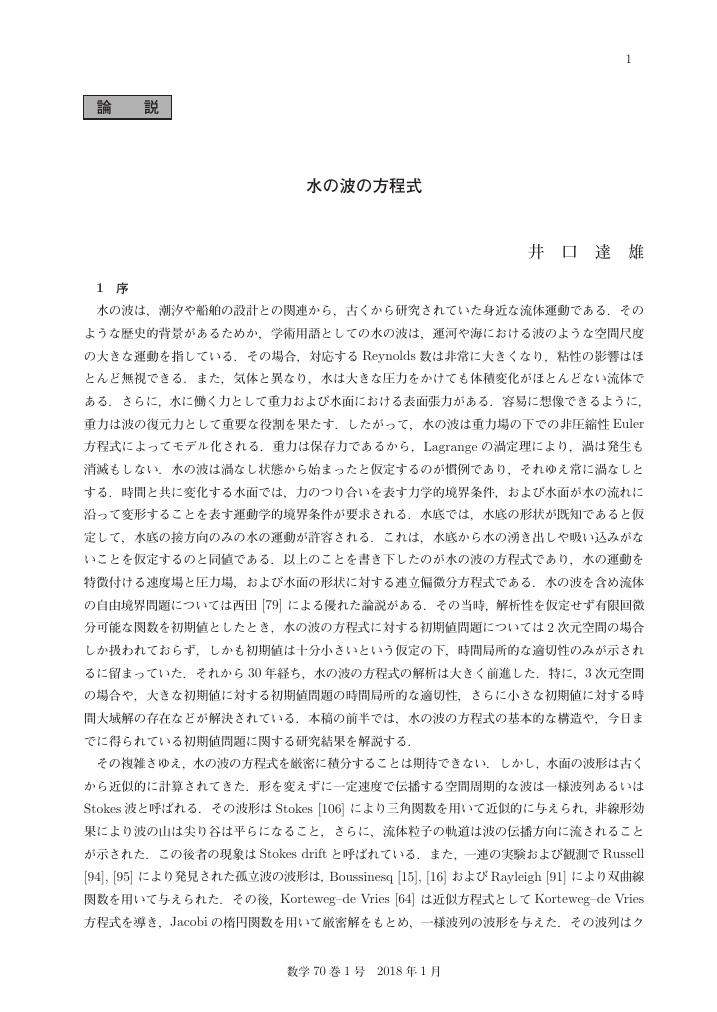2 0 0 0 OA 人の手で金型づくりの基本を身に付ける“人づくり”
- 著者
- 伊熊 英明 牟田 真也
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.6, pp.494-497, 2019-06-05 (Released:2019-06-05)
2 0 0 0 OA 法廷証第3394号: 宣誓供述書/ 大内義秀
- 巻号頁・発行日
- 1947
2 0 0 0 OA 清代内河水運史の研究
2 0 0 0 OA フォルティーニによるパゾリーニ批判
- 著者
- 米川 良夫
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.14-28, 1989-10-20
Il saggio che Franco Fortini pubblico sul <<Menabo>>n. 2, nel 1960, con il titolo "Le poesie italiane di questi anni", conteneva una critica lucida e penetrante e nello stesso tempo molto appassionata sulla poesia di Pier Paolo Pasolini. Nonostante il limite di natura cronologica e la impostazione ideologico-morale che ci sembra troppo rigoristica, il saggio rimane ancora molto stimolante. La nostra indagine sul testo fortiniano tende a stabilire alcuni punti di contatti, sia di consenso sia di dissenso, con altri contributi alla critica pasoliniana, come quelli di Barberi Squarotti o di Citati e quelli piu recenti di Santato o di Rinaldi.
2 0 0 0 OA 日本の労働時間はなぜ減らないのか? : 長時間労働の社会学的考察
- 著者
- 小野浩
- 出版者
- 労働政策研究・研修機構
- 雑誌
- 日本労働研究雑誌
- 巻号頁・発行日
- vol.2016年(12月), no.677, 2016-12
2 0 0 0 OA 宇宙機における船内ドローンへのワイヤレス給電
- 著者
- 嶋田 修平 川崎 治 本田 さゆり 鈴木 宏和
- 出版者
- The Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics
- 雑誌
- 日本AEM学会誌 (ISSN:09194452)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.39-44, 2022 (Released:2022-04-20)
- 参考文献数
- 7
Wireless Power Transfer (WPT) for spacecraft can be contributed various merits, such as workload reduction, safety improvement, high heat insulation, long lifetime. Our team developed WPT prototype for space drone. WPT used mag-netic field resonance, and class E inverter (switching frequency = 6.78MHz). We performed some critical tests (electrical and EMI). As a result of the electric test, the secondary circuit was the highest, which reached thermal equilibrium at about 50 ° C (< Tj). As a result of EMI test, WPT confirmed the range of MIL-STD-461C RE02(excluding switching frequency and its harmonics).
- 著者
- 下川 勇
- 出版者
- 福井工業大学
- 雑誌
- 福井工業大学研究紀要 Memoirs of Fukui University of Technology (ISSN:18844456)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.402-411, 2009
- 被引用文献数
- 2
This paper aims to make clear the concept "universal"of Architecture in the Italian renaissance, through the architect/theorist Vincenzo Scamozzi in the 16th century Italy. In the 16th century, Italy pushed forward the universalization of the concepts that integrate each art. Yet, Scamozzi constituted a logic that puts Architecture in a high position and puts Painting/Sculpture in its subordinate position. In this logic, the concept that has an important role is "scienza". Architecture becomes a more excellent art than Painting/Sculpture, on the condition that it secures the inevitable relationship with the scienza. Scamozzi's architectural book "Idea della architettura universale" is the concept that was composed by the scienza. This means that "invenzione", "disegno", which have a deep relation with scienza, compose the concept "architettura universale", as scienza dose.
2 0 0 0 OA 親企業がJクラブの戦略性に与える影響と対応 クラブの自律性と主体性の分析
- 著者
- 中村 英仁 藤山 敬史
- 出版者
- 日本スポーツマネジメント学会
- 雑誌
- スポーツマネジメント研究 (ISSN:18840094)
- 巻号頁・発行日
- pp.2022-004, (Released:2022-11-15)
- 参考文献数
- 41
The purpose of this study is to clarify (1) how the autonomy set by the parent company affects the strategic decision-making of J. League clubs and (2) how clubs negotiate with their parent company over autonomy, focusing on agency. Although literature in management studies has discussed the relationship between subsidiary autonomy and strategic behavior, there is no empirical research on J. League clubs. Therefore, this study analyzes a fourteenyear case of Yokohama F. Marinos to examine the above two research questions. First, this paper describes how the parent company of Yokohama F. Marinos had an impact on the club from 2009, reducing the club's autonomy and constraining its ability to be strategic. Next, we describe how Yokohama F. Marinos responded to the change by extending its autonomy through negotiation and improving its productivity. Finally, we discuss the contributions of this study.
2 0 0 0 日本刀が語る歴史と文化
2 0 0 0 OA 花袋行脚 : 史蹟名勝
2 0 0 0 OA ウエルシュ菌主要毒素の構造と機能及び活性発現機構に関する研究
- 著者
- 櫻井 純
- 出版者
- 日本細菌学会
- 雑誌
- 日本細菌学雑誌 (ISSN:00214930)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.367-379, 2006-11-25 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 79
- 被引用文献数
- 2
ウエルシュ菌が産生する多くの毒素の中で主要毒素と言われているα, β, εそして, L毒素は, いずれもユニークなタンパク毒素で, 本菌の感染症と密接に関係していると考えられている. そこで, ウエルシュ菌感染症の解明のため, 主要毒素の構造と機能を解析し, さらに, それぞれの毒素の作用機構について, 1) α毒素は, 毒素自身が有する酵素活性で組織を破壊するのでなく, 標的細胞の細胞内情報伝達系を活性化して恒常性の維持に混乱を与え, 細胞破壊, 致死活性を引き起こすこと, 2) β毒素は, 特異的に血球系細胞に結合し, ラフト上でオリゴマーを形成後, 細胞内情報伝達系に混乱を与え, 致死活性と細胞毒性を示すこと, 3) ε 毒素は, 脳細胞や腎細胞など標的細胞の膜上でオリゴマーを形成して膜障害作用を与えること, そして, 4) 酵素成分と膜結合成分からなる二成分毒素であるし毒素は, 膜結合成分が細胞膜に結合してオリゴマーを形成後, ラフトに集積し, これに酵素成分が結合してエンドサイトーシスで細胞内に侵入し, その後, 初期エンドソームから酵素成分が細胞質に遊離してアクチンをADPリボシル化して細胞毒性を示すことを証明した.
2 0 0 0 OA 福岡縣に現れた珍らしい鳥(其二)
- 著者
- 安部 幸六
- 出版者
- The Ornithological Society of Japan
- 雑誌
- 鳥 (ISSN:00409480)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.59, pp.274-278, 1949-12-20 (Released:2008-12-24)
Gives detailed account of rare birds captured or observed in Fukuoka Prefecture. Halcyon pileata, Locustella c. ochtensis, Haematopus ostralegus osculans, Synthliborhamphus wumisuzume, Anser fabalis serrirostris, Cygnus cygnus, Gallicrex cinerea, Porzana p. pusilla, Fulica a. atra, Platalea minor, Botaurus s. stellaris, Demigretta sacra ringeri, Podiceps c. cristatus, Nuci fraga caryocalactes japonicus, and an albino Corvus levaillantii japonensis are dealt with.
2 0 0 0 OA ジンメルの美学――独創的な折衷主義?(下)
- 著者
- マイアー インゴ 田村 豪 中村 徳仁
- 出版者
- 京都大学社会思想史研究会
- 雑誌
- 思想のプリズム (ISSN:24364495)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.53-79, 2022 (Released:2022-10-17)
- 著者
- 西田 紘子
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.1-17, 2019 (Released:2020-10-15)
1980年代以降、米国では、D. ルーウィンの『一般化された音程と変形』(1987)で提唱された変形理論から発展して、H. クランペンハウアーやB. ハイアー、R. コーンによる一連の論考を中心にネオ・リーマン理論が形作られてきた。この理論は、ポスト調性音楽や後期ロマン主義音楽を分析対象として展開されてきたが、2000年代に入ると音楽理論史的な問い直しも現れ始めた。すなわち、ネオ・リーマン理論の論者たちが、ドイツの音楽理論家フーゴー・リーマンによる諸概念をどのように領有したか、それが主要な論点の一つである。 その代表的論考(Engebretsen 2011)によれば、和声進行に関する「進行/転換 Schritt/Wechsel」というリーマンの概念と分類学(Riemann 1880)は、ネオ・リーマン理論において「同主調」「導音転換」「平行調」(すなわちPLR)の変形群へと置き換えられたものの、両者には和音近親や調性の捉え方等の違いがあるという。その点で、ネオ・リーマン理論はリーマン理論を再発見しただけでなくその趣旨を更新したと言われる。 こうした主張は一定の妥当性を有する一方、以下の3点から、通史的に再考されなくてはならない。(1)リーマンの概念とその元となったA. エッティンゲンの概念(1866)との関係や、リーマンの理論的思考の心理学的転回を含めたリーマンの和声理論の動態、(2)ネオ・リーマン理論の各論者によるPLR以外も含む変形諸概念との関係、(3)2000年代以降のネオ・リーマン理論第2世代(Kopp 2002, Rings 2011)におけるPLR変形の変容およびそれとリーマンの諸概念との関係、である。本稿ではこれらの点から、より広範で緻密な言説分析の基に先行研究による歴史化を更新し、リーマンに由来する諸概念の変容の過程を、領有と歴史化の相互作用および方法の洗練過程として示した。
2 0 0 0 OA 水の波の方程式
- 著者
- 井口 達雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.1-25, 2018-01-25 (Released:2020-01-26)
- 参考文献数
- 120
- 著者
- 王 筱 江崎 哲也
- 出版者
- 山梨大学教育国際化推進機構
- 雑誌
- 高等教育と国際化 : 山梨大学教育国際化推進機構紀要年報 (ISSN:21893993)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.37-43, 2018-11-20
本研究では、日本語を母語とする大学生が、教員を「先生」と呼ぶ要因を解明するため、一対一で話す場面を設定し、「調査協力者の属性(性別、年齢、専攻)」、「力関係(年上/ 同年齢)」、「相手の属性(調査協力者が所属する大学の教員であるかどうか、性別)」、「親疎関係(親しい:プライベートの付き合いがある友達・親しくない:友達ではない)」、「教授されたか否か、またその内容(学問的/ 実用的)」の五つの要因を質問事項に入れ、日本語を母語とする大学生及び大学院生を対象にアンケート調査を実施した。決定木分析を用いて分析を試みた結果、「先生」という呼称選択を決定づける主な要因は「力関係(年上・同齢者)」であることがわかった。また、「相手の属性(調査協力者が所属する大学の教員であること)」と「教えられた内容(学問的・実用的)」も要因となることが示唆された。一方、所属する大学の教員であることを知っていても、「先生」と呼ばない学生が少数いることもわかった。
2 0 0 0 OA シリコン量子ビット素子の研究動向
- 著者
- 森 貴洋 樽茶 清悟
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.12, pp.1052-1056, 2019-12-05 (Released:2019-12-05)
- 参考文献数
- 11
2 0 0 0 OA タイムトラベルはなぜ不可能か : 時間の矢と宇宙論的考察 (<特集>とき)
- 著者
- 松田 卓也
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.890, pp.13-16, 1993-01-05 (Released:2017-06-21)
- 参考文献数
- 3