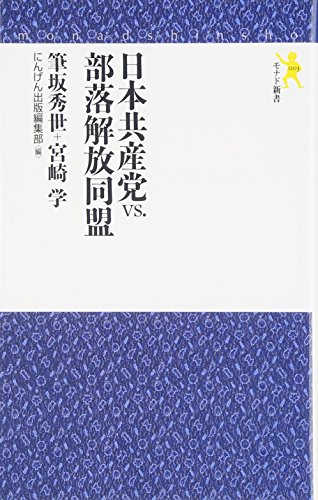2 0 0 0 IR 高齢者福祉と地域における公私の戦略的役割分担 - 変化する地方自治体の競争優位 -
- 著者
- 粟沢 尚志
- 雑誌
- 千葉経済論叢 = The Chiba-Keizai ronso (ISSN:0915972X)
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.1-21,
本稿は、経営戦略論におけるポジショニング・アプローチに依拠する筆者の近年の研究を総合して、行政と民間との戦略的役割分担を議論することを目的としている。まず、地方自治体の戦略的ポジショニングを納税者、民間事業者、家族、高齢者の各々が持つ影響力を考慮した上で分析する。次に納税者が与える影響力を、地方財政の代表的理論である足による投票の考え方をマーケティング論的に解釈する。さらに、民間事業者から受けるそれについては、従来の地方財政論の研究とは異なり地方自治体の持つ知に着目する。そして、自治体が持つ知ナレッジの陳腐化を考慮すると、民間事業者と比べた場合の競争劣位は長期化するものの、動態的な変化を経て新たな競争優位を持つ安定的な状態へと再び戻ってくることを理論的に示す。最後に、それを公的介護保険にあてはめ、制度導入前からの現状分析や今後の変化の予想へと応用している。
2 0 0 0 OA 人工肛門を自己抜去し人工肛門再造設術を施行した慢性統合失調症患者の1例
- 著者
- 水野 翔大 瀬尾 雄樹 西山 亮 亀山 哲章 秋山 芳伸
- 出版者
- 日本腹部救急医学会
- 雑誌
- 日本腹部救急医学会雑誌 (ISSN:13402242)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.069-072, 2019-01-31 (Released:2020-03-24)
- 参考文献数
- 4
症例は76歳,男性。46歳時に統合失調症を発症し,長期間精神科病院に入院中であった。下腹部痛を訴え,腹部CTでS状結腸を閉塞機転とする大腸閉塞,多発肝転移の所見を認めたため精査加療目的に当院転院搬送された。経肛門イレウス管の挿入を試みたが,ガイドワイヤーが穿孔したために緊急手術をすすめた。しかし本人が手術を拒否したため,保存的に経過観察した。その10日後に一転し手術希望があったため,横行結腸人工肛門造設術を施行した。術後2日目の夜間,人工肛門を自身で牽引し,横行結腸が腸間膜ごと脱出している状態になったため,緊急で人工肛門再造設術を施行した。精神疾患合併患者の術後管理において当院ではさまざまな工夫をしているが,人工肛門の自己抜去という想定外の事象を経験した。精神疾患合併患者の術後管理においては人工肛門も自己抜去の対象となりうることを念頭に置く必要があることが示唆された。
2 0 0 0 OA 立位・膝立ち位における前方リーチ動作の比較 ─筋電図を用いて─
- 著者
- 兵頭 甲子太郎 丸山 仁司
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.183-187, 2008 (Released:2008-06-11)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2
本研究の目的は,立位・膝立ち位にて2種類のリーチ動作を行わせ,肢位や施行方法の違いによる筋電図学的変化について検討していくことである。対象は整形外科的疾患の既住のない健常成人11名とし,立位・膝立ち位それぞれにて2つのパターンでの前方リーチ動作を行わせ,その時の大殿筋,大腿二頭筋,腹直筋,脊柱起立筋の筋活動とリーチ距離を測定した。実験の結果から,膝立ち位では立位と比べ大腿二頭筋の筋活動の割合の増加がみられた。また,リーチ動作を2つのパターンで行うことにより,筋活動に変化が表れたことから,臨床において特定の筋をより強調した形での動作が可能になるのではないかと考えている。
2 0 0 0 OA 児童期の不安障害に対する認知行動療法の展望(展望)
- 著者
- 石川 信一 坂野 雄二
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.125-136, 2004-09-30 (Released:2019-04-06)
- 被引用文献数
- 1
本論文の目的は、児童期の不安障害のレビューを行い、児童における不安障害に対する認知行動療法の効果について検討を行うことであった。第1に、児童期の不安障害は、全般性不安障害/過剰不安障害、社会恐怖、分離不安障害、パニック障害、特定の恐怖症、強迫性障害の6つに分類されることが示された。第2に、児童期の不安障害の有病率は10%弱であること、不安障害の各症状は併発率が高いことが示された。第3に、不安症状をもつ児童は学校や他の社会的状況において不適応を示すこと、不安障害を示す成人の多くは児童期から不安症状をもつことがわかった。不安障害の児童に対する認知行動療法の展望の結果、個別介入、集団介入、早期介入、両親を含めた介入の効果が無作為化比較試験によって証明された。最後に、本邦において、効果的な治療法を構築するために、不安障害の児童に対する治療法の研究が必要であることが指摘された。
- 著者
- 磯崎新 [ほか作] 大分市教育委員会美術館建設準備室編集
- 出版者
- 大分市教育委員会
- 巻号頁・発行日
- 1998
2 0 0 0 IR 違式詿違条例の研究 : 文明開化と庶民生活の相克
- 著者
- 春田 国男
- 出版者
- 別府大学短期大学部
- 雑誌
- 別府大学短期大学部紀要 (ISSN:02864991)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.33-48, 1994-01
2 0 0 0 OA 【特集】SDGs最前線 : 自然エネルギーが日本でのパリ協定とSDGs実現のカギとなる
- 著者
- 田中 信一郎
- 出版者
- 千葉商科大学経済研究所
- 雑誌
- CUC view & vision = CUC view & vision (ISSN:13420542)
- 巻号頁・発行日
- no.47, pp.21-26, 2019-03-31
2 0 0 0 OA ほうれんそうをゆでる
- 著者
- 河村 フジ子
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.190-192, 1986-12-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 添い寝が子どもの信頼感・自立心・依存心へ及ぼす影響
- 著者
- 吉田 美奈
- 出版者
- 上田女子短期大学
- 雑誌
- 紀要 (ISSN:21883114)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.17-29, 2018-01-31
2 0 0 0 IR 大仏師定覚
- 著者
- 三宅 久雄
- 出版者
- 奈良大学文学部文化財学科
- 雑誌
- 文化財学報 (ISSN:09191518)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.9-19, 2009-03
建仁三年(一二〇三)造立の東大寺南大門仁王像は、昭和六十三年から平成五年にかけて解体修理が行われ、その際、発見された銘記や納入経の奥書から注目すべきいくつかの事柄が判明した。そのうちのひとつに、大仏師として従来知られていた運慶、快慶のほかに、推測はされていたが、湛慶と定覚が起用されたことが確かめられたことがある。加えて大方の予想を裏切り、阿形像は運慶と快慶、畔形像は定覚と湛慶が分担したことも明らかになり、新たな問題をなげかけた。当時、運慶の長男湛慶は三十歳、この慶派の後継ぎと組んで畔形像の造像に当たったのが定覚である。周知のとおり、定覚という仏師は大仏殿両脇侍像、四天王像復興において康慶、運慶、快慶とともに活躍した慶派の四人の大仏師のうちの一人である。慶派の中では重要な位置を占めているように思えるが、彼の現存作例は南大門仁王像のみであり、しかもこの仁王像からは定覚個人の作風を知ることは、まずできない。出自もはっきりとせず、知名度の高いわりには謎に包まれた仏師である。ここで南大門仁王像の銘文を契機として、この定覚についてあらためて考えてみたい。
2 0 0 0 日本共産党vs.部落解放同盟
- 著者
- 筆坂秀世 宮崎学著 にんげん出版編集部編
- 出版者
- にんげん出版
- 巻号頁・発行日
- 2010
2 0 0 0 OA 神戸児童連続殺傷事件,加害者Aの更生過程の考察
- 著者
- 木村 隆夫 Takao Kimura
- 雑誌
- 日本福祉大学子ども発達学論集 = The Journal of child development
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.41-59, 2013-01-31
2 0 0 0 OA インド仏教の法滅思想(2)初期仏教資料をめぐって
- 著者
- 渡辺 章悟
- 出版者
- 東洋大学文学部
- 雑誌
- 東洋学論叢 = Bulletin of Orientology (ISSN:03859487)
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.100-85, 2001-03
2 0 0 0 OA 法医学における DNA 型鑑定の歴史
- 著者
- 押田 茂實 鉄 堅 岩上 悦子
- 出版者
- 日本大学医学会
- 雑誌
- 日大医学雑誌 (ISSN:00290424)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.5, pp.278-283, 2009-10-01 (Released:2010-04-20)
- 参考文献数
- 25
Since the method of minisatellites for the identification of humans with restriction-fragment-length polymorphism (RFLP) was reported by Jeffreys et al. in 1985, the revolution has taken place within the field of forensic genetics. In the crime case, the DNA markers have advantages over the traditional biological markers and the DNA technologies have been improved continuously. Today, the multiplex STR (short tandem repeat analysis) polymorphisms have become the major and widely used method for human identification test both in criminal investigation and mass disaster victim identification.
2 0 0 0 OA 昭和基地のインフラ整備について
- 著者
- 藤野 博行
- 巻号頁・発行日
- 2019-06-03
第16回南極設営シンポジウム 2019年6月3日(月)国立極地研究所極地観測棟3F 主催:国立極地研究所
2 0 0 0 OA The Great Gatsbyにおける目の意識
- 著者
- 石田 敏行
- 出版者
- 横浜国立大学
- 雑誌
- 横浜国立大学人文紀要. 第二類, 語学・文学 (ISSN:0513563X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.63-75, 1988-10-31
2 0 0 0 OA サツマイモ栽培への品質工学の適用
- 著者
- 金築 利旺 原田 真介 桑原 修 岩垂 邦秀 奥 展威 矢野 宏
- 出版者
- 一般社団法人 品質工学会
- 雑誌
- 品質工学 (ISSN:2189633X)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.21-28, 2013-02-01 (Released:2016-10-17)
- 参考文献数
- 7
A second experiment in the application of quality engineering to sweet-potato cultivation was carried out. The first experiment took two years: an L18 orthogonal array experiment was carried out in the first year and then a confirmatory experiment was carried out in the following year. In the second experiment, the confirmatory experiment was carried out under conditions prepared in advance so that the orthogonal array experiment and the confirmatory experiment could be carried out simultaneously, which enabled the whole experiment to be finished within one year. The sweet potatoes were evaluated by analysis of variance;calculations were performed to determine interaction effects among months of cultivation, the size of the harvested potatoes, and relevant control factors and noise factors. As a result, it was found that months of cultivation and potato size are closely related. Relationships between months of cultivation and potato size were derived for each control factor level, enabling cultivation conditions to be selected for harvesting sweet potatoes of any desired size.