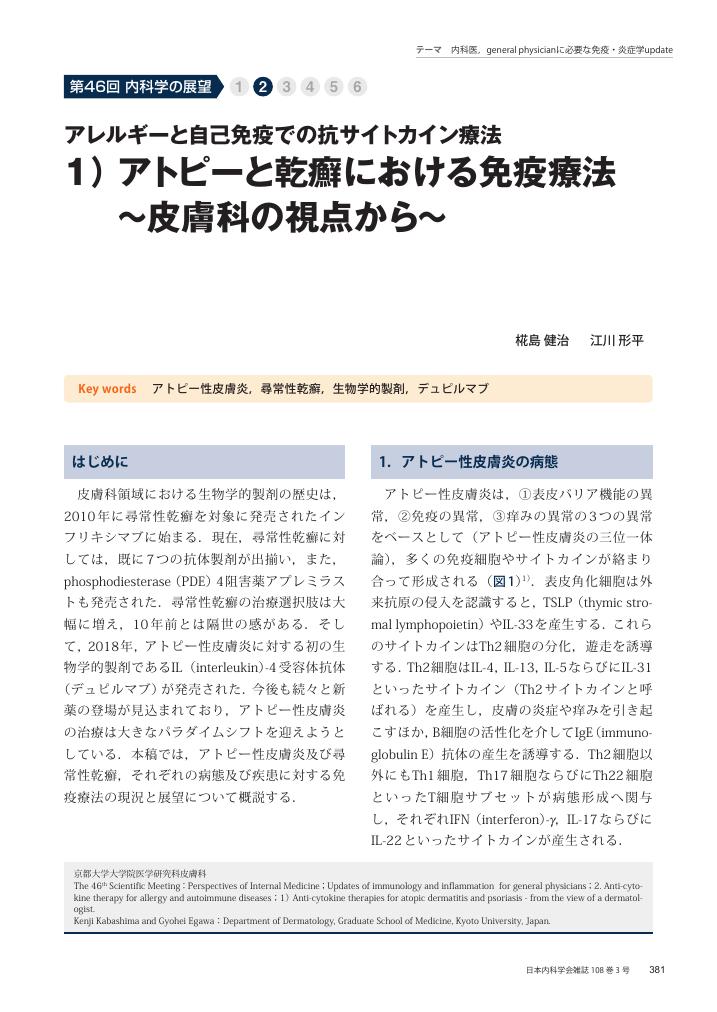2 0 0 0 OA 王粲の「七哀詩」と建安詩
- 著者
- 道家 春代
- 出版者
- 中国中世文学会
- 雑誌
- 中国中世文学研究 (ISSN:05780942)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.1-13, 1993-05-29
2 0 0 0 OA 世界の豆料理の調理特性
- 著者
- 吉田 真美 冨田 綾子
- 出版者
- 日本食生活学会
- 雑誌
- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.69-79, 2017 (Released:2017-10-31)
- 参考文献数
- 93
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this study was to investigate characteristics of bean cooking in the world. The countries investigated were mainly selected by high bean consumption by citizens (an average of over 3.5 kg/year), bean-consumption data having been published in the "World statistics 2017". Other countries were also selected by their research importance. Totally 21 countries or cultural regions were selected for research concerning bean cooking. 86 cook books from all these countries were collected and used as reference books in this study. The recipes involving beans as an ingredient were investigated in each book and 1192 total recipes were found. Detailed data in each recipe, such as species of beans used, the style (e.g. whole or cut) of beans during cooking, seasonings, spices and pot herbs used, were input into Excel. And a database and cross tabulation were made. The characteristics of bean dishes in 21 countries or cultural regions were revealed through the analyses. The kinds of beans used for bean dishes vary according to world regions. Soybeans are used only in East Asian countries, mainly in Japan, Korea and China. Chickpeas and lentils are mainly used in West Asia and surrounding areas. Black beans are used mainly in Mexico and Latin America. Beans prepared for consumption fall into four general styles: whole beans (predominant in most countries), chopped or sliced beans, bean pastes and purees (most common in three Asian countries) and sprouts. The study of seasoning methods for various bean dishes was also conducted. Spices such as pepper, chili, coriander and cumin, are mainly used globally for the seasoning of bean dishes. But in three Asian countries, seasonings such as soy sauce, miso, sake and mirin are more commonly used and the use of other spices is minimum. Beans are cooked by simmering in curries, stews and soups. In addition, beans are often ingredients in salads. A bean-paste dish called hummus, in which beans are mashed and seasoned, are often found in Middle Eastern countries.
2 0 0 0 OA 人工知能と機械学習,深層学習
- 著者
- 間下 以大
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.3, pp.235-240, 2018 (Released:2020-03-01)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA ブロックチェーン技術のアート産業への応用可能性
- 著者
- 施井 泰平
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.4, pp.367-376, 2019-12-27 (Released:2020-01-29)
- 参考文献数
- 12
The expectation for Blockchain technology has been continued, although its social implementation has not so widely progressing yet. Blockchain is thought as a general-purpose technology, it has been expanded with being subdivided. Art market is expecting especially for the robustness in falsify in characteristics of Blockchain technology. They hope its early implementation in the art market and activation of the market.
2 0 0 0 IR 語形成のそもそもを考える
- 著者
- 萩澤 大輝
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部言語学研究室
- 雑誌
- 東京大学言語学論集 = Tokyo University linguistic papers (TULIP) (ISSN:13458663)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.41-58, 2020-10-31
哲学における存在論研究では「語とは何か」という問いが議論されている。認知言語学的な観点からすると、その議論に見られる混乱はプロトタイプカテゴリー観を取ることで適切に整理することができる。そのうえで、哲学と言語学の知見を接続するには、語の典型をミームという存在者だと見なす説が有望である。ではミームはいかに発見されるだろうか。まず、人間は万物流転の世界を体制化している。語をはじめとする言語的ミームが立ち現れる過程は、その体制化の一環であるリンク発見ゲームとして定式化できる。そこでは同一性や実在論にまつわる素朴理論が採用されている。これを踏まえると、派生は客観的な変化ではなく「見え」としての変化である。This paper starts by showing that the confusion surrounding the philosophical discussion in recent years of the ontology of words can be sorted out by the prototype theory of categorization adopted in cognitive linguistics. It goes on to argue that the insights into words gained so far in philosophy and linguistics can be straightforwardly integrated into a theory that views a prototypical word as a meme. This leads to the question of how we identify memes as such. Living as we do in a world where everything is in flux, we have to create order in that world to make our experience coherent. Words as linguistic memes emerge as we participate in a game in which we form, drawing on naïve theories, links of similarity and association. Viewing words as memes allows us to think of morphological derivation as a process by which a link of partial identity is established between multiple word types, rather than as one producing an objective change.論文 Articles
2 0 0 0 OA UHF テレビジョン受信機
- 著者
- 阪本 陽一 西口 忠昭
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン (ISSN:18849644)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.10, pp.720-726, 1967 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 4
2 0 0 0 敗軍の将、兵を語る 都議選スペシャル 緑の暴風に、自民の自壊
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1900, pp.74-77, 2017-07-17
都議会議員候補の主張なり政策なりが十二分に都民に届く前に国政の問題が起きてしまいました。私自身のことは選挙妨害だと思っています。(編集部注:「私自身のこと」とは週刊文春が「下村博文元文科相『加計学園から闇献金200万円』」と題するスクープ記事…
2 0 0 0 IR 映画文化の現状と可能性
- 著者
- 石垣 尚志
- 雑誌
- 目白大学人文学研究 = Mejiro journal of humanities (ISSN:13495186)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.99-11, 2010
2 0 0 0 OA 抗体医薬とは
- 著者
- 熊谷 泉
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.7, pp.286-289, 2020-07-20 (Released:2021-07-01)
- 参考文献数
- 6
抗体研究は生命科学・バイオテクノロジーにおいて,極めて重要な概念・技術を生み出してきた。また,抗体研究を含む免疫学の発展においては,日本人研究者が多大な貢献をしている。19世紀後半の血清療法の時代から抗体は分子標的薬*1としての可能性が指摘されていた。20世紀の生物化学・分子生物学の知見の蓄積と遺伝子組換え技術の成熟により,キメラ抗体,ヒト化抗体やヒト抗体が作製され,抗体医薬を用いた分子標的治療が現実のものとなっている。この数年間の世界の医薬品売上第1位は抗体医薬である。
2 0 0 0 19世紀のイギリス心霊主義の社会精神史的意義に関する研究
本研究の目的は、19世紀における心霊主義の展開を骨相学、社会主義(社会改革)、神智学、心霊研究協会などを中心に検討していくことにより、超自然・非合理に軸足をおく現象と一般に考えられている心霊主義が、それとは逆に理性主義的な思考法に基づく「合理宗教」という側面が強く見られることを検証することにあった。平成15年度においては、ジョージ・クームの骨相学を中心に検討し、ヒプノティズムと融合して骨相ヒプノティズムとなって心霊主義の潮流に合流する経緯をたどった。平成15年7月31日から8月29日まで夏季休暇期間を利用してロンドンとチューリヒに滞在してブリティッシュ・ライブラリー、心霊研究協会などの諸機関で同主題に関する資料調査を実施した。平成16年度においては、ブラヴァツキー夫人やアニー・ベサントなどの神智学、フレデリック・マイヤーズ(心霊研究協会)の心理学を中心に検討し、心霊主義が霊的進化論や心理学へと展開していく経緯をたどった。平成17年1月4日から1月12日まで冬季休暇期間を利用してシドニー大学フィッシャー図書館及びニューサウスウェールズ州立図書館で同主題に関する資料調査を実施した。平成15年度から平成16年度の2年間にわたる研究期間において、研究課題「19世紀のイギリス心霊主義の社会精神史的意義に関する研究」をほぼ当初計画通りに実施し、その成果を研究報告書(全48頁)にまとめることができた。
2 0 0 0 OA 1)アトピーと乾癬における免疫療法~皮膚科の視点から~
- 著者
- 椛島 健治 江川 形平
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, no.3, pp.381-386, 2019-03-10 (Released:2020-03-10)
- 参考文献数
- 4
- 著者
- Sinan Albayrak Serkan Ordu Hatice Yuksel Hakan Ozhan Ömer Yazgan Mehmet Yazici
- 出版者
- International Heart Journal Association
- 雑誌
- International Heart Journal (ISSN:13492365)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.5, pp.545-553, 2009 (Released:2009-10-07)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 8 14
Slow coronary flow (SCF) is the phenomenon of slow progression of angiographic contrast in the coronary arteries in the absence of stenosis in the epicardial vessels in some patients presenting with chest pain. There are no definite treatment modalities for patients with SCF. Our aim was to investigate the efficacy of nebivolol in patients with slow coronary flow by monitoring its effects on endothelial function and different markers of inflammation. Forty-two patients (16 females, 26 males; mean age, 55 ± 10) with slow coronary flow (SCF) were included in the study. After baseline assessment, the patients were administered nebivolol 5 mg once daily. After 12 weeks of nebivolol therapy, the biochemical and ultrasonographic examinations were repeated. Chest pain relief was detected in 38 patients after treatment (90%). Systolic and diastolic blood pressure and high sensitive CRP were significantly decreased after nebivolol therapy. Among brachial artery dilation variables that reflect endothelial function, basal resistive index (RI), post-flow mediated dilation RI, and post-nitrate mediated dilation RI were significantly decreased after therapy. Nebivolol is effective at improving endothelial function in patients with SCF. It controls chest pain, decreases CRP, and has favorable effects on brachial artery dilation variables in patients with coronary slow flow.
- 著者
- ベスト アントニー
- 出版者
- 京都大学人文科学研究所
- 雑誌
- 人文學報 (ISSN:04490274)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, pp.63-87, 2001-06
2 0 0 0 OA 性転換手術後の超高位の直腸腟瘻に対する経仙骨的瘻孔閉鎖術の1例
- 著者
- 豊坂 昭弘 村田 尚之 三嶋 康裕 安藤 達也 大室 儁 関 保二 金廣 裕道
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器外科学会
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.4, pp.417-423, 2009-04-01 (Released:2011-12-23)
- 参考文献数
- 28
日本で受けた男性性転換手術後に晩期合併症として超高位の直腸膣瘻を経験し局所的に閉鎖しえたので報告する.患者は33歳で,7年前に男性から女性への性転換手術を受けた.3年前から人工膣から出血,排便をみている.注腸および内視鏡検査で,直腸S状部の超高位の直腸と人工膣が大きな瘻孔を形成していた.まず人工肛門を造設し,2か月後経仙骨的経路で手術を施行し癒着に難渋したが瘻孔を閉鎖した.術後は順調に経過し,2か月後人工肛門を閉鎖した.現在術後1年3月経過し再発はなく,美容的にも満足している.術後は再発の恐れから膣は使用されていない.本例は解剖学的に通常では発生しえない直腸S状部の超高位の直腸膣瘻であり,このような超高位の直腸S状部の直腸膣瘻の報告は内外とも見られず,局所的手術で修復した報告も見られないので報告した.本例での瘻孔の原因は人工膣内へ狭窄防止用ステントの使用による圧迫壊死であった.