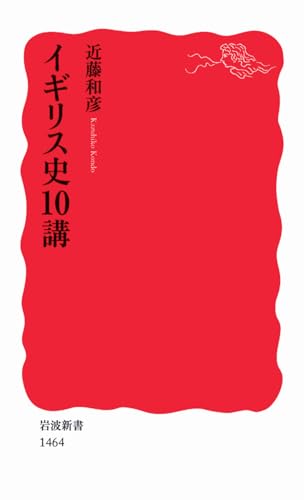2 0 0 0 OA 教育現場における先端技術や教育ビッグデータの利活用について
- 著者
- 桐生 崇
- 雑誌
- 情報教育シンポジウム論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, pp.1, 2019-08-10
Society 5.0時代を見据え、文部科学省では、昨年11月、「新時代の学びを支える先端技術のフル活用に向けて〜柴山・学びの革新プラン〜」(以下「柴山・学びの革新プラン」という。)を公表しました。この「柴山・学びの革新プラン」を踏まえ、本年6月、多様な子供たちを「誰一人取り残すことのない、公正に個別最適化された学び」を実現するため、ICTを基盤とした先端技術を効果的に活用するための具体的な方策について検討し、新時代に求められる教育の在り方や、教育現場でICT環境を基盤とした先端技術や教育ビッグデータを活用する意義や課題を整理し、今後の取組方策をまとめた「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策(最終まとめ)」を公表しました。今回は、この最終まとめに基づき、ICTを基盤とした先端技術と教育ビッグデータを効果的に活用していくための様々な取組を両輪として、新時代の学校、子供の学びを実現するための取組を説明します。
- 著者
- 菅瀬 晶子 Akiko Sugase
- 出版者
- 国立民族学博物館
- 雑誌
- 民博通信 = Minpaku Tsushin (ISSN:03862836)
- 巻号頁・発行日
- vol.138, pp.28-29, 2012-09-28
- 著者
- 中内 基博
- 出版者
- 早稲田大学
- 雑誌
- 産業経営 (ISSN:02864428)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.21-36, 2004-12-15
本稿は,ベンチャー企業が成長に伴って,起業家型マネジメントからプロフェッショナル・マネジメントへ移行する際のトップ・マネジメント組織のあり方を探求したものである。先行研究は,組織の成長とともに創業社長の能力不足が顕著となることから,それにあわせて創業社長はプロフェッショナル・マネジャーに交代すべきと主張してきた。しかし,そうした実証結果は一致した結論を得ていない。本稿では組織の成長に合わせた創業社長交代の議論を精緻化するにあたり,戦略的意思決定主体を社長という個人からTMTというチームへ拡張する。そうした場合,組織の成長に合わせてTMTの能力不足を補うことができさえすれば,創業社長の交代は必ずしも必要ではないと考えるのである。ここで,TMTの能力不足を補う鍵となるのは適度な新メンバーの加入比率と創業メンバー比率である。新メンバーは新しい知識や経験を有していることから,TMTのマネジメント能力を向上させる可能性がある。また,創業メンバーは,創業社長の理解者として創業社長をサポートすることが期待される一方で,変化への抵抗を示し,新しいスキルの習得を妨げる可能性がある。したがって,それらの適度なバランスがパフォーマンスを高めるためには重要であると考えられるのである。
2 0 0 0 IR 私立大学教員の懲戒処分手続に関する判例 : 教員の人事・身分保障と私立大学教授会の権限
- 著者
- 佐藤 俊二 サトウ シュンジ Shunji Sato
- 雑誌
- 経済と経営
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.1-22, 1981-09-25
- 著者
- 篠田 武司 櫻井 純理
- 出版者
- 立命館大学産業社会学会
- 雑誌
- 立命館産業社会論集 (ISSN:02882205)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.51-71, 2014-06
- 著者
- 岸田 鑑彦
- 出版者
- 中央労働災害防止協会
- 雑誌
- 安全と健康 (ISSN:18810462)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.254-256, 2015-03
- 著者
- 向井 蘭
- 出版者
- 中央労働災害防止協会
- 雑誌
- 安全と健康 (ISSN:18810462)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.11, pp.1086-1088, 2016-11
- 著者
- Kazuko Iwamoto Hirokazu Kawamoto Fumiaki Takeshita Shinichi Matsumura Ikuto Ayaki Tatsuya Moriyama Nobuhiro Zaima
- 出版者
- Japan Oil Chemists' Society
- 雑誌
- Journal of Oleo Science (ISSN:13458957)
- 巻号頁・発行日
- pp.ess19135, (Released:2019-08-14)
- 被引用文献数
- 10
Ginkgo biloba extract (GBE) is widely used as herbal medicine. Preventive effect of GBE against dementia, including Alzheimer’s disease, has been reported. The bioactive compounds in GBE that impart these beneficial effects, flavonoids and terpene lactones, have poor bioavailability. Our previous study found distribution of bioactive compounds of sesame extract in mice brain after mixing it with turmeric oil. Here, we evaluate the distribution of bioactive compounds of GBE by combining it with the mixture of sesame extract and turmeric oil (MST). The content of terpene lactones in mice serum was significantly increased in a dose-dependent manner after administration of GBE. However, the contents of terpene lactones in mice brain were not significantly changed. Concentration of ginkgolide A in mice brain increased significantly when GBE was co-administrated with MST than when GBE was administered alone. These results suggest that MST may be effective in enhancing the bioavailability of ginkgolide A in GBE.
2 0 0 0 OA 人工呼吸管理中に発症したハエ幼虫症の1例
- 著者
- 吉富 淳 佐藤 篤彦 須田 隆文 千田 金吾
- 出版者
- The Japanese Respiratory Society
- 雑誌
- 日本胸部疾患学会雑誌 (ISSN:03011542)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.12, pp.1352-1355, 1997-12-25 (Released:2010-02-23)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2
症例は86歳の女性で, 気管支拡張症感染増悪のため1996年6月10日に緊急入院し, 気管内挿管下に人工呼吸管理となった. 病室は3階の個室でほぼ毎日家族が付き添っていた. 口腔内洗浄も連日行われていたが, 6月19日に鼻腔, 口腔から体長約1cmのハエ幼虫 (ヒロズキンバエ) が20匹以上出現した. 虫体を除去するとともに, 内視鏡にて鼻咽腔から喉頭を観察したが, ハエ幼虫の温床となるような化膿性病変や壊死性病変は指摘できなかった. 経過から, 挿管後数日の間に親バエが鎮静剤の投与された患者の鼻腔または口腔に産卵したと考えられた. 清潔を旨とする病院においてもハエの侵入は認められ, ハエ幼虫症という事態が起こり得ることに留意する必要がある.
2 0 0 0 0 (ゼロ) の暁 : 原子爆彈の發明・製造・決戰の記録
- 著者
- W.L.ローレンス著 崎川範行訳
- 出版者
- 創元社
- 巻号頁・発行日
- 1951
2 0 0 0 OA 南京遺文
- 著者
- 佐佐木信綱, 橋本進吉 編
- 出版者
- 佐佐木信綱
- 巻号頁・発行日
- vol.〔本編〕, 1921
2 0 0 0 OA 全身性エリテマトーデスにおける炎症と動脈硬化
- 著者
- 舟久保 ゆう
- 出版者
- 日本臨床免疫学会
- 雑誌
- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.6, pp.470-480, 2012 (Released:2012-12-31)
- 参考文献数
- 67
- 被引用文献数
- 2 8
全身性エリテマトーデス(Systemic lupus erythematosus : SLE)は若年女性に好発する慢性炎症性の自己免疫疾患である.SLE患者は動脈硬化性心血管病による死亡率および罹病率が高く,画像診断では若年齢から潜在性動脈硬化が進んでいることも明らかになった.動脈硬化は血管内皮傷害を発端に炎症性細胞やメディエーターが関与した血管の慢性炎症と認識されており,SLEにおける動脈硬化発症・進展過程にも慢性炎症や免疫異常の関与が示唆されている.SLEの動脈硬化危険因子として脂質異常症,高血圧,耐糖能異常といった古典的心血管危険因子だけでなく,高CRP血症,高ホモシスチン血症,高疾患活動性,炎症性サイトカイン,血管内皮傷害,自己抗体や治療薬などが候補にあがっている.今後はSLE患者でも動脈硬化リスクを評価する必要があり,さらに動脈硬化の予防戦略と最適な治療法の確立が期待される.
- 著者
- Sung-Yong Choi Jung-Hyun Choi
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.837-843, 2016 (Released:2016-03-31)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 3 11
[Purpose] The purpose of this study was to examine the effects of cervical traction treatment, cranial rhythmic impulse treatment, a manual therapy, and McKenzie exercise, a dynamic strengthening exercise, on patients who have the neck muscle stiffness of the infrequent episodic tension-type (IETTH) headache and frequent episodic tension-type headache(FETTH), as well as to provide the basic materials for clinical interventions. [Subjects] Twenty-seven subjects (males: 15, females: 12) who were diagnosed with IETTH and FETTH after treatment by a neurologist were divided into three groups: (a cervical traction group (CTG, n=9), a cranial rhythmic contractiongroup (CRIG, n=9), and a McKenzie exercise group (MEG, n=9). An intervention was conducted for each group and the differences in their degrees of neck pain and changes in muscle tone were observed. [Results] In the within-group comparison of each group, headache significantly decreased in CTG. According to the results of the analysis of the muscle tone of the upper trapezius, there was a statistically significant difference in MEG on the right side and in CRIG on the left side. According to the results of the analysis of the muscle tone of the sternocleidomastoid muscle, there was a statistically significant difference in MEG on the right side and in CRIG on the left side. [Conclusion] In the comparison of the splenius capitis muscle between the groups, there was a statistically significant difference on the right side. Hence, compared to the other methods, cervical traction is concluded to be more effective at reducing headaches in IETTH and FETTH patients.
2 0 0 0 OA 日本産チーズバエ科(双翅目)の分類
- 著者
- 岩佐 光啓
- 出版者
- The Japan Society of Medical Entomology and Zoology
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.33-39, 1998-03-15 (Released:2016-08-18)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 3 5
日本産チーズバエ科(Family Piophilidae)のハエについては, 福原(1965)が2種, Piophila casei (Linnaeus)チーズバエおよびProtopiophila latipes (Meigen)チビチーズバエを記録して以来, 分類学的研究はなされていなかった。本報告では, いままで記録されていた2種に加えて次の日本新記録3種を見出した;Protopiophila contecta (Walker)ミナミチーズバエ(新称), Liopiophila varipes (Meigen)ケブカチーズバエ(新称), Stearibia nigriceps (Meigen)クロチーズバエ(新称)。これにより日本産の種は5種となり, これらの種の特徴を示した図とともに再記載を行い, 検索表を付した。本科の成虫は, 野外で腐肉によく集まり, 幼虫は, 人を含む動物の死骸, 骨(骨髄)を好む死肉・腐肉食性の種が多い。とくにPiophila casei (Linnaeus)チーズバエは, 人類親和性で, 肉製品, 魚, チーズ, 毛皮などに発生することが知られている。
2 0 0 0 OA 三叉神経痛の重だるさに抑肝散が有効であった1例
- 著者
- 瀧波 慶和 三田 建一郎 長井 篤 山川 淳一 小原 洋昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.4, pp.358-361, 2017 (Released:2018-02-07)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
77歳男性,主訴:左下顎部痛と重だるさ。左下顎部を中心に痛みがあり,近医で三叉神経痛第3枝領域と診断された。カルバマゼピンの処方により一時的に痛みは治まったが,再度同部位の焼けつくような痛みが出現し,当院ペインクリニック外来に紹介となった。1日に数十回の瞬間的な強い発作があり,うつ気分,食欲不振,意欲低下,口渇,下肢冷感,皮膚乾燥,舌診では紅色,やや腫大し,辺縁歯痕,舌尖紅,白苔。脈診で沈,腹診では腹力は虚(2/5)で心下痞,小腹不仁を認めた。下顎神経ブロックにより痛みは一時消失するが再燃を繰り返す状態で,この間も重だるさは継続していた。初診から35ヵ月後に,重だるさに対して抑肝散エキス7.5g/分3を処方したところ重だるさは消失した。1年6ヵ月経過した現在も下顎神経ブロックおよび鎮痛剤なしで経過している。
2 0 0 0 OA 清代中国と江戸日本の篆書比較論 : 市河米庵『米庵墨談』を中心に
- 著者
- 曹 悦
- 出版者
- 関西大学大学院東アジア文化研究科
- 雑誌
- 東アジア文化交渉研究 = Journal of East Asian cultural interaction studies (ISSN:18827748)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.467-482, 2018-03-31
The reign of the Edo period was established by Tokugawa Ieyasu. In this period, the policy of culture and education was put into force, and during the rise of innovation of calligraphy, two different styles which were Karayou and Wayou were appeared. The seal script calligraphy was a part of Karayou calligraphy, and it began to develop in the real sense from Edo period. The theory of Karayou calligraphy was influenced by the theory of China, and naturally the theory of the seal script calligraphy was influenced by the theory of the seal script calligraphy of China. In this paper, it would take an example of Ichigawa Beiann who was one of the member of Bakumatsu Sannpitsu, and choose his theory of calligraphy, Beiann Bokudann. Then analyzed the content of the seal script calligraphy and compared it with the theory of Chinese in the same period. Consequently we can see the relationship and degree of exchange study between Edo Japan and China in Qing dynasty.
2 0 0 0 OA 1.靴の商品学
- 著者
- 大塚 斌
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.7, pp.471-480, 1995-07-25 (Released:2010-09-30)
2 0 0 0 OA 山寺史料としての『沙石集』
- 著者
- 上川 通夫
- 出版者
- 愛知県立大学日本文化学部
- 雑誌
- 愛知県立大学日本文化学部論集 = Bulletin of School of Japanese Studies Aichi Prefectural University (ISSN:21899177)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.41-54, 2019-03-09
2 0 0 0 OA 南東方面海軍作戦. 其の一(自一九四二年五月至一九四三年二月)
- 著者
- 第二復員局残務処理部
- 出版者
- [第二復員局残務処理部]
- 巻号頁・発行日
- 1947-01