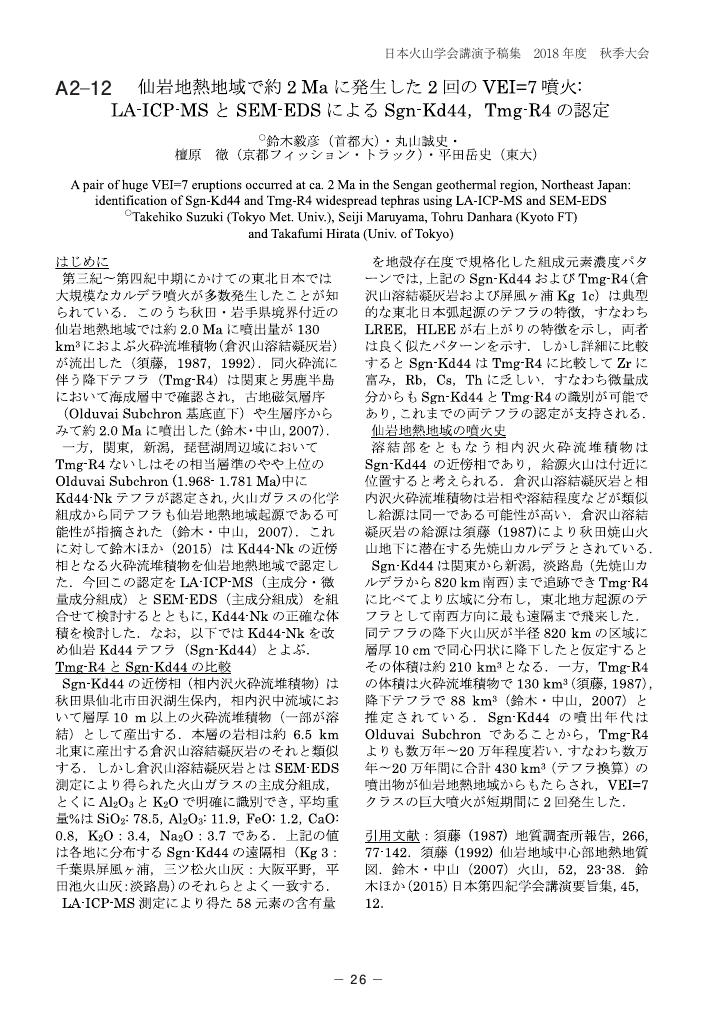17 0 0 0 OA 長野県中部に分布する守屋層火山岩類(中新統)のジルコンU-Pb年代とその層序学的意義
- 著者
- 星 博幸 岩野 英樹 檀原 徹
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.128, no.1, pp.143-152, 2022-07-06 (Released:2022-07-06)
- 参考文献数
- 46
守屋層は北部フォッサマグナ南縁部の中新世古環境や伊豆弧衝突に関連した地殻運動を記録していると推定されるが,その上部を構成する変質火山岩類の年代がよくわかっていなかった.今回,守屋層最上部の唐沢川酸性火山岩部層から15.5±0.2<sub>(2σ)</sub> MaのジルコンU-Pb年代を得た.この結果より,本部層の火山岩類の形成は15.5 Ma頃だったと考えられる.守屋山地域の火山活動はN8帯の下限年代である17.0 Ma以降に始まり15.5 Ma頃まで継続したと考えられ,15.5 Ma以降も火山活動が継続していた可能性はある.守屋層は下部の砕屑岩部分が北部フォッサマグナの内村層に対比されているが,上部の火山岩類も含む守屋層全体が内村層に対比可能と考えられる.この火山岩類の活動は設楽火山岩類の主要活動(約15-13 Ma)に先立って起こったが,設楽火山岩類の一部である津具火山岩類の活動とは同時期だった可能性がある.
- 著者
- 星 博幸 川上 裕 岩野 英樹 檀原 徹
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.128, no.1, pp.229-237, 2022-11-03 (Released:2022-11-03)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 3
紀伊半島の四万十付加体竜神コンプレックスの堆積年代はこれまで主に半島西部及び中央部で調査され,半島東部からは年代データの報告がなかった.筆者らは半島東部の竜神コンプレックス寒川ユニットに挟在する珪長質細粒凝灰岩からジルコンを分離し,68.1±0.4(2σ)MaのU-Pb年代と13.3±1.6(2σ)MaのFT年代を決定した.U-Pb年代はマーストリヒチアン期後期の堆積を示唆し,これは半島西部及び中央部で放射年代と放散虫化石から推定されている堆積年代と類似する.一方,FT年代は試料採取地周辺に分布する熊野酸性岩類や大峯酸性岩類などの中期中新世火成岩類の放射年代と類似するため,中期中新世火成岩類の熱影響によってリセットされた年代と考えられる.
- 著者
- 鈴木 毅彦 丸山 誠史 檀原 徹 平田 岳史
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 日本火山学会講演予稿集 2018 (ISSN:24335320)
- 巻号頁・発行日
- pp.26, 2018 (Released:2019-03-06)
3 0 0 0 OA 歴史時代に噴出した同一火山由来の軽石層の同定:
- 著者
- 生田 正文 丹羽 正和 檀原 徹 山下 透 丸山 誠史 鎌滝 孝信 小林 哲夫 黒澤 英樹 國分(齋藤) 陽子 平田 岳史
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.3, pp.89-107, 2016-03-15 (Released:2016-06-21)
- 参考文献数
- 67
- 被引用文献数
- 11
既往文献の火山ガラス屈折率データからは識別が困難であった桜島の歴史時代の噴火(文明,安永,大正)軽石について,本研究では火山ガラスの水和部と未水和部とを区別して屈折率測定を行い,斜方輝石の屈折率も含めてそれぞれの軽石に違いがあることを見出した.一方,宮崎平野南部で掘削したコアに含まれる軽石濃集層に対して鉱物組成分析,火山ガラスの形態分類や屈折率測定,斜方輝石の屈折率測定,および炭質物の放射性炭素年代測定を行い,本研究による歴史時代の桜島噴火起源の軽石の分析と比較した.また,それぞれの火山ガラスについてレーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析法による主成分・微量元素同時分析を行った.その結果,軽石濃集層は桜島文明テフラに対比されることが判明した.桜島文明テフラは,軽石の状態で宮崎平野南部まで到達していた可能性が高い.
3 0 0 0 OA 岡山市周辺の吉備高原に分布する古第三系「山砂利層」と海成中新統
- 著者
- 鈴木 茂之 松原 尚志 松浦 浩久 檀原 徹 岩野 英樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.115, no.Supplement, pp.S139-S151, 2009 (Released:2012-01-26)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1 4
吉備層群(いわゆる「山砂利層」)は,ほとんど中~大礫サイズの亜円礫からなる,谷埋め成の地層である.時代決定に有効な化石は得られず,更新統とされていたが,稀に挟まれる凝灰岩層を対象とするフィッション・トラック年代測定によって,地層の定義や対比が行えるようになってきた.いくつかの堆積期があることが分かってきたが,岩相では区別しがたく,地層区分は高密度の踏査による地層の追跡が必要である.各層の基底は,地層を構成する礫を運んだ当時の河の谷地形を示す.この復元された古地形は,底からの比高が150m以上に達する深い谷地形である.これは一般的な沈降を続ける堆積盆に形成された地形より,むしろ後背地側の地形である.すなわち吉備層群には,一般的な沈降する堆積盆の地層に対する区分や定義の方法とは異なる,新しい取り組みが必要であり,堆積の要因についても考えなくてはならない.これらは案内者一同を悩ませ続けている課題であり,見学旅行を通じて議論をいただきたい.
2 0 0 0 OA 東北日本男鹿半島,赤島層の放射年代
- 著者
- 鹿野 和彦 谷 健一郎 岩野 英樹 檀原 徹 石塚 治 大口 健志 Daniel J. Dunkley
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.6, pp.351-364, 2012-06-15 (Released:2012-11-07)
- 参考文献数
- 76
- 被引用文献数
- 7 8
赤島層デイサイト溶結火山礫凝灰岩についてジルコンのU-Pb年代とフィッション・トラック(FT)年代,斜長石のAr-Arプラトー年代を測定し,それぞれ72 Ma,65〜63 Ma,34 Maの値を得た.ジルコンは自形に近い外形とこれに調和的な累帯構造を保持し,かつ溶結した基質や軽石もしくは緻密なレンズの中に散在しており,本質結晶と考えられる.個々のジルコンのU-Pb年代値は集中して標準偏差も1〜2 Maと小さく,マグマの噴出年代を示している可能性が高い.FT年代値は,FTの短縮化が確認できるので,噴出後に熱的影響を受けて若返ったと考えることができる.斜長石のAr-Ar年代値は,段階加熱の広い範囲で安定しているものの,プラトー年代値は上位の門前層火山岩の同位体年代値の範囲内にあり,門前層の火山活動によってアルバイト化して若返った可能性が高い.得られたU-Pb年代は,東北日本においても後期白亜紀の後半に酸性火山活動が活発であったとする見解を支持する.
2 0 0 0 OA 宮崎平野に分布するテフラから推定される過去60万年間の霧島火山の爆発的噴火史
- 著者
- 長岡 信治 新井 房夫 檀原 徹
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.1, pp.121-152, 2010-02-15 (Released:2010-05-21)
- 参考文献数
- 75
- 被引用文献数
- 5 7
The study investigates the past 1 Ma tephrostratigrapy of the Miyazaki plain in southern Japan. There are over 50 tephra layers, 80% of which originate from Kirishima volcano 25 km west of the plain. Several widely spread marker tephra layers in the layers and fission-track dating are used to establish tephrochronology. The explosive eruptive history of the volcano was reconstructed on the basis of tephrostratigraphy and tephrochronology. The history has two volcano groups: Pre-Kirishima 900-600 ka and Kirishima 600-0 ka. Pre-Kirishima volcanoes are unknown in detail. Kirishima volcano is divided into the Older Kirishima volcano, 600-330 ka, and the Younger Kirishima volcano, 330-0 ka. The Older Kirishima is characterized by calder-forming eruptions and large-scale pyroclastic flows, > 100 km3 in volume. Older Kirishima consists of four stages: O1 (600-530 ka), O2 (530-520 ka), O3 (520-340 ka), and O4 (340-330 ka). The tephra of O1 includes over five crystal-enriched ash fall layers, which indicate that vulcanian and phreatomagmatic eruptions occurred intermittently at that stage. O2 is the first calder-forming stage, in which the Kobayashi-Kasamori pumice fall and pyroclastic flows and Kobayashi caldera were formed. The pumice falls and a co-ignimbrite ash fall of the pyroclastic flow were dispersed over 1000 km east of the source, and covered the western half of the main island of Japan. O3 tephra layers are composed of over ten tephra layers formed by intermittent plinian and phreatomagmatic eruptions. The latter indicates that lakes emerged in the caldera. O4 stage is a large-scale eruption with the Kakuto pyroclasatic flow and Kakuto caldera forming. The Kakuto pyroclastic flow was accompanied by a pumice fall and a scoria fall. They were small-scale scatterings near the source from small-scale eruptions, while the co-ignimbrite ash fall reached Kanto, which is 1000 km east of the source. The Younger Kirishima began with intermittent pumice and scoria falls soon after the O4 stage. The Younger Kirishima forms the main landform in the Kirishima volcano. Most of the Younger Kirishima tephra layers of more than twenty scoria and pumice falls were caused by plinian and sub-plinian eruptions accompanied by lava flows. The activity of the Younger Kirishima volcano is subdivided into four stages: Y1 (330-130 ka), Y2 (130-50 ka), Y3 (50-30 ka), and Y4 (30-0 ka) on the basis of thick soil and erosive horizon, which suggest quiet volcanic activity with no eruptions or only lava flow eruptions. Y1 includes over five tephra layers from sub-plinian eruptions in the western part of Kirishima volcano. There is a long quiet period between 240 ka and 130 ka. Y2 has six scoria falls, which show sub-plinian eruptions in the western part of the volcano. Y3 tephra is composed of Uchiyama pumice fall, Iwaokoshi pumice fall, and Awaokoshi scoria fall. Iwaokoshi from Onaminoike 40 ka old and Awaokoshi from Hinamori-dake 30 ka old, were much larger eruptions than other tephra of the Younger Kirishima volcano. Forming stratovolcano at the source, they reach the Pacific Ocean and Miyazaki plain 50 km east of the source, while most of the Younger Kirishima tephra are distributed near Kirishima volcano. Y4 has more than ten pumice, scoria, and ash falls, which include historically recorded tephra layers. Of them, the Kirishima-Kobayashi pumice fall from Karakuni-dake 16.7 ka spread over the widest area, covering half of the Miyazaki plain and reaching the Pacific Ocean.
1 0 0 0 OA 戸賀火山 : 東北日本, 男鹿半島西端のアルカリ流紋岩質ダブリング
- 著者
- 鹿野 和彦 大口 健志 林 信太郎 宇都 浩三 檀原 徹
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.5, pp.373-396, 2002-11-29 (Released:2017-03-20)
- 参考文献数
- 82
- 被引用文献数
- 5
An alkali-rhyolite tuff-ring is newly identified in the western end of the Oga Peninsula and named as Toga volcano in this paper. The existence of this maar-type volcano at the Toga Bay has been suspected for a long time because of the elliptical embayment reminiscent of a maar and the distribution of the Toga Pumice localized along the bay coast. The Toga Pumice is cornposed mainly of pumice and non- to poorly-vesicular glass shards, but many pumices of lapilli size are rounded and fines are poor giving a sandy epiclastic appearance to the deposit. In our latest survey along the bay coast, the Toga Pumice is found to be in direct contact with the basement rocks. The contact steeply inclines at 40-50° and envelopes an elliptical area 2.0 km×2.4 km covering the bay and bay coast to form a funnel-shape structure. The basement rocks at the contact are brecciated to a depth of several tens of centimeters, or collapsed into fragments to be contained in the Toga Pumice. The beds inside the inferred crater incline toward the center of the crater at 10-30° or much smaller angles, presumably reflecting a shallow concave structure infilling the more steeply sided crater. The deposit is thinly to thickly bedded to be parallel- to wavy- or cross-stratified, inversely to normally graded with many furrows, rip-up clasts and load casts, and is sorted as well as fines-depleted pyroclastic flow deposits and/or pyroclastic surge deposits. These features are characterisitic to turbidites and indicate the place of emplacement was filled with water. Constituent glass shards are, however, commonly platy or blocky and likely to be phreatomagmatic in origin, and pumice lapilli are interpreted to have been originally angular but rounded by repeated entrainment and abrasion in multiple phreatomagmatic eruptions and succeeding emplacement in the crater lake. A pyroclastic surge deposit (Oga Pumice Tuff) correlative in composition and age to the Toga Pumice occurs at Anden and Wakimoto, 11 km and 15 km east of Toga, respectively. The juvenile pumice lapilli are angular to subrounded, in contrast with the pumice lapilli of the Toga Pumice.
1 0 0 0 OA 北上山地中西部,盛岡市薮川地域の外山高原で見出されたチバニアン期後半のテフラ
- 著者
- 内野 隆之 工藤 崇 古澤 明 岩野 英樹 檀原 徹 小松原 琢
- 出版者
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター
- 雑誌
- 地質調査研究報告 (ISSN:13464272)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.67-85, 2022-08-29 (Released:2022-08-31)
- 参考文献数
- 35
盛岡市薮川地域,外山川沿いの谷底低地を埋める第四紀堆積物から80 cm厚の降下火砕堆積物を発見し,薮川テフラと命名した.本テフラは発泡した軽石を多く含み,中性~珪長質火山岩,トーナル岩,チャートなどの石質岩片を少量伴う.また,テフラ中には高温型石英・長石・普通角閃石・直方輝石・チタン鉄鉱・黒雲母が含まれる.テフラに含まれる火山ガラスの組成は比較的高いSiO2・K2Oと低いCaO・MgO・TiO2で特徴づけられ,またその屈折率は1.495 – 1.498である.軽石中のジルコンからは0.24 ± 0.04 Maのフィッション・トラック年代が得られ,本テフラはチバニアン期後半に堆積したと判断される.そして,記載岩石学的特徴,火山ガラスの屈折率,ジルコン年代などから,岩手山東麓に分布する大台白色火山灰に対比できる可能性がある.
1 0 0 0 OA 房総半島上総層群のフィッション・トラック年代
- 著者
- 渡辺 真人 檀原 徹
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.6, pp.545-556, 1996-06-15 (Released:2008-04-11)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 27 27
1 0 0 0 OA 中国山地西南部,山口県伊陸盆地周辺の水系変化と断層運動
- 著者
- 山内 一彦 白石 健一郎 檀原 徹
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.5, pp.643-670, 2014-10-25 (Released:2014-11-13)
- 参考文献数
- 50
This paper examines changes to the river system and faulting in the Ikachi Basin and surrounding area in the southwestern part of the Chugoku Mountains since the Middle Pleistocene, based of an investigation of the fluvial terrace and tectonic landforms. Fluvial terrace surfaces in the study area are classified into five levels: H, M1, M2, L1, and L2, in descending order. The M1 terrace surface is widely observed in the Ikachi Basin, and there is a narrow band of Sanbe-Kisuki tephra on the top layer of the terrace deposit, suggesting that the surface was formed around 110-115 ka. Aira-Tn tephra is observed in the L2 terrace deposit, indicating that it was formed around 30 ka. The distribution of terrace and deposit indicates the existence of the Paleo-Shiwari River, which differed from the river system existing today. The Paleo-Shiwari River flowed northwestward from the southeastern margin of the Ikachi Basin, and from near Hizumi, westward through the basin. There is a possibility that the upper reaches of the Paleo-Shiwari River reached Yashiro Island. The Paleo-Shiwari River lost its upper reaches as a result of river capture around the current Obatake-Seto in Middle Pleistocene. Furthermore, as a result of continued large-scale uplifting in the downstream area of the Paleo-Shiwari River basin, accompanied by activities of the Hizumi and Oguni faults since the Middle Pleistocene, the height of the riverbed of the Paleo-Shiwari River increased and its riverbed slope became gentle. At the same time, continued large-scale subsidence with faulting from the downstream basin of the Yuu River to Aki-Nada led to a gradual steepening of the riverbed of the Yuu River, and the valley head of the Yuu River along the fracture zone expanded due to erosion. Subsequently, the Paleo-Shiwari River was captured by the Yuu River at the Hizumi depression around 110-115 ka during the formation period of the M1 surface. It is concluded that river capture between the Yuu River and the Shiwari River occurred due to the influence of crustal movements.
- 著者
- 工藤 崇 檀原 徹 岩野 英樹 山下 透 柳沢 幸夫
- 出版者
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター
- 雑誌
- 地質調査研究報告 (ISSN:13464272)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.7, pp.273-280, 2011
新潟県加茂地域,三条市塩野淵において,中部中新統の七谷層から黒雲母に富むテフラを発見し,塩野淵バイオタイト(Sbi)テフラと命名した.本テフラは灰色を呈する層厚9 cmの結晶質中粒~極粗粒砂サイズの凝灰岩で,七谷層の玄武岩~安山岩火山砕屑岩と明灰色塊状泥岩の間に挟在する.本テフラの構成鉱物は,斜長石(オリゴクレース及びバイトゥナイト組成),石英,サニディン,黒雲母,不透明鉱物を主体とし,微量のジルコンと褐れん石を伴う.本テフラのジルコンFT年代は13.8±0.3 Maであり,微化石層序と調和する.本テフラは,同じく七谷層に挟在し,紀伊半島の室生火砕流堆積物に対比されるKbiテフラと同様な層準にあり,非常によく似た層相を示す.しかし,SbiテフラとKbiテフラは,斜長石組成の不一致,微量に含まれる重鉱物の組み合わせの不一致,ジルコンのウラン濃度の不一致から対比されない.したがって,今後,両者の対比にあたっては注意が必要である.
- 著者
- 工藤 崇 檀原 徹 岩野 英樹 山下 透 三輪 美智子 平松 力 柳沢 幸夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, no.5, pp.277-288, 2011
- 被引用文献数
- 1 2
新潟堆積盆加茂地域において,中部中新統の七谷層から黒雲母に富むテフラを発見し,駒出川バイオタイト(Kbi)テフラと命名した.本テフラは灰色を呈する層厚9 cmの結晶質中粒~粗粒砂サイズの凝灰岩で,七谷層上部の明灰色泥岩中に挟在する.本テフラの構成鉱物は石英,斜長石(オリゴクレース~ラブラドライト組成),サニディン,黒雲母を主体とし,微量のざくろ石,赤色および無色のジルコンを伴う.本テフラは浮遊性有孔虫化石帯区分のN.9帯,石灰質ナンノ化石帯区分のCN4帯に含まれ,堆積年代は14.2~14.7 Maと見積もられる.本テフラのジルコンFT年代は14.6±0.3 Maであり,微化石層序と良く調和する.記載岩石学的特徴,FT年代,微化石層序の一致から,Kbiテフラ,紀伊半島の室生火砕流堆積物,房総半島木の根層中のKn-1テフラの三者は対比可能であり,熊野酸性岩の形成に関連した広域テフラの可能性が高い.
- 著者
- 山下 透 檀原 徹 岩野 英樹 星 博幸 川上 裕 角井 朝昭 新正 裕尚 和田 穣隆
- 出版者
- 日本地質学会
- 雑誌
- 地質學雜誌 = THE JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.7, pp.340-352, 2007-07-15
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 10 8
紀伊半島北部に分布する室生火砕流堆積物とその周辺の凝灰岩(石仏凝灰岩,古寺凝灰岩,玉手山凝灰岩)および外帯中新世珪長質岩類について,屈折率を用いた軽鉱物組合せモード分析を行った.その結果,紀伊半島北部の中期中新世珪長質火砕流堆積物の斜長石系列は,すべてオリゴクレース~ラブラドライトで特徴付けられることから,これら4者は対比された.加えて室生火砕流堆積物は外帯に分布する熊野酸性岩類の流紋岩質凝灰岩の一部と対比できた.これらのことから,室生火砕流堆積物と石仏凝灰岩,古寺凝灰岩,玉手山凝灰岩は15 Maの熊野地域のカルデラを給源とする同一の大規模火砕流堆積物であると推定される.また熊野酸性岩類の中のアルバイトで特徴付けられる流紋岩質凝灰岩は,同じ軽鉱物組合せをもつ中奥弧状岩脈を給源とする可能性がある.<br>
1 0 0 0 OA 中期中新世テフラの広域対比:房総半島Kn-1凝灰岩と紀伊半島室生火砕流堆積物
- 著者
- 檀原 徹 星 博幸 岩野 英樹 山下 透 三田 勲
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.7, pp.384-389, 2007 (Released:2008-03-29)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 3 1
中期中新世前期(15 Ma)テフラの広域対比を提案する.記載岩石学的および放射年代学的分析から,房総半島のKn-1凝灰岩は約400 km離れた紀伊半島の火砕流堆積物と対比される.Kn-1は木の根層中に挟まる約16 m厚の珪長質凝灰岩で,紀伊半島北部の室生火砕流堆積物とそれに対比される火砕流堆積物(玉手山凝灰岩,石仏凝灰岩)と共通した造岩鉱物および火山ガラスをもつ.Kn-1のジルコンのフィッション・トラック年代は約15 Maで,紀伊半島の火砕流堆積物の年代と区別できない.玉手山-石仏-室生火砕流堆積物は熊野酸性岩類や大峯花崗岩類を含む紀伊半島外帯火成活動で起きたカルデラ噴火に由来することから,Kn-1凝灰岩も紀伊半島外帯(おそらく熊野)起源の広域テフラと考えられる.
1 0 0 0 OA 六甲山地西麓に分布する高塚山火山灰層のフィッション・トラック年代とその対比
- 著者
- 加藤 茂弘 佐藤 裕司 松原 尚志 兵頭 政幸 檀原 徹
- 出版者
- Japan Association for Quaternary Research
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.411-417, 1999-10-01 (Released:2009-08-21)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 6 5
六甲山地西麓に分布する明美累層高塚山部層に挾在する高塚山火山灰層から0.41±0.12Maのフィッション・トラック年代を得た.高塚山火山灰層の岩石記載的特徴は,大阪層群のMa9層最下部に挾まれる港島II火山灰層のそれにほぼ一致し,両火山灰層の対比を支持する.さらに高塚山火山灰層は,岩石記載的特徴と降下年代の類似性から,約0.39Maに噴出したと推定される琵琶湖高島沖ボーリングコアのBT76火山灰層に対比される可能性が高い.高塚山火山灰層の年代と対比結果から,高塚山部層に挾在する海成層は大阪層群のMa9層に対比でき,酸素同位体比ステージ11に相当する時代に堆積したと考えられる.
1 0 0 0 OA 洞爺カルデラ噴火をもたらしたマグマシステム
- 著者
- 東宮 昭彦 後藤 芳彦 檀原 徹 デ・シルヴァ シャナカ
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2019年大会
- 巻号頁・発行日
- 2019-03-14
[背景・手法] 大規模火砕流を伴うカルデラ形成噴火は,大災害を引き起こすため,的確な事前予測が求められる.それには噴火の準備過程やトリガーの理解が必要であり,適切な対象における詳細な岩石学的分析とマグマ過程推定はその有力手段である.洞爺カルデラ噴火は,新鮮な試料が得られるなど対象として適切であり,さらに火砕流影響範囲内に都市や重要インフラ等が存在することから,その理解は社会的意義も大きい.また,後カルデラ火山として中島と有珠を持ち,後者は日本有数の活火山でもある. 洞爺カルデラには多数の研究例があり(e.g., 鈴木・他, 1970; 池田・勝井, 1986; Machida et al., 1987; Feebrey, 1995; Lee, 1996; 町田・山縣, 1996),大規模火砕流と広域火山灰を150km3以上放出する破局的噴火を約11万年前に起こしたこと,マグマは高シリカ流紋岩マグマであること,などが判明している.しかし,噴出物のユニット区分や対比は研究者ごとに見解が分かれるほか,岩石学的解釈には不適切な点があった.そこで,新たな地質調査に基づき,ユニット区分や対比の見直し,ユニットごとの分布範囲と噴出量推定などを行なった.さらに,全岩化学組成(XRF),火山ガラスおよび鉱物化学組成(EPMA, LA-ICP-MS)の分析,および種々の解析を行ない,噴火推移やマグマ過程を見直した.[結果] 洞爺カルデラ噴出物は下位からunit 1〜6に分けられ,噴出量合計は広域火山灰や海没部分を除き36.8km3以上であった [詳細はGoto et al. (2018)を参照].unit 1は細粒の火山ガラス片からなる降下火山灰層,unit 2, 4, 5, 6は火砕サージ・火砕流堆積物,unit 3はベースサージと降下火砕物の互層である.このうちunit 4やunit 5下部, 6下部は岩塊に富む.本質軽石の大半は白色で,unit 6を除き全岩組成は均質である(SiO2≒77%・K2O≒2.8-3.2%; Feebrey(1995)のopx-HSRに相当).unit 6の本質軽石の一部は灰色や縞状で,全岩組成に2種のバリエーションがある.1つは中島の安山岩組成へと向かうもの(同hb-LSR),もう1つは有珠の流紋岩組成まで伸びるもの(同cum-HSR)である. ガラスおよび鉱物組成も,unit 6でバリエーションが大きい.たとえば斜長石は,An組成の違いからtype-A, -B,-Cに大別できる.このうちtype-A (An≒12)が圧倒的に多い.type-Bは基本的にAn≧90であるが,An≒80のサブグループ(type-B')もみられる.type-Cは,type-C1(An≒20),-C2(≒35),-C3(≒55)に細分され,C2, C3には部分溶融組織がある.直方輝石や磁鉄鉱もほぼ同様のバリエーションを持つ.石英はtype-A,単斜輝石はB',ホルンブレンドとイルメナイトはC2とC3のみにみられた.マグマA(type-A斑晶を持つマグマ;以下同様)は主マグマ溜まりの珪長質端成分マグマ,マグマBは高温苦鉄質マグマ,それ以外は両者の中間的マグマと考えられる.輝石温度計(Putirka, 2008),鉄チタン酸化物温度計(Andersen & Lindsley, 1985),などから見積もった各マグマ温度は,Aが≦800℃,C1, C2, C3, B'が800〜890℃,Bが≧900℃,となった.斑晶の微量元素濃度や累帯構造から,C2, C3, B'は近縁で噴火直前までA, C1と物質的やりとりがない,B'はBを元々の起源とする,C1のみ噴火前にAと相互作用した,といったことが推定できた. type-A斑晶には逆累帯が発達せず,元素拡散の速い磁鉄鉱でも拡散時間は数日以下と短い.一方,type-Bの斜長石や輝石の多くはMgなどが顕著に拡散し,高温マグマ注入から噴火まで数百年程度あった.[推定されるマグマ過程] 洞爺カルデラ噴火は,水蒸気プリニー式噴火(unit 1)で始まり,大量の火砕サージ(unit 2)の放出が続いたが,その後噴出レートが一旦低下して小規模マグマ水蒸気噴火(unit 3)に移行した.しかしほどなくカルデラ陥没が始まり(unit 4),大規模火砕流放出(unit 5, 6)に至った.unit 2放出によるマグマ溜まり圧力低下が,噴出レートの一旦低下とその後のカルデラ陥没を引き起こしたと考えられる. 噴火直前には,主マグマ溜まりにマグマA(高シリカ流紋岩)が大量に蓄積していたほか,C1, C2, C3, B', Bのマグマが存在した.マグマAはマッシュ状マグマ溜まりから珪長質メルトが分離・蓄積したものであろう(e.g., Wolff et al., 2015).高温マグマ(B)は数百年以上前に貫入し,上記マッシュとの相互作用によってマグマC2, C3, B'を生じさせた.マグマAには,噴火直前まで高温マグマの影響が全くなく,マグマ混合は噴火直前〜最中に受動的に生じたと考えられる.噴火のトリガーは高温マグマ注入ではなく,断層運動など外的トリガー(e.g., Gregg et al., 2015)の可能性が高い.噴火末期にみられるマグマ組成のバリエーションは,中島や有珠との関連を想起させ,更なる再検討が必要である.
- 著者
- 山下 透 檀原 徹 岩野 英樹 星 博幸 川上 裕 角井 朝昭 新正 裕尚 和田 穣隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.7, pp.340-352, 2007 (Released:2008-03-29)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 1 8
紀伊半島北部に分布する室生火砕流堆積物とその周辺の凝灰岩(石仏凝灰岩,古寺凝灰岩,玉手山凝灰岩)および外帯中新世珪長質岩類について,屈折率を用いた軽鉱物組合せモード分析を行った.その結果,紀伊半島北部の中期中新世珪長質火砕流堆積物の斜長石系列は,すべてオリゴクレース~ラブラドライトで特徴付けられることから,これら4者は対比された.加えて室生火砕流堆積物は外帯に分布する熊野酸性岩類の流紋岩質凝灰岩の一部と対比できた.これらのことから,室生火砕流堆積物と石仏凝灰岩,古寺凝灰岩,玉手山凝灰岩は15 Maの熊野地域のカルデラを給源とする同一の大規模火砕流堆積物であると推定される.また熊野酸性岩類の中のアルバイトで特徴付けられる流紋岩質凝灰岩は,同じ軽鉱物組合せをもつ中奥弧状岩脈を給源とする可能性がある.
- 著者
- 後藤 芳彦 松塚 悟 亀山 聖二 檀原 徹
- 出版者
- 特定非営利活動法人日本火山学会
- 雑誌
- 火山 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.17-33, 2015-03-31
我々は,北海道洞爺カルデラ中島火山の火山地質を明らかにするため,ヘリコプター搭載型の高分解能レーザースキャナを用いたレーザーマッピングと,地表地質調査を行った.レーザーマッピングは中島の全域を含む3×3kmで行い,計測データから3次元のデジタル地形図を作成した.地表地質調査は3次元デジタル地形図を用いて中島の全域で行い,詳細な産状記載と岩石記載を行った.デジタル地形図と地表地質調査から,中島の詳細な火山地質と形成史が明らかになった.中島は,デイサイトおよび安山岩質マグマが噴出して形成した8個の溶岩ドーム(東山ドーム,西山ドーム,北西ドーム,北山ドーム,南西ドーム,観音島ドーム,弁天島ドーム,饅頭島ドーム),デイサイトマグマが湖底堆積物を押し上げて形成した潜在ドーム(北東岬ドーム),およびデイサイト質のマグマ水蒸気噴火により形成したタフコーン(東山火砕丘)からなる.中島の北東部と南西部には,泥岩と砂岩からなる湖底堆積物が分布しており,中島の火山活動がカルデラ底の隆起を伴ったことを示す.中島は,洞爺カルデラ中央部のリサージェントドームの形成と,それに伴うデイサイト〜安山岩質マグマの噴出により形成されたと考えられる.高分解能レーザースキャナによる地形計測と3次元デジタル地形図を用いた地質調査は,火山地質の解明に極めて有効である.