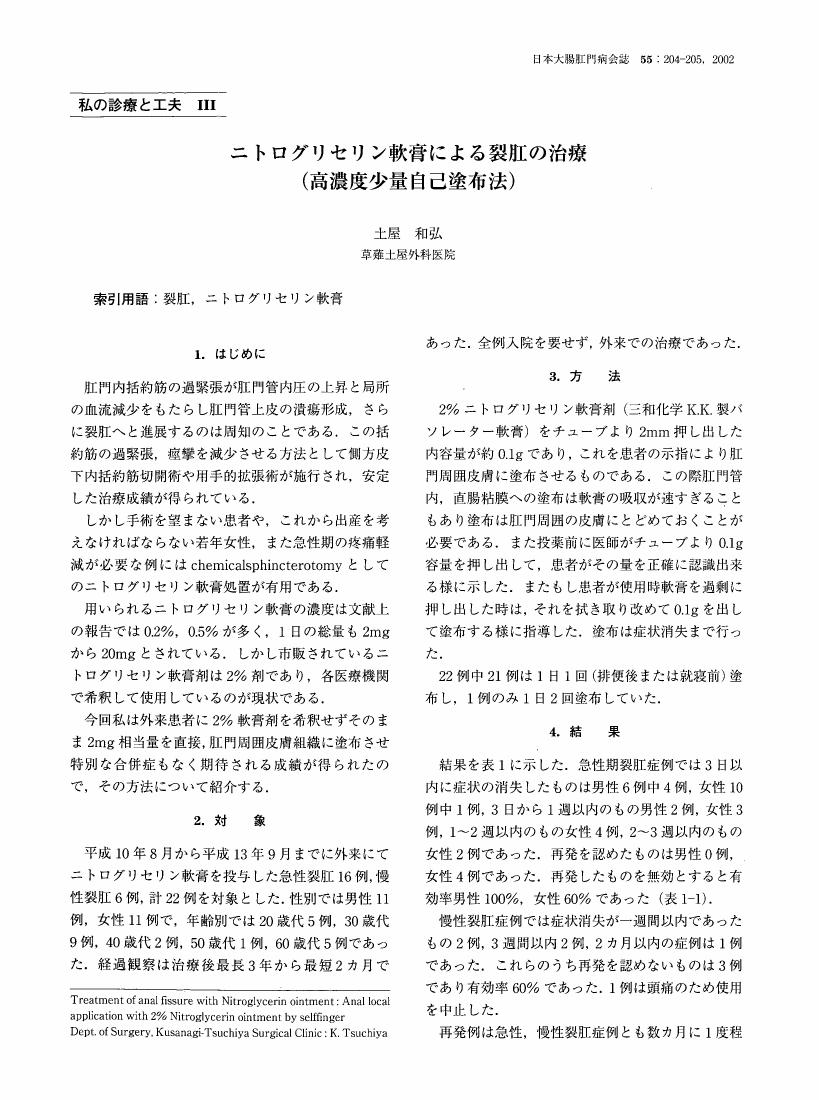1 0 0 0 OA 大腸癌手術の化学的腸管処置におけるカナマイシンおよびメトロニダゾール併用投与の有用性
- 著者
- 一万田 充洋 衛藤 剛 中嶋 健太郎 平塚 孝宏 赤木 智徳 柴田 智隆 上田 貴威 白下 英史 猪股 雅史
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.214-221, 2017 (Released:2017-03-30)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 3
目的:大腸癌手術の化学的腸管処置におけるカナマイシン(KM)+メトロニダゾール(MNZ)併用投与の有用性をSSIサーベイランスデータに基づき明らかにする.対象と方法:2010年1月から2015年12月までに行った大腸癌手術344例を術前の化学的腸管処置の方法により3群(抗生剤なし群178例,KM単独投与群87例,KM+MNZ併用投与群79例)に分けて創部SSI発生率を検討した.また,創部SSI発生と各リスク因子の関連について単変量および多変量解析を行った.結果:KM+MNZ併用投与群における創部SSI発生率は他の2群と比較して有意に低値であった(ともにP<0.05).創部SSI発生のリスク因子は男性(P=0.035),KM+MNZ併用投与群以外(P=0.011)であった.結語:大腸癌手術の化学的腸管処置における術前KM+MNZ併用投与は創部SSIの発生率低下に有用と考えられた.
- 著者
- K. Tsuchiya
- 出版者
- The Japan Society of Coloproctology
- 雑誌
- Nippon Daicho Komonbyo Gakkai Zasshi (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.204-205, 2002 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 日本大腸肛門病学会臨床研究の利益相反に関する指針の改定について
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.Annc01_17-Annc01_35, 2018 (Released:2017-12-26)
1 0 0 0 OA 潰瘍性大腸炎に対する回腸嚢肛門吻合術後の妊娠,分娩について
- 著者
- 坂下 吉弘 竹末 芳生 横山 隆 大毛 宏喜
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.173-177, 2000 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2 1
潰瘍性大腸炎に対し,大腸全摘,回腸嚢肛門吻合術を行った若年女性患者の妊娠出産を含めた術後のquality of lifeについて,女性患者23例のうち,20~39歳の12例に対してアンケート調査を行い検討した.術後の出産症例は5例で,計7児出産していた.回腸瘻閉鎖から初回出産までの平均期間は3年8カ月(1年7カ月~8年3カ月)であった.分娩方法は帝王切開が3例計5回,経膣分娩が2例計2回であった.帝王切開の理由は,児逆位,胎児仮死,早期剥離で,いずれも産科的な適応によるものであった.児性別は男児4例,女児3例で,7例とも妊娠週数は,正期産であった.生下時体重は2,638g~3,778gで,いずれも正常児で身体的異常を認めなかった.妊娠中に排便回数の増加を認めた症例はなかったが,2例で妊娠後期に漏便の増加を認めた.しかし,分娩後,妊娠前の状態に戻り,機能低下を残す症例はなく,回腸嚢肛門吻合術後の妊娠,出産は安全であると結論した.
1 0 0 0 OA 直腸癌における骨盤内臓器全摘術の適応と予後
- 著者
- 斎藤 典男 更科 広実 布村 正夫 幸田 圭史 滝口 伸浩 佐野 隆久 竹中 修 早田 浩明 寺戸 孝之 尾崎 和義 近藤 英介 知久 毅 若月 一雄 鈴木 弘文 安富 淳 小林 信義 菅谷 芳樹 吉村 光太郎 石川 文彦 中島 伸之
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.5, pp.381-388, 1995 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2 1
初発および再発直腸癌に対する骨盤内臓器全摘術(TPE)の適応と予後について検討した.対象は最近の13年間に施工した初発TPE22例と局所再発TPE14例の計36例である,36例中15例(初発6,再発9)に術前照射(30~40Gy)を行った.再発TPEでは初発例に比べ手術侵襲(手術時間,出血量)が大きく術後合併症の頻度も高く,術前照射群で同様の傾向を示した.5年生存率は初発TPE例で55.2%を示し,n0~n1群は良好であった.再発TPEの5年生存率は48.6%であるが,無再発5年生存率は31.1%と低値を示した.再発TPEでの長期生存例は,術前照射群に認められた.再発および再々発型式は,血行性転移が主であった.初発例のTPEは安全であり,遠隔転移の有無に関係なく局所制御の意味で従来の適応を拡大してよいと考えられた.再発例に対するTPEでは,厳重な症例選択により,生命予後の延長と良好なQOLの得られる症例も認められた.
1 0 0 0 OA ストレス状態における大腸粘液の動態に関する実験的研究
- 著者
- 岡村 慎也
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.222-229, 1996 (Released:2009-10-16)
- 参考文献数
- 30
防御因子としての大腸粘液の重要性を明らかにするために, 雑種成犬12頭に慢性拘束ストレス負荷実験を行い, 消化管粘膜における粘液糖蛋白質の指標となる粘膜ヘキソサミン濃度を測定し, 大腸粘膜の粘液糖蛋白質量の変化を検討した.さらにストレスを継続しながら, 粘液合成・分泌促進作用を有するテプレノンを経口投与し, 投与後の大腸粘膜の粘液糖蛋白質量の変化を検討した.その結果, ストレス負荷によりイヌの大腸粘液糖蛋白質量は低下し, 大腸に粘膜病変を形成する傾向を認めた.またテプレノンは大腸粘液糖蛋白質の分泌を促進させ, 粘膜病変の形成を抑制する傾向を認めた.以上より, 大腸粘液は大腸粘膜を保護する防御因子として非常に重要であり, ストレス負荷により減少し, テプレノン投与により増加することが示唆された。
1 0 0 0 OA I.大腸憩室疾患-日本における最近の傾向
- 著者
- 石川 信 加藤 順
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.10, pp.1010-1014, 2008 (Released:2008-11-05)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 8 7
大腸憩室は,欧米,本邦ともに年代とともに増加してきている.本邦での1980年の報告では大腸憩室の保有率は5.5%を占めるに過ぎなかったが,1990年代の発表では10.9%∼39.7%の頻度と報告されている.また,罹患率は加齢とともに増加し,40歳以下では16∼22%の頻度であるが,80歳以上では42∼60%に達する. 欧米において大腸憩室はS状結腸を中心に左側に群発するが,本邦では右側型が多くみられるのが特徴である.しかし,近年は右側型に左側型が合併した両側型が増加してきており,また,年齢とともに左側結腸の憩室が増加する傾向にある. 出血の頻度に関しては欧米の報告では大腸憩室の3∼47%に認めるとされるが,本邦では数%に過ぎず頻度は低い.しかしながら高齢者に多くみられるとの報告があり,今後高齢化が進む本邦においても憩室出血例が増加することが懸念される.
1 0 0 0 OA 大腸憩室疾患の疫学と臨床
- 著者
- 井上 幹夫
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.6, pp.904-913, 1992 (Released:2009-12-03)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 12 9
1 0 0 0 OA 臨床的逆追跡からみた大腸ポリープの自然史
- 著者
- 多田 正大 下野 道広 本井 重博 須藤 洋昌 郡 大裕 川井 啓市
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.73-77,154, 1981 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
大腸癌や腺腫の生体内における自然史に関して,明らかでない点が多い.殊に内視鏡検査の普及によって,大腸ポリープは発見され次第にポリペクトミーによって切除されるのが通例であるため,その長期経過観察例は稀である.著者らは大腸ポリープ7例について,経過観察することができたので,その自然史の一端について検討した.その結果,大腸癌のvolume doubling time(tD)は344.8日であった.腺腫では大きさにほとんど変化がないもの,急速に成長するもの,がみられた.成長する腺腫(腺管腺腫)のtDは213.4日であり,癌よりも短期間であった.腺腫の成長率の差は,その発生部位や個人の排便回数の差による細胞脱落因子によるものか,それとも宿主因子によるものか現時点では解明できないが,同様の数少い症例を集積して解明されるべき問題であると思われる.
1 0 0 0 Crohn病に対する症状別副腎皮質ステロイドの初回投与量について
- 著者
- 長浜 孝 櫻井 俊弘 古賀 有希 蒲池 紫乃 平井 郁夫 佐藤 茂 真武 弘明 松井 敏幸 八尾 恒良
- 出版者
- The Japan Society of Coloproctology
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.6, pp.273-278, 2003-06-01
- 参考文献数
- 17
Crohn病 (CD) に対するprednisolone (Predonine<SUP>®</SUP>; PSL) の適切な初回投与量を検討した.<BR>対象 : 外来通院中にPSLが投与されたCD患者45例, 84回のPSL治療.<BR>方法 : 症状別に初回1日投与量と経時的累積症状消失率を算出した.<BR>成績 : 下痢ではPSL初回投与量0.5mg/kg以上 (初回投与量 : 28.3±6.0mg/日) の群が有意に高率, 早期に症状が消失したが (p<0.006), 0.75mg/kg以上投与しても有意差はなかった (p=0.140). 腹痛では0.75mg/kgから1.03mg/kg(30.0±5.8mg/日)の群が有意に高率, 早期に症状が消失していた. 食欲不振・全身倦怠感, 発熱, 関節痛・結節性紅斑は0.24mg/kgから0.49mg/kg未満(30.0±5.8mg/日)の群とそれ以上の量の群とで累積症状消失率に差はなかった (p=0.818).<BR>上記成績に考察を加え, PSLの初回1日投与量は, 下痢に対しては30mg, 腹痛には35mg, 食欲不振・全身倦怠感, 発熱, 関節痛・結節性紅斑には15~20mgを目安とし, 体重, 活動指数によって増減するのが適切と考えた.
1 0 0 0 OA S状結腸癌および術後肝転移に日本住血吸虫卵が併存した1例
- 著者
- 柵山 尚紀 小林 昭広 小嶋 基寛 池田 公治 松永 理絵 河野 眞吾 伊藤 雅昭 齋藤 典男
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, pp.170-175, 2016 (Released:2016-02-22)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
S状結腸癌とその術後肝転移に日本住血吸虫卵が併存した症例を経験したので報告する.症例は72歳,男性.貧血,便潜血陽性を主訴にS状結腸癌と診断され,手術治療目的に当院紹介受診となった.S状結腸癌type2 cSS N1 H0 P0 M0 cStage IIIbの診断で,腹腔鏡下S状結腸切除術を施行した.術後病理診断は,S状結腸癌 pSE,pN1,pM0 pStage IIIa with Schistosoma japonicum eggであった.虫卵の分布は切除腸管全般にわたっており,癌との関連性は否定的であった.術後,9ヵ月後に肝転移を発症し腹腔鏡下肝部分切除術を施行.術後病理所見は転移性肝癌でも癌部非癌部にかかわらず虫卵の併存を認めた.患者は生活歴に山梨県甲府市に在住があった.本症例では虫卵が死卵であり活動性もないことから日虫症に対する治療は施行せず,術後化学療法も通常通り施行した.
1 0 0 0 OA 炎症性腸疾患の家族内発生
- 著者
- 樋渡 信夫 中嶋 和幸 山崎 日出雄 熊谷 裕司 山下 和良 森元 富造
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.7, pp.889-893, 1987 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 6 2
炎症性腸疾患の家族内発生の頻度と臨床像を明らかにする目的で,自験例について検討した.潰瘍性大腸炎296家系(1954年~87.6)のうち,潰瘍性大腸炎の多発は8家系(2.7%)に認めた.このうち6家系は兄弟例,2家系は母子例であった.発症年齢の近似は2家系,発症時期の近似は3家系,病型の類似は3家系に認められた。家族内発症例と"非家族例"との比較では臨床像に差はなかった.クローン病に関しては,85家系中3家系(3.5%)に家族内発生を認めた.1家系は母子例,2家系は兄弟例であり,3家系ともそれぞれ罹患範囲が同じであった.同一家系に3例以上の発症や,クローン病と潰瘍性大腸炎の混在を認めた家系はなかった.炎症性腸疾患の家族内発生が高頻度にみられたことは,偶然によるものではなく,遺伝的要因と環境要因が病因に強く関与していることが示唆された.
1 0 0 0 OA 「腹腔鏡下大腸切除術 導入へのヒントから今後の可能性まで」
- 著者
- 宮島 伸宣
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.9, pp.611-611, 2000 (Released:2009-06-05)
1 0 0 0 有窓式円筒肛門鏡の処置における有用性
- 著者
- 辻 順行 高野 正博 黒水 丈次 辻 大志 辻 時夫
- 出版者
- The Japan Society of Coloproctology
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.8, pp.740-741, 1999-08
1 0 0 0 当院におけるDay Surgeryの実際と問題点
- 著者
- 辻 順行 黒水 丈次 豊原 敏光
- 出版者
- The Japan Society of Coloproctology
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.10, pp.1030-1037, 1999-10-01
- 被引用文献数
- 2
平成9年4月から平成11年3月までに当クリニックで行われたday surgeryの218例を対象として分析を加え, 以下の結果を得た. (1) 同時期にクリニックで手術が決定された症例の内訳をみると, day surgeryが59%, 短期入院手術が5%, 普通の入院手術が36%で, day surgeryが過半数を占めた.また希望の入院日数に関するアンケートをみるとday surgeryが41.2%, 1週間までの入院が56.9%で計98.1%を占めた.以上より肛門疾患の入院日数は今後ますます短くなると思われた. (2) day surgeryの麻酔 (仙骨硬膜外麻酔または局所麻酔) については施行時の疼痛の強さ, 施行の際の難易性, 合併症の頻度, 診療時間等を十分に検討した上で決定すべきであると思われた. (3) 術後の早期出血については術後の安静時間を十分に確保すること, 創面に対し止血綿を使用するなど十分な止血操作を加えることで防止は可能と思われた.また痔核の晩期出血については最低3週間は溶解しない吸収糸の使用, 根部結紮にゴム輪結紮の併用や口側粘膜下に硬化剤の注射, 排便指導等を行うことで極力減らせると思われた. (4) 術後の疼痛については閉鎖術式の場合, 半閉鎖の高さを浅くする, 上皮のみを縫合するなど肛門の緊張を上げない工夫をし, 術前より緊張の高い症例では術中に緊張を下げる操作を加える, 嵌頓痔核の手術はしない.また結紮切除の数は肛門の緊張が弱い症例を除いては2ヵ所までとし, それ以上は二期的手術, 短期入院手術とすること等で軽減できると思われた.またアンケートをとると術後の鎮痛剤として, 坐薬は患者の挿入時の不安が強く, 経口薬が適当であると思われた. (5) 費用の点でday surgeryと2週間入院手術症例の比較を痔核症例で行うとday surgeryは入院手術の約1/4であった.
- 著者
- 鮫島 伸一 澤田 俊夫 長廻 紘
- 出版者
- The Japan Society of Coloproctology
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.8, pp.415-421, 2005
- 被引用文献数
- 20 35
第59回大腸癌研究会では,本邦における肛門部扁平上皮癌と痔瘻癌の,臨床病理,治療法,予後について,会員施設にアンケートを実施した.肛門部悪性腫瘍症例は総数で1,540例報告され,1,029例(66.8%)は腺癌,粘液癌で,扁平上皮癌は226例(14.7%)であった.肛門部扁平上皮癌患者の平均年齢は63.4歳で,男女比は1:2.25であった.組織型では中分化型扁平上皮癌が50.4%と最も多くみられ,低分化癌も24.4%にみられた.47.6%にリンパ節転移を認め,そけいリンパ節の転移率は25%であった.腫瘍マーカーは,stage II~IVの52%の症例でSCCの上昇を認めた.治療法では68.4%でAPRを含む治療が行われたが,放射線療法,化学療法が増加している.全肛門部扁平上皮癌の5年生存率は51.4%で,治療法による予後の有意差は認められなかった.<BR>痔瘻癌痔瘻罹患年数は18.8年で,粘液癌が60.8%でリンパ節転移は28.9%にみられた.治療は95.0%にAPRないしTPEが行われた.5年生存率は,stage 0,Iで90.1%,stage IIで66.7%,stager IIIで29.0%であった.
1 0 0 0 OA クローン病による消化管膀胱瘻の2例
- 著者
- 張 仁俊 澁澤 三喜 角田 明良 神山 剛一 高田 学 横山 登 吉沢 太人 保田 尚邦 中尾 健太郎 草野 満夫 田中 弦
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.4, pp.254-259, 1997 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 1
クローン病による消化管膀胱瘻は比較的まれで本邦では62例の報告がある.今回,著者らは教室においてクローン病による消化管膀胱瘻を2例経験したので報告する.症例1は32歳,男性.腹痛,発熱,混濁尿のため慢性膀胱炎として治療を受けていたが,糞尿が出現したため入院となった.小腸造影,注腸造影にて直腸S状結腸瘻,回腸直腸瘻がみられた.膀胱造影にて造影剤の漏出を認め,腸管膀胱瘻が強く疑われた.症例2はクローン病のためsalazosulfa-pyridineの内服治療を受けている28歳の男性.血尿,気尿,発熱を主訴に入院.膀胱造影にて直腸が造影され,クローン病による直腸膀胱瘻と診断した.いずれの症例も中心静脈栄養や成分栄養剤,prednisolonの投与等の内科的治療が奏効せず腸管切除と瘻孔部を含めた膀胱部分切除術を施行した.
1 0 0 0 OA 潰瘍性大腸炎とCrohn病の父子発生例
- 著者
- 中嶋 均 村元 和則 奈良 秀八州 芳賀 陽一
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.8, pp.573-580, 1998 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 1
Crohn病と潰瘍性大腸炎の家族内発生は特発性炎症性腸疾患の成因,とくに遺伝的成因を究明する上で注目されている.筆者らは潰瘍性大腸炎とCrohn病の父子発生の1家系を経験した.症例1は25歳の男性,増悪する腹痛に対して開腹手術を施行し,その手術所見および手術標本の組織所見よりCrohn病と診断された.症例2は症例1の父で息子(長男)のCrohn病発症4年経過後に,粘血便を主訴として受診し,大腸内視鏡および生検組織所見にて潰瘍性大腸炎と診断した.本邦においては,Crohn病と潰瘍性大腸炎の異種の炎症性腸疾患の家族内発生例はこれまで6例と稀である.この家系におけるHLA検索ではこれまで同種の家族内発生例で示唆されているような一定の表現型を指摘し得なかった.
1 0 0 0 レーザーメス使用による根部結紮のない痔核手術方法
- 著者
- 宇都宮 高賢 菊田 信一
- 出版者
- The Japan Society of Coloproctology
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.253-254, 1999-03
- 被引用文献数
- 6 2
1 0 0 0 OA 潰瘍性大腸炎ならびにその類縁疾患の免疫学的研究
- 著者
- 小林 絢三 北野 厚生 山口 勝治 水野 滋 溝口 靖紘
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.195-202,257, 1976 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 38
X線,内視鏡ならびに生検により診断し得た潰瘍性大腸炎15例,大腸結核3例,ンクロー病4例.ベーチエット病1例,計23例を対象として,主として細胞性免疫の立場から検討を加えた。潰瘍性大腸炎においてはT-cell populationはもとよりその機能も対照群より低下し,T-cell系の障害を支持する成績を得た。病期による差ではT-cell機能は活動期では非常にぱらつきがあり,免疫学的に不安定であることを示すが寛解期に入ると,その分布の巾が狭くなり病態として落着いた状態となると考えられる。これに対し,大腸粘膜なちびに菌抗原に対しては陽性を示すものが多いことが特徴づけられる。クローン病においては病巣は小腸にみられたが,全例T-cell系の障害を示し,その程度は潰瘍性大腸炎におけるそれよりも強かった。また,大腸結核症全例にPHA responseが高い結果が得られた。