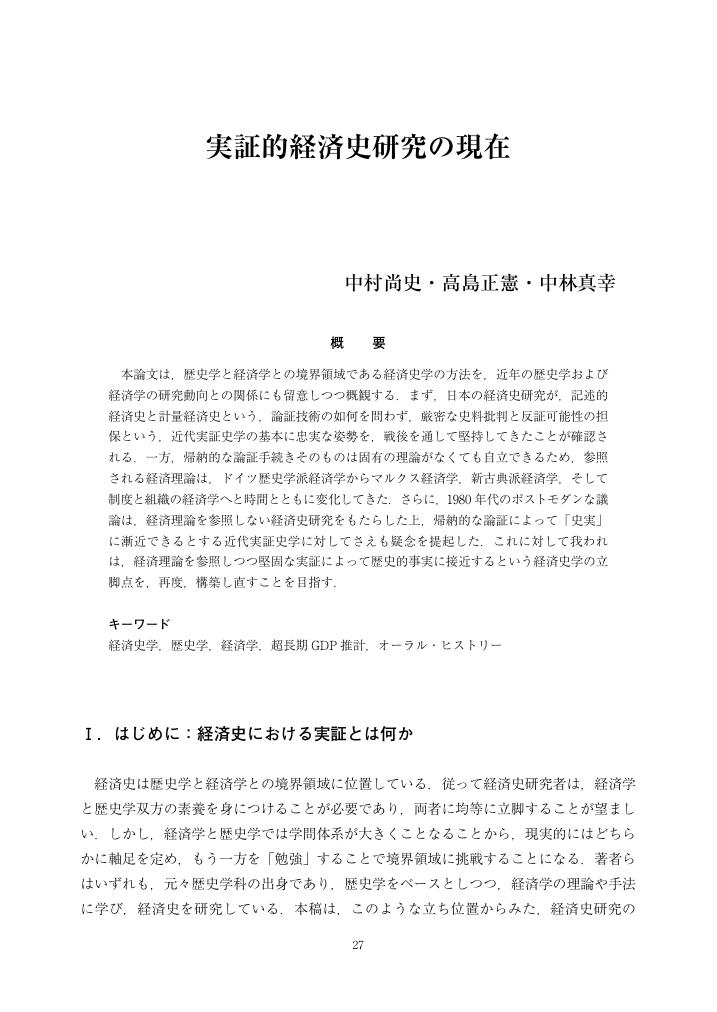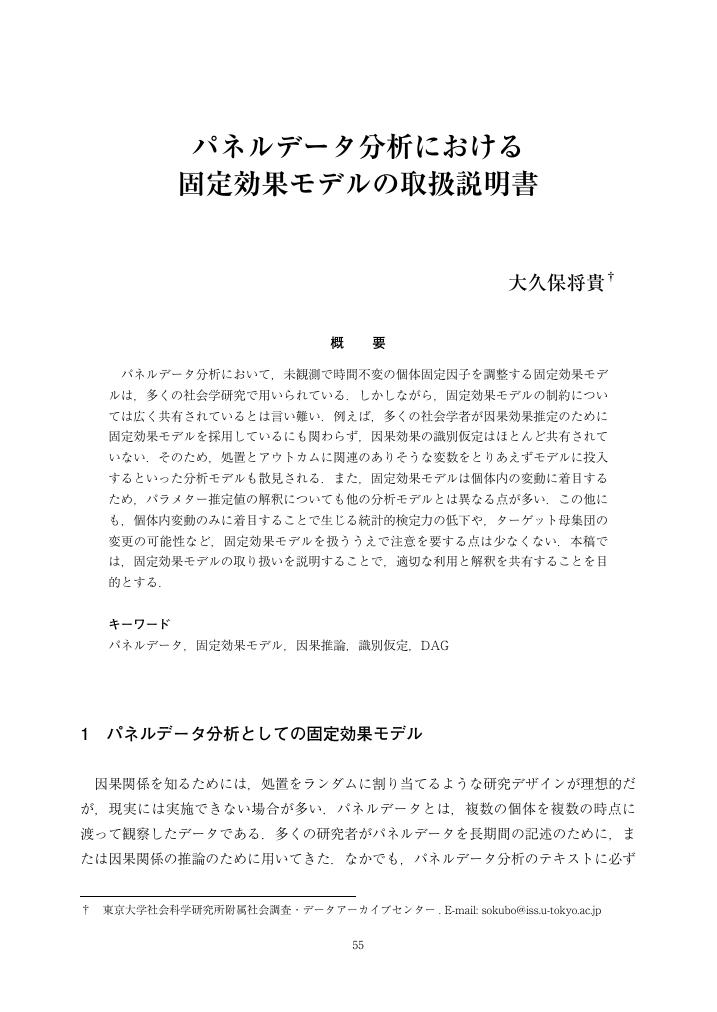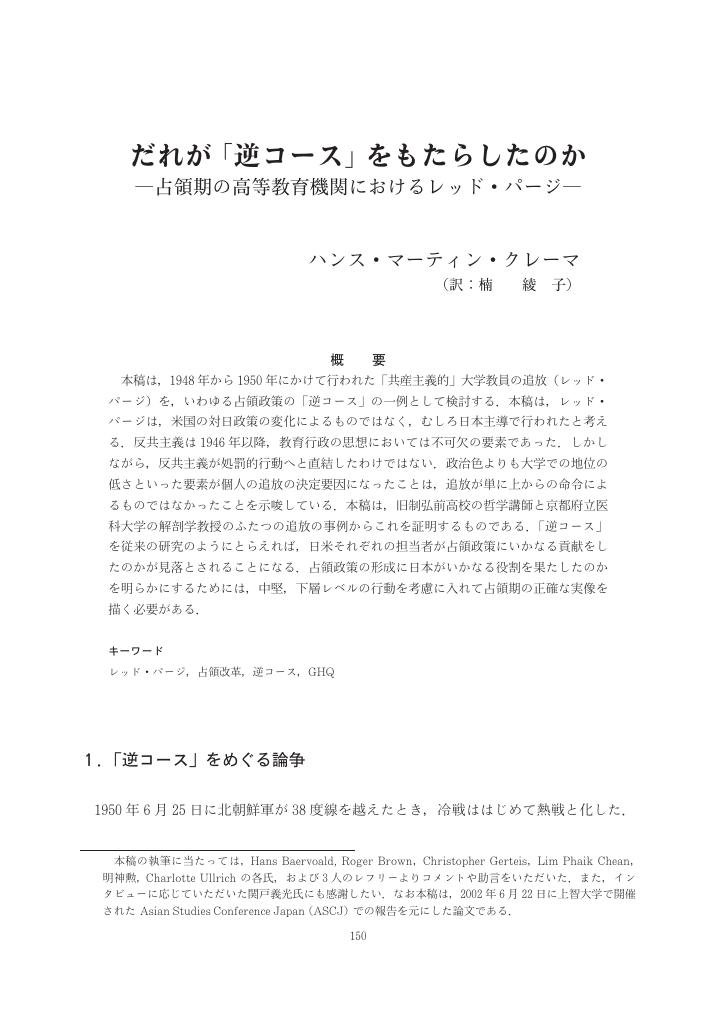25 0 0 0 OA 実証的経済史研究の現在
- 著者
- 中村 尚史 高島 正憲 中林 真幸
- 出版者
- 国立大学法人 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.27-53, 2021-03-31 (Released:2021-05-13)
21 0 0 0 OA 静かなる流出:ポスト3.11における日本人高度人材の豪州への移住
- 著者
- 大石 奈々 濱田 伊織
- 出版者
- 国立大学法人 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.93-116, 2021-03-31 (Released:2021-05-13)
20 0 0 0 OA パネルデータ分析における固定効果モデルの取扱説明書
- 著者
- 大久保 将貴
- 出版者
- 国立大学法人 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.55-68, 2021-03-31 (Released:2021-05-13)
20 0 0 0 OA だれが「逆コース」をもたらしたのか ―占領期の高等教育機関におけるレッド・パージ―
- 著者
- ハンス・マーティン・クレーマ
- 出版者
- 国立大学法人 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.150-170, 2007-12-17 (Released:2021-02-09)
18 0 0 0 IR 家族の近現代--生と性のポリティクスとジェンダー (特集 歴史社会学)
- 著者
- 牟田 和恵
- 出版者
- 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.97-116, 2006
日本における家族の歴史社会学研究の蓄積について,とくに隣接領域である家族社会学との関連においてレビューする.その際,80年代以降に若手フェミニスト研究者たちを中心的担い手として展開した「近代家族」論に注目し,それが,家族をめぐる学問領域においてもっていた意味と意義を確認する.その上で,ポストモダン・フェミニズムを経た新たなジェンダー概念の導入により,「ジェンダー家族」という概念を提起し,日本近代の天皇制と家族に関する分析を行なう.結論として,家族の歴史社会学的研究を現代に生かしていく方途を提言する.
17 0 0 0 IR だれが「逆コース」をもたらしたのか ―占領期の高等教育機関におけるレッド・パージ―
- 著者
- ハンス・マーティン・クレーマ 楠 綾子
- 出版者
- 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.150-170, 2007
本稿は,1948年から1950年にかけて行われた「共産主義的」大学教員の追放(レッド・パージ)を,いわゆる占領政策の「逆コース」の一例として検討する.本稿は,レッド・パージは,米国の対日政策の変化によるものではなく,むしろ日本主導で行われたと考える.反共主義は1946年以降,教育行政の思想においては不可欠の要素であった.しかしながら,反共主義が処罰的行動へと直結したわけではない.政治色よりも大学での地位の低さといった要素が個人の追放の決定要因になったことは,追放が単に上からの命令によるものではなかったことを示唆している.本稿は,旧制弘前高校の哲学講師と京都府立医科大学の解剖学教授のふたつの追放の事例からこれを証明するものである.「逆コース」を従来の研究のようにとらえれば,日米それぞれの担当者が占領政策にいかなる貢献をしたのかが見落とされることになる.占領政策の形成に日本がいかなる役割を果たしたのかを明らかにするためには,中堅,下層レベルの行動を考慮に入れて占領期の正確な実像を描く必要がある.
- 著者
- 中村 かれん
- 出版者
- 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社會科學研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3/4, pp.184-205, 2006-03-28
日本の聴覚障害者を代表する団体は,政府の利益を推進するよう設計された法的環境のなかで単に活動しているというだけでなく,さらに進んで,システムを自己の利益のために操作することにも成功している.この団体は,政治権力による統制を避けるために,団体をアメーバのように細分化し,団体構造の柔軟性を保ってきた.本論文は,日本の市民社会構造の中での政治権力とそれに対する抵抗の問題を取り上げる.
15 0 0 0 OA 金融ビッグバンはなぜ失敗したのか : 官僚主導改革と政治家の介入
- 著者
- 岡本 至
- 出版者
- 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社會科學研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.109-139, 2005-02-07
1990年代の「金融ビッグバン」は,日本の金融システムの抜本的自由化を図り,自由で公正でグローバルな金融市場を創出することを目指したものだった.しかし現在,証券市場の停滞や銀行の不良債権問題などに見るように,改革は所期の目的を果たしていない.これはなぜか,論文は,ビッグバン失敗の原因を,改革が証券業の自出化に留まり銀行部門への政府の保護が継続したこと,そして政府の証券市場に対する場当たり的介入にあることを確認する.その上で論文は,この問題は,改革が大蔵省証券局のイニシアティブによる「ボトムアップの改革」であったこと,大蔵省解体後,政治家が金融行政に介入するようになったこと,という金融ガバナンス上の問題に起因していると結論する.
- 著者
- 平田 恵子 山崎 由希子
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 社會科學研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.162-190, 2006-01-31
国際規範に関する分析は概して,システムレベルの規範の普及に着目している.本稿では,そのような分析はネオリアリズム,新自由主義制度派,構造主義などに根ざしており,主に二つの問題があると主張する.一つは,それらの分析が普及に成功した規範の実例に多大な関心を払っているのに対し,失敗したものについては見過ごしていることである.もう一つの問題はそれらの分析が,規範の普及する過程において国際規範と国内構造がどのように関連しているかを検証できていないことである.この関連を見過ごすことにより,システムレベルの研究は国際規範が国内の領域に広がる具体的なメカニズムとプロセスを明らかにできないでいる.本稿は国内構造(特に文化・政治的構造)が国内レベルにおける国際規範の普及を可能にする主要要素であると主張する.日本における反捕鯨規範の受け入れ拒否を分析するにあたり本稿は,このような国内構造が反捕鯨規範の出現や受け入れを阻むフィルターとして機能していると論じるものである.
13 0 0 0 OA リベラル・コミュニタリアン論争再訪
- 著者
- 宇野 重規
- 出版者
- 国立大学法人 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.89-108, 2013-03-26 (Released:2021-02-09)
12 0 0 0 OA 平成ヤクザ : バブル崩壊と暴対法(「ISS-O. U. P. Prize」受賞論文)
- 著者
- ヒル ピーター (訳)橋本 陽子
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 社會科學研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.186-209, 2005-02-07
本論は,1989年に「昭和」という時代が終ったあとに生じた,ヤクザ(暴力団)の企業活動の発展を探るものである.平成以降,ヤクザは,彼らの経済環境に大きな影響をあたえた二つの出来事と格闘してきた.その出来事とは,バブル経済の崩壊と1992年の暴対法(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」)の施行である.バブル崩壊以後の経済不況のもとで,ヤクザは金になる事業を奪われたが,その分他の手段で補った.暴対法は,合法とされたヤクザの行為に新しい規制を加えたため,従来の行為による事業は高くつくことになったが,団員たちは新しい収入源の開拓に向うようになった.とりわけ,バブル経済と暴対法のダブルパンチヘの対応として増えたのが,覚せい剤取引や窃盗団であった.本論は,経済的な困難が長引くと,これまで彼らの世界を安定させてきた組織内あるいは組織間のメカニズムが弱体化するであろうという結論を導く.
11 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染症に関する壮年パネル調査 ―概要と記述統計分析―
- 著者
- 飯田 高 石田 賢示 伊藤 亜聖 勝又 裕斗 加藤 晋 庄司 匡宏 ケネス・盛・マッケルウェイン
- 出版者
- 国立大学法人 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.95-125, 2022-03-08 (Released:2022-04-28)
9 0 0 0 IR 包摂社会の中の社会的孤立 : 他県からの移住者に注目して
- 著者
- 阿部 彩
- 出版者
- 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社會科學研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.13-30, 2014-05-08
特集 福井県における生活保障のガバナンス本稿は、福井県における大規模アンケート調査のデータを用いて、社会的交流(家族を含む他者とのコミュニケーションや付き合い)、社会的サポート(情緒的および手段的サポート)、社会的参加(地域活動やボランティア活動など)の3つの次元における社会的孤立について分析を行ったものである。そして、年齢や性別、家族構成、結婚状況、就労形態、離職経験、学歴をコントロールした上で、福井県への移住者と福井県生まれの人に社会的孤立となる確率に違いがあるかを分析したその結果、社会的交流においては、女性において、福井県生まれの人に比べて、福井県に移住してから20年未満の人、および30年以上の人は、高い確率で孤立状況となることがわかった。この関係は、男性においては見られなかった。社会的サポートについては、福井県生まれとそうでない人の間に有意な差はなかった。しかし、社会的参加については、男性のみにおいて福井県に移住してから20年未満の人は約2.5倍から2倍の確率で孤立するリスクが高かった。This paper analyzes three types of social isolation (1. Communication, 2. Social support, 3. Participation) using a large-scale micro-data of Fukui Prefecture in Japan. The results indicate that divorcees, those living alone and migrants from other prefectures face a significantly higher risk of social isolation even after controlling for age, gender, socio-economic status, and household structure. The migrant women face higher risk for lacking communication with others, while migrant men face higher risk of lack of social participation compared to natives of the Fukui Prefecture. The analysis shows that there are different risk factors for different types of social isolation and that moving from other prefecture, even after many years of residence, still pose risk of social isolation.
8 0 0 0 OA ポスト・ジェンダー期の女性の性売買 ―性に関する人権の再定義―
- 著者
- 中里見 博
- 出版者
- 国立大学法人 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.39-69, 2007-02-02 (Released:2021-02-09)
8 0 0 0 IR 国際関係論と歴史社会学--ポスト国際関係史を求めて (特集 歴史社会学)
- 著者
- 大賀 哲
- 出版者
- 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.37-55, 2006
本稿の趣旨は,実証主義とポスト実証主義の認識論的差異,国際関係論における理論と歴史の方法論的な差異を踏まえながら,国際関係論における歴史社会学の用法を考察していくことにある.歴史社会学の用法や,理論と歴史の差異,言説分析の可能性とその限界等は既に社会学で広範に議論されているが,国際関係論において,歴史社会学のもつ可能性についての研究は少なく,未だ十分に議論されていないというのが現状である.本稿の意図するところはまさに国際関係論における歴史社会学の展開を掘り下げ,その研究上の可能性を考察する事にある.具体的には二つの歴史社会学(ウェーバー型とフーコー型)を比較検討し,とりわけフーコー型の歴史社会学にどのような特徴・妥当性があるのかを吟味していく.換言すれば,歴史社会学における先進的な研究動向を取り入れ,ポスト構造主義の概念を援用して歴史・思想要因を考察する.そして,ポスト国際関係史(或いはポスト国際関係論)を再構成した場合にそこにどのような可能性があるのかを検証する.
8 0 0 0 OA 教育の歴史社会学 : その展開と課題
- 著者
- 広田 照幸
- 出版者
- 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社會科學研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3/4, pp.137-155, 2006-03-28
本稿は,戦後日本において,歴史社会学的な観点から教育の諸問題を考察した研究の成立と発展をたどり,課題を検討する.1950年代には社会学的な歴史研究の4つの方向が存在した.しかし,1950年代後半からの高度成長によって,それらは途絶した.代わって,1960年前後に歴史研究に着手した若い教育社会学者たちは,機能主義的近代化論に依拠した研究を始めた.それは,当時の教育の課題と密接に関わった歴史研究であった.近代化が達成された後の1970年代半ば~1980年代には,教育社会学者たちは「学歴主義」に注目することで,行き詰まりを免れ,現代社会と密接に関わる歴史研究をまとめることができた.1990年代には教育の歴史社会学の研究成果は量的に増加した.そこでは,これまでの研究がより各論的に追求されるとともに,ポストモダン論などに刺激された言説研究や社会史研究が新たに登場した.しかし,学歴主義の風化,ポストモダン論の変質,大胆な教育改革などの社会の変化は,歴史研究の現代的意義を希薄なものにしてしまった.教育の歴史社会学は,現代社会の変化をふまえた,新たな問題の立て方を必要としている.
7 0 0 0 OA 新型コロナ危機への財政的対応:2020年前半期の記録
- 著者
- 安藤 道人 古川 知志雄 中田 大悟 角谷 和彦
- 出版者
- 国立大学法人 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.1, pp.129-158, 2021-03-31 (Released:2021-05-13)
7 0 0 0 IR 選挙制度の非一貫性と投票判断基準 (特集 選挙制度改革後の政党政治)
- 著者
- 前田 幸男
- 出版者
- 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.67-83, 2007
1994年の選挙制度改革は,衆議院の選挙制度として小選挙区比例代表並立制を導入することで,従来の中選挙区制下の候補者・利益誘導中心の選挙とは異なる政党・政策中心の選挙を実現することを目的とした.しかし,衆議院の選挙制度は総体として存在する複数の選挙制度の一部に過ぎない.衆議院議員・党中央組織が,地方議員・党地方組織と密接な関係を持っている以上,衆議院の選挙制度を変更した効果が地方レベルで相殺される可能性が存在する.本稿の目的は,予期される選挙制度改革の影響が有権者の態度において確認できるか,さらには,その影響が地方レベルの選挙制度により相殺されているかを,検討することにある.具体的には,JES IIのデータに地方選挙のデータを結合し,衆議院選挙における判断基準としての政党志向と候補者志向が,如何に都道府県議会選挙区定数の影響を受けているかを分析する.
7 0 0 0 OA 「法の支配」再考 : 憲法学の観点から
- 著者
- 愛敬 浩二
- 出版者
- 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社會科學研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.5/6, pp.3-26, 2005-03-30
英語圏の法哲学やイギリスの憲法理論においては一般に,「法の支配」の多義性・論争性が強調されるので,「法の支配」を「善き法の支配rule of good law」と混交する考え方は消極的に評価される.他方,日本の司法制度改革を理論的に主導した佐藤幸治の議論の特徴は,「法の支配」それ自体が本来的に「善きもの」であるかのように語る点にある.この語り口を可能にするのが,「法の支配」と「法治主義」の法秩序形成観における差異を強調し,前者の優位を論ずる佐藤の独特な「法の支配」論である.本稿は,戦後公法学の論争上に佐藤の「法の支配」論を位置づけた上で,現代イギリス憲法学の理論動向を参考にしながら,佐藤の憲法学説を批判的に検討する.そして,佐藤の議論のように,政治道徳哲学への越境を禁欲し,法理論の枠内で「法の支配」を厳密に概念構成する学説が孕む問題性を明らかにする.
7 0 0 0 OA 労働と格差の政治哲学(<特集>「労働」と「格差」)
- 著者
- 宇野 重規
- 出版者
- 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社會科學研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3/4, pp.153-172, 2011-03-15
本稿は「労働」と「格差」について, 政治哲学の立場からアプローチする. 現代社会において, 労働は生産力のみならず社会的なきずなをもたらし, さらに人々に自己実現の機会を与えている. 対するに格差は, 社会の構成員の間に不平等感や不公正感を生み出すことで, 社会の分断をもたらす危険性をもつ. このように労働と格差は, 正負の意味で政治哲学の重要なテーマであるが, これまでの政治哲学は必ずしも積極的に向き合ってこなかった. その理由を政治思想の歴史に探ると同時に, 現代において労働と格差の問題を積極的に論じている三人の政治哲学者の議論を比較する. この場合, メーダが, 政治哲学と経済学的思考を峻別するのに対し, ロールズは, ある程度, 経済学的思考も取り入れつつ, 独自の政治哲学を構想する. また, 現代社会が大きく労働に依存している現状に対しメーダが批判的であるのと比べ, ネグリのように, あくまで労働の場を通じて社会の変革を目指す政治哲学もある. 三者の比較の上に, 新たな労働と格差の政治哲学を展望する.