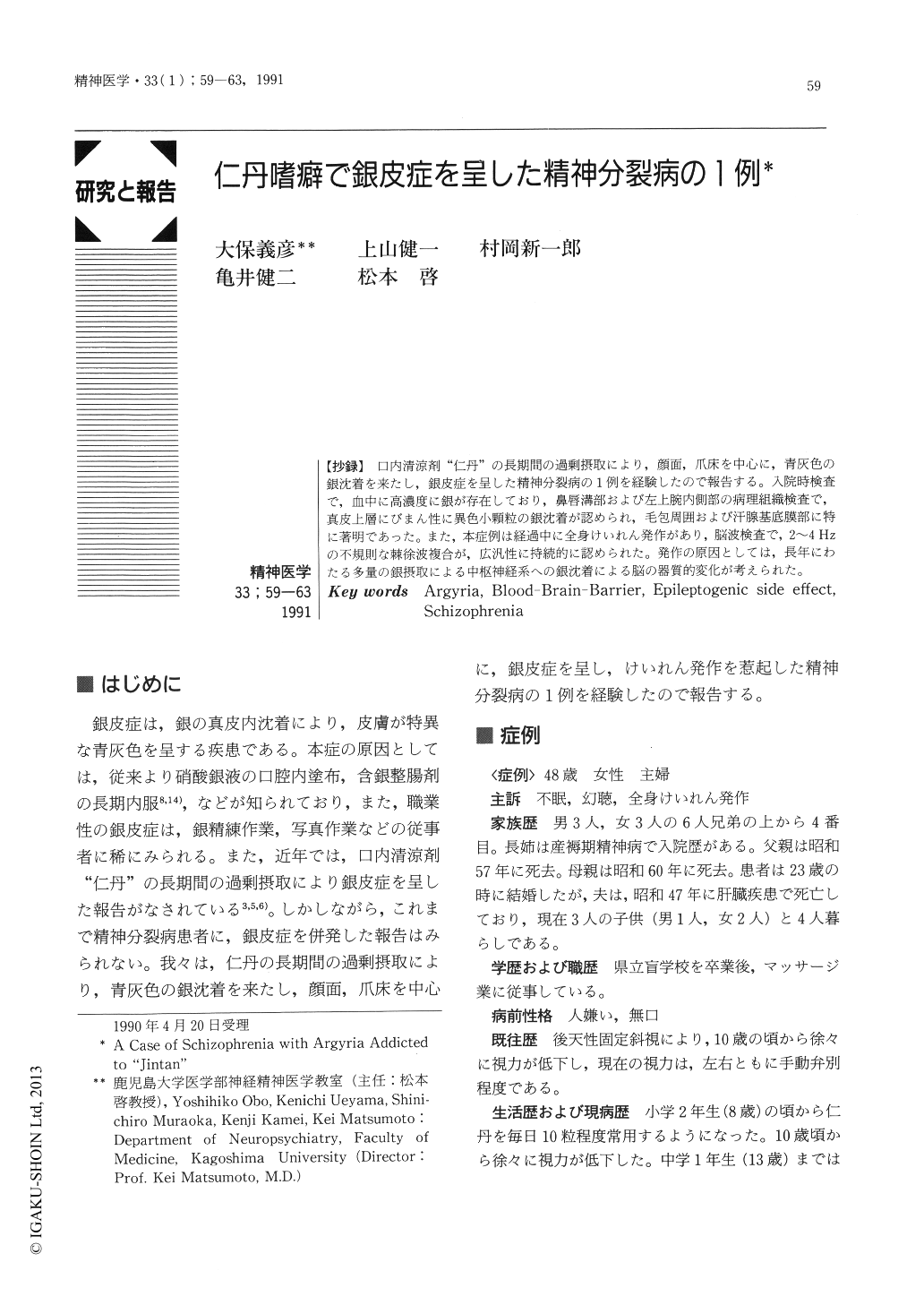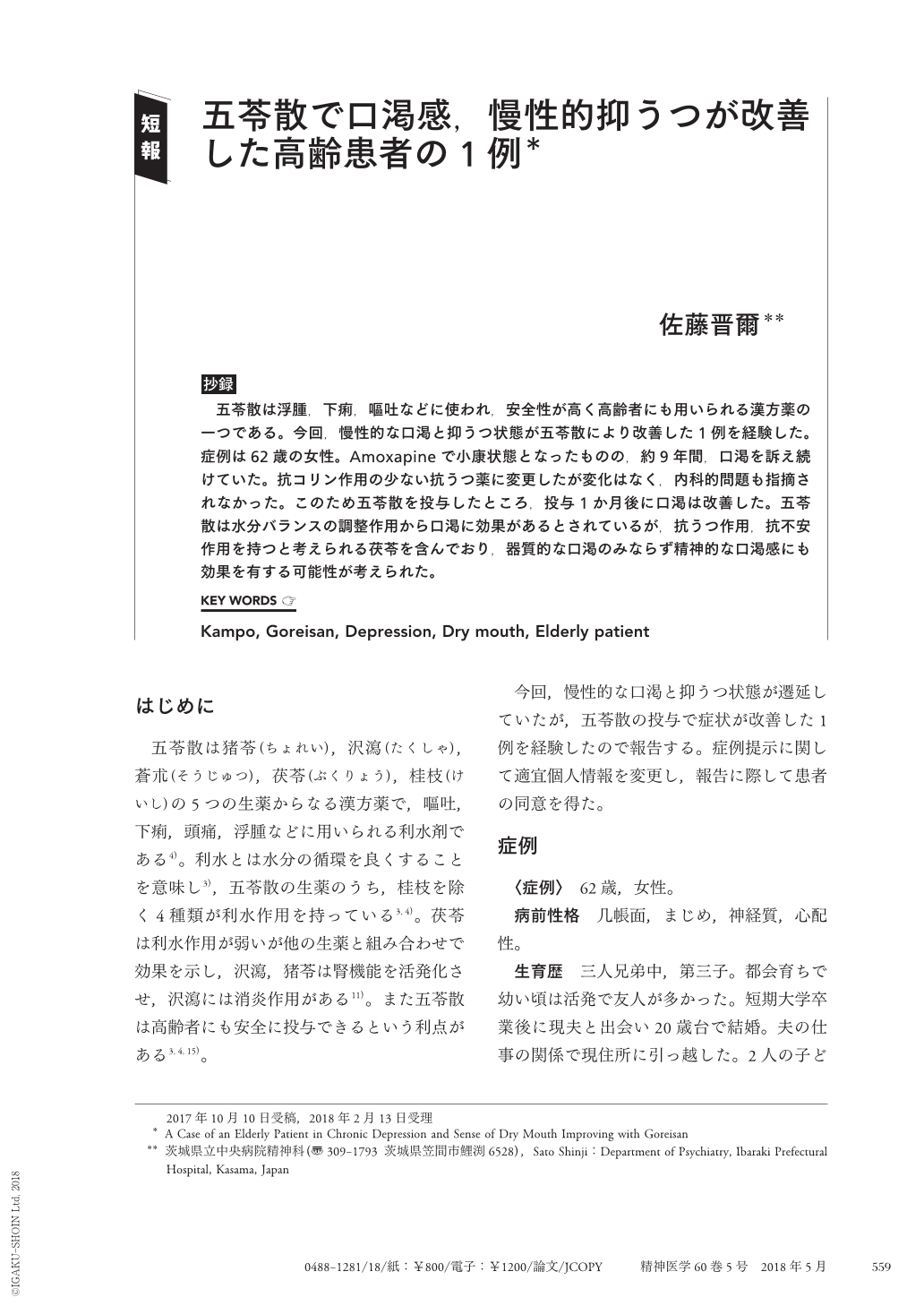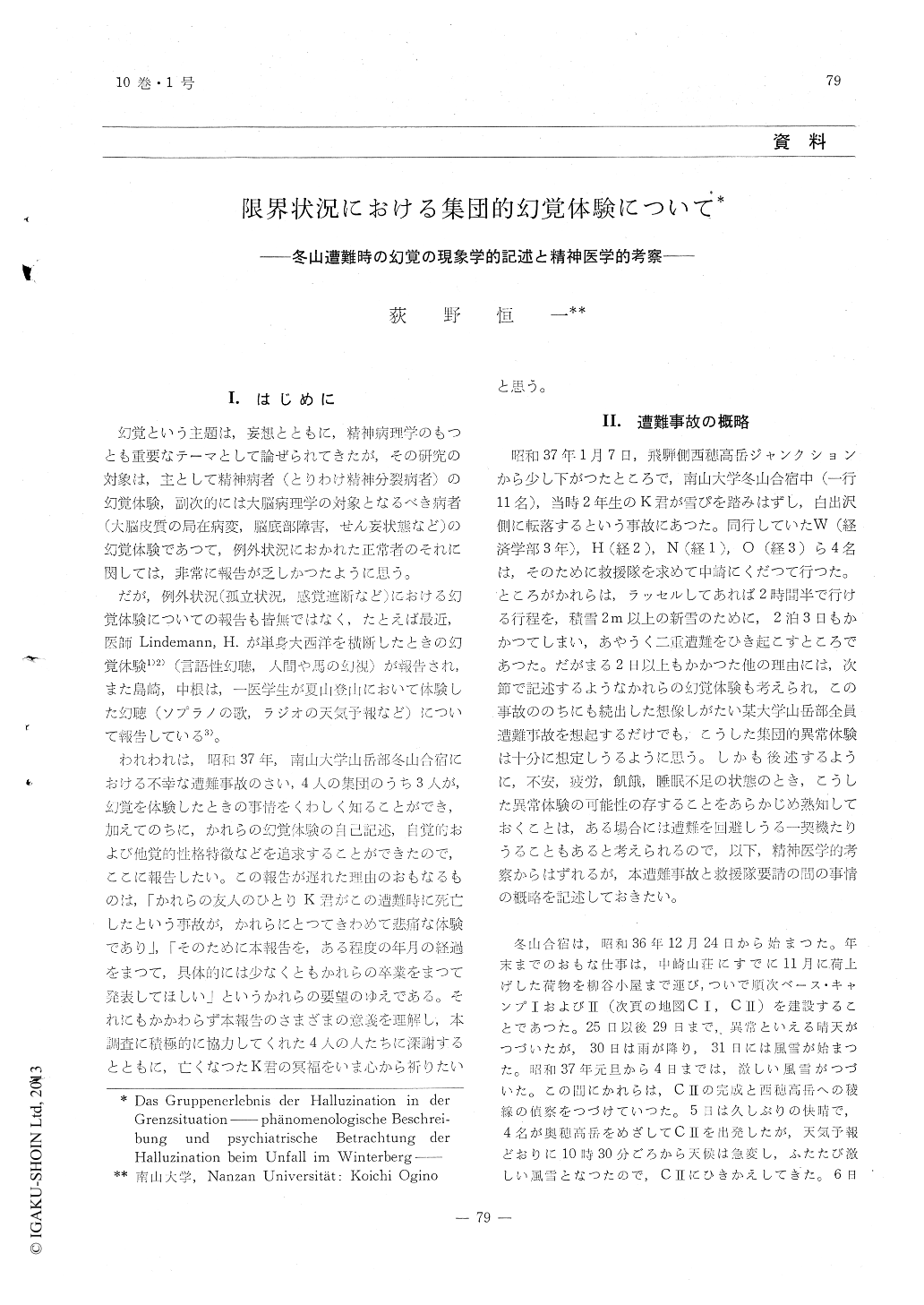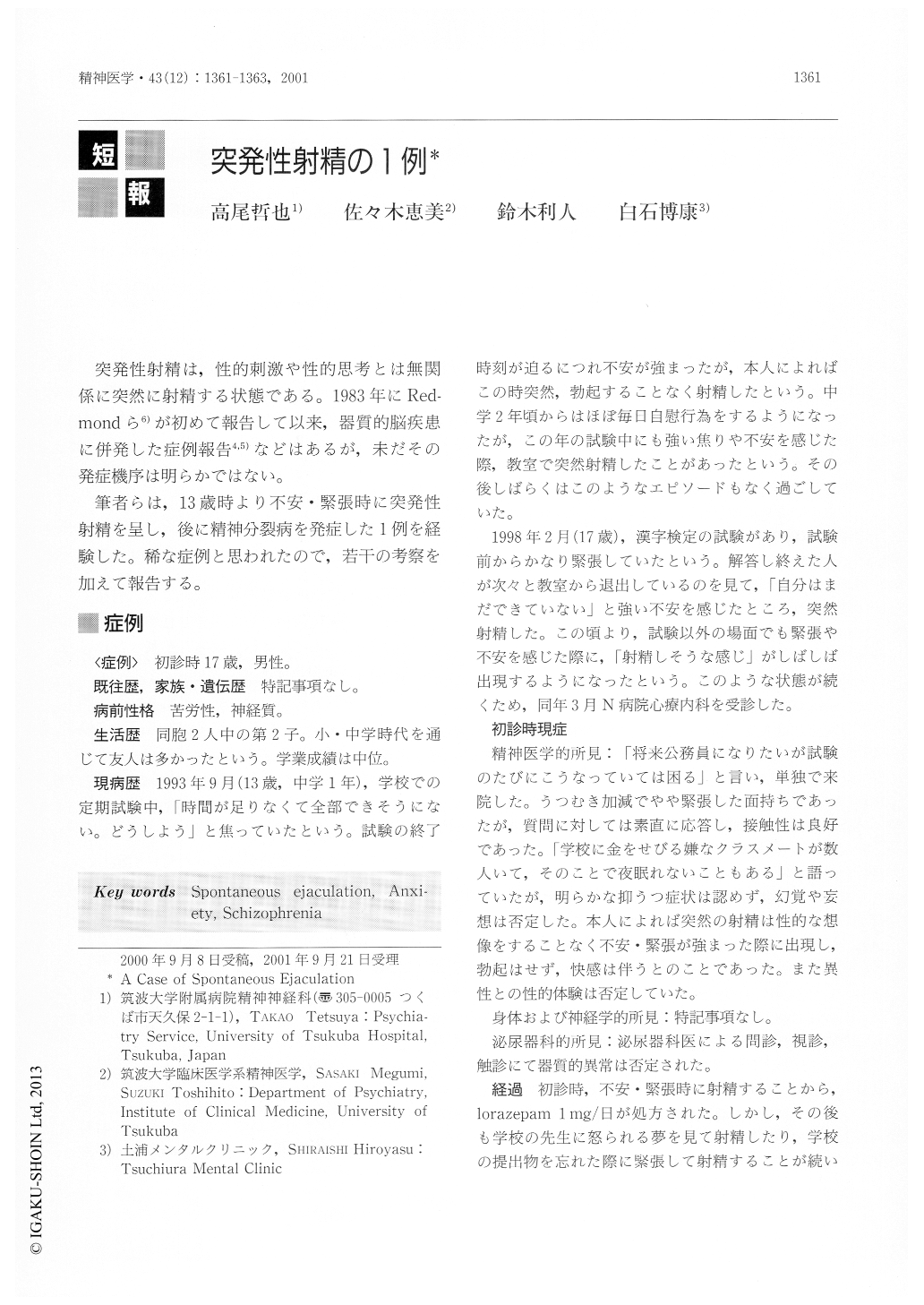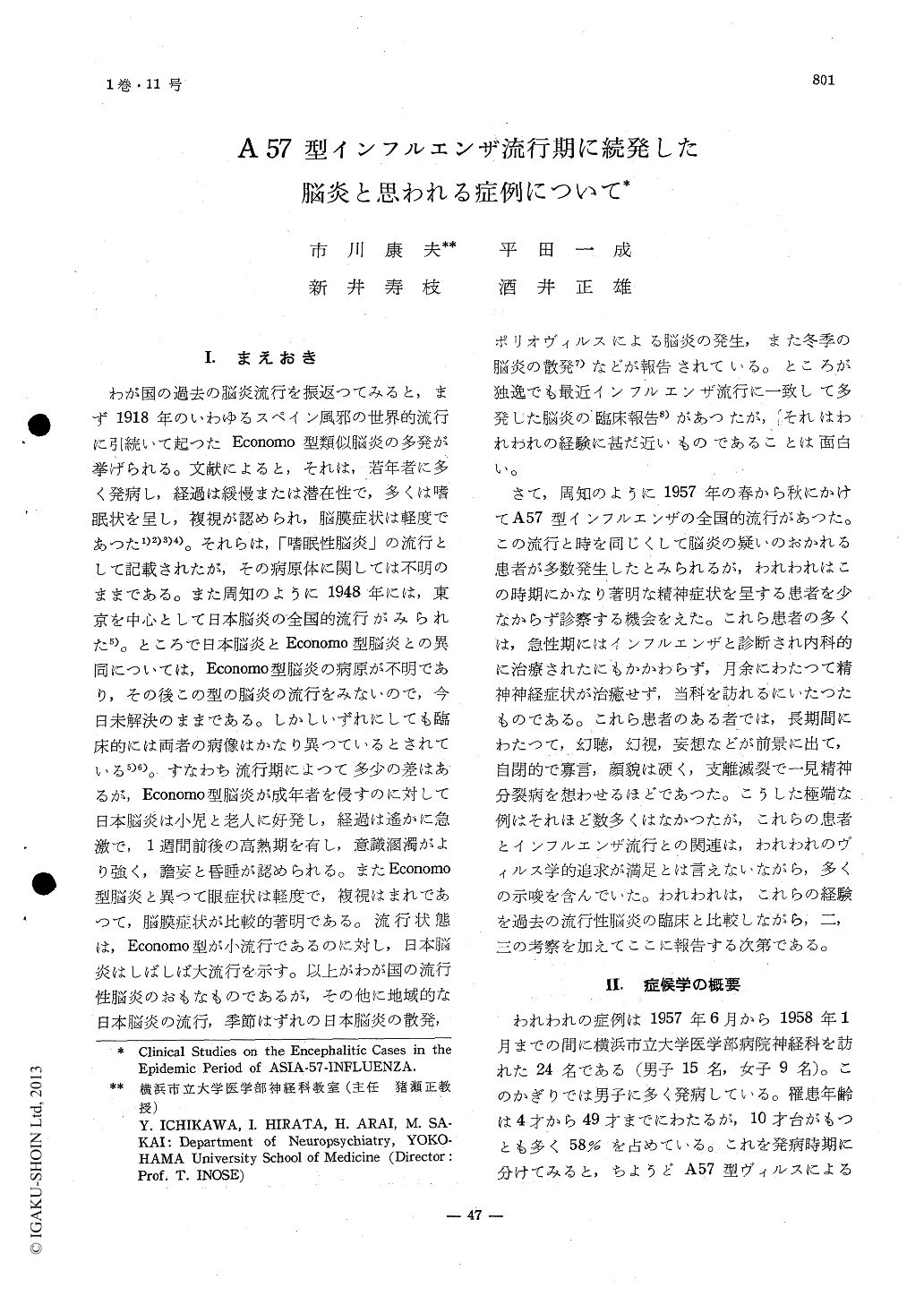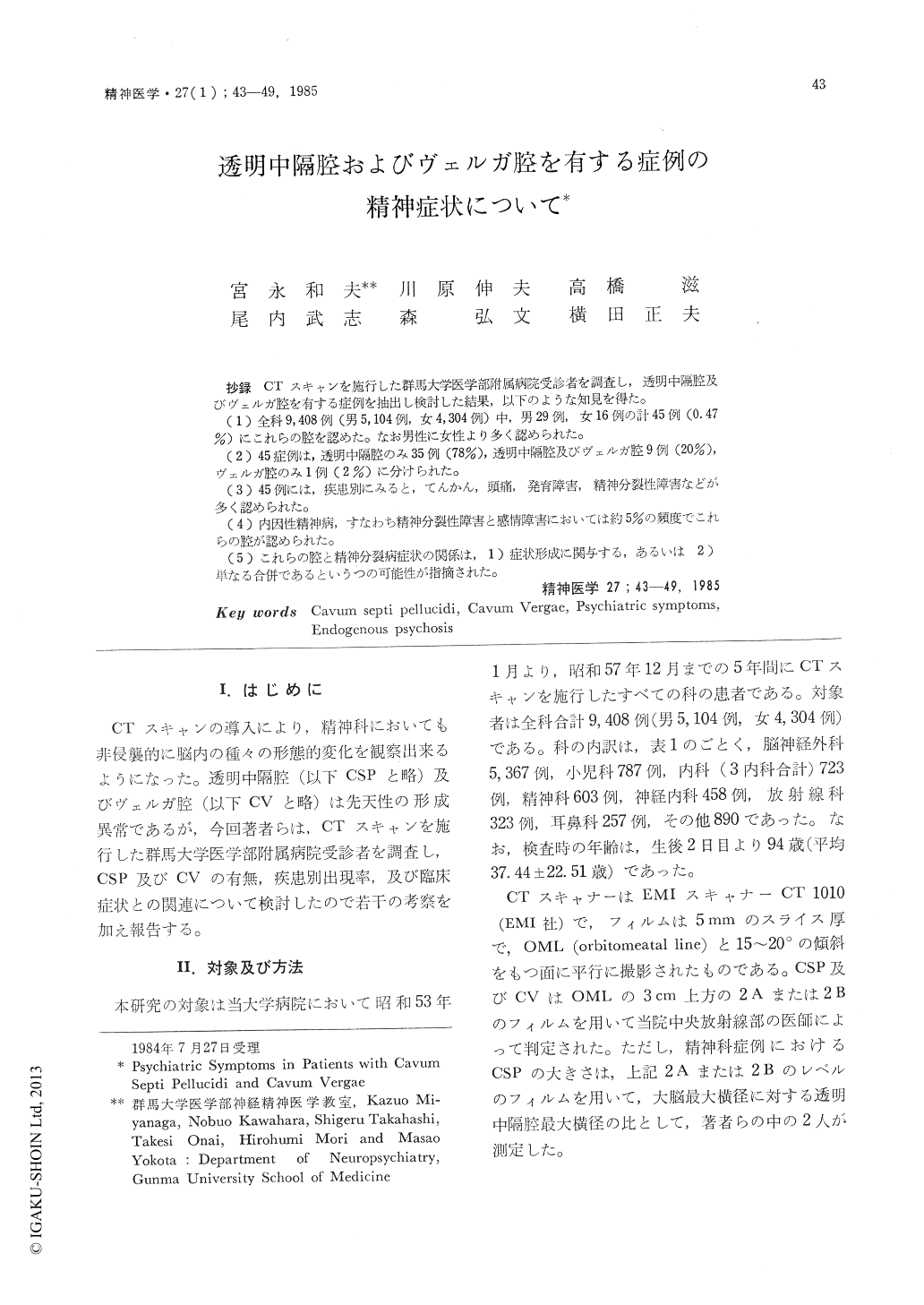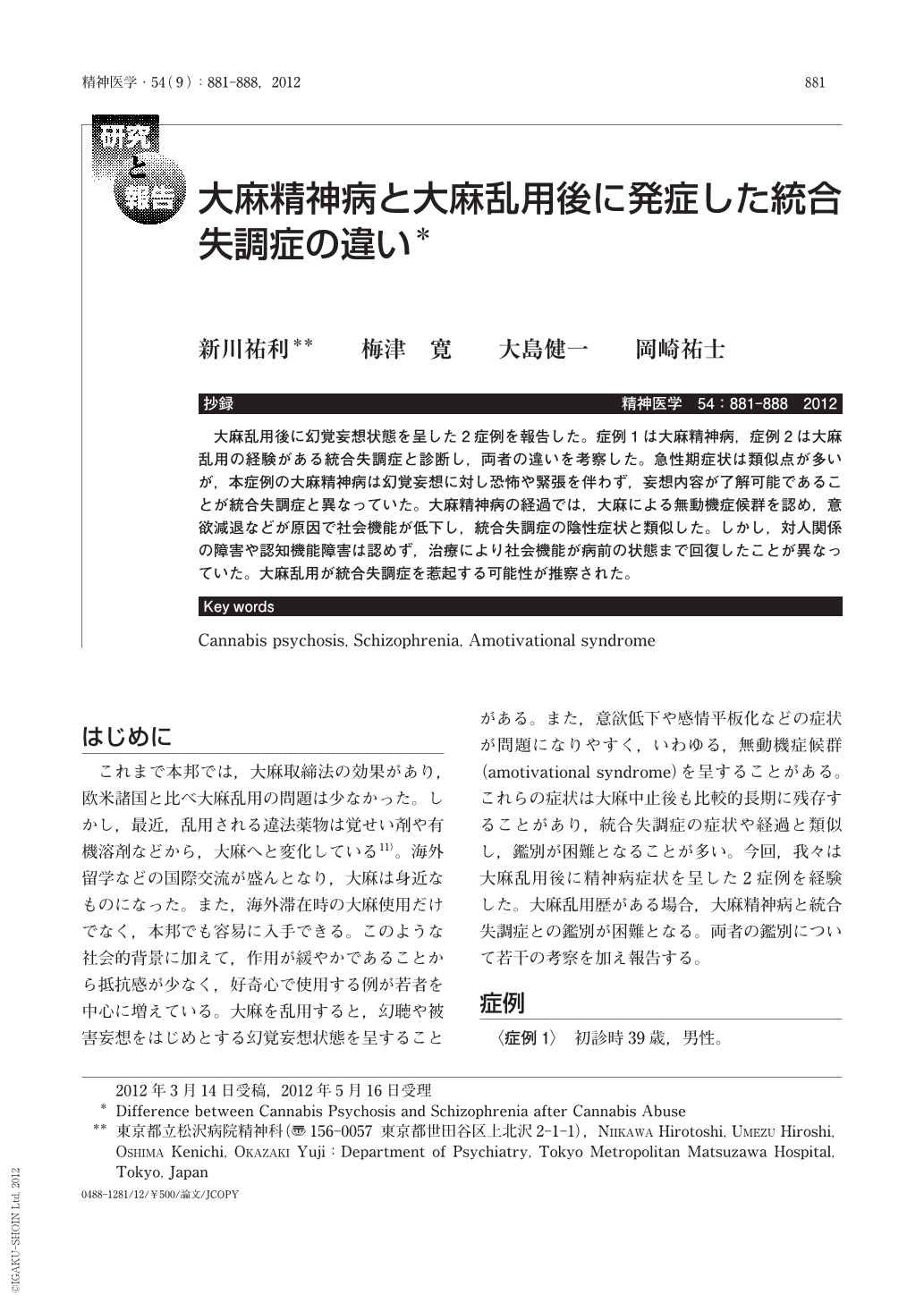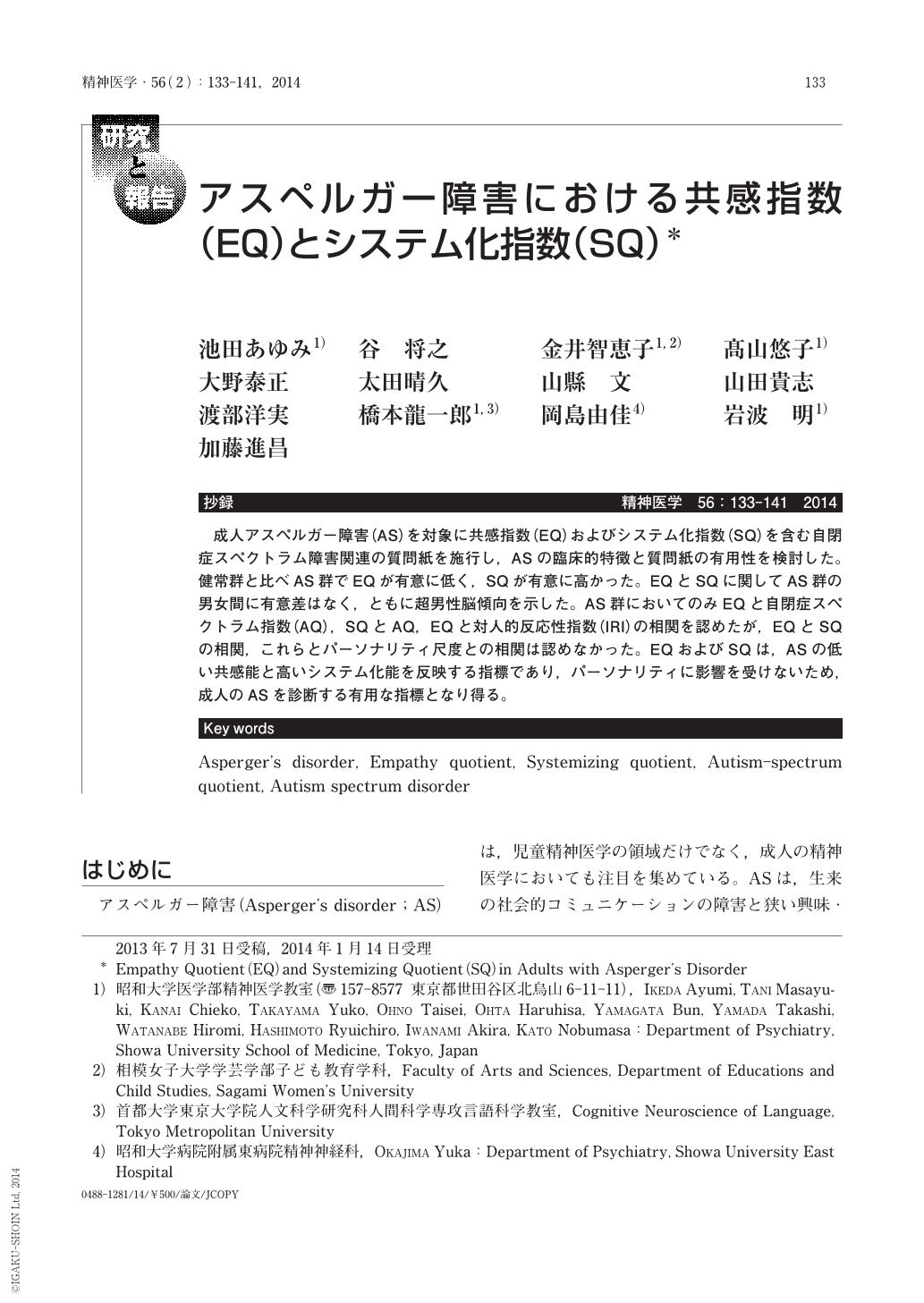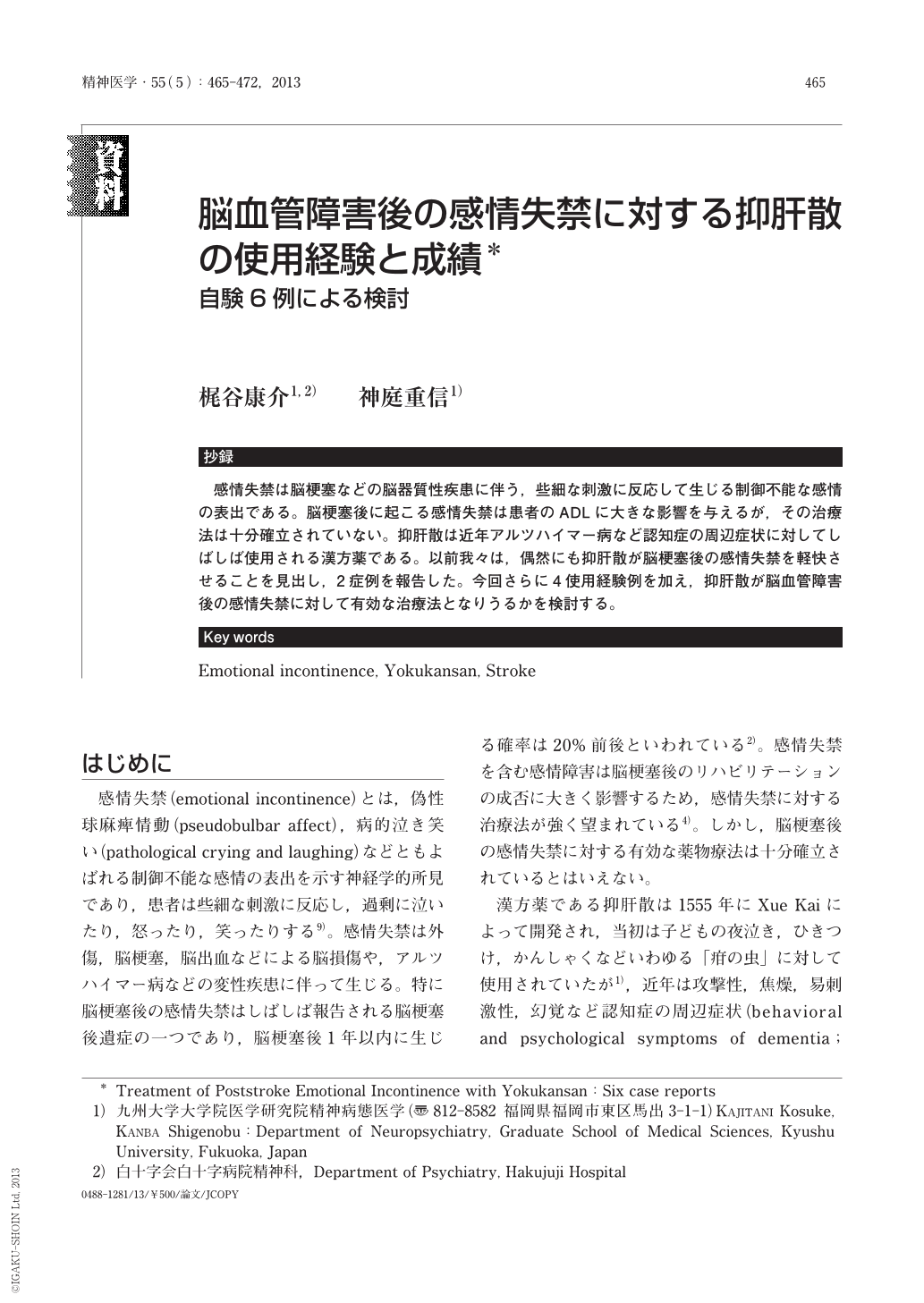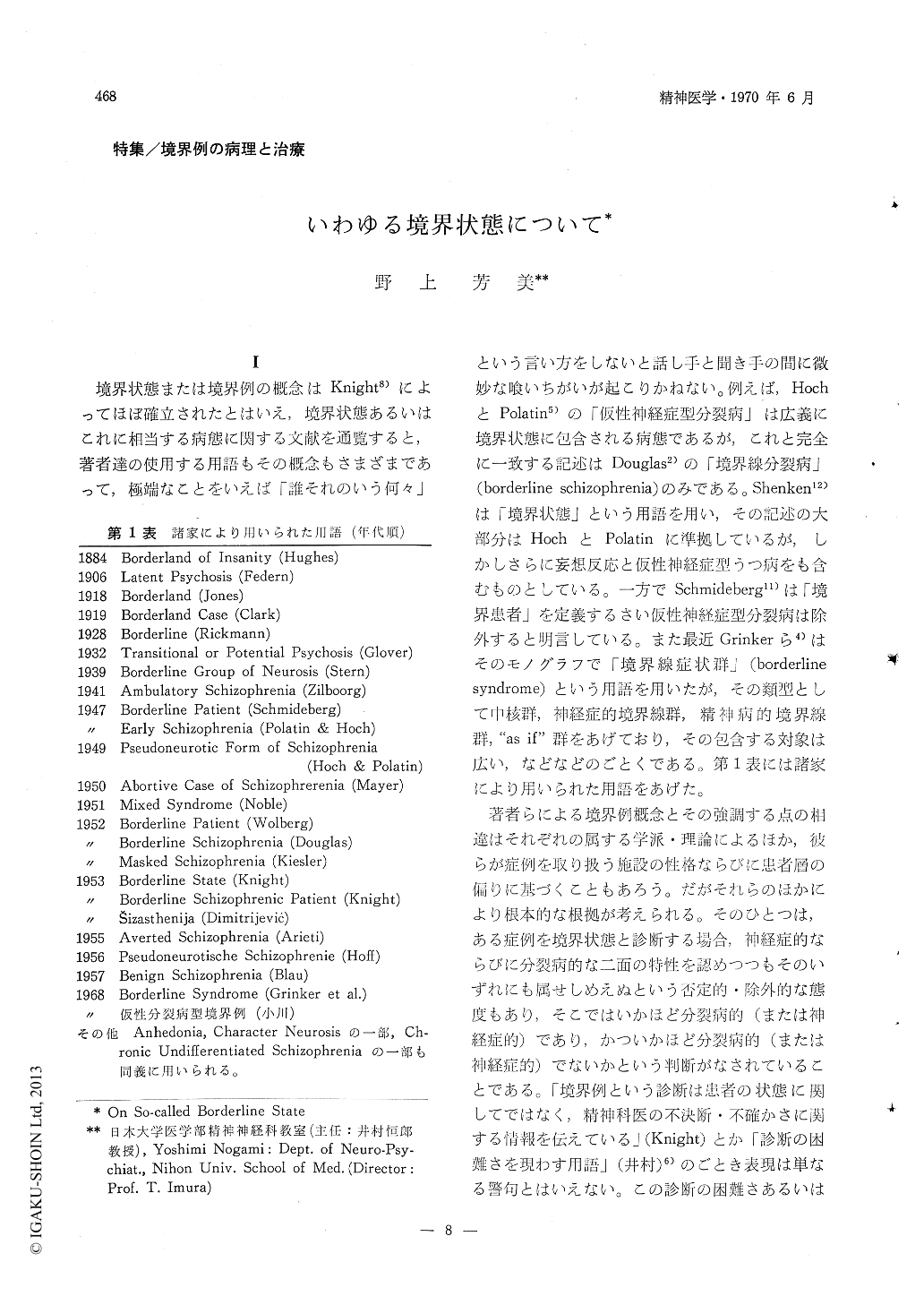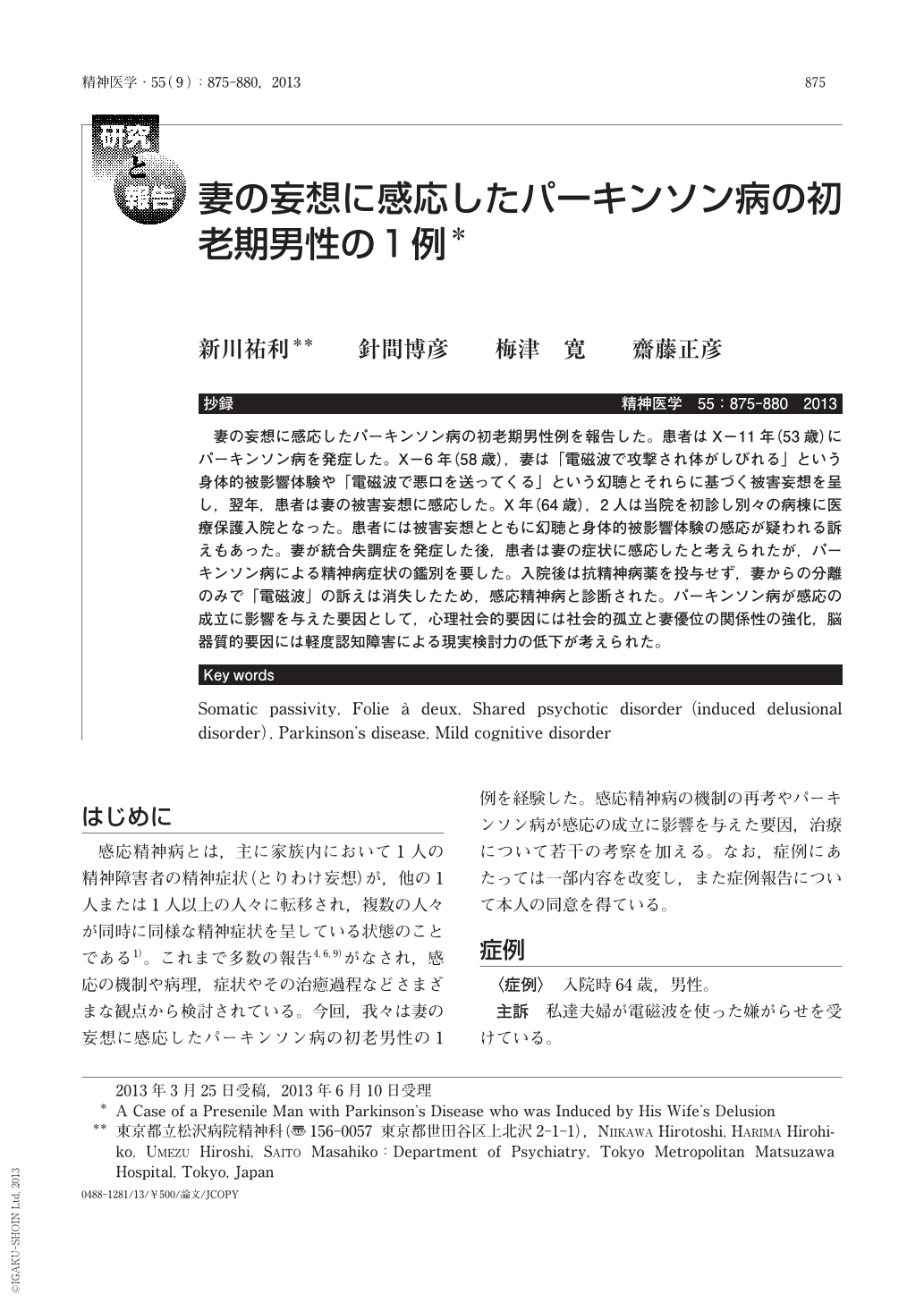3 0 0 0 自己と他者―脳機能画像での検討
- 著者
- 杉浦 元亮
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.223-230, 2009-03-15
はじめに 「自己と他者」という概念には,わかるようでわからない,曖昧なところがある。 自分の身体,自分の顔,自分の名前は明確に他者の身体,他者の顔,他者の名前,と区別ができる。その区別ができなくなったら大きな問題だし,そういう意味で自己と他者を区別する能力というものが脳に存在することは,誰もが認めるであろう。 では,「自分の家族」とか「自分の友人」はどうであろうか。「自分の」というのだから「自己」の側にいるのかもしれないし,明らかに自分とは異なる人格を指しているのだから「他者」なのかもしれない。この「自分の家族」や「自分の友人」を,そうでない人々と区別する能力は,自分の身体や顔や名前を他者のそれと区別する能力と,やや趣が異なりそうだ。 さらに,こちらはどうだろう。多くの若者が「本当の自分」がわからないことに焦り,本当の自分を探すために,(多くの場合比喩的な意味で)旅に出る。若者が見失ったり,発見したりする「本当の自分」とは,いったい何なのか。この意味での「自己」に相対する「他者」とは何なのか。この意味で自己と他者を区別する能力について考えるためには,また別の考え方が必要そうである。 このように「自己と他者」は,少なくとも単一の明確に定義できる概念ではない。そのこと自体は,心理学・哲学では昔から自明のことで,多くの論者が複数の「自己」や「自己と他者の区別」(の概念)について,盛んにそれぞれの立場と動機でさまざまな分類・モデルを提唱してきた6)。その数多くの分類・モデルそれぞれは,それぞれの立場で合理的であり,合目的的である。しかし筆者が,神経科学や認知科学の研究者という立場で脳内基盤を研究する目的で眺めたとき,「自己」や「自己と他者の区別」という概念を包括的に明確に解剖した分類・モデルは(筆者の知る限り)いまだ確立されていない。 本稿で筆者は,脳機能画像研究者としての立場から,「自己と他者の区別」の脳内基盤を解明する目的で,「自己と他者」の多因子モデルを提案する。脳機能画像研究者の立場で「自己と他者の区別」の脳内基盤を解明するということは,「自己と他者の区別」を実現する脳内情報処理をできる限り明確に定義し,これに関与する脳領域あるいはその複数の脳領域で構成される脳ネットワークを明らかにするということである。したがって,ここで提案するモデルは,次の3つの条件を満たしている必要がある。まず,①「自己と他者の区別」を独特の脳内情報処理として定義・説明できなければならない。それから,②その情報処理能力が特定の神経基盤に依存している必要がある。この2つは具体的には,中枢神経系の障害(できれば特定の脳領域の損傷)によってその脳内情報処理能力が特異的に欠落している(と考えられる)例を挙げられること,で同時に満たされる。そして,③脳機能画像実験の課題操作でその情報処理を作動させたり,抑制したりすることが可能,あるいはその情報処理能力の個人差を定義し,なんらかの心理測定法で量的評価ができること,が必要である。 これら3つの条件は,精神疾患の臨床と相性がよい。精神疾患の症状・障害の多くはなんらかの意味で「自己と他者の区別」の障害としてとらえることが可能である。条件1と2を満たすモデルがあれば,とらえどころのない精神疾患の症状・障害を,脳内情報処理能力の欠落/低下の概念で明確に定義・説明することができる。また,症状・障害の原因となる神経基盤から,その分子基盤(障害の原因となっている蛋白や遺伝子)を特定できる可能性が出てくる。そして条件3を満たせば,脳機能画像を用いた診断の可能性が出てくる。 筆者は,これまで自己顔認知の脳メカニズムについて,脳機能画像を用いた研究を行ってきた。その中で,自分の顔の認知に特異的な認知処理が単一の脳内情報処理や脳ネットワークでは説明できないことを実感した。「自己」について神経科学的に説明するためには,より包括的な「自己と他者の区別」の多因子モデルが必要であると確信するに至った。本稿では,まずこれまでの自己顔認知研究のあらましをまとめ,そのうえで現在筆者の妄想する「自己と他者」の多層性モデルを説明し,最後に「自己と他者」をめぐる脳画像研究の今後について述べる。
- 著者
- 谷 敏昭
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.7, pp.727-733, 2007-07
- 著者
- 山本 暢朋 稲田 俊也
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.5, pp.457-460, 2009-05
2 0 0 0 ライシャワー事件の波紋
- 著者
- 林 暲
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.6, pp.475-476, 1964-06-15
さる3月24日,虎の門の付近に所用があつてタクシーで米大使館にそつた霊南坂を下りかけると坂下の方に車や人が集まつて何やらあわただしい空気である。いそぐままに坂下近くで車をすてて歩きながら聞くともなしに耳にしたところではライシャワー大使が刺されたという。虎ノ門病院に近い目的のビルについて,病院に収容されたこと,傷は脚で全治2週間くらいという話をきかされた。午後1時ごろのことである。夕刊で犯人は精神障害者らしいということを見てやれやれそうかと思つたが,さて問題はそれからであつた。国会会期中のことでもあり,当然本件についての質問が集中しそこに当局の思いつきのような逆行的な答弁の現われる傾向も見られた。新聞,週刊誌などには例によつて患者をすべて野獣視する野放しということばを用い,責任の追求はこれまで精神衛生的施策をなおざりにした厚生当局よりも警察,治安対策の方面に集中し,政府も早川自治相兼国家公安委員長に詰腹を切らせることで当面を糊塗した。また犯人の実態についての確かなことの解らぬままに,変質者,精神異常,分裂病,また精神薄弱といつたよび方がされ,また林髞氏のような非専門家が例のごとき変質者危険論,隔離論を語る始末で,全体として警察行政的な対策のとびだす恐れも十分うかがえたので,3月26日に厚生省精神衛生課長をつかまえて,このさい精神衛生審議会にこの事態についての対策を諮問するなり,あるいは審議会が独自で意見の具申をするようにできまいかと申入れた。とくに厚生省としては犯人の患者の実態,家人が一度精神病院に入院させながらその後家庭看護に終始してきた事情などについてよく調べておくべきであり,犯人の身柄は検察庁におさえられて専門家に見せられないにせよ,家人の協力を得て発病以来の経過をきぎ,家人が最初の入院以后精神病院に不信の念をいだくようになつたらしい事情などを確かめる必要があるといった。課長はいずれの提案に対しても難色があり,どうなるかと思つたが,審議会はともかく4月2日にとりいそぎ開催されることになり,これには厚生大臣も出席するということになつた。
2 0 0 0 仁丹嗜癖で銀皮症を呈した精神分裂病の1例
【抄録】 口内清涼剤“仁丹”の長期間の過剰摂取により,顔面,爪床を中心に,青灰色の銀沈着を来たし,銀皮症を呈した精神分裂病の1例を経験したので報告する。入院時検査で,血中に高濃度に銀が存在しており,鼻唇溝部および左上腕内側部の病理組織検査で,真皮上層にびまん性に異色小顆粒の銀沈着が認められ,毛包周囲および汗腺基底膜部に特に著明であった。また,本症例は経過中に全身けいれん発作があり,脳波検査で,2〜4Hzの不規則な棘徐波複合が,広汎性に持続的に認められた。発作の原因としては,長年にわたる多量の銀摂取による中枢神経系への銀沈着による脳の器質的変化が考えられた。
2 0 0 0 五苓散で口渇感,慢性的抑うつが改善した高齢患者の1例
抄録 五苓散は浮腫,下痢,嘔吐などに使われ,安全性が高く高齢者にも用いられる漢方薬の一つである。今回,慢性的な口渇と抑うつ状態が五苓散により改善した1例を経験した。症例は62歳の女性。Amoxapineで小康状態となったものの,約9年間,口渇を訴え続けていた。抗コリン作用の少ない抗うつ薬に変更したが変化はなく,内科的問題も指摘されなかった。このため五苓散を投与したところ,投与1か月後に口渇は改善した。五苓散は水分バランスの調整作用から口渇に効果があるとされているが,抗うつ作用,抗不安作用を持つと考えられる茯苓を含んでおり,器質的な口渇のみならず精神的な口渇感にも効果を有する可能性が考えられた。
I.はじめに 幻覚という主題は,妄想とともに,精神病理学のもつとも重要なテーマとして論ぜられてきたが,その研究の対象は,主として精神病者(とりわけ精神分裂病者)の幻覚体験,副次的には大脳病理学の対象となるべき病者(大脳皮質の局在病変,脳底部障害,せん妄状態など)の幻覚体験であつて,例外状況におかれた正常者のそれに関しては,非常に報告が乏しかつたように思う。 だが,例外状況(孤立状況,感覚遮断など)における幻覚体験についての報告も皆無ではなく,たとえば最近,医師Lindemann, H. が単身大西洋を横断したときの幻覚体験1)2)(言語性幻聴,人間や馬の幻視)が報告され,また島崎,中根は,一医学生が夏山登山において体験した幻聴(ソプラノの歌,ラジオの天気予報など)について報告している3)。
2 0 0 0 突発性射精の1例
Ⅰ.まえおき わが国の過去の脳炎流行を振返つてみると,まず1918年のいわゆるスペイン風邪の世界的流行に引続いて起つたEconomo型類似脳炎の多発が挙げられる。文献によると,それは,若年者に多く発病し,経過は緩慢または潜在性で,多くは嗜眠状を呈し,複視が認められ,脳膜症状は軽度であつた1)2)3)4)。それらは,「嗜眠性脳炎」の流行として記載されたが,その病原体に関しては不明のままである。また周知のように1948年には,東京を中心として日本脳炎の全国的流行がみられた5)。ところで日本脳炎とEconomo型脳炎との異同については,Economo型脳炎の病原が不明であり,その後この型の脳炎の流行をみないので,今日未解決のままである。しかしいずれにしても臨床的には両者の病像はかなり異つているとされている5)6)。すなわち流行期によつて多少の差はあるが,Economo型脳炎が成年者を侵すのに対して日本脳炎は小児と老人に好発し,経過は遙かに急激で,1週間前後の高熱期を有し,意識溷濁がより強く,譫妄と昏睡が認められる。またEconomo型脳炎と異つて眼症状は軽度で,複視はまれであつて,脳膜症状が比較的著明である。流行状態は,Economo型が小流行であるのに対し,日本脳炎はしばしば大流行を示す。以上がわが国の流行性脳炎のおもなものであるが,その他に地域的な日本脳炎の流行,季節はずれの日本脳炎の散発,ポリオヴィルスによる脳炎の発生,また冬季の脳炎の散発7)などが報告されている。ところが独逸でも最近インフルエンザ流行に一致して多発した脳炎の臨床報告8)があつたが,それはわれわれの経験に甚だ近いものであることは面白い。 さて,周知のように1957年の春から秋にかけてA57型インフルエンザの全国的流行があつた。この流行と時を同じくして脳炎の疑いのおかれる患者が多数発生したとみられるが,われわれはこの時期にかなり著明な精神症状を呈する患者を少なからず診察する機会をえた。これら患者の多くは,急性期にはインフルエンザと診断され内科的に治療されたにもかかわらず,月余にわたつて精神神経症状が治癒せず,当科を訪れるにいたつたものである。これら患者のある者では,長期間にわたつて,幻聴,幻視,妄想などが前景に出て,自閉的で寡言,顔貌は硬く,支離滅裂で一見精神分裂病を想わせるほどであつた。こうした極端な例はそれほど数多くはなかつたが,これらの患者とインフルエンザ流行との関連は,われわれのヴィルス学的追求が満足とは言えないながら,多くの示唆を含んでいた。われわれは,これらの経験を過去の流行性脳炎の臨床と比較しながら,二,三の考察を加えてここに報告する次第である。
2 0 0 0 統合失調症の減少と軽症化はあるのか
- 著者
- 須賀 英道
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.11, pp.1019-1027, 2017-11-15
はじめに 統合失調症が日本で減少してきたことや軽症化もみられることは,多くの精神科医が指摘していることである。これは日本に限ったことではなく,海外でも統合失調症は消えて行くのではないか5)とまで言われて久しい。多くの精神科医がその傾向を感じる中で,日本では根拠のないことは何も言えないといった風潮がある。日本では最近の疫学調査が十分なされておらずエビデンスがないため当然かもしれない。しかし,この見方はエビデンス医学の視点であり,科学者にとっては手法として今後も続けるべきであるが,臨床現場で精神科に従事する医師の誰もがあるべき見方でもないだろう。 逆に,臨床家がエビデンス手法の束縛によって患者と接する日頃の臨床の場で何も言えなくなっていく30)ことのほうが怖くもある。村上陽一郎の言葉を借りれば,精神科医には科学者もいれば,臨床家もあり得るということである。一人の臨床家としてこの場を借りて,誰もが感じている統合失調症の減少と軽症化について言及し,今後の疫学調査など研究にも波及することを望むところである。 最近の臨床現場で,統合失調症の初発患者との出会いが四半世紀前に比して少なくなり,また軽症化していると,多くの精神科医が感じているのは事実である。これは,気分障害や,不安障害,発達障害,認知症の患者に接することが増え,統合失調症とのかかわりの頻度が相対的に減ったこともある。また,入院の必要とされるような精神病症状の目立つケースについては,行政区域内で規定された病院に受診となるようなルートの確立によって一極化が生じ,一般精神科医のもとに来なくなったこともあろう。こうした最近の流れが,減少と軽症化のイメージをより強めているとも言える。ここでは,一元的な見方でなく,さまざまな視点から統合失調症の減少と軽症化について考察してみたい。
2 0 0 0 透明中隔腔およびヴェルガ腔を有する症例の精神症状についで
- 著者
- 宮永 和夫 川原 伸夫 高橋 滋 尾内 武志 森 弘文 横田 正夫
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.43-49, 1985-01-15
抄録 CTスキャンを施行した群馬大学医学部附属病院受診者を調査し,透明中隔腔及びヴェルガ腔を有する症例を抽出し検討した結果,以下のような知見を得た。 (1)全科9,408例(男5,104例,女4,304例)中,男29例,女16例の計45例(0.47%)にこれらの腔を認めた。なお男性に女性より多く認められた。 (2)45症例は,透明中隔腔のみ35例(78%),透明中隔腔及びヴェルガ腔9例(20%),ヴェルガ腔のみ1例(2%)に分けられた。 (3)45例には,疾患別にみると,てんかん,頭痛,発育障害,精神分裂性障害などが多く認められた。 (4)内因性精神病,すなわち精神分裂性障害と感情障害においては約5%の頻度でこれらの腔が認められた。 (5)これらの腔と精神分裂病症状の関係は,1)症状形成に関与する,あるいは 2)単なる合併であるというつの可能性が指摘された。
2 0 0 0 大麻精神病と大麻乱用後に発症した統合失調症の違い
- 著者
- 新川 祐利 梅津 寛 大島 健一 岡崎 祐士
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.9, pp.881-888, 2012-09-15
抄録 大麻乱用後に幻覚妄想状態を呈した2症例を報告した。症例1は大麻精神病,症例2は大麻乱用の経験がある統合失調症と診断し,両者の違いを考察した。急性期症状は類似点が多いが,本症例の大麻精神病は幻覚妄想に対し恐怖や緊張を伴わず,妄想内容が了解可能であることが統合失調症と異なっていた。大麻精神病の経過では,大麻による無動機症候群を認め,意欲減退などが原因で社会機能が低下し,統合失調症の陰性症状と類似した。しかし,対人関係の障害や認知機能障害は認めず,治療により社会機能が病前の状態まで回復したことが異なっていた。大麻乱用が統合失調症を惹起する可能性が推察された。
2 0 0 0 頭部外傷後に二次性躁状態を呈した1例
身体疾患による症状性をはじめ脳卒中や頭部外傷などの脳損傷による脳器質性の二次性躁状態は多くはないが,対応が困難なことから,近年リエゾン精神医学の重要な状態像の1つとされている5)。このうち頭部外傷による二次性躁状態の発生頻度は,Jorgeら3)によると9%とそれほど稀でないとされているが,現場からの精神科医への依頼が少ないためか,その報告例は散見するにすぎない。今回我々は,交通事故による頭部外傷(脳振盪)で救命救急センターに搬送された後に,躁状態を呈した1例を経験したので報告する。
2 0 0 0 祈祷性精神症(病)
諸言 祈祷性精神症は,東京慈恵会医科大学初代主任教授森田正馬が,「余の所謂祈祷性精神症に就いて」(1915(大正4)年,「神経学雑誌」第3巻2号)によって世界で最初に報告した。その論文の中で,迷信,まじない,祈祷などに基づいて発症する心因性でありながら精神病性症状を呈する疾患群に対して名づけた呼称である1)。その論文では「祈祷性精神症」とされ,後に名称は祈祷性精神病と改められている。心因性である疾患に病は好ましくなく,さらに少なくとも,当時宗教的行為に際して生じる心身における症状を「病」と表現することはできなかったと思われる。 現在のわが国の精神医学の教科書にもあまり記載されなくなっている。操作的診断基準を基にした疾患分類が普及した結果,このような原因による呼称は過去のものとなったこと,また実際に,このような病態に我々が遭遇することがまれになってきたのも事実である。一方,現代では,経過中の病態の変化が激しく,症候のみの分類では疾患の本質がどこにあり,治療をどのように進めるべきか明確になりにくくなっている。その意味では,伝統的な疾患概念ではあるが,もう一度原因論に立ち戻って精神疾患を考える意義を伝えてくれているといえるかもしれない。
2 0 0 0 我亡霊を見たり
新年早々亡霊とは縁起でもないが,わが国の精神医学はここしばらく亡霊に崇られて悩んでいる状態であるし,私自身その運命をひしひしと感じているので,このような題を記すことを御容赦いただきたい。私は昨年7月31日信州大学に20年15日勤めて不恰好な退職をしたが,それは20年前の私の患者の亡霊がこの大学の紛争の種となって崇りをしたせいであったからである。その後,昔信州へ来て顕微鏡一つ,本一冊なかった頃この大学の一回生二回生に講義するために患者を借りた病院へアルバイトに行っているが,そういう亡霊がまだそのまま居るのである。そのうえ悪いことに昔新しいclientとして私が治療して治ったと思った患者たちが亡霊となってこの病院に沈澱しており,地獄の声でまだ私の名を覚えていて呼びかけてくる。20年間社会精神医学的に及ばずながら世話をして社会復帰させていた患者がとうとう破綻をきたして,昔の美しい面影はどこへやら,グロテスクなPraecox-GefuhlのPhysiognomieをもってこの期にとばかり眼前に化けて出てくる。 大学にいたころはもうこのようなVerblodung,Dementia praecoxは卒業した時代になったと妄想していた。私は,ことに若い人々の間で,あるいは新しい見解の人々の間でnotoriousな,Kraepelinの本が好きで,あの本の8版を欲張りにも2部所持していて,自宅と勤め先とに置いておき,いつもひっくりかえしては見ているので,この亡霊のことはよく承知しており,ソビエトの人々がクレペリンの見方を今もなお固持しているのを尊敬と軽蔑の混ったambivalentな気持で眺めていたにもかかわらず,実際この多くの亡霊達と面と向かってauseinandersetzenしなければならない立場に至ると,精神医学の歴戦30余年の勇士もぎょっとしてたじろがざるをえないのである。
2 0 0 0 統合失調症認知機能簡易評価尺度日本語版(BACS-J)
- 著者
- 兼田 康宏 住吉 太幹 中込 和幸 沼田 周助 田中 恒彦 上岡 義典 大森 哲郎 Richard S.E. Keefe
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- pp.913-917, 2008-09-15
はじめに 統合失調症患者の社会機能に及ぼす影響に関しては,その中核症状ともいえる認知機能障害が精神症状以上に重要な要因であると考えられつつある4,5)。統合失調症の認知機能障害は広範囲な領域に及び,なかでも注意・遂行機能・記憶・言語機能・運動機能の領域が注目されている。認知機能の評価においては,認知の各領域を評価するいくつかの検査を目的に応じて組み合わせて(神経心理学的テストバッテリー,NTB)行われている。しかしながら,NTBは通常専門的かつ高価で時間を要する。そこで,統合失調症患者の認知機能を幅広く簡便に評価し得る尺度は日常臨床および研究において大変有用であろう。統合失調症認知機能簡易評価尺度(The Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia;BACS)は最近Keefeら7)によって開発されたもので,言語性記憶,ワーキング・メモリ(作動記憶),運動機能,注意,言語流暢性,および遂行機能を評価する6つの検査で構成され,所要時間約30分と実用的な認知機能評価尺度である。我々はその有用性に着目し,臨床応用のために,原著者の許可を得たうえで,日本語版(BACS-J)を作成したのでここに紹介する。日本語訳にあたっては,まず2名が独立して仮日本語訳を作成し,その後訳者2名に第3者を加えた計3名で協議したうえで日本語訳を作成し,さらにその後,原文を知らない者2名に独立して日本語訳のback-translationを行わせ,この英文のそれぞれを原著者に確認してもらった。なお,BACS-Jの信頼性,妥当性については,すでに検討されている6)。
2 0 0 0 アスペルガー障害における共感指数(EQ)とシステム化指数(SQ)
- 著者
- 池田 あゆみ 谷 将之 金井 智恵子 髙山 悠子 大野 泰正 太田 晴久 山縣 文 山田 貴志 渡部 洋実 橋本 龍一郎 岡島 由佳 岩波 明 加藤 進昌
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- pp.133-141, 2014-02-15
抄録 成人アスペルガー障害(AS)を対象に共感指数(EQ)およびシステム化指数(SQ)を含む自閉症スペクトラム障害関連の質問紙を施行し,ASの臨床的特徴と質問紙の有用性を検討した。健常群と比べAS群でEQが有意に低く,SQが有意に高かった。EQとSQに関してAS群の男女間に有意差はなく,ともに超男性脳傾向を示した。AS群においてのみEQと自閉症スペクトラム指数(AQ),SQとAQ,EQと対人的反応性指数(IRI)の相関を認めたが,EQとSQの相関,これらとパーソナリティ尺度との相関は認めなかった。EQおよびSQは,ASの低い共感能と高いシステム化能を反映する指標であり,パーソナリティに影響を受けないため,成人のASを診断する有用な指標となり得る。
2 0 0 0 いわゆる境界状態について
Ⅰ 境界状態または境界例の概念はKnight8)によってほぼ確立されたとはいえ,境界状態あるいはこれに相当する病態に関する文献を通覧すると,著者達の使用する用語もその概念もさまざまであって,極端なことをいえば「誰それのいう何々」という言い方をしないと話し手と聞き手の間に微妙な喰いちがいが起こりかねない。例えば,HochとPolatin5)の「仮性神経症型分裂病」は広義に境界状態に包含される病態であるが,これと完全に一致する記述はDouglas2)の「境界線分裂病」(borderline schizophrenia)のみである。Shenken12)は「境界状態」という用語を用い,その記述の大部分はHochとPolatinに準拠しているが,しかしさらに妄想反応と仮性神経症型うつ病をも含むものとしている。一方でSchmideberg11)は「境界患者」を定義するさい仮性神経症型分裂病は除外すると明言している。また最近Grinkerら4)はそのモノグラフで「境界線症状群」(borderline syndrome)という用語を用いたが,その類型として中核群,神経症的境界線群,精神病的境界線群,“as if”群をあげており,その包含する対象は広い,などなどのごとくである。第1表には諸家により用いられた用語をあげた。 著者らによる境界例概念とその強調する点の相違はそれぞれの属する学派・理論によるほか,彼らが症例を取り扱う施設の性格ならびに患者層の偏りに基づくこともあろう。だがそれらのほかにより根本的な根拠が考えられる。そのひとつは,ある症例を境界状態と診断する場合,神経症的ならびに分裂病的な二面の特性を認めつつもそのいずれにも属せしめえぬという否定的・除外的な態度もあり,そこではいかほど分裂病的(または神経症的)であり,かついかほど分裂病的(または神経症的)でないかという判断がなされていることである。「境界例という診断は患者の状態に関してではなく,精神科医の不決断・不確かさに関する情報を伝えている」(Knight)とか「診断の困難さを現わす用語」(井村)6)のごとき表現は単なる警句とはいえない。この診断の困難さあるいは不決断の幅,すなわち「精神病理学的スペクトル上の境界帯域」の幅は診断する側の抱く分裂病概念の幅に相応して狭くも広くもなる理である。あのGlover3)やZilboorg16)はこの不決断を認めぬ立場といえよう。もちろん,多くの人は境界例を広く分裂圏内に含まれる病態と認めてはいるが,万人に承認される境界例独自の病態特異的な所見が乏しい以上,不決断の幅は医師の主観に従って動揺せざるをえない。分裂病の診断基準にかかわる問題である。
2 0 0 0 妻の妄想に感応したパーキンソン病の初老期男性の1例
抄録 妻の妄想に感応したパーキンソン病の初老期男性例を報告した。患者はX-11年(53歳)にパーキンソン病を発症した。X-6年(58歳),妻は「電磁波で攻撃され体がしびれる」という身体的被影響体験や「電磁波で悪口を送ってくる」という幻聴とそれらに基づく被害妄想を呈し,翌年,患者は妻の被害妄想に感応した。X年(64歳),2人は当院を初診し別々の病棟に医療保護入院となった。患者には被害妄想とともに幻聴と身体的被影響体験の感応が疑われる訴えもあった。妻が統合失調症を発症した後,患者は妻の症状に感応したと考えられたが,パーキンソン病による精神病症状の鑑別を要した。入院後は抗精神病薬を投与せず,妻からの分離のみで「電磁波」の訴えは消失したため,感応精神病と診断された。パーキンソン病が感応の成立に影響を与えた要因として,心理社会的要因には社会的孤立と妻優位の関係性の強化,脳器質的要因には軽度認知障害による現実検討力の低下が考えられた。