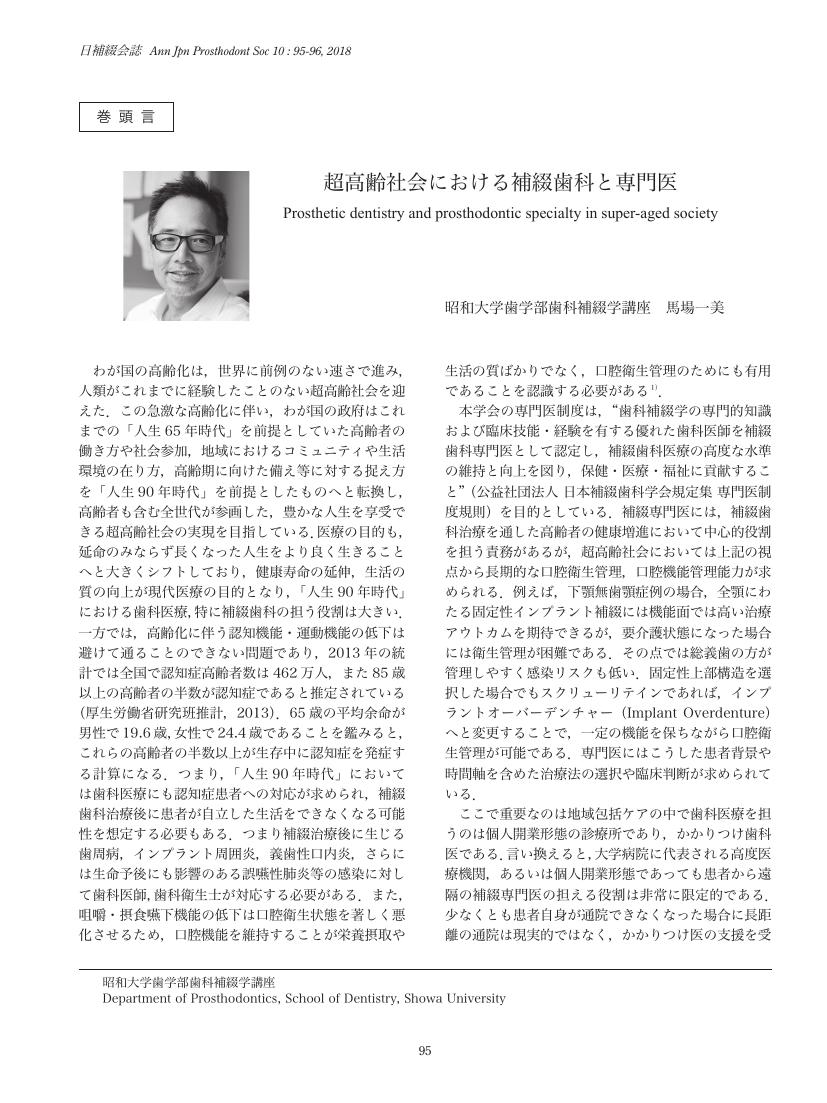1 0 0 0 OA 摂食・嚥下障害への対応 ―摂食・嚥下障害の評価と訓練―
- 著者
- 戸原 玄 阿部 仁子 中山 渕利 植田 耕一郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.265-271, 2013 (Released:2013-11-06)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
日本では要介護高齢者が増加しているため,誤嚥性肺炎の予防が重要である.誤嚥性肺炎は摂食・嚥下障害により引き起こされるため,患者の食べる機能を正しく評価した対応が重要である.訪問診療で利用可能な評価法にはスクリーニングテストと嚥下内視鏡検査があり,嚥下内視鏡検査は近年小型化が図られている.咀嚼中には食塊が咽頭に送り込まれるため相対的に嚥下反射が遅延するが,症例によっては噛み方を工夫することで嚥下反射遅延を防ぐことができる可能性がある.歯科的な対応のうち特殊な補綴物には舌接触補助床および軟口蓋挙上装置がある.また,新しい訓練方法として開口訓練により舌骨上筋群を鍛えて嚥下機能を改善する方法がある.
1 0 0 0 OA ノンメタルクラスプデンチャーの現状
- 著者
- 谷田部 優
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.32-37, 2019 (Released:2019-01-26)
- 参考文献数
- 34
近年,部分床義歯による欠損補綴においても審美性への配慮が大切になっており,ノンメタルクラスプデンチャーを目にする機会も増えてきた.日本補綴歯科学会は,ポジションペーパーでノンメタルクラスプデンチャーを製作する際の臨床指針を示しているが,未だに不明な点も多く,装着後の対応に苦慮する場合も少なくない.本稿では,ノンメタルクラスプデンチャーで用いられる材料を整理し,レジンクラスプが歯周組織に与える影響,維持機構や審美性への配慮について,現時点でのエビデンスと見解を整理する.また,基本的な設計例を通して臨床上注意すべき点について述べる.
1 0 0 0 OA 歯間乳頭の安定を目指して
- 著者
- 六人部 慶彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.4, pp.376-380, 2016 (Released:2016-11-09)
- 参考文献数
- 10
歯間乳頭は,歯科医師が補綴処置を行ううえで,形態をコントロールできる軟組織の一つであり,再建するためには歯周組織の十分な診査・診断が必要である.下部鼓形空隙にブラックスペースが存在し審美性を損ねている場合でも,補綴を前提とする際には,隣接面歯頸部のフィニッシュラインの設定位置と修復物の形態を症例に応じてコントロールすることにより,ある程度歯間乳頭を再建させることができる.特に前歯部においては,食物の停滞や発音のような機能的な側面に加えて審美性が最優先されるため,下部鼓形空隙のブラックスペースは許容されない傾向にあり,世界的な潮流として歯間乳頭を保存あるいは再建することの必要性がクローズアップされている.その術式も外科的1,2),矯正的3,4),補綴的5,6)アプローチが報告されている.ここでは,天然歯形態から学ぶ歯間乳頭再建のために修復物に与えるべき形態,フィニッシュラインの設定位置などこれら診断の目安となる歯間乳頭の存在に影響を及ぼす要因7)について考察したい.
1 0 0 0 OA 補綴歯科治療病名システムの信頼性と妥当性の検討
- 著者
- 松香 芳三 萩原 芳幸 玉置 勝司 竹内 久裕 藤澤 政紀 小野 高裕 築山 能大 永尾 寛 津賀 一弘 會田 英紀 近藤 尚知 笛木 賢治 塚崎 弘明 石橋 寛二 藤井 重壽 平井 敏博 佐々木 啓一 矢谷 博文 五十嵐 順正 佐藤 裕二 市川 哲雄 松村 英雄 山森 徹雄 窪木 拓男 馬場 一美 古谷野 潔
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.281-290, 2013 (Released:2013-11-06)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 2 1
目的:(社)日本補綴歯科学会は病態とその発現機序の把握に基づく適切な補綴歯科治療を国民に提供するために,補綴歯科治療における新たな病名システムを提案した.これは患者に生じている「障害」を病名の基本とし,この障害を引き起こしている「要因」を併記して病名システムとするものであり,「A(要因)によるB(障害)」を病名システムの基本的な表現法としている.本研究の目的は考案した方法に従って決定した補綴歯科治療における病名の信頼性と妥当性を検討することである.方法:模擬患者カルテを作成し,(社)日本補綴歯科学会診療ガイドライン委員会で模範解答としての病名(以下,模範病名)を決定した.その後,合計50 名の評価者(日本補綴歯科学会専門医(以下,補綴歯科専門医)ならびに大学病院研修歯科医(以下,研修医))に診断をしてもらい,評価者間における病名の一致度(信頼性)ならびに(社)日本補綴歯科学会診療ガイドライン委員会による模範病名との一致度(妥当性)を検討した.結果:評価者間の一致度を検討するための算出したKrippendorff’s αは全体では0.378,補綴歯科専門医では0.370,研修医では0.401 であった.Krippendorff’s αは模範病名との一致度の高い上位10 名の評価者(補綴歯科専門医:3 名,研修医:7 名)では0.524,上位2 名の評価者(補綴歯科専門医:1 名,研修医:1 名)では0.648 と上昇した.日常的に頻繁に遭遇する病名に関しては模範病名との一致度が高かったが,日常的に遭遇しない病名は模範病名との一致度は低い状況であった.さらに,模範病名との一致度とアンケート回答時間や診療経験年数の関連性を検討したところ,相関関係はみられなかった.結論:全評価者間の一致度を指標とした本病名システムの信頼性は高くはなかったが,模範病名との一致度の高い評価者間では一致度が高かった.日常的に遭遇する補綴関連病名については模範病名との一致度が高かった.以上から(公社)日本補綴歯科学会の新しい病名システムは臨床上十分な信頼性と妥当性を有することが示唆された.
1 0 0 0 OA 睡眠医学は睡眠時ブラキシズムの診断・治療に必要か?
- 著者
- 加藤 隆史 原木 真吾 辻阪 亮子 東山 亮 矢谷 博文
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.145-152, 2016 (Released:2016-05-26)
- 参考文献数
- 56
睡眠時ブラキシズムは歯科医療の中でも特に関心が高い睡眠関連疾患の一つである.睡眠時ブラキシズムの研究が進むにつれ,歯科医学的な常識だけでSBの診断や臨床の正当性を説明することができない様々な実態が明らかとなってきた.したがって,睡眠時ブラキシズムの診断や治療の新しい展開を切り開くためには,歯科臨床問題中心型の診断や治療だけでなく,病態生理学的な側面を勘案した医学的な診断・治療論理が求められると考えられる.本稿では,睡眠医学領域の視点を踏まえた診断の重要性を提案し概説する.
1 0 0 0 OA QOLの向上を求め患者の強い訴えに応じて無口蓋全部床義歯を製作した1症例
- 著者
- 吉村 万由子
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.271-274, 2017 (Released:2017-07-23)
- 参考文献数
- 2
症例の概要:患者は60歳女性.歯科治療に対する恐怖および歯の挺出による審美不良と義歯不適合による咀嚼困難を訴えて来院した.挺出歯の抜歯および上下顎全部床義歯を製作することとした.患者の強い訴えに応じて無口蓋全部床義歯を製作し,良好な経過とともにQOLの向上も得られた.考察:義歯補綴は,咬合,咀嚼,嚥下などの機能回復に留まらず,審美性や快適性などの主観的な満足獲得も重要であり,本症例は患者の要求を重視して治療を行ったことが,高い満足度に繋がったと考えられる.結論:義歯の装着感に不満を持ち,通常形態の義歯を受け入れられない患者に対し,顎堤の異常吸収,疼痛や咀嚼障害が起こらないよう配慮したうえで,患者の要望を考慮した義歯形態としたことで良好な結果を得た.
1 0 0 0 OA 松井論文の『インプラント周囲の角化歯肉』と弘岡論文の『歯周インプラント補綴』について
- 著者
- 中居 伸行
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.3, pp.196-201, 2018 (Released:2018-08-02)
- 参考文献数
- 20
『インプラント周囲の角化歯肉』と『歯周インプラント補綴』についてcritical discussionを試みた.前者では科学的根拠に基づく慎重な治療介入が,後者では慎重な補綴設計が肝要であると思われた.『スカンジナビア型』では「必要性に基づくこと」を介入原則としているが,『米国型』では,術者の主体的意志がさらにそこに添加されているように感じられた,両者の取り組み方の違いは,臨床介入の際の判断基準Shouldしたほうがいいこと,Canしてもいいこと,Not have toしなくてもいいこと,Shouldn’tしないほうがいいことに関する視座の違いから生じているのだろう.
1 0 0 0 OA 部分床義歯装着後の口腔内管理
- 著者
- 石上 友彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.20-25, 2019 (Released:2019-01-26)
- 参考文献数
- 8
種々異なる義歯装着後の口腔内ですが,大切なのは義歯の安定と残存歯の保全と咬合のバランスが義歯装着当初を維持し続けるように口腔内の管理を行う事です.義歯の支持力,咀嚼に対する把持力そして義歯全体としての維持力のバランス,さらに,患者さんの義歯に対する要求度の違い,患者さんと歯科医師の人間関係等,種々の関係が相乗的に義歯の術後経過に影響を与えます.つまり,これら種々の関係に統合した補綴歯科治療が患者さんの生涯の伴侶として望まれます.そして,どのような治療を行うにしても種々のバランスを考えた口腔内管理が必要不可欠です.
1 0 0 0 OA 超高齢社会がかかりつけ歯科医に求めること
- 著者
- 須貝 昭弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.111-115, 2019 (Released:2019-05-02)
「来院する患者さんの口腔内を責任を持って一生面倒みよう」と開業して30年が経過した.今となってはその「一生」は自分の一生であって患者の一生ではないことがわかる.永く来院していた高齢の患者の中には気がつくといつの間にか来院が途絶えてしまい,最期までかかわれていないことも多い.超高齢社会になり口腔機能を維持することが健康寿命の延伸につながることが注目され,通院できなくなっても歯科治療を必要としている高齢者は数多くいて,かかりつけ歯科医として最期までかかわることが求められるようになってきている.かかりつけ歯科医として超高齢社会で何が求められているのかを考えてみたい.
1 0 0 0 OA 3Dプリンターを利用した新しいロストワックス鋳造法と従来法との鋳造性に関する比較研究
- 著者
- 髙田 朝 金髙 弘恭 布目 祥子 加藤 裕光 菊池 雅彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.242-250, 2017 (Released:2017-07-23)
- 参考文献数
- 45
目的:液槽光重合方式の3Dプリンターを利用した新しいロストワックス鋳造法の臨床的有用性を評価することを目的とし,鋳造体の寸法変化率および表面粗さを測定し,従来法との比較検討を行った.方法:原型サンプルは3Dプリンターを利用して2種の3Dプリンター用レジンで製作した.また,インレーワックスとパターン用レジンでも同形状の原型サンプルを製作した.鋳型の製作条件は,埋没材と加熱条件を組み合わせて6条件とした.鋳造体の寸法変化率は,円柱の直径を鋳造前後に測定して評価した.鋳造体の表面粗さは,鋳造体表面を表面粗さ計およびSEMを使用して定性的,定量的に評価した.結果:鋳造体の寸法変化率および表面粗さともに,3Dプリンターを利用した新しいロストワックス鋳造法による製作物は従来法のものと比較し,条件により大きな値をとることもあったものの,一定の条件下においては,同等の優れた値を示すことが確認された.結論:液槽光重合方式の3Dプリンターを利用した新しいロストワックス鋳造法は,適切な条件選択により,寸法変化率と表面粗さともに従来法とほぼ同等とすることが可能であり,臨床上有用であることが示唆された.
1 0 0 0 OA 歯冠修復物と固定性補綴装置の接着と合着
- 著者
- 小峰 太 松村 英雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.4, pp.343-352, 2012-10-10 (Released:2012-11-14)
- 参考文献数
- 65
- 被引用文献数
- 2
ここ10年ほどの間にレジン系装着材料で修復物,固定性補綴装置を接着する症例が増加している.この傾向は,ジルコニアセラミック修復システムの導入と,歯質,セラミックス,合金の接着に有効な種々の機能性モノマー,重合開始剤の開発によるところが大きい.本稿では,最近普及しつつあるセラミックスおよび金属製修復物と補綴装置の接着システムについて概観し,合着と接着の使い分けについても解説する.
1 0 0 0 OA 補綴歯科領域における顎関節症治療法の歴史的変遷
- 著者
- 矢谷 博文
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.3, pp.229-245, 2012 (Released:2012-09-21)
- 参考文献数
- 180
- 被引用文献数
- 1
本総説は,顎関節症(TMD)の治療法,特に補綴歯科領域のおける保存療法が,歴史とともにどのように変遷を重ねてきたかについて病因論の変遷とともに歴史を追って詳述した.膨大な臨床研究が積み重ねられた結果,現在では,1)TMDは臨床症状の類似したいくつかの病態からなる包括的名称であること,2)生物精神社会的モデルを発症機序の基本とした多因子の病態であること,3)その生物精神社会的モデルの枠の中で各病態の治療や長期的な管理がなされる必要があること,4)各病態とも症状の自然消退の期待できる(self-limiting)疾患であるゆえ,まず可逆的な保存治療を優先させること,が共通の理解となった.今後は,TMDの各種保存療法の治療効果を病態別に明らかにするために,治療の結果を測る方法の標準化が強く求められる.
- 著者
- 疋田 一洋 舞田 健夫 川上 智史 池田 和博 齊藤 正人 田村 誠 小西 ゆみ子 神成 克映 内山 洋一 平井 敏博
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 = Annals of Japan Prosthodontic Society (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.64-70, 2009-01-10
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 2 3
<B>目的:</B>試作したCAD/CAM用ハイブリッドレジンブロックの臨床的な有効性を評価することを目的とした.<br><B>方法:</B>ハイブリッド型硬質レジンを加圧,加熱重合し,歯科用CAD/CAMシステムの加工用ブロックサイズに成型加工した.患者36名(女性29名,男性7名)の小臼歯43本,大臼歯8本,合計51本に対しハイブリッドレジンブロックから製作したジャケットクラウンを製作し,6ヶ月から12ヶ月後,平均9.6ヶ月における臨床的評価を行った.評価項目は,辺縁適合性,表面性状,咬耗,破折,クラック,着色,プラークの付着,周囲歯肉の炎症,対合歯の咬耗の9項目とした.<br><B>結果:</B>15.7%(8症例)において,咬合面の一部に光沢の消失が認められ,5.9%(3症例)において,クラウン表面の一部に着色が認められた.また,装着後1~3ヶ月で4症例について脱離が認められたが,クラウンのクラックや破折は認められず,再装着を行い,その後は問題なく経過している.他の評価項目については装着時と変化は認められなかった.<br><B>結論:</B>ハイブリッドレジンブロックを材料に歯科用CAD/CAMシステムを用いて製作したジャケットクラウン51本を装着し,平均9.6カ月の予後観察を行ったところ,一部に光沢の消失と着色が認められたが,他には問題はなく,クラウンの材料として有効であることが示唆された.
1 0 0 0 OA 補綴装置や歯の延命に向けて,顎口腔の力はコントロールできるだろうか?
- 著者
- 服部 佳功 田中 恭恵
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.4, pp.351-356, 2015 (Released:2015-10-22)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 超高齢社会における補綴歯科と専門医
- 著者
- 馬場 一美
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.95-96, 2018 (Released:2018-05-13)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 各種市販ノンクラスプデンチャー材料の曲げ特性
- 著者
- 廣瀬 知二
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 = Annals of Japan Prosthodontic Society (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.272-280, 2013-07-10
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 1
<b>目的:</b>素材の異なる各種市販ノンクラスプデンチャー材料の特徴を,曲げ特性の面から明らかにする.<br><b>方法:</b>ノンクラスプデンチャー材料(ポリアミド系樹脂:ルシトーンFRS,ポリカーボネート系樹脂:レイニング樹脂,ポリエステル系樹脂:エステショット,アクリル系樹脂:アクリトーン),加熱重合型アクリル樹脂(アクロン)を対象に,成形したままの試験片(乾燥)と30日間水中浸漬試験片(浸漬)の3点曲げ試験を行った.応力-ひずみ曲線を作成し,曲げ強さ,曲げ弾性係数,0.05% 耐力を算出した.得られたデータについて各材料の比較,材料ごとの乾燥と浸漬の比較を行った.<br><b>結果:</b>応力-ひずみ曲線は,アクロンが脆性材料の特徴を示すのに対し,ノンクラスプデンチャー材料はいずれも靱性材料の特徴を示した.曲げ強さはレイニング樹脂を除き,アクロンに比べ有意に小さい値を示した.曲げ弾性係数はいずれのノンクラスプデンチャー材料も,アクロンに比較して有意に小さい値を示した.0.05% 耐力はエステショットが他のノンクラスプデンチャー材料に比較して有意に大きい値を示した.アクリトーンの曲げ強さ,曲げ弾性係数,0.05% 耐力は浸漬が乾燥に比べ有意に小さい値を示した.<br><b>結論:</b>各材料の曲げ特性は素材となる樹脂の性質に基づくことが示唆された.ノンクラスプデンチャーの症例選択,義歯設計には材料の基礎的物性を把握した上での十分な配慮が必要である.
1 0 0 0 OA 地域高齢者の20歯以上保有と軽度認知機能障害の関連:1年の前向きコホート研究
- 著者
- 西村 一将 大井 孝 高津 匡樹 服部 佳功 坪井 明人 菊池 雅彦 大森 芳 寶澤 篤 辻 一郎 渡邉 誠
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.126-134, 2011-04-10 (Released:2011-04-21)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 2
目的:地域高齢者を対象に,20歯以上の保有と1年間での軽度認知機能障害(Mild Cognitive Impairment: MCI)発現との関連を検討した.方法:70歳以上の地域高齢者に対して心身の総合機能評価を2年にわたり実施し,1年目のベースライン調査時にMCIを認めず,かつ2年目の追跡調査が可能であった557名(女性310名)を分析対象とした.認知機能の評価にはMini-Mental State Examination(MMSE)を用い,スコアが26点以上を正常,25点以下をMCIとした.現在歯数については歯冠を残す20本以上の歯の有無について調査した.MCI発現との関連が疑われるその他の項目として,年齢,Body Mass Index,脳卒中既往,心疾患既往,高血圧,糖尿病,喫煙,飲酒,抑うつ傾向,学歴,配偶者の有無,ソーシャルサポートの状態,身体活動度,主観的健康感について調査した.結果:多重ロジスティック回帰分析を用いてベースライン調査から1年後のMCI発現の規定因子を検索した結果,男性において20歯以上の保有が,他の因子と独立して認知機能低下発現に対し有意なオッズ比の低値(オッズ比:0.19,95%信頼区間:0.04-0.82)を示した.結論:現在歯を20歯以上保有することは,咀嚼機能の維持のみならず,高齢期における認知機能の維持においても優位性を持つ可能性が示唆された.
1 0 0 0 CAD/CAM技術を応用した全部床義歯製作法
- 著者
- 金澤 学
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 = Annals of Japan Prosthodontic Society (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.126-129, 2013-04-10
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2
現在の全部床義歯製作法には,臨床・技工操作ともに非常に煩雑で熟練した手技を要する.この問題点を解決するために,われわれはCAD/CAM技術を応用した全部床義歯製作法を考案した.この手法では,改良した旧義歯あるいはパイロットデンチャーをCTによりスキャンし,粘膜面と顎間関係を三次元データとしてPCに取り込む.CADソフトウェア上にて,新しい義歯をデザインした後,顔貌シミュレーションにより新義歯装着時の顔貌の確認を行う.必要があれば,Rapid Prototypingを用いて試適用義歯を作製し,義歯試適を行う.これにより,問題がなければ,マシニングセンタによりアクリルブロックを義歯床形態に切削加工し,人工歯を接着し最終義歯を完成する.
1 0 0 0 OA インプラント治療における光学印象の活用
- 著者
- 田中 晋平 高場 雅之 深澤 翔太 渡邊 理平 夏堀 礼二 近藤 尚知 馬場 一美
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.23-31, 2018 (Released:2018-05-13)
- 参考文献数
- 9
インプラント治療はCT(Computed Tomography)のDICOM(Digital Imaging and COmmunication in Medicine)データがデジタルデータであることから,デジタル・デンティストリーと親和性が高く,比較的早期からデジタル技術が導入されてきた.シミュレーションソフトウェアやガイドサージャリーやナビゲーションシステムによる安全な手術などはもとより,今日ではCAD/CAMを用いたインプラント上部構造が広く普及した. 光学印象の普及はデジタルワークフローの枠組みを技工のみでなく,臨床手技にまで拡大するもので,すでに一部のシステムにおいては,光学印象からインプラント上部構造製作までが系統的に整備され,フルデジタルワークフローによるトップダウントリートメントは,完成形に近づいたといえよう. 一方で,光学印象に関連したデジタルワークフローは従来のワークフローと比較して柔軟性に劣る,従来のワークフローで得られる最高レベルの精度が担保されていない,など幾つかの制限があることも事実である.本稿では,インプラント治療における光学印象の活用の変遷と現状を提示するとともに,今後の展開について,現在直面している技術的限界に焦点を当てながら考察する.
1 0 0 0 OA ガラスファイバーポストの表面処理法に関する微小引張り試験による検討
- 著者
- 青崎 有美
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.3, pp.238-247, 2011-07-10 (Released:2011-09-01)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 1
目的:広く用いられているガラスファイバーポストについて,口腔内での機能を想定した接着耐久性試験を行い,接着耐久性のある最適な表面処理法を明らかにする.方法:表面処理なしと各種表面処理;シラン処理(機能性モノマーなし),有機溶媒+シラン処理(機能性モノマーなし),シラン処理(機能性モノマーあり),酸処理+シラン処理(機能性モノマーあり),酸処理+シラン処理を含むボンディング剤の 6処理について検討した.処理を行ったポストとデュアルキュア型支台築造用コンポジットレジンとの複合体試料を製作し,大気中・水中浸漬・繰り返し荷重負荷(水中)の3種類の実験条件について微小引張り試験を行い,接着強さの測定および破断様相を検討した.結果:未処理を含む 6種類の表面処理のうち,最も厳しい実験条件である水中での繰り返し荷重試験後に最も高い接着強さを示したのは,酸処理後に機能性モノマーを含んだシランカップリング剤で処理した条件であった.ただし,機能性モノマーを含まないシランカップリング剤であっても,有機溶媒による前処理を行うことによって,接着強さおよび耐久性は著しく向上した.結論:未処理を含む 6種類の表面処理条件のうち 4種類において,接着強さが向上した.そのうち最も適切な表面処理法は,酸処理後に機能性モノマーを含むシランカップリング剤で処理する方法であった.