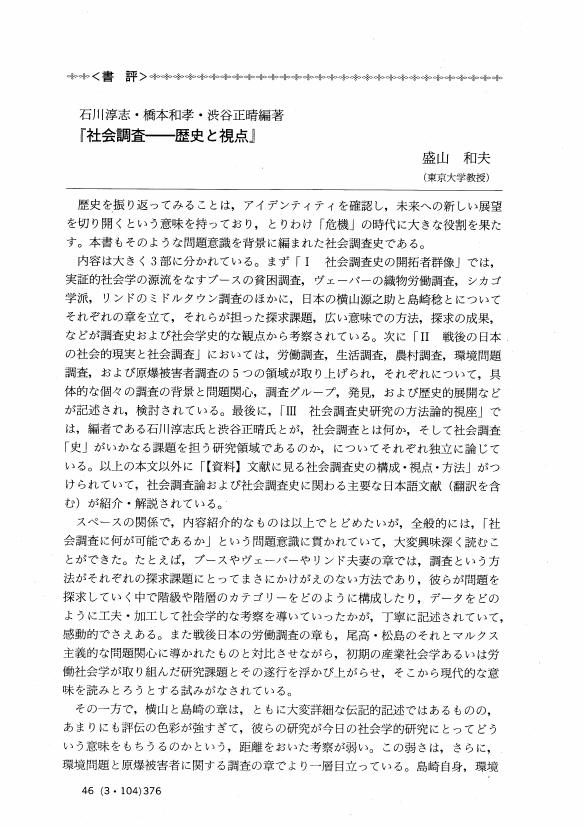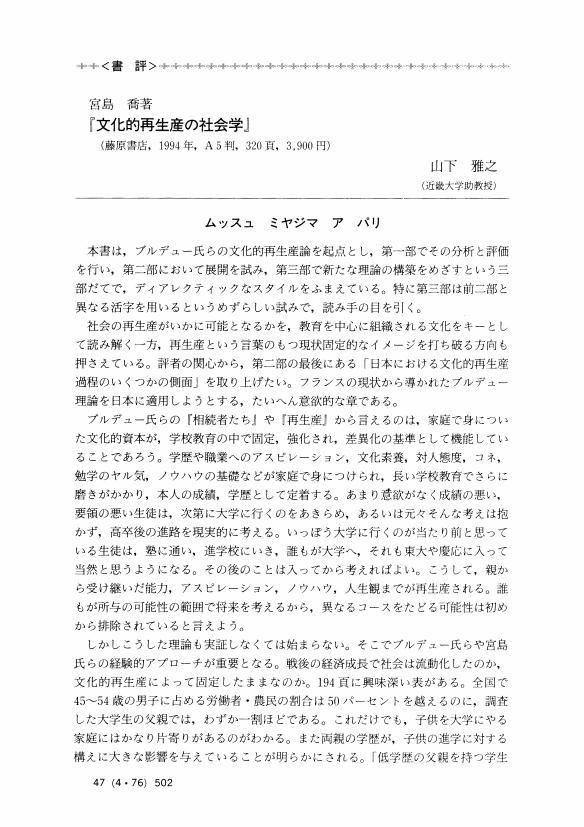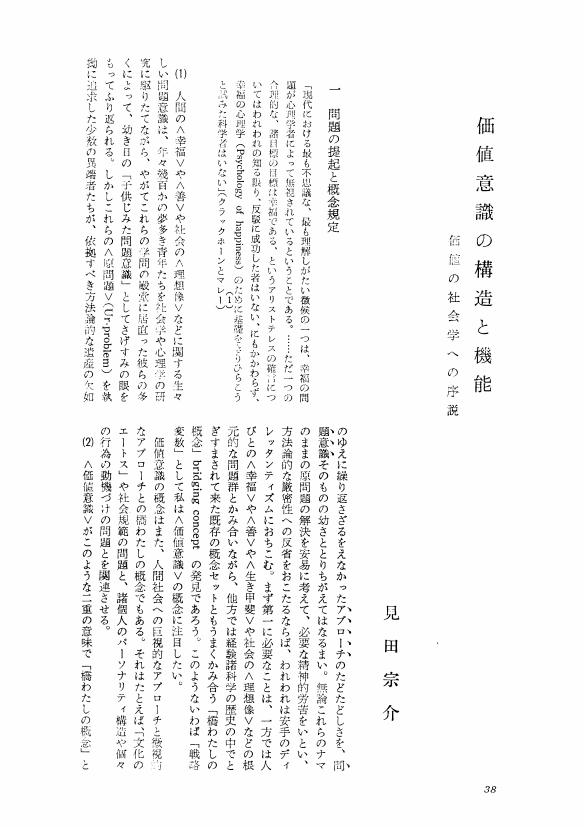3 0 0 0 OA テーマ別研究動向 (犯罪)
3 0 0 0 OA 石川淳志・橋本和孝・渋谷正晴編著『社会調査-歴史と視点』
- 著者
- 盛山 和夫
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.376-377, 1995-12-30 (Released:2009-10-19)
3 0 0 0 OA 社會人類學者との會見記
- 著者
- 古野 清人
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.103-112, 1951-08-30 (Released:2009-11-11)
3 0 0 0 <書評> 福武・日高・高橋編「社会学辞典」
3 0 0 0 OA 夫婦生活の幸福度の豫測と測定
- 著者
- 執行 嵐
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.3, pp.61-91, 1953-04-30 (Released:2009-11-11)
- 参考文献数
- 101
Family stability is an important concern in modern society. In Japan, there has never been any predictive study concerning this problem. In order to stimulate Japanese scholars and case workers to undertake study of this problem it is desirable to know something of the nature of such studies in foreign countries, especially in the United States where most work has been done on the problem to date. This paper is limited to a review of research methods in the United States.Such predictive studies can be classified into four types, according to the following two criteria.A. Predication of probabilities of marital happiness from premarital factors, or prediction from marital conditions.B. Prediction of probabilities of marital happiness by the use of other, methods, such as the post-facto, the cross-sectional, the follow-up and the longitudinal methods.The nature of these techniques can be suggested in this manner;1. Post-facto predictive studies from premarital experience.2. Post-facto predictive studies from marital life.3. Follow-up predictive studies from premarital life.4. Follow-up predictive studies from marital life.The following are the methodological problems dealt with in this article according to this classification.1. The halo effect in post-facto studies.2. The representative nature of samples.3. Combinations of predictive items between husband and wife and configurations of predictive factors.4. Reliability and validity of happiness scales and predictive scales.5. Various problems in practice, etc. Finally, this paper treats, from the methodological and practical point of view, the relation between the method of statistical prediction and the method of prediction from case studies.
3 0 0 0 OA 宮島喬著『文化的再生産の社会学』
- 著者
- 山下 雅之
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.502-503, 1997-03-30 (Released:2009-10-13)
3 0 0 0 ダイアド関係と紛争過程
- 著者
- 長谷川 公一
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.354-373, 1983
対立や紛争はどのような社会現象か。そこでは、主体はどのような課題に直面するのか。従来の紛争研究は、主体間の目標達成の両立不可能性に焦点をあてる社会関係論の視角からするものと、社会システムの不均衡状態に焦点をあてる全体システムの視角からするものとに大別できる。本稿は前者の系譜をふまえ、ダイアド関係を動態的にモデル構成し、そのうえで、紛争化過程および紛争過程における紛争当事者の課題を論じたものである。まず、ダイアド関係の利害連関は、対立、結合、分離の三状相に分節される。資源動員能力の格差にもとつく優位な主体の側の劣位者側への意思決定の貫徹可能性に注目すると、相互行為のパタンは、紛争、抑圧的支配、互酬的支配、協働、並存の五過程に分節される。ダイアド関係は、これらの問を移行する動態的な過程である。紛争過程への移行に際しては、対立状相の意識化に次いで、紛争行動を選択するか、紛争回避行動を採るかの意思決定が課題となる。選択を規定するのは、劣位な主体では相対的剥奪感であり、一般には報酬・コストのバランスである。両当事者の紛争行動の選択によって、紛争過程は開始される。紛争行動の実施にあたって、当事者は、 (1) 資源の動員可能性、対抗行為の (2) 戦略的有効性および (3) 規範的許容性、これらの検討を課題とする。とくに劣位な主体は、対抗集団の組織化などによる、対抗力の拡大と資源動員能力の格差の克服とを緊要な課題としている。
- 著者
- 安村 克己
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.449-463,492*-491, 1988-03-31
本稿は、社会現象の科学的認識に、社会学理論の構成が急務であるという問題意識から、社会学的認識の科学基礎論を検討する。考察にあたっては、社会学史において伝統的な自然主義-反自然主義の哲学的論争には触れず、理想的な科学基礎論として、カッシーラーの精密科学認識論を提示する。さらに、その認識論と、社会学的認識固有の問題を探究したヴェーバーの社会学認識論とを比較.検討することによって、社会学理論構成の哲学的基礎をより明瞭にしてみたい。<BR>カッシーラーとヴェーバーは、伝統的自然科学認識論に対して、概念論と「法則性」概念の観点から、その難点を同様に指摘する。さらに、カッシーラーの精密科学認識論とヴェーバーの社会学認識論には、共通の認識論的特徴として、 (1) 認識における主観的思惟介在の前提、 (2) 科学概念の概念形成論、 (3) 法則と理念型の認識論的特徴、といった点が見られる。ヴェーバー社会学は、社会現象固有の属性ゆえに「自由な創意」に制約を課し、却って社会学的認識の科学的真理を放棄した。しかし、ヴェーバーの提起する社会学的対象の属性に関する問題には、科学的認識が可能であり、それは、カッシーラーの科学基礎論に基づいてはじめて達成されると考えられる。本稿は、カッシーラー哲学が社会学理論構成の哲学的基礎を考察するさいの指針となることを結論とする。
- 著者
- 道場 親信
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.240-258, 2006-09-30
- 被引用文献数
- 3
本稿では, 社会運動史の視点から1960-70年代の「市民運動」「住民運動」がもっている歴史的な意味を再検証するとともに, それが近年の「市民社会」論に対して不可欠の問題提起を含んでいることを明らかにする.その際, 近年の社会運動研究の一部に存在する, 運動史の誤った「段階論」的理解を批判的に取り上げるとともに, 同時代の論議の場に差し戻して検証することで, その "誤り" が, 「公共性」「市民社会」を論じるあり方にもバイアスを与えていることを論じていきたい.その上で, これらの誤解の背後には, 社会運動理解の文脈の歴史的な断絶, 論議の中断が存在することを論じる.1960-70年代の社会運動がもっていた運動主体をめぐる論議の蓄積は, 今日の社会運動, また「市民社会」や「公共性」のあり方をめぐる論議の中で正当な評価を得ているとは必ずしも言い難い.この点につき本稿では, 当時の議論の水準を, とりわけ「住民運動」と呼ばれる運動の展開に即して再確認するとともに, 「地域エゴイズム」というキーワードを手がかりに, 運動文脈の適切な理解を妨げる認識論的な問題が当時と今日を貫いて存在していることを明らかにしたい.
- 著者
- 宍戸 邦章/佐々木 尚之 佐々木 尚之
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.336-355, 2011-12-31
- 被引用文献数
- 3
本稿の目的は, 2000年から2010年の期間に8回実施されたJapanese General Social Surveys (JGSS) の累積データに基づいて, 時代や世代の効果を考慮しながら, 日本人の幸福感の規定構造を検討することである. JGSSは, 各年または2年に1回実施されている反復横断調査であり, このデータをプールすることで, 単年度の調査では明らかにできない時代や世代の効果を検討することができる. また, 時代や世代の効果を統制しながら, 個人レベルの変数の効果を検討することで, 特定の調査時点だけで成り立つ知見ではなく, より一般化可能な知見を得ることができる. 分析手法は, 階層的Age-Period-Cohort Analysisである. 個人は時代と世代の2つの社会的コンテクストに同時にネストされていると考え, 時代と世代を集団レベル, 年齢および幸福感を規定する他の独立変数を個人レベルに設定して分析を行う.<br>分析の結果, 次のことが明らかになった. (1) 年齢の効果はU字曲線を描く, (2) 2003年に幸福感が低下した, (3) 1935年出生コーホートや80年以降コーホートで幸福感が低い, (4) 出身階層や人生初期の社会的機会が幸福感の加齢に伴う推移パターンに影響を与えている, (5) 絶対世帯所得よりも相対世帯所得のほうが幸福感との関連が強い, (6) 就労状態や婚姻状態が幸福感に与える効果は男女によって異なる.
2 0 0 0 OA 価値意識の構造と機能
- 著者
- 見田 宗介
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.38-52,113, 1962-08-30 (Released:2010-02-19)
- 参考文献数
- 72
2 0 0 0 OA 戦後10年における犯罪非行現象の分析
- 著者
- 犯罪問題研究部会
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.90-127, 1957-02-25 (Released:2009-11-11)
- 著者
- 宮島 喬
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.154-155, 2015 (Released:2016-06-30)
2 0 0 0 OA 下夷美幸著『日本の家族と戸籍――なぜ「夫婦と未婚の子」単位なのか』
- 著者
- 嘉本 伊都子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.345-346, 2020 (Released:2021-09-30)
2 0 0 0 OA 社会学教科書の比較社会学
- 著者
- 苅谷 剛彦
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.626-640, 2005-12-31 (Released:2009-10-19)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 5 1
大学教育の場を通じて, 社会学の知識は, どのように教えられるのか.この論文では, 日米で使われている社会学入門の教科書の比較分析を通じて, 日本とアメリカにおける教育的知識としての社会学知の生産・再生産様式の特徴について分析を加える.問題設定の1節に続き, 2節では, 教科書の分析を通して, 社会学知がどのように編集され, 提示されているのかを比較する.その上で, 3節では, アメリカの大学教育の特徴を, 日本と比較しながら検討する.社会学知が伝達される当の舞台である大学の教室が, 日米でどのように異なるのか.それが, 教科書における知識の社会的構成にどのような影響を与えているのかを検討するのである.そこでは, 日本の大学教育の特徴が, 社会学知の標準化の程度を弱めていることが明らかとなる.4節では, これらの分析をふまえて, 日本における社会学知の生産と再生産が抱える課題について考察を加える.そこでは, アメリカに比べ社会学知のノーマル・サイエンス化が進んでいない日本において, 社会学知の方法知 (社会学的なものの見方の伝達) へのシフトが起きていることの問題性について考察する.
2 0 0 0 OA 教育達成の社会経済的格差 趨勢とメカニズムの分析
- 著者
- 近藤 博之 古田 和久
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.682-698, 2009-03-31 (Released:2010-04-01)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 13 6
教育の階層差に関する近年の一般的な見方は,教育拡大にもかかわらず不平等が長期にわたり継続しているとするものである.本稿では,戦後の日本社会の教育格差の趨勢とそこに働いているメカニズムを,順序ロジット・モデル(とくに部分的比例オッズ・モデル)を用いて分析した.2005年SSM調査データから,父職・親学歴・財所有の3つの説明変数を構成して吟味した結果,(1)高度経済成長期以降の進学となる中年コーホートで明らかに格差縮小が進んだこと,(2)1980年代後半以降の進学者からなる若年コーホートで親学歴に局所的な格差拡大の動きが生じているものの,財所有の効果は一貫して低下しており,父職の効果もコーホートを通してそれほど変化していないことが明らかとなった.これより,大局的および長期的に格差縮小が進んできたことが確認された.さらに,代表的な格差生成メカニズムとして相対的リスク回避(relative risk aversion: RRA)説を取り上げ,その解釈が日本のデータにあてはまるかどうかを,仮説が成立するための必要条件を定式化して検証した.その結果,(3)親学歴ついてはRRA仮説の予想と一致する効果パターンが得られるものの,父職の効果についてはRRA仮説の予想と一致しないことが明らかとなった.このことから,日本の場合は世代間職業移動を前提にした相対的リスク回避説が妥当しないと結論づけられた.
2 0 0 0 OA 宗教市場理論の射程
- 著者
- 沼尻 正之
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.85-101, 2002-09-30 (Released:2009-10-19)
- 参考文献数
- 26
本稿は, 近年ロドニー・スタークらアメリカの宗教社会学者たちにより提唱されている, 従来の世俗化論争の枠組を越えた, 新たな宗教社会学理論, およびその理論的基礎に基づいて展開されている宗教市場理論について検証することを目的としている.以下ではまずはじめに, 彼らが反世俗化論を唱える際の理論的根拠に関して, 宗教の定義の問題, 剥奪理論との関係についての議論を取り上げて論じる.次に, 彼らによる宗教変動の理論を, 宗教集団の類型論 (チャーチ・セクト・カルト), 宗教・呪術・科学の三者の関係についての議論, 宗教変動の三要素 (世俗化・リバイバル・宗教的刷新) を取り上げて説明する.その上で更に, 彼らの宗教市場理論について検討する.合理的選択理論などを基礎とする, この宗教市場モデルは, 一般の市場の場合と同様に宗教も, 多元主義的状況でその活発さを増すという考え方に基づくものであるが, この視点をとることで, 現代社会における伝統宗教の盛衰や, カルト的新宗教の台頭状況などが, どのように整合的に説明できるかを示す.最後に, こうした理論の持ついくつかの問題点を挙げ, それらを克服するために今後どのような課題があるのかを考察することで, 彼らの理論の持つ射程を明らかにしたい.
2 0 0 0 OA ダブル・バインドへのシステム論的アプローチ
- 著者
- 長谷 正人
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.310-324, 1989-12-31 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 1 1
ダブル・バインドは、日常的コミュニヶーションに現れる論理的パラドックスの問題として哲学的に考察されてきた、しかし、ダブル・バインドは同時に関係性とシステムについての問題でもある。このパースペクティヴからみたとき、ダプル・バインドは社会学的問題となる。システム論からみたダブル・バインド状況は次のようなものである。システムのあるレベルでポジティヴ・フィードバックが起こり、システムに変化の可能性が生じている。それにもかかわらず、もう一つ上のレベルでネガティヴ・フィードバックが起こり変化への動きを内に孕んだままシステムは安定してしまうのである。このようなダブル・バインド状況からの解放は、ポジティヴ・フィードバックに対する抑制を解き、システム全体にポジティヴ・フィードバックを引き起こすことになる。ダプル・バインドへのこのようなアプローチは、社会システムが硬直化した秩序状態にあるとき、これをどう変化させればよいか、という問題にも示唆を与えるだろう。
2 0 0 0 OA 「探求の語り」再考 病気を「受け入れていない」線維筋痛症患者の語りを通して
- 著者
- 野島 那津子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.88-106, 2018 (Released:2019-06-30)
- 参考文献数
- 15
A. W. フランクが理想型として提示する「探求の語り」は, 病いの「受容」と苦しみによって新たな何かが獲得されるという信念を語り手に要請する. この「成功した生」の道徳的な語りは, 病いを受け入れられない人の語りを, 失敗した生のそれとして貶める可能性がある. また, 道徳的行為主体に至る個人の努力が強調される一方で, 苦しみを受け入れ経験を語る過程における他者や社会経済的要因の考察が, 不十分または不在である. こうした問題を乗り越えるために本稿では, 病気を「受け入れていない」線維筋痛症患者の語りを通して, 「探求の語り」の成立要件としての病いの「受容」のあり方について検討し, 以下の知見を得た. (1) 病気を「受け入れる/受け入れない」ことの責任は, 周囲の人々と共同で担われ得る. (2) 「耳ざわりのいい」物語が流通する中で病人像が規範化され, そこから逸脱した病者の生き方/あり方が否定され得る. (3) 周囲の人間が病気を受け入れない場合, 病いの「受容」は個人化され得る. (4) 病いを受け入れていなくても, 病者は経験の分有に向けて語り得る. 以上の知見から本稿は, 他者との分有や共同を含めた病いの「受容」の多様なあり方を「探求の語り」に認めることを提起する. 「耳ざわりのいい」物語だけが聞かれる危険性に対しては, 個々の語りのさまざまな「探求」を聴き手が見出し, ヴァリエーション豊かな「探求の語り」が提示されねばならない.
2 0 0 0 OA 出身階層の資本構造と高校生の進路選択
- 著者
- 古田 和久
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.21-36, 2018 (Released:2019-06-30)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 2
本稿の目的は, 社会階層構造を吟味したうえで, 出身階層による進路選択の差異を分析し, 家族の保有資本量と構成による格差のメカニズムを探究することである. 2012年に実施された「高校生と母親調査, 2012」を用い, 家族の階層およびそれと高校生の進路希望との関係を分析した. 第1に, 出身家庭の資本構造を区別するため, 親の職業, 学歴, 世帯年収, 預貯金, 文化的所有財に潜在クラス分析を適用し, 5クラスのモデルを得た. それによれば, 家族の階層は経済資本と文化資本の量だけでなく, 資本構成によっても分化していた. 具体的には, 経済資本と文化資本の両方を豊富にもつ層ともたない層に加え, 一方の所有量は多いが他方は少ない2つの非対称な階層, および中間層の存在を確認した. 第2に, 出身階層による進路希望の格差は資本総量とともに, 資本構成によっても生じていた. 資本量が最も多い層と少ない層の間には進路希望の顕著な差異が観察されるのと同時に, 資本構成が非対称な2つの層を比較すれば, 経済資本よりも文化資本を多く所有する層において大学進学希望率が高かった. 第3に, 文化資本の効果は上層と中間層との間で確認された. 他方, 経済資本の効果が最も顕在化するのは, 文化資本の蓄積が少ない階層においてであった. これらの結果は, 多次元の社会階層構造を反映して, 各要因が組み合わされ教育機会の格差が複合的に生じていることを具体的に示すものである.