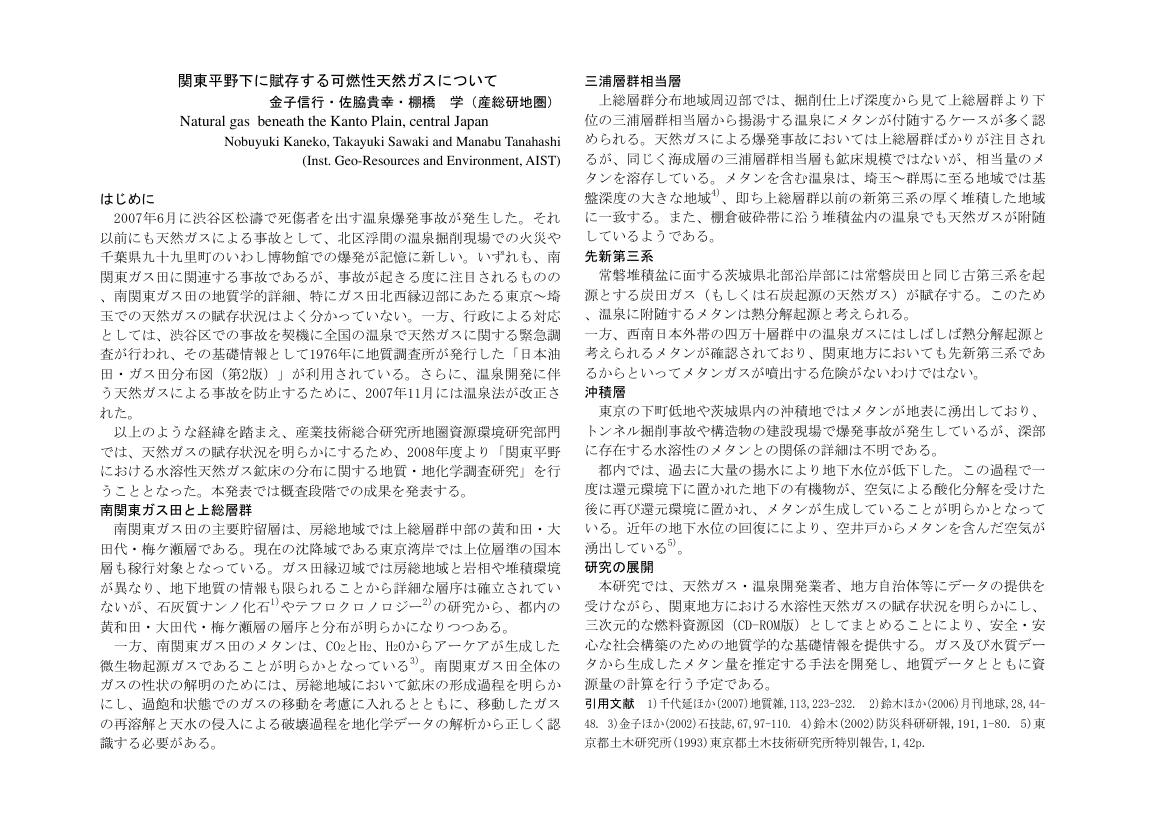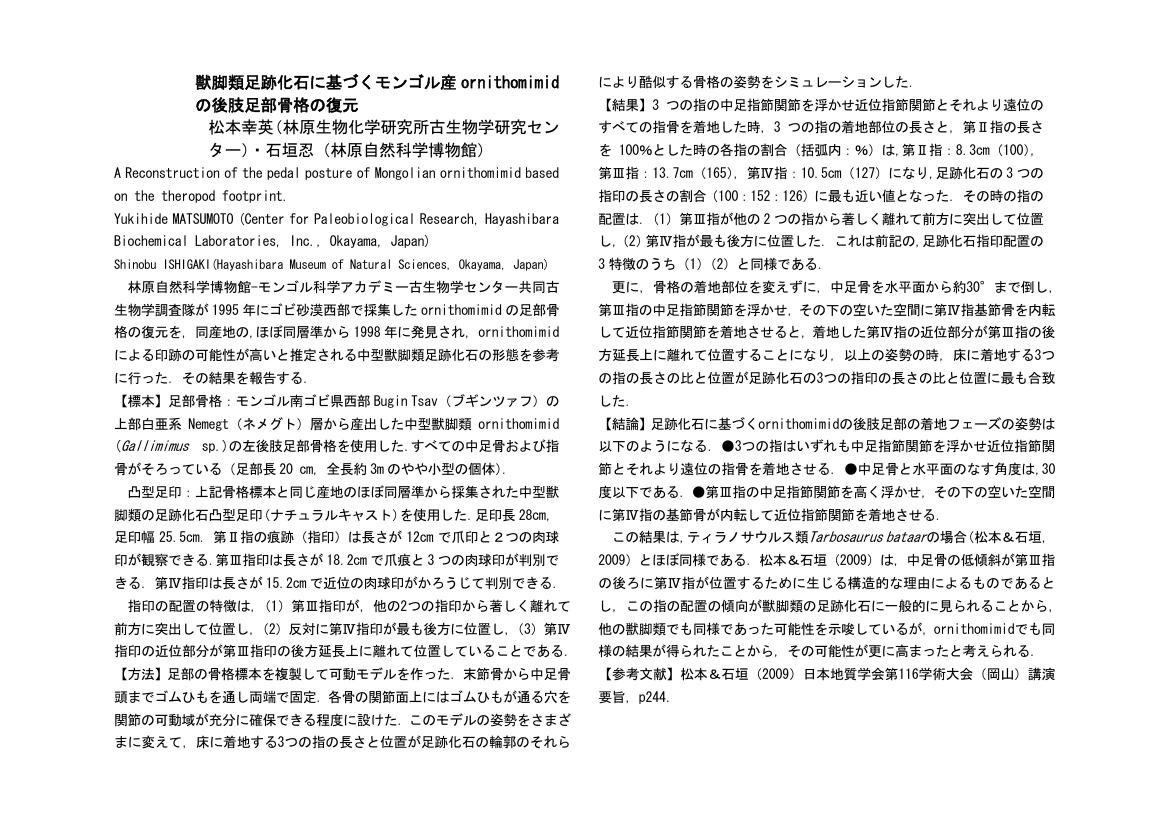4 0 0 0 OA 第三紀・第四紀境界層準の広域火山灰層:福田・辻又川・Kd38火山灰層
- 著者
- 吉川 周作 里口 保文 長橋 良隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.3, pp.258-270, 1996-03-15 (Released:2008-04-11)
- 参考文献数
- 57
- 被引用文献数
- 22 31
4 0 0 0 OA 伊豆半島南部の新第三系白浜層群に見られる浅海底火山活動と堆積・造構過程との相互作用
- 著者
- 狩野 謙一 伊藤 谷生
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.8, pp.413-432, 2016-08-15 (Released:2016-09-02)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 2
伊豆半島南部に分布する新第三系の白浜層群中には伊豆-小笠原弧背弧域の浅海火山活動と,それに密接に関係した堆積・造構作用を示す露頭が海岸部に好露出している.ここで見られる現象は,未固結堆積物に貫入する様々な形態の岩脈,ドーム,火山岩頚,ラコリスなど,および貫入岩体周縁部での水冷破砕とぺぺライト形成,母岩の熱水変質作用,枕状溶岩,自破砕溶岩を含む水中火山岩の噴出・堆積過程,火山活動に起因する堆積物重力流の発生・再堆積,地質図規模の緩やかなドーム・べースン構造,貫入岩体周辺での急傾斜部,堆積同時性断層の形成などである.本巡検では,半島南東部の下田地域,南伊豆地域,西伊豆地域の海蝕崖,海食台でこれらの現象を観察する.これらは,火山性島弧の背弧やリフト帯の浅海域での海底火山活動の実態を理解するための好例である.
4 0 0 0 高校地学教科書における火成岩分類法の問題点
- 著者
- 高橋 正樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.315-315, 2010
4 0 0 0 OA 更新統足柄層群に貫入する矢倉岳石英閃緑岩体のK-Ar年代と化学組成ならびにSr同位体比
- 著者
- 倉沢 一 今永 勇 松本 哲一 柴田 賢
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.4, pp.331-334, 1989-04-15 (Released:2008-04-11)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 6 6
4 0 0 0 OA 中部沖縄トラフ底で採取されたピストンコアに記録された約7300年前の堆積環境の急激な変化
- 著者
- 川村 喜一郎 池原 研 藤岡 換太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.5, pp.184-192, 2007 (Released:2007-12-28)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
堆積システムの急激な変化が中部沖縄トラフの3 mと5 m長の2本のコアに記録されていた.構成される石英粒子の中央粒径は,7325年前の年代のK-Ah層で下位から上位に向けて急激に減少した.その中央粒径の減少は,約20 μmの粗粒粒子の除去による結果である.K-Ah層の年代で生じたこの変化は,1)海水準上昇で沖縄トラフと堆積物供給源である中国大陸とが離れたこと,2)トラフ内で8000~7000年前に黒潮の堆積物供給バリアが形成され,大陸からの堆積物のほとんどが強い海流により掃きとばされたことによって生じたと推測される.さらに,微細組織がその下位での水平配列から上位でのランダム配列へ変化する.その水平配列は,高堆積速度条件下で生じた無生物擾乱からの結果であると判断できる.このように,中部沖縄トラフでは,今日のような堆積システムが約7300年前に形成されて,現在までにそれが持続していると考えられる.
3 0 0 0 OA 房総半島南部沿岸の海岸段丘と津波堆積物に記録された関東地震の履歴
- 著者
- 宍倉 正展 鎌滝 孝信 藤原 治
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.7, pp.357-370, 2016-07-15 (Released:2016-08-02)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 1 1
フィリピン海プレートが沈み込む相模トラフ沿いでは,過去からプレート間地震(いわゆる関東地震)がくり返し生じてきた.歴史上に記録されている1703年元禄関東地震と1923年大正関東地震では,南関東沿岸に地殻変動を伴い,大きな津波が襲ったことが知られている.地殻変動は海岸段丘などの離水海岸地形や隆起生物遺骸として,また津波は津波堆積物として,それぞれ地形や地層に記録されている.房総半島南部沿岸では,地殻変動や津波の影響を特に大きく受け,複数のレベルに海岸段丘が発達していたり,縄文海進期の内湾堆積物中に複数枚の津波堆積物が挟まれていたりする.これらの記録を解読することで,過去7000年から8000年以上に渡る地震や津波の履歴を復元することができる.
3 0 0 0 OA 世界遺産の島・屋久島の地質と成り立ち
- 著者
- 安間 了 山本 由弦 下司 信夫 七山 太 中川 正二郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.Supplement, pp.S101-S125, 2014-08-31 (Released:2014-12-26)
- 参考文献数
- 65
- 被引用文献数
- 1 3
世界自然遺産・屋久島の生物多様性を支えるのは海洋性の環境の中に現出する高山地形である.多くの海洋島が火山からなるのに対して,屋久島の基盤を構成するのは四万十帯の砕屑性堆積岩類と屋久島花崗岩である.本巡検では高山を形成する屋久島花崗岩の貫入機構を,正長石巨晶の定方向配列,岩脈の分布,貫入に伴う母岩の変形と接触変成作用の観察を通して議論する.母岩の四万十帯の地層や枕状溶岩の産状,付加体中での圧密,メランジュやデュープレックス構造の形成,地震による液状化構造がどのような順序で発達したかを観察し,付加体の変形史とメランジュの認定基準について議論する.また鬼界カルデラの噴火に伴う火砕流堆積物の産状,噴火による地震が引き起こした液状化などの構造を観察し,海中における爆発的噴火がもたらしうる災害のシナリオを検討する.
3 0 0 0 OA O-177 式根島火山の生成シナリオ
- 著者
- 大島 治
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 第106年学術大会(99’名古屋) (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.99, 1999-10-05 (Released:2017-08-24)
3 0 0 0 OA 三浦半島衣笠付近の堆積性蛇紋岩
- 著者
- 狩野 謙一 伊藤 谷生 増田 俊明
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.10, pp.641-644, 1975-10-15 (Released:2008-04-11)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 5 6
3 0 0 0 OA 汎用ポータブルPCを利用した野外調査の現状の利点と課題
- 著者
- 吉川 敏之
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.3, pp.184-189, 2012-03-15 (Released:2012-08-03)
- 参考文献数
- 10
Today's portable computing devices are suitable for geological field surveys because digital field data are easily stored and shared. However, most specialized systems for this purpose are expensive and require specific software and/or hardware. Widespread use of such systems would require readily available hardware and software. As a case study, a portable computer and software for general use were tested in a geological field survey, yielding the following results. The advantages of using a digital device were text input using a clipboard extension utility, sketching over a digital photograph, GPS assistance, and the portability of reference data. Disadvantages include the lower quality of route maps, difficulty in sketching by hand, limited battery life, and the need to protect the device from water and dust. Despite these limitations, the use of portable computing devices is already advantageous in some cases and has the potential for greater convenience during field work.
3 0 0 0 OA 瀬戸内区中新統:鮎河層群と綴喜層群
- 著者
- 入月 俊明 栗原 行人
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.1, pp.355-369, 2023-07-08 (Released:2023-07-08)
- 参考文献数
- 56
瀬戸内区中新統の,従来,第一瀬戸内累層群と呼ばれた下部中新統上部〜中部中新統下部は様々な化石を豊富に含んでいることから,古くより地質学・古生物学的研究が盛んに行われてきた.これらの中新統からは,特に,前期中新世の明世動物群や中期中新世最温暖期(Mid-Miocene Climatic Optimum)の門ノ沢動物群を特徴づける貝化石が豊富に産出することで知られている.近年,微化石に基づく生層序学的研究が進み,瀬戸内区中新統の海成層は,相対的海水準が上昇した4つの期間に形成されたことが明らかにされた.このように,瀬戸内区中新統は,前期から中期中新世における汎世界的な気候変動や日本列島の構造運動に関連した古環境や動植物群の時間空間的変化を知る上で,最も適したフィールドである.本巡検では,近畿地方に分布する瀬戸内区中新統の代表的な地層である滋賀県甲賀市の鮎河層群と京都府綴喜郡宇治田原町の綴喜層群の分布域に赴き,これらの浅海成層と明世動物群を構成する貝化石群集の観察を通じて,両層群の対比や当時の古環境について理解する.
3 0 0 0 OA 千島海溝沿岸域において認められる超巨大地震津波痕跡群と広域地殻変動
- 著者
- 七山 太 渡辺 和明 重野 聖之 石井 正之 石渡 一人 猪熊 樹人
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.6, pp.413-433, 2018-06-15 (Released:2018-08-18)
- 参考文献数
- 66
- 被引用文献数
- 3 4
千島海溝沿岸域は本邦屈指の地震多発地帯である.この地には未開の原野も多く,手つかずの自然が残されており,400~500年間隔で繰り返し発生した超巨大地震(17世紀型)によって生じた離水地形や津波堆積物が観察できる唯一無二の地域と言える.また北海道東部には偏西風によってもたらされた完新世テフラが1000年オーダーの頻度で挟在し,地震津波イベントの同時性を議論するうえで有用である.津波堆積物の自然露頭は北海道東部太平洋沿岸でも限られるが,この巡検で最初に議論する根室市西端部のガッカラ浜地域には小規模な沿岸湿原が存在し,その太平洋側には湿原堆積物の断面である泥炭層が,高さ約2m程度の海蝕崖が連続して露出している.この露頭では,6層の完新世テフラと過去4000年間に発生した12層の津波堆積物を確認することができる.一方,根室海峡に面する風蓮湖と野付半島には,我が国には珍しい現在も活動的なバリアーシステムが認められている.これらの沿岸地形を特徴づける分岐砂嘴(バリアースピット)の相互の分岐関係と7層の完新世テフラとの対比によって,過去5000年間の地形発達史が解読され,このうち過去3回分の離水(強制的海退)については,超巨大地震(17世紀型)に伴う数mオーダーの広域地殻変動が大きく寄与している可能性が示唆される.
3 0 0 0 OA 組成データ解析の問題点とその解決方法
- 著者
- 太田 亨 新井 宏嘉
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.3, pp.173-187, 2006 (Released:2006-07-14)
- 参考文献数
- 78
- 被引用文献数
- 15 11
岩石・鉱物の化学組成,砕屑物の粒度組成やモード組成,生物の群集組成などで利用される組成データは変数の総量が一定であるために定数和制約を受ける.このような形式のデータを対象とした統計学的推定,検定の方法論は最近まで確立されていなかった.しかし,近年,組成データの厳密な統計学的解析方法が急激に進歩した.本論では,このような手法の1つである対数比解析と単体解析を実例を交えて紹介する.対数比解析は,組成データを単体空間から実空間に写像する方法である.単体解析は,単体空間に属する組成データに対して,新たに統計量や解析方法を開発する試みである.今後はこのような解析方法を用いて,より適切な論理的基盤から地質学的諸現象を解析することが重要となるであろう.
- 著者
- 隈 隆成 西本 昌司 村宮 悠介 吉田 英一
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.1, pp.145-151, 2023-02-22 (Released:2023-02-21)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1 1
Carbonate concretions occur in sedimentary rocks of widely varying geological ages throughout the world. Recently, more than 100 gigantic carbonate concretions with diameters ranging from 1 to 9 m have been identified along the Unosaki coast of Oga Peninsula, Akita Prefecture, Japan. The formation process of such gigantic concretions, some of which along the Unosaki coast contain whale bones, remains uncertain. A mineral composition analysis reveals that the major mineral of the concretions is dolomite. Considering the location of dolomite precipitation, their composition implies that the concretions were formed in a reducing environment in which sulfate ions were removed. Stable carbon and oxygen isotopic analysis reveals that the CaCO3 of whale bone and concretions contains light δ13C and heavy δ18O, suggesting that whale organic matter contributed to the formation of the concretions. The gigantic carbonate concretions were presumably formed by the accumulation and burial of whale carcasses with high sedimentation rates, and subsequent reaction of carbon decomposed by benthic and microbial activity with seawater.
3 0 0 0 OA 東南極における最終間氷期以降の氷床・海水準変動の復元:現状と今後の課題
- 著者
- 石輪 健樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.128, no.1, pp.465-474, 2022-12-29 (Released:2022-12-29)
- 参考文献数
- 91
地球温暖化が危惧される現在,将来の気候変動に対する南極氷床の振る舞いを理解することは学術的にも社会的にも喫緊の課題である.南極氷床は多様な時間スケールで変動するため,人工衛星や現地測地観測など比較的短期の変動を捉える観測手法に加え,地質記録やモデルシミュレーションを用いた数十年から数十万の長期的な時間スケールの南極氷床変動の復元が重要である.海水準記録は地質記録とglacial isostatic adjustment(GIA)モデルから復元が可能であり,全球的な氷床量すなわち海水量を反映する.そのため,長期的な時間スケールの南極氷床変動の復元において重要な指標である.本論文では,東南極における海水準変動の先行研究とGIAモデルの現状をまとめ,東南極海水準変動復元の研究における今後の展望を述べる.
3 0 0 0 OA 富士山東方で1.1kaに発生した大規模火山性斜面崩壊
- 著者
- 山元 孝広 石塚 吉浩 下司 信夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.126, no.3, pp.127-136, 2020-03-15 (Released:2020-07-31)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1 2
富士山東方の静岡県小山町の新東名高速道路の2018年度建設工事現場で,大規模な火山性の斜面崩壊堆積物を確認し,大御神岩屑なだれ堆積物と命名した.この堆積物は,大洞山東斜面に堆積していた富士火山起源のスコリア降下火砕物が表層崩壊を起こしたもので,その南東山麓に長さ4.5 km,最大幅1.5 km,体積9.3×106 m3の規模で広がっている.堆積物直下に神津島天上山テフラの降下層準があること,直上土壌の14C 暦年代から,発生時期は平安時代のAD 838から10世紀前半に特定された.この期間中には東海・南海連動の巨大地震であるAD 887の仁和地震が起きており,この地震動によって斜面崩壊が発生した可能性が強い.
3 0 0 0 OA 関東平野下に賦存する可燃性天然ガスについて
- 著者
- 金子 信行 佐脇 貴幸 棚橋 学
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 第115年学術大会(2008秋田) (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.426, 2008 (Released:2009-02-20)
- 参考文献数
- 6
3 0 0 0 OA 大陸リソスフェア(テクトスフェア)はなぜ安定か?
- 著者
- 片山 郁夫 是永 淳
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 第114年学術大会(2007札幌) (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.341, 2007 (Released:2009-01-30)
3 0 0 0 OA 天平の産金地,宮城県箟岳丘陵の砂金と地質の研究史
- 著者
- 鈴木 舜一
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.116, no.6, pp.341-346, 2010 (Released:2010-10-13)
- 参考文献数
- 38
Gold placer was discovered at Nonodake Hill in the mid-eighth century, making it the site of the earliest gold diggings in Japan. Watanabe (1935) was the first geologist to discuss the source of the placer gold, suggesting that it was derived from a Tertiary conglomerate containing rounded fragments of vein quartz, and that the primary source was pre-Tertiary gold veins in the Kitakami Mountains. Onoda (1942) agreed with Watanabe’s view. However, Yagyu (1953) suggested that the placer gold was derived from Tertiary gold veins on the northern side of Nonodake Hill. Taguchi and Ozaki (1994) undertook chemical analyses of particles of placer gold using a scanning electron microscope with an X-ray microanalyzer. Their results support Watanabe’s view on the primary source of the placer gold.
3 0 0 0 OA 獣脚類足跡化石に基づくモンゴル産ornithomimidの後肢足部骨格の復元
- 著者
- 松本 幸英 石垣 忍
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 第117年学術大会(2010富山) (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.467, 2010 (Released:2011-03-31)
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 1