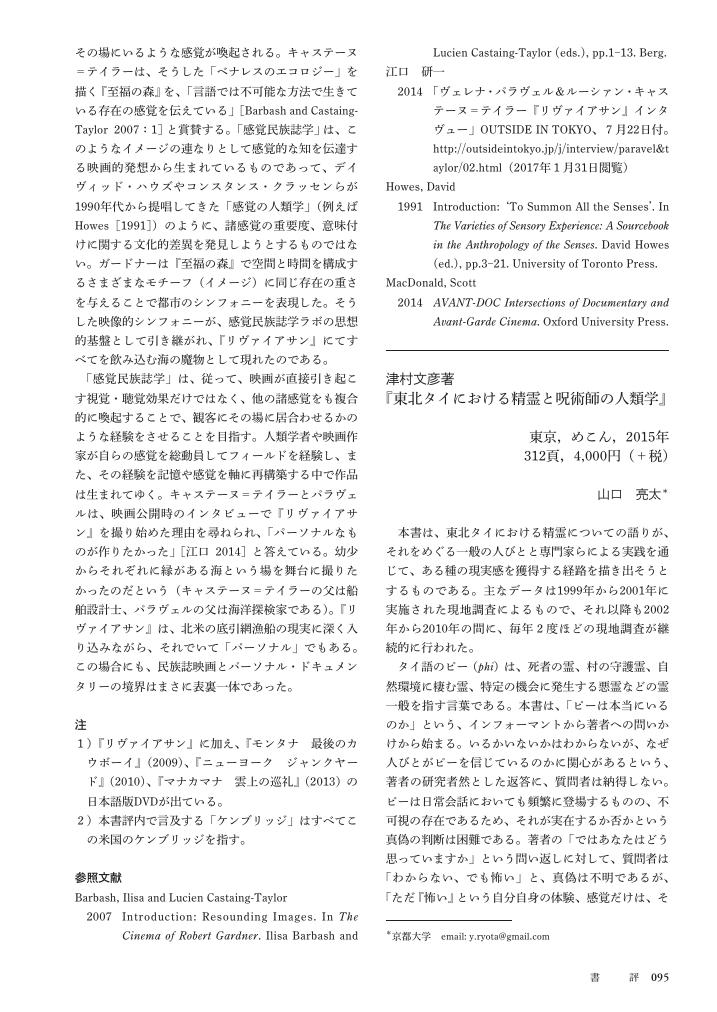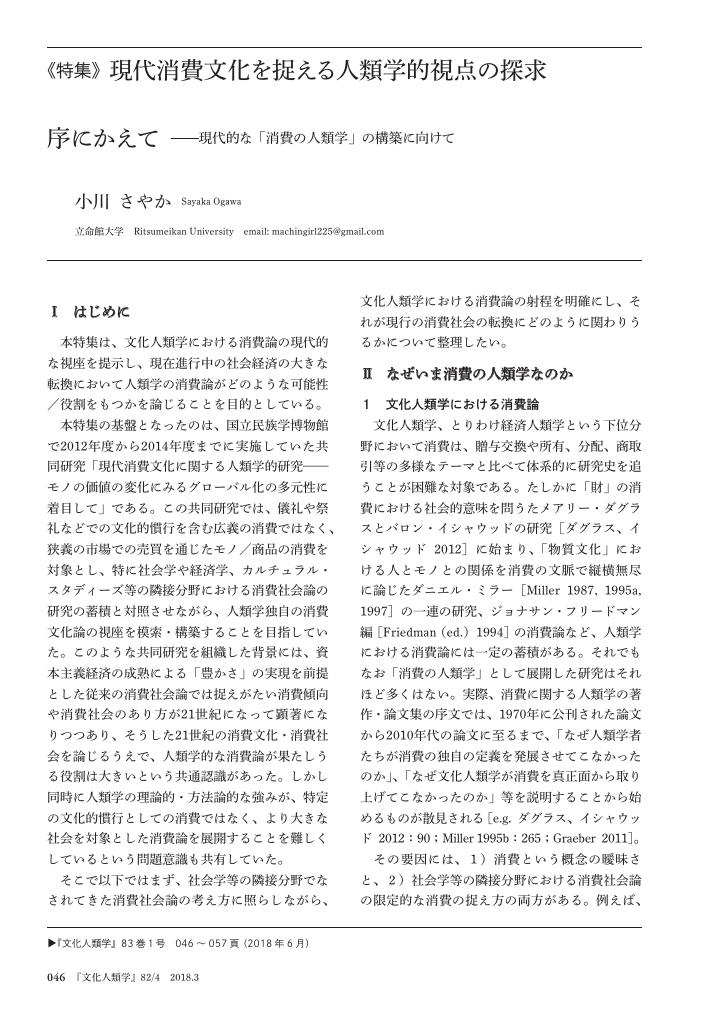2 0 0 0 OA 庚申信仰研究法私見 : 日本民俗学者の批判に答う
- 著者
- 窪 徳忠
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1-2, pp.412-437, 1960-03-25 (Released:2018-03-27)
Since the Edo period there has been a prevailing opinion, that the origin of the Japanese Koshin Belief had been derived from Taoism in China, but in recent years Japanese folklorists, with Mr. Kunio YANAGITA as the leader, have come to assert that it was native to Japan. Up to now neither has yet claimed a definite conclusion on this question. The writer thinks that both hypotheses have weaknesses in their methodologies : the former referred only to the literature without reaching into the folk beliefs and customs of the Edo period ; the latter depends only on the results of field work with the presumed ignorance of historical documents. In addition, neither the former nor the latter compare Japanese Koshin Belief in detail with Taoism at all. The writer intends to synthesize the historical records from the Heian period, when Koshin Belief began to appear in Japan, to Meiji Era, with recent field work results, and to compare it with Chinese Taoism and the functions of the Chinese Koshin Belief. He assumed that this method would be the best to determine whether the Koshin Belief has its origin in Japan or not. As the result, Japanese Koshin Belief has come to be judged as the complex of Chinese Taoism, Buddhism including the esoteric form, Shintoism, Shugendo, magical medicine and various Japanese folk beliefs and customs. This study has been published by him under the title of Koshin Belief in Japan. His view-point has been furthermore substantiated by his field research throughout Japan excluding Hokkaido and by his bibliographic survey on this subject. The Japanese folklorist school still insists strongly on the Japanese origin. But he cannot rely on their methodology and is suspicious of how they deal with the data the amount of which in their possession seems not sufficient enough to be handled quantitatively, as well as qualitatively. He can hardly, at present, say whether it was native to Japan, and thinks that he does not need to correct his opinion which Mr. YANAGITA should take into account.
2 0 0 0 OA 悲しみの配置と痛みの感知 ルワンダの国家が規定するシティズンシップと人びとのモラリティ
- 著者
- 近藤 有希子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.1, pp.058-077, 2019 (Released:2019-09-04)
- 参考文献数
- 47
本論では、虐殺後のルワンダにおいて、和解し統合されたシティズンシップを創り出す装置として、虐殺記念週間におこなわれる集会や虐殺生存者基金に着目して、そのなかで方向づけられる人びとの倫理的な応答のあり方を検討する。それらの装置は、凄惨な紛争によって分断された人びとを等しく「ルワンダ人」として包摂する試みのもとに適用されてきた。他方で、そのとき形成される「国家の歴史」においては、トゥチだけを「生存者」、つまり「真のシティズン」として認定し、フトゥを一様に「加害者」、つまり「二級のシティズン」として位置づける効果を孕んでいる。そこでは愛する者の死を悼み、自身の壮絶な体験を嘆くことができるか否かという点で、格差をともなう承認の配置がおこなわれており、人びとの感情が規律化される事態が生じていた。 このような状況下にあって、村のなかには「トゥチの生存者」というカテゴリーに依拠して、その生存を確保させる者もいる。彼女たちの哀悼は、公的な場においてしばしば「国家の歴史」に一致した、およそ流暢な語りのなかに見出される。他方で、村に暮らす大半の人びとが虐殺時にはなんらかの脅威に曝されており、善悪に二分できない「灰色の領域」にあった。このような「国家の歴史」にはあてはまらない経験を生きる者たちの、決して語り慣れることのない発話は、かれらが代替不可能な個別の記憶とともに生き延びようとするときに現出している。 このとき地域社会のモラリティは、多くの者がみずからの経験に対して「言葉をもたない」ことにおいて開示されていた。なぜなら、統制されえない身体化された記憶、「語りえなさ」の発露としての情動こそが、体験の一般化を拒否する沈黙の作用とも重なりながら、個々人のかけがえのない経験を感知して、それに付随する痛みへの想像力の回路を開くからである。ここに、避けがたくともに生きる人びとの倫理的な応答性が導かれていた。
2 0 0 0 OA 表象と政治性 : アイヌをめぐる文化人類学的言説に関する素描
- 著者
- 木名瀬 高嗣
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.1-21, 1997-06-30 (Released:2018-03-27)
社会的レヴェルでのアイヌをめぐる問題の浮上や, 学者がそれに対して責任を果たすべきであるという気運の高まりに比して, アイヌに関する「現在」的な問題に対する文化人類学による取り組みの蓄積は依然乏しいままである。本稿は文化人類学におけるアイヌ研究の今後の可能性を模索するため, 日本におけるこの分野の言説の政治性について歴史的に考察する。そこに看取される論理への批判的視点から帝国日本の黎明期以来のアイヌを対象化する学的言説を概観したときに浮かび上がってくるのは, それらの言説が「国民」創出の過程と相関を保ちつつ, 文化的に「同化」していくアイヌの差異を永続的に対象化するレトリックを精緻なものにしていったプロセスである。本稿では, それらの言説のなかでアイヌの「現在」が捨象されることによって具体的現実のレヴェルで展開する「政治」が隠蔽されてきたことを明らかにする。
2 0 0 0 OA 少数民族地域におけるバイリンガル教育に関する一考察 ―中国・内モンゴル自治区の事例から―
- 著者
- ア ラタ
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第43回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.97, 2009 (Released:2009-05-28)
本報告では、民族言語を教授言語とし、共通言語の漢語を教科として学習するタイプを選択している内モンゴル自治区におけるバイリンガル教育を切口として、中国内モンゴル自治区の事例を内モンゴル自治区のモンゴル族の視点から、モンゴル族の民族らしさをどう維持してきたかについて考察を加えることを目的とする。それによって、中国の少数民族地域における民族教育のあり方の一端を提示することを試みる。
2 0 0 0 OA 書道界の制度と力学 : 現代日本の書道会と展覧会活動についての考察
- 著者
- 大野 加奈子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.165-187, 2007-09-30 (Released:2017-08-22)
本稿では、日本の伝統文化とされる「書」について、現在見られる日本の書道界のシステムをそこで活動する一般修練者の立場から記述して提示し、茶道やいけ花の家元制度と比較してその特徴を考察する。日本の書は、本来情報伝達手段であり実用的なものであったが、日本の近代化の中で実用的価値が薄れ消滅の危機を迎えた。「芸術」「伝統文化」へその存在価値を求めた書は、義務教育への参入を通して日本人の誰もが書を経験するものとなり、日展をはじめ出品数2万点を越す全国規模の大型展覧会の開催といった活動を通し、現在の日本の書とそれを支える書道界を作り上げた。日本の書道界では、日展を権威のヒエラルヒーの頂点とした、全国規模の大型展覧会での受賞歴により階梯を登るシステムが形成されている。そのシステムを家元制度と称し、西山松之助が『家元制度の展開』で書道界(会)について述べている。書道界(会)のシステムを家元制度との比較から考察し、そこに働く力学を探る。書道界(会)は家元制度的な組織運営形態をとっているが、代々続く家元や継承すべき型は存在せず、書道界で地歩を築き上昇するための方策として家元的制度を採用していること、またそうすることで書道界全体が日本の「伝統文化」の中に位置づけられるのを目指す意図があったことを示す。
2 0 0 0 OA リンガとフェティシズム
- 著者
- 宇田川 妙子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.4, pp.574-601, 2011-03-31
親子関係および親族関係は、現在、家族の多様化や生殖技術の発達などを背景に、多くの関心が集中し論争の場になっている。一方、人類学では、それ以前からすでに多くの議論が重ねられていたものの、周知のとおり、1970年前後からその研究は衰退の道をたどってしまった。原因の一つは、シュナイダーの議論に代表されるように、その研究姿勢に生物学的な関係を本質的とみなす前提が隠されており、その背景には西洋的な親族観が存在しているという批判であった。その後の親族研究も、1990年代以降「復興」したとはいえ、いまだ従来の西洋的な枠組みを脱したとはいい難い。むしろ、その批判・脱構築を急いだせいか、逆に西洋的枠組みの再生産につながってしまった観も否めない。こうした現状に対して本稿は、具体的にはイタリアの事例を用いながら「親子関係の複数性」という視点を導入して、親族研究そのものをより根源的に再考していこうとするものである。我々は通常、父と母は一人ずつであるという一元的な親子観になじんでいる。イタリアでも通常は、子供の親はその子を生んだ男女であるとみなされ、一元的かつ生物学中心主義的な観念はひろく普及している。その典型が2004年に成立した補助生殖医療法である。しかしその一方で、オジオバがオイメイの面倒をみるなど、子供の生活には、親以外にも様々な役割をする、非親族も含めた大人たちが常日頃から様々な形で関わっており、それらの関係が親子関係と共存しながら、その一元性を相対化しているように見える。もちろん、こうした複数的な親子関係はイタリアに限らない。ただし本稿が注目したいのは、親を父母一人ずつとみなす一元的な親子観が生物学的な生殖をモデルとしていることに気付くならば、これこそ西洋的な親族観の最も端的な象徴であり、ゆえに複数的な親子関係とは、その親族観をより根源的に相対化し、親族研究が「復興」後も抱えている根深い問題をあぶりだす有効な視点の一つになるのではないかという点である。そこからは、従来の系譜関係偏重の研究では看過されがちだったシブリング関係の意義や重要性など、新たな議論の糸口も浮かび上がってくるだろう。本稿では最後に、そうした新たな論点をいくつか具体的に指摘していくことによって、今後の親族研究の展開に資することとしたい。
2 0 0 0 OA 津村文彦著 『東北タイにおける精霊と呪術師の人類学』
- 著者
- 山口 亮太
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.1, pp.095-098, 2017 (Released:2018-03-15)
2 0 0 0 OA 「民衆的工芸」という他者表象 : 植民地状況下の中国北部における日本民芸運動
- 著者
- 金谷 美和
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.403-424, 2000-03-30 (Released:2018-03-27)
本論では, 日本民芸運動を事例にして, 日本の植民地という状況下において支配する側にいた人々が, 他者をどのように概念化し, 記述し, 理解しようとしたかを検討することで, 文化表象, ことに物質文化の表象について考察する。「民衆的工芸」=「民芸」という概念は, 大正時代末に柳宗悦を中心とする民芸運動によって作られた。流通機構の変化や機械生産の導入などにより衰退していた, 地方の手工芸による日用生活用品を取りあげて「民衆的工芸」=「民芸」と名付け, それらのもつ美的価値と, 「地方性」, 「民衆性」という性質から, 真正なる日本文化を示すものであると主張した。民芸運動の活動は, 日本が植民地支配下においていた中国北部においても行われ, その言論は, 日本の中国支配, さらには「満州国」や「大東亜共栄圏」を支持するものとなっていった。ここでは, 中国北部の民芸運動の中心人物であった吉田璋也と, 中国での運動から距離をおいていた柳宗悦の言説を比較し, 異なる文化を尊重することから始まった民芸運動が, 日本の植民地支配を支える方向に向かっていった原因が, 柳の民芸論に内包されていたことを明らかにする。そして, 文化表象には創造性と支配の2つの側面があること, 異文化表象の政治性を批判するだけでなく, 文化表象の創造性を問うことで文化表象についての議論が新たな方向に向かう可能性を示唆する。
2 0 0 0 OA 都市祭礼を通じた「伝承の再現」 ー東京都北区王子における「狐の行列」の事例からー
- 著者
- 李 婧
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 The 56th Annual Meeting of the Japanese Society of Cultural Anthropology 日本文化人類学会第56回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.C06, 2022 (Released:2022-09-13)
日本の都市祭礼の中には、過去から持続する伝統的なものに限らず、現代になって「伝統」の名のもとに新しく創られたものの、特に1970年代以降は多数見られる。本発表はその一事例である東京都北区王子で実施されている「狐の行列」という都市祭礼を取り上げ、祭礼の現場における人々のパフォーマンスと物の使用に焦点を当てながら、新しく創られた都市祭礼における持続性について考察するものである。
- 著者
- 岩谷 彩子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.3, pp.441-458, 2009-12-31 (Released:2017-08-18)
本稿は、インドの移動民ヴァギリが想起し語る夢を事例として、日常的に変容を続ける自己の営みを探求する試みである。従来の人類学的な夢研究では、テクスト化された夢を当該社会の集合表象として分析する研究や、危機に陥った自己が新しい世界観や時間構造のもとで自己を語りなおし、社会のなかで再構造化される契機として夢をみなす研究が提出されてきた。これに対して本稿では、語りや解釈を逃れる夢のイメージの持続が反復的な夢の想起をうながしている状況に着目した。ヴァギリ社会には「神の夢を見たら儀礼をする」という言説があり、多くの夢は儀礼を契機に想起されている。しかし、夢は必ずしも安定的に想起され語られるわけではない。本稿では同一個人に時間をあけて同じ夢を語ってもらい、その語りの変容について考察した。そこで明らかになったのは、第一に、ヴァギリの夢に繰り返し立ち現れる内/外を行き来する運動イメージの重要性である。この運動のイメージが夢の解釈を握る重要な基点となっており、そこから夢を見る主体がおかれた状況の変化に応じるかたちで、夢に現れる身体感覚や表象のあり方に変化が見られた。第二に、夢の想起と語りは、常に自己をとりまく他者との関係に依存しているという点である。夢を反復想起して他者に語る過程で、類似したイメージの夢が異なる主体間で反復されていた。また、語りに夢のイメージを意味づける観点が導入されたり、語りそびれた部分が残ることで夢のイメージが保持されていた。このように他者との関係において夢として想起され語られた運動イメージと身体感覚の持続と消失が、その後の夢とその語りを自己にもたらしていた。自己は予測不可能な他者との出会いと想起の機会に依存し、語りつくせない夢のイメージに導かれている。本稿では、そのような自らにずれを生じ続ける自己を〈身体-自己〉として例証した。それは、自己がメタモルフォーシスする持続的な過程なのである。
2 0 0 0 OA 薩瑪の巫祭と大仙の巫術 : 滿洲巫俗踏査報告
- 著者
- 秋葉 隆
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.237-257, 1935-04-01 (Released:2018-03-27)
- 著者
- 吉田 航太
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.3, pp.385-403, 2018 (Released:2019-05-12)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
本論文は、インドネシア東ジャワ州スラバヤ市で日本人技術者が開発した廃棄物堆肥化技術の事例を通じて、インフラ/バウンダリーオブジェクトというテクノロジーの二つのモードの差異を明らかにするものである。スーザン・L・スターのインフラストラクチャーの議論はバウンダリーオブジェクト論と連続性があり、前者は後者の発展型とされる。しかし、両者の間には解釈の対象としての象徴と、実践の対象としての道具という断絶が存在しており、インドネシアでの開発事業で 新たに誕生した生ゴミ堆肥化技術の事例の分析からこのことを明らかにする。スハルト政権崩壊後に発生した埋立処分場の反対運動をきっかけに、スラバヤ市は深刻なゴミ問題に悩まされた。これに取り組む開発プロジェクトが開始され、日本人技術者が開発したコンポスト手法がひとつのテクノロジーとして結実するに至った。このテクノロジーはスムーズに開発に成功したが、その後のインフラ化で困難に直面している。この事例から、スター的な協働のネットワークが長期の時間性に耐えなければならないという問題を抱えていること、テクノロジーが確固とした象徴的価値を獲得しなければならないことを議論する。
2 0 0 0 OA E-Pと人類学的思考の歴史(<特集>人文学としての人類学の再創造に向けて)
- 著者
- 佐々木 重洋
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.2, pp.242-262, 2015-09-30 (Released:2017-04-03)
本稿の目的は、エヴァンズ=プリチャード(以下、E-P)の思考の軌跡と、彼が示していた問題意識と手法をあらためて批判的に再検討し、その知的遺産と検討課題を現在に再接続させることにある。本稿では、民族誌や論考、講義録や書簡から読み取ることができるE-Pの構想のなかでも、人間の知覚と認識、その作用に影響を与えるものとしての社会、それも決して閉じた固定的なシステムではなく、人間関係の動態的な諸関係としてのそれとは何かをモンテスキューにさかのぼりつつ自省し続けた点と、民族誌と人類学の主要な仕事としていち早く解釈という営為を強調した点にとくに注目し、その背景を再検討した。アザンデの妖術やヌアーの宗教を扱った民族誌においては、当時の西欧的思考の枠組みに対する疑義ないし違和感が表明されていたが、E-Pとその後進たちの遺産は、そこに「インテレクチュアル・ヒストリー派」としての省察がともなうかぎり、主知主義批判、表象主義批判や言語中心主義批判、主客二元論批判や心身二元論批判としても、今なお私たちにとって着想の源泉たり得る。さらに、共感や友情を強調したその人文学的経験主義からは、絶えず自己に立ち返り、自らが影響を受けている知的枠組みと社会背景に対する自省を保ちつつ、調査する者と調査される者のあいだの共約不可能性を乗り越えようとする姿勢を継承でき、それはフィールドワークと民族誌を取り巻く思想的、物理的環境が大きく変わりつつある今こそ、あらためて参照に値することを指摘した。今日、E-Pに立ち返って考えることは、モンテスキューを脱構築しつつ、人類学的思考が哲学や社会学はもとより、法学や政治学、経済学などと未分化の状態であった時点に立ち返って考えることにつながるものでもあり、今後の人類学が人文学とどのように関係すべきかという点も含めた人類学の知のあり方を模索するうえで一定の意義があると考える。
- 著者
- 岡野 英之
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.1, pp.019-038, 2019 (Released:2019-09-04)
- 参考文献数
- 37
アフリカ諸国の紛争を扱った政治人類学および政治学の研究において、社会の統治過程に見られるパトロン=クライアント関係の分析は重要な課題の1つとなってきた。これらの議論では、パトロンとクライアントとの間に取り結ばれるインフォーマルな人間関係が統治のツールとなっているという理解が前提となっている。政治学ではパトロン=クライアント関係に対して議会制民主主義と官僚制が対置され、両者を導入することにより、統治の場からパトロン=クライアント関係を払拭できると考えられる。では、官僚制や民主主義が組織運営に導入されると、パトロン=クライアント関係を支えるモラリティは失われるのだろうか。本稿では、内戦後のシエラレオネでバイクタクシー業を統括する全国規模の職業団体「全国商業モーターバイクライダー協会」(以降、「全国バイク協会」と略称する)を取り上げ、その日常業務について考察する。内戦末期に隆盛したバイクタクシー業では、その管理・運営においてある種のパトロン=クライアント関係が重要な役割を果たした。しかし、民主主義と官僚制に基づく組織運営を求める国際社会の潮流ともあいまって、全国バイク協会が設立される際には、官僚制的な仕組みや役員選挙制度が導入された。ただし、これによって従来のパトロン=クライアント関係が払拭されたというわけではない。ライダーたちは、官僚的で非人格的な業務を行うべきである執行役員に対してクライアントシップをもって接する。それに対して執行役員もパトロンシップをもって応えようとする。全国バイク協会の日常的な活動から見えてくるのは、執行役員がパトロン=クライアント関係のモラリティと官僚制のロジックの両者を翻訳しながらライダーとの関係性を築いていることである。
2 0 0 0 OA 沼沢喜市先生を偲ぶ
- 著者
- 山田 隆治
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.84-86, 1980-06-30 (Released:2018-03-27)
- 著者
- 小池 淳一
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.119-123, 2002
- 著者
- 川橋 範子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.394-412, 2003-12-30 (Released:2018-03-22)
「文明化」された場所での「未開」の人々の展示が永続的な権力の不均衡をもたらす、とのクリフォードの主張はよく知られている。「エキゾティックな展示」の歴史は、地域研究において特にジェンダー化されて現れることが多い。欧米の日本研究においては現在でも植民地主義的フェミニズムの表象が流通しており、オリエンタリズム批判は充分有効であるといえる。近年、宗教研究の分野では、中絶された胎児である水子の供養儀礼をめぐって、日本の女性を胎児の崇りに怯える無抵抗な「異質な他者」と描くテキストが多くの支持を得ている。これは現在でもフェミニスト宗教研究に影響力をもつM.ディリーが女性と宗教に関する言説のなかで、非西洋の女性たちを受動的な犠牲者として不均衡な力関係のなかに封じこめて描いてしまったことと同質である。本稿では、地域研究、フェミニズム、宗教学、ポストコロニアル批判などのジャンルが交差する地点で、日本の女性と宗教をめぐる表象の問いに焦点をしぼり、地域研究がどのように「差異」を実体化して、「我々」から切り離された「どこか遠くの女性たち」という「他者」をつくりだすことに加担してきたか、を批判的に考察したい。この試みを通じて、フェミニスト民族誌の再編の一可能性を探っていく。
- 著者
- 星野 晋
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.3, pp.435-455, 2013-01-31 (Released:2017-04-10)
病むことに苦しむ患者を前にして、医師は対象を客観化し科学的にアプローチすることと人間として気遣うことという、二つの相矛盾する要求にさらされる。医師たちはどのようにこの二つの要求の折り合いをつけているのだろうか。医学教育において、この難問に正面から向き合うことになる最初の体験が肉眼解剖実習である。医学的には「人体の構造と機能の関連を理解する」ことを目標とする解剖実習は、実際の遺体を扱うという感情の起伏をともなう非日常的体験であり、医師になることが強く自覚される機会であるため、職業的アイデンティティが形作られるイニシエーションと位置づけられる。実習が進むにつれ、感情を排除し対象を医学的人体としてとらえる「解剖実習モード」が形成され、医学生たちは「日常生活モード」と自在に切り替える術を身につける。その過程で、解剖の対象はヒトでもモノでもない「ご遺体」としかいいようのない何かになっていく。かつては医学的人体であることを強調するドイツ語由来の「ライヘ」という表現が用いられていたが、「ご遺体」という独特の言い回しが一般化した背景には、解剖体が引き取り手のない遺体から献体によるものに変わったことも影響していると推察される。このことにより、学生は喪服を着て火葬に参列するなど、遺体をヒトとして扱うことへの要求は以前よりも増しているといえる。ところで、解剖実習モードへの切り替えの技術は、臨床における医師のまなざしや態度につながっていく。医師は「臨床モード」と「日常生活モード」を切り替えながら、二つの要求に対応するようになる。そして医療の対象はヒトでもモノでもない「患者」となる。近年医学教育や臨床過程において、これまで現場で経験知として学ばれ、実践されていたことがらは、可視化され標準化され、評価システムに組み込まれる傾向にある。教育や臨床の現場において、このことが一方で現実とのギャップを生み、他方で専門職のタスクを不必要に増大させていることが危惧される。こうした現状にあって、イニシエーションであり、古典的ともいえる体験学習スタイルを保持している肉眼解剖実習は、再評価されてしかるべきであると筆者は考える。
2 0 0 0 OA 序にかえて 現代的な「消費の人類学」の構築に向けて
- 著者
- 小川 さやか
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.1, pp.046-057, 2018 (Released:2019-02-24)
- 参考文献数
- 45