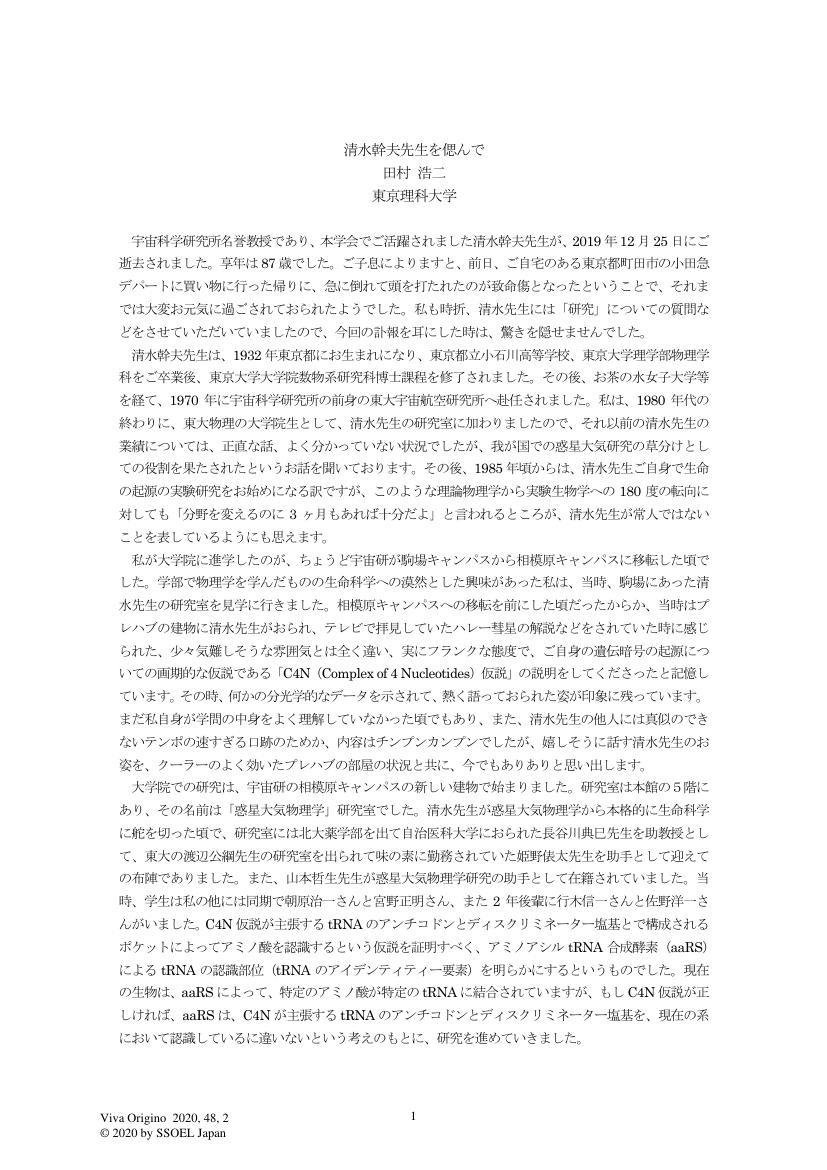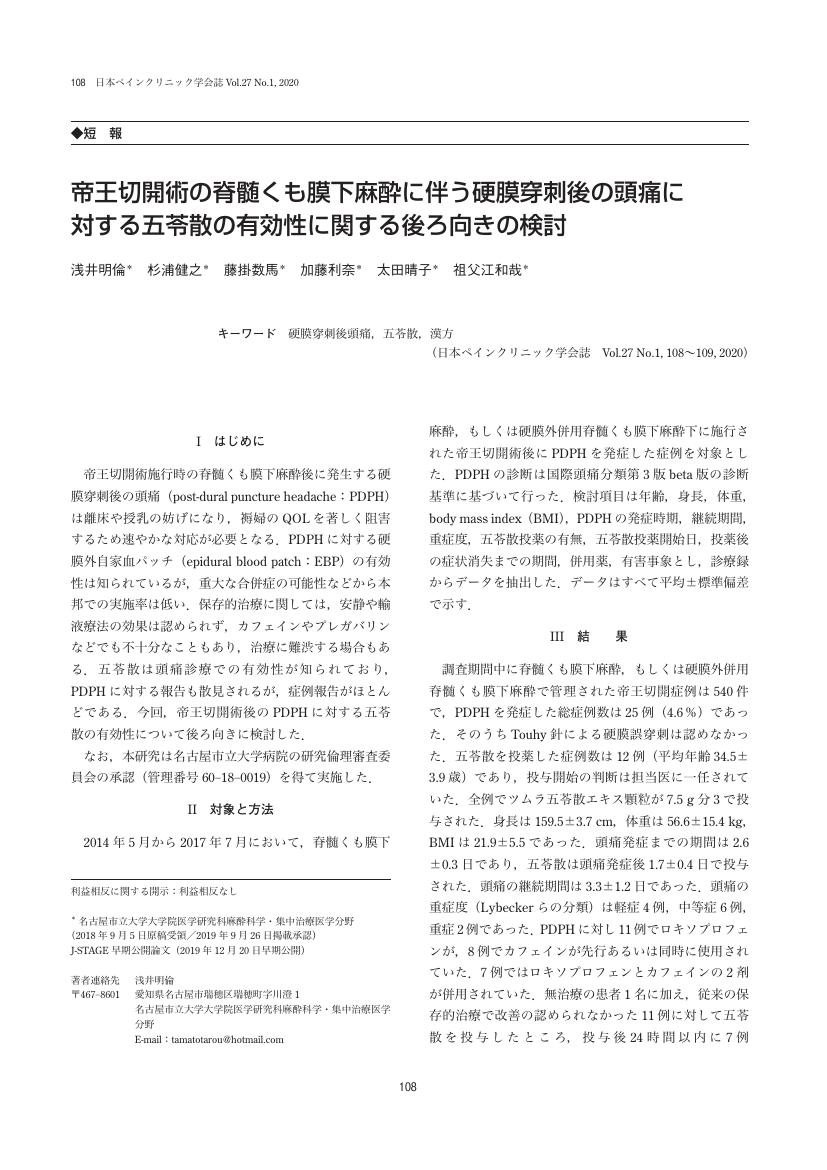1 0 0 0 生体反応の集積・予知・創出を基盤としたシステム生物合成科学
- 著者
- 葛山 智久
- 雑誌
- 学術変革領域研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2022-06-16
1 0 0 0 OA Chin down肢位とは何か ― 言語聴覚士に対するアンケート調査 ―
- 著者
- 岡田 澄子 才藤 栄一 飯泉 智子 重田 律子 九里 葉子 馬場 尊 松尾 浩一郎 横山 通夫 Jeffrey B PALMER
- 出版者
- 一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌 (ISSN:13438441)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.148-158, 2005-08-31 (Released:2020-12-26)
- 参考文献数
- 15
嚥下肢位として広く使用されているChin downを機能解剖学的肢位と関連づけることを目的に,摂食・嚥下障害を扱っている日本の言語聴覚士34名を対象に郵送と電子メールでアンケート調査した.回収率は88% (30名).1)Chin downの日本語名称は「顎引き」57%,「頚部前屈位」20%など様々で5通りの呼称があった.回答者の臨床経験年数,取り扱い患者数による傾向の違いはなかった.2)Chin downとして5つの頭頚部の機能解剖学的肢位像からの選択では,頭屈位53%,頚屈位30%,複合屈曲位17%の3肢位像が選択された.3)5つの頭頚部肢位像の呼称としては,肢位像おのおのが複数の名称で呼ばれ,逆に同じ呼称が複数の肢位像に対して重複して用いられ,1対1に対応させることが困難であった.4)Chin downに比べChin tuckという名称は知られていなかった.5)回答者のコメントとして「名称や肢位の違いは意識していなかった」などの感想があった.これらの結果は,Chin down肢位が機能解剖学的肢位としては極めて不明瞭に認識され,かつ,多数の異なった解釈が存在していることを意味した.Chin downをめぐっては,実際,その効果についていくつかの矛盾した結果が争点となっている.以上のアンケート結果は,その背景として様々な呼称と種々の定義が存在し,多くの混乱が存在する現状をよく反映していた.混乱の原因として,1)肢位が専ら俗称による呼称を用いて論じられ,また,具体的操作として定義されてきた,2)頭頚部肢位の運動が主に頭部と頚部の2通りの運動で構成されているという概念が欠如していた,3)訳語を選択する際に多様な解釈が介在した,などが重要と考えられた.今後,Chin downを機能解剖学的に明確に定義したうえで,その効果を明らかにしていく重要性が結論された.
- 著者
- 猪刈 由紀 踊 共二 佐藤 公美 皆川 卓 Yuki IKARI Tomoji ODORI Hitomi SATO Taku MINAGAWA
- 出版者
- 甲南大学文学部
- 雑誌
- 甲南大學紀要.文学編 = The Journal of Konan University. Faculty of Letters (ISSN:04542878)
- 巻号頁・発行日
- vol.172, pp.199-213, 2022-03-30
- 著者
- 岸本 尚子 季 思雨 辻 果歩 谷口 景一朗 佐藤 誠 前 真之 二宮 秀與 井上 隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.69, pp.745-750, 2022-06-20 (Released:2022-06-20)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
In recent years, passive designs, that acquire solar radiation from large windows during winter time, are becoming widespread. However, due to privacy issues, there are some houses in which curtains and other shading devices remain closed throughout the year. In this research, we focused on the roller blinds that can control the solar radiation and view, in response to the weather conditions and the surrounding environment, and measure the solar heat gain and the heat transfer by component of the windows with roller blinds under the actual environment.
1 0 0 0 OA 和洋木造家屋構造図解
- 著者
- 北与惣松, 加瀬正衛 共著
- 出版者
- 須原屋書店
- 巻号頁・発行日
- vol.説明, 1918
1 0 0 0 OA Crazy vocoder は砕けない~でもちょっとくだけた未来の話を~
- 著者
- 森勢 将雅
- 雑誌
- 研究報告音楽情報科学(MUS) (ISSN:21888752)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022-MUS-134, no.6, pp.1-6, 2022-06-10
現在の音声合成研究者が論文に Vocoder と記載するとき,その多くは Deep neural network (DNN) を用いて何らかのパラメータから高品質な音声波形を生成する Neural vocoder を指すのではないだろうか.もしそうであれば,音声符号化という役割ではなく,高品質な音声を合成したいという高品質 Vocoder が持つ『黄金の精神』が,Neural vocoder 世代に受け継がれたことを意味する.本稿では,恐らく今後失われていくであろう伝統的な Vocoder の波形生成部のアルゴリズム,および一連の知識がまだ音声研究において役立つかという将来展望について紹介する.
- 著者
- 北村 勝誠 伊藤 友弥 伊藤 浩明
- 出版者
- 一般社団法人日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.141-147, 2022-06-20 (Released:2022-06-20)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 3
【目的】小児アナフィラキシー症例における木の実類の現状を明らかにする.【方法】2017年4月~2021年3月に愛知県下の救急指定施設をアナフィラキシーで受診した15歳未満の全患者調査から,食物を原因とする2,480例のうち木の実類による308例を解析した.【結果】症例数は2017年度40例,2018年度74例,2019年度94例,2020年度100例と増加した.原因食物に占める割合は,2017年は木の実類が6.0%で鶏卵,牛乳,小麦につぐ第4位であったが,2020年は18.8%で第1位となった.年齢別原因食物では2020年に木の実類は1,2歳,3-6歳群の第1位となった.189例(61.8%)が入院し,うち3例が集中治療室に入院した.147例がアドレナリン投与を受け,エピペンⓇ所有は55例であった.木の実類の内訳はクルミ,カシューナッツ,マカダミアナッツ,ピスタチオの順に多かった.【結語】15歳未満のアナフィラキシー症例において,木の実類の割合が明らかに増加していた.
1 0 0 0 OA 清水幹夫先生を偲んで
- 著者
- 田村 浩二
- 出版者
- 生命の起原および進化学会
- 雑誌
- Viva Origino (ISSN:09104003)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.2, 2020 (Released:2021-11-05)
1 0 0 0 融合領域としての子どもの貧困研究
- 著者
- 阿部 彩
- 出版者
- 東京都立大学
- 雑誌
- 学術変革領域研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2022-06-16
1 0 0 0 OA ステップファミリーと「多様な家族」の限界 子どもの視点から壁を超える
- 著者
- 野沢 慎司
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会家族関係学部会
- 雑誌
- 家族関係学 (ISSN:09154752)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.13-23, 2021 (Released:2022-01-18)
- 参考文献数
- 45
1 0 0 0 OA 宇宙鉱物学が拓く銀河物質循環
- 著者
- 瀧川 晶
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 岩石鉱物科学 (ISSN:1345630X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.220225, 2022 (Released:2022-06-18)
- 参考文献数
- 68
Astromineralogy has developed as an interdisciplinary field between astronomy and mineralogy since the discovery of crystalline silicate dust from stellar atmospheres by infrared observations in the late 1990s. Cosmic dust repeatedly forms and is destroyed along with the physical evolution of stars, and thus is a carrier of metallic elements in the galactic material circulation. Minerals found in the solar system and on Earth are observed outside the solar system as well. In addition, presolar grains are the very survivors of circumstellar dust, and are the key to understanding the observed dust and its formation process. Understanding the galactic material circulation through the formation and evolution of cosmic dust requires knowledge not only of astronomy but also of petrology and mineralogy. In this paper, I review the progress of astromineralogy including the author's research and discuss how mineralogy has contributed to the development of astromineralogy.
1 0 0 0 OA 2018年コロンビア大統領選挙 ――左派は存在感を高めていくのか――
- 著者
- 古賀 優子
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- ラテンアメリカ・レポート (ISSN:09103317)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.26-40, 2019 (Released:2019-03-07)
- 参考文献数
- 3
2018年コロンビア大統領選挙は、FARCとの和平合意後に実施された最初の大統領選挙であった。当初は和平合意履行の是非が争点になるのではないかとみられていたが、実際は和平よりも急進左派の是非にたどり着いた。これまでみられなかった左派の躍進はコロンビアにあって注目すべき現象であったが、左派候補が勝利するには至らなかった。その背景には、歴史的に急進的な政治を好まない国民の意識が挙げられる。また、既成政党の組織票が力を失う一方で、SNSはまだ十分な影響力を獲得していない。今回の大統領選挙の背景には、このような政治の変化があったのではないか。政党離れは進行しており、右派・左派に関わらず、カリスマのある候補が出現すれば、将来的に大統領選挙で勝利する可能性もあると考えられる。
1 0 0 0 力が制御する生体秩序の創発
- 著者
- 茂木 文夫
- 雑誌
- 学術変革領域研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2022-06-16
1 0 0 0 OA リチャード•カンティロンとジェイムズ•ステュアート (平成一二年一〇月一二日 提出)
- 著者
- 小林 昇
- 出版者
- The Japan Academy
- 雑誌
- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.175-212, 2001 (Released:2007-06-22)
Ever since its 'discovery' by William S. Jevons toward the end of the 19th century, Richard Cantillon's sole published work, Essai sur la nature du commerce en général, 1755, has been given critical acclaim by such first-rate theoreticians as H. Higgs, J.A. Schumpeter, F. Hayek, T.W. Hutchison, and J.R. Hicks. It is widely recognized as an essential golden link between William Petty and Francois Quesnay in the history of economics. On the other hand, James Steuart's major work, An Inquiry into the Principles of Political Oeconomy, 2 vols., also published in the latter half of the 18th century, 1767, has long been neglected both in Great Britain and in France, and has been duely acknowledged only after the end of World War II. That it was given some notice in France during the French Revolution and translated into French by E.F. Sénover and published, and that even its another French translation was also completed (but not published) by Goguel, failed to secure a rightful place for Steuart in the history of political economy during his days and after.It is indeed of great academic interest and importance to place James Steuart in pre-Adam Smith political economy of the 18th century and to examine how Steuart's Principles is related with Cantillon's Essai, both positively and negatively. Because of the asymmetrical reception of these two works, however, this task has effectively only begun, and has thus far produced only A. Brewer's Richard Cantillon. Pioneer of Economic Theory, 1992. And it has recently been shown empirically by P. Groenewegen that the Cantillon to whom Steuart referred to was not Richard Cantillon but his brother-in-law, Philip Cantillon, and The Analysis o f Trade, 1759 by Philip explains in its inside of cover that the author followed Richard's work very closely, but it is of far inferior quality than the latter's Essai. Thus, it is hardly imaginable that Richard Cantillon's work had a direct impact on James Steuart's. However, within the context of chaos during the early phase of the establishment of political economy as a discipline in the 18th century, it is quite worth-while to examine whether or not Richard Cantillon had any indirect influence on James Steuart, and if so, in what forms.This being said, however, these two classics do not render themselves to ready comparison. Cantillon's Essai is characterized by the clarity and rigor of its purely theoretical analysis while Steuart's The Principles is an attempt at equally theoretical development but always on the basis of detailed historical and institutional, thus complex, reality of how national economies operated. Abundant fruit can be expected when today's observers free themselves from their narrow theory or theoretical outlook in assessing them.In this essay, I do not attempt a direct and detailed comparison of these classical masters. Instead I try to compare them on how they dealt with the following broader and urgent issues of political economy: a. the principle of wealth, b. population, c. money, d. industry, profit, and entrepreneur, e. circular flow, and f. the issues of economic liberalism versus mercantilism (or rather dirigisme in French context).We must also note that these two classical authors both were born outside England, obtained meaningful experiences particularly in France, and looked at the same subject matters of money, credit and the circular flow from their respective angles of observation. They are sure to give us fresh insights and perspectives on the so-called 'nationality of political economy' (Jevons).
- 著者
- 浅井 明倫 杉浦 健之 藤掛 数馬 加藤 利奈 太田 晴子 祖父江 和哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.108-109, 2020-02-25 (Released:2020-03-04)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 社会変化に伴う現代青年の特徴に関する一考察―多元的自己と「ネット的思考」の影響―
- 著者
- 髙木 由起子 廣瀬 幸市
- 出版者
- 愛知教育大学教育臨床総合センター
- 雑誌
- 愛知教育大学教育臨床総合センター紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.27-34, 2021-07
高校において表面的な関わりをし、深く思考しない、自分の感情を理解し表出することができない生徒が増えてきているように感じる。また、いくつかの調査から、青少年が幸せと感じる割合は年々増えているが、一方で自殺者数も増加し続けているという結果が読み取れる。そこで、青年の変化に関連すると思われる内容について文献を調査した。従来心理学では、大人になるということは一元的自己を獲得していくこととされてきたが、変化していく社会に適応する形として、多元的自己の傾向が指摘されている。また、インターネットで好まれる言語形式の影響を受け、深く考えない曖昧さを欠いた短絡的思考(本稿では「ネット的思考」と呼ぶ)が広まっているという指摘がある。これらを概観して、現代社会に適応する形態として現れたと言える、多元的自己と「ネット的思考」を特徴としてもつ現代の青年について、その課題を推察した。