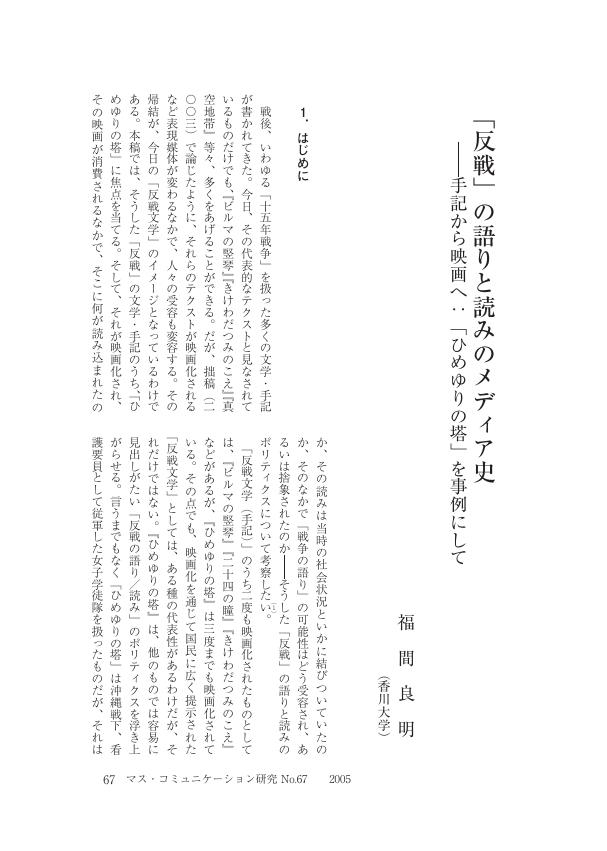- 著者
- 金 明蘭
- 出版者
- 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.44, 1997
1 0 0 0 OA リアルタイム呼吸性洞性不整脈抽出法を用いた作業負荷の制御
- 著者
- 小谷 潔 斉藤 毅 立花 誠 高増 潔
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.252-260, 2005 (Released:2007-01-19)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 3
Respiratory sinus arrhythmia (RSA) is well known as a noninvasive index of cardiac vagal activity, which has an important role in maintaining homeostasis. In this study, we improved the signal processing of RSA in the respiratory phase domain for real-time analysis and used results of this signal processing to control the mental arithmetic workloads of subjects. Four healthy subjects performed two experiments : a self-speeded workload and a real-time task controlled workload. In these experiments, we obtained R—R intervals from electrocardiograms with a sampling frequency of 1 kHz, and respiratory information from elastic chest band with a sampling frequency of 100 Hz. Further, we placed an accelerometer on the larynx and sampled at the rate of 100 Hz. First, we conducted the self-speeded task experiment for 10 minutes. Subjects were required to do mental arithmetic at their best pace and to take two rest periods, approximately 1-minute each. The amplitude of RSA after averaging 24 respirations was lower when the subjects were working than when they were resting (P <0.001); we found that the amplitude of RSA reflects even short-term working or resting. This suggests the possibility of controlling the mental workload by using RSA amplitude data. Second, the average of rest and working RSA amplitudes was set as a threshold. If the average RSA amplitude for a subject's last 24 respirations was higher than the threshold, we assigned a mental arithmetic task at a pace of 20 questions per minute; if the average was lower, we stopped the task. Results of the experiment showed that the RSA amplitude was controlled well by changing the workload. In both experiments, the value of the RSA amplitude varied among individuals and within individuals, but the sensitivity to a task remained unchanged within individuals.
1 0 0 0 軟属腫小体,軟属腫反応と軟属腫BOTEサイン
“みずいぼ”にみられる「軟属腫小体」「軟属腫反応」と比較的新しい概念(用語)である「BOTEサイン」について述べる.いずれも“みずいぼ”の病態に深く関わるもので,よりよい“みずいぼ”診療を目指すにあたり必要な知識である. “みずいぼ”は伝染性軟属腫の俗称で,ポックスウイルス科に属する伝染性軟属腫ウイルスの感染により生じる.中心臍窩を有する表面平滑な小丘疹を臨床的特徴とし,小児の体幹や四肢に多発することが多い.ピンセットで内容を圧出する“みずいぼとり”が治療の主なものであるが,本法が疼痛や出血を伴うことや,“みずいぼ”が基本的に自然治癒する疾患であることから,随伴症状に対する以外特段の治療なしで経過をみることもある.“みずいぼとり”では粥状物が圧出されるが,この中に含まれる多量のウイルスの直接・関接接触や自家接種が他者への感染伝搬や悪化(多発)の原因になる.
- 著者
- 福田 英嗣 鈴木 琢 佐藤 八千代 猿谷 佳奈子 向井 秀樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.11, pp.2195-2201, 2010-10-20 (Released:2014-11-28)
重症なアトピー性皮膚炎(Atopic dermatitis:AD)患者の入院治療は,短期間に皮膚症状を改善する有用な治療法である.しかし,入院中に使用される比較的多くの量のステロイド外用薬が生体に及ぼす影響については明らかではない.今回われわれはADの入院患者において,入院時(検査は入院翌日)および退院時の血中コルチゾール値を測定し,その推移について検討を行った.対象は,当院皮膚科に2007年5月から2008年8月までに入院加療した重症度の高いAD患者である.11歳から43歳(平均値±SD:27.4±7.5歳)の20名(男性12名,女性8名)に,入院時および退院時の朝7時から8時の間に血中コルチゾール値を測定した.結果は入院時の血中コルチゾール値は3.7±5.7 μg/dl(平均値±SD)と低下を示していたが,退院時は11.6±4.4 μg/dlと上昇した.この推移には統計上有意差を認めた(p<0.05).また,入院期間は13.3±4.7日(平均値±SD)であり,血中コルチゾール値が基準値である4.0 μg/dlに復するのに必要な入院期間は平均4.8日(推定)であった.入院中に使用したステロイド外用量はII群が8.6±6.3 g/日(平均値±SD),III群が4.8±5.8 g/日であり,ステロイド外用薬の使用量と血中コルチゾール値の変化量には差がなかった.今回の検討で, 入院を要する重症AD患者では,入院時には副腎皮質機能が抑制されているケースが多く,入院治療を行うことにより皮膚症状の改善が認められ,さらに入院時に基準値より低かった16症例のうち1例を除き退院時には基準値以上になり副腎皮質機能が正常に回復することが示された.重症AD患者においての入院療法は,短期間で効率的に皮膚状態を改善させるのみでなく,抑制状態にある内分泌系機能も同時に回復させることが示された.
1 0 0 0 OA 「反戦」の語りと読みのメディア史 手記から映画へ:「ひめゆりの塔」を事例にして
- 著者
- 福間 良明
- 出版者
- 日本マス・コミュニケーション学会
- 雑誌
- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, pp.67-83, 2005-07-31 (Released:2017-10-06)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 膀胱腫瘍の治療成績:東海地方会泌尿器腫瘍登録2,304例の検討
- 著者
- 鈴木 和雄 高士 宗久 小幡 浩司 深津 英捷 大串 典雅 置塩 則彦 栃木 宏水 酒井 俊助 篠田 正幸 牛山 知己
- 出版者
- 社団法人日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.1, pp.96-102, 1990
- 被引用文献数
- 3
1980年から1986年の7年間に東海地方会泌尿器腫瘍登録に登録された膀胱腫瘍2,304例について主に治療成績を中心に検討を行った.<br>膀胱腫瘍全体の5年相対 (実測) 生存率は73.8% (61.9%) であった. 深達度別ではTa; 101.9% (88.0%), T1; 87.6% (75.3%), T2; 57.9% (47.8%), T3; 33.7% (28.2%), T4; 6.1% (5.0%) であった. 組織型・異型度別ではG1; 93.7% (78.8%), G2; 87.2% (74.1%), G3; 47.3% (38.9%) となり, 移行上皮癌以外の膀胱悪性腫瘍は48.9% (42.4%), 複数組織型の混在した腫瘍は48.8% (41.3%) となっている. T2, G3以上で明らかに生存率は低下した. 移行上皮癌以外の膀胱悪性腫瘍および複数組織型の混在した腫瘍は移行上皮癌 grade 3とほぼ同様の結果であった. TUR施行症例の5年相対 (実測) 生存率は98.1% (82.2%) であった. 深達度別ではTa; 103.9% (89.7%), T1; 96.0% (82.6%), T2; 61.1% (49.1%), 異型度別ではG1; 102.2% (86.6%), G2; 104.3% (88.3%), G3; 56.9% (48.3%) であり, T1, G2以下がTURの適応と思われた. 膀胱全摘施行症例の5年相対 (実測) 生存率は62.4% (52.3%) であった. 深達度別ではTa; 102.3% (90.6%), T1; 77.8% (68.2%), T2; 56.3% (47.9%), T3; 41.8% (34.9%), T4; 15.2% (13.1%), 異型度別ではG1; 96.9% (80.9%), G2; 63.6% (55.7%), G3; 55.4% (47.1%) となっている. 進行癌症例の相対(実測)生存率は3年5.3% (4.8%), 5年0.87% (0.73%) と極めて予後不良であった.
- 著者
- 河野 俊行 加賀見 一彰
- 出版者
- 有斐閣
- 雑誌
- ジュリスト (ISSN:04480791)
- 巻号頁・発行日
- no.1342, pp.170-176, 2007-10-01
- 著者
- 中村 高康
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.2, pp.194-204, 2012-06-30 (Released:2018-04-04)
90年代以降の大学入学者選抜制度を取り巻く環境変化の中で最も基本的なことは、大学進学率の上昇に伴う長期的な入学者層の変化である。しかし、こうした入学者層の変化に対応した入試多様化・軽量化現象に対しては、これを批判的に見て学力重視の改革を唱える議論と、これを時代の趨勢と見て社会変動の兆候ととらえる議論とがある。いずれにも共通するのは現代を転機ととらえる思考であるが、その思考自体を相対化する必要がある。
1 0 0 0 OA 加重相乗平均の加重相加平均による近似 : 関数電卓なしに実効為替レートは近似計算可能か
- 著者
- 小川 健
- 出版者
- 専修大学社会科学研究所
- 雑誌
- 専修大学社会科学研究所月報 = The Monthly Bulletin of Social Science (ISSN:0286312X)
- 巻号頁・発行日
- vol.646, pp.1-14, 2017-04-20
本稿では関数電卓なしでの実効為替レートの近似計算公式を裏付けるために、加重相乗平均を加重相加平均で近似計算許容可能かどうかを検証する。本手法が成立すればGDP の平均成長率など経済学の多くで必要となる(加重の)相乗平均に対し通常の電卓で計算可能な(加重の)相加平均で近似計算が可能になり、殆ど関数電卓を持っていない中堅私大以下の低学年においても経済学の通常の小テスト及び定期試験での座学による計算問題の可能性が広がる。近似では自然対数のテイラー展開を利用した線形近似、つまり x≒1 のとき ln(x)≒x-1 の適用範囲に落とし込んで計算を行う。なおこの近似は本来、1次同次のコブ=ダグラス型関数に相当する加重相乗平均を、多変数関数と見なした時のテイラー展開を利用した線形近似で直ちに導出できるものである。検証の結果、この近似公式による誤差はかなり大きく見積もっても、1から最大で小数第n 位以内のずれに対しおよそ小数第2n 位までの誤差に収められることが分かった。これは高々数%以内のずれが多い数値例に対し、少なくとも教育上は加重相乗平均が加重相加平均で近似計算可能であることを意味する。
- 著者
- 金江 亮
- 出版者
- 桃山学院大学総合研究所
- 雑誌
- 桃山学院大学経済経営論集 = ST.ANDREW'S UNIVERSITY ECONOMIC AND BUSINESS REVIEW (ISSN:02869721)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.139-152, 2019-07-26
- 著者
- 森 武夫
- 出版者
- 日本犯罪心理学会
- 雑誌
- 犯罪心理学研究 (ISSN:00177547)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.12-22, 1966
<p>Y-G test was performed to 224 adolescent boys between 14 and 19 years old. The results were analysed by ages and 4 criminal types, that is, larceny (L), bodily injury and violencies (V), extortion (E) and sexual misconducts (S). (Table 2)</p><p>We made "A" and "B" scales for discriminating the 4 types. "A" scales made of responses of over 50 % to every type. (Table 3) "B" scale made of the responses statistically significant to every type. (Table 4) Each scale gives 4 scores; L-score, V-score, E-score, and S-score per a delinquent.</p><p>Both scales discriminated the types with fairly good level, namely, the highest score tended to point out his misdeed. (Table 5 & 7)</p><p>This suggests that there is a new type of criminal theory which depends on the idea of vector.</p><p>In the future, the other types of criminal behaivor, as vectors, will be added to this study.</p>
- 著者
- Koji Kimura Kouichi Hayashi Koji Hagihara Hitoshi Izuno Naohisa Happo Shinya Hosokawa Motohiro Suzuki Hiroo Tajiri
- 出版者
- The Japan Institute of Metals and Materials
- 雑誌
- MATERIALS TRANSACTIONS (ISSN:13459678)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.539-542, 2017-04-01 (Released:2017-03-25)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 10 16
We performed X-ray fluorescence holography measurements on a single crystal Mg85Zn6Y9 alloy, having a synchronized 18R long period stacking ordered structure, and successfully obtained Zn Kα holograms. The reconstruction shows “U”-shaped atomic images in remarkable contrast to the prediction of an existing model with Zn6Y8 L12 clusters. To explain this feature we calculated holograms using a model with positional fluctuations, and fit the reconstruction to the experimental results. It was found that large rotational fluctuations of the clusters can explain the “U”-shaped images.
1 0 0 0 OA 性問題行動における認知の役割に対する考察
- 著者
- 本多 隆司
- 出版者
- 桃山学院大学総合研究所
- 雑誌
- 人間文化研究 = Journal of Humanities Research St. Andrew's University (ISSN:21889031)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.261-276, 2017-03-10
1 0 0 0 OA [ちくほう地域研究] 昭和二八年 北九州や筑豊の大水害を撮った人々の記憶
- 著者
- 末永 裕貴 久門 守
- 出版者
- 近畿大学産業理工学部
- 雑誌
- かやのもり:近畿大学産業理工学部研究報告 = Reports of Faculty of Humanity-Oriented Science and Engineering, Kindai University (ISSN:13495801)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.66-73, 2016-07-15
1 0 0 0 OA <ちくほう地域研究> 資料と証言で振り返る「昭和二八年筑豊の大水害」
- 著者
- 久門 守
- 出版者
- 近畿大学産業理工学部
- 雑誌
- かやのもり:近畿大学産業理工学部研究報告 = Reports of Faculty of Humanity-Oriented Science and Engineering, Kinki University (ISSN:13495801)
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.57-65, 2014-07-01
1 0 0 0 OA [ちくほう地域研究] 筑豊の隣の街にあったヤマ--「小倉炭鉱」発掘記
- 著者
- 久門 守
- 出版者
- 近畿大学産業理工学部
- 雑誌
- かやのもり:近畿大学産業理工学部研究報告 = Reports of School of Humanity-Oriented Science and Engineering, Kinki University (ISSN:13495801)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.5-12, 2010-12-01
1 0 0 0 OA 自己組織化ニューラルネットワークの開発と鉱物同定への適用
- 著者
- 本庄 鉄弥 土屋 範芳 中塚 勝人
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- 資源と素材 (ISSN:09161740)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.4, pp.205-211, 1995-04-25 (Released:2011-01-27)
- 参考文献数
- 37
Self-Organizing Neural Network (SONN) was constructed for the purpose of mineral identification. This system consists of two different kinds of networks, Kohonen's Self-Organizing Map and three layer feedforward neural network based on the back-propagation learning algorithm. The former step, Self-Organizing Map, could divide minerals into some categories by the similarities on the selected characteristics of minerals. This rough division of whole input patterns on feature maps was closely analogous to the first step of classification by human brains. The later step, each category had the three layer feedforward neural network independently, and then the minerals belonging to the same category could be identified.In this study, 82 minerals were identified by 5 characteristics of cleavage, metallic luster, Mohs hardness, streak, and color. Some minerals have plural input patterns on the 5 characteristics mentioned above. Therefore, total number of input patterns was 119 for 82 minerals.After constructing the feature maps and the back-propagation learning, this system could suggest the suitable mineral name for unlearning input patterns. The advantage of the proposed method is that scaling up of the system is possible with relatively small increase in learning times. Further, it should be stressed that this technique can be used in other problems where recognition and identification are necessary.
- 著者
- 朝本 明弘
- 出版者
- メディカ出版
- 雑誌
- ペリネイタル・ケア (ISSN:09108718)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.8, pp.671-675, 1996-08
- 被引用文献数
- 3
1 0 0 0 OA 情報技術の導入時における社会的支援の在り方
- 著者
- 小松 裕子 小郷 直言
- 出版者
- 高岡短期大学
- 雑誌
- 高岡短期大学紀要 (ISSN:09157387)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.99-116, 1997