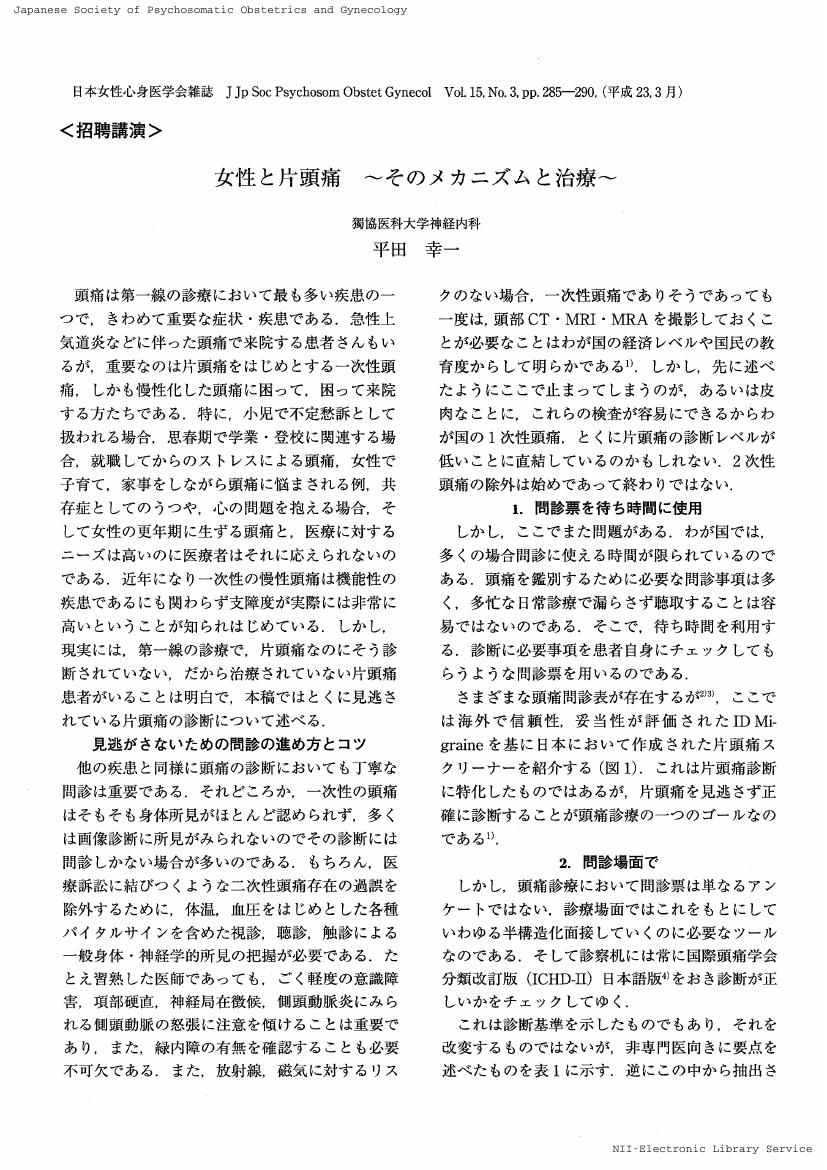1 0 0 0 IR ウィルバーのアートマン・プロジェクト
- 著者
- 清水 大介
- 出版者
- 花園大学文学部
- 雑誌
- 花園大学文学部研究紀要 = Annual journal Faculty of Letters, Hanazono University (ISSN:1342467X)
- 巻号頁・発行日
- no.51, pp.45-85, 2019
1 0 0 0 写真でみる貨物鉄道百三十年
- 著者
- 日本貨物鉄道株式会社写真でみる貨物鉄道百三十年編集委員会編集
- 出版者
- 交通新聞サービス (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2007
1 0 0 0 女子体育
- 著者
- 日本女子体育連盟 編
- 出版者
- 日本女子体育連盟
- 巻号頁・発行日
- vol.9(5), no.94, 1967-05
1 0 0 0 OA 田中里尚『リクルートスーツの社会史』2019,青土社
- 著者
- 矢吹 康夫[評者] ヤブキ ヤスオ Yasuo Yabuki
- 雑誌
- 社会学研究科年報
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.51-52, 2020
1 0 0 0 OA 讃岐の崇徳院をめぐる西行和歌の位相とその表現性
- 著者
- 平田 英夫
- 出版者
- 藤女子大学日本語・日本文学会
- 雑誌
- 藤女子大学国文学雑誌 (ISSN:02869454)
- 巻号頁・発行日
- no.99, pp.17-28, 2019-03
1 0 0 0 OA 膝前十字靱帯損傷症例における全身の関節柔軟性と膝関節弛緩性との関連性について
- 著者
- 曽我 孝 宮本 礼人
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.38 Suppl. No.2 (第46回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.CbPI1323, 2011 (Released:2011-05-26)
【目的】 関節包や靱帯などの軟部組織の伸張性や、筋緊張により関節可動範囲は変化し、正常可動範囲を超えると関節の緩みや亜脱臼を伴う。そして全身的に関節が緩い場合、靱帯損傷や亜脱臼などを生じる可能性が高くなる。 臨床場面では靱帯損傷症例を経験することがあるが、その中でも膝前十字靱帯(以下、ACL)損傷症例は多い。ACL損傷症例において膝関節弛緩性を評価することは重要であり、ACL再建術後も定期的に評価を行う。そこで今回ACL損傷症例の全身の関節柔軟性と膝関節弛緩性(特にACLに着目して)との間に関連性があるかどうかを検討した。【方法】 今回ACL損傷と診断され、当院で半腱様筋腱、薄筋腱を用いてACL再建術を施行した31名(男性11名、女性20名、平均年齢30.6±11.4歳)を対象とした。関節柔軟性の評価は中嶋のLooseness Testを使用し、手関節、肘関節、肩関節、股関節、膝関節、足関節に脊柱を加えた7部位を評価した。7項目中3項目以上が陽性であれば全身の関節柔軟性は高いと判定した。膝関節弛緩性の評価は膝関節前方弛緩測定器(KNEE LAX3、GATSO社製)を使用し、術前、術後6ヶ月の両膝関節前方移動量を測定した。KNEE LAX3における前方移動量は132Nの力を加えたときの数値(単位:mm)である。得られた結果からLooseness Testと前方移動量(健側、患側、患健差)の相関関係を調べた。統計学的分析としてピアソンの相関係数を用いて検定した。なお有意水準は5%未満(P<0.05)とした。【説明と同意】 対象者には本研究の主旨を十分に説明し、同意を得てから測定を実施した。測定に必要な個人情報、測定結果などは本研究のみに使用し、対象者のプライバシーが保護されていることを加えて説明した。【結果】 今回Looseness Testと術前後の両膝関節前方移動量との間には正の相関が認められると仮定していたが、実際相関が認められたのは術前患側(r=0.5896、P=0.0004)、術前患健差(r=0.4458、P=0.0119)のみであった。【考察】 術前患側の膝関節弛緩性が全身の関節柔軟性と正の相関があることより、ACLを損傷した場合、全身の関節柔軟性が高いほどACL以外の軟部組織の伸張性及び筋緊張が膝関節弛緩性に影響すると考えられる。関節柔軟性を決める要因としては靱帯や関節包、筋肉(筋膜)、腱、皮膚などが挙げられる。この中で特に関節柔軟性に関与しているのが靱帯や関節包で、次いで筋肉(筋膜)と言われ、腱や皮膚の影響は小さい。今回膝関節弛緩性についてはACLに着目して研究を行ったが、ACL本来の柔軟性は全身の関節柔軟性にそれほど関連がないことから、膝関節においては関節包や筋肉(筋膜)が膝関節柔軟性に大きく影響しているのではないかと考えられる。今後、関節包や筋肉などの軟部組織が関節柔軟性にどれほど関連しているかを検討していきたい。【理学療法学研究としての意義】 ACL損傷症例のほとんどがスポーツによる受傷であり、その大半がスポーツ復帰を強く希望されている。その為に再建術を施行されるが、症例によっては手術までに長期間を要する場合がある。関節柔軟性が高い場合、膝関節への負担を考慮すると関節の支持性を高めるTrainingが重要となってくる。また再断裂や反対側の予防的観点からも同じことが言える。
1 0 0 0 OA 光機能材料
- 著者
- 宮本 大樹
- 出版者
- 一般社団法人 粉体粉末冶金協会
- 雑誌
- 粉体および粉末冶金 (ISSN:05328799)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.174, 1999-02-15 (Released:2009-05-22)
1 0 0 0 OA 女性と片頭痛 : そのメカニズムと治療(<特集>第39回日本女性心身医学会学術集会報告)
- 著者
- 平田 幸一
- 出版者
- 一般社団法人 日本女性心身医学会
- 雑誌
- 女性心身医学 (ISSN:13452894)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.285-290, 2011-03-31 (Released:2017-01-26)
- 著者
- Ayako Aizawa
- 出版者
- Global Business Research Center
- 雑誌
- Annals of Business Administrative Science (ISSN:13474464)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.111-125, 2020-06-15 (Released:2020-06-15)
- 参考文献数
- 24
Fuel economy competition has heated up as a result of the oil crises of the 1970s, the environmental issues occurring since the 1990s, and the Japanese government’s economic policies, so that fuel economy has become a key competition index. However, for engineers who measure fuel economy, it is (i) a vague and unstable metric that fluctuates because of a number of factors and (ii) a quality that does not affect safety and so is not subject to recall. Competitive pressure regarding fuel economy led to arbitrary measurements. This eventually became normalized, and since 2016, cases of organizational corruption in the Japanese automotive industry have been uncovered one after another.
- 著者
- Wei Huang
- 出版者
- Global Business Research Center
- 雑誌
- Annals of Business Administrative Science (ISSN:13474464)
- 巻号頁・発行日
- pp.0200429a, (Released:2020-06-11)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2
Company A’s Project R is a freemium-model game business wherein the company makes money by (a) obtaining a large number of users who play its game essentially for free and (b) converting a small number of them into paying users. In Project R, paying ability boosting items were added to increase profits. Doing this initially increased monthly sales by 20%; however, after two months, the playing time of existing non-paying users declined, and more new non-paying users abandoned the game as well. It seems that the addition of paying ability boosting items could shorten a game’s life span by destroying the balance between (a) and (b) and causing a long-term decline in revenue. This paper runs a simulation to verify this.
- 著者
- Kenichi Kuwashima
- 出版者
- Global Business Research Center
- 雑誌
- Annals of Business Administrative Science (ISSN:13474464)
- 巻号頁・発行日
- pp.0200422a, (Released:2020-06-05)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 3
Large-scale university–industry collaborations that are worth some 10 billion yen and run for 10 years have begun to appear in Japan since the mid-2010s. This paper focuses on the drug development project being conducted by Chugai Pharmaceutical Co, Ltd. and Osaka University, which is a pioneering case of this kind of collaboration, and explores the background of how this project came to be. For the companies involved in university–industry collaborations, the most important point for consideration is generally whether or not they will achieve results (from the university’s contributions) that are sufficient to justify their investment. For Chugai Pharmaceutical, the deciding factor in making its 10-billion-yen investment was that Osaka University had been selected for the World Premier International Research Center Initiative (WPI) of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) and had built up research capabilities to make a sufficient contribution to Chugai. In that sense, we could say that this collaboration came into being because of the government’s support in building the innovation base and because of switching over from government sponsorship to corporate sponsorship after the operation of the base was on track. This so-called government-support-based, large-scale university–industry collaboration is a potential role model for university–industry collaborations in the future.
1 0 0 0 OA 石油中の非炭化水素成分
- 著者
- 冨永 博夫
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.8, pp.699-705, 1968-08-01 (Released:2009-11-13)
- 参考文献数
- 32
1 0 0 0 OA 江戸落語集 : 新訳
- 著者
- 村川 雄規 戸崎 晃明 福田 道雄 太田 昭彦
- 出版者
- 日本繁殖生物学会
- 雑誌
- 日本繁殖生物学会 講演要旨集 第103回日本繁殖生物学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.74, 2010 (Released:2010-08-25)
【目的】フンボルトペンギンの配偶システムは一夫一妻制(monogamy)とされるが、つがい外交尾を行うことが確認されており、その配偶システムはより複雑である可能性がある。本研究では、分子遺伝学的な手法による家系解析を用いて、飼育下でのこの種における配偶システムの詳細を解析した。【方法】新規に開発した親子鑑定のための15個のマイクロサテライトマーカー(総合父権否定確率 0.999998)を用い、葛西臨海水族園の飼育群のうち、行動学的に推定した48家族(両親のべ85羽、雛のべ123羽)の遺伝子型を比較検討し、家系解析を行った。【結果】雛123羽のうち122羽(99.2%)においてその遺伝子型において親子関係に矛盾が生じなかった。残る1羽(0.8%)No.328においては、推定された70♂と129♀の両親のうち、70♂との遺伝子型に矛盾が生じた。そこで、70♂以外の父親候補となりうる全ての雄個体との間で解析を行ったところ、No.328は180♂を父親とするつがい外受精の雛であることが強く示された。頻度自体は低いものの、つがい外受精が確認されたことから、飼育下におけるフンボルトペンギンは社会的monogamyではあるものの厳格な遺伝的monogamyとはいえないことが明らかとなった。また、フンボルトペンギンは絶滅危惧種の一種であり、ワシントン条約により国際商業取引が禁止されているため、今後飼育群に野生個体を加えることは極めて困難である。したがって、飼育施設では限られた個体数の中で、遺伝的多様性を維持しつつ継代・繁殖を続けていかねばならない。そのため個体間における血縁関係の正確な把握が重要となる。したがって、分子遺伝学的な手法を用いた家系解析は、配偶システムの解明のみならず、種の保全の観点から極めて有用であると考えられる。
1 0 0 0 OA 複合型塩素系除菌・洗浄剤の各種病原微生物に対する有効性
- 著者
- 小倉 憂也 小澤 智子 野島 康弘 菊野 理津子
- 出版者
- 一般社団法人 日本環境感染学会
- 雑誌
- 日本環境感染学会誌 (ISSN:1882532X)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.6, pp.391-398, 2015 (Released:2016-01-26)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 4 3
本研究では,ペルオキソ一硫酸水素カリウムを主成分とする環境除菌・洗浄剤(RST)の有効性について,メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA),多剤耐性緑膿菌(MDRP),ノロウイルス代替のネコカリシウイルス(FCV)およびC型肝炎ウイルス代替のウシウイルス性下痢症ウイルス(BVDV)を対象として評価した.懸濁試験において,1%RSTは,0.03%ウシ血清アルブミンを負荷物質とした試験条件では1分間の作用時間で,MRSA,MDRPに対して4 log10以上の殺菌効果を示し,またFCVに対し4 log10以上のウイルス不活化効果を示した.1分間作用の懸濁試験による評価において有効塩素濃度が同じ次亜塩素酸ナトリウム(NaOCl)よりもRSTはウイルス不活化効果が高かった.浸漬試験においてはキャリアに付着させたBVDVに対して0.1%NaOClは0.9 log10の,また1%RSTでは3.3 log10の減少であった.また,試験薬含浸ワイプによる拭き取り試験では,1%RST含浸ワイプは,FCVに対し4.5 log10以上の除去効果を示した.これらの結果からRSTは,病院環境における日常の衛生管理において,選択肢の一つになり得る製剤であることが示唆された.
1 0 0 0 OA <書評>現代歴史学の時代区分へ --『思想』特集「時代区分論」に寄せて--
- 著者
- 谷口 良生
- 出版者
- 京都大学大学院文学研究科西洋史研究室
- 雑誌
- フェネストラ : 京大西洋史学報 = Fenestra (ISSN:24344737)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.44-49, 2020-04-30
1 0 0 0 OA P基板/N基板を用いた逆導通サイリスタの過渡応答特性
- 著者
- 下田 義雄 佐藤 秀隆
- 出版者
- The Institute of Electrical Engineers of Japan
- 雑誌
- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.8-9, pp.1004-1009, 1999-08-01 (Released:2008-12-19)
- 参考文献数
- 12
Reverse conducting thyristors are analyzed using a two-dimensional simulator to investigate the effects of substrate types, P-type or N-type, on transient characteristics. The ramp currents with four kinds of rise-time are applied to the thyristors. The thyristor with a P-type substrate shows faster turn-on time and lower clamping-voltage change than that of an N-substrate for the applied ramp currents. The excellent transient response to the P-type substrate thyristor is caused by the accelerated carrier, which results from the high electric field appearing in the P-base region.
1 0 0 0 OA キェルケゴールによるショーペンハウアーノート
- 著者
- 桝形 公也
- 出版者
- 桃山学院大学総合研究所
- 雑誌
- 桃山学院大学キリスト教論集 = St. Andrew's University Journal of Christian Studies (ISSN:0286973X)
- 巻号頁・発行日
- no.54, pp.33-84, 2019-01-23
1 0 0 0 IR 岐阜城の空間認知 : 文献・絵図・考古資料を用いて
- 著者
- 内堀 信雄
- 出版者
- 金沢大学人文学類歴史文化学コース 大学院人間社会環境研究科 考古学研究室
- 雑誌
- 金大考古 = The Archaeological Journal of Kanazawa University
- 巻号頁・発行日
- no.64, pp.13-21, 2009-06-30
1 0 0 0 漢方薬由来成分(グリチルレチン酸)の胎児移行を認めた1症例
- 著者
- 岡野 友美 角 玄一郎 梶本 めぐみ 吉村 智雄 杉本 久秀 髙畑 暁 安田 勝彦
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.119-125, 2017
<p>漢方薬は西洋薬に比べて胎児への影響が少ないと考えられ,妊娠時にしばしば投与される.胎児への影響に関しては漢方薬の胎児への移行の有無や程度を理解しなければならない.しかし,漢方薬の胎児移行についてはわれわれの調べた範囲ではこれまでに報告がない.今回,初めて漢方薬由来成分の胎児移行を確認したので症例の臨床経過を文献的考察も含めて報告する.症例は35歳の初産婦,妊娠39週6日で女児3222gを自然分娩した.妊娠前からうつ,てんかん,橋本病があり,妊娠21週3日から分娩まで抑肝散,リスぺリドン,レボチロキシンの3種薬剤を継続服用していた.分娩後に当院で基本検査として実施している臍帯血検査でCRPは正常範囲内にもかかわらず,白血球増多症(26000/µl),好中球増多症(18070/µl),高コルチゾール血症(269 ng/ml)がみられた.しかし,無治療で分娩119時間後(出生5日目)には白血球,好中球,コルチゾールは全て正常化した.漢方薬の甘草由来成分のグリチルレチン酸による白血球増多症,好中球増多症ならびに高コルチゾール血症が疑われたため,検査機関に依頼したところ,液体クロマトグラフィー・マス・マススぺクトロメトリー法にて,臍帯血中にグリチルレチン酸が検出された.漢方薬を服用していない母親から生まれた児の臍帯血3例を対照として検査したところ,3例ともグリチルレチン酸は検出されなかった.また,本症例の血中グリチルレチン酸は分娩119時間後には検出されなかった.これらのことから,グリチルレチン酸が白血球増多症,好中球増多症,高コルチゾール血症に関与した可能性が示唆された.〔産婦の進歩69(2):119-125,2017(平成29年5月)〕</p>