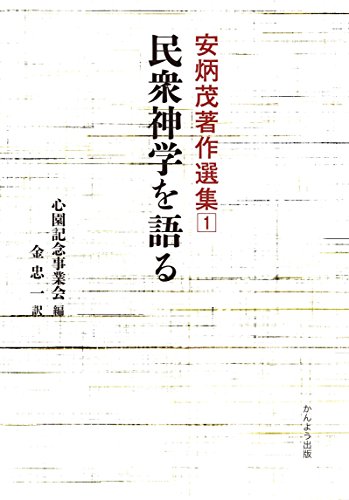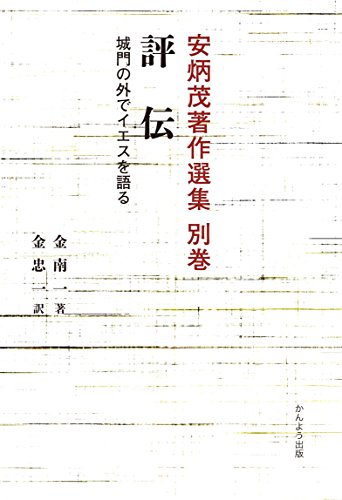2 0 0 0 史料散歩 「御屋しき」は江か於大か : 徳川家康自筆消息の宛名
- 著者
- 大野 瑞男
- 出版者
- 吉川弘文館
- 雑誌
- 日本歴史 (ISSN:03869164)
- 巻号頁・発行日
- no.778, pp.109-111, 2013-03
2 0 0 0 IR 戦国三武将のパーソナリティに関する精神分析的探究--原子価論の観点から
- 著者
- 黒崎 優美
- 出版者
- 奈良大学大学院
- 雑誌
- 奈良大学大学院研究年報 (ISSN:13420453)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.65-79, 2009
本稿の主な目的は、戦国時代を代表する武将である織田信長・豊臣秀吉・徳川家康のパーソナリティについて、原子価論の観点から考察を行うことである。「原子価」(valency)は、Bion,W(1961)により精神分析学に導入されHafsi,M(2006)によってパーソナリティ論へと発展した概念であり、対象間の繋がり方の類型、すなわち、「依存」(dependency)、「闘争」(fight)、「つがい」(pairing)、そして「逃避」(flight)を規定する。戦国三武将の個性を際立たせるホトトギス考をはじめ、主立った史実や歴史上のエピソードなどを素材として用いることにより検討を行った結果、信長には闘争、秀吉にはつがい、そして家康には依存の原子価を特徴づける内容が多くみられた。このことから、三者はそれぞれ異なる原子価をもち、それが仕事のやり方や対人関係のあり方に大きな影響を与え、さらにその生涯を終えてからも、後の人々によってそれぞれの原子価特性を強化するような史実の解釈や新たな歴史的エピソードの追加がなされながら現在に至っていることが明らかとなった。最後に、リーダーシップ論からみた三者の原子価について、さらに逃避原子価に相当するホトトギス考についても言及した。
- 著者
- 西田 友広
- 出版者
- 日本古文書学会
- 雑誌
- 古文書研究 (ISSN:03862429)
- 巻号頁・発行日
- no.59, pp.52-66, 2004-09
2 0 0 0 室町期興福寺の延年
- 著者
- 松尾 恒一
- 出版者
- 和光大学人文学部
- 雑誌
- 和光大学人文学部紀要 (ISSN:02881764)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.p182-170, 1993
2 0 0 0 興福寺本「僧綱補任」の性質について
- 著者
- 小山田 和夫
- 出版者
- 立正大学史学会
- 雑誌
- 立正史学 (ISSN:03868966)
- 巻号頁・発行日
- no.55, pp.p42-64, 1984-03
2 0 0 0 興福寺の維摩会の成立とその展開
- 著者
- 上田 晃円
- 出版者
- 南都仏教研究会
- 雑誌
- 南都仏教 (ISSN:05472032)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.p33-68, 1980-12
2 0 0 0 望陀布の復元に関する覚書
- 著者
- 井口 崇
- 出版者
- 千葉歴史学会
- 雑誌
- 千葉史学 (ISSN:02868148)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.79-89, 1998-05
2 0 0 0 評伝 : 城門の外でイエスを語る
2 0 0 0 IR 2.5次元ミュージカル活性化の諸相 : 演目と作曲家の多元性に着眼して
- 著者
- 増山 賢治
- 出版者
- 愛知県立芸術大学
- 雑誌
- 愛知県立芸術大学紀要 = The bulletin of Aichi University of the Arts (ISSN:03898369)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.97-113, 2015
- 著者
- 松田 誠
- 出版者
- 美術出版社
- 雑誌
- 美術手帖 : monthly art magazine (ISSN:02872218)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1038, pp.18-25, 2016-07
- 著者
- 瀬田 和久 野口 大二郎 藤原 稔
- 出版者
- 教育システム情報学会
- 雑誌
- 教育システム情報学会研究報告 (ISSN:13434527)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.4, pp.35-42, 2010-11
2 0 0 0 IR 『幸福を与える智慧』における国家論 : ウイグル哲学の頂点における理想的国家像
- 著者
- アブドゥラフマン ムフタル
- 出版者
- 九州大学哲学会
- 雑誌
- 哲学論文集 (ISSN:0285774X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.37-55, 2013-09
プラスチック難燃剤テトラブロモビスフェノールA (TBBPA) をオリーブオイルに懸濁させ、0 (対照群)、350、700及び1,400 mg/kg体重の投与用量、10 mL/kg体重の投与液量で、1日1回14日間、ICR雄マウスに胃ゾンデを用いて強制経口投与し、血液・血清生化学及び病理学的に検索した。<BR>その結果、投与群で血清総コレステロール及び肝臓重量の増加が認められた。主要臓器の組織観察では、投与群の肝臓に肝細胞の腫脹、炎症性細胞の浸潤及び肝細胞の壊死が多く認められた。
2 0 0 0 貯蔵に伴う蒸留酒のマクロなクラスターサイズの変化
- 著者
- 秋山 稔 三上 慶浩
- 出版者
- Brewing Society of Japan
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.3, pp.178-185, 2006
貯蔵に伴う蒸留酒のクラスターサイズの変化を定量的に決定するために<BR>(1) マクロなクラスターサイズを (1) 式と (2) 式で定義した。<BR>(2) エタノール水溶液での水分子とエタノール分子の水和クラスターへの分率であるP<SUB>w</SUB>とP<SUB>E</SUB>とを贋-NMRにおける化学シフト値の濃度変化から (5) 式により求めた。<BR>(3) 蒸留酒として, ウィスキーを選び, ウィスキーでの分率P<SUB>w</SUB>*とP<SUB>E</SUB>*とをP<SUB>w</SUB>とP<SUB>E</SUB>を基礎にし, ウィスキーとエタノール水溶液から蒸発する水分子数の比とエタノール分子数の比を測定することによって, (12) 式から算出した。<BR>(4) 算出されたP<SUB>w</SUB>*とP<SUB>E</SUB>*から (4) 式により, ウィスキーでの3種のマクロなクラスターサイズを求めた。<BR>(5) 本研究で定義されたマクロなクラスターサイズの25年の貯蔵に伴う変化はエタノールクラスターで大きく減少しているが, 水和クラスターと水クラスターではそれに較べて小さい。
2 0 0 0 OA 戦略的演劇論I : 映画と比較した演劇の独自性
- 著者
- 稲山 訓央
- 出版者
- 聖泉大学
- 雑誌
- 聖泉論叢 (ISSN:13434365)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.185-203, 2003
含意が広く散漫となりがちな、演劇という事象について、文化的に類似性の高い映画と比較することで、演劇のみが為しえ、伝えうるものは何かということを論ずる。映画は瞬間の積み重ねを撮影していくことで成り立つものである。したがって、実際に起こった出来事を記録した映画というものも存在するし、また演じ手も、演技をコマ切れに行っていくことが可能である。対して演劇は、劇場の中で、観客と舞台という虚構の場をあえて設定し、演技を一連のものとして、寸断することなく行わなくてはならない。つまり、映画よりも、演劇のほうが虚構性が高いと言える。さらに、映像・音響技術が発達した今日、演劇でしか表現できないことに、「匂い」があると考える。劇場の広さに条件はあるものの、「匂い」を使うことで、演劇の独自性や面白さを追求することができるのではないだろうか。
- 著者
- 許 雪姫 杉本 史子
- 出版者
- 愛知大学現代中国学会
- 雑誌
- 中国21 (ISSN:13428241)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.97-122, 2012-03
2 0 0 0 新興満洲国女性の表象形成と亡命ロシア女性 : 『満洲グラフ』より
- 著者
- 生田 美智子
- 出版者
- ハルビン・ウラジオストクを語る会
- 雑誌
- Север (ISSN:18835287)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.5-21, 2013-03
2 0 0 0 「満洲国」の対日留学政策
- 著者
- 浜口 裕子
- 出版者
- 拓殖大学政治経済研究所
- 雑誌
- 政治・経済・法律研究 (ISSN:13446630)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.57-81, 2013-03
- 著者
- 川副 令
- 出版者
- 早稲田大学出版部
- 雑誌
- 平和研究 (ISSN:03850749)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.103-125, 2013