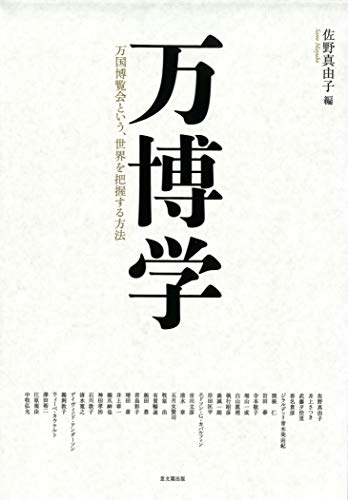1 0 0 0 OA 大学キャンパスのバス待ち列の現況と各キャンパスの対策
- 著者
- 司 隆 佐藤 雅明 伊藤 昌毅 厳 網林
- 雑誌
- 研究報告高度交通システムとスマートコミュニティ(ITS) (ISSN:21888965)
- 巻号頁・発行日
- vol.2017-ITS-71, no.18, pp.1-8, 2017-11-08
大学キャンパスへのバスが混雑している地域の分布とその対策について,11 の大学キャンパスにおいて調査した.都市郊外型の大学キャンパスにおいてバス待ちができるキャンパスが点在し,各々列を整備する人を配置して対応するキャンパスが相当数存在した.またバスの時刻表を調べるアプリケーションが実装されている大学も多かったが,バス待ち列に対応するアプリケーションはあまり製作されていない状況であることがわかった.
1 0 0 0 OA ウィリアム・ワーズワスの「不滅のオード」について
- 著者
- 布施 伸之
- 出版者
- 信州豊南女子短期大学
- 雑誌
- 信州豊南女子短期大学紀要 = Bulletin of Shinshu Honan Women's Junior College (ISSN:02897644)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.75-95, 1990-03-01
1 0 0 0 万博学 : 万国博覧会という、世界を把握する方法
- 出版者
- 思文閣出版
- 雑誌
- 万博学 : 万国博覧会という、世界を把握する方法
- 巻号頁・発行日
- 2020-08-01
・序説・万国博覧会という、世界を把握する方法 / 佐野真由子・万国博覧会と「ピアノ」の誕生 / 井上さつき ・新興産業としての七宝業と博覧会 : 技芸と技術と近代工芸 / 武藤夕佳里 ・勧農開物翁の幕末・明治 : 田中芳男と博覧会・博物館 / 沓名貴彦 ・万国博覧会とオスマン帝国人の世界観 / ジラルデッリ青木美由紀 ・渋沢栄一と万国博覧会 : パリ万博(1867年)からパナマ太平洋万博(1915年)まで / 関根仁 【BIEの設立と万博の20世紀】・国際博覧会の歴史に博覧会国際事務局(BIE)が果たした役割 / 岩田泰 ・フランスと1928年国際博覧会条約 / 寺本敬子 ・紀元2600年記念日本万博の計画とその周辺 : 1930年代の国際博覧会日本展示をめぐる連続性 / 増山一成・戦時宣伝と写真壁画 : 山端祥玉と1939年ニューヨーク万国博覧会の《躍進日本》を中心に / 白山眞理 ・万博日本館にみる「展示デザイン」の変遷 / 構成・執筆:執行昭彦, 森誠一朗, 岸田匡平 ・ポストコロニアル時代のアイデンティティ・ポリティクスと万国博覧会におけるフィリピン館 : 1958-1992 / エドソン・G・カバルフィン ・[コラム]モントリオールの困惑 : 1967年博の日本館展示問題 / 市川文彦 【特集 1970年大阪万博】・[コラム]大阪万博への飛翔 / 清水章 ・1970年大阪万博の基本理念 : 「万国博を考える会」による草案作成の背景と経緯 / 五月女賢司 ・昭和天皇と万国博覧会 / 牧原出 ・リニアと原爆 : 大阪万博日本館における科学技術展示の生成 / 有賀暢迪 ・大阪万博における企業パビリオンのブループリント / 飯田豊・1970年日本万国博覧会における仏教的造形物の役割 / 君島彩子・1970年キリスト教界における戦後主体性論争 : 大阪万博キリスト教館と万博反対運動 / 増田斎・建築家と万国博覧会 : EXPO'70の黒川紀章から考える / 井上章一 ・1970年日本万国博覧会の先進性と評価をめぐって : 産業技術史の視点から / 橋爪紳也 【世界を映し続ける万博】・《堺屋太一オーラル・ヒストリー 》万博に戦後史を読む : 沖縄海洋博(1975年)を中心に / 聞き手 : 牧原出, 佐野真由子 ・沖縄国際海洋博覧会と沖縄観光 / 神田孝治・展示装飾業からディスプレイ業へ : 大阪万博前後からの展開 / 石川敦子 ・万国博覧会に関する来場経験者の長期記憶 : モントリオール、大阪、バンクーバー、ブリスベン、愛知の万博を題材に / 清水寛之, デイヴィッド・アンダーソン ・[コラム]上海万博の「セルヴィス・ルソー」 : グローバル・アート・ヒストリーへの階梯 / 鵜飼敦子 ・物語作りとデザイン : ミラノ万博 / ウィーベ・カウテルト ・博覧会の「ゆきさき」を考える : 博覧会をつくる現場から / 澤田裕二 ・万博における中国要素(プレゼンス) / 江原規由 ・万国博覧会の遺産としての博物館 : 夢の後始末をめぐって / 中牧弘允・近代博から現代博への運営システム転換1851~2017 : 褒賞制・売却制・展示法に映った<世界> / 市川文彦 あとがき研究会の記録索引(博覧会/人物) 執筆者紹介英文目次
1 0 0 0 OA 形容詞の連用形名詞法について
- 著者
- 林 謙太郎 ハヤシ ケンタロウ Kentarou Hayashi
- 雑誌
- 二松學舍大學論集
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.95-114, 1998-03-31
1 0 0 0 OA 岩手大学図書館旧宮崎文庫所蔵『十和田山本地由来記』の翻刻(一)
- 著者
- 家井 美千子
- 出版者
- 岩手大学人文社会科学部
- 雑誌
- Artes Liberales = アルテスリベラレス (ISSN:03854183)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, pp.55-71, 2017-06-30
1 0 0 0 OA 岩手大学図書館旧宮崎文庫所蔵『十和田山本地由来記』の翻刻(二)
- 著者
- 家井 美千子
- 出版者
- 岩手大学人文社会科学部
- 雑誌
- Artes Liberales = アルテスリベラレス (ISSN:03854183)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, pp.173-186, 2017-12-25
1 0 0 0 OA pHメーターのわかりやすい説明
- 著者
- 林 久史 ハヤシ ヒサシ Hisashi Hayashi
- 雑誌
- 日本女子大学紀要. 理学部 = Journal of Japan Women's University. Faculty of science
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.43-48, 2012-03-31
1 0 0 0 OA 蘇我氏と外来文化に関する研究
- 著者
- 小林 幹男
- 出版者
- 長野女子短期大学出版会
- 雑誌
- 長野女子短期大学研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.57-76, 2000-12-20
蘇我氏の系譜は、『古事記』の孝元天皇、あるいはその孫にあたる武内宿禰を祖とする説、『上宮聖徳法王帝説』などの石河宿禰を祖とする説、あるいは満智を祖とし、満智が百済の木満致と同一人物であるとする説などがある。その本居地についても、大和国高市郡の蘇我の地、大和国葛城地方、河内国石川地方とする説がある。『日本書紀』の記事によると、百済・新羅・高句麗からの氏族の渡来、および仏教をはじめとする多く文化や技術を受容したのは、応神天皇から推古天皇の時代に目立って多い。この時期は、中国や朝鮮半島の諸国が、互いに抗争を繰り返した激動の時代であり、わが国も中国や半島諸国と通交して、積極的な外交政策を展開した時期である。その前段の時代、すなわち応神天皇から雄略天皇の時代は、中国の史書『宋書』などに記されている「倭の五王」の時代と対応する年代であり、欽明天皇から推古天皇の時代は、蘇我氏が渡来系氏族を配下において、大陸文化の受容と普及に努め、開明的な屯倉経営を推進して農民の名籍編成などを行い、積極的に農業生産力の増強を図って中央政界をリードした時期である。蘇我馬子が建立した飛鳥寺は、高句麗方式の伽藍配置を採用し、北魏様式の飛鳥大仏を造り、百済から渡来した僧侶や技術指導者たちを動員して完成した。蘇我氏の開明的性格を如実に物語る歴史的事実である。4~7世紀のわが国古代の文化は、「倭の五王」などの渉外関係史、蘇我氏と渡来系氏族の研究を基礎にしてこそ、その歴史の真実に迫ることができるものと考える。
1 0 0 0 OA ブロックチェーンと秘密分散法を用いた情報ライフサイクル制御
- 著者
- 今田 丈雅 松浦 幹太
- 雑誌
- コンピュータセキュリティシンポジウム2017論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.2, 2017-10-16
われわれは今日なんらかのコミュニケーションツールを使って情報の伝達をしている. 情報伝達にあたっては中央サーバーを経由しており, ユーザーからはデータの制御権が離れてしまう. このため後から政府の検閲によってセンシティブなデータが見られてしまう可能性がある. そのような脅威に対抗するためにはデータに期限を設定し, 自動で消去されるような仕組みが必要である. 本研究では公開分散型台帳と秘密分散法を組み合わせることによって上記の要請を満たすプロトコルを提案する. このシステムは従来研究と異なり, 信頼できる第三者機関やセキュアなハードウエアを必要とせずシビル攻撃にも耐性があるという性質を持つ.
1 0 0 0 OA CFT を多用する組織における仕事満足の向上
- 著者
- 石塚 浩
- 出版者
- 文教大学経営学部
- 雑誌
- 経営論集 = Journal of Public and Private Management (ISSN:21892490)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.1-15, 2015-03-01
ネットワークの視点から、CFT のもたらす効果と副作用、副作用を減じる方法について考察し、収集したデータをもとに分析した。CFT では橋渡し型ネットワークが活用されているといえるが、同様のネットワークは、人事異動においても形成されている。CFT および人事異動が盛んな企業ほど業績が高いが、その理由は橋渡し型ネットワークの形成によるものと考えられる。CFT と人事異動は、個人の仕事満足にプラスの影響を与えているが、関係づくりの負担などの副作用もあると考えられる。組織レベルでビジョンを共有し相互信頼を実現すれば、このような副作用を抑えることができる。ビジョン共有と相互信頼の実現は、トップと直属上司のリーダーシップのあり方、そして両者のリーダーシップの整合性に依存している。 Many organizations use cross-functional teams (CFTs) to realize creative management that causes innovation. The effects of CFTs primarily depend on associating members who belong to different artments of an organization. New information, unique ideas, and different views are gathered and considered to solve problems.We think that these bridging network effects can be found by conducting frequent changes in personnel. This paper considers the negative effects of CFTs on job satisfaction.Despite several researches having advocated the positive effects of CFTs, they may create stress among participants and cause the participants to become increasingly busy. They may become exhausted with the new relationships created by CFTs. We gathered data on CFTs, changes in personnel, and job satisfaction. In addition, we conducted statistical analyses on these data. The result reveals that common vision and mutual trust in firms contribute toward job satisfaction. Common vision andmutual trust that are created through proper leaderships compensate for the negative effects of CFTs.
1 0 0 0 OA 浦野聡編 『古代地中海の聖域と社会』 (勉誠出版、二〇一七)
- 著者
- 桜井 万里子 サクライ マリコ Mariko Sakurai
- 雑誌
- 史苑
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.1, pp.259-264, 2018-02-26
1 0 0 0 OA 脂肪性肝疾患の栄養管理: 脂質と糖質の摂取に関する最新の知見
1 0 0 0 OA プログラム学習における専門的概念導入に用いられる言語表現の調査
1 0 0 0 OA 発信者情報開示を命じる仮処分について
- 著者
- 清水 宏
- 出版者
- 東洋大学通信教育部
- 雑誌
- 東洋通信 = Toyo University Correspondance Course News Letter (ISSN:18837859)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.25-36, 2016-10
- 著者
- 中谷 裕教 山口 陽子 Nakatani hironori Yamaguchi yoko
- 雑誌
- 【C】平成21年電気学会電子・情報・システム部門大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- pp.211-214, 2009-09-03
我々は外界の情報の多くを視覚を通して得ている。しかし視野内の全ての物を処理すると時間がかかり刻一刻変化する環境に対応できない。正確さを欠いたとしても、直感的にかつ瞬時に外界を認識し判断を下すには、何らかの価値観に基づいて処理すべき優先順位を事前に設定し、優先度の高いものを処理すべきである。本研究では、処理の優先順位の定量的評価から各被験者の価値観を推定し、価値観の違いによる脳活動の違いを比較した。
1 0 0 0 OA 初級中国語における教授法の探索
- 著者
- 張 [ロ] Zhang Lu
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学研究部論集 A:人文科学編 = The Bulletin of Central Research Institute Fukuoka University Series A:Humanities (ISSN:13464698)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.11-20, 2012-12
1 0 0 0 OA 山の奥の奥まで入所勧奨は追いかけてきた : ハンセン病療養所「星塚敬愛園」聞き取り
- 著者
- 福岡 安則 黒坂 愛衣
- 出版者
- 埼玉大学大学院文化科学研究科
- 雑誌
- 日本アジア研究 : 埼玉大学大学院文化科学研究科博士後期課程紀要 = Journal of Japanese & Asian Studies (ISSN:13490028)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.191-209, 2013
ハンセン病療養所のなかで60年ちかくを過ごしてきた,ある女性のライフストーリー。 山口トキさんは,1922(大正11)年,鹿児島県生まれ。1953(昭和28)年,星塚敬愛園に強制収容された。1955(昭和30)年に園内で結婚。その年の大晦日に,舞い上がった火鉢の灰を浴びてしまい,失明。違憲国賠訴訟では第1次原告の一人となって闘った。2010年8月の聞き取り時点で88 歳。聞き手は,福岡安則,黒坂愛衣,金沙織(キム・サジク),北田有希。2011年1月,お部屋をお訪ねして,原稿の確認をさせていただいた。そのときの補充の語りは,注に記載するほか,本文中には〈 〉で示す。 山口トキさんは,19歳のときに症状が出始めた。戦後のある時期から,保健所職員が自宅を訪ねて来るようになる。入所勧奨は,当初は穏やかであったが,執拗で,だんだん威圧的になった。収容を逃れるため,父親に懇願して山の中に小屋をつくってもらい,隠れ住んだ。そこにも巡査がやってきて「療養所に行かないなら,手錠をかけてでも引っ張っていくぞ」と脅した。トキさんはさらに山奥の小屋へと逃げるが,そこにもまた,入所勧奨の追手がやってきて,精神的に追い詰められていったという。それにしても,家族が食べ物を運んでくれたとはいえ,3年もの期間,山小屋でひとり隠れ住んだという彼女の苦労はすさまじい。 トキさんは,入所から2年後,目の見えない夫と結婚。その後,夫は耳も聞こえなくなり,まわりとのコミュニケーションが断たれてしまった。トキさんは,病棟で毎日の世話をするうちに,夫の手で夫の頭にカタカナの文字をなぞることで,言葉を伝える方法を編み出す。会話が成り立つようになったことで,夫が生きる希望をとりもどす物語は,感動的だ。 トキさんは,裁判の第1次原告になったのは,まわりから勧められたからにすぎないと言うけれども,その気持ちの背後には,以上のような体験があったからこそであろう。
1 0 0 0 OA 大学と企業の連携による新たな交流機会と場の創出
- 著者
- 長尾 洋子 畑中 朋子 平井 宏典
- 出版者
- 和光大学社会経済研究所
- 雑誌
- 和光経済 = Wako Keizai (ISSN:02865866)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.17-45, 2020-09
Universities are expected to play a role in society as a cultural resource which offers new ideas and values created through intellectual activities. However, it is concerning that such expectations are not fully met because the learning environment of Japanese universities tends to be homogenous and uniform. This paper addresses such lack of diversity by examining an action research project aimed at creating a space for stimulating new ideas and values through the collaboration between Wako University and a local restaurant/café business in Machida City, a suburb of Tokyo. The project developed an original learning program modelled on informal conversations in a living room or café. It was designed for students and the public to meet people with different backgrounds, listen to each other and share ideas and values. The keys to making this work were changing the contexts of learning and facilitating multi-directionalexchanges among participants.
1 0 0 0 OA 有機ゲルマニウム配合化粧料の皮膚保湿効果
- 著者
- 山下 裕司 山崎 舞 鈴木 真綾 萩原 宏美 田上 八郎 平尾 哲二 坂本 一民
- 出版者
- 千葉科学大学
- 雑誌
- 千葉科学大学紀要 = The University Bulletin of Chiba Institute of Science (ISSN:18823505)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.67-74, 2016-02-28
古来から天然の薬として服用されてきた有機ゲルマニウムは、角層中のコーニファイドエンベロープ形成や細胞間脂質を構成するセラミド合成促進などの効果が近年見出され、皮膚への有効性が期待されている。昨年、我々は有機ゲルマニウムを配合したクリームを皮膚に塗布した際の角層水分量と経表皮水分蒸散量(TEWL)の変化について調べ、有機ゲルマニウムに角層の保湿性を向上する傾向があることを報告した。本研究では、剤型をクリームから化粧水に変更し、市販の有機ゲルマニウム含有化粧水と含有されない化粧水を用いて角層水分量、TEWL、皮膚粘弾性、および皮膚色の変化から皮膚への塗布効果を調べた。4週間の連用塗布によって、有機ゲルマニウム配合化粧水は未配合化粧水に比べて有意に角層水分量は増加したが、その他の評価項目に関しては著しい差は見られなかった。また、本研究では、この角層水分量の増加に対して表皮中のフィラグリンから産生されるピロリドンカルボン酸量との関係について調べた。化粧水中の有機ゲルマニウムの有無に関係なく皮膚の保湿能に関係するピロリドンカルボン酸量は変化しておらず、有機ゲルマニウム配合化粧水の高い保湿機能が天然保湿成分の量的変化に関与していないことが示唆された。
1 0 0 0 OA 高度成長期における教員の社会的地位をめぐる一考察 : 教員養成の「修士レベル化」に寄せて
- 著者
- 河野 誠哉 カワノ セイヤ Seiya Kawano
- 雑誌
- 大学改革と生涯学習 : 山梨学院生涯学習センター紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.第17号, pp.29-44, 2013-03-27