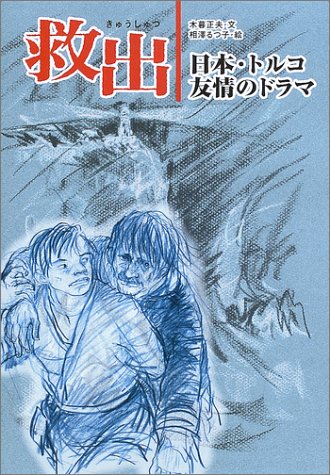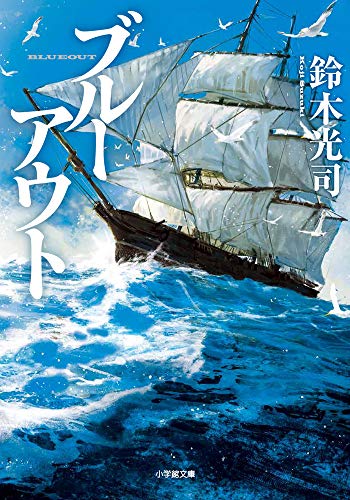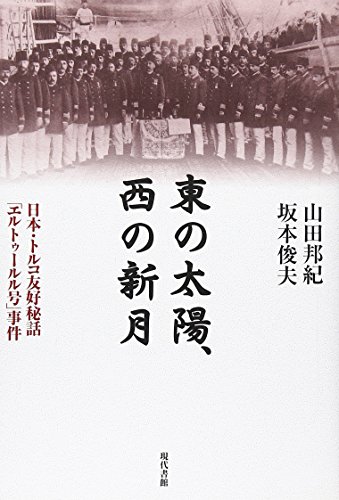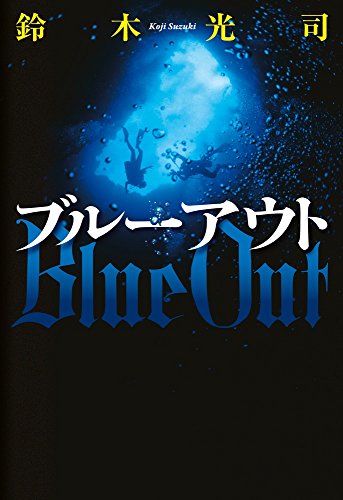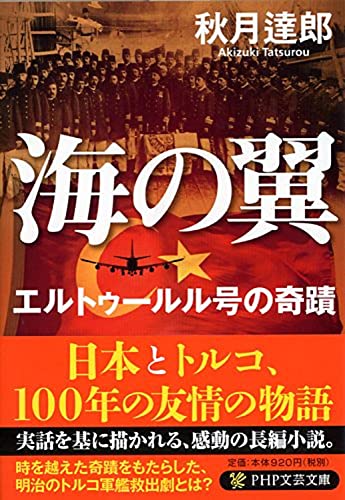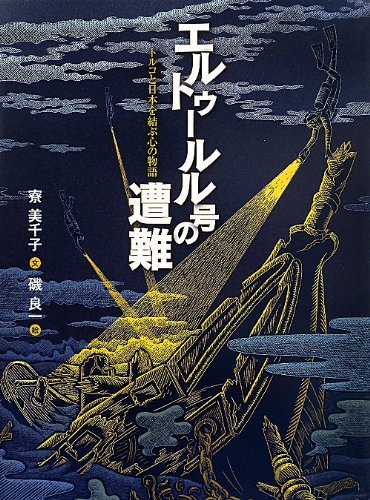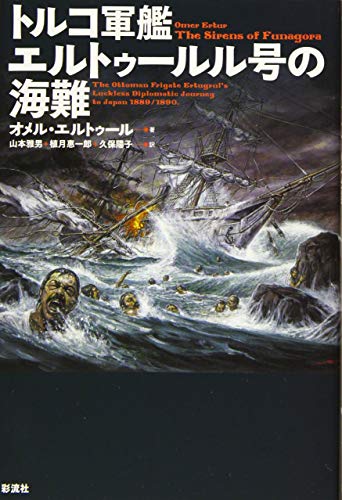- 著者
- 姉帯 沙織
- 出版者
- コ・メディカル形態機能学会
- 雑誌
- 形態・機能 (ISSN:13477145)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.22-25, 2023 (Released:2023-08-21)
- 参考文献数
- 10
1 0 0 0 救出 : 日本・トルコ友情のドラマ
- 著者
- 山田邦紀 坂本俊夫著
- 出版者
- 現代書館
- 巻号頁・発行日
- 2007
1 0 0 0 海の翼 : エルトゥールル号の奇蹟
1 0 0 0 エルトゥールル号の遭難 : トルコと日本を結ぶ心の物語
1 0 0 0 トルコ軍艦エルトゥールル号の海難
- 著者
- オメル・エルトゥール著 山本雅男 植月惠一郎 久保陽子訳
- 出版者
- 彩流社
- 巻号頁・発行日
- 2015
1 0 0 0 OA VR 空間におけるクロスモダリティ活用への取り組み
- 著者
- 河合 隆史
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.11-16, 2019 (Released:2020-02-01)
- 参考文献数
- 7
本稿では,VR 空間におけるクロスモダリティの活用について,筆者らの取り組みを中心に紹介する.具体的に,VR空間におけるラバーハンド錯覚の追試をはじめ,クロスモダリティによる身体イメージの操作を意図したシステム設計へのアプローチについて述べる.さらに,VR 空間におけるクロスモダリティの活用にかかる,期待や課題について述べる.
1 0 0 0 OA ヂフテリーアナトキシンの抗原能力に關する研究
- 著者
- 小野 貞幹 楠瀬 哲志
- 出版者
- 社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 日本傳染病學會雜誌 (ISSN:00214817)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.10-11, 1944-10-20 (Released:2011-11-25)
1 0 0 0 OA 心霊研究とスピリチュアリズムの発展史概観(第23回生命情報科学シンポジウム)
- 著者
- 渡部 俊彦
- 出版者
- International Society of Life Information Science
- 雑誌
- 国際生命情報科学会誌 (ISSN:13419226)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.81-90, 2007-03-01 (Released:2019-04-30)
- 参考文献数
- 24
1848年にアメリカで発生した叩音事件から科学者らによる心霊現象の研究、近代心霊研究が始まった。欧米を中心として、心霊現象や死後の霊魂存在を実験によって探求する研究が行われ、イギリスでは心霊研究協会(SPR)が生まれた。さらに、霊魂存在や霊魂との交信の可能性を認めるスピリチュアリストが生まれた。ここから、新しい人生指導原理であるスピリチュアリズムが誕生した。欧米の心霊研究は浅野和三郎によって日本に紹介され、彼は心霊科学研究会を設立し日本スピリチュアリズム(日本神霊主義)を生んだ。脇長生が日本神霊主義を発展させた。さらに桑原啓善がイギリスの霊界通信の内容を加味させて、ネオ・スピリチュアリズムを作り出した。
1 0 0 0 OA 実験的に交尾拒否姿勢を抑止したモンキチョウの既交尾雌に対する雄の求愛行動
- 著者
- 入江 萩子 渡辺 守
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物教育学会
- 雑誌
- 生物教育 (ISSN:0287119X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.68-75, 2009 (Released:2019-09-28)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1
For high school students, evolution of animal behavior seems to be the most difficult concept to understand due to unavailable examples off ered by text books. In the present study, we developed teaching materials for the evolution of animal behavior and proposed the methodology. In the Japanese sulfur butterfl y Colias erate, polyandrous alba females are the dominant morph in the female population, though mated females do not easily re-accept males courting. The wings of mated alba captured in the field were closed by glue, and they were tethered in the grassland where males were searching for mates. We observed 1,830 entries of males into the imaginary hemisphere of 1 m radius around each female. A half of the males noticed and visited our females. Due to the closed wings, every female was unable to show the mate refusal posture, so the males continued their courtship behavior. However, the duration of hovering around the females was short in the morning, and most males left the females without touching them. Because newly emerged females promptly accept copulation with males in the early morning, males might prefer virgin females to mated ones. On the other hand, males that visited the females around noon prolonged the duration of hovering and tried to copulate persistently. The adaptive significance on the behavioral sequence was easily observed due to the closing femalesʼ wings. Manipulation of the butterfl y wings in the field observation was discussed in the viewpoint of the teaching materials for high school education on evolutionary biology.
1 0 0 0 OA 国際通貨体制の変遷 :為替レート制度とトリレンマ制度
- 著者
- 伊藤 宏之 河合 正弘
- 出版者
- 財務省財務総合政策研究所
- 雑誌
- フィナンシャル・レビュー (ISSN:09125892)
- 巻号頁・発行日
- vol.153, pp.76-122, 2023 (Released:2023-08-24)
- 参考文献数
- 42
本論文は,為替レート制度と国際金融のトリレンマ制度に焦点を当てて,国際通貨体制の変遷を明らかにする。為替レート制度は,為替レート変動の程度や為替レート安定化のアンカー通貨が何かによって決まり,トリレンマ制度は為替レートの安定性,金融市場の開放度,金融政策の独立性の程度の組み合わせによって決まる。伝統的なFrankel-Wei(1996)やその修正版であるKawai-Pontines(2016)の推定式から,為替レートの安定性の指数(推定式の二乗平均平方根誤差(RMSE))を得ることができるだけでなく,各国にとっての為替レート安定化の対象であるアンカー通貨を特定することができる。金融市場の開放度は,各国の対外資産と対外負債の和の対GDP比,対貿易比によって示すことができる。金融政策の独立性は,各国の短期金利が海外金利と国内外の経済要因(国内のGDPギャップやインフレ率,海外の成長率や原油価格)のどちらにどの程度反応するかによって示すことができる。トリレンマのいずれの指数も0から1の間をとるものとして測定される。 100か国以上の諸国における為替レート制度の分析から,世界全体や各地域における主要通貨圏(米ドル圏,ユーロ圏,英ポンド圏,日本円圏,中国人民元圏)と自由な為替フロート制を採用する経済圏の規模およびその変遷を求めることができる。また,各国のトリレンマの組み合わせがどのように変化してきたかをトリレンマ三角形に図示することで,直観的な分析が可能になる。本論文から,いくつかの興味深い結果が得られる。 第1に,米ドル圏の世界経済シェアは依然として世界最大であるものの,ユーロ圏の出現と近年における人民元圏の急速な台頭により,低下する傾向にある。同時に,為替フロート制を採用する経済圏の世界シェアは拡大する傾向にある。第2に,一部の例外(ユーロ地域諸国など)を除き,先進国と新興・発展途上国の両者は,為替レートの柔軟性と金融市場の開放度を高める方向で,トリレンマ制度を選択してきた。今日,自由な為替フロート制,開放的な金融市場,独立した金融政策の維持という「コーナー制度」を採用する国は,先進国,新興・発展途上国の間で広がりを見せている。その一方,安定的な為替レート,閉鎖的な金融市場,独立した金融政策の維持という別の「コーナー制度」を採用する先進国は存在しない。また,安定的な為替レート,開放的な金融市場,独立した金融政策の放棄という3つ目の「コーナー制度」を採用する先進国はユーロ地域などに存在するが,それを採用する新興・発展途上国はごく少数に限られる。その一方,これら3つのコーナー制度以外の組み合わせ(「中間領域」を含む)を選択する国も多い。第3に,先進国と新興・発展途上国の両者に最良のマクロ経済パフォーマンスをもたらすトリレンマ制度は存在しない。
1 0 0 0 OA 2020年代の国際通貨システム
- 著者
- 河合 正弘
- 出版者
- 財務省財務総合政策研究所
- 雑誌
- フィナンシャル・レビュー (ISSN:09125892)
- 巻号頁・発行日
- vol.153, pp.9-75, 2023 (Released:2023-08-24)
- 参考文献数
- 52
第2次世界大戦後の国際通貨システムは,1971年のニクソン・ショックを境に大きく変貌した。それまでのIMF・ブレトンウッズ体制と呼ばれる米ドルを基軸通貨とする固定為替レート制から,1973年以降,主要先進諸国を中心に変動為替レート制に移行したからである。国際通貨システムは,1999年の西欧11か国による共通通貨ユーロの創出によって,複数基軸通貨制度へと展開し,第2の変貌を遂げることになった。2007-09年には,国際通貨システムの中心国である米国発の世界金融危機が起きたが,最も支配的な国際通貨としての米ドルの機能が損なわれる事態には至っていない。2010-15年の欧州金融危機により,ユーロのもつ制度的な脆弱性が明らかになり,ユーロが世界的な規模で米ドルに匹敵する役割を果たすようになることは容易でないことが示された。中国は世界金融危機以降,増大する経済力・金融力を背景に人民元の国際化を積極的に進め,米国の通貨・金融覇権に対する競争に乗り出している。ロシアも2022年のウクライナ侵攻後の金融制裁により,人民元への傾斜を深めている。しかし,人民元が本格的な国際通貨になるためには,国際資本移動の自由化や開放的で深み・厚みがあり流動性の高い人民元建て金融市場の存在が欠かせず,それには相当の期間を要すると考えられる。 本稿では,まず国際通貨システムの諸類型を固定為替レート制度,変動為替レート制度,協調的通貨制度(欧州通貨制度〔EMS〕とユーロの経済通貨同盟〔EMU〕)の3つにまとめ,それぞれの特徴を整理する。次いで,国際通貨システムの主要な柱として,通貨の交換性,為替レート制度と金融政策の枠組み,国際通貨の選択,グローバル金融セーフティーネットを取り上げて説明する。さらに,国際通貨システムの焦点として,グローバル・インバランスと米国の経常収支赤字,ユーロの導入と欧州金融危機,発展途上国の金融危機・債務危機,中国人民元の国際化,中央銀行デジタル通貨を取り上げて分析する。最後に,国際通貨システムの将来として4つの将来シナリオ(「新たな米ドル本位制」,「グローバルな準備通貨制度」,「多極的な国際通貨システム」,「国際通貨システムの分断」)を挙げ,ユーロ経済通貨同盟の強靭化,アジアにおける準備通貨の創出と金融協力,国際通貨システムの分断のリスクについて論じる。
- 著者
- 藤谷 武史
- 出版者
- 財務省財務総合政策研究所
- 雑誌
- フィナンシャル・レビュー (ISSN:09125892)
- 巻号頁・発行日
- vol.152, pp.4-29, 2023 (Released:2023-08-24)
- 参考文献数
- 70
「法と経済学」(法の経済分析)の分野の古典的業績に数えられるのが,「厚生主義(welfarism)の下では,法制度は効率性のみを追求し,所得分配の不公平性の問題は専ら税制および財政的給付(tax and transfer)を通じた所得再分配によって対応すべきである」という命題を提出した,Kaplow & Shavell (1994)(以下,「KS1994」)である。KS1994は,米国を中心とする「法と経済学」の研究者に幅広く受容された一方で,所得分配の問題に関心の強い論者からは,法と経済学が専ら法の効率性の観点を重視し,所得分配の公平の問題を等閑視することに免罪符を与えるものとして,批判の対象となってきた。しかし,わが国では,こうした論争自体,必ずしも広く知られているとは言えない状況にある。 本論文では,この缺を補うべく,関連文献を渉猟して,米国におけるKS1994をめぐる論争から得られた理論的蓄積を整理し(その際には,議論の拡散を避けるため,広い意味での厚生主義に依拠する陣営内部での論争に焦点を絞ることとした。),特に同論文の命題の射程を検討した。 検討の結果,以下の諸点が明らかとなった。まず,厚生主義者でKS1994の成果を全面的に否定する者は見当たらず,批判のほとんどは,KS1994が理論モデルから言える範囲を超えて一般的な射程を持つ「かのように語られる」点に向けられていた。理論モデルから言える範囲では,KS1994の結論は穏当ですらある。たとえば,KS1994は,「所得」以外の不平等について法制度が対応することについては否定も肯定もしておらず,衡平を考慮した法的権原(entitlement)の分配もKS1994の理論モデルからは必ずしも排除されない。また,KS1994が成り立つ条件も実は限定されている。例えば,所得再分配の手段としてみた場合に常に「所得税+給付」が優れているとも限らず,政治的に利用可能な手段であるとも限らない。論争を通じて明らかとなったこれら諸点は,いずれもKS1994が十分に述べなかった理論モデルの留保条件や射程を明らかにし,KS1994を理論的に補完するものである。ただし,政策的指針として見た場合には,「これら理論的留保により補完されたKS1994」がそのオリジナルの形態に比べて,簡明さゆえの魅力を大きく損われたものになっていることは否定しがたい。
1 0 0 0 OA 鈴木一人(著)『宇宙開発と国際政治』を読み返して
- 著者
- 石垣 勝
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.281, pp.50, 2017 (Released:2020-12-15)
- 著者
- 竹鼻 一也 川上 茂久 Chatchote Thitaram 松野 啓太
- 出版者
- 日本野生動物医学会
- 雑誌
- 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.17-27, 2022-03-01 (Released:2022-05-02)
- 参考文献数
- 46
若齢アジアゾウに致死的出血病を引き起こす原因とされるElephant endotheliotropic herpesvirus(EEHV)は,世界中のゾウ飼育施設において多くの死亡例をもたらし,直近20年の間で飼育下アジアゾウの最も主要な死亡原因となっている。EEHVはゾウを自然宿主とし,他のヘルペスウイルス種と同様に潜伏感染する。若齢ゾウにおいては,何らかの原因で血中ウイルス量が異常上昇することに伴い,致死的出血病に至ることがある。発症後の治療には反応が乏しく,有効な治療法が確立されているとは言い難いものの,発症初期に積極的な治療を行うことで救命率向上が認められる。そのため,飼育施設においては日常的な検査体制の確立による早期診断および早期治療開始が求められる。
1 0 0 0 ユダヤ人世界征服陰謀の神話 : シオン賢者の議定書
- 著者
- ノーマン・コーン著 内田樹訳
- 出版者
- ダイナミックセラーズ
- 巻号頁・発行日
- 1991
1 0 0 0 OA 大腸ポリペクトミー・コールドポリペクトミー・EMRのコツ
- 著者
- 樫田 博史
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.311-325, 2017 (Released:2017-03-22)
- 参考文献数
- 18
有茎性病変は通常のポリペクトミーの適応である.無茎性や平坦型病変で大きいもの,小さくとも癌を疑うような病変はEMR(やESD)の適応である.コールドポリペクトミーの適応は,癌を疑わない無茎性ないし平坦型病変で,9mm以下までが妥当な線と思われる.有茎性ポリープでは,頭部寄りにスネアをかける.茎が太い場合は出血予防のために留置スネアも使用する.コールドポリペクトミーの場合,周囲粘膜を含めて切除するため,常に病変をスネアの中央付近に捉えるよう,微調整しながらスネアを閉じる.EMRの成否の大半は,局注にかかっていると言っても過言ではない.屈曲部やヒダにまたがっている病変では口側から局注を開始する.SM癌を除く大きい病変では中央部から局注を開始する方が膨隆を得られやすい.穿刺した針で病変を少し持ち上げるようにし,注入しながら針をゆっくり引き戻していく.スネアをかける際は,軽く病変を押さえ込むようにするが,筋層を巻き込まないよう注意する.患者が痛みを訴える場合や,介助者がゴムのような弾力を感じてなかなか切れない場合は,筋層を巻き込んでいる可能性が高いので中止する.