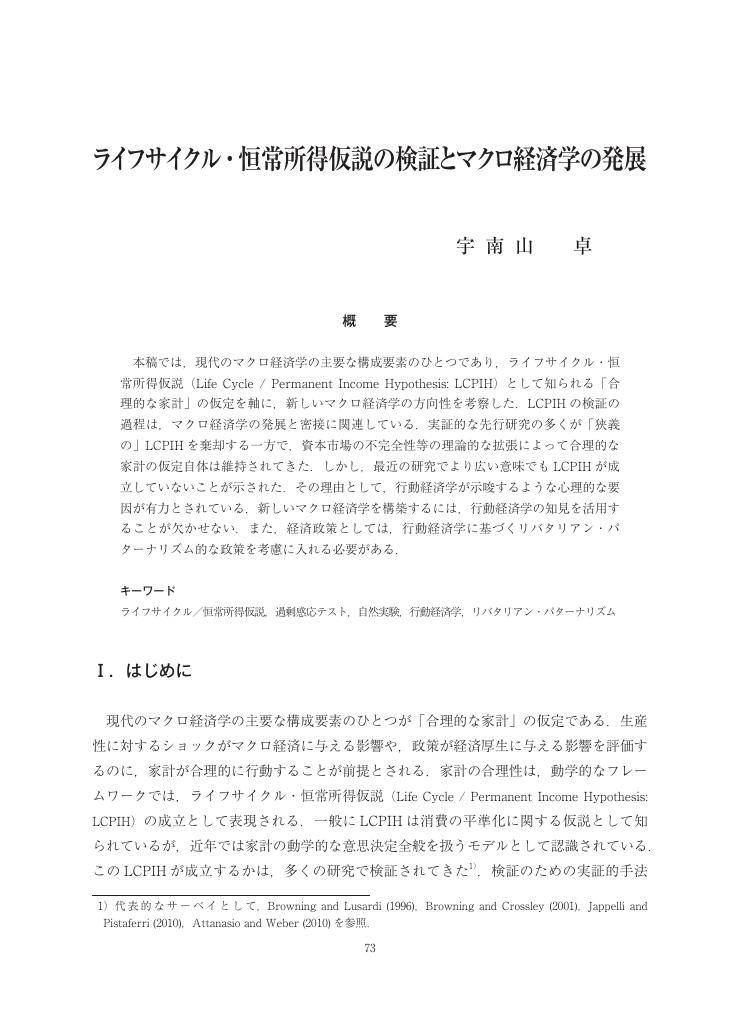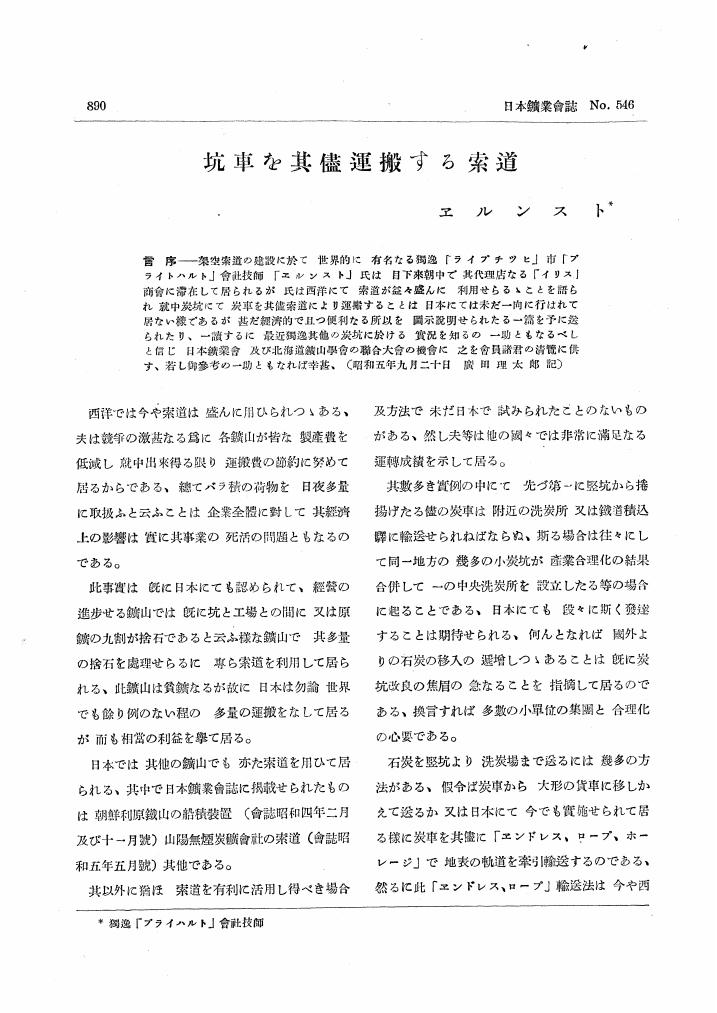1 0 0 0 Securitarian
1 0 0 0 OA 鉱物界 : 中等教育
1 0 0 0 OA 正倉院御物見取圖
- 巻号頁・発行日
- 1000
1 0 0 0 OA 地理空間情報とIC定期券データを用いた教師あり学習による駅商圏の異方的推定
- 著者
- 兒玉 庸平 朱山 裕宜 宮崎 祐丞 竹内 孝
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第36回 (2022)
- 巻号頁・発行日
- pp.3G3OS15a04, 2022 (Released:2022-07-11)
鉄道事業者は新駅設置時の需要推定や駅改良の効果測定に際して,駅勢圏(駅周辺エリアで居住・就業する人がどの駅を利用しているかを示す商圏の一種)の推定を実施する.従来は駅中心ら半径数km以内を駅勢圏とし,国勢調査などの統計データを用いて鉄道利用者数を推定する手法が用いられるが,異方性を考慮しないため,実際の駅勢圏に即しておらず予測と実態との間に大きな乖離が生じている.近年,IC定期券サービスや経路検索サービスの登場により大規模な空間データの取得が可能となり,より空間的に細かい粒度で精度の高い駅勢圏の推定が期待される.本研究では,郵便番号ごとのIC定期券登録数から駅勢圏を定義し,郵便番号ごとの各駅のIC定期登録数を予測する問題として駅勢圏推定を定式化する.さらに対象エリア内の郵便番号から近隣駅までの所要時間,駅同士の地理的関係性などの地理空間情報を用いた教師あり学習によって駅勢圏の推定法を提案する.従来手法と比較し,提案法による新駅需要の推定誤差が削減されたことを示す.
1 0 0 0 OA ペトリネットの可達解析
- 著者
- 宮本 俊幸
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.20-27, 2019-07-01 (Released:2019-07-01)
- 参考文献数
- 43
離散事象システム・並行システムのモデル化言語の一つであるペトリネットは,1962年にカール・アダム・ペトリによって導入されて以来,様々な理論及び応用研究がなされてきた.ペトリネットにおける最も基本的な解析問題の一つに,与えられた状態に到達可能かどうかを判定する可達問題がある.可達問題は決定可能であるが,計算量が指数オーダとなるためペトリネットにおける諸性質の解析は容易ではない.近年の計算機能力の進歩や様々な手法の開発により,ある程度の規模のペトリネットまでは可達問題を解くことができるようになっている.本稿ではペトリネットの可達問題に対する最近の手法である,記号状態表現を用いる手法,アンフォールディングを用いる手法,モジュラー可達空間を用いる手法,モデル検査ツールを用いる手法を概説する.
- 著者
- 笠田 竜太
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.7, pp.409-413, 2018 (Released:2020-04-02)
- 参考文献数
- 17
材料の局所的な機械的強度を調べるために広く用いられているナノインデンテーション法の現状と課題について概説し,原子力・核融合材料研究への応用について述べる。
1 0 0 0 OA 全般性不安障害と診断された患者への認知行動的介入(実践研究)
- 著者
- 金 外淑 村上 正人 松野 俊夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.143-156, 2006-09-30 (Released:2019-04-06)
外来通院中の全般性不安障害患者に対して、認知行動的諸技法を用い、治療効果が得られた症例を取り上げ、認知行動的介入による心理技法の導入とその臨床経過について報告する。面接による治療は52セッションであった。介入の初期段階は患者特有の心配・不安に対する仕方に注目し、論理情動行動療法による認知再構成法を用い、心配や不安時に生じる認知の仕方について理解させた。中期段階は、イメージを用いた「心配へのエクスポージャー」と「言葉による反応妨害法」を組み合わせた介入を行った。後期段階では、おもに問題解決訓練を導入し、出来事に対する問題解決の能力を向上させ、自信を高める介入を行った。その結果、過剰な心配・不安症状を訴える頻度も減り、次第に日常生活上のストレスも以前より柔軟に対処できるようになった。
1 0 0 0 OA 喉頭癌放射線治療での麦門冬湯の咽頭痛予防
- 著者
- 金谷 浩一郎 今手 祐二 竹本 剛 蓮池 耕二 綿貫 浩一 守谷 啓司
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.2, pp.203-209, 2002-02-01 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1 2
PURPOSE: Tsumura Co.'s Bakumondo-to (TJ-29) is a Chinese herb medicine prescribed widely in Japan for bronchitis and laryngitis. It is well known that TJ-29 not only has a variety of effects including anti-inflammatory and antitussive properties, but also is capable of increasing salivary secretions. The purpose of this study is to examine whether TJ-29 can reduce mucosal toxicity caused by radiotherapy in patients with early laryngeal carcinoma.METHODS AND MATERIALS: Between 1993 and 1999, 20 patients with primary early laryngeal carcinoma were treated by radiotherapy at Nagato General Hospital. All patients were treated with 2 Gy per fraction daily, 5 days a week. Eight patients formed the control group (no TJ-29) and 12 patients received TJ-29 throughout the radiation therapy. The severity of daily subjective symptoms such as hoarseness, xerostomia or pharyngoxerosis, cough, and sore throat were graded O to 3 according to descriptions on the clinical charts.RESULTS: No statistically significant between-group differences were seen in subjective hoarseness, xerostomia or pharyngoxerosis, and cough. However the mean final grade of subjective sore throat was less severe in the TJ-29 group (p=0.023).CONCLUSION: Despite the limited number of patients, this study suggests that TJ-29 was able to reduce the severity of mucositis induced by radiotherapy. Further intensive research is needed.
1 0 0 0 OA ライフサイクル・恒常所得仮説の検証とマクロ経済学の発展
- 著者
- 宇南山 卓
- 出版者
- 国立大学法人 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.73-90, 2011-11-01 (Released:2021-02-09)
1 0 0 0 運輸審議会半年報
- 出版者
- 運輸大臣官房審理官室
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和36年7-12月, 1962
1 0 0 0 OA V.胃食道逆流症(GERD)による咳嗽
- 著者
- 金光 禎寛
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.10, pp.2124-2131, 2020-10-10 (Released:2021-10-10)
- 参考文献数
- 12
咳は,胃食道逆流症(gastroesophageal reflux disease:GERD)の食道外症状の1つである.本邦でのGERDの有病率の増加に伴い,GERD咳嗽も増加傾向で,慢性咳嗽の原因として,咳喘息と共に頻度が高い.一方で,胸やけ等の典型的な食道症状を伴わないことも多く,咳の罹病期間が長期に及び,生活の質を低下させる.診断に難渋することも多いが,Fスケール等の質問票の活用やPPIに加えて消化管運動機能改善薬の併用がGERD咳嗽の診断・治療に対して有用な可能性を述べる.
1 0 0 0 OA 分娩施設のない離島に住む母親の妊娠期・産褥期におけるセルフケア行動
- 著者
- 猪目 安里 井上 尚美 吉留 厚子
- 出版者
- 一般社団法人 日本助産学会
- 雑誌
- 日本助産学会誌 (ISSN:09176357)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.81-91, 2020 (Released:2020-06-30)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
目 的分娩施設のない離島に住む母親の妊娠期・産褥期のセルフケア行動の実態を明らかにし,セルフケア行動の特徴に合わせた保健指導を考える資料とする。対象と方法分娩施設のない離島に住む分娩後1年以内の母親9名を対象に,インタビューガイドに基づき,半構造的面接法を用いてフォーカス・グループ・インタビューを行った。結 果分娩施設のない離島に住む母親は,妊娠期は【経験者やインターネットから情報収集】を行い,【家族の協力を得ながら自分の体と胎児の為のセルフケア】を行っていた。また,《妊娠に伴う体調の変化に応じて自ら病院を受診》,《自分で出血を観察しながらの対処行動》という【早めの対処行動と症状の観察】と,《島の昔からの文化にならった食事を摂る》の【島に伝承された食文化にもとづいたセルフケア】という特徴があった。産褥期は【産後の回復に向けたセルフケア】を行っていた。《体調の変化に応じて早期の常備薬の内服,病院受診》,《乳房トラブルに対して情報源にアプローチし,対応》する【異常症状に対して行動・対応】,《産後の針仕事と水仕事はしてはいけない》,《母乳をたくさん出すために魚汁を必ず飲む》という【島の昔からの文化にならったセルフケア】に特徴があった。結 論分娩施設のない離島に住む母親は,分娩施設がなく,産科医・小児科医が常駐ではない環境にあるからこそ異常に移行しないようにしなければならないという強い思いから,異常症状を自身の感覚を通して敏感に察知し,自ら判断・行動していた。分娩施設のない離島における妊産婦が安心・安全に妊娠期・産褥期を過ごすためには,島に伝承されているセルフケア行動も取り入れつつ,母親が身体の変化に敏感になり,感覚を通して変化を察知できるように,医療従事者は正しい情報を与え,担保していくような関わりが必要かもしれない。
1 0 0 0 OA 坑車を其儘運搬する索道
- 著者
- ヱルンスト
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- 日本鑛業會誌 (ISSN:03694194)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.546, pp.890-895, 1930-10-22 (Released:2011-07-13)