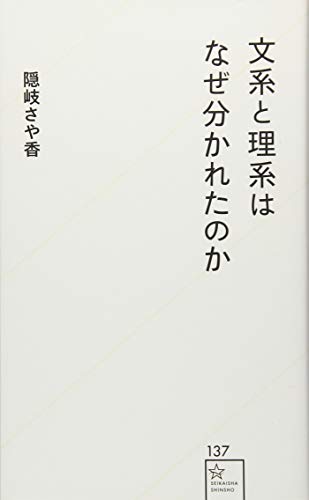1 0 0 0 全駐留軍労働組合運動史
- 著者
- 全駐留軍労働組合 編
- 出版者
- 労働旬報社
- 巻号頁・発行日
- vol.第5巻, 1992
- 著者
- Eyal Kurzbaum Yoram Zimmels Robert Armon
- 出版者
- The Society for Actinomycetes Japan
- 雑誌
- 日本放線菌学会誌 (ISSN:09145818)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.31-38, 2010-12-25 (Released:2010-12-15)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 4 9
In the present study, Streptomyces sp. CW1 was isolated from a constructed wetland system mesocosm and identified as such based on 16S rDNA analysis, and additional biochemical properties were evaluated. This isolate was found to be halotolerant (up to 11% NaCl) and able to grow and utilize biopolymers such as: agarose, agar, gellan gum (a bacterial polysaccharide), polypectate and chitin as the sole carbon and energy source. Since the primary isolation was performed based on its capability to degrade phenol, the high cell yield coefficient showed rapid growth on phenol (0.82–0.98 mg dry biomass/mg phenol). Its halotolerance and the capability to biodegrade biopolymers found mainly in the marine environments, suggest on its primordial oceanic origin. In the present study some of its characteristics are described and discussed along with its beneficial use for wastewater purification processes in constructed wetland systems.
- 著者
- 日本精神科診断学会 [編]
- 出版者
- 日本精神科診断学会
- 巻号頁・発行日
- 2008
1 0 0 0 OA 箸の持ち方に関する調査 -幼児・中学生・大学生の比較-
- 著者
- 宇都宮 通子 五島 淑子
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 創立40周年日本調理科学会平成19年度大会
- 巻号頁・発行日
- pp.37, 2007 (Released:2007-08-30)
【目的】 日本は、箸を使って食事をする文化圏に属している。近年、その箸の持ち方が個性化してきていると懸念されている。そこで、幼児・中学生・大学生の箸の持ち方の実態を探り、「伝統的な持ち方」をする人の割合が低下している理由を考察することを通して、箸の持ち方を決定する要因等を検討した。 【方法】 (1)中学生505人・大学生262人に対し、質問紙法による調査を行った。実施時期は、平成18年6月~9月、内容は、箸の持ち方・箸の持ち方の決定要因・箸の持ち方と作法・箸の持ち方と意識についてである。 (2)保育園・幼稚園に通園し、昼食時に箸を使用する1歳児クラスから5歳児クラスの幼児499名に対し、昼食での箸使用時の観察等により、箸の持ち方の調査を行った。実施時期は、平成18年6月~19年2月、内容は、箸の持ち方・持ち方の類型化・掌の長さ・箸の持ち方へ取り組む様子についてである。 【結果】 箸の「伝統的な持ち方」の割合は、5歳児が1割弱、中学1年生が6割弱、大学生が7割弱で、年齢が高くなるにしたがって増加した。また、向井・橋本(1986年)がおこなった20年前の調査と比較し、伝統型でも鉛筆型でもない、「その他の型」が増加したことが明らかになった。箸の「伝統的な持ち方」の習得には、心身の発達・教育(家庭教育・集団教育)・適切な道具「箸」の使用などが重要であることが示唆された。
1 0 0 0 CQ ham radio. 別冊, CQジュニア
- 出版者
- [CQ出版]
- 巻号頁・発行日
- 1960
- 著者
- Arisa Hamahata Seiya Mitsusada Tomoyuki Iwata Ken Nakajima Yuki Ogawa Akira Miyazaki Marina Kobayashi Yushi Fujiwara Yu Asano Kazuhisa Mabuchi Miki Yoshida Ayako Misawa
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.21, pp.3435-3440, 2021-11-01 (Released:2021-11-01)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
A 79-year-old man with underlying alcoholic liver cirrhosis presented with complaints of a fever, abdominal pain, and difficulty walking. A diagnostic work-up revealed liver atrophy and chylous ascites, and spontaneous bacterial peritonitis (SBP) was diagnosed based on the cell and neutrophil counts. The Burkholderia cepacia complex (Bcc) was detected on blood and ascitic fluid cultures. Although broad-spectrum antibiotic therapy was initiated, the infection was difficult to control, and the patient died of multiple organ failure. Bcc is often multidrug-resistant and difficult to treat. SBP caused by Bcc has been rarely reported and may have a serious course, thus necessitating caution.
- 著者
- Akihiro Kotani Yasuhiro Oda Yosuke Hirakawa Motonobu Nakamura Yoshifumi Hamasaki Masaomi Nangaku
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.21, pp.3447-3452, 2021-11-01 (Released:2021-11-01)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
A 77-year-old man developed peritoneal dialysis-related peritonitis caused by Streptococcus oralis, a rare pathogen causing the disease. The infection, which was not controlled by one-week intraperitoneal administration of cefazolin and ceftazidime, was cured only after switching to two-week intravenous administration of cefazolin and ceftazidime. The patient had no major dental disease or recent history of dental intervention. This case suggests that S. oralis might cause peritoneal dialysis-related peritonitis with persistent systemic inflammation via an extra-oral infection route. The clinical course is discussed along with a review of the literature.
- 著者
- Hayato Yamana Sachiko Ono Nobuaki Michihata Taisuke Jo Hideo Yasunaga
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.21, pp.3401-3408, 2021-11-01 (Released:2021-11-01)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 4
Objective Maoto is a traditional Japanese Kampo formula used to treat influenza. However, clinical evidence for maoto has been limited to small-scale studies of its effect in alleviating symptoms. The present study evaluated whether or not the addition of maoto to a neuraminidase inhibitor was associated with a reduction in hospitalization following influenza. Methods Using the JMDC Claims Database, we identified outpatients <60 years old who were diagnosed with influenza by an antigen test from September 2013 to August 2018. One-to-five propensity score matching was conducted between patients who received maoto in addition to a neuraminidase inhibitor and those who received a neuraminidase inhibitor alone. Hospitalization within seven days of the influenza diagnosis was compared in the matched groups using the Mantel-Haenszel test. Results We identified 1.79 million cases of influenza from the database in the 5-year study period. Maoto was prescribed for 3.9% of the 1.67 million cases receiving a neuraminidase inhibitor. In the 64,613 propensity score-matched groups of patients, the 7-day hospitalization rate was 0.116% (n=75) for patients with maoto and 0.122% (n=394) for patients without maoto. The difference between these treatment groups was nonsignificant (common odds ratio, 0.95; 95% confidence interval, 0.74 to 1.22; p=0.695). Conclusion The addition of maoto to a neuraminidase inhibitor was not associated with a decrease in hospitalization among nonelderly patients with influenza. Further research is necessary to clarify the indication and efficacy of maoto.
1 0 0 0 IR 実験室における化学物質管理-国内法令と富山大学薬品管理支援システム(TULIP)の紹介-
- 著者
- 屋敷 香奈 浜崎 景 稲寺 秀邦
- 出版者
- 富山大学医学会
- 雑誌
- Toyama medical journal (ISSN:21892466)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.10-13, 2020-03
大学の実験室で使用する試薬やガス等の化学物質には,ヒトの健康への有害性や火災・爆発の危険性を有するもの,環境を破壊するものが数多く含まれる。化学物質を安全かつ適切に取り扱うためには,個々の化学物質の特性に加え,法規制を理解する必要がある。本稿では労働安全衛生法や毒物及び劇物取締法などの大学の実験室で特に注意を払うべき化学物質規制の国内法令についてその目的と要求事項を中心に解説する。またラベル表示,安全データシート(Safety Data Sheet:SDS)による個々の化学物質の危険有害性や取扱注意事項,適用法令等の確認方法を記載する。最後に各研究室での試薬・ガスボンベの管理に有用だと思われる富山大学薬品管理支援システム(TULIP)について紹介する。 Many of the chemical substances used in university laboratories, such as reagents and gases, are potential fire and explosive hazards and are harmful to human health and the environment. To handle chemical substances safely and appropriately, it is necessary to understand the laws and regulations governing their use as well as the individual characteristics of chemical substances. In this article, we explain Japanese laws and regulations, such as the Industrial Safety and Health Law and the Poisonous and Deleterious Substances Control Law, which must be followed when working with chemical substances in university laboratories. We also explain how to check for hazards, handle precautions, and follow applicable laws on chemical substances based on the information on labels and safety data sheets. We then introduce the Toyama University Lab. chemicals InPut System (TULIP), which is considered effective for the proper management of reagents and gas cylinders in laboratories.
1 0 0 0 IR 2017~2018年度アミューズメント産業研究所プロジェクト研究 将棋の効果的指導法と教育効果に関する研究 : 将棋教室、将棋指導における長期間にわたる活動から得られた実例と分析(要約)
- 著者
- 古作 登 小田切 秀人 川崎 一克 寺谷 睦
- 出版者
- 大阪商業大学アミューズメント産業研究所
- 雑誌
- 大阪商業大学アミューズメント産業研究所紀要 (ISSN:18811949)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.181-214, 2019-06
- 著者
- 犬飼 裕一
- 出版者
- 日本大学文理学部人文科学研究所
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:02866447)
- 巻号頁・発行日
- no.101, pp.61-90, 2021
1 0 0 0 OA 高脂肪食誘導性の非肥満糖尿病発症メカニズム
- 著者
- Kromhout Gert
- 出版者
- 文林堂
- 雑誌
- 航空ファン (ISSN:04506650)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.10, pp.20-23, 2016-10
- 著者
- Tokunaga Katsuhiko
- 出版者
- 文林堂
- 雑誌
- 航空ファン (ISSN:04506650)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.32-37, 2010-04
- 著者
- 蓑輪 圭祐 下村 匠 川端 雄一郎 藤井 隆史 富山 潤
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集E2(材料・コンクリート構造)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.4, pp.134-149, 2021
- 被引用文献数
- 2
<p> 温湿度,降雨,日射の環境作用がコンクリートの乾燥収縮に及ぼす影響を把握するため,同時に作製した角柱試験体を全国 4 地点で屋外暴露し,水分量と収縮量の経時変化を測定した.その結果,各地の一年間の収縮量はほぼ同等であったが,季節ごとの収縮の進行が異なることが明らかとなった.温湿度の変動・日射・降雨の影響を考慮できるコンクリートの水分移動および収縮に関する数値解析法を用いた検討により,湿度の変動と降雨が収縮量に及ぼす影響が大きいことを明らかにした.湿度の変動と降雨の影響を考慮する係数を平均湿度と降雨時間割合から算出し,平均湿度に乗じた見かけの相対湿度を乾燥収縮予測式に用いることで,屋外におけるコンクリートの収縮を簡易的に予測できることを示した.</p>
1 0 0 0 小型インピンジャーを用いる通気法による食品中シアン化合物の分析
- 著者
- 森 葉子 植田 康次 櫻井 有紀 青木 明 岡本 誉士典 神野 透人
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.5, pp.162-165, 2021-10-25 (Released:2021-11-02)
- 参考文献数
- 7
食品中のシアン化合物の簡便,迅速な測定法を確立する目的で,日本産業規格(JIS)工場排水試験法で採用されている通気法を参考に,小型インピンジャーを用いる前処理について検討を行った.その結果,シアン化物イオンとして10 ppmに相当するアミグダリンをビワ種子粉末に添加して実施した分析法の性能評価では,真度83.9%,併行精度1.18%,室内精度4.67%の良好な結果が得られた.本法を用いて,市販されている食品中のシアン化合物を調査した結果,10食品中のビワ種子粉末3食品において10 ppmを超えるシアン化合物が検出された.
- 著者
- 鈴木 知華 野村 昌代 奥富 幸
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.5, pp.139-147, 2021-10-25 (Released:2021-11-02)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
愛玩動物用飼料中の無機砒素の濃度測定について,液体クロマトグラフ-誘導結合プラズマ質量分析計(LC-ICPMS)を用いた定量法を開発した.2 w/v%TMAH溶液を試料に添加後,加熱抽出し,試料溶液をpH調整しLCICP-MSに注入した.共同試験は,5種類の愛玩動物用飼料を用い9試験室で実施した.ドライ製品及び素材乾燥ジャーキーに2 mg/kg相当量を,ウェット製品に0.5 mg/kg相当量を,成型ジャーキーに1 mg/kg相当量を,ビスケットに0.2 mg/kg相当量のAs (III)を添加した.その結果,平均回収率,繰返し精度及び室間再現精度の相対標準偏差(RSDr及びRSDR)並びにHorRatは,それぞれ95.4%から98.3%,2.9%以下及び9.1%以下並びに0.51以下であった.
- 著者
- 小林 傳司
- 出版者
- 南山大学社会倫理研究所
- 雑誌
- 社会と倫理 (ISSN:13440616)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.197-209, 2015