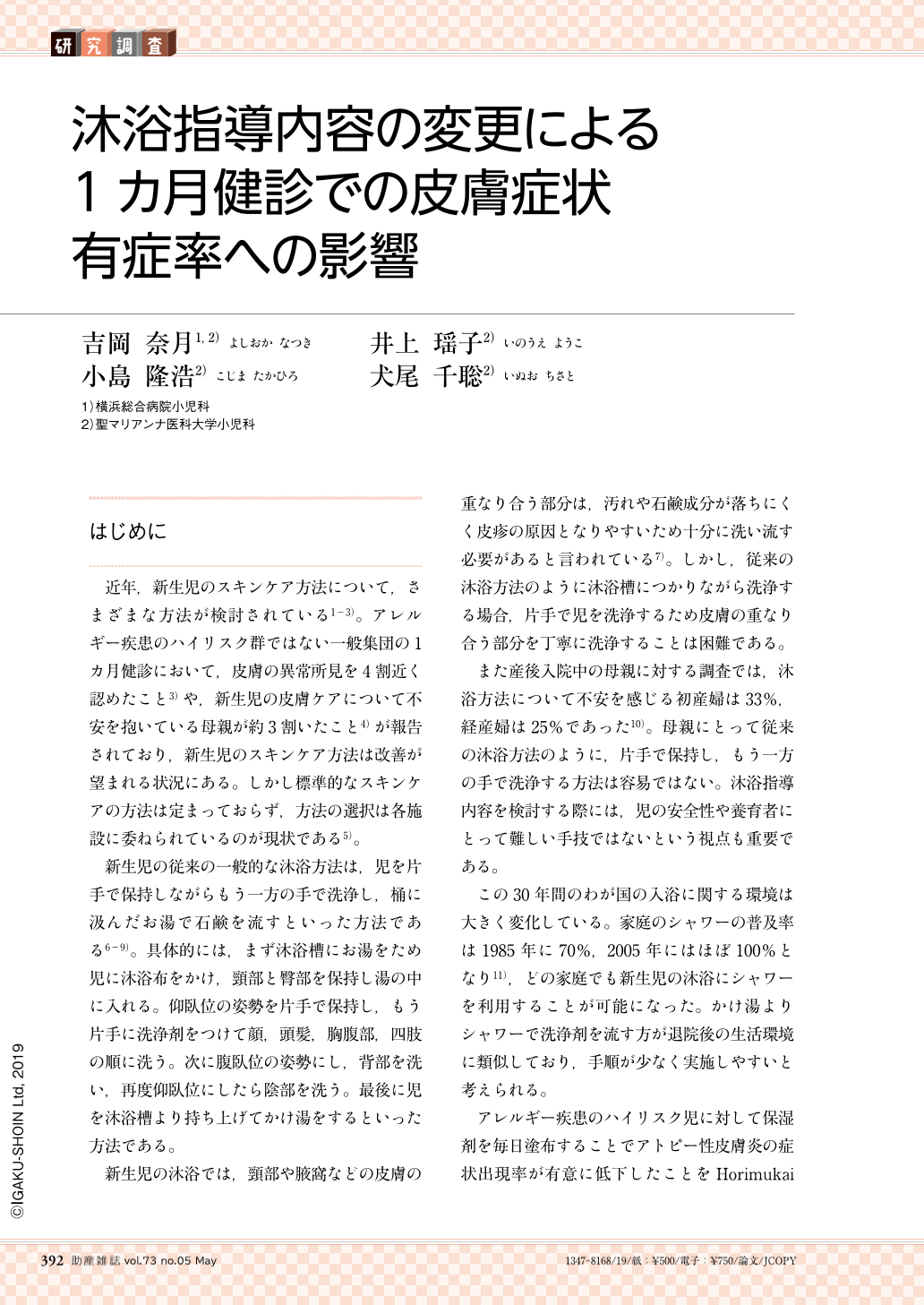1 0 0 0 OA 鑑賞のエスノメソドロジー - 音楽のイメージについて語ること -
- 著者
- 竹尾 宗馬
- 巻号頁・発行日
- pp.1-38,
授与大学:弘前大学; 学位種類:修士(教育学); 授与年月日:平成31年3月22日
- 著者
- ドイツ憲法判例研究会
- 出版者
- 第一法規
- 雑誌
- 自治研究 (ISSN:02875209)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.2, pp.151-158, 2020-02
- 著者
- 一瀬 早百合
- 出版者
- 田園調布学園大学
- 雑誌
- 田園調布学園大学紀要 = Bulletin of Den-En Chofu University (ISSN:18828205)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.199-210, 2015
障害のある子どもをもつ親のメンタルヘルスの実態を「保護者のためのこころのケア相談」における語りをKJ法にて分析し,明らかにした。障害のある子どもの出現は,一旦決着がついていた過去の解決されていない問題,原家族との関係やトラウマを再燃させることになると考えられる。子どもの出生以後の過度の疲労や傷つき体験が手当てされていないこと,さらに現在の生活における家族,特に夫との関係やママ友や所属集団での生きづらさがメンタルヘルスに負の影響を与えることになる。それらが長期化すると,自分自身のふるまいに不安を感じ,無価値な存在なのではないかという自己否定感が強まり,メンタルヘルスが危機的な状況となる。一方では,その焦りが子どもへの虐待へ向かう場合もある。メンタルヘルスサポートには現在の生活における家族や所属集団での「生きづらさ」だけではなく,過去からの様々な「傷つき体験」へのケアというライフヒストリーの視点が必要である。
- 著者
- 近藤 祐磨
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, 2014
Ⅰ 問題の所在と研究目的<br> 昨今の環境保全運動の高まりとともに,環境保全運動を対象とした研究もさまざまな学問領域で蓄積されつつある.しかし,社会化された自然という観点からの研究は少ない.環境保全研究における地理学の独自性は,英語圏で展開されていて社会化された自然を主題とする「自然の地理学」研究から示唆を得ることができる.そこで,本研究は,福岡県糸島市における2つの海岸林保全運動を事例として,海岸林がいかにして「保全すべきもの」として見出されたのか,保全運動がいかなる主体間関係の構築によって展開されたのかを明らかにする.<br>Ⅱ 深江の浜における海岸林保全運動<br> 糸島市二丈深江地区では,「深江の浜」を保全対象とする「深江の自然と環境を守る会」が2011年4月に発足し,地域住民を主体とした保全運動が実践されている.<br> 保全運動は,行政が始めた地域活動への人的・財政的支援制度が契機で始まった.2012年5月には,市民・企業・行政が連携した大規模な環境美化活動の一環として,市との共催で活動が実施され,校区内の小中学校や事業所が活動に積極的に参加するようになったり,活動内容も増えたりと,運動が拡大した.校区内のさまざまな主体が次々と加わって,地域的な社会運動に発展しているといえる.<br> 同団体は海岸林を郷土の誇りであり,防風・防砂機能を果たすものだと意味づけており,校区住民の世代間交流を図りながら保全運動を行うことを目指している.<br>Ⅲ 幣の浜における海岸林保全運動<br> 糸島市志摩芥屋地区では,市を象徴する海岸林「幣の浜」を保全対象とする「里浜つなぎ隊」が2013年2月に結成され,移住者や外部者を主体とした保全運動が実践されている.<br> 保全運動は,福島第一原発事故で東京から移住した元新聞記者の女性が,2012年秋のマツ枯れ被害に衝撃を受けたことが契機で始まった.女性は,相談相手であった近隣の移住者(大学教員)の仲介と,公私にわたる交友関係を生かして,研究者や専門家,政治家・市職員との人的ネットワークを急速に拡大させ,大規模な運動を展開している.<br> 活動には,計画中も含めて,①市民参加型のイベントを主催して広く参加を募るものと,②既存の海岸林保全策とは異なる方法を提示するものがある.①は,マツ枯れの拡大を防ぐための枝拾い活動,②は,環境系NPO法人から影響を受けて,マツ枯れの主たる原因をめぐる論争(森林病害虫説と大気汚染説)のうち大気汚染説に立脚した,土壌の酸性化を中和させるための炭撒き活動である.<br> 同団体は,国によるマツ枯れ防止の薬剤散布を絶対視する地元住民の風潮と,薬剤の子どもに対する健康上の影響に疑念を抱いている.同団体は空間一帯を新しいコモンズのモデルを創出する場と意味づけており,薬剤散布によらない市民主導の海岸林保全と,マツ林にこだわらない新たな海岸の創成を目指している.しかし,市を象徴する白砂青松の復活を目指すメディアや民間企業から,マツ林復活に取り組む団体と誤解されている節がある.<br>Ⅳ 主体による認識と実践の多様性<br> 本研究から,海岸林保全運動において,対象となる環境への社会的な意味づけが,同じ環境を共有する地域内でも主体によって多様であることが判明した.また,保全運動が起きている複数の事例間でも内部の様相は異なるため,特定地域内部における意味づけの多様性と地域ごとの特殊性が,環境保全運動をめぐる状況をきわめて複雑なものにしている.海岸林保全運動の契機・主体・意味づけのいずれもが多様で複雑である.<br> しかし,本研究ですべての主体の意味づけが具体的に明らかになったわけではない.とくに保全運動の中核を担っていない一般住民による意味づけの量的な研究や,玄界灘地域全体での海岸林保全運動がリージョナルにどのような影響を与えているのかについての研究が今後の課題である.
1 0 0 0 OA 松本清張「黒地の絵」論
- 著者
- 李 彦樺
- 出版者
- 関西大学国文学会
- 雑誌
- 國文學 (ISSN:03898628)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, pp.1-30, 2015-03-31
1 0 0 0 IR 松本清張「黒地の絵」論
- 著者
- 李 彦樺
- 出版者
- 関西大学国文学会
- 雑誌
- 国文学 (ISSN:03898628)
- 巻号頁・発行日
- no.99, pp.352-323, 2015-03
1 0 0 0 ドップラーライダーによる前線通過時の強風観測
- 著者
- 丸山 敬 竹見 哲也 山田 広幸 山口 弘誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本風工学会
- 雑誌
- 日本風工学会年次研究発表会・梗概集
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, 2021
<p>建物被害の原因となる強風特性に関して、これまで地表面摩擦に起因する「風の乱れ」だけを考慮することが多く行われてきた。しかし、観測技術の進歩に伴い、ダウンバーストや竜巻、ガストフロントなど局所的ではあるが激甚な建物被害を引き起こす極端気象現象が明らかになるにつれ、これら積雲対流下の上昇・下降気流に由来する風速の急変を伴う「突風」を考慮した強風ハザード評価が正確な被害予測に不可欠であると考えられる。そこで本研究では、積雲対流による「突風」の影響を明らかにするためドップラーライダーによって観測された前線通過時の記録を紹介し、積雲対流下における接地境界層内の気流性状について考察する。</p>
1 0 0 0 安保条約の条約期限に関する考察(1)
- 著者
- 鍛治 一郎
- 出版者
- 大阪大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 阪大法学 = Osaka law review (ISSN:04384997)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.5, pp.873-900, 2020-01
1 0 0 0 安保条約の条約期限に関する考察(2・完)
- 著者
- 鍛治 一郎
- 出版者
- 大阪大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 阪大法学 = Osaka law review (ISSN:04384997)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.6, pp.1275-1303, 2020-03
1 0 0 0 Art McEvily 80 歳誕生日記念シンポジウム : Fatigue and Fracture of Traditional and Advanced Materials に参加して
- 著者
- 遠藤 正浩
- 出版者
- 社団法人日本材料学会
- 雑誌
- 材料 = JOURNAL OF THE SOCIETY OF MATERIALS SCIENCE, JAPAN (ISSN:05145163)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.10, 2006-10-15
1 0 0 0 沐浴指導内容の変更による1カ月健診での皮膚症状有症率への影響
はじめに 近年,新生児のスキンケア方法について,さまざまな方法が検討されている1−3)。アレルギー疾患のハイリスク群ではない一般集団の1カ月健診において,皮膚の異常所見を4割近く認めたこと3)や,新生児の皮膚ケアについて不安を抱いている母親が約3割いたこと4)が報告されており,新生児のスキンケア方法は改善が望まれる状況にある。しかし標準的なスキンケアの方法は定まっておらず,方法の選択は各施設に委ねられているのが現状である5)。 新生児の従来の一般的な沐浴方法は,児を片手で保持しながらもう一方の手で洗浄し,桶に汲んだお湯で石鹸を流すといった方法である6−9)。具体的には,まず沐浴槽にお湯をため児に沐浴布をかけ,頸部と臀部を保持し湯の中に入れる。仰臥位の姿勢を片手で保持し,もう片手に洗浄剤をつけて顔,頭髪,胸腹部,四肢の順に洗う。次に腹臥位の姿勢にし,背部を洗い,再度仰臥位にしたら陰部を洗う。最後に児を沐浴槽より持ち上げてかけ湯をするといった方法である。 新生児の沐浴では,頸部や腋窩などの皮膚の重なり合う部分は,汚れや石鹸成分が落ちにくく皮疹の原因となりやすいため十分に洗い流す必要があると言われている7)。しかし,従来の沐浴方法のように沐浴槽につかりながら洗浄する場合,片手で児を洗浄するため皮膚の重なり合う部分を丁寧に洗浄することは困難である。 また産後入院中の母親に対する調査では,沐浴方法について不安を感じる初産婦は33%,経産婦は25%であった10)。母親にとって従来の沐浴方法のように,片手で保持し,もう一方の手で洗浄する方法は容易ではない。沐浴指導内容を検討する際には,児の安全性や養育者にとって難しい手技ではないという視点も重要である。 この30年間のわが国の入浴に関する環境は大きく変化している。家庭のシャワーの普及率は1985年に70%,2005年にはほぼ100%となり11),どの家庭でも新生児の沐浴にシャワーを利用することが可能になった。かけ湯よりシャワーで洗浄剤を流す方が退院後の生活環境に類似しており,手順が少なく実施しやすいと考えられる。 アレルギー疾患のハイリスク児に対して保湿剤を毎日塗布することでアトピー性皮膚炎の症状出現率が有意に低下したことをHorimukaiら12),Simpsonら13)が相次いで報告した。またヨーロッパの正常新生児のスキンケアの勧告14)では,適切な組成の保湿剤は皮膚バリア機能を良好に保つため,一般集団の新生児に対しても保湿剤の塗布を推奨している。 以上より,養育者が不安なく丁寧に洗い,洗浄剤を十分に流し,保湿剤塗布をするスキンケアが,1カ月健診における皮膚状態に良好な影響を与えるのではないかと考えた。 A病院ではこのような背景を元に,2015年から児を寝かせた状態で両手を用いて洗い,洗浄成分をシャワーで流し,保湿剤塗布を行う沐浴指導内容に変更した。そこで,1カ月健診における皮膚異常の有症率を変更前と変更後で比較し検討した。
1 0 0 0 OA 齊地の思想文化と古代中國 : 博士學位請求論文
1 0 0 0 東日本太平洋沿岸地域出土須恵器フラスコ瓶の編年--湖西産を中心に
- 著者
- 高橋 透
- 出版者
- 明治大学文学部考古学研究室
- 雑誌
- 考古学集刊 (ISSN:18814476)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.75-97, 2009-05
1 0 0 0 7世紀の東日本における湖西産須恵器瓶類の流通
- 著者
- 高橋 透
- 出版者
- 駿台史学会
- 雑誌
- 駿台史學 (ISSN:05625955)
- 巻号頁・発行日
- no.143, pp.51-77, 2011-08
1 0 0 0 特別講演 ランドスケープの方法 : 土木家への提案
- 著者
- 進士 五十八
- 出版者
- 国土技術研究センター
- 雑誌
- JICE report : Report of Japan Institute of Construction Engineering (ISSN:13474502)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.20-39, 2013
1 0 0 0 IR ランドスケープデザインにおけるディズニーランダゼーションの構築
- 著者
- 片桐 保昭
- 出版者
- 科学技術社会論学会
- 雑誌
- 科学技術社会論学会 第5回 年次研究大会・総会予稿集
- 巻号頁・発行日
- pp.111-112, 2006
科学技術社会論学会 第5回 年次研究大会・総会
1 0 0 0 IR 創られゆく風景--北海道のランドスケープデザインにおける政治性と実践
- 著者
- 片桐 保昭
- 出版者
- 北海道大学大学院文学研究科北方研究教育センター
- 雑誌
- 北方人文研究 = Journal of the Center for Northern Humanities (ISSN:1882773X)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.69-85, 2008-03
1 0 0 0 OA 創られゆく風景 : 北海道のランドスケープデザインにおける政治性と実践
- 著者
- 片桐 保昭
- 出版者
- 北海道大学大学院文学研究科北方研究教育センター
- 雑誌
- 北方人文研究 (ISSN:1882773X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.69-85, 2008-03-31
This study focuses on landscape design as practicing processes in designing workshop not regarded as modern system of depressing subjectivity. Hokkaido has been treated advanced area of landscape design. But residents are not always participating to construct public gardens. Administrative organizations of public parks want symbolic and clearly meaningful shapes by appropriating previous exiting objects in designing such spaces for the reasons of constructing needs. But designers regard these as capricious things and want more good shapes. These ‘good’ designs are often not objective and cannot explain by official needs. Hence, official symbolic objects are sighted on central symbolic place in the landscape and ‘good’ designed objects are sighted on peripherals and not conspicuous. In these processes, ‘aesthetical’ values without rationality or functionality in modern context are acted as agencies. Because of their ambiguous values, designers’ practices are rather not symbolic and peripheral on the landscape. These practiced designs have interpretative flexibility for each subject to feel the whole landscapes. On these processes of designing landscape, ambiguous agencies are acted to subjects. Landscapes are constructed not only meaningful symbolic objects but also rather not meaningful shapes felt by each subjects. These agencies are peripheral values constructed in each subjects’ experiences: and the processes of acting these agencies in landscape design processes are respected as subjects’ possibility.
1 0 0 0 IR 吉澤商店主・河浦謙一の足跡(2)活動写真時代の幕開き
- 著者
- 入江 良郎
- 出版者
- 東京国立近代美術館
- 雑誌
- 東京国立近代美術館研究紀要 = Bulletin of the National Museum of Modern Art, Tokyo (ISSN:09147489)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.6-40, 2018
1 0 0 0 IR 東欧諸国におけるリュミエ-ル映画の受容--シネマトグラフの世界的浸透-2-
- 著者
- 永冶 日出雄
- 出版者
- 愛知教育大学
- 雑誌
- 愛知教育大学研究報告 人文科学 (ISSN:03887375)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.p141-154, 1995-02